
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
「学生時代に最も打ち込んだこと」は、多くの就職活動生が作成に悩むエントリーシートや面接の頻出テーマです。
重要なのは経験の大小ではなく、そこから何を学び、どう行動したかを論理的に伝えることにあります。
本記事では、企業の評価ポイントから具体的な書き方、経験別例文までを網羅的に解説します。
自信を持ってアピールできる内容を作成するため、ぜひご活用ください。
目次[目次を全て表示する]
【学生時代に最も打ち込んだこと】とは
「学生時代に最も打ち込んだこと」とは、学業や部活動、アルバイトなどにおいて、目標達成や課題解決のために最も主体的に取り組んだ経験を指します。
一般的に「ガクチカ」と略され、多くの企業で問われる質問です。
エントリーシートでの記述はもちろん、面接の序盤であなたの人物像を深く理解するために質問されることが多く、就職活動を通して頻繁に伝える機会があります。
このエピソードから、企業はあなたの価値観や潜在能力を読み取ろうとしています。
ガクチカと一緒?
結論として、「学生時代に最も打ち込んだこと」と「ガクチカ」は同じ意味です。
「ガクチカ」とは、「学生時代に力を入れたこと」を略した就職活動における用語です。
エントリーシートの設問では正式名称で問われますが、面接官や就活生の間では「ガクチカ」という言葉が広く使われています。
企業によっては「学生時代に挑戦したこと」など表現が異なる場合もありますが、基本的には同じ内容を求められていると理解して問題ありません。
ガクチカと自己PRの違い
ガクチカと自己PRでは、アピールする重点が異なります。
ガクチカは、目標達成や課題解決に向けた「過程(プロセス)」とそこから得た「学び」を伝えるものです。
一方、自己PRは、自身の「強みや能力」が企業の求める人物像と合致しており、入社後にどう貢献できるかをアピールすることが目的です。
ガクチカで語るエピソードは、自己PRで示す強みの具体的な根拠となり得るため、両者には密接な関連性があります。
27卒必見!! 一つの過去経験から同時に自己PRとガクチカを作成できるツールを紹介
「自己PRとガクチカが被ってしまう」
「ガクチカ書いてたのに自己PRみたいになってる...」
そんな方のために、同じエピソードから同時に自己PRとガクチカを生成できるツールを紹介します!
あなたの様々な過去経験から自己PRもガクチカも一緒に作成して、魅力的だと感じた方をそれぞれ自己PR、ガクチカに採用してみてください。
27卒必見!! 一つの過去経験から同時に自己PRとガクチカを作成できるツールを紹介
「自己PRとガクチカが被ってしまう」
「ガクチカ書いてたのに自己PRみたいになってる...」
そんな方のために、同じエピソードから同時に自己PRとガクチカを生成できるツールを紹介します!
あなたの様々な過去経験から自己PRもガクチカも一緒に作成して、魅力的だと感じた方をそれぞれ自己PR、ガクチカに採用してみてください。
【学生時代に最も打ち込んだこと】を聞く企業の意図
企業がガクチカを質問するのは、単に経験の優劣を知りたいからではありません。
その経験を通じて、その就活生が自社にマッチする人材か、入社後に活躍できるポテンシャルがあるかを見極めることが目的です。
物事への向き合い方やモチベーションの源泉を知ることで、あなたの本質的な強みや価値観を理解しようとしています。
1.人柄や価値観
何に情熱を注ぎ、どのような状況でモチベーションを感じるのか、といったエピソードから、あなたの根源的な人柄や価値観が明らかになります。
企業は、その価値観が自社の企業理念や社風と合致しているかを見ています。
自社との親和性が高い人材は、入社後も意欲的に業務に取り組み、早期離職のリスクが低いと考えられるためです。
ガクチカは、あなたと企業の相性を測る重要な判断材料となっています。
2.物事への取り組み方
企業は、あなたが目標や課題に対して、どのように向き合い、行動したのかというプロセスを重視しています。
仕事では常に困難な状況に直面するためです。
課題の原因を分析し、解決策を考え、周囲を巻き込みながら粘り強く実行した経験は、入社後の業務への取り組み方を想起させます。
ガクチカは、あなたの思考の特性や行動力を具体的に示すことで、入社後も再現性のある活躍ができるかどうかのポテンシャルを測る指標となります。
3.得た学びやスキル
経験を通じて何を得たのかを自分の言葉で語れるかは、あなたの成長意欲や学習能力を示す重要な要素です。
企業は、単に行動した事実だけでなく、その経験を客観的に振り返り、次に活かせる学びやスキルを抽出できているかを見ています。
成功体験はもちろん、失敗体験から何を学んだかを語ることも評価されます。
経験から学びを得て成長し続けられる人材は、入社後も高いパフォーマンスを発揮すると期待されるためです。
【学生時代に最も打ち込んだこと】の見つけ方3選
「ガクチカとして語れるような特別な経験はない」と感じる方も多いかもしれません。
しかし、重要なのは経験の規模ではなく、あなた自身の思考や行動を深く掘り下げることです。
自己分析を通じて過去の経験を多角的に見つめ直すことで、アピールできる要素は必ず見つかります。
ここでは、そのための具体的な方法を3つご紹介します。
方法1.モチベーショングラフ

モチベーショングラフは、自分の価値観や強みを発見するための手法です。
横軸に時間、縦軸にモチベーションの高低を設定し、これまでの人生の浮き沈みをグラフ化します。
特に、モチベーションが大きく上がった(山)あるいは下がった(谷)出来事に注目してください。
その時に「なぜ」感情が動いたのかを深掘りすることで、あなたの原動力や人柄、困難を乗り越える際の行動特性が見えてきます。
これらがガクチカの核となるエピソードに繋がります。
方法2.過去経験を「目的・課題・行動・結果」で整理
過去の経験を構造的に整理し、アピールポイントを明確化する手法です。
学業、サークル活動、アルバイトなど、学生時代の経験をリストアップしてください。
そして、それぞれの経験について「目的(なぜ取り組んだか)」「課題(どんな困難があったか)」「行動(どう乗り越えたか)」「結果(何を得たか)」の4項目で具体的に書き出します。
この作業を通じて、漠然とした記憶が論理的なエピソードへと整理され、自身の強みや貢献が明確になります。
方法3.喜怒哀楽を切り口に経験を掘り起こす
自身の感情を起点として、印象深い経験を掘り起こす方法です。
学生時代を振り返り、「心から嬉しかったこと(喜)」「悔しくてたまらなかったこと(怒)」「目標を達成し楽しかったこと(楽)」などを具体的に書き出してみましょう。
感情が大きく動いた出来事には、あなたの価値観や譲れない信念が強く反映されています。
特に悔しさなどのネガティブな感情は、強い課題意識や改善意欲の表れであり、主体的な行動を示すガクチカのエピソードに繋がりやすいです。
自己分析に行き詰まったら...
一人での自己分析に限界を感じた際は、他者の視点を借りる「他己分析」が有効です。
信頼できる友人や家族、あるいは大学のキャリアセンターの職員に相談してみましょう。
「私の長所はどこだと思うか」「学生時代に私が熱中していたように見えたことは何か」といった質問を投げかけることで、自分では当たり前だと思っていた行動が、実は強みとして捉えられていたと気づくことがあります。
客観的な視点を取り入れることで、新たな発見に繋がるはずです。
【学生時代に最も打ち込んだこと】エピソードの選び方のポイント3選
自己分析によって複数のエピソード候補が見つかったら、次は「どのエピソードを語るか」を戦略的に選択する段階です。
単に印象深いだけでなく、企業の評価ポイントを押さえ、自身の魅力を最大限に伝えられるものを選ぶ必要があります。
ここでは、採用担当者により響くエピソードを選ぶための3つの重要なポイントを解説します。
1.学びやスキルを得られたもの
企業が知りたいのは、経験そのものよりも「その経験から何を学び、成長したか」です。
そのため、具体的な学びやスキルを得られたエピソードを選びましょう。
例えば、課題解決能力や論理的思考力、チームで成果を出す力など、社会人として求められる汎用的な能力に繋がる学びを語れるものが理想的です。
その学びを入社後にどう活かせるかまでを示すことで、あなたのポテンシャルを効果的にアピールでき、入社後の活躍イメージを持たせることができます。
2.大学時代など直近の経験
エピソードは、可能な限り大学時代など、現在に近い時期の経験を選びましょう。
直近の経験であるほど、あなたの人格や能力を形づくる現在の姿と直結していると判断され、説得力が増すためです。
高校以前の経験が全く駄目というわけではありませんが、その場合は「その経験が今の自分の価値観や強みにどう繋がっているか」を論理的に説明する必要があります。
企業が知りたいのは過去の実績よりも「今のあなた」であるため、現在の自分を最もよく表す経験を選ぶことが重要です。
3.周囲を巻き込んだ経験
仕事は組織やチームで行うものであり、一人では完結しません。
そのため、個人で成し遂げたことよりも、周囲の人々と協力し、巻き込みながら目標を達成した経験の方が高く評価される傾向にあります。
必ずしもリーダーである必要はありません。
チームの一員として、目標達成のためにどのように働きかけたか、意見の異なるメンバーをどう調整したか、といった経験は、あなたの協調性やコミュニケーション能力を示す好材料となります。
入社後の組織への貢献を期待させることができます。
【学生時代に最も打ち込んだこと】の構成はSTAR法
魅力的なエピソードも、構成が分かりづらければ採用担当者には伝わりません。
そこでおすすめするのが、論理的な構成フレームワークである「STAR法」です。
これはSituation(状況)、Task(課題・目標)、Action(行動)、Result(結果)の頭文字を取ったものです。
この順番に沿って情報を整理することで、聞き手が状況を理解しやすく、説得力のあるガクチカを組み立てることができます。
1.Situation(状況)
ここでは、エピソードの前提となる背景情報を簡潔に説明します。
「いつ」「どこで」「どのような組織で」「自身がどんな役割だったか」を具体的に示し、聞き手がイメージしやすいように土台を整える部分です。
専門用語などは避け、誰が聞いても理解できる客観的な事実を述べるように心掛けましょう。
話の導入部分であるため、長くなりすぎないように注意し、これから続く課題や行動への橋渡しとなるように構成することが重要です。
2.Task(課題・目標)
ここでは、当時の状況において自身が向き合った「課題」や設定した「目標」を具体的に述べます。
なぜその課題を解決すべきだと考えたのか、どのような目標を掲げたのかを明確にすることで、あなたの主体性を示すことができます。
可能であれば「売上が前年比10%減」「新入生の定着率50%」のように、数字を用いて定量的に示すと、課題の大きさや目標の具体性が伝わりやすくなります。
この課題設定の的確さが、後の行動の説得力を高めます。
3.Action(行動)
STAR法の中で最も重要な部分です。
設定した課題や目標に対し、あなたが「何を考え」「具体的にどう行動したか」を詳細に説明します。
「頑張った」といった抽象的な言葉ではなく、「なぜその施策が有効だと考えたか」という思考のプロセスや、周囲をどのように巻き込んだかを具体的に述べましょう。
第三者ではなく、あなた自身が主体となって考え、行動したことが明確に伝わるように意識することが、最も重要なポイントとなります。
4.Result(結果)
あなたの行動がもたらした「結果」や「成果」を具体的に示します。
Taskで提示した課題に対し、状況がどう改善したのかを「売上が10%向上した」のように、可能な限り定量的に述べると客観性と説得力が増します。
さらに重要なのが、その経験全体を通じて「何を学んだか」を語ることです。
得られた学びやスキル、そしてそれを今後どのように活かしていきたいかを伝えることで、あなたの成長意欲と将来性をアピールすることができます。
【学生時代に最も打ち込んだこと】テーマ別例文15選
ここからは、「学生時代に最も打ち込んだこと」の具体的な例文をテーマ別に15個ご紹介します。
これまで解説した「STAR法」が文章にどう落とし込まれているかに注目し、ご自身の経験に置き換えて考えてみてください。
例文はあくまで構成や表現の参考です。
あなたに近いテーマの例文から、魅力的なガクチカを作成するためのヒントを見つけましょう。
部活動・サークル活動の例文4選
部活動やサークル活動は、ガクチカの定番テーマであり、多くの学生がアピールしやすい経験です。
このテーマでは、目標達成に向けた継続力、規律性、そしてチームで成果を出すための協調性やリーダーシップなどを効果的に示すことができます。
重要なのは、役職や実績の有無ではなく、「チームの課題に対し、自身がどのように考え、働きかけたか」という主体的なプロセスです。
練習への取り組みや組織運営への貢献などを具体的に語りましょう。
私が学生時代に最も打ち込んだことは、サッカー部での守備力強化です。(S)私が所属するチームは、守備の連携不足から失点が多く、リーグ下位に低迷していました。(T)そこで私は、チームの課題である失点数を前年比で20%削減するという目標を掲げました。(A)まず、過去1年間の全失点シーンを分析し、特定のパターンで崩されていることを突き止めました。その分析結果を基に、守備時のポジショニングルールの徹底と、選手間の声掛けの重要性をDF陣に提案し、練習に取り入れました。さらに練習後10分間のミーティングを習慣化し、日々の課題を即座に修正するサイクルを構築しました。(R)結果、チームの守備意識が向上し、リーグ戦の総失点数を前年比30%減に抑えることができました。この経験から、現状を客観的に分析し、周囲と協働して課題を解決する力を学びました。
野球部で副主将としてチームの練習改革に打ち込みました。(S)私のチームは選手の意欲に差があり、練習のマンネリ化が課題でした。(T)そこで私は、全部員が主体的に練習へ参加する環境を作ることを目標に掲げました。(A)まず、全部員30名と個人面談を実施し、練習への意見をヒアリングしました。その結果「実戦経験を積みたい」という声が多数挙がったため、監督に交渉し、週2回、実戦形式の練習を導入しました。また、選手の多様なニーズに応えるため、個々の課題に応じて練習内容を選べる「選択制練習」の時間も新たに設けました。(R)結果、練習に活気が生まれチームの一体感が高まり、秋季リーグでは過去最高の準優勝を達成しました。この経験から、傾聴力と、現状を改善するための実行力を学びました。
吹奏楽団の定期演奏会で集客責任者として550人の動員を達成した経験です。(S)私が所属する楽団では、例年の来場者数が約300人と伸び悩んでおり、団員の士気にも影響していました。(T)そこで私は、過去最高の500人を動員するという目標を立てました。(A)従来の学内広報だけでは限界があると考え、SNSでの情報発信を強化しました。演奏動画や団員紹介を毎日投稿し、オンラインでの認知度向上を図りました。また、大学周辺の商店街30店舗に直接交渉しポスターを掲示していただくなど、地域住民へのアプローチも積極的に行いました。(R)結果、当日は目標を上回る550名の方に来場いただき、満席の会場で演奏を届けられました。この経験から、目標達成のための課題分析力と実行力を学びました。
ダンスサークルで、初心者の定着率向上に尽力しました。(S)所属するサークルでは、経験者と初心者の実力差が大きく、練習についていけない初心者の退会が課題でした。(T)そこで、誰もが楽しく活動を続けられる環境を作りたいと考え、新入生の退会者ゼロを目標に掲げました。(A)私は、週に一度、初心者向けの基礎練習会を企画・開催しました。経験者が初心者を個別に指導する時間を設け、技術的な不安を解消する場としました。また、全体の練習では、全員が輝けるよう振り付けをレベル別にアレンジし、互いに教え合う文化を醸成しました。(R)結果、新入生の練習参加率が向上し、退会者をゼロに抑えることに成功しました。この経験から、多様なメンバーの立場を理解し、目標達成に向けて働きかける調整力を学びました。
アルバイトの例文3選
アルバイト経験は、社会人として求められる基本的な対人能力や責任感をアピールする絶好の機会です。
このテーマでは、顧客のニーズを汲み取る力、売上などの目標に対するコミットメント、そして新人教育などを通じた組織への貢献意欲を示すことができます。
「指示された業務をこなした」で終わらせず、「店舗の課題に対し、一従業員としてどのように考え、売上向上や業務効率化に貢献したか」という主体的な視点で語ることが重要です。
カフェのアルバイトで、リピート客の増加に貢献しました。(S)私が勤務する店舗は、駅前にあり顧客の出入りは多いものの、リピート率の低さが課題でした。(T)そこで私は、お客様に「また来たい」と思っていただける店を目指し、常連客を1.5倍に増やすという目標を立てました。(A)まず、お客様一人ひとりの顔と名前、好みのメニューを覚えることから始め、再来店時には「〇〇様、いつもありがとうございます」と積極的にお声がけしました。また、会話の中からニーズを汲み取り、新商品をおすすめするなど、マニュアルを超えた接客を心掛けました。(R)結果、私の接客をきっかけに常連になってくださるお客様が増え、店舗のリピート率向上に貢献できました。この経験から、相手の立場に立って考え、信頼関係を構築する力を学びました。
アパレル店のアルバイトで、店舗の売上目標達成に尽力しました。(S)私が勤務していた店舗では、個人に売上目標はなく、店舗全体の目標達成への意識が低い点が課題でした。(T)そこで私は、スタッフ全員で目標を達成する喜びを分かち合いたいと考え、3ヶ月連続での店舗目標達成を掲げました。(A)まず、店長に提案し、スタッフ個々の得意な商品ジャンルを基に「担当制」を導入しました。各担当者が責任を持って商品の知識を深め、接客に活かす仕組みです。また、朝礼で個々の成功事例を共有する時間を設け、店舗全体の接客スキル向上を図りました。(R)結果、チームの一体感が高まり、3ヶ月連続で店舗の売上目標を120%達成できました。この経験から、目標達成のために周囲を巻き込むことの重要性を学びました。
塾講師のアルバイトで、担当生徒の学習意欲向上に取り組みました。(S)私が担当していた生徒は、数学への苦手意識が強く、宿題も提出しない状況でした。(T)そこで、まずは「数学は楽しい」と感じてもらうことを目標に、生徒との信頼関係構築から始めました。(A)授業では一方的に教えるのではなく、生徒の好きなゲームの話などを交えながら対話を重視し、生徒が心を開いてくれるよう努めました。また、生徒の理解度に合わせてオリジナルの演習問題を作成し、「解ける喜び」を実感できる小さな成功体験を積み重ねさせました。(R)結果、生徒は徐々に学習への意欲を取り戻し、3ヶ月後の定期テストでは数学の点数を30点上げることに成功しました。この経験から、相手に寄り添い、その人の成長のために粘り強く働きかける力を学びました。
学業・ゼミ活動の例文2選
学生の本分である学業やゼミ活動は、あなたの知的好奇心や論理的思考力をアピールするのに最適なテーマです。
研究や論文執筆の経験は、課題設定能力、情報収集力、分析力、そして粘り強く物事に取り組む姿勢を示すことができます。
専門分野の知識そのものよりも、「未知の課題に対してどのように向き合い、仮説と検証を繰り返して結論を導き出したか」という思考プロセスを具体的に伝えることが重要です。
卒業論文の執筆に最も打ち込みました。(S)私は「地域活性化におけるSNSの役割」をテーマに研究していましたが、先行研究が少なく、統計データも存在しない状況でした。(T)そこで、論文の独自性と説得力を高めるため、自身で一次データを収集し、実態に基づいた考察を行うことを目標としました。(A)まず、研究対象地域の商店街店主30名にアポイントを取り、ヒアリング調査を実施しました。対話を通じてSNS活用の実態や課題を収集し、得られた回答を分類・分析することで、成功事例に共通する要因を抽出しました。(R)結果、地域活性化には双方向のコミュニケーションが不可欠であるという独自の結論を導き、論文は教授から高く評価されました。この経験から、主体的に課題を設定し、粘り強く解決策を探求する力を学びました。
所属していたマーケティングゼミの共同研究に注力しました。(S)私たちのグループは、ある企業の製品の売上向上策を立案する課題に取り組んでいましたが、議論が発散し、方向性が定まらないという問題に直面しました。(T)そこで私は、チームの意見をまとめ、期限内に質の高い提案を行うことを自身の目標としました。(A)まず、各メンバーの意見をホワイトボードに書き出して可視化し、論点を整理しました。その上で、各自の強みを活かせるように調査や分析の役割を再分担し、議論の交通整理役を担いました。意見が対立した際は、双方の意見の共通点を探り、代替案を提示することで合意形成を図りました。(R)結果、チームは一つにまとまり、私たちの提案はゼミ内で最優秀賞を受賞しました。この経験から、多様な意見を調整し、チームの成果を最大化する調整力を学びました。
その他の活動例文6選
部活動やアルバイト以外にも、あなたの主体性やユニークな強みをアピールできる経験は数多く存在します。
留学や長期インターンシップ、学生団体の立ち上げといった経験は、行動力や課題解決能力を直接的に示すことができます。
また、資格取得や趣味、ボランティア活動なども、目標設定能力や継続力、社会貢献意識といった人柄を伝える上で有効な題材です。
これらの経験を企業の求める能力と結びつけて語りましょう。
1年間の米国留学で、多様性を受け入れ目標を達成する力を養いました。(S)留学当初は語学力や文化の壁に苦しみ、現地の学生の輪に入れず孤立していました。(T)そこで「語学力をビジネスレベルまで向上させ、現地の友人を10人作る」という目標を設定しました。(A)そのために、毎日3人の初対面の人と話すというルールを自身に課しました。また、授業外でも交流の機会を増やすため、地域のボランティア活動に参加し、現地学生との共同作業に積極的に取り組みました。(R)結果、帰国時にはTOEICのスコアを200点向上させることができ、国籍の異なる15人の友人ができました。この経験から、困難な環境でも主体的に行動し、周囲を巻き込む力を学びました。
ITベンチャーでの半年間の長期インターンシップに注力しました。(S)私が配属されたマーケティング部では、自社アプリのダウンロード数が伸び悩んでいました。(T)そこで私はインターン生として、SNS経由のダウンロード数を3ヶ月で2倍にするという目標を掲げました。(A)まず、競合他社のSNSを徹底的に分析し、自社アカウントに不足している要素を洗い出しました。その上で、ターゲットである大学生に響くような、共感を呼ぶコンテンツの企画を社員の方に提案し、実行しました。週次で効果測定を行い、投稿内容の改善を繰り返すPDCAサイクルを回し続けました。(R)結果、3ヶ月で目標を上回る2.5倍のダウンロード数を達成し、事業の成長に貢献できました。この経験から、課題解決のための分析力と実行力を学びました。
大学2年次に挑戦した日商簿記2級の取得に力を入れました。(S)将来は企業の経営に携わりたいという思いから、その基礎となる会計知識の必要性を感じていました。(T)そこで、体系的な知識を身につけた証として、半年後の簿記2級試験に一回で合格するという目標を立てました。(A)合格から逆算して半年の学習計画を立て、毎日3時間の勉強時間を確保しました。特に、苦手な工業簿記の克服のため、参考書を3周繰り返し解き、基礎を徹底的に固めました。また、スマートフォンのアプリを活用し、通学中の隙間時間も有効に活用しました。(R)計画的な学習を継続した結果、無事に一度の受験で合格できました。この経験から、目標達成に向けた自己管理能力と継続力を身につけました。
趣味である動画編集とYouTubeでの発信活動に打ち込みました。(S)当初、自身のチャンネルは再生数が伸び悩んでいました。(T)そこで「半年でチャンネル登録者数を1000人にする」という具体的な目標を設定しました。(A)まず、人気チャンネルの動画を分析し、視聴者を惹きつける構成やサムネイルの共通点を研究しました。そして、自身の動画にも視聴者目線を意識したテロップや効果音を取り入れ、最後まで飽きさせない工夫を凝らしました。また、コメント欄で視聴者と積極的に交流し、ファンの育成にも努めました。(R)結果、半年で目標を達成し、現在では登録者数3000人を超えるチャンネルに成長しました。この経験を通じ、現状を分析し、改善策を継続する力を養いました。
地域の子ども食堂での学習支援ボランティアに2年間取り組みました。(S)そこでは、家庭環境が原因で学習習慣が身についていない子どもが多いという課題がありました。(T)私は、子どもたちに「学ぶ楽しさ」を知ってもらい、学習意欲を引き出すことを目標としました。(A)一方的に勉強を教えるのではなく、一人ひとりと対話し、興味や関心事を理解することから始めました。そして、その子の好きなキャラクターを例に問題を出すなど、学習に興味を持つきっかけ作りを工夫しました。また、小さな成功体験を積めるよう、個別の学習計画を立ててサポートしました。(R)結果、担当した子どもが「勉強が楽しい」と言ってくれるようになり、テストの点数が上がりました。この経験から、相手の立場に寄り添う傾聴力と、粘り強く働きかける力を学びました。
「地域活性化」を目的とする学生団体をゼロから立ち上げました。(S)私の大学には、地域貢献に関心を持つ学生は多いものの、活動の受け皿となる団体がありませんでした。(T)そこで、学生と地域を繋ぐハブとなる団体を作ることを決意し、1年間で行政と連携したイベントを実現させることを目標としました。(A)まず、SNSで想いを発信し、賛同してくれた友人10名と団体を設立しました。市役所に何度も足を運んで担当者の方と交渉を重ね、地域の課題をヒアリングしました。その課題を解決するイベントを企画・提案し、開催の許可を得ました。(R)結果、大学や市役所の協力を得て、地域の魅力を発信するイベントを成功させることができました。この経験から、ゼロから物事を創造する行動力と、周囲を巻き込む推進力を学びました。
【学生時代に最も打ち込んだこと】面接での話し方のコツ3選
エントリーシートが通過しても、面接で上手く伝えられなければ意味がありません。
「1分で説明してください」など、限られた時間で魅力を伝えるには、書き言葉とは異なる話し方の技術が必要です。
面接官に分かりやすく、かつ印象的にガクチカを伝えるための3つの重要なコツを解説します。
これらを意識するだけで、あなたの話の説得力は格段に向上します。
1. 結論から話す(PREP法)
面接では、必ず「結論」から話し始めてください。
聞き手である面接官の理解を助け、話の要点を明確にするためです。
この際に有効なのが「PREP法」という構成です。
【Point(結論)→Reason(理由)→Example(具体例)→Point(結論)】の順で話します。
「私が打ち込んだのは〇〇です(P)。なぜなら〜(R)、具体的には〜(E)、この経験を活かし〜(P)」
と展開することで、話が論理的で分かりやすくなり、簡潔にまとまります。
2. 具体的な数字やエピソードを交える
話に説得力と具体性を持たせるため、数字や客観的な事実を積極的に活用しましょう。
「頑張りました」ではなく「毎日3時間の練習を継続しました」、「改善しました」ではなく「売上を前年比10%向上させました」と話すことで、成果が明確に伝わります。
また、当時の心境や仲間との印象的な会話など、短いエピソードを交えると、あなたの人柄が伝わり、話がより生き生きとして面接官の記憶に残りやすくなります。
3. 熱意を込めてイキイキと話す
同じ内容でも、話し方一つで印象は大きく変わります。
面接官は、あなたが本当にその経験に情熱を注いでいたか、その熱量も見ています。
自信を持って、少し明るい表情とハキハキした声で話すことを心掛けましょう。
身振り手振りを交えたり、重要な部分を少し強調したりすることも有効です。
あなたが自分の言葉で楽しそうに語る姿は、それだけでポジティブな人柄のアピールとなり、面接官を惹きつけます。
深掘り質問対策
面接官はあなたの1分程度の説明を聞いた後、さらに思考の深さや人柄を見るために「深掘り質問」をします。
「なぜそれに取り組もうと思ったのですか?」「一番大変だったことは何ですか?」「その経験を弊社でどう活かせますか?」といった質問を想定し、事前に回答を準備しておきましょう。
これらの質問にスムーズに答えられることで、経験について深く考察できていることを示し、自己分析能力の高さをアピールできます。
【学生時代に最も打ち込んだこと】で差別化するコツ
多くの就活生が似たテーマを語る中で、あなたのガクチカを際立たせるにはどうすれば良いのでしょうか。
重要なのは、経験の珍しさではなく「伝え方の工夫」です。
あなたならではの視点を加え、志望企業との関連性を意識することで、ありふれた経験も採用担当者の記憶に残る魅力的なエピソードに変わります。
ここではそのための3つのコツを解説します。
過程の中での取り組みを数字で表す
結果を数字で示すことは多くの学生が意識しますが、そこに至るまでの「過程」を数字で表現すると、独自性と説得力が格段に増します。
例えば「頑張った」ではなく「毎日30ページの論文を読み込んだ」、「ヒアリングした」ではなく「50人の学生にアンケートを実施した」と表現するのです。
これにより、あなたの行動の具体的な量や思考の深さが伝わり、取り組みへの真摯な姿勢を客観的に示すことができます。
志望先とマッチング度を高くする
同じエピソードでも、企業の社風や価値観に合わせて伝える側面を変えることで、マッチング度の高さをアピールできます。
事前に企業のホームページなどで「求める人物像」を研究しましょう。
例えば「チームワーク」を重んじる企業には協調性を発揮した側面を、「挑戦」を奨励する企業には主体的に課題を設定した側面を強調して伝えます。
これにより、企業への深い理解と入社意欲の高さを示すことができます。
志望先に活かせる経験を含める
ガクチカの締めくくりとして、その経験から得た学びやスキルが「入社後、具体的にどう活かせるか」を明確に伝えましょう。
例えば「この経験で培ったデータ分析力は、貴社のマーケティング業務において、顧客ニーズの把握に貢献できると考えております」といった形です。
過去の経験談で終わらせず、未来の貢献まで言及することで、あなたが自社で活躍する姿を面接官に具体的にイメージさせることができ、強い印象を残せます。
【学生時代に最も打ち込んだこと】を伝えるときの注意点
素晴らしい経験も、伝え方を誤ると評価を下げてしまう可能性があります。
アピールのつもりが、意図せずマイナスの印象を与えてしまうケースは少なくありません。
ここでは、ガクチカを伝える際に避けるべき3つの重要な注意点を解説します。
信頼性を損なわず、あなたの魅力を正しく伝えるために、必ず押さえておきましょう。
複数のテーマを取り上げない
アピールしたいことが多い場合でも、ガクチカで語るテーマは必ず一つに絞りましょう。
複数のエピソードを盛り込むと、一つひとつの内容が浅くなり、あなたがどのように課題と向き合ったのかという最も重要な部分が伝わりません。
一つの経験をSTAR法に沿って深く掘り下げて語ることで、あなたの思考の深さや人柄が明確に伝わります。
あれもこれもと話すのは、要点をまとめる能力が低いという印象にも繋がりかねません。
企業の求める人物と乖離しない
あなたのガクチカでアピールする強みや価値観が、企業の求める人物像と大きくかけ離れていないかを確認しましょう。
例えば、協調性を重んじる企業に対して、個人での成果のみを過度に強調するエピソードはミスマッチな印象を与える可能性があります。
企業の理念や社風を事前に研究し、自身の経験の中から、その企業で働く上で親和性の高い側面を切り取って伝える配慮が重要です。
嘘・誇張は控える
自分を良く見せたい一心で、事実と異なる内容を話したり、成果を過度に誇張したりすることは絶対に避けてください。
経験豊富な面接官は、深掘り質問を通じて話の矛盾を簡単に見抜きます。
嘘が発覚すれば、その時点で信頼を完全に失い、評価されることはありません。
結果の大小よりも、あなたが真摯に取り組んだ事実とその過程で得た学びこそが評価の対象です。
誠実・正直であることが最も重要です。
【学生時代に最も打ち込んだこと】のNG例文3選
ここでは、多くの就活生が陥りがちなガクチカの失敗例を3つのパターンに分けてご紹介します。
良い例文から学ぶだけでなく、悪い例文から「なぜ評価されないのか」を理解することも非常に重要です。
ご自身のガクチカがこれらのNG例に当てはまっていないか、客観的な視点で見直してみましょう。
NG例文1. ウケの悪いエピソード
私が学生時代に最も打ち込んだことは、麻雀です。勝負のスリルに魅了され、友人たちと夜を徹して卓を囲みました。ただ打つだけでなく、過去の対戦記録を分析して相手の癖を読み、確率論を勉強して、どのような状況でも最適な一打を選択できるよう訓練しました。その結果、常に勝ち越すことができるようになり、アルバイト代以上の収入を得ることもありました。この経験から、状況を冷静に分析する力と、勝負どころを見極める度胸が身についたと自負しています。
【改善ポイント】
社会人としての倫理観を疑われるテーマ(ギャンブル等)は避け、別のエピソードを選びましょう。
NG例文2. 複数のエピソード
私が学生時代に打ち込んだことはたくさんあります。まず、テニスサークルでは副部長として新入生歓迎イベントを企画し、参加率を向上させました。次に、飲食店のアルバイトでは、接客スキルを磨き、常連のお客様を増やすことに貢献しました。新人教育も任されるようになり、後輩の指導にも力を入れました。また、学業にももちろん力を入れており、TOEICのスコアを800点まで伸ばすために毎日英語の勉強を継続しました。これらの経験を通じて、リーダーシップやコミュニケーション能力、継続力を身につけることができました。
【改善ポイント】
最も伝えたいエピソードを一つに絞り、STAR法を用いて深く掘り下げましょう。
NG例文3. 具体性に欠ける内容
私が学生時代に最も打ち込んだことは、カフェのアルバイトです。私はお店をより良くするために、様々な課題を見つけて改善に取り組みました。スタッフ間のコミュニケーションを活性化させ、みんなで協力し合える良い雰囲気を作りました。お客様に対しても、常に笑顔で丁寧な接客を心掛けた結果、お店の評判も良くなったと思います。この経験を通じて、課題解決能力や協調性など、社会人として必要な多くのことを学ぶことができました。この力を活かして、貴社に貢献したいです。
【改善ポイント】
自身の思考や行動が伝わるよう、具体的な数字や固有名詞、エピソードを盛り込みましょう。
【学生時代に最も打ち込んだこと】よくある質問
最後に、多くの就活生が抱くガクチカに関する疑問についてQ&A形式でお答えします。
エピソードの選び方から文字数への対応まで、エントリーシートを完成させる上でつまずきやすいポイントをまとめました。
ここでの疑問を解消し、自信を持ってあなたのガクチカを提出、伝えられるように準備を整えましょう。
ガクチカが複数ある場合、どれを選べばいいですか?
複数の候補がある場合は、応募する企業の「求める人物像」に最も合致するエピソードを選びましょう。
例えば、チームワークを重視する企業であれば協調性を発揮した経験を、挑戦を奨励する企業であれば高い目標を掲げ主体的に行動した経験を選ぶのが効果的です。
企業の理念や事業内容を研究し、どのエピソードが最も入社後の活躍をイメージさせられるかを基準に、戦略的に選択することをおすすめします。
嘘をついたり、話を「盛って」も大丈夫ですか?
嘘や過度な誇張は絶対に避けるべきです。
面接での深掘り質問で矛盾が生じ、必ず見抜かれます。
発覚した場合、信頼性を完全に失い、評価されることはありません。
結果の大小そのものよりも、課題に対してどう向き合い、何を学んだかというプロセスが評価の対象です。
自身の経験を等身大で、誠実に語ることが最も重要です。
あなたの強みを効果的に見せる「表現の工夫」と、事実を偽る「嘘」は全く異なることを理解してください。
200字、400字、600字など文字数指定への対応方法は?
まず600字程度の、伝えたい要素をすべて含んだ「完全版」を作成することをおすすめします。
そこから指定文字数に合わせて情報を削っていく方法が効率的です。
400字の場合は、状況説明(S)などを簡潔にし、行動(A)を中心に具体性を保ちます。
200字の場合は、各要素の要点のみを抜き出し、「〇〇という課題を△△という行動で解決し、□□を学んだ」という骨子を明確に伝えることを最優先しましょう。
まとめ
本記事では、「学生時代に最も打ち込んだこと」の見つけ方から、構成法、具体的な例文までを網羅的に解説しました。
重要なのは、決して経験の大小や華やかさではありません。
あなた自身が課題とどう向き合い、何を考え、どのように行動して乗り越えたのか。
そのプロセスと学びを、あなた自身の言葉で伝えることが最も大切です。
自己分析は時に大変な作業ですが、この記事で紹介したフレームワークが、あなたの素晴らしい経験の価値を再発見する一助となれば幸いです。
自信を持って、あなただけの物語を語ってください。
心より応援しております。


_720x550.webp)

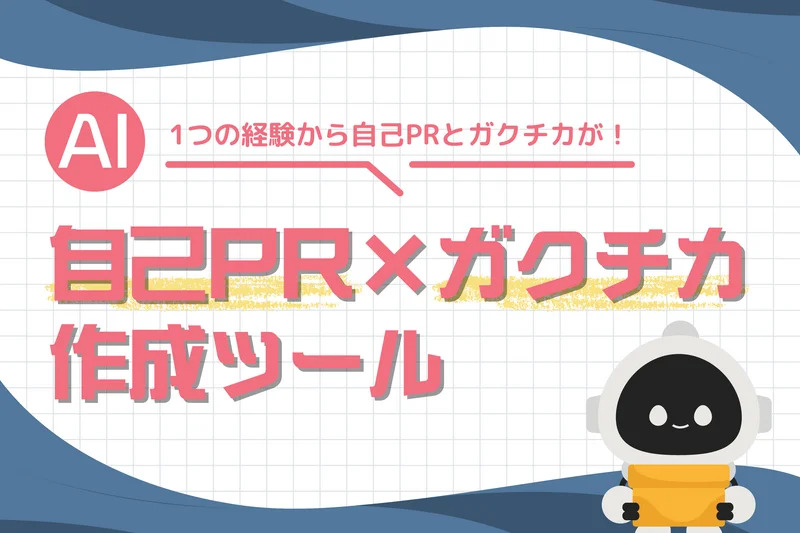















_720x550.webp)












