
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
目次[目次を全て表示する]
はじめに
リース業界は、金融とモノをつなぐ役割を持ち、企業や自治体が必要とする設備・機械を所有せず利用できるようにする仕組みを提供しています。
銀行や証券と同じ金融領域に属しながらも、実際のモノの取扱いや残価リスク、減価償却といった会計知識も関わるため、他の金融業界とは異なる特徴を持ちます。
就職活動においては、総合系とメーカー系で事業モデルが異なることや、営業・審査・アセットマネジメントなど複数の職種が存在する点がポイントとなり、志望動機や自己PRを考える上で理解しておくことが欠かせません。
就活で差をつけるためには、単なる業界概要の暗記ではなく、案件の仕組みや収益構造を理解し、自分の強みをどのように活かせるか具体的に語れることが重要です。
リースの仕組みと収益設計
リースとは、貸手が資産を調達し、借手に一定期間貸与する取引を指します。
借手は資産を購入する場合に比べて初期投資を抑えられ、キャッシュフローを安定させることができます。
一方で貸手は、資産取得に伴う資金調達コスト、残価設定、保険料や保守費用、そして借手の与信リスクを考慮しながらリース料を設定します。
この収益モデルは、単に貸し出して終わりではなく、会計処理・税務処理・残価管理など多岐にわたる専門性を必要とするため、業界を志望する就活生には理解しておきたい知識領域となります。
リースビジネスの本質は「資金効率」と「リスク管理」の両立にあり、金融知識と実物資産の知識を併せ持つことが求められる点が大きな特徴です。
ファイナンス/オペレーティングの違いと契約条件
リースは大きく分けて「ファイナンスリース」と「オペレーティングリース」の2種類に分かれます。
ファイナンスリースは中途解約ができない契約であり、借手は耐用年数の大部分にわたって資産を利用し続けることになります。
契約上は資産を所有しないものの、実質的には購入に近い性質を持ちます。
これに対してオペレーティングリースは、耐用年数の一部に限定して資産を貸し出す契約形態であり、利用終了後に資産を再リースしたり売却したりすることを前提としています。
特に航空機や船舶のような大型資産はオペレーティングリースが多く、リース会社にとって残価リスクを伴うため、適切な資産価値の見積もりが重要となります。
就活で語れると強いポイントは、ファイナンスリース=購入代替、オペレーティングリース=使用権の提供と理解して説明できることです。
収益の分解:料率・金利・残価・与信の設計
リース契約における収益は、リース料として受け取る金額に内包されています。
その中には、資金調達に伴う金利コスト、資産の減価償却費、保険・保守費用、さらにリース会社の営業利益が含まれています。
特に重要なのは残価の設定であり、契約終了時に資産を再販できる価格をどのように見積もるかが、貸手のリスクと収益性を大きく左右します。
また、借手の信用力に応じて料率が変動するため、与信管理も欠かせない要素です。
これらの要素をバランス良く設計することで、貸手と借手双方にメリットのある契約が成立します。
リース料の裏側には「金利・残価・与信・期間」の4つの要素が絡み合っていることを理解すると、業界研究が一段深まります。
会計・税務の勘所(減価償却・IFRS/日本基準の要点)
会計上、リース取引は国際基準(IFRS)と日本基準で扱いが異なります。
IFRSでは、借手はほぼ全てのリースを資産計上・負債計上する「オンバランス処理」が求められ、経済的実態を反映する形が主流です。
一方、日本基準では、ファイナンスリースは原則オンバランスですが、オペレーティングリースはオフバランス処理が認められています。
この違いにより、企業は財務指標や資本効率を踏まえてリース活用を検討します。
また、税務面では減価償却費をリース会社が計上するため、借手にとっては費用平準化の効果があり、キャッシュフロー管理の観点からも有用です。
面接で語れると評価されやすいのは、会計・税務の違いを簡潔に説明し、企業側の意思決定に与える影響を理解している点です。
業界マップ:総合系とメーカー系の戦い方
リース業界には大きく分けて「総合リース」と「メーカー系リース」の2種類があります。
総合リースは金融機関や商社を母体に持ち、幅広い分野でリース事業を展開しています。
一方、メーカー系リースは親会社であるメーカーが製造した製品を中心に扱い、グループシナジーを活かしてビジネスを拡大しています。
両者はビジネスモデルや案件の獲得方法が大きく異なるため、就活生は違いを整理して志望動機に活かすことが大切です。
総合系=幅広い顧客・資産、メーカー系=グループ製品特化という構造を理解すると、企業ごとの特徴が見えやすくなります。
総合リースの強み・弱みと代表企業
総合リースは、銀行や商社といった大規模な金融・流通ネットワークを背景に、多様な業界の顧客にサービスを提供できます。
強みは、業界を超えた幅広い案件を扱えること、海外進出やプロジェクトファイナンスにも強いことです。
代表的な企業にはオリックス、三菱HCキャピタル、東京センチュリーなどがあります。
これらの企業は、オートリースや航空機リース、再生可能エネルギーなど新規分野にも積極的に展開しています。
一方で、総合リースは扱う分野が広いため、専門性よりも総合力が求められる傾向が強く、案件規模も大きいことから調整力やファイナンススキルが必須となります。
総合リースに向いているのは、多様な顧客と関わりながら広い分野にチャレンジしたい人です。
メーカー系の強み・弱みと代表企業
メーカー系リースは、親会社であるメーカーの製品を中心にリースを展開します。
例えば日立キャピタル(現:日立キャピタルと三菱UFJリースが統合した三菱HCキャピタルの一部)、三井住友ファイナンス&リース、NECキャピタルソリューションなどがあります。
強みは、グループの製品を活用した強力な販売力と、親会社の顧客基盤に基づく安定した案件獲得です。
また、製品知識に基づいた専門的な提案ができる点も魅力です。
一方で、取り扱う分野が親会社の製品に依存する傾向が強いため、総合系に比べると事業の幅が限定的になることがあります。
メーカー系は、専門分野の知識を活かしながら親会社の製品と顧客に深く入り込む働き方を志向する人に向いています。
取扱資産の違いが生む案件の勝ち筋
総合系とメーカー系では、取り扱う資産の種類にも違いがあります。
総合系は、オフィス機器から自動車、航空機、船舶、さらには再生可能エネルギー設備まで幅広い分野に対応しています。
これにより、案件規模が非常に大きく、ストラクチャリングや海外案件といったダイナミックな仕事に携われる可能性があります。
一方でメーカー系は、自社グループの強みを活かした分野に集中するため、IT機器、医療機器、建設機械など特定領域で深い知識と強みを発揮します。
就活生にとっては、総合系かメーカー系かを選ぶことが、自分のキャリア志向と直結する大きな分岐点となります。
広く浅く挑戦したいなら総合系、専門性を深めたいならメーカー系という整理で志望動機を構築するのが効果的です。
市場規模と最新トレンド(2024–2025)
リース業界は、設備投資や資金調達のニーズに応える仕組みとして、国内外で安定した需要を持っています。
日本のリース取扱高は近年数兆円規模で推移しており、特にオートリースやIT機器の需要拡大が全体を支えています。
また、コロナ禍以降は航空機リースの需要回復や再生可能エネルギー案件の拡大といった新しい潮流が見られます。
就活生にとっては、市場の成長性とリスクの両面を理解しておくことが重要です。
リース業界のトレンドは「オートリース」「航空機リース」「サステナブル金融」「DX」の4本柱で理解すると整理しやすくなります。
オートリース・航空機・IT/医療機器の動向
オートリースはリース業界の中でも特に大きなセグメントであり、法人車両の保有コスト削減や管理効率化ニーズから安定した需要があります。
近年ではEVやカーシェアとの親和性が高まり、脱炭素社会の流れとともに拡大が期待されています。
航空機リースはコロナ禍で大きく落ち込みましたが、国際線需要の回復に伴い徐々に再拡大しており、オペレーティングリースのリスク管理が重視されています。
さらに、IT機器や医療機器のリースも拡大傾向にあり、企業のデジタル投資や医療現場の効率化に直結する領域として注目されています。
資産タイプごとの動きを理解すると、自分がどの分野に興味を持って志望するかを具体的に説明できるようになります。
エネルギー・PPA・サステナブルファイナンス
リース業界では再生可能エネルギー分野への参入が加速しています。
特に太陽光や風力発電設備のリースは、PPA(Power Purchase Agreement:電力購入契約)と組み合わせることで新たなビジネスモデルを形成しています。
企業が環境目標を達成するために設備投資を進める中、リース会社は資金調達と資産管理のノウハウを活かして持続可能なエネルギー導入を支援しています。
サステナブルファイナンスの観点からもESG投資の一翼を担っており、今後は脱炭素経済に貢献する役割がさらに期待されます。
環境分野への展開は、志望動機で「社会貢献」と「金融スキル」を結びつける具体例として活用できます。
DX/データ活用(残価予測・リスク管理の高度化)
デジタルトランスフォーメーション(DX)はリース業界でも重要なテーマです。
残価予測にAIを活用することでリスクを低減したり、IoTデータを活用して稼働状況をモニタリングするなど、データ駆動型のサービスが拡大しています。
また、営業支援や与信管理の分野でもデジタルツールが導入され、効率的かつ精緻な判断が可能になっています。
これにより、リース会社は従来の金融サービスにとどまらず、顧客の資産活用を最適化する「ソリューション企業」としての位置づけを強めています。
DXは単なる効率化ではなく、リース会社のビジネスモデルを「モノの利用最適化」に変革するキーワードです。
主要企業の読み解き方
リース業界は総合系とメーカー系に大別されますが、企業ごとに事業領域や収益構造、海外展開の方針が異なります。
就活生にとっては、単なる企業名の暗記ではなく、各社の強みや事業ポートフォリオを理解したうえで、どの観点から志望動機につなげるかを整理することが重要です。
企業研究では「事業領域」「数字」「海外展開」「リスク管理」の4つの視点を持つことが差別化につながります。
事業ポートフォリオ・海外展開・与信姿勢
総合リース企業であるオリックスは、リース事業に加えて不動産、生命保険、環境エネルギーなど幅広い事業に展開しており、まさに総合金融サービス企業としての色合いが強いです。
三菱HCキャピタルは三菱UFJリースと日立キャピタルの統合によって誕生し、総合力とメーカー系の知見を兼ね備えています。
東京センチュリーは伊藤忠商事との関係性を活かし、航空機リースやICT分野で存在感を発揮しています。
メーカー系では三井住友ファイナンス&リースやNECキャピタルソリューションが親会社の強みを背景に専門分野を深掘りしています。
与信姿勢については、総合系は幅広い案件を受ける一方で、メーカー系はグループの顧客を中心に堅実な与信管理を行う傾向があります。
企業によって「攻めの事業展開」か「安定した顧客基盤重視」かでスタンスが異なる点を把握しておくと志望動機で活かせます。
指標で比較する視点(取扱高/営業収益/ROAの見方)
主要企業を比較する際には、単に取扱高の大小を見るだけでは不十分です。
リース取扱高は市場規模や顧客基盤の大きさを示す一方、営業収益や純利益率は案件の収益性を反映します。
さらに、ROA(総資産利益率)は資産効率を示す指標であり、資産規模の大きなリース業界において重要な視点となります。
例えば、オリックスは多角化によって収益源を分散しているのに対し、東京センチュリーは航空機やICTに集中投資することで高い成長率を狙っています。
これらの指標を用いて「自分がどの企業のビジネススタイルに魅力を感じるか」を明確にすると、説得力のある志望理由につながります。
面接では「なぜこの企業か」を問われるため、数字を根拠にして説明できると他の就活生との差別化になります。
志望動機に落とす“企業別フック”
志望動機を作成する際には、企業ごとの特徴を自分の経験や価値観と結びつけることが重要です。
例えば「オリックスなら海外展開を活かしてグローバル案件に挑戦したい」「東京センチュリーならICT分野に強みを持つ点に魅力を感じ、自分のIT経験を活かしたい」といった形です。
メーカー系の場合は「親会社の技術や製品を金融と組み合わせることで社会に貢献したい」と結びつけると自然です。
単なる知識の羅列ではなく、自分のキャリア志向と企業の特徴をリンクさせることで説得力のある志望理由を構築できます。
志望動機は「企業の強み × 自分の強み」をかけ合わせて語るのが最も効果的です。
仕事理解:職種とキャリア
リース業界でのキャリアを考える際、最初に理解すべきは職種ごとの役割です。
営業・審査・アセットマネジメント・ストラクチャリングなどの職種が有機的に連携し、1つの案件を組成・運営していきます。
就活生は、この流れを理解した上で「自分はどの部分に強みを発揮できそうか」を整理することが大切です。
仕事理解のポイントは「営業が入口、審査が守り、AM・ストラクチャリングが価値創造」という役割分担を把握することです。
営業(法人/アセット)・審査/ストラクチャリング・AMの役割
営業職は企業や自治体のニーズを把握し、資産導入をサポートするリース契約を提案します。
法人営業では幅広い業界にアプローチし、資金調達や設備投資の課題を解決する提案を行います。
アセット営業では、自動車や航空機、IT機器など特定の資産に特化し、残価や耐用年数に基づく専門性を発揮します。
審査部門は、顧客の財務状況や信用力を分析し、貸倒リスクを最小化する判断を担います。
ストラクチャリングは大型案件において資金スキームを設計し、税務・会計・法律の知識を活かして複雑な契約を組み立てます。
アセットマネジメント(AM)はリース終了後の資産売却や再リースを担当し、資産の価値を最大限に活かすことが役割です。
リース会社の強みは、案件獲得からリスク管理、資産の出口戦略までをワンストップで提供できる点にあります。
1日の流れと案件フェーズ
リース営業の1日は、顧客との打ち合わせや社内調整から始まります。
午前は取引先企業を訪問し、設備導入の背景や資金計画をヒアリングします。
午後は社内に戻り、審査部門と協議し、与信や契約条件を詰めるケースが多いです。
案件によっては、弁護士や税理士と協力して契約スキームを整えることもあります。
契約が成立した後は、リース料の入金確認や資産の保守契約管理を行い、契約終了時には資産の売却先を探すなど出口戦略を検討します。
案件の流れを理解していると、面接で「自分がどの段階で価値を発揮したいか」を具体的に語れるようになります。
向いている人の特徴と活かせる経験
リース業界に向いているのは、金融リテラシーを持ちつつ、実物資産に興味を持てる人です。
営業においては人と人との信頼関係を築く力が重要であり、交渉力や調整力が評価されます。
審査やストラクチャリングでは、財務分析力や論理的思考力が求められ、数字に基づいた判断ができる人が活躍します。
アセットマネジメントでは、市場動向を分析し資産価値を高める視点が必要です。
学生時代の経験では、チームでの課題解決、データ分析、営業活動やインターンでの対人経験などがアピールポイントになります。
「人との関係構築」×「数字や分析への強み」の両方をアピールできると、リース業界との相性が高いと評価されやすいです。
選考対策
リース業界の選考では、金融知識の基礎理解と顧客提案力に加えて、志望動機の具体性や業界理解の深さが重視されます。
特に、銀行や証券、保険といった他の金融業界との差別化を明確に語れるかどうかが合否の分かれ目となります。
ガクチカや志望理由を語る際には、「リースだからこそできる価値提供」を具体的に述べることが大切です。
選考突破のカギは「リースの仕組み理解 × 自分の経験 × 企業の特徴」を組み合わせて語ることです。
よく問われるキーワード(残価/耐用年数/回収/与信)
面接やESでは、リース特有の用語を踏まえた質問が出ることがあります。
例えば「残価」については、リース終了後に資産がどれだけ価値を持つかを見積もる概念であり、リスク管理に直結します。
「耐用年数」は減価償却や契約条件に影響を与えます。
「回収」は貸倒れリスクをどう管理するかの視点であり、「与信」は借手の信用力を分析して取引可能かを判断するプロセスです。
これらのキーワードを理解していると、業界研究が深いことを示せるだけでなく、説得力のある回答につながります。
リース業界の基本用語を理解し、自分の言葉で説明できることが他の就活生との差別化になります。
志望動機の作り方とNG例
志望動機は「なぜ金融か」→「なぜリースか」→「なぜこの企業か」という流れで構築すると自然です。
「金融業界で顧客の成長を支援したい」という軸を示した上で、「リースは金融と実物資産の両方を扱うため、現場に近い課題解決ができる」という点を強調すると説得力があります。
さらに「御社は再生可能エネルギー分野に強みがあるため、環境課題の解決に貢献できる」と企業ごとの特徴を組み込めば完成度が高まります。
一方でNGなのは「大手だから」「安定しているから」といった抽象的な理由のみを述べることです。
具体性が欠けると他の候補者との差がつかなくなります。
志望動機は「業界選択理由」と「企業選択理由」をセットで語るのが鉄則です。
面接で効く逆質問テンプレ
逆質問は単なる興味を示す場ではなく、業界理解と意欲をアピールする場です。
例えば「御社が注力している〇〇分野で、若手が担う役割はどのようなものですか」と質問すれば、自分がそのフィールドで活躍したい意欲を伝えられます。
また「DXやサステナブル金融の展開において、今後若手が学ぶべきスキルは何でしょうか」と聞くと、業界動向を理解している姿勢を示せます。
さらに「審査やAMと営業の連携はどのように行われていますか」と質問することで、業務フローに関心を持っていることを伝えられます。
逆質問は「業界理解」+「自分のキャリア志向」を結びつけて行うのが最も効果的です。
まとめ
リース業界は、金融と実物資産を結びつける独自の立ち位置を持ち、企業の成長や社会課題の解決に不可欠な役割を担っています。
総合系とメーカー系でビジネスモデルは大きく異なり、幅広い案件を扱う総合力か、専門分野での深い知識を活かすかによってキャリアの方向性も変わります。
市場としてはオートリース、航空機リース、IT機器リースが成長を支えるとともに、再生可能エネルギーやDXといった新分野が拡大しているため、今後も多様な挑戦の場が広がっていくでしょう。
就職活動においては、リースの仕組みや収益構造を理解した上で、企業ごとの強みを自分の経験と結びつけて志望動機を語ることが大切です。
さらに、リース特有の用語やリスク管理の観点を把握していると、面接での説得力が格段に高まります。
逆質問の場でも業界トレンドやキャリア志向に触れることで、単なる受け身ではなく積極的な学びの姿勢を示せます。
リース業界研究のゴールは「なぜリース業界なのか」「なぜこの企業なのか」を自分の言葉で語れる状態になることです。
本記事を参考に、最新データと仕組み理解を踏まえた志望動機を完成させ、就活で一歩先を行く準備を整えましょう。

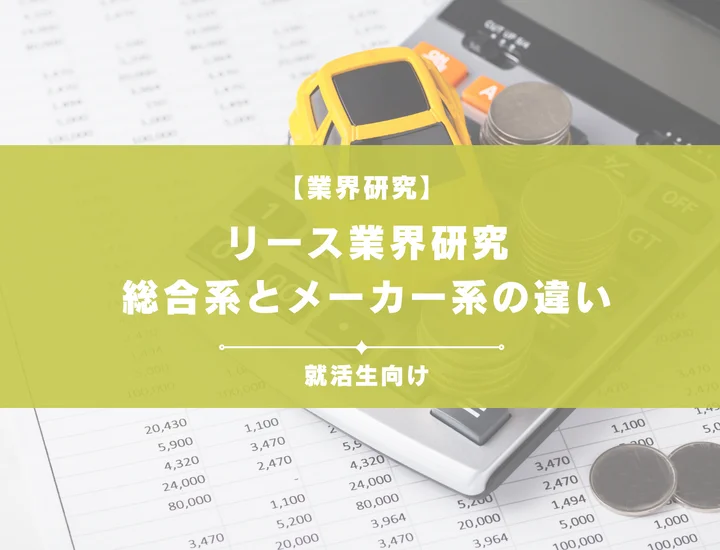



_720x550.webp)




