
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
面接は準備が必要なのか、それとも準備しない方が良いのかと悩む就活生は少なくありません。
「面接は準備しない方がいい」という極端な意見を聞いて、対策の必要性に不安を感じている人もいるでしょう。
しかし、結論から言えば、面接は「準備しすぎは良くないが、最低限の準備は必須」です。
準備不足では、あなたの魅力や入社意欲は企業に全く伝わりません。
かといって、回答を丸暗記しすぎると、棒読みになったり、想定外の質問に対応できなくなったりして逆効果になることもあります。
この記事では、「準備しない方がいい」と言われる理由を深掘りしつつ、大学3年生が自然体で臨みながらも高評価を勝ち取るための、最適な面接準備のバランスを徹底解説します。
この記事を読んで、自信を持って面接に臨める対策を始めましょう。
【面接は準備しない方が良い?】なぜそう言われるのか
準備しすぎると、かえって不自然に見えてしまうから
「面接は準備しない方が良い」という意見が生まれる最大の理由は、準備しすぎると「素のあなた」が見えなくなるからです。
完璧な回答を準備しすぎてしまうと、面接官の質問に答える際、用意した文章を必死に思い出そうとして棒読みになってしまうことがあります。
また、面接官は、あなたの用意した答えの奥にある人間性や、入社意欲のリアルな熱量を知りたいと考えています。
しかし、準備に頼りすぎると、想定外の質問をされた時に、準備した回答に無理やり結びつけようとして話が不自然になったり、話す内容がブレたりすることもあります。
取り繕った完璧な回答よりも、多少拙くても、あなた自身の言葉で話す自然体な姿勢の方が、面接官には魅力的に映り、評価される傾向があるのです。
【面接は準備しない方が良い?】対策をしないと起こりうること
準備不足のまま面接に臨むと、さまざまなリスクが生じます。
面接は、企業にあなたという人間を採用するメリットをプレゼンテーションする場です。
準備を全くしないまま面接に臨むのは、武器を持たずに重要な商談に臨むのと同じです。
面接官は「採用したい」という前提で話を聞いていますが、準備を怠っていると、あなたの魅力や能力以前に「この人は本気でウチの会社に入りたいのかな?」と疑問を抱いてしまい、結果としてあなたの評価を大きく下げてしまうリスクがあります。
伝え方が定まらない
答えが曖昧で説得力に欠けてしまう恐れがあります。
面接で必ず聞かれる志望動機や自己PRについて、事前に深く掘り下げて考えていないと、その場で思いついた浅い回答しかできず、内容に具体性や説得力が欠けてしまいます。
例えば、「御社の成長性に魅力を感じました」だけでは、「なぜそう思うのか?」「具体的にどんな点で?」という掘り下げの質問に答えられず、面接官を混乱させてしまいます。
論理的に、かつ具体的なエピソードを交えてあなたの考えを伝えられなければ、面接官にあなたのポテンシャルを十分に理解してもらうのは難しいでしょう。
態度やマナーがわからない
基本的な礼儀を欠くと評価を下げる原因となります。
面接はビジネスの場であり、基本的なビジネスマナーが備わっているかどうかも評価の対象となります。
挨拶やお辞儀の仕方、入退室の作法といったマナーが身についていないと、「社会人としての基礎ができていない」と判断され、能力以前の問題でマイナス評価につながります。
特に、Web面接においても、入室・退室時の挨拶や、話す際の姿勢、画面を通した目線などは非常に重要です。
事前に確認し、練習しておかないと、当日の立ち居振る舞いに不安が残り、面接に集中できなくなってしまいます。
準備不足が見抜かれる
志望度が低いと判断されてしまう可能性があります。
企業研究を怠り、応募企業について表面的な知識しか持っていない場合や、質問への回答が他の企業でも言えるような内容だった場合、面接官には「この学生はうちの会社についてほとんど知らないな」「志望度が低いな」と思われてしまいます。
面接官は、あなたがどれだけ自社を特別に志望しているか、どれだけ入社後に活躍するイメージを持っているかを知りたいのです。
最低限の企業理解や、あなた自身の過去の経験に基づいた一貫性のある回答ができないと、志望度が低いと見抜かれ、即座に不採用へとつながるでしょう。
【面接は準備しない方が良い?】おすすめの対策
自然体を意識しつつ、最低限の準備をしておくことが大切です。
「準備しすぎ」を避けて「自然体」を大切にするためには、回答の「核」となる部分だけをしっかり固めておくのが最も効果的です。
大切なのは、回答を文章として丸暗記することではなく、「キーワード」や「話の骨子」だけを準備しておくことです。
この準備があれば、本番では面接官との会話の流れに合わせて、あなた自身の言葉で自然に話すことができます。
頻出質問の回答を考えておく
事前に答えを整理しておくと落ち着いて話せます。
面接で必ず聞かれる「志望動機」「自己PR」「ガクチカ(学生時代に頑張ったこと)」などの頻出質問については、自分の経験を深く掘り下げ、論理が通った「核」を作っておきましょう。
この核は、「一番伝えたい結論」と「それを裏付ける具体的なエピソード」の2点で構成されます。
この2点さえ整理しておけば、本番では多少緊張しても、核をもとに言葉を紡ぎ出せるため、落ち着いて熱意のある受け答えができます。
業界・企業研究や自己分析をしておく
志望理由や強みを具体的に伝えられるようになります。
「なぜこの業界でなければならないのか?」「なぜ他社ではなくこの企業なのか?」という、面接の根幹となる質問に説得力を持たせるためには、徹底した企業研究が不可欠です。
また、あなた自身の「長所・短所」「成功体験・失敗体験」といった自己分析を深めておけば、面接でどんな質問がきても、あなたらしい一貫性のあるエピソードで答えられます。
企業研究と自己分析は、面接の土台となる最も重要な準備であり、これを怠ると他の対策がすべて無意味になりかねません。
マナーを確認しておく
面接の場にふさわしい立ち居振る舞いが身につきます。
「第一印象」は面接の評価に大きく影響します。
入室から退室までの一連の流れや、話すときの姿勢、Web面接での背景、目線といった基本的なビジネスマナーは、事前に一度確認し、練習しておきましょう。
マナーは単なる形式ではなく、相手への敬意を示すものであり、これが身についていれば面接に集中でき、自信を持って臨むことができます。
この「最低限の準備」に時間をかけることが、結果的に本番でのパフォーマンス向上につながります。
こちらの記事も参考にしてみてください。
【面接は準備しない方が良い?】対策は就活前から!
就活が始まる前から少しずつ準備を進めておくと安心です。
面接対策は、選考が始まってから焦って行うものではなく、大学3年生の今のうちから少しずつ準備を進めておくことが理想的です。
例えば、自己分析は、サークルやゼミ、アルバイトなどの日々の活動を通して「自分がどんな時にやりがいを感じたか」「どんな壁にぶつかり、どう乗り越えたか」を意識的に振り返るだけでも進められます。
また、業界研究も、ニュースや経済記事をチェックする習慣をつけるだけで、業界の動向や課題に対する視野を広げることができます。
選考直前になって慌てて準備するのではなく、日々の生活の中で「就活の視点」を持つことで、無理なく、着実に面接の土台を固めることができ、他の就活生と差をつけることができるでしょう。
【面接は準備しない方が良い?】対策のポイント
自然体を大切にしながらも、意識して取り組むべきポイントがあります。
「準備しすぎない」という姿勢は大切ですが、「面接という非日常の場」で自然体を出すためには、意識的な練習によってその自然体を定着させる必要があります。
ここで紹介する2つのポイントは、一人練習や対人練習のどちらにも共通して取り組むべき、重要な実践的練習です。
明るく丁寧に話す練習をする
第一印象を良くするためには、声のトーンや話し方を磨いておくことが大切です。
面接官は、話の内容だけでなく、あなたの「話し方」からも人柄やコミュニケーション能力を読み取っています。
内容が完璧でも、声が小さかったり、早口だったりすると、「自信がない」「入社後のコミュニケーションに不安がある」と判断されかねません。
友人や家族に協力してもらい、「いつもよりワントーン高い声」と「相手が聞き取りやすいスピード」で話す練習を繰り返してみましょう。
面接官の目を見て、ハキハキと話す練習をすることで、より良い印象を与え、あなたの魅力を最大限に引き出すことができます。
模擬面接や面接アプリで練習する
実践的な練習を重ねることで、自信を持って本番に臨めるようになります。
頭の中で回答を考えているだけでは、本番でスムーズに話せるとは限りません。
最も効果的なのは、「人前で話すこと」に慣れることです。
大学のキャリアセンターや就活エージェントなどを活用して模擬面接を受けるか、面接練習アプリを利用して、本番と同じ緊張感を伴う中で話す練習を重ねましょう。
準備した内容が伝わるか、不意な質問に対応できるかを試す実践的な練習は、あなたの自信を裏付ける根拠となります。
こちらの記事も是非参考にしてみてください。
【面接は準備しない方が良い?】面接で頻出の質問と回答例文
頻出の質問に備えることで、自信をもって面接に臨めます。
面接の「核」となる回答を準備するために、ここでは特に重要な質問と、具体的な業界や職種を想定した回答のポイントを紹介します。
これらの例文を丸暗記するのではなく、構成や論理の流れを参考にし、あなたの具体的な経験に置き換えるための「ヒント」として活用してください。
自己紹介
第一印象を決める大切な質問です。
回答例文
本日はお時間をいただきありがとうございます。
〇〇大学商学部マーケティング学科の〇〇と申します。
大学では、消費者行動分析を専攻し、特にWeb広告の効果測定に関する卒業論文を作成しました。
学業以外では、大学公認のダンスサークルで会計を担当し、年間予算の管理と透明化に尽力いたしました。
貴社の「新しい働き方を創造する」という企業理念に深く共感しており、本日の面接で、私の学びと貴社への貢献意欲をお伝えできればと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
志望動機
企業の理解度と熱意を問われる定番の質問です。
回答例文
私が貴社を志望する理由は、「医療現場のIT化を推進し、ミスをゼロにする」という貴社の強い使命感に共感したからです。
私は、病院でのボランティア経験を通じて、紙ベースの煩雑な情報管理が医療従事者に大きな負担をかけている現状を目の当たりにしました。
貴社が持つ医療機関向け電子カルテシステムにおける国内トップシェアの技術力と、それを支えるサポート体制に魅力を感じています。
入社後は営業職として、お客様である病院のニーズを深く聞き出し、貴社のシステムを導入することで、医療の質と効率の両面から社会に貢献したいと考えています。
自己PR
自分の強みをアピールする重要な質問です。
回答例文
私の強みは、目標達成のために粘り強く周囲を巻き込む「推進力」です。
大学3年次に参加した食品メーカーの製品開発インターンシップで、チームで市場調査を担当した際、目標としていた調査対象者数が集まらないという課題に直面しました。
私は、チームメンバーに対し、個々の得意分野に合わせて「SNSでの拡散」「大学内での直接依頼」などの役割を明確に割り振り、毎日進捗を確認するミーティングを主導しました。
その結果、チーム全体の士気が向上し、期限までに目標を上回る調査対象者数を確保することができました。
この推進力を活かし、貴社の企画職として目標達成に貢献します。
長所と短所
自己分析の深さが試される質問です。
回答例文
私の長所は、「多様な意見を尊重し、建設的な結論を導き出す傾聴力と調整力」があることです。
ゼミのグループワークで意見が対立した際、すべてのメンバーの主張を丁寧に聞き出し、共通の目的を再確認することで、全員が納得できる解決策を導き出しました。
一方、短所は「他人の意見を尊重しすぎるあまり、自分の意見を主張するのが遅くなることがある」点です。
この短所を改善するため、現在は、意見を聞いた上で、必ず「私の考えはこうです」と明確に発言するよう意識的に心がけています。
入社後は、チームワークを活かしつつ、主体性を持って業務に取り組みます。
ガクチカ(学生時代に頑張ったこと)
努力や成果を伝える代表的な質問です。
回答例文
学生時代に最も力を入れたのは、地域密着型スポーツクラブでのボランティア活動における、「地域イベント参加者数の増加」です。
高齢化によりイベントの参加者数が減少していたため、「参加者数を前年比20%増やす」という目標を立てました。
私は、若年層のニーズに応えるため、SNSを通じた情報発信を提案し、写真や動画に特化したコンテンツ作成を担当しました。
この結果、イベントの認知度が向上し、目標を上回る前年比30%増の参加者数を達成できました。
この経験から、現状を分析し、ターゲット層に合わせた新しい方法にチャレンジする重要性を学びました。
入社後に取り組みたいこと
将来のビジョンを示すことが求められます。
回答例文
入社後は、まずWebディレクターとして、貴社の主幹事業であるオンライン学習プラットフォームのサービス改善プロジェクトに参画し、ユーザーの利便性を高めるためのUI/UX改善に注力したいと考えています。
将来的には、現在の市場で不足している社会人向けリスキリングコンテンツのニーズを捉え、ユーザーの学習効果を最大化できるような新しいeラーニングコンテンツの企画・開発に携わりたいです。
常に市場の動向にアンテナを張り、貴社のEdTech分野におけるイノベーションを牽引する一員となることを目指します。
挫折した経験
困難にどう向き合ったかを見られる質問です。
回答例文
最も大きな挫折は、大学2年次に参加した海外短期留学プログラムで、現地の学生とのコミュニケーションが全く取れず、孤立してしまったことです。
語学力への自信が過信であったことに気づき、当時は非常に落ち込みました。
しかし、この経験を無駄にしたくないと考え、失敗の原因を「座学偏重」と分析し、そこから現地の学生に積極的に話しかける回数を増やす、ディスカッションに必ず参加するなど、行動を徹底的に変えました。
この経験を通じて、失敗を糧にする「自己反省力」と、状況を打破するための「主体的な行動力」を身につけることができました。
時事問題について
社会人としての視野や関心が問われます。
回答例文
私が関心を持っている時事問題は、「半導体産業における国際的なサプライチェーンの再構築」です。
これは、貴社のようなエレクトロニクス業界全体にとって、リスクとチャンスが入り混じる重要な課題だと認識しています。
地政学的なリスクの高まりを受け、国内での生産体制強化や、特定地域に依存しない調達先の多様化が急務となっています。
この状況下で、貴社が特に注力されている国内工場の新設とAIを活用した生産効率向上の取り組みは、日本経済の安全保障上も極めて重要だと考えます。
逆質問
意欲や理解度を示せる最後のチャンスです。
回答例文
ぜひお伺いしたいのですが、貴社の人事部門で現在、若手社員の方が最もチャレンジングだと感じている業務、または、入社後に活躍するために特に求められるスキルやマインドセットはどのようなことでしょうか? また、貴社が今後、海外市場において特に注力していく予定の地域や事業があれば、具体的に教えていただきたいです。
【面接は準備しない方が良い?】事前にやっておきたい対策
当日慌てないために最低限の準備は欠かせません。
面接の質を高めるためには、直前の準備で不安要素をゼロにしておくことが重要です。
どんなに回答を完璧に準備していても、当日になって慌ててしまうと実力が発揮できません。
面接前日までに必ず以下の基本的な確認を済ませておきましょう。
スケジュールや服装などの基本的な準備
忘れ物や遅刻を防ぎ、安心して面接に臨めます。
Web面接の場合は、使用するデバイスの充電、インターネットの通信環境の確認、背景の整理、そして適切な明るさの確保を徹底しましょう。
対面面接の場合は、会場までのルートと所要時間の再確認、企業から指定された持ち物の準備(特に履歴書、筆記用具、印鑑など)、そして清潔感のある服装の準備を怠らないようにしてください。
これらの基本的な準備が万全であることこそが、心の余裕につながります。
頻出質問と伝え方の最終確認
最後に答え方を整理しておくと落ち着いて話せます。
面接前日の夜には、作成した「回答の核」を再度見返し、「伝えたいキーワード」を頭の中で整理しましょう。
この時、一字一句暗記しようとしないのがポイントです。
面接官の目線になって、「この質問には、このエピソードを伝えよう」と流れを確認するだけに留めましょう。
回答を完璧に再現しようとするよりも、キーワードと骨子を意識することで、リラックスして本番に臨め、あなた自身の言葉で自然に話せるようになります。
まとめ
面接の準備は「やりすぎず、手を抜きすぎない」のバランスが命です。
「準備しない方がいい」という言葉に惑わされず、自己分析や企業研究といった「核」となる土台だけはしっかりと固めておきましょう。
その核があれば、本番で多少緊張しても、あなたの「素の魅力」と「論理的な思考力」が面接官に伝わります。
大切なのは、飾らないあなた自身の言葉で、入社への熱意と将来の可能性を示すことです。
今日紹介した対策を実践して、自信を持って面接に挑んでください。

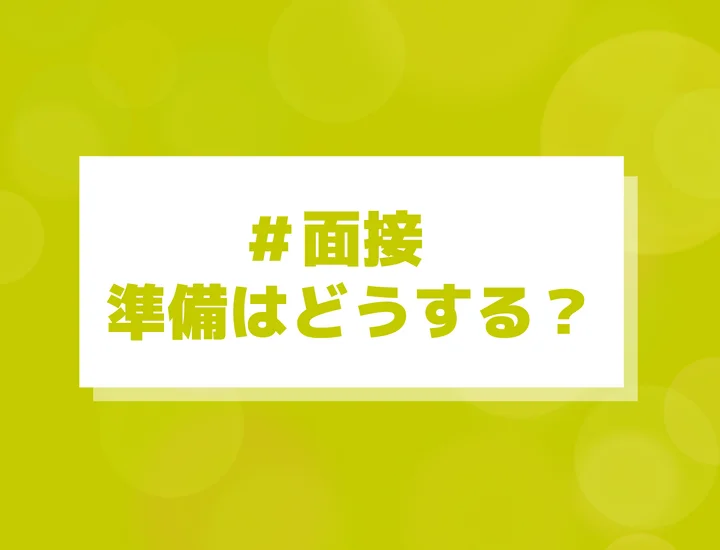





の適職50選】「-A」と「-T」別に向いていてる仕事をご紹介!_720x550.webp)




