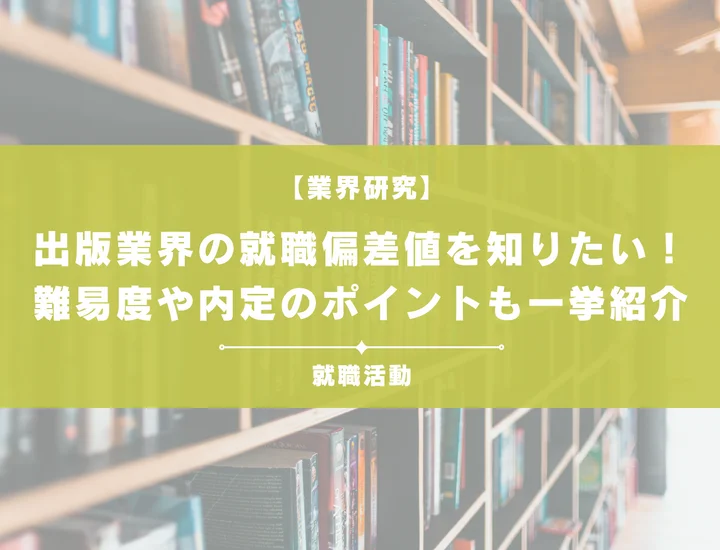HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
目次[目次を全て表示する]
就職偏差値とは
就職偏差値とは、企業の入社難易度を分かりやすく数値化した指標を指します。
大学受験の偏差値と同様に、数値が高いほど入社が難しいとされています。
ただし、これらは予備校や就職情報サイトが、人気度や選考難易度から独自に算出したもので、公式データではありません。
とはいえ、出版業界のような人気業界の難易度を客観的に把握する上で、多くの就活生が参考にしている便利な指標と言えるでしょう。
出版業界の就職偏差値ランキング
出版業界は、就活生から根強い人気があり、就職偏差値は総じて高い傾向にあります。
特に、講談社、集英社、小学館といった大手総合出版社は、マスコミ業界の中でも最難関レベルとして知られています。
ここでは、最新の情報を基にした出版業界の就職偏差値ランキングを紹介します。
ご自身の志望企業がどの程度の難易度なのか、目安として確認してみましょう。
【出版業界】Aランク(就職偏差値70以上)
【70】神話級作家(ノーベル文学賞・ピューリッツァー賞・ゴンクール賞クラス)
Aランクは世界的に評価される作家や作品が多く、出版業界の頂点に位置する層です。
こうした作家は文学賞受賞歴や国際的な評価が高く、出版社のブランド力向上に直結します。
入社や契約を目指すには、文章力だけでなく企画力や提案力が高く求められます。
【出版業界】Bランク(就職偏差値66以上)
【69】国宝級作家(芥川賞・直木賞・三島由紀夫賞・本屋大賞クラス)
【68】大ヒット作家(江戸川乱歩賞・小説現代長編新人賞クラス) ラノベ作家(アニメ化・電撃小説大賞)
【67】講談社 小学館 集英社 KADOKAWA 医学書院 福音館書店 医歯薬出版
【66】文藝春秋 東洋経済新報社 朝日新聞出版 日経BP NHK出版 新潮社 ダイヤモンド社 中外医学社
Bランクは国内で知名度の高い出版社や人気作家が多い層です。
大手出版社や受賞作家を多数抱え、安定した出版実績があります。
入社には出版業界の基礎知識や文章力、加えてヒット作を企画するためのマーケティング理解が重要です。
【出版業界】Cランク(就職偏差値61以上)
Cランク以降の就職偏差値を見るには会員登録が必要です。
無料登録すると、Cランク以降の就職偏差値をはじめとした
会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。
登録はカンタン1分で完了します。会員登録をして今すぐ出版業界の就職偏差値をチェックしましょう!
【65】宝島社 インプレス 旺文社 高橋書店 幻冬舎 岩波書店 中央公論新社 南江堂
【64】光文社 ポプラ社 昭文社 有斐閣 技術論評社 PHP研究所 日本能率協会マネジメントセンター
【63】中央法規出版 白泉社 翔泳社 オーム社 JTBパブリッシング マガジンハウス SBクリエイティブ メディックメディア ハーパーコリンズ・ジャパン
【62】中央経済社 早川書房 成美堂出版 ナツメ社 丸善出版 徳間書店 熊谷書店 世界思想社数学者 筑摩書房 秋田書店 日本関税協会デアゴスティーニジャパン
【61】メディカ出版 一迅社 扶桑社 永岡書店 主婦の友社 星雲社 東京官書普及 羊土社 主婦と生活社 ミネルヴァ書房 マイナビ出版 メジカルビュー社 ワニブックス 金融財政事情研究会
Cランクは中堅出版社や専門書・雑誌を中心に扱う企業が多い層です。
教育書や専門書、ライトノベルなどジャンル特化型の出版社が多く、幅広い知識や企画力が求められます。
入社には編集経験や企画力を示す作品例やインターン経験が評価されやすいです。
【出版業界】Dランク(就職偏差値56以上)
【60】西束社 文理 スターツ出版 ディスカヴァー・トゥエンティワン ベースボールマガジン社 秀和システム 実業之日本社 世界文化社 くもん出版 文響社 サンマーク出版
【59】祥伝社 朝倉書店 東京ニュース通信社 東京創元社 日本評論社 日外アソシエーツ 偕成社 アスク エクスナレッジ かんき出版バイインターナショナル アシェットコレクションジャパン
【58】弘文堂 地方小出版流通センター コスミック出版 共立出版 竹書房 岩崎書店 みすず書房 ジャパンタイムズ出版 南山堂 三省堂 白水社 自由国民社 東洋館出版社
【57】大学図書出版 東京リーガルマインド 明治図書出版 実務教育出版 平凡社 河合出版 森北出版 TOブックス 芳文社 日本文芸社 柏書房 アスコム ハースト婦人画報社
【56】コロナ社 化学同人 交通新聞社 明石書店 じほう 明日香出版社 日本ヴォーグ社 国書刊行会 吉川弘文館 創元社 サイエンス社 みらい 童心社 南雲堂 マイクロマガジン社 Jリサーチ出版 声の教育社
Dランクは地方出版社や教育・専門分野に特化した中小規模出版社が多い層です。
地域密着型の書籍や専門書を中心に出版し、地道な営業力や企画力が求められます。
入社には、対象読者への理解や編集経験、企画提案力をアピールすることが重要です。
【出版業界】Eランク(就職偏差値50以上)
【55】くろしお出版 桐原書店 晶文社 清文社 金剛出版 市ケ谷出版社 日本スポーツ企画出版社 へるす出版 少年画報社 1CCCメディアハウス 白夜書房 マッグガーデン フロンティアワークス
Eランクは小規模・専門分野や地域密着型の出版社が中心です。
趣味・学習・スポーツ関連などニッチジャンルを扱う企業が多く、個別の強みや専門性が求められます。
入社には、特定分野の知識や編集・企画の経験を具体的に示すことが有効です。
【出版業界】とは
出版業界とは、書籍、雑誌、コミック、教科書などの印刷物を企画、制作し、読者に届ける産業を指します。
単に紙の媒体を製造・販売するだけでなく、情報や知識、物語といったコンテンツを通じて、社会の文化を形成し、人々の知的好奇心を満たす重要な役割を担っています。
近年は電子書籍やWebメディアなど、デジタルの領域にも事業が急速に拡大しています。
ここでは、その具体的なプロセスや役割について詳しく解説していきます。
書籍や雑誌などの印刷物を制作・販売する業界
出版業界の最も伝統的かつ中心的なビジネスは、書籍や雑誌、コミックといった紙媒体の印刷物を制作し、販売することです。
このプロセスは、まず編集者がどのような本や雑誌が読者に求められているかを考え、企画を立てることから始まります。
企画が通れば、著者に執筆を依頼し、デザイナーやイラストレーターと協力しながら原稿を完成させ、印刷所に発注します。
完成した出版物は、取次(出版流通会社)を通じて全国の書店に配本され、読者の手元に届きます。
出版社は、この一連の流れを管理し、生み出されたコンテンツから利益を得ます。
読者が書店で手に取る一冊一冊には、こうした多くの人々の仕事が詰まっています。
近年は紙媒体だけでなく、電子書籍として同時に展開することも一般的になっています。
このコンテンツを生み出す力が、業界の核となる機能です。
情報や知識、文化を広める役割を持つ
出版業界は、単なる営利産業としてだけでなく、社会的なインフラとしての一面も持っています。
それは、情報や知識、そして文化を広く人々に伝え、次世代に継承していくという重要な役割です。
例えば、学術書や専門書は研究の成果を社会に還元し、教科書は教育の基盤を支えます。
雑誌や新書は、最新の時事問題やトレンドを分かりやすく解説し、人々の視野を広げます。
また、小説やコミック、写真集といったエンターテイメント作品は、人々の心を豊かにし、時には社会現象を生み出すほどの文化的な影響力も持ちます。
インターネットが普及した現代においても、専門家である編集者や校閲者によって情報の正確性や質が担保された出版物は、信頼できる情報源として大きな価値を持っています。
このように、出版業界は社会の知的活動や文化の発展に不可欠な存在と言えるでしょう。
企画・編集・流通・販売まで一貫したプロセス
一冊の本が読者に届くまでには、多くの部門が連携する一貫したプロセスが存在します。
まず企画・編集部門が、市場のニーズを読み取り、著者と協力して原稿を制作します。
ここでは、読者の心に響く内容にするための推敲や、誤字脱字をなくす校閲作業が行われます。
次に、制作部門がデザイナーと協力してDTPデータを作成し、印刷所と連携して印刷・製本を行います。
完成した出版物は、そのまま書店に並ぶわけではありません。
取次と呼ばれる出版流通会社を経由し、全国の書店に配本されます。
この流れを管理するのが流通部門です。
そして、書店でより多くの読者に手に取ってもらえるよう、POPの作成やイベントの企画、メディアへの宣伝活動を行うのが営業・販売促進部門の役割です。
近年は、これに加えて電子書籍の配信やWebメディアでのプロモーションも重要な業務となっています。
これら全ての機能が連動して、出版ビジネスは成り立っています。
【出版業界】特徴
就職偏差値が高い出版業界は、他の業界とは異なるいくつかの独自の特徴を持っています。
コンテンツそのものの魅力がビジネスの根幹となるクリエイティブな側面が強い一方で、市場の変化に対応するためのデジタル化が急務となっています。
また、社内の人間だけでなく、多くの外部クリエイターとの協働が不可欠です。
ここでは、出版業界を目指すなら知っておきたい、3つの主要な特徴について詳しく見ていきます。
コンテンツ重視でクリエイティブな要素が強い
出版業界の最大の特徴は、コンテンツ、すなわち情報や物語そのものが商品である点です。
自動車や家電メーカーとは異なり、製造するのはモノではなく、アイデアや知識、感動といった無形の価値です。
そのため、編集者をはじめとする社員には、常に新しい企画を生み出すクリエイティブな発想力が求められます。
何が読者に受けるのか、世の中のトレンドはどこにあるのかを敏感に察知し、それを形にするセンスがビジネスの成功に直結します。
また、一冊の本のデザイン、タイトルの付け方、帯のキャッチコピー一つひとつにも、読者の興味を引くための工夫が凝らされます。
どれだけ素晴らしい原稿であっても、その魅力を最大限に引き出す編集やデザインがなければ、ヒットには繋がりません。
このように、論理的な分析だけでなく、人の心を動かす感性や創造性が強く求められるのが、この業界の大きな特徴です。
市場規模は縮小傾向だがデジタル化が進む
出版業界を目指す上で、市場の現状を理解しておくことは不可欠です。
残念ながら、雑誌や書籍といった紙媒体の市場規模は、スマートフォンの普及やライフスタイルの変化により、長期的に縮小傾向が続いています。
いわゆる出版不況と呼ばれる状況です。
しかし、業界が衰退しているわけではありません。
紙の代わりに急成長しているのが、電子書籍やコミックアプリ、Webメディアといったデジタル領域です。
多くの出版社は、単なる印刷物の会社から、コンテンツを多様な形で提供する総合コンテンツプロバイダーへと変貌を遂げようとしています。
例えば、人気コミックを電子配信するだけでなく、アニメ化やゲーム化、海外展開といったライツビジネスで大きな収益を上げています。
このように、業界全体が大きな変革期を迎えており、紙の知識だけでなく、デジタルへの対応力や新しいビジネスモデルを考える力が求められています。
著者やクリエイターとの協働が多い
出版社の仕事、特に編集職は、社内で完結する業務よりも、社外の著者やクリエイターとの協働が中心となります。
編集者は、小説家、漫画家、学者、ジャーナリスト、イラストレーター、デザイナー、カメラマンといった、様々な分野の専門家とチームを組んで一つの作品を作り上げます。
彼らの才能を最大限に引き出し、時には良き相談相手として、時には厳しい意見を交わしながら、最高のコンテンツを生み出すためのパートナーとなることが求められます。
そのため、高度なコミュニケーション能力や調整力が不可欠です。
また、相手のスケジュールを管理し、締め切りまでに原稿を完成させるための粘り強い交渉力も必要です。
社外の才能ある人々と深く関わり、彼らの情熱に触れながらモノづくりができる点は、この業界ならではの大きな魅力であり、同時に高い対人スキルが求められる所以でもあります。
【出版業界】向いている人
就職偏差値の高い出版業界では、どのような人材が求められているのでしょうか。
単に本が好きというだけでは務まらない、専門的な適性があります。
コンテンツの根幹となる言葉や物事への深い探究心、そして多くの人を巻き込む協調性などが挙げられます。
ここでは、出版業界の仕事、特に編集や企画といった職種で活躍できる人の特徴を、3つのポイントに絞って具体的に解説していきます。
文章や言葉を扱うことが好きな人
出版業界の扱う商品の核は、文章や言葉です。
そのため、文章を読んだり、書いたり、あるいは深く吟味したりすることが根源的に好きな人が向いています。
これは単に趣味として小説を読むのが好きというレベルに留まりません。
例えば編集者であれば、著者の原稿を読み込み、より読者に伝わる表現はないか、論理の矛盾はないかを考え抜き、提案する必要があります。
一つの単語の選び方、句読点の打ち方一つで、文章のニュアンスが大きく変わることを理解する繊細な言語感覚が求められます。
また、営業職や販売促進職であっても、本の魅力を伝えるためのキャッチコピーを考えたり、書店向けの案内文を作成したりと、言葉を扱う場面は非常に多いです。
地道な校閲作業や、膨大な量の資料を読み込むことを苦とせず、言葉の力で何かを伝えたいという強い意志を持つ人にとって、最適な環境と言えるでしょう。
好奇心が旺盛で幅広い知識を持つ人
編集者や企画職の仕事は、新しい企画の種を見つけることから始まります。
その種は、日常生活のあらゆる場所に隠されています。
そのため、好奇心が旺盛で、常に世の中の動きにアンテナを張っている人が求められます。
政治経済、科学、歴史、サブカルチャー、グルメ、スポーツなど、一見自分の担当分野とは関係なさそうなことにも広く興味を持ち、情報をインプットし続ける姿勢が重要です。
異なる分野の知識が結びつくことで、今までにないユニークな企画が生まれることも少なくありません。
また、著者と深い議論を交わしたり、専門的な内容の原稿を扱ったりする上でも、幅広い教養は不可欠な武器となります。
面接においても、最近気になったニュースや流行について深く掘り下げられることが多いため、日頃から自分の興味の幅を広げておくことが、選考を突破する鍵にもなるでしょう。
人と協力して物を作るのが好きな人
出版物の制作は、個人作業ではなくチームプレーです。
前述の通り、著者やデザイナー、印刷所、営業担当者など、非常に多くの人々が関わります。
編集者はその中心に立ち、プロジェクト全体を円滑に進めるハブ(中継点)としての役割を担います。
そのため、自分一人の力で何かを成し遂げたいという志向の人よりも、多様な専門家と協力し、彼らの力を引き出しながら一つの目標に向かっていくプロセスを楽しめる人が向いています。
時には、立場の異なる人々の間で意見が対立することもあります。
そうした場面でも、粘り強く調整し、全員が納得できる着地点を見つけ出す力が求められます。
自分が表舞台に立つよりも、著者やクリエイターを支える黒子(くろこ)として、最高の作品が生まれる環境を整えることにやりがいを感じられる人にとって、出版業界はまさに天職と言えるでしょう。
【出版業界】内定をもらうためのポイント
就職偏差値が最難関レベルの出版業界から内定を勝ち取るためには、入念な準備と戦略が不可欠です。
単に本が好き、雑誌が好きといった熱意だけでは、多くのライバルとの差別化は図れません。
自分が即戦力として、あるいは将来的に会社に貢献できる人材であることを具体的に示す必要があります。
ここでは、出版業界の選考を突破するために、特に重要な3つのポイントについて詳しく解説していきます。
企画力やアイデア力を具体的な経験で示す
出版業界の選考、特に編集職では、ほぼ間違いなく企画力を問われます。
エントリーシートで企画書の提出を求められたり、面接でどんな本を作りたいかを質問されたりします。
この時、単に自分の好きな分野の企画を提案するだけでは不十分です。
なぜ今、その企画が読者に求められているのか、ターゲットは誰か、競合する書籍とどう差別化するか、といったマーケティングの視点まで含めて論理的に説明する必要があります。
また、学生時代の経験を通じて、自らの企画力をアピールすることも有効です。
例えば、サークル活動でフリーペーパーを制作した経験や、イベントを企画して集客に成功した経験など、自らアイデアを出し、それを実行に移した具体的なエピソードを語れるように準備しましょう。
アイデアの着眼点と、それを実現する実行力の両方を示すことが重要です。
業界理解を深く示す
志望動機において、業界や企業への理解度の深さは、熱意を測る重要な指標となります。
なぜ他の業界ではなく出版業界なのか、そして、数ある出版社の中で、なぜその会社でなければならないのかを明確に語る必要があります。
そのためには、徹底した企業研究が不可欠です。
その会社の代表的な出版物や最近のヒット作を読み込むのはもちろんのこと、IR情報(上場企業の場合)やインタビュー記事などを読み込み、その会社が今、どのような分野に力を入れ、どのような戦略(例:デジタル展開、海外事業、ライツビジネス)で成長しようとしているのかを把握しましょう。
その上で、紙媒体の市場縮小といった業界が抱える課題を理解し、それに対して自分が入社後どのように貢献できるのかを、自分の強みと結びつけて具体的に提案できると、他の就活生と大きな差をつけることができます。
コミュニケーション能力や調整力を強調する
出版社の仕事は、著者やデザイナーといった社外のクリエイターや、社内の営業・制作部門など、多くの人と関わるハブとなります。
そのため、選考ではコミュニケーション能力や調整力が非常に重視されます。
面接官は、学生時代の経験を通じて、この素質があるかどうかを見ています。
例えば、部活動やサークル活動、アルバbイトなどで、立場の異なるメンバーの意見をまとめたり、対立する意見を調整したりして、プロジェクトを成功に導いた経験は、強力なアピール材料となります。
大切なのは、単にリーダーシップを発揮したというだけでなく、どのように人の話を聞き、信頼関係を築き、困難な状況を乗り越えたのかという具体的なプロセスを語ることです。
編集者は著者にとっての伴走者であるため、相手の才能を引き出し、気持ちよく仕事をしてもらうための人間的な魅力や調整力を示すことが重要です。
【出版業界】よくある質問
就職偏差値が高く、独特な文化を持つ出版業界については、就職活動を進める上で様々な疑問が浮かぶことでしょう。
専攻による有利不利、求められるスキル、キャリアパスなど、気になる点は多いはずです。
ここでは、出版業界を志望する就活生から特によく寄せられる3つの質問について、分かりやすく回答していきます。
文系・理系どちらが有利ですか?
結論から言うと、文系・理系どちらかが一方的に有利ということはありません。
確かに、扱うコンテンツの特性上、文学部や法学部、経済学部といった文系出身の社員が多い傾向はあります。
しかし、理系学生の需要も非常に高まっています。
例えば、科学雑誌、医学・看護系の専門書、IT関連の書籍などを制作する部門では、理系分野の専門知識がそのまま業務に活かされます。
また、近年はWebメディアの運営や電子書籍の販売において、データ分析に基づいたマーケティングが不可欠となっており、理系学生が持つ論理的思考力やデータ解析スキルが重宝される場面も増えています。
選考においては、文系か理系かという枠組みよりも、自分の専門性や学んできたことを、出版社のどのような仕事に活かせるのかを具体的に説明できることの方がはるかに重要です。
電子書籍やWeb媒体への対応は必須ですか?
必須であると言えるでしょう。
前述の通り、紙媒体の市場が縮小する中で、出版業界の成長はデジタル領域にかかっています。
もはや、電子書籍やWebメディアは紙の補完的な役割ではなく、ビジネスの柱の一つとなっています。
もちろん、入社時点ですべての専門知識を持っている必要はありません。
しかし、少なくとも電子書籍を日常的に利用していたり、関心のある分野のWebメディアを定期的にチェックしていたりするなど、デジタルコンテンツへの関心の高さを示すことは重要です。
面接でどんな本を作りたいかという質問に対し、紙媒体だけでなく、SNSでのプロモーション展開やWebメディアとの連動企画まで含めて提案できれば、業界の現状をよく理解していると評価されるでしょう。
紙の文化を尊重しつつも、新しいテクノロジーやプラットフォームに柔軟に対応していく姿勢が求められています。
編集職未経験でも入社できますか?
はい、新卒採用においては、編集職の経験は一切問われません。
企業側も、学生に実務経験がないことは承知の上で採用活動を行っています。
中途採用であれば即戦力としての実務経験が求められますが、新卒採用で重視されるのは、あくまでポテンシャルです。
そのポテンシャルとは、旺盛な好奇心、物事を深く考える力、新しい企画を生み出す発想力、そして著者やクリエイターと信頼関係を築けるコミュニケーション能力などです。
これらの素養があるかどうかを、学生時代の経験や面接での対話、企画書の出来栄えなどから総合的に判断します。
編集プロダクションでのアルバイト経験などが必須となることはありません。
それよりも、自分が大学時代に何を学び、何に熱中し、そこからどのような力を得たのかを、自信を持って語ることの方が大切です。
未経験であることを恐れる必要は全くありません。
まとめ
出版業界は、就職偏差値が示す通り、入社するのが非常に難しい業界の一つです。
しかし、情報や文化、物語を世に送り出し、人々の知的好奇心を満たすという仕事は、他では得難い大きな魅力とやりがいに満ちています。
業界の現状とそこで求められる人物像を深く理解し、万全の準備を整えて、ぜひこの知的なフィールドへの挑戦を成功させてください。