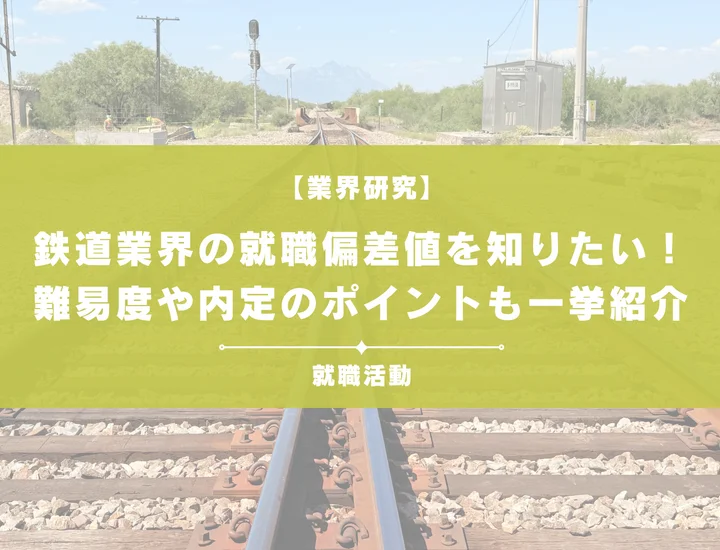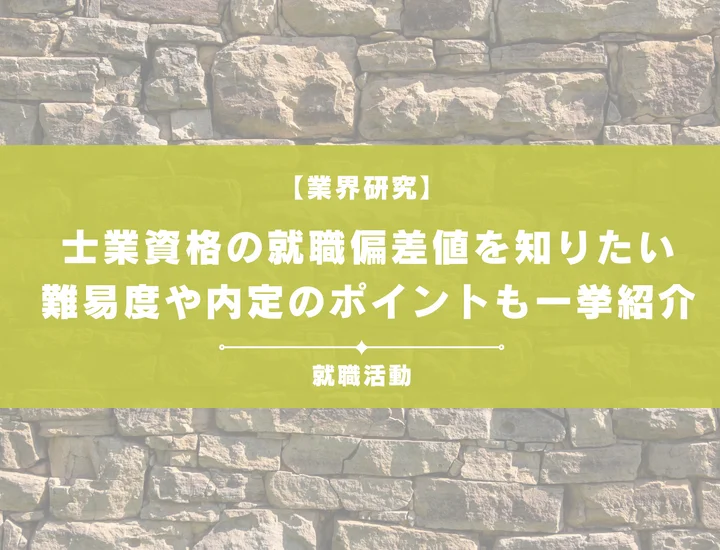HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
目次[目次を全て表示する]
就職偏差値とは
就職偏差値とは、企業の入社難易度を相対的に示すために使われる指標のことです。
これは特定の機関が出す公式なデータではなく、主に就職活動生の情報交換の中で使われる俗語的なものです。
しかし、人気度、選考の難しさ、採用実績(学歴)などを基にしているため、業界研究や企業選びのひとつの目安として役立ちます。
今回の鉄道業界の就職偏差値ランキングも、そうした視点で参考にしてください。
鉄道業界の就職偏差値ランキング
ここでは、鉄道業界の就職偏差値ランキングを紹介します。
このランキングは、企業の安定性、給与水準、採用倍率、就活生からの人気度などを総合的に判断して作成されたものです。
ただし、偏差値はあくまで目安の一つです。
このランキングを参考に、各社の特徴や事業内容の研究を深めていきましょう。
【鉄道業界】Aランク(就職偏差値70以上)
【70】JR東海
業界の最高峰に位置するのがJR東海です。
東海道新幹線という日本の大動脈を基盤に持つだけでなく、リニア中央新幹線という国家規模のプロジェクトを推進しており、他社とは一線を画す存在です。
入社難易度は極めて高く、高学歴層の応募が集中します。
徹底した企業研究はもちろんのこと、日本のインフラを支えるという強い使命感や、プレッシャーの中で高いパフォーマンスを発揮できる素養をアピールすることが不可欠です。
【鉄道業界】Bランク(就職偏差値66以上)
【69】JR東日本 阪急阪神HD
【68】東急
【67】東急電鉄 阪急電鉄
【66】小田急電鉄 京王電鉄 東武鉄道 京成電鉄 東京メトロ
Aランクに匹敵するJR東日本や、首都圏・関西圏の主要路線を担う大手私鉄が並びます。
これらの企業は、鉄道事業だけでなく不動産開発や生活関連サービス(街づくり)に強みを持ち、多角的な経営を展開しています。
入社のためには、鉄道事業への理解はもちろん、各社の沿線開発やDX推進といった多角的な事業への深い理解と、そこで自身がどう貢献できるかを明確に示す必要があります。
インターンシップへの参加などを通じて、早期から企業との接点を持つことも重要になるでしょう。
【鉄道業界】Cランク(就職偏差値61以上)
Cランク以降の就職偏差値を見るには会員登録が必要です。
無料登録すると、Cランク以降の就職偏差値をはじめとした
会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。
登録はカンタン1分で完了します。会員登録をして今すぐ鉄道業界の就職偏差値をチェックしましょう!
【65】JR西日本 近畿日本鉄道 大阪メトロ
【64】JR九州 名古屋鉄道 京浜急行電鉄 西武鉄道
【63】相模鉄道 南海電鉄 京阪電気鉄道 西日本鉄道 阪神電気鉄道
【62】JR貨物
【61】JR北海道 JR四国 静岡鉄道 遠州鉄道
JR各社や、各地域で確固たる基盤を持つ大手・準大手私鉄が中心となるランクです。
Bランク企業と同様に安定性が高い一方で、より地域密着型の事業展開や観光開発に特色を出している企業が多く見られます。
対策としては、Bランク企業に準じた準備に加え、「なぜ首都圏(関西圏)ではなく、その地域なのか」を明確に伝えることが重要です。
地域活性化への貢献意欲や、各社独自の取り組み(例えばJR九州のクルーズトレインや多角化戦略)に対する具体的なキャリアプランを示すと良いでしょう。
【鉄道業界】Dランク(就職偏差値56以上)
【60】神戸電鉄 広島電鉄 新京成電鉄
【59】山陽電気鉄道 京福電気鉄道 伊予鉄グループ
【58】秩父鉄道 宇都宮ライトレール
【57】一畑電気鉄道 神戸高速鉄道
【56】長野電鉄 関東鉄道 会津鉄道 島原鉄道 のと鉄道 福井鉄道 秩父鉄道 豊橋鉄道 伊豆箱根鉄道 富山地方鉄道 北陸鉄道 関西高速鉄道 紀州鉄道
Cランクまでの企業と比べると規模は小さくなりますが、それぞれの地域で重要な交通インフラを担う中堅私鉄や地方鉄道が多く含まれます。
宇都宮ライトレールのような新しい形態の交通事業者もここに入ります。
入社対策としては、大手企業との違いを明確に理解し、その地域社会に根差して働きたいという強い意志を示すことが求められます。
安定志向だけでなく、地域住民の目線に立ったサービス改善の提案など、主体的な姿勢をアピールすることが重要です。
【鉄道業界】Eランク(就職偏差値50以上)
【55】長良川鉄道 樽見鉄道 明知鉄道 天竜浜名湖鉄道 道南いさりび鉄道 IGRいわて銀河鉄道 秋田内陸縦貫鉄道 山形鉄道 真岡鐵道 鹿島臨海鉄道 わたらせ渓谷鐵道 えちごトキめき鉄道 肥薩おれんじ鉄道 平成筑豊鉄道 松浦鉄道 南阿蘇鉄道 土佐くろしお鉄道 北近畿タンゴ鉄道 信楽高原鐵道 若桜鉄道
主に地方の交通を担う第三セクター鉄道が中心となるランクです。
これらの企業は地域住民の生活の足を守るという重要な役割を担っていますが、経営環境は厳しい場合も少なくありません。
入社のためには、鉄道が好きという情熱はもちろんのこと、厳しい経営環境の中でコスト意識を持ち、地域と一体となって観光誘致や利用促進に貢献できるアイデアと実行力を示す必要があります。
少数精鋭で幅広い業務を担うことも多いため、柔軟性や主体性が特に重視されるでしょう。
【鉄道業界】とは
鉄道業界と聞くと、多くの人が日々の通勤や通学で利用する電車を思い浮かべるでしょう。
この業界は、人々の移動や物流を支える、社会に欠かせないインフラ産業です。
その事業内容は多岐にわたり、単に列車を運行するだけでなく、駅周辺の不動産開発や生活関連サービスまで及びます。
ここでは、鉄道業界の基本的な全体像について、3つの側面から詳しく解説していきます。
人々の移動や物流を「支える」社会基盤
鉄道業界の最も根幹となる役割は、人々の移動や物流を支える社会基盤(インフラ)である点です。
多くの人にとって、鉄道は通勤、通学、旅行など、日常生活に欠かせない移動手段です。
これがもし停止すれば、都市機能は麻痺し、経済活動にも甚大な影響が出ます。
また、旅客輸送だけでなく、貨物輸送も重要な役割です。
コンテナや資源を運ぶ貨物列車は、日本の物流網の根幹を担っています。
このように、鉄道業界は電気や水道、ガスと同じように、社会の土台として機能しています。
そのため、他の業界と比べても特に高い公共性と社会貢献性が求められます。
日々の安全で正確な運行を維持すること自体が、社会への大きな貢献となるのです。
この社会を支えているという使命感が、この業界で働く最大の魅力の一つと言えるでしょう。
JR、大手私鉄、公営(地下鉄など)、第三セクターなど様々な種類の企業
一口に鉄道業界といっても、その中には成り立ちや事業規模が異なる、様々な種類の企業が存在します。
最も規模が大きいのは、分割民営化によって誕生したJRグループ(JR東日本、JR東海、JR西日本など)です。
広大なエリアで新幹線や在来線を運行しています。
次に、特定の沿線エリアで鉄道事業と街づくりを一体的に行う大手私鉄(東急、阪急阪神HD、小田急など)があります。
また、大都市圏の交通を担う公営鉄道(東京メトロ、大阪メトロなどの地下鉄)も大きな存在です。
さらに、地方では、自治体と民間が共同出資する第三セクター鉄道が、地域住民の足を守っています。
就職偏差値ランキングでは、主にJRや大手私鉄が上位に来ますが、企業の種類によって経営の安定性、事業の多角化の度合い、そして求められる役割も大きく異なります。
業界研究の際は、この違いを理解することが重要です。
鉄道事業を核とした「街づくり」や生活サービス
現代の鉄道会社、特に大手私鉄やJRは、単に電車を走らせるだけの会社ではありません。
彼らは鉄道事業を核として、駅ビルや商業施設の運営、不動産開発(マンションやオフィスビル)、ホテル、レジャー施設、さらにはスーパーやクレジットカード事業まで、幅広く手掛けています。
これは、鉄道の利用客を増やすと同時に、沿線エリア全体の価値を高めるためです。
電車に乗ってもらうだけでなく、沿線に住んでもらい、沿線で買い物をしてもらう。
こうした循環を生み出すビジネスモデルを確立しています。
そのため、総合職として入社した場合、鉄道の現場だけでなく、こうした多角化した事業部門で働く可能性も大いにあります。
鉄道業界を志望する際は、この街づくりや生活サービスといった側面にも目を向けることが、企業理解を深める鍵となります。
【鉄道業界】特徴
鉄道業界には、他の産業にはない独特な特徴がいくつかあります。
最も大きいのは、社会インフラを担うことによる高い公共性と、それを支えるための厳格な規律です。
また、非常に大規模な設備を必要とする装置産業としての側面も持ちます。
ここでは、就職活動を進める上で知っておきたい、鉄道業界の主な特徴を3つのポイントに分けて解説します。
これらの特徴が、鉄道業界の就職偏差値や働き方にも影響を与えています。
社会貢献性や公共性が非常に高いビジネスモデル
鉄道業界の最大の特徴は、そのビジネスモデルが極めて高い社会貢献性と公共性に基づいている点です。
鉄道は、大勢の人々を定時性・安全性・効率性の面で優位性を持って輸送できるシステムです。
この機能は、特に都市部において、人々の通勤・通学や経済活動を支える血液のような役割を果たしています。
利益を追求する民間企業でありながらも、その事業の根幹は公共の利益に資するものでなければなりません。
そのため、法律による規制(鉄道事業法など)も多く、安全の確保は何よりも優先されます。
景気が悪化したからといって、簡単に路線を廃止したり、運行本数を極端に減らしたりすることはできません。
このように、利益追求と公共性の維持という、時には相反する要素のバランスを取りながら経営を行うことが求められる、非常に特殊で責任の重い業界です。
多くの部門が連携する「チームワーク」と「規律」
鉄道の安全で正確な運行は、一人の力では決して成り立ちません。
運転士や車掌といった乗務員はもちろん、駅で案内や安全確認を行う駅係員、車両を点検・整備する車両部門、線路や電気設備を保守する工務・電気部門、そして全体の運行を管理する指令員など、数えきれないほどの部門が関わっています。
これらの部門が、定められたルール(規律)を守り、緊密に連携(チームワーク)することで、初めて電車は安全に動きます。
一つのミスや連絡漏れが、大事故につながる危険性を常にはらんでいます。
そのため、鉄道業界で働く人々には、自分の役割を確実に果たす責任感と、他部門と円滑に連携する協調性、そして何よりも定められた規律を厳格に守る姿勢が強く求められます。
個人のファインプレーよりも、組織全体としての確実なプレーが評価される世界です。
長期的な安定運用と、時代に合わせた変革
鉄道業界は、大規模なインフラを維持・管理する必要があるため、非常に長期的な視点での経営が求められます。
これは、就職偏差値が高い理由の一つである安定性にもつながっています。
しかし、現代は大きな変革期を迎えています。
日本では人口減少が始まり、特に地方では利用客の減少が深刻な問題となっています。
また、新型コロナウイルスの影響でリモートワークが普及し、都市部の通勤需要も以前とは変わってきました。
こうした社会の変化に対応するため、各社は必死に変革に取り組んでいます。
例えば、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進による業務効率化、MaaS(マース)と呼ばれる新しい移動サービスの開発、不動産や非鉄道事業のさらなる強化などです。
伝統的な安定性を維持しつつ、未来に向けてどう変わっていくか。
その両立が今、強く求められています。
【鉄道業界】向いている人
鉄道業界は、その公共性の高さから、特有の素養を持った人材を求めています。
高い就職偏差値の企業を突破するには、この業界の仕事の本質を理解し、自身がそれにマッチしていることをアピールする必要があります。
ここでは、どのような人が鉄道業界に向いているのか、代表的な3つの特徴をご紹介します。
自分がこれらの特徴を持っているか、自己分析の参考にしてみてください。
「使命感」や「責任感」を持てる人
鉄道業界で働く上で、最も重要な資質は、強い使命感と責任感です。
鉄道の仕事は、数えきれないほど多くの人々の命と生活を預かる仕事です。
台風や大雪といった悪天候の日でも、多くの人が駅で待っている限り、安全を確保した上で電車を動かし続けなければなりません。
また、深夜や早朝の勤務、万が一のトラブル対応など、厳しい場面も多々あります。
そうした時に支えとなるのが、社会インフラを支えているという使命感や、お客様を安全に目的地まで送り届けるという責任感です。
華やかな仕事ばかりではありませんが、自分の仕事が社会の役に立っていると実感できることは、大きなやりがいにつながります。
日々の当たり前を守るために、強い意志を持って職務を全うできる人が求められています。
コツコツと物事に取り組める人
鉄道の安全は、日々の地道な作業の積み重ねによって支えられています。
例えば、車両の点検や線路の保守作業は、一つ一つのボルトの緩みを確認したり、ミリ単位のズレを修正したりといった、非常に細かく、根気のいる仕事です。
駅係員の指差確認や、乗務員の喚呼(かんこ)といった安全動作も、毎日何百回と繰り返されます。
こうした作業は一見地味に見えるかもしれませんが、どれか一つでも怠ると大事故につながりかねません。
そのため、派手な成果を追い求めるタイプの人よりも、決められたルールや手順を守り、どんなに単調な作業であっても、その重要性を理解してコツコツと真面目に取り組み続けられる人が高く評価されます。
日々の当たり前を、当たり前にやり続ける力こそが、この業界では最も重要視される能力の一つです。
グローバルな視点よりも「地域社会の発展」に関心がある人
商社やメーカーのように世界を舞台に活躍する仕事とは異なり、鉄道業界のビジネスの基盤は、あくまで自社の沿線という限られた地域です。
もちろん、インバウンド(訪日外国人)対応などで国際的な側面もありますが、仕事の中心は、その地域に住む人々を輸送し、その地域の価値を高めていくことです。
そのため、グローバルに活躍したいという志向性よりも、自分が関わる地域社会を豊かにしたい、地元の人々の生活を便利にしたい、といった地域貢献への関心が強い人の方が向いています。
大手私鉄のビジネスモデルは、まさに沿線地域との共存共栄です。
自分の仕事が、目の前の地域の発展に直接的につながることにやりがいを感じられる人にとって、鉄道業界は非常に魅力的な職場となるでしょう。
【鉄道業界】内定をもらうためのポイント
就職偏差値ランキング上位の鉄道業界から内定を獲得するためには、ポイントを押さえた選考対策が不可欠です。
単に人気があるから、安定しているからという理由だけでは、多くのライバルに埋もれてしまいます。
この業界ならではの視点を持ち、企業研究と自己分析を深く行う必要があります。
ここでは、内定を勝ち取るために特に意識すべき3つの重要なポイントを紹介します。
「なぜ鉄道業界なのか」を社会貢献性や使命感と絡めて語る
選考で必ず問われるのが、なぜ他の業界ではなく鉄道業界なのか、という志望動機です。
鉄道業界は、社会インフラを支えるという非常に強い使命感と公共性を持っています。
この点に共感していることを、自分の言葉で具体的に伝えることが重要です。
例えば、単に安定しているから、という理由だけでは評価されません。
そうではなく、人々の生活の基盤を支える仕事に魅力を感じたことや、日々の当たり前を守る責任感にやりがいを感じることなどを、自身の経験と結びつけて語る必要があります。
例えば、アルバイトでの経験から縁の下の力持ちとして支える役割に喜びを感じた、といったエピソードです。
社会貢献性の高さを理解し、その重い責任を自ら進んで引き受ける覚悟があることを示すことが、内定への第一歩となります。
規律を守り、チームで「安全」を達成した経験をアピール
鉄道業界が何よりも重視するキーワードは安全です。
そして、その安全は厳格な規律とチームワークによって守られています。
したがって、学生時代の経験の中で、自分がルールや決まり事をいかに重視し、それを守ってきたかをアピールすることが非常に有効です。
例えば、部活動やサークル活動、アルバイト先で、安全やルール遵守に関するマニュアルを作成した経験や、ミスを防ぐための仕組みづくりに貢献した経験などです。
また、個人の力だけでなく、チーム全体で目標を達成するために、自分がどのような役割を果たしたかを具体的に述べましょう。
鉄道の仕事はチームプレーが基本です。
高い協調性を持ち、組織の一員として規律正しく行動できる人材であることを示すことが、高い評価につながります。
沿線地域への理解や、その「街づくり」にどう貢献したいかを示す
特に大手私鉄やJRを志望する場合、鉄道事業だけでなく、不動産開発や生活サービスといった街づくりへの理解が不可欠です。
なぜ数ある鉄道会社の中で、その会社を選んだのかを説明する際、沿線地域の特色や魅力、そして課題について、自分なりの考えを持っていることを示しましょう。
実際にその沿線に足を運び、駅周辺の施設を見たり、人々の流れを観察したりすることも企業研究になります。
その上で、自分が入社したら、その会社の持つリソース(鉄道網、不動産、ブランド力など)を活用して、沿線価値をどのように高めていきたいか、具体的なアイデアを提案できると理想的です。
例えば、子育て世代を呼び込むためのサービスや、地域の活性化につながるイベント企画などです。
地域への深い関心と貢献意欲を見せることが重要です。
【鉄道業界】よくある質問
鉄道業界は、その特殊な業務内容から、就活生にとって疑問に思う点も多いようです。
就職偏差値やランキングだけでなく、実際の働き方や求められる資質について、不安を感じるかもしれません。
ここでは、就職活動生から特によく寄せられる3つの質問を選び、それぞれ分かりやすくお答えしていきます。
企業研究の一環として参考にしてください。
JRと私鉄の違いは?
JRと私鉄は、まずその成り立ちが異なります。
JRは、もともと日本国有鉄道(国鉄)という国の機関でしたが、1987年に分割・民営化されて誕生しました。
そのため、事業エリアが都道府県をまたぐ非常に広範なものであることが特徴です。
一方、私鉄(民営鉄道)は、もともと民間企業として設立され、特定の地域(沿線)の輸送を担うために発展してきました。
特に大手私鉄は、鉄道事業と同時に、沿線の宅地開発や商業施設の運営、レジャー事業などを一体的に進めることで、沿線価値そのものを高める街づくりを得意としています。
JRも民営化以降は多角化を進めていますが、私鉄ほど鉄道事業と不動産事業の結びつきが強くないケースもあります。
就職偏差値や企業研究の際は、こうした事業エリアの広さや、ビジネスモデルの違いを理解しておくことが大切です。
鉄道に詳しくない(鉄道オタクでない)と不利ですか?
結論から言うと、鉄道に詳しくないこと(いわゆる鉄道オタクでないこと)が選考で不利になることは全くありません。
もちろん、鉄道が好きであることは、志望動機の一つとして説得力を持つ場合があります。
しかし、企業側が求めているのは、鉄道の車両形式に詳しい人ではなく、安全という使命を理解し、社会インフラを支える責任感を持ち、チームの一員として規律を守って働ける人です。
むしろ、過度な鉄道愛が、冷静な業務遂行の妨げになると判断されることすらあります。
大切なのは、鉄道の知識量ではなく、なぜ鉄道会社で働きたいのか、その会社で何を成し遂げたいのかを、自分の言葉で論理的に説明できることです。
趣味としての鉄道と、仕事としての鉄道は全く別物であると理解し、後者の視点で企業研究や自己分析を進めることが重要です。
泊まり勤務やシフト制は全員が経験しますか?
鉄道会社では、職種によって働き方が大きく異なります。
駅係員、車掌、運転士といった、鉄道の運行に直接関わる現業職(プロフェッショナル職などとも呼ばれます)の場合は、基本的に泊まり勤務を含むシフト制となります。
例えば、朝出勤して翌日の朝まで働き(途中に仮眠時間あり)、その日は非番(明け番)で休み、次の日が公休、といったサイクルです。
一方、本社などで働く総合職(事務系・技術系)の場合は、基本的には土日祝日休みのカレンダー通りの勤務形態が多いです。
ただし、総合職であっても、入社後の研修やキャリア形成の一環として、一定期間、駅や乗務員の仕事を経験するためにシフト勤務に入るケースがほとんどの会社であります。
将来的にどの職種を志望するにせよ、鉄道業界はこうした24時間365日動く現場の仕事によって支えられている、という理解は不可欠です。
まとめ
鉄道業界の就職偏差値ランキングや、業界の特徴、内定のポイントについて解説しました。
この業界は、高い安定性と社会貢献性が魅力ですが、同時に重い責任と規律が求められます。
ランキングはあくまで目安とし、各社の事業内容や社風を深く研究することが大切です。
自分の適性と照らし合わせ、なぜこの業界で働きたいのかを深く掘り下げて、選考に臨んでください。