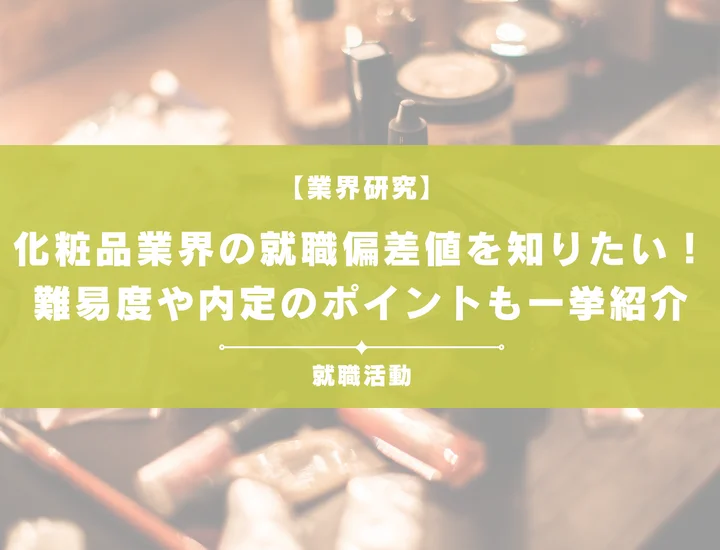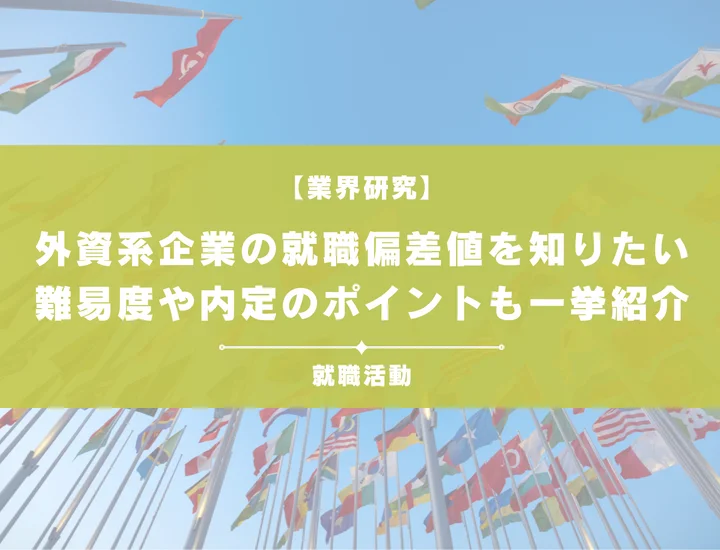HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
目次[目次を全て表示する]
就職偏差値とは
就職偏差値とは、主に就職活動を行う学生が、企業の入社難易度を客観的に測るために使う指標のことです。
予備校などが算出する大学の偏差値と同様に、企業の人気度、選考の倍率、求められる学歴や専門性、内定者の実績などを基に、相対的な難しさが数値化されています。
ただし、これは公的なデータではなく、就職活動関連の掲示板や情報サイトなどで独自に集計された、あくまで目安の一つです。
数値が高いほど入社が難しいとされ、業界研究や企業選びの参考として広く利用されています。
化粧品業界の就職偏差値ランキング
化粧品業界の就職偏差値ランキングは、業界内に数多く存在する企業の入社難易度を相対的に比較できるようにしたものです。
化粧品業界は、その華やかなイメージや人々の生活への密着度の高さから、学生、特に女性から長年にわたり絶大な人気を誇ります。
このランキングを目安に、各企業の位置づけを把握し、十分な選考対策を練ることが重要です。
【化粧品業界】Aランク(就職偏差値70以上)
【70】LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン(化粧品部門)
Aランクは、世界最大のラグジュアリー(高級ブランド)グループであるLVMHの化粧品部門が頂点です。
世界中の優秀な学生と競うことになる、最難関のポジションです。
ビジネスレベルを遥かに超える語学力(英語・フランス語)が最低条件となります。
化粧品への関心だけでなく、ラグジュアリービジネス全体への深い洞察力と戦略的思考が求められます。
【化粧品業界】Bランク(就職偏差値66以上)
【69】資生堂(R&D) P&Gジャパン ユニリーバジャパン 日本ロレアル
【68】資生堂(総合職) 花王(化粧品部門) ユニ・チャーム ヘンケルジャパン
【67】コーセー ロート製薬(化粧品部門) ELC日本(エスティローダー日本法人)
【66】ライオン(化粧品部門) JNTLコンシューマーヘルス
Bランクは、国内大手の資生堂・花王・コーセーと、P&Gや日本ロレアルといった世界的な外資系消費財メーカーが中心です。
R&D(研究開発職)と総合職(事務系)の両方で、就活生から圧倒的な人気を誇り、極めて高い競争率となります。
各社のブランド戦略やグローバル戦略の違いを深く分析し、「なぜこの会社なのか」を明確に語る必要があります。
高い論理性、リーダーシップ経験、そして外資系企業を目指す場合は高い語学力が求められます。
【化粧品業界】Cランク(就職偏差値61以上)
Cランク以降の就職偏差値を見るには会員登録が必要です。
無料登録すると、Cランク以降の就職偏差値をはじめとした
会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。
登録はカンタン1分で完了します。会員登録をして今すぐ化粧品業界の就職偏差値をチェックしましょう!
【65】マンダム ニベア花王 カネボウ化粧品
【64】ポーラ・オルビス ミルボン クラシエ(化粧品部門) ザ・プロアクティブカンパニー
【63】サンスター ファンケル DHC ノエビア ヤーマン MTG
【62】アジュバン アクシージア ハウスオブローゼ 新日本製薬
【61】ハーバー研究所 シーボン アイビー化粧品 タカラベルモント
Cランクは、マンダムやファンケル、ミルボンなど、特定の分野や販売チャネルで確固たる地位を築く国内の優良メーカーが中心です。
通販系(ファンケル、DHC)や、美容機器(ヤーマン、MTG)、サロン専売品(ミルボン)など、特色ある企業が並びます。
Bランク同様に人気が高く、各社のユニークなビジネスモデルや製品開発の哲学への深い理解が不可欠です。
なぜその分野(例:美容機器)に関心を持ったのかを、自身の経験と結びつけて説明する準備が必要です。
【化粧品業界】Dランク(就職偏差値56以上)
【60】銀座ステファニー化粧品 牛乳石鹸共進社
【59】資生堂(美容部員) クレ・ド・ポーボーテ(美容部員) 日本ロレアル(美容部員) ELC日本(美容部員) シャネル(美容部員) ディオール(美容部員) イヴ・サンローラン(美容部員) クラブコスメチックス
【58】ポーラ(美容部員) アルビオン(美容部員) コーセー(美容部員) コスメデコルテ(美容部員) トム・フォード・ビューティ(美容部員) ドルチェ&ガッバーナ・ビューティ(撤退)
【57】花王ビューティブランズカウンセリング HERA(美容部員) カバーマーク(美容部員) クリニーク(美容部員) ボビイブラウン(美容部員) リバイタルグラナス(美容部員) ディシラ(美容部員) アスタリフト(美容部員)
【56】3CE(美容部員) エチュードハウス(美容部員) カネボウ(美容部員) ちふれ(美容部員) シーボン(美容部員) クラランス(美容部員) マキアージュ(美容部員) ラ・ロッシュ・ポゼ(美容部員)
Dランクは、Bランク以上に名を連ねる大手国内メーカーや、Aランクの外資系ラグジュアリーブランドの「美容部員(BA)」、すなわち美容職の採用が中心です。
同じ会社でも、Bランクの総合職や研究職とは採用枠や求められる資質が異なります。
高い接客スキル、おもてなしの心、そして何よりも「そのブランドが好き」という熱意が最も重要視されます。
メイクアップ技術や、個人としての売上目標に対するコミットメントも求められる傾向があります。
【化粧品業界】Eランク(就職偏差値50以上)
【55】クロバーコーポレーション 加美乃素本舗 天然新素材科学研究所 ロイヤル化粧品 日本機能性コスメ研究所 神戸美人ぬか本舗 ナリス化粧品 ホソカワミクロン化粧品 アロインス化粧品 イオン化粧品 メイコー化粧品 ドクターデヴィアス化粧品
Eランクは、地域に根差して安定した経営を続ける中堅企業や、特定の技術・素材(例:OEM)に強みを持つBtoB(企業間取引)寄りの企業が中心です。
一般消費者向けの知名度はDランク以上と比べて低いかもしれませんが、業界を支える重要な企業群です。
学歴的なハードルは比較的緩やかになる傾向があります。
「なぜ大手ではなく、その会社なのか」を、その企業の技術力や地域貢献性などと絡めて説明する企業研究が対策となります。
【化粧品業界】とは
化粧品業界は、スキンケア、メイクアップ、ヘアケア、フレグランス(香水)といった製品を通じて、人々の美と健康を支える産業です。
製品の提供だけでなく、美容に関する情報やサービス、エステティックなども含めて幅広く扱います。
日々の生活に彩りや自信を与え、時にはコンプレックスの解消を手助けするなど、人々の心の豊かさにも深く貢献する、暮らしに密着した業界と言えます。
人々の「美」と「健康」に関わる製品(スキンケア、メイクアップ等)を提供する
化粧品業界が提供する製品の範囲は非常に広いです。
まず、肌を健やかに保つためのスキンケア製品(化粧水、乳液、美容液、日焼け止めなど)があります。
これらは、肌の保湿や紫外線防御といった、健康維持の側面が強い分野です。
次に、外見を彩り、個性を表現するためのメイクアップ製品(ファンデーション、口紅、アイシャドウなど)があります。
こちらは、自己表現やTPOに合わせた身だしなみという、文化的な側面を持ちます。
さらに、ヘアケア(シャンプー、トリートメント)、ボディケア(ボディソープ、ハンドクリーム)、フレグランス(香水)なども、人々の清潔さや快適さ、心の満足感を満たす重要なカテゴリーです。
このように、化粧品業界は単に容姿を飾るだけでなく、皮膚科学に基づいた健康の維持・改善から、日々の生活の質(QOL)の向上まで、人々の根源的な欲求に応える幅広い役割を担っています。
国内大手メーカー、外資系、通販専門、OEM(受託製造)など多様な企業
化粧品業界は、多様なビジネスモデルの企業によって構成されています。
まず、資生堂、花王、コーセー、ポーラ・オルビスなどに代表される国内大手メーカーが存在します。
これらは、強力な研究開発力と、ドラッグストアから百貨店までを網羅する広範な販売チャネル、長い歴史を持つブランド力が強みです。
次に、ロレアル、P&G、エスティローダーといった外資系企業です。
これらは、世界的に有名なプレステージブランド(高級ブランド)を多く持ち、先進的なマーケティング戦略を得意とします。
また、ファンケルやDHC、オルビスのように、通信販売やD2C(Direct to Consumer)を主軸とし、無添加や健康食品との連携といった独自のコンセプトで強い地位を築いている企業群もあります。
さらに、業界の重要なプレイヤーとして、OEM(相手先ブランドによる製造)やODM(相手先ブランドによる設計・製造)を専門とする受託製造企業(日本コルマー、東洋ビューティなど)があります。
これらは表に名前が出ることはありませんが、高い技術力で多くのブランドの生産を支えています。
製品を通じて、自己表現や「心の豊かさ」を創出する役割
化粧品が持つ価値は、その機能性だけではありません。
むしろ、それを使用することによって得られる心の満足感、すなわち自信や喜び、安らぎといった感情的な価値こそが、この業界の本質的な役割です。
例えば、メイクアップは自分のなりたいイメージを表現する自己表現の手段であり、自信を持って人と接するためのスイッチにもなります。
また、一日の終わりに好きな香りのスキンケア製品で自分自身をケアする時間は、ストレスを和らげるリラックスのひとときとなります。
このように、化粧品は単なるモノではなく、それを使う体験(コト消費)を通じて、人々の自己肯定感を高めたり、日々の生活に彩りを加えたりする力を持っています。
化粧品業界は、製品というツールを用いて、顧客の人生に前向きな変化をもたらし、心の豊かさを創出する役割を担っているのです。
【化粧品業界】特徴
化粧品業界は、流行の移り変わりが非常に早いことが最大の特徴です。
SNSやインフルエンサーの影響力が極めて強く、次々と新しいトレンドやヒット商品が生まれます。
その一方で、スキンケアなどの基礎化粧品は生活必需品としての側面も持つため、景気変動の影響を受けにくい安定した需要も併せ持ちます。
近年は、AIやARといったIT技術を活用したマーケティングや研究開発、いわゆるビューティーテックの分野も急速に進化しています。
トレンドの移り変わりが早い
化粧品業界、特にメイクアップ製品の分野は、トレンドのサイクルが極めて速いのが特徴です。
かつては雑誌やテレビが流行の発信源でしたが、現在はSNS、特にInstagramやTikTok、YouTubeがその中心です。
インフルエンサーや美容系クリエイターが紹介した商品が、瞬く間にヒット商品となり、時には品切れを起こすことも珍しくありません。
このスピード感に対応するため、企業には迅速な商品開発とマーケティング戦略が求められます。
また、消費者の価値観も多様化しており、サステナビリティ(環境配慮)やヴィーガン(動物性原料不使用)、ジェンダーレス(性別を問わない)といった新しい視点が次々とトレンドになっています。
企業は、こうした細分化するニーズやSNS上の兆候をリアルタイムで分析し、柔軟に商品やプロモーションに反映させる俊敏性が不可欠です。
常にアンテナを高く張り、変化を先取りする姿勢が求められる業界です。
景気変動の影響を受けにくい安定した需要がある
化粧品業界は、景気の波に比較的強いディフェンシブ産業とされています。
これは、スキンケアなどの基礎化粧品が、多くの人にとって日々の生活に欠かせない必需品であるためです。
景気が悪化しても、肌の健康を保つための支出は簡単には削られません。
また、不況下でも口紅のような比較的手頃な贅沢品(スモールラグジュアリー)の売上が伸びる現象は、リップスティック効果として知られています。
高価な耐久消費財の購入は控えても、化粧品を買うことで心の満足感を得ようとする消費者心理が働くためです。
もちろん、パンデミックでメイクアップ製品の需要が一時的に落ち込むなど、社会情勢による影響は受けます。
しかし、その場合でもスキンケアやセルフケア製品の需要が伸びるなど、カテゴリー間で需要がスライドする傾向があります。
総じて、人々の美と健康への関心は普遍的であり、景気変動に左右されにくい安定した需要基盤を持っていることが、この業界の大きな特徴です。
テクノロジーによる効率化・変革が急速に進んでいる
化粧品業界は、近年ビューティーテックと呼ばれるテクノロジーとの融合が急速に進んでいます。
これは、AI、AR(拡張現実)、ビッグデータなどを活用し、研究開発からマーケティング、顧客体験までを変革しようとする動きです。
例えば、研究開発分野では、AIが膨大な論文や成分データを解析し、新たな有効成分の発見をスピードアップさせています。
マーケティング分野では、SNSの投稿を分析して次のトレンドを予測したり、ECサイトでの購買データを基に最適な商品を推薦(レコメンド)したりすることが一般的です。
また、顧客体験の面では、スマートフォンのカメラで肌の状態をAIが診断するアプリや、AR技術を使ってオンライン上でメイクアップ製品を試せるバーチャルシミュレーターが普及しています。
これにより、従来は店舗でしかできなかった体験がデジタルで可能になりました。
このように、化粧品業界は伝統的な産業でありながら、最先端のIT技術を駆使して、よりパーソナライズされた(個人に最適化された)製品やサービスを生み出す、データ駆動型の産業へと変貌を遂げているのです。
【化粧品業界】向いている人
化粧品業界は、製品を通じて人々に喜びや自信を提供することに強いやりがいを感じる人に向いています。
また、トレンドに敏感で、常に新しい情報やアイデアを好奇心を持って取り入れられる柔軟性も求められます。
さらに、化粧品は科学的な根拠に基づく研究開発と、人の心に訴えかける感性的なブランド戦略の両輪で成り立っており、その両方、あるいはいずれかに強い関心を持てることも重要です。
「喜び」や「自信」を提供することにやりがいを感じる人
化粧品業界が提供する最大の価値は、製品そのものではなく、それを使った顧客が得られる心の満足感、すなわち喜びや自信です。
肌の調子が良いだけでその日一日を前向きに過ごせたり、新しいメイクに挑戦することで新しい自分を発見できたりします。
このように、化粧品は人々の自己肯定感を高め、人生を豊かにする力を持っています。
したがって、自分が開発や企画、販売に携わった製品を通じて、誰かのコンプレックスを解消する手伝いをしたい、あるいは誰かの毎日を今より少しでも輝かせたい、という想いを持つ人に最適です。
顧客の悩みに深く共感し、その期待を超える喜びを届けることに強いやりがいを感じられるかどうかが重要です。
人の内面的な変化に貢献したいという、ホスピタリティや利他の精神が求められます。
新しい情報やアイデアを柔軟に取り入れられる人
化粧品業界は、トレンドの移り変わりが非常に激しい世界です。
消費者のニーズは多様化し、SNSを通じて新しい流行が次々と生まれます。
このような環境では、過去の成功体験にとらわれず、常に新しい情報やアイデアを柔軟に取り入れる姿勢が不可欠です。
必要なのは、高い情報感度と好奇心です。
化粧品のことだけを追うのではなく、ファッション、食、ライフスタイル、あるいは新しいテクノロジーや社会の価値観の変化など、幅広い分野にアンテナを張ることが求められます。
そして、集めた情報を単に知っているだけでなく、それを分析し、自社の製品開発やマーケティング戦略にどう活かせるかを考える応用力が必要です。
変化を恐れるのではなく、変化を楽しみ、それをビジネスチャンスとして捉えられる柔軟な思考を持つ人が活躍できる業界です。
科学的側面(研究)や、感性的側面(ブランド戦略)に関心がある人
化粧品業界は、非常にユニークな特性を持つ産業です。
それは、最先端の皮膚科学や化学に基づく科学的側面と、消費者の五感や心に訴えかける感性的な側面が共存している点です。
一方では、研究職(理系)が中心となり、成分の有効性や安全性をミクロン単位で追求する、論理とデータの世界があります。
どうすれば肌に浸透するか、どうすれば効果が出るかを科学的に立証します。
もう一方では、マーケティング職(文系)が中心となり、製品のネーミング、パッケージデザイン、広告宣伝を通じて、ブランドの夢や憧れといった世界観を創り出す、感性とクリエイティブの世界があります。
したがって、論理的な思考で物事の仕組みを解明するのが好きな人(科学的側面)も、人の心を動かすストーリーやデザインを考えるのが好きな人(感性的側面)も、どちらも活躍の場があります。
この両極端とも言える側面に関心を持てる人にとって、非常に奥深く、やりがいのある業界です。
【化粧品業界】内定をもらうためのポイント
化粧品業界は就職偏差値が高い人気業界であり、内定を獲得するには戦略的な対策が必要です。
単に製品が好きだという熱意だけでは不十分です。
なぜ他社ではなくその会社なのかを、企業理念や経営戦略と結びつけて語る必要があります。
また、トレンドを自分なりに分析する力や、単なる消費者目線ではなく、利益を生み出すビジネス目線を持っていることをアピールすることが、選考を突破する上で高く評価されます。
「なぜその会社か」を製品愛ではなく、企業理念や戦略と絡めて語る
化粧品業界の選考では、多くの学生がその会社の製品が好きだという熱意をアピールします。
もちろん製品愛は重要ですが、それだけでは採用の決め手にはなりません。
なぜなら、企業はファンではなく、ビジネスパートナーとなる人材を探しているからです。
面接官が知りたいのは、数ある化粧品会社の中で、なぜその会社を志望するのかという論理的な理由です。
そのためには、製品の好みを超えて、その企業の経営理念、ブランド戦略、研究開発への姿勢、あるいはグローバル展開の方針などを深く研究する必要があります。
例えば、資生堂の強みは何か、ロレアルの戦略は何かを比較分析します。
その上で、自分自身の経験や強みが、その会社のどの戦略(例えば、アジア市場の開拓や、デジタルマーケティングの強化など)に、どのように貢献できるのかを具体的に結びつけて語ることが不可欠です。
製品の消費者としての視点から、ビジネスを創る側としての視点へ切り替えることが、内定への第一歩です。
トレンドを分析し、ターゲットに響く企画や提案を行った経験をアピール
化粧品業界はトレンドが命です。
そのため、新しい流行を敏感に察知し、それをビジネスに活かす能力が求められます。
学生時代の経験の中で、単に流行を追っていただけでなく、それを分析し、何らかの企画や提案に繋げたエピソードは強力なアピールになります。
例えば、所属するサークルのSNS運用を担当し、フォロワーの属性や反応(エンゲージメント)を分析して投稿内容を改善した経験。
あるいは、アルバート先で、若者層のトレンドを基に新メニューや新しい販売方法を提案し、売上に貢献した経験などです。
重要なのは、ただ流行に詳しかった、ということではありません。
そのトレンドの背景にある消費者のニーズは何かを考察し、ターゲット層に響くような具体的な行動(企画・提案)に移し、結果(例えば、フォロワー数の増加や売上向上)に結びつけたプロセスを論理的に説明することです。
こうした経験は、入社後もマーケティングや商品企画で活かせる能力として高く評価されます。
消費者目線とビジネス目線の両方を持ち、入社後にどう貢献したいかを具体的に
化粧品業界で働くには、二つの視点のバランスが不可欠です。
一つは、製品を実際に使う生活者としての消費者目線です。
これは、顧客の悩みや不満、あるいは小さな喜びに共感する力であり、商品開発の原点となります。
しかし、それだけでは十分ではありません。
もう一つの、ビジネス目線、つまり企業としてどうやって利益を生み出し、事業を継続させていくかという視点が不可欠です。
例えば、どんなに素晴らしい成分でも、コストが高すぎて製品価格が現実的でなければ、ビジネスとして成立しません。
選考では、この両方の視点を持っていることを示すことが重要です。
自分が消費者として感じる課題やアイデアを提示しつつ、それをどうすれば採算の取れる事業として実現できるか、あるいは会社の強みをどう活かせば他社と差別化できるか、といったビジネスの観点から入社後の貢献イメージを具体的に語ることが求められます。
会社は利益を生み出す組織であるという前提を理解していることが、高く評価されます。
【化粧品業界】よくある質問
就職偏差値も高く人気の化粧品業界ですが、その働き方については意外と知られていないことも多いです。
総合職のキャリアパスとして美容部員を経験するのか、男性でも活躍の場があるのか、あるいは文系と理系の採用では何が違うのかなど、就職活動生からよく寄せられる質問は様々です。
ここでは、そうした化粧品業界特有の疑問について解説します。
総合職でも美容部員(BA)を経験しますか?
企業によって方針は異なりますが、特に国内の大手化粧品メーカーの総合職(マーケティング職や営業職)採用では、入社後の研修の一環として、美容部員(BA:ビューティーアドバイザー)や販売職を一定期間経験することが多いです。
これは、化粧品ビジネスの最前線である店頭に立ち、お客様の生の声を直接聞くことが、将来どの部門で働く上でも不可欠な経験となると考えられているからです。
お客様がどのような悩みを持ち、何を求めて製品を選ぶのかを肌で知ることは、机上のデータ分析だけでは得られません。
また、販売現場の苦労や喜びを理解することは、将来、営業担当としてBAをサポートしたり、マーケティング担当として現場が売りやすい製品を企画したりする上で、非常に重要な基盤となります。
一部の外資系企業やBtoBが中心のOEM企業などでは、こうした現場研修がない場合もありますが、多くのBtoCメーカーにおいては、キャリアの第一歩として現場理解を重視する傾向が強いです。
男性でも活躍できますか?
結論から言えば、男性でも全く問題なく活躍できます。
むしろ、男性ならではの視点が強みになる場面も多々あります。
確かに、歴史的に女性従業員が多い業界ではありますが、それは消費者も女性が中心だったためです。
近年は、男性の美意識の高まりからメンズコスメ市場が急成長しており、男性の視点を持った商品企画やマーケティングが不可欠になっています。
また、理系職である研究開発や生産技術の分野では、性別に関係なく専門性が評価されます。
営業職や経営企画、財務といった部門でも、もちろん性別は問われません。
むしろ、近年のジェンダーレスというトレンドや、ダイバーシティ&インクルージョン(多様性の推進)という経営課題において、固定化された性別役割意識にとらわれない柔軟な発想が求められています。
男性だから不利になるということはなく、化粧品業界で何を成し遂げたいかという明確なビジョンと能力があれば、性別を問わず活躍の場は広がっています。
理系(研究職)と文系(総合職)の採用の違いは?
化粧品業界の採用は、大きく理系(研究職・技術職)と文系(事務系・総合職)の二つに分かれており、採用プロセスや求められる資質が異なります。
理系採用は、主に研究開発、生産技術、品質管理などの職種が対象です。
化学、生物学、薬学、農学などの専門知識が必須であり、大学での研究内容そのものが選考で重要視されます。
多くの場合、修士課程や博士課程修了者が対象となる専門職採用です。
一方、文系採用(総合職)は、マーケティング(商品企画)、営業、人事、経理などの職種が対象です。
こちらは学部学科不問のポテンシャル採用が一般的です。
学生時代の経験(ガクチカ)やリーダーシップ、論理的思考力、コミュニケーション能力といった汎用的なスキルが評価されます。
選考ルートも最初から分かれていることがほとんどで、理系は研究内容を発表する技術面接が、文系は志望動機や自己PRを中心とした面接が課されます。
まとめ
化粧品業界は、就職偏差値が示す通り非常に人気が高いですが、それは製品を通じて人々の心に豊かさや自信を届けるという、大きなやりがいがあるからです。
最先端の科学的な探究心と、トレンドを掴む感性の両方が求められる奥深い業界でもあります。
選考では、単なる製品のファンとしてではなく、各社の経営戦略を深く理解し、自分がビジネスの視点からどう貢献できるかを具体的に示すことが、内定獲得の鍵となります。