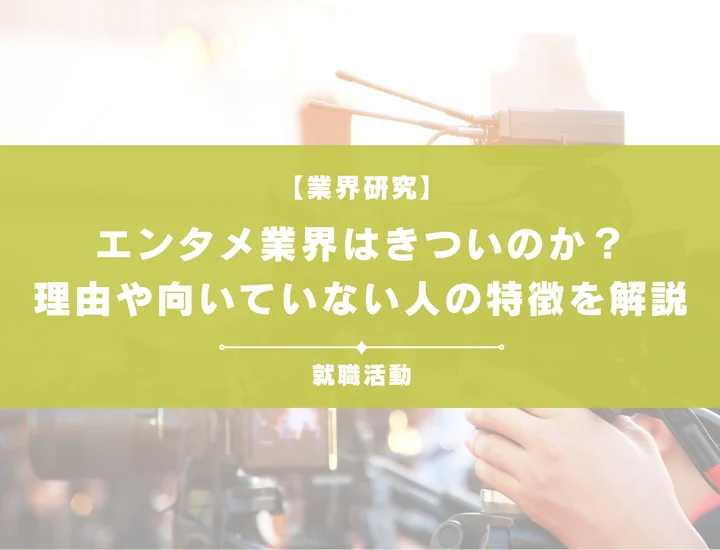HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
エンタメ業界と聞くと、華やかな舞台や感動的なコンテンツを思い浮かべ、「好き」を仕事にしたいと憧れる就活生も多いでしょう。
しかし同時に、「エンタメ業界はきつい」という噂を耳にして、不安を感じている人もいるかもしれません。
この記事では、就活アドバイザーとして、エンタメ業界のリアルな仕事内容から、なぜ「きつい」と言われるのか、そしてどんな人が活躍できるのかまで、徹底的に解説していきます。
あなたの「好き」を仕事にするための具体的なヒントが、きっと見つかるはずです。
【エンタメ業界はきついのか】エンタメ業界はきつい?
結論から言えば、エンタメ業界の仕事は「きつい」側面があるのは事実です。
多くの人々を感動させ、熱狂させるコンテンツを生み出す裏側では、想像以上のプレッシャーや不規則な労働時間が存在します。
華やかなイメージだけで飛び込むと、厳しい現実に直面してしまうかもしれません。
しかし、その「きつさ」を上回るほどの、他では得難いやりがいや達成感があるのも、この業界の大きな魅力です。
大切なのは、その実態を正しく理解することです。
【エンタメ業界はきついのか】エンタメ業界の仕事内容
エンタメ業界と一口に言っても、その仕事内容は非常に多岐にわたります。
私たちが普段目にするテレビ番組、映画、音楽、ゲーム、イベントなどは、実に多くのプロフェッショナルたちの手によって支えられています。
例えば、ゼロから企画を生み出す人、それを形にする制作現場の人、完成した作品を世に広める宣伝の人、アーティストを支えるマネージャー、そしてそれら全体のビジネスを動かす営業や管理部門の人など、役割は様々です。
共通しているのは、「人々に感動や楽しみを届ける」という目的のために、それぞれの専門性を発揮している点です。
あなたがエンタメ業界のどの部分に魅力を感じ、どのように貢献したいのかを考えるためにも、まずは具体的な仕事内容を知ることが重要です。
自分の強みが活かせるフィールドがどこにあるのか、一緒に見ていきましょう。
企画・制作
エンタメ業界の根幹を担うのが、コンテンツの「企画・制作」の仕事です。
テレビ番組のプロデューサーやディレクター、映画の脚本家、ゲームプランナー、音楽のA&R(アーティストの発掘・育成・制作担当)などがこれにあたります。
彼らの仕事は、世の中のトレンドや人々のニーズを読み取り、「何が面白いか」「何が求められているか」を常に考え、新しいアイデアを生み出すことから始まります。
企画が通れば、次はそれを実現するための予算管理、スタッフやキャストの調整、制作スケジュールの管理など、多くの実務が発生します。
締切や予算という厳しい制約の中で、最高のクオリティを追求し続けなければなりません。
ゼロからモノを生み出す苦しさはありますが、自分の企画したものが世に出て、人々の心を動かした時の達成感は、何物にも代えがたい大きなやりがいとなるでしょう。
クリエイティブな発想力だけでなく、多くの人を巻き込む推進力やタフな交渉力も求められる仕事です。
宣伝・プロモーション
どれだけ素晴らしいコンテンツを制作しても、それが人々に届かなければ意味がありません。
その「届ける」役割を担うのが、「宣伝・プロモーション」の仕事です。
制作された映画、音楽、ゲーム、イベントなどを、いかに多くの人に知ってもらい、興味を持ってもらうかを考え、実行します。
具体的な手法は、テレビCMや雑誌広告といった従来型のメディア戦略から、SNSでのキャンペーン、Web広告、インフルエンサーとのタイアップ、プレスリリースの配信、公開記念イベントの企画運営まで、非常に多岐にわたります。
常に世の中のトレンドや空気感を読み、ターゲット層に最も響く言葉やビジュアル、タイミングを戦略的に選ばなくてはなりません。
SNSでの「バズ」を狙うなど、時には仕掛け人としてのセンスも問われます。
結果が再生回数や動員数といった数字で明確に出るため、プレッシャーも大きいですが、自分の仕掛けたプロモーションが社会的なムーブメントになった時の喜びは格別です。
営業・渉外
エンタメ業界における「営業・渉外」は、コンテンツやアーティストをビジネスとして成立させるために不可欠な役割を担います。
例えば、テレビ局の営業担当であれば、スポンサー企業に対して番組の企画を提案し、CM枠を販売します。
広告代理店と連携し、クライアントの課題を解決するようなタイアップ企画を立案することもあります。
また、レコード会社であれば、CDショップや配信プラットフォームに自社のアーティストの楽曲をより良い条件で展開してもらうよう交渉します。
映画会社であれば、劇場(映画館)に作品を上映してもらうための交渉を行います。
単にモノを売るのではなく、企画やコンテンツの「価値」を伝え、ビジネスパートナーとして信頼関係を築くことが求められます。
交渉力やコミュニケーション能力はもちろんのこと、自社コンテンツへの深い理解と、業界全体の動向を把握する情報収集力も重要になる、まさにビジネスの最前線と言える仕事です。
マネジメント
エンタメ業界、特に芸能プロダクションや音楽事務所において中心的な仕事の一つが「マネジメント」です。
一般的に「芸能マネージャー」と呼ばれるこの仕事は、担当するアーティストやタレントがその才能を最大限に発揮し、長く活躍できるよう全面的にサポートすることです。
具体的な業務は、日々のスケジュール管理、仕事現場への送迎・帯同、メディアやクライアントとの出演交渉、ギャランティの調整など多岐にわたります。
しかし、単なるスケジュール管理に留まらず、担当アーティストの将来的なキャリアプランを一緒に考え、時にはメンタル面のケアも行うなど、公私にわたるパートナーとしての役割が求められます。
そのため、何よりもアーティストとの強固な信頼関係が欠かせません。
アーティストの成功を一番近くで支え、喜びを分かち合えることは大きなやりがいですが、同時に、その人生を背負うという重い責任も伴う、非常にタフさが求められる仕事です。
【エンタメ業界はきついのか】エンタメ業界の主な職種
エンタメ業界の仕事内容を理解したところで、次はさらに具体的な「職種」に目を向けてみましょう。
業界が多岐にわたるため、存在する職種も膨大です。
例えば、テレビ業界には番組を作るプロデューサーやディレクター、AD(アシスタントディレクター)がいますし、音楽業界にはアーティストを発掘するA&Rや、ライブを作るイベンターがいます。
映画業界、ゲーム業界、広告業界にも、それぞれ専門的な職種が存在します。
これらの職種は、それぞれが独自の専門性を持ちながらも、一つのコンテンツを成功させるという共通の目的に向かって密接に連携しています。
ここでは、新卒の皆さんが目指す可能性のある、代表的な職種をいくつかピックアップして紹介します。
自分がどのポジションで輝きたいか、イメージしながら読んでみてください。
プロデューサー/ディレクター
プロデューサーとディレクターは、主にテレビ、映画、映像制作の現場における中心的な存在です。
プロデューサーは、企画の立案から予算の確保、スタッフやキャストの選定、全体のスケジュール管理まで、プロジェクト全体を統括する「責任者」です。
ビジネス的な視点を持ち、企画を成功に導くためのあらゆる判断を行います。
一方、ディレクターは、現場での「演出家」です。
企画の意図を汲み取り、カメラマンや音声、演者などに具体的な指示を出し、コンテンツのクオリティを高めていく役割を担います。
新卒でいきなりプロデューサーやディレクターになることは稀で、多くの場合、AD(アシスタントディレクター)としてキャリアをスタートし、厳しい下積み経験を経てステップアップしていきます。
求められるのは、強いリーダーシップと、予期せぬトラブルにも対応できる柔軟な判断力、そして何より作品を面白くするための飽くなき探究心です。
A&R (Artist and Repertoire)
A&Rは、主にレコード会社(音楽業界)に存在する職種で、「アーティスト・アンド・レパートリー」の略です。
その役割は、新しい才能(アーティスト)を発掘し、契約・育成すること、そしてそのアーティストに合った楽曲(レパートリー)を制作し、世に送り出すまでの一連の流れをトータルで担当することです。
具体的には、ライブハウスに足を運んで新人を探したり、デモテープを聴いたりすることから始まり、契約後はアーティストと共に音楽性や方向性を議論し、レコーディングのディレクション、プロモーション戦略の立案まで行います。
アーティストの最も身近なパートナーとして、その才能を信じ、二人三脚でヒットを目指します。
音楽的センスやトレンドを読む力はもちろん、アーティストの魅力を引き出すコミュニケーション能力、そしてビジネスとして成立させるための戦略的思考が求められる、音楽業界の花形職種の一つです。
芸能マネージャー
「マネジメント」の仕事内容でも触れましたが、芸能マネージャーは芸能プロダクションに所属し、タレントやアーティストの活動を支える職種です。
担当タレントのスケジュール管理、現場への帯同、メディアや制作会社との出演交渉が主な業務となります。
しかし、その本質は「担当タレントをいかに売るか」という戦略的な視点と実行力にあります。
タレントの個性や強みを深く理解し、それが活かせる仕事を取ってくる営業力や、将来を見据えたキャリアプランニング能力も重要です。
また、タレントが常にベストなパフォーマンスを発揮できるよう、体調管理やメンタルケアにも気を配る必要があります。
勤務時間は担当タレントのスケジュールに完全に左右されるため、非常に不規則で体力的なきつさもありますが、タレントがブレイクし、多くの人々に愛される姿を一番近くで見届けられることは、何物にも代えがたいやりがいとなるでしょう。
広告・宣伝担当
エンタメ企業(映画会社、レコード会社、ゲーム会社など)における広告・宣伝担当は、自社が制作・保有するコンテンツやアーティストを世の中に広めるための戦略を立て、実行する職種です。
仕事内容は「宣伝・プロモーション」のセクションで解説した通りですが、企業内のポジションとして、より経営的な視点も求められます。
限られた宣伝予算の中で、いかに最大の効果を生み出すかを常に考えなければなりません。
テレビCM、雑誌、Webメディア、SNSなど、多様な広告手法の中から最適な組み合わせ(メディアミックス)を設計し、広告代理店やメディア各社と交渉・調整を行います。
世の中のトレンドや人々の関心を敏感に察知し、コンテンツの魅力を的確に伝えるキャッチコピーやビジュアルを考えるクリエイティブな側面もあります。
自分の仕掛けた広告が話題となり、コンテンツのヒットに直結した時の達成感は非常に大きい仕事です。
イベントプランナー
コンサート、フェス、ファンミーティング、展示会、舞台など、エンタメ業界における「リアルな体験」を企画・制作・運営するのがイベントプランナーの仕事です。
音楽事務所やイベント制作会社、広告代理店などに所属します。
アーティストのコンセプトやクライアントの要望に基づき、イベントの企画を立案することから始まります。
企画が決定すれば、会場の手配、予算管理、当日の音響・照明・映像などのテクニカルスタッフの手配、警備計画、グッズ制作、チケット販売戦略の立案など、準備すべきことは山積みです。
当日は予期せぬトラブルがつきものであり、それらに臨機応変に対応しながら、イベント全体がスムーズに進行するよう指揮を執ります。
何ヶ月もかけて準備したものが、当日の観客の熱狂や笑顔として形になる瞬間は、この仕事ならではの醍醐味です。
体力と精神力、そして細部まで気を配れる緻密さが求められます。
【エンタメ業界はきついのか】エンタメ業界がきついとされる理由
さて、エンタメ業界の華やかな仕事内容や職種を見てきましたが、ここで改めて「なぜエンタメ業界はきついのか」という根本的な理由について深掘りしていきます。
憧れだけで入社した後に「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、厳しい側面を直視することは非常に重要です。
「きつい」と言われる理由は、単なるイメージではなく、業界特有の構造的な問題や働き方に起因しています。
例えば、コンテンツの締切に追われるプレッシャーや、人々の余暇時間に合わせて動くという特性上、どうしても労働時間が不規則になりがちです。
ここで挙げる理由を理解した上で、それでも挑戦したいと思えるかどうかが、あなたにとっての適性を判断する一つの材料になるはずです。
労働時間が不規則で長時間になりがち
エンタメ業界がきついと言われる最大の理由の一つが、労働時間です。
多くの職種で、定時退社という概念が当てはまりにくい現実があります。
例えば、テレビ番組の制作現場では、撮影が深夜や早朝に及ぶことは日常茶飯事ですし、放送日(締切)前は編集作業で泊まり込みになることも珍しくありません。
芸能マネージャーであれば、担当タレントの早朝ロケや深夜の生放送に合わせて動くため、生活リズムは不規則になります。
イベント運営も、本番当日は早朝から深夜まで現場に張り付くことになります。
このように、コンテンツのスケジュールやアーティストの都合が最優先されるため、自分の時間をコントロールしにくいのが実情です。
体力的な負担が非常に大きいことは覚悟しておく必要があるでしょう。
成果主義とプレッシャー
エンタメ業界は、良くも悪くも「結果」が全ての世界です。
制作した番組の視聴率、映画の興行収入、CDの売上枚数、イベントの動員数など、成果が明確な数字となって表れます。
ヒットを生み出せば大きな評価を得られますが、そうでなければ厳しい評価にさらされます。
常に「次も当てなければならない」というプレッシャーの中で仕事を続けることになります。
また、クリエイティブな仕事であるがゆえに、「面白いもの」を生み出す苦しみも伴います。
自分の企画がなかなか通らなかったり、アイデアが枯渇してしまったりすることもあるでしょう。
精神的なタフさがなければ、このプレッシャーに押しつぶされてしまう可能性もあります。
この厳しさこそが、業界のクオリティを支えている側面もありますが、向き不向きが分かれる点でもあります。
休日が不安定・プライベートとの両立が難しい
労働時間の不規則さとも関連しますが、休日の取り方も一般的な企業とは異なります。
エンタメ業界が提供するサービスの多くは、人々が休む土日祝日や長期休暇中に最も需要が高まります。
コンサートやイベント、舞台公演などは土日がメインですし、テレビ番組も特番などは連休に合わせて放送されることが多いです。
そのため、カレンダー通りの休みを取ることは難しい職種がほとんどです。
振替休日が取得できる場合もありますが、それもプロジェクトの状況次第です。
友人や家族とスケジュールを合わせにくいといった、プライベート面での制約が出てくることは覚悟しておく必要があります。
仕事に情熱を注ぐあまり、プライベートを犠牲にしがちになる人も少なくないため、自分なりのバランスの取り方を見つけることが重要になります。
人間関係のストレス
エンタメ業界は「人」が中心のビジネスです。
アーティスト、タレント、クリエイター、制作スタッフ、クライアント、広告代理店など、非常に多くの、そしてしばしば個性の強い人々と関わりながら仕事を進めていくことになります。
特に、制作現場やマネジメント業務では、様々な立場の人の間に立ち、利害関係や意見の対立を調整する役割を担うことが多くなります。
自分の思い通りに進まないことや、理不尽な要求に対応しなければならない場面も少なくありません。
それぞれのプロフェッショナルが強いこだわりを持っているからこそ、衝突も起こりやすいのです。
高いコミュニケーション能力と、異なる意見をまとめ上げる調整力、そして多少のことでは動じない精神的な強さがなければ、人間関係のストレスで疲弊してしまう可能性もあります。
給与体系(特に下積み時代)
華やかなイメージとは裏腹に、給与面での厳しさも「きつい」と言われる理由の一つです。
もちろん、ヒットを生み出すプロデューサーやトップアーティストになれば高収入が期待できますが、そこに至るまでの道は平坦ではありません。
特に、制作会社のアシスタントディレクター(AD)や、一部の専門職のアシスタントなど、いわゆる「下積み」と呼ばれる期間は、長時間労働に見合った給与とは言えないケースも残念ながら存在します。
業界全体として、若いうちは「経験を積ませてもらう」という意識が根強く残っている側面もあります。
「好き」という気持ちだけで乗り切るには限界があるため、入社前に企業の給与体系や福利厚生をしっかりと確認し、自身のキャリアプランと照らし合わせて現実的に判断することが重要です。
エンタメ業界の現状・課題
エンタメ業界を目指す上で、その「きつさ」だけでなく、業界全体が今どのような状況にあり、どんな課題を抱えているのかを理解しておくことも非常に重要です。
エンタメ業界は今、テクノロジーの急速な進化と消費者のライフスタイルの変化によって、大きな変革期を迎えています。
かつてのテレビやCDといったマスメディア中心の時代から、インターネットやスマートフォンが中心の時代へと移行し、コンテンツの楽しみ方も大きく変わりました。
こうした変化に対応し、新たなビジネスモデルを構築することが、業界全体の喫緊の課題となっています。
ここでは、エンタメ業界が直面している主な課題を整理してみましょう。
デジタル化・サブスクリプションへの対応
エンタメ業界における最大の課題は、デジタル化への対応です。
特に音楽業界ではCDの売上が減少し、Apple MusicやSpotifyといった「サブスクリプション(定額制)サービス」でのストリーミング再生が主流になりました。
映像業界でも、NetflixやAmazon Prime Videoなどの動画配信サービスが急速に普及し、テレビ局や映画会社は従来のビジネスモデルからの転換を迫られています。
サブスクリプションモデルは、1回ごとの売上(CDやDVD)に比べて、1ユーザーあたりの単価が低くなりがちなため、いかに多くのユーザーを獲得し、継続してもらうかという新たな戦いが始まっています。
デジタルプラットフォーム上でどうやって自社のコンテンツを目立たせ、収益を上げていくかという戦略が、企業の明暗を分ける時代になっています。
コンテンツの多様化と競争激化
スマートフォンの普及により、誰もが手軽にコンテンツを楽しめるようになった一方で、人々の「可処分時間(自由に使える時間)」の奪い合いは激化しています。
かつてはテレビ番組、映画、音楽、ゲームなどがエンタメの中心でしたが、今やYouTube、TikTokといったSNS、さらには個人のライブ配信なども、強力なライバルとなっています。
消費者が触れるコンテンツが爆発的に増えたことで、一つ一つのコンテンツが注目されにくくなっています。
このような環境下で、既存のエンタメ企業は、単に質の高いコンテンツを作るだけでなく、SNSなどと連動させたり、新たなテクノロジーを取り入れたりするなど、消費者に「選ばれる」ための工夫をこれまで以上に凝らさなければならなくなっています。
働き方改革の遅れ
「きついとされる理由」でも触れた通り、エンタメ業界は伝統的に長時間労働や旧態依然とした業界慣習が残りやすいと指摘されてきました。
特にテレビ制作現場などは、その労働環境の厳しさが社会的な問題として取り上げられることもあります。
優秀な人材を確保し、長く活躍してもらうためには、こうした働き方の改善が急務です。
近年では、大手企業を中心にコンプライアンスの強化やハラスメント防止の取り組み、労働時間の管理などを進める動きも出てきていますが、業界全体としてはまだ道半ばと言えるでしょう。
「好きだから」「やりがいがあるから」という理由だけで、過度な負担を強いる構造から脱却し、持続可能な働き方を実現できるかどうかが、業界の将来を左右する大きな課題となっています。
エンタメ業界の今後の動向
課題が山積する一方で、エンタメ業界には大きな可能性も広がっています。
変化の激しい時代だからこそ、新しい技術やアイデアを取り入れることで、これまでにない感動体験を生み出すチャンスに満ちているとも言えます。
これからのエンタメ業界は、国内市場だけに留まらず、グローバルな視点を持つこと、そしてAIやVRといった最先端技術をいかに活用するかが成長の鍵となります。
また、コンテンツそのものの力、すなわち「IP(知的財産)」を軸にしたビジネス展開がますます重要になっていくでしょう。
就活生の皆さんにとっては、こうした新しい動きの中でこそ、若い感性やデジタルネイティブとしての感覚が強みとして活かせるはずです。
グローバル市場の開拓
日本の国内市場が少子高齢化などで縮小傾向にある中、エンタメ業界が今後さらに成長していくためには、海外市場への展開が不可欠です。
すでに日本のアニメやゲームは世界的に高い評価を得ており、大きな収益源となっています。
今後は、音楽(J-POP)や映画、ドラマなども、K-POPや韓国ドラマのように世界市場で成功する事例をいかに生み出していくかが問われています。
そのためには、各国の文化や好みに合わせたローカライズ戦略や、海外のプラットフォーム(NetflixやSpotifyなど)を効果的に活用したプロモーションが重要になります。
語学力はもちろんのこと、異文化への理解やグローバルな視点を持った人材が、これからのエンタメ業界ではますます求められるようになるでしょう。
テクノロジー(AI, VR/AR)の活用
AI(人工知能)、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、メタバースといった最先端技術は、エンタメの未来を大きく変える可能性を秘めています。
例えば、AIを活用して音楽制作や映像編集の効率を上げたり、個々のユーザーの好みに合わせたコンテンツをAIが推薦したりする技術はすでに実用化されています。
さらに、VR技術を使えば、自宅にいながらにしてライブ会場の最前列にいるかのような臨場感を味わえますし、AR技術を使えば、現実世界にキャラクターが登場するような新しいゲーム体験が可能になります。
これらの技術をエンターテインメントとどう融合させ、人々を驚かせるような新しい体験価値を創造できるかが、今後の競争力を左右する重要なポイントとなるでしょう。
IPビジネスの強化
IP(Intellectual Property=知的財産)とは、アニメ、漫画、ゲームのキャラクターやストーリー、アーティストそのものなど、企業が生み出した独自のコンテンツを指します。
今後のエンタメ業界では、このIPをいかに育て、多角的に展開していくか(IPビジネス)が収益の柱となっていきます。
例えば、一つの人気アニメ作品から、映画化、ゲーム化、グッズ販売、テーマパークのアトラクション化、海外展開など、様々なビジネスを生み出すことができます。
一つのIPを長期間にわたって愛されるブランドとして育て上げることで、安定的な収益を見込めます。
そのため、企業は新たなIPを創出すると同時に、既存のIPの価値を最大化するための戦略に力を入れています。
【エンタメ業界はきついのか】エンタメ業界に向いている人
ここまでエンタメ業界のリアルな「きつさ」や「課題」、そして「将来性」について見てきました。
これらを踏まえた上で、では一体どんな人がこの業界で活躍できるのでしょうか。
厳しい環境であることは事実ですが、だからこそ、特定の強みやマインドセットを持った人にとっては、他では得られない大きなやりがいを感じられる場所でもあります。
単に「エンタメが好き」というだけでなく、その「好き」を仕事として昇華させるための素養が求められます。
あなたがこれらの特徴に当てはまるか、自分自身と照らし合わせながら考えてみてください。
エンタメが心から好きで、探究心がある人
まず大前提として、エンターテインメントが心から好きであることが不可欠です。
しかし、ここで言う「好き」とは、単なる消費者としての「好き」ではありません。
なぜこのドラマはヒットしたのか、このアーティストのどこに人々は惹かれるのか、このゲームの何が面白いのか、常に「なぜ」を考え、分析し、探求する姿勢が求められます。
トレンドを追いかけるだけでなく、その裏にある構造や仕掛けを理解しようとする知的好奇心が、新しい企画や戦略を生み出す源泉となります。
仕事としてエンタメに触れ続けることは、時に「好き」だけでは乗り越えられない壁にもぶつかりますが、その探究心こそがあなたを支える原動力になるはずです。
体力と精神的なタフさがある人
「きつい理由」で散々触れてきた通り、エンタメ業界は体力勝負、精神力勝負の側面が非常に強いです。
不規則な勤務時間、タイトなスケジュール、休日出勤、大きなプレッシャーなどは日常の一部です。
まずは、自分の体調管理をしっかりできることがプロとしての最低条件です。
さらに重要なのが精神的なタフさ。
プロジェクトがうまくいかない時、厳しいフィードバックを受けた時、人間関係で悩んだ時、そこで落ち込みすぎず、すぐに気持ちを切り替えて次に向かえる「レジリエンス(回復力)」が求められます。
困難な状況でも、明るく前向きに乗り越えていけるような頑健さが、この業界で長く活躍するための鍵となります。
コミュニケーション能力が高く、調整役が得意な人
エンタメの仕事は、決して一人では完結しません。
プロデューサー、ディレクター、アーティスト、技術スタッフ、営業、宣伝、クライアントなど、非常に多くの人々と連携しながら進めていきます。
それぞれの立場や専門性が異なるため、時には意見が対立することもあります。
そうした場面で、相手の意図を正確に汲み取り、自分の考えを分かりやすく伝え、円滑な人間関係を築けるコミュニケーション能力は必須スキルです。
特に、異なる立場の人の間に立って利害を調整し、プロジェクトを円滑に推進できる「調整力」は、多くの職種で高く評価されます。
人を巻き込み、チームをまとめることが得意な人は、エンタメ業界で重宝されるでしょう。
トレンドに敏感で、新しいもの好きな人
エンタメ業界は、世の中の「今」を映し出す鏡のような存在です。
人々の興味関心は日々移り変わっていくため、常に最新のトレンドにアンテナを張っておく必要があります。
単に流行を知っているだけでなく、なぜそれが流行っているのかを自分なりに分析し、それを自分の仕事に取り入れようとする姿勢が重要です。
SNSで話題のトピック、新しいアプリ、若者の間で流行っている言葉など、あらゆる情報に敏感であることが求められます。
「ミーハーであること」も、この業界では立派な才能の一つです。
好奇心旺盛で、新しいものやサービスを試すことに抵抗がない人は、常に新鮮なアイデアを生み出す源泉となるでしょう。
人を楽しませることに喜びを感じる人
エンタメ業界の仕事の本質は、「人々に楽しみや感動を届けること」です。
その多くは、スポットライトを浴びるアーティストやタレントを支える「裏方」の仕事です。
自分が表に出るのではなく、自分の仕事を通じて誰かが笑顔になったり、感動してくれたりすることに、最大の喜びを感じられる人でなければ務まりません。
地道な資料作成、深夜までの編集作業、煩雑なスケジュール調整。
そうした泥臭い仕事の先に、観客の歓声や視聴者からの「面白かった」という声があります。
その瞬間のために全力を尽くせる、ホスピタリティ精神に溢れた人こそが、エンタメ業界で輝ける人材です。
【エンタメ業界はきついのか】エンタメ業界に向いていない人
一方で、エンタメ業界の特性と自分の価値観が合わないと感じる人もいるでしょう。
ミスマッチな就職は、あなたにとっても企業にとっても不幸な結果を招きます。
憧れだけで判断せず、自分の本質と向き合うことが大切です。
ここで挙げる特徴は、あくまで一般的な傾向であり、絶対的なものではありません。
しかし、もし「自分はこれに当てはまるかもしれない」と感じたら、なぜエンタメ業界なのかをもう一度深く考えるきっかけにしてみてください。
安定志向で、プライベートを最優先したい人
エンタメ業界は「変化」と「不規則」が常です。
決まった時間に会社に行き、決まった時間に帰る、カレンダー通りの休日を過ごす、といった安定した働き方を最優先にしたい人には、正直なところ厳しい環境かもしれません。
仕事のために土日に稼働したり、夜遅くまで対応したりすることが求められる場面が多くあります。
もちろん、最近は働き方改革を進める企業も増えていますが、業界の特性上、仕事とプライベートの境界線が曖昧になりがちなのは事実です。
「仕事も大事だけど、プライベートの時間は絶対に確保したい」という価値観を強く持っている人は、他の業界の方が幸せに働ける可能性も視野に入れた方がよいでしょう。
指示待ちで、受け身な姿勢の人
エンタメ業界の仕事は、マニュアル通りにこなすルーティンワークは比較的少なく、常に「次、何をすべきか」「どうすればもっと良くなるか」を自分で考えて行動することが求められます。
現場では予期せぬトラブルがつきものであり、その場で最善の判断を下さなければなりません。
ADの仕事一つとっても、先輩から指示されるのを待っているだけでは成長できません。
自ら先輩の動きを見て仕事を覚え、次に必要とされることを先読みして準備するような能動的な姿勢が不可欠です。
「誰かに教えてもらう」という受け身の姿勢では、変化の速い業界のスピードについていくのは難しいでしょう。
地道な作業や裏方仕事が苦手な人
エンタメ業界の仕事は、華やかなイメージとは裏腹に、その9割以上が地道で泥臭い作業の積み重ねで成り立っています。
企画を通すための膨大な資料作成、ロケ地への許可取り、予算管理のための細かい計算、イベント会場での機材運び、アーティストの送迎など、スポットライトとは無縁の「裏方」としての仕事がほとんどです。
「人前に出て注目されたい」「クリエイティブなことだけしていたい」という思いが強すぎると、入社後のギャップに苦しむことになります。
人々の感動を生み出すために、縁の下の力持ちとして地道な努力を厭わない、そうした覚悟が持てない人には向いていないかもしれません。
エンタメ業界に行くためにすべきこと
エンタメ業界の「きつさ」も「やりがい」も理解した上で、「それでも挑戦したい」と決意したあなたへ。
ここからは、その熱意を形にするための具体的な行動、つまり「就活で何をすべきか」をアドバイスします。
エンタメ業界の採用は、「好き」という熱意はもちろんのこと、それを行動に移せているか、そして業界の厳しい現実を理解した上で覚悟ができているか、という点を見ています。
単なる憧れではない、本気の姿勢をアピールするために、学生時代から準備できることはたくさんあります。
アルバイトやインターンで実務経験を積む
エンタメ業界を目指す上で最も有効な手段の一つが、アルバイトやインターンシップで「現場」を経験することです。
テレビ局のAD、イベント運営スタッフ、ライブハウスのスタッフ、制作会社のインターンなど、探せば様々なチャンスがあります。
実際に業界の空気感や仕事の流れを肌で感じることで、あなたが抱いているイメージと現実とのギャップを確かめることができます。
また、そこで得た経験は、エントリーシートや面接で語る上で、何よりも強力な武器となります。
「きつい」と言われる現場を実際に経験した上で「それでもやりたい」と語る志望動機には、机上の空論ではない圧倒的な説得力が生まれます。
志望動機を徹底的に深掘りする
エンタメ業界の面接で最も重要な質問が「志望動機」です。
「エンタメが好きだから」「感動を与えたいから」という理由は、志望者全員が言う前提であり、それだけでは全く評価されません。
「なぜ、数ある業界の中でエンタメなのか」「なぜ、競合他社ではなく、その会社なのか」「入社して、具体的に何を成し遂げたいのか」という問いに、あなた自身の具体的な経験に基づいて答えられなければなりません。
例えば、「学生時代にイベントを企画した経験から、裏方として人を喜ばせることにやりがいを感じた」といった原体験と結びつけ、その会社でしか実現できないことを論理的に説明する必要があります。
圧倒的なアウトプットとインプット
エンタメ業界で働くには、世の中のコンテンツに対する圧倒的なインプット(知識)と、それに対する自分なりの考えを発信するアウトプットの習慣が不可欠です。
映画、音楽、ドラマ、本、舞台、ゲームなど、ジャンルを問わず、流行っているものからニッチなものまで幅広く触れましょう。
そして、ただ消費するだけでなく、「なぜこれが面白いのか」「自分ならどう作るか」を常に考え、その分析や感想をSNSやブログ、ノートなどに書き留める習慣をつけてください。
学生時代に自分で動画を制作した、イベントを企画したといった具体的な「アウトプット」の経験も非常に強いアピールになります。
あなたの「好き」が本物であることを、行動で示しましょう。
適職診断ツールを用いる
エンタメ業界のリアルを知るにつれ、「自分は本当のところ、この業界に向いているのだろうか」と不安になることもあるかもしれません。
業界研究や自己分析を進める中で、客観的な視点が欲しくなるのは当然のことです。
そうした時に役立つのが、「適職診断ツール」です。
これらのツールは、いくつかの質問に答えるだけで、あなたの性格的な強みや弱み、価値観、向いている仕事の傾向などを分析してくれます。
エンタメ業界の仕事、例えば「プレッシャーの中で成果を出す仕事」や「多くの人と協力して進める仕事」が、あなたの特性と合致しているかどうかを判断する一つの材料として活用できます。
ただし、診断結果はあくまで参考です。
結果に一喜一憂するのではなく、自己分析を深めるための「きっかけ」として上手に使いましょう。
【エンタメ業界はきついのか】適性がわからないときは
適職診断ツールを使ってみたり、自己分析を重ねてみたりしても、「エンタメ業界が自分に合うか、まだ確信が持てない」という人も多いと思います。
それはとても真剣に自分のキャリアを考えている証拠です。
適性がわからないと感じる一番の理由は、まだ「業界のリアル」と「自分の本質」の両方の理解が足りていないからです。
そんな時は、まず自己分析をさらに深掘りしましょう。
自分が「何を大切にして働きたいか」(例えば、やりがい、安定、成長、仲間など)を明確にすることがスタートです。
その上で、もう一度業界研究に戻り、特に「きつい」とされる側面が、自分の大切にしたい価値観と両立できるかを冷静に考えてみてください。
OB・OG訪問やインターンシップで、実際に働いている人の生の声を聞くことも、適性を見極める上で非常に有効な手段です。
おわりに
エンタメ業界は、確かに「きつい」側面を持つ厳しい世界です。
しかし、それ以上に、人々の心を動かし、人生に彩りを与えるという、何物にも代えがたい大きなやりがいがある仕事です。
この記事を読んで、そのリアルな部分を理解した上で、それでもなお「挑戦したい」という情熱が湧き上がってきたのなら、あなたはきっとこの業界に向いています。
その「覚悟」こそが、あなたの就活における最大の武器になります。
ぜひ自信を持って、その熱意をぶつけてみてください。
あなたの挑戦を心から応援しています。