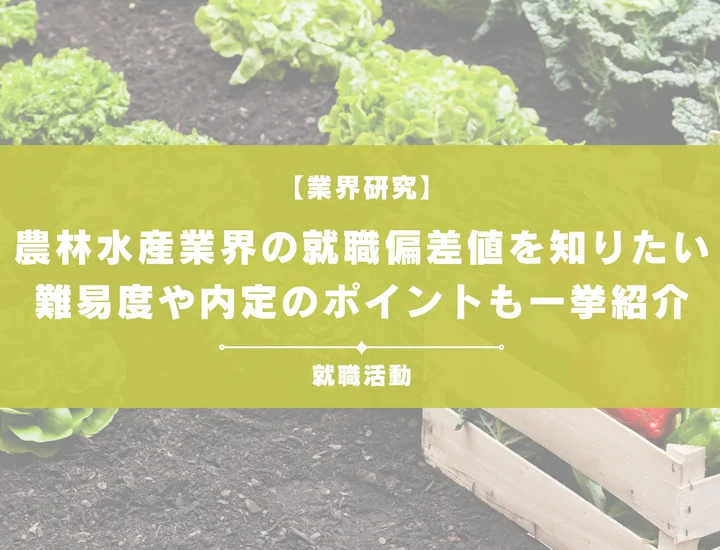HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
目次[目次を全て表示する]
はじめに
「SE やめとけ」という言葉を、インターネット検索やSNSなどで目にしたことはありませんか。
IT業界は成長していると聞く一方で、なぜこのようなネガティブな意見が出るのでしょうか。
就職活動を進める中で、SE(システムエンジニア)という職種に興味を持ちつつも、こうした声に不安を感じている方は少なくないはずです。
この記事では、なぜSEはやめとけと言われるのか、その具体的な理由から、向いている人・向いていない人の特徴、そしてSE以外のIT関連のキャリアパスまで、幅広く解説します。
表面的な情報に惑わされず、ご自身の適性を見極め、納得のいくキャリア選択をするための一助としてください。
【SEやめとけ】そう言われる理由とは
SEはIT社会を支える重要な仕事ですが、「やめとけ」という声が上がるのには、やはりそれなりの理由があります。
その多くは、IT業界、特にシステム開発の現場特有の働き方やプレッシャーに関連しています。
もちろん、これらすべての要素が、すべてのSEに当てはまるわけではありません。
しかし、SEという職種を検討する上で、ネガティブな側面として語られがちなポイントを知っておくことは非常に重要です。
ここでは、SEはやめとけと言われる代表的な3つの理由を深掘りし、その実態について具体的に解説していきます。
長時間労働や納期に追われやすい
SEの仕事は、プロジェクト単位で進むことが基本です。
そして、プロジェクトには必ず「納期」が存在します。
この納期が、SEの働き方に大きな影響を与えます。
特に、システムのリリース前や、プロジェクトの最終段階(テストフェーズ)になると、作業が集中しがちです。
予期せぬ不具合(バグ)の修正や、追加の要望への対応に追われ、残業や休日出勤が続くことも珍しくありません。
また、システム障害は時間を選ばず発生するため、緊急の呼び出しに対応する必要が出てくるケースもあります。
特に客先常駐(SES)という形態の場合、自社のカレンダー通りに休めず、常駐先のスケジュールに合わせなければならないこともあります。
もちろん、近年は働き方改革の影響で、労働時間管理を厳格に行う企業も増えてはいます。
しかし、業界の構造上、納期のプレッシャーが完全になくなることはありません。
この体力的な負担と、プライベートの時間が確保しにくいという側面が、「やめとけ」と言われる最も大きな理由の一つです。
技術の変化が早く常に勉強が必要になる
IT業界の技術革新のスピードは、他の業界と比べても非常に速いです。
数年前に主流だった技術が、今では古いものとして扱われることも日常茶飯事。
新しいプログラミング言語、フレームワーク、クラウドサービスなどが次々と登場します。
SEとして第一線で活躍し続けるためには、これらの新しい技術を自主的にキャッチアップし、知識を常にアップデートし続ける必要があります。
業務時間内に研修が組まれることもありますが、それだけでは足りず、多くの場合、業務時間外や休日を使って自己研鑽に励まなければなりません。
この「学び続ける姿勢」を楽しめる人にとっては、自身の市場価値を高め続けることができる魅力的な環境です。
しかし、学生時代の勉強のように「卒業したら終わり」ではなく、終わりなき学習が求められることに苦痛を感じる人もいます。
「プライベートの時間は、仕事と切り離して趣味や休息に使いたい」と考える人にとって、この絶え間ない自己研鑽へのプレッシャーは、非常に重い負担となります。
クライアント対応や仕様変更で振り回されることがある
SEは、ただ黙々とパソコンに向かっている技術職、というイメージがあるかもしれませんが、実際には「顧客(クライアント)」との折衝が非常に多い仕事です。
顧客の「こんなシステムが欲しい」という曖昧な要望をヒアリングし、それを具体的なシステムの「仕様」に落とし込むのがSEの重要な役割です。
しかし、顧客自身がITに詳しくないケースも多く、開発の途中で「やっぱり、こうしてほしい」と突然の仕様変更を要求されることがあります。
この仕様変更は、時にプロジェクトの根幹に関わるものであり、それまで数週間かけて作り上げてきた設計やプログラムを、根本からやり直さなければならない事態(いわゆる「手戻り」)を招きます。
こうした理不尽とも思える状況でも、SEはシステムの専門家として、顧客の要望と、技術的な実現可能性や納期のバランスを取りながら、粘り強く調整・交渉を行う必要があります。
技術的なスキルだけでなく、高いコミュニケーション能力やストレス耐性が求められるこの側面に疲れ果ててしまう人も少なくありません。
【SEやめとけ】向いていない人の特徴
「SE やめとけ」という言葉が、すべての就活生に当てはまるわけではありません。
しかし、SEという仕事の特性上、残念ながらミスマッチが起こりやすいのも事実です。
もし、これから挙げる特徴にご自身が強く当てはまると感じる場合、SEとして働き始めたとしても、大きなストレスを抱え込み、早期に離職してしまう可能性があります。
ご自身の性格や得意・不得意と、SEに求められる素養がどれだけ一致しているか、あるいは異なっているか。
ここでしっかりと見極めていきましょう。
納期プレッシャーに弱い人は継続が難しい
SEの仕事から「納期」という概念を取り除くことは不可能です。
プロジェクトは常にスケジュールに基づいて進行し、遅延はクライアントのビジネスに多大な影響を与えるため、許されないという強いプレッシャーが常にかかります。
納期が近づくにつれて、業務は密度を増し、精神的な余裕も失われがちです。
このプレッシャーを「適度な緊張感」としてポジティブに捉え、パフォーマンスを上げられる人もいます。
しかし、多くの人にとっては、締切に追われる状況は大きなストレスとなります。
特に、責任感が強く真面目な人ほど、「もし遅れたらどうしよう」という不安から自分を追い詰めてしまい、精神的に疲弊してしまうことがあります。
もしあなたが、テスト勉強を一夜漬けでやるような状況で極度のストレスを感じたり、時間に追われると焦ってミスを連発してしまったりするタイプであれば、SEの仕事は非常に苦しいものになるでしょう。
マイペースに、自分のリズムでじっくりと仕事を進めたいと考える人には、継続が難しい環境かもしれません。
ロジカルな思考や調査が苦手だと負担が大きい
SEの仕事の根幹は、論理的思考(ロジカルシンキング)にあります。
顧客の曖昧で、時には矛盾すら含む要望を整理し、誰が読んでも誤解のないよう、筋道を立ててシステムの仕様書に落とし込む作業が求められます。
また、システム開発において、エラーやバグ(不具合)はつきものです。
エラーが発生した際、SEは「なぜこの問題が起きたのか」を突き止めなければなりません。
そのプロセスは、まさに論理的な推理そのものです。
考えられる原因の仮説を立て、一つひとつ検証し、問題を切り分けていく地道な調査作業が必要となります。
この作業は、感覚や直感で進めることはできません。
物事を順序立てて考えることが苦手な人や、パズルを解くような地道な分析作業を苦痛に感じる人には、日々の業務が大きな負担となります。
さらに、分からないことに直面した際、自力でインターネットや技術書、過去の資料を調べて解決する「自己解決能力」も不可欠です。
論理的に物事を考え、粘り強く未知の問題を調査することに楽しさを見出せない場合、SEとしての適性は低いと言わざるを得ません。
ルーティンよりも変化のある仕事を好む人は適性が低い
この見出しは、少し意外に思われるかもしれません。
IT業界は「変化が激しい」と前述した通りですが、SEの日々の「業務」に焦点を当てると、非常に地道で単調な作業の側面も色濃く存在します。
「ルーティン」とは少し異なりますが、長時間にわたってPCに向かい、一つの作業に没頭し続ける忍耐力が求められるのです。
例えば、プログラミングのフェーズでは、設計書に基づいて何時間もコードを書き続けます。
テストのフェーズでは、決められた手順書に沿って、ひたすら同じような操作を繰り返し、システムが正しく動くかを確認します。
バグが見つかれば、その原因を特定するために、膨大なログやコードとにらめっこを続けます。
これらの作業は、高い集中力を要する一方で、外から見れば非常に単調なデスクワークです。
「毎日違う場所に行きたい」「たくさんの人と直接会って話す仕事がしたい」といった、物理的な変化や刺激を強く求める人にとっては、SEのこうした地道な作業は退屈で苦痛に感じる可能性があります。
もちろん、プロジェクトが変われば扱う技術や顧客も変わるという「変化」はありますが、日々の業務の多くはPCの前での論理的な作業が占めることを理解しておく必要があります。
【SEやめとけ】後悔しやすい瞬間はあるの?
就職活動中は、どの企業も良い面をアピールするため、入社後の「現実」を正確に想像するのは難しいものです。
「SE やめとけ」という言葉の意味を、身をもって知ることになる瞬間は、残念ながら存在します。
入社前に抱いていた華やかなIT業界のイメージと、実際に直面する業務の厳しさとのギャップ。
そのギャップが大きければ大きいほど、「こんなはずではなかった」という後悔につながります。
ここでは、多くのSE経験者が「この仕事を選んで後悔した」と感じやすい、具体的な3つの瞬間についてご紹介します。
想像以上の残業と緊急対応の多さに驚いたとき
「IT業界は忙しい」「SEは残業が多い」という話は、就活生もある程度は耳にしているはずです。
しかし、その「程度」が自らの想像をはるかに超えていた時、人は強く後悔します。
特にプロジェクトが「炎上」と呼ばれる危機的状況に陥った場合、連日の終電帰りや、会社に泊まり込む事態も起こり得ます。
また、自分が担当したシステムが稼働を開始した後も、安心はできません。
システムに重大な障害が発生すれば、それが深夜であろうと休日であろうと、緊急の呼び出しがかかります。
友人との約束や家族との大切な時間を、会社の都合で突然キャンセルせなければならない。
こうした経験が続くと、「自分は一体何のために働いているのだろう」という虚無感に襲われます。
ワークライフバランスを重視したいと考えていた人ほど、この現実とのギャップは深刻です。
自分の時間をコントロールできない理不尽さに直面し、入社前に企業の「平均残業時間」といった表面的な数字だけでなく、障害対応の体制やプロジェクトの繁忙期について、もっと突っ込んで調べておくべきだったと後悔する瞬間です。
仕様変更で仕事が振り出しに戻りモチベが下がったとき
SEの仕事は、顧客の要望を形にすることです。
しかし、その要望自体が開発の途中で変わってしまうことは、残念ながら頻繁に起こります。
開発がある程度進み、システムの形が見えてきた段階になって、顧客から「やはり、ここの仕様を変えたい」という一言。
その一言が、それまで数週間、あるいは数ヶ月かけて作り上げてきた設計やプログラムを、根本から覆すものであった場合、SEの心は折れかけます。
いわゆる「ちゃぶ台返し」と呼ばれる状況です。
特に、顧客と直接やり取りしている上司や営業担当者の調整能力が低く、顧客の言いなりになって変更を受け入れてしまう場合、現場のSEはその理不尽な手戻り作業をすべて引き受けることになります。
自分が費やしてきた時間と労力が、一瞬にして無駄になったと感じる瞬間、「何のために頑張ってきたのだろう」と、仕事へのモチベーションは急速に低下します。
技術力や努力だけではどうにもならない、こうしたビジネス上の調整や人間関係のストレスに直面した時、SEという仕事の厳しさを痛感し、後悔につながります。
技術のキャッチアップが追いつかず自信をなくしたとき
「SE やめとけ」と言われる理由として、技術の速い流れに対応し続ける必要がある、と述べました。
入社当初は、新しい知識を学ぶこと自体が新鮮で、同期と競い合いながら楽しく感じられるかもしれません。
しかし、数年が経ち、中堅と呼ばれる立場になると状況は変わってきます。
日々の業務に追われる中で、かつてのように学習時間を確保することが難しくなっていきます。
一方で、技術のトレンドは容赦なく移り変わり、次々と新しいツールや言語が登場します。
ふと周りを見渡すと、自分より新しい技術に詳しい後輩が入社してきたり、同期が難易度の高い資格を取得していたりします。
自分だけが時代に取り残されていくような焦燥感。
「この技術、知らないの?」と言われるのが怖くなる。
かつては得意だった分野でさえ、新しい手法に対応できず、自信を失っていく。
学び続けることに疲れを感じ、自分の市場価値が下がっていく恐怖に直面した時、「自分はもうSEとしてやっていけないかもしれない」と、この職業を選んだこと自体を後悔し始めるのです。
【SEやめとけ】そうではないケースも存在する
ここまで「SE やめとけ」と言われる厳しい側面を多く見てきましたが、誤解しないでほしいのは、すべてのSEがそのような環境で疲弊しているわけではない、ということです。
同じ「SE」という肩書きであっても、所属する企業の業態や、担当する業務内容、そして個人の適性によって、その働き方は大きく異なります。
ネガティブなイメージだけで、IT業界全体やSEという職種の可能性を閉ざしてしまうのは、非常にもったいないことです。
ここでは、「SE やめとけ」のイメージとは対極にある、比較的働きやすいとされる3つのケースについて解説します。
残業が少なく働きやすい社内SEの場合
「SE やめとけ」というイメージの多くは、顧客のシステム開発を請け負うSIer(エスアイヤー)や、客先に常駐して働くSES企業のSEに当てはまることが多いです。
一方で、これらの企業とは異なり、自社の情報システム部門で働くSE、いわゆる「社内SE」という働き方があります。
社内SEの主な仕事は、自社で利用するシステムの開発・運用・保守や、社員からのITに関する問い合わせ対応(ヘルプデスク)などです。
顧客が「社外」ではなく「社内の他部署」であるため、SIerのSEが直面するような、無理な納期や理不理尽な仕様変更のプレッシャーが比較的少ない傾向にあります。
また、自社の業務時間に合わせて働くため、残業が少なく、ワークライフバランスを保ちやすいことが最大の魅力です。
ただし、「楽な仕事」というわけではありません。
会社のITインフラ全般を少人数で支えるため、幅広い知識が求められますし、時には経営層に対してIT戦略を提案するような重責を担うこともあります。
最新技術の追求よりも、安定した環境で自社のビジネスに貢献したいと考える人にとって、社内SEは「SE やめとけ」のイメージを覆す、非常に有力な選択肢となります。
要件定義や上流工程中心で技術負担が軽い場合
SEの仕事は、その工程によって役割が分かれています。
顧客から「どのようなシステムが欲しいか」をヒアリングし、システムの全体像を決める「要件定義」や「基本設計」といった工程を「上流工程」と呼びます。
一方で、その設計書に基づいて、実際にプログラミング(コーディング)やテストを行う工程を「下流工程」と呼びます。
「SE やめとけ」の理由である「技術のキャッチアップが追いつかない」という悩みは、特に下流工程で最新の技術を駆使するプログラマー寄りのSEに多い悩みです。
もし、あなたがキャリアを積んだり、最初から上流工程を専門に扱う企業(コンサルティングファームなど)に所属したりする場合、自ら手を動かしてコードを書く機会は減っていきます。
その代わり、顧客の業務内容を深く理解する力、要望を的確に引き出すヒアリング能力、複雑な要件を分かりやすい資料にまとめるドキュメント作成能力、そしてプロジェクトを円滑に進めるための交渉力や調整力といった、ビジネススキルやコミュニケーション能力がより強く求められます。
技術の最前線を追い続ける負担は軽い一方で、プロジェクトの成否を左右する重い責任を担います。
技術そのものよりも、ITを使って顧客の課題を解決するプロセスに興味がある人には、適した働き方と言えるでしょう。
自分の適性がプログラミング・論理的思考と一致している場合
結局のところ、「SE やめとけ」という言葉は、その人の適性に合わなかった場合に、最も強く響くものです。
逆に言えば、SEという仕事に求められるスキルと、あなた自身の特性が強く一致しているのであれば、それは「天職」にさえなり得ます。
例えば、物事を順序立てて考えることが好きで、パズルやクイズを解くような問題解決のプロセスに喜びを感じる人。
あるいは、一つのことに集中し始めると時間を忘れて没頭できる人。
そして、新しい知識や技術に触れることにワクワクし、知的好奇心が旺盛な人。
こうした素養を持つ人にとって、SEの仕事は苦痛どころか、やりがいの宝庫です。
「やめとけ」と言われる理由である長時間労働や困難な仕様変更でさえも、自らの論理的思考と技術力を駆使して乗り越えるべき「課題」として、前向きに捉えることができます。
複雑なバグの原因を何時間もかけて突き止め、ついに解決した時の達成感。
自分が作り上げたシステムが、世の中の役に立っているという実感。
これらは、SEという仕事でしか味わえない、何物にも代えがたい喜びです。
もし、自分の適性がSEと一致していると強く感じるならば、周囲のネガティブな声に惑わされる必要は一切ありません。
【SEやめとけ】SE以外のおすすめ職種
「SE やめとけ」という情報に触れ、自己分析を進めた結果、「やはり自分にはSEは向いていないかもしれない」と感じた方もいるでしょう。
しかし、だからといってIT業界全体を諦める必要はありません。
IT業界には、SE以外にも多様な職種が存在します。
SEに求められる論理的思考力やITへの関心は、他の職種でも大いに役立つ素養です。
開発の最前線とは異なる場所で、あなたの能力を発揮できるかもしれません。
ここでは、SEとは異なるアプローチでITやビジネスに関わる、3つのおすすめ職種を紹介します。
ITコンサル(技術よりも課題解決が中心)
ITコンサルタントは、企業の経営者が抱える様々な課題を、ITの力を活用して解決に導く専門家です。
SEが「どのようにシステムを作るか(How)」を主に考えるのに対し、ITコンサルタントは「そもそも、なぜそのシステムが必要なのか(Why)」や「経営課題を解決するためには、何をすべきか(What)」という、より上流の、経営戦略に近い視点でプロジェクトに関わります。
具体的な業務としては、クライアントの経営層や業務部門にヒアリングを行い、現状の業務プロセスを分析し、最適なIT戦略の立案やシステム導入の提案を行います。
SEのように自らプログラミングを行うことはほとんどありません。
求められるのは、技術力以上に、高度な論理的思考力、課題発見・解決能力、そして経営層を納得させるプレゼンテーション能力です。
技術の細かな変化に振り回されるよりも、ビジネスの根幹から課題解決に携わりたいという強い意志を持つ人に向いています。
ただし、SE以上に成果へのプレッシャーは厳しく、激務であることも多いため、その点は覚悟が必要です。
カスタマーサクセス(導入支援が中心の職種)
カスタマーサクセスは、比較的新しい職種ですが、特にSaaS(サブスクリプション型のソフトウェアサービス)を提供する企業で急速に広まっています。
その役割は、自社のサービスを契約・導入してくれた顧客が、そのサービスを最大限に活用し、期待していた成果(サクセス)を達成できるように支援することです。
具体的な業務は、サービスの導入初期設定のサポート、操作方法のトレーニング、より効果的な使い方のアドバイス、顧客からの要望やフィードバックを収集して開発部門に伝える、など多岐にわたります。
SEのような開発技術は必須ではありませんが、自社サービスに関する深い知識は必要です。
それ以上に、顧客のビジネスや課題に寄り添う共感力、そして高いコミュニケーション能力が求められます。
「売って終わり」ではなく、顧客と長期的な関係を築き、伴走者として成功をサポートする仕事です。
「SE やめとけ」の理由である納期や仕様変更のプレッシャーとは異なり、顧客から直接「ありがとう」と言われる機会も多く、やりがいを感じやすいのが特徴です。
技術を追求するよりも、人と関わり、サポートすることに喜びを感じる人に適しています。
Webマーケティング・企画系の職種
SEがシステムという「モノ(箱)」を作る仕事だとすれば、Webマーケティングや企画系の職種は、そのモノやサービスを「どのように世の中に広め、利用してもらうか」を考える仕事です。
具体的な業務内容は、Webサイトのアクセスデータを分析し、どうすればより多くの人に見てもらえるか(SEO対策)を考えたり、インターネット広告を効果的に運用したり、SNSを活用したキャンペーンを企画したり、様々です。
ITの知識は、データ分析ツールを使ったり、Webの仕組みを理解したりする上で必要不可。
しかし、その中心となるスキルは、市場のトレンドや消費者の心理を読み解くマーケティングの視点です。
SEの開発作業とは異なり、自分の行った施策の結果が「アクセス数」や「売上」といった目に見える数字としてダイレクトに返ってくるのが、この仕事の厳しさであり、面白さでもあります。
論理的に考える力はSEとも共通しますが、どちらかと言えば、数字の分析や、世の中の流行、人の行動心理などに強い興味がある人に向いています。
IT業界の成長性を享受しつつ、開発とは違った角度からビジネスを動かしたい人におすすめの職種です。
【SEやめとけ】SEを避けたい就活生がすべきこと
「SE やめとけ」という情報をきっかけに、SEという職種を候補から外そう、あるいはIT業界そのものをやめようかと考えている就活生もいるかもしれません。
しかし、ネガティブな情報だけを理由に、自分の可能性を狭めてしまうのは早計です。
大切なのは、その情報を「自分ごと」として捉え直し、自分自身のキャリア選択に活かすことです。
もし、SEを避けるという選択をするのであれば、それは他人の意見に流された結果ではなく、自分なりの明確な理由に基づくべきです。
ここでは、SEを避けたいと考えた就活生が、次に取るべき具体的な行動を3つ提案します。
適性を見極めるために自己分析を深める
「SE やめとけ」と聞いて、なぜ自分は「避けたい」と感じたのでしょうか。
その理由を深く掘り下げることが、すべてのスタートです。
単に「大変そうだから」という曖昧な理由ではなく、どの要素が自分にとって耐え難いのかを特定する必要があります。
例えば、「長時間労働や納期プレッシャーに弱い」と感じたのか、「継続的な技術の勉強が負担」だと感じたのか、それとも「顧客との仕様変更のやり取りがストレスになりそう」だと感じたのか。
過去のアルバイトや部活動、学業の経験を振り返り、自分がどのような状況で力を発揮し、どのような状況で強いストレスを感じたかを具体的に洗い出してみましょう。
「コツコツと地道な作業を続けるのが得意」なのか、「人とコミュニケーションを取りながら進める方が好き」なのか。
自己分析を深めることで、SEという職種の「どの部分」が自分に合わないのかが明確になります。
その「合わない部分」を正確に理解することこそが、SE以外の、本当に自分にマッチする職種を見つけるための最短ルートになります。
仕事への優先順位を明確にして職種比較をする
自己分析によって、自分が仕事に求めるもの、逆に避けたいものが明確になったら、次は「仕事選びの軸」を決定します。
つまり、働く上で「何を最優先にするか」の優先順位をつけることです。
給与、勤務地、ワークライフバランス、仕事のやりがい、会社の安定性、将来性、社風など、様々な要素があります。
残念ながら、これらすべての条件が完璧に揃った仕事は、現実的には存在しません。
何かを得るためには、何かを妥協する必要があります。
「SE やめとけ」の理由である「長時間労働」を絶対に避けたいのであれば、「ワークライフバランス」の優先順位を最高に設定すべきです。
その代わり、若いうちからの高年収や、急成長のベンチャー企業での刺激は得られないかもしれません。
この自分なりの「優先順位のモノサシ」を持って、初めて、SEと他の職種を公平に比較することができます。
例えば、ITコンサルは給与が高いかもしれませんが、SE以上に激務である可能性が高いです。
社内SEは安定していますが、最新技術に触れる機会は減るかもしれません。
何を妥協し、何を最優先にするか。
この軸が定まっていれば、他人の意見や表面的な情報に振り回されず、納得感のある選択ができます。
IT以外のインターンに参加して働き方を理解する
「SE やめとけ」という言葉に触れると、IT業界全体に対してネガティブなイメージを持ってしまうかもしれません。
しかし、それが本当に「IT業界」が合わないのか、それとも「SEという職種」が合わないだけなのかは、まだ分かりません。
そこでおすすめしたいのが、あえてITとは全く異なる業界のインターンシップに参加してみることです。
例えば、メーカー、金融、商社、小売、サービス業など、世の中には多種多様な仕事があります。
他業界の働き方、仕事の進め方、企業文化を実際に肌で感じることで、IT業界やSEという仕事を、より客観的に、比較対象を持って見つめ直すことができます。
もしかすると、他業界の営業職を体験してみて、「自分はやはり顧客と直接話すよりも、PCに向かって論理を組み立てる方が合っている」と、逆にSEへの適性を再認識するかもしれません。
あるいは、「IT業界特有のスピード感や変化こそが、自分が求めていたものだ」と気づくかもしれません。
もちろん、その逆も然りです。
様々な選択肢を実際に体験し、比較検討すること。
それこそが、「SE やめとке」という情報に触れた就活生が、最も建設的に取るべき行動の一つです。
【SEやめとけ】自分はSEに向いている?チェックリスト
「SE やめとけ」という声がある一方で、SEとして生き生きと働き、高いパフォーマンスを発揮している人が大勢いるのもまた事実です。
結局のところ、仕事が「きつい」と感じるか、「やりがい」と感じるかは、その人の適性や価値観との相性、つまり「マッチング」の問題に尽きます。
ここでは、SEという仕事に求められる基本的な素養について、3つのシンプルな質問を用意しました。
「やめとけ」という声が気になる今だからこそ、フラットな目線で、ご自身がどの程度当てはまるか、自己分析の材料としてチェックしてみてください。
論理的な説明や整理が得意か
SEの仕事は、論理の積み重ねで成り立っています。
顧客の曖昧な要望を聞き出し、それを「誰が」「いつ」「何を」「どうする」といった形で、矛盾や漏れがないように整理し、システムという論理的な形に落とし込む必要があります。
また、プロジェクトはチームで進めるため、自分の考えを他者に正確に伝える能力が不可欠です。
「なぜこのシステムが必要なのか」「なぜこのエラーが起きたのか」「なぜこの設計が最適だと考えたのか」。
こうした事柄を、ITに詳しくない顧客や、忙しいチームメンバーに対して、感情論ではなく、理由や根拠を明確にして筋道立てて説明する場面が非常に多くあります。
普段の会話やレポート作成において、物事を順序立てて話したり、複雑な情報を図や箇条書きで整理したりすることが得意だと感じるでしょうか。
もし、こうした論理的な思考や説明、情報の整理といった作業に楽しさや得意意識を感じるなら、SEとしての基本的な素養は十分に備わっていると言えます。
新しい知識を継続して学ぶことに抵抗がないか
「SE やめとけ」の理由として、絶え間ない勉強の必要性を挙げました。
これは裏を返せば、学ぶことが好きな人にとっては、最高の環境であるとも言えます。
IT業界の技術は日進月歩で、大学で学んだ知識があっという間に古くなる世界です。
SEとして働く以上、業務に必要な技術はもちろん、業界の最新トレンドに対しても常にアンテナを張り、自主的にインプットし続ける姿勢が求められます。
このチェックリストで問いたいのは、勉強が「大好き」かどうかではありません。
大切なのは、新しい知識や技術に対して「抵抗がない」かどうかです。
あなたは、知らないことや、やったことがない課題に直面した時、それを「面倒だ」「避けたい」と強く感じますか。
それとも、「面白そうだ」「どうなっているんだろう」と、知的好奇心が刺激され、自ら調べ始めるタイプでしょうか。
学生時代の勉強も、テストのために仕方なくやるというよりは、新しいことを知るプロセス自体に、ある程度の楽しさを見出せていたでしょうか。
もし後者であれば、SEの「学び続ける」という特性は、あなたにとって大きな負担にはならない可能性が高いです。
一つの作業を集中して続けるのが苦ではないか
SEの仕事には、顧客との折衝や会議といった華やかな側面もありますが、その実、キャリアの多くの時間は、PCの前での地道な作業によって占められます。
例えば、詳細な設計書を作成するために、何時間も仕様とにらめっこする。
あるいは、設計書に基づいて、黙々とプログラミングのコードを書き続ける。
そして、システムが正しく動くか、決められた手順に沿って、ひたすらテストを繰り返す。
もしバグ(不具合)が見つかれば、そのたった一つの原因を突き止めるために、膨大なログやコードの中から問題箇所を探し当てるまで、何時間も画面に集中し続ける必要があります。
こうした作業は、高い集中力と忍耐力を要求されます。
あなたは、数時間、誰とも話さずPCの前に座り、一つの課題に没頭することは苦痛でしょうか、それとも得意な方でしょうか。
すぐに飽きてしまったり、周りの音や動きが気になって集中が途切れたりするタイプの人には、SEのこうした業務は非常に辛い時間となるでしょう。
逆に、一度集中し始めると時間を忘れて没頭できる、いわゆる「ゾーン」に入る体験が多い人は、SEの作業に高い適性を持っていると言えます。
よくある質問
ここまで「SE やめとけ」というキーワードを軸に、その理由から適性、代替職種、就活生が取るべき行動まで、多角的に解説を進めてきました。
SEという仕事の光と影、その両面が見えてきたかと思います。
しかし、それでもまだ、「結局、自分はどう判断すればいいのか」と、具体的な疑問や不安が残っているかもしれません。
ここでは、SEのキャリアを考える上で、就活生の皆さんから特によく寄せられる3つの質問について、Q&A形式で簡潔にお答えします。
SEは本当にやめといた方がいいの?
結論から言えば、「適性や価値観が合わない人にとっては、やめておいた方が賢明」ですが、「すべての人にとって、やめておくべき職種」では全くありません。
本記事で解説した通り、「SE やめとけ」と言われる背景には、納期プレッシャー、継続的な学習、顧客との折衝といった、この職種特有の厳しさがあります。
これらの要素が、ご自身の価値観(例えば、ワークライフバランスを最優先したい、学ぶことは苦痛だ、など)と根本的に相反する場合、SEとして働き続けることは大きなストレスとなり、後悔につながる可能性が高いです。
しかし、逆に、論理的に物事を考えるのが好きで、新しい技術にワクワクし、自分が作ったもので課題を解決することに達成感を覚える人にとっては、これほどやりがいのある仕事もありません。
「やめとけ」という言葉は、あくまで一つの側面、あるいは適性が合わなかった人の意見である可能性を考慮し、ご自身の適性や優先順位と照らし合わせて、冷静に判断することが最も重要です。
SEを避けるとIT業界で内定は取りにくくなる?
これは、ある側面では「はい」と言えます。
現在、IT業界は深刻な人手不足にあり、その中でも特にSE(システム開発を担う人材)の採用枠は、業界全体で見ても非常に大きいです。
そのため、文系・理系を問わず、未経験からIT業界を目指す学生にとって、SEは最も間口が広い「入り口」となっているのが実情です。
したがって、SEという職種を最初から完全に避けてしまうと、応募できる企業の数や職種が限定され、結果として内定獲得の難易度は相対的に上がる可能性があります。
しかし、もちろん「内定が取れなくなる」わけではありません。
IT業界の仕事はSEだけではありません。
本記事で紹介したITコンサル、カスタマーサクセス、Webマーケティングのほか、営業職、企画職、デザイナーなど、様々な職種がIT企業には存在します。
もしSEを避けるのであれば、なぜSEではダメなのか、そして代わりにどの職種で、どのようなことを成し遂げたいのか、より明確な志望動機と自己分析が求められる、と考えておくと良いでしょう。
SEと他のIT職種の違いはどれくらいある?
同じIT業界の職種でも、役割や求められるスキルは大きく異なります。
SE(システムエンジニア)は、その中でも特に「システム開発プロジェクト」の中核を担う職種です。
顧客の要望を聞いてシステムの「設計図(仕様)」を作り、時には自らプログラミングも行い、システムを完成させて納品するまでの一連の流れに責任を持ちます。
これに対し、プログラマーは、SEが作った設計図に基づいて「コードを書く(作る)」ことに特化しています。
ITコンサルタントは、SEよりもさらに上流の「どのシステムを、何のために作るべきか」という経営戦略レベルから関わります。
社内SEは、顧客が「社外」ではなく「社内」であり、開発よりも自社システムの運用・保守やIT環境の整備が中心となります。
WebマーケターやWebデザイナーは、システム開発そのものよりも、Webサイトを通じた集客や、デザイン(見た目)の部分を専門に担当します。
このように、職種によって仕事内容、関わる相手、必要なスキルセットは全く異なります。
SEは、その中でも技術とビジネスの「橋渡し役」として、最も広範な知識とスキルが求められる職種の一つと言えます。
まとめ
「SE やめとけ」という、就活生にとっては不安を煽るようなキーワード。
この記事では、その言葉の背景にある理由、SEの仕事の厳しさとやりがい、そしてIT業界の多様なキャリアパスについて、できるだけ具体的に解説してきました。
ネガティブな情報に触れると、ついその職種や業界全体を敬遠してしまいがちです。
この記事が、表面的な情報に振り回されることなく、ご自身が心から納得できるキャリア選択をするための、一つの道しるべとなれば幸いです。


_720x550.webp)