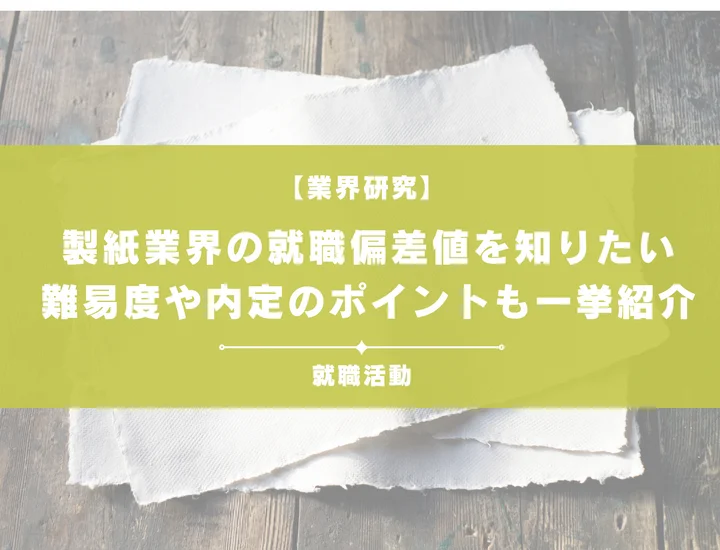HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
この記事では、製紙業界の就職偏差値ランキングの目安から、仕事のリアルな中身、そして内定を掴むための具体的なポイントまで、余すところなくお伝えします。
一見、伝統的で安定しているように見える製紙業界ですが、実は今、環境問題への対応や新素材の開発といった、未来に向けた大きな「変革期」を迎えているんです。
この記事を読めば、製紙業界があなたにとって本当に「働く価値のある場所」なのか、その判断材料がきっと見つかります。
目次[目次を全て表示する]
就職偏差値とは
就職活動を進める中で、「就職偏差値」という言葉を耳にしたことがあるかもしれませんね。
これは、大学受験の偏差値と同じように、企業の入社難易度を相対的に示した指標の一つです。
主に、企業の人気度、採用実績、待遇、安定性などを基に、就活生の間や特定のメディアで作成されることが多いです。
ただし、公的なデータではなく、あくまで目安である点には注意が必要です。
すべてを鵜呑みにする必要はありませんが、業界内での企業の位置づけや、どれくらいの準備が必要かを把握する上で、参考情報の一つとして活用するのは有効な手段と言えるでしょう。
製紙業界の就職偏差値ランキング
では、私たちの生活に欠かせない「紙」を供給する製紙業界の就職偏差値はどのようになっているのでしょうか。
製紙業界は、巨大な設備産業であり、国内市場が成熟していることから、比較的安定した大手企業が上位を占める傾向にあります。
ここでは、Digmedia編集部が独自にリサーチした、一般的な製紙業界の就職偏差値ランキング(目安)をランク別にご紹介します。
ご自身の企業研究や志望度を測る一つの材料としてチェックしてみてください。
【製紙業界】Aランク(就職偏差値70以上)
【70】王子製紙 レンゴー ニッポン高度紙工業 日本紙パルプ商事
製紙業界のトップメーカー(王子)、段ボール最大手(レンゴー)、専門商社トップ(日パ商事)、高い技術力を持つ専門紙メーカー(ニッポン高度紙工業)が並びます。
業界の枠を超えた大手企業としての人気と難易度を誇ります。
高い学歴や専門性に加え、商社であればグローバルな視点、メーカーであれば事業の多角化に対応できる柔軟な思考力が求められます。
【製紙業界】Bランク(就職偏差値66以上)
Bランク以降の就職偏差値を見るには会員登録が必要です。
無料登録すると、Bランク以降の就職偏差値をはじめとした
会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。
登録はカンタン1分で完了します。会員登録をして今すぐ製紙業界の就職偏差値をチェックしましょう!
【69】日本製紙 日本紙通商 エイピーピー・ジャパン
【68】大王製紙 王子マテリア 王子コンテナー トッパンパッケージプロダクツ トッパングラフィックコミュニケーションズ
【67】北越コーポレーション セッツカートン
【66】巴川コーポレーション 大王パッケージ
王子製紙に次ぐ業界大手メーカー(日本製紙、大王製紙)や、その関連商社・パッケージング企業が中心です。
大手グループの安定性や事業規模から、Aランクに次ぐ高い人気を集めます。
ペーパーレス化が進む中、紙以外の分野(パッケージ、新素材など)への事業展開を理解し、そこでどう貢献できるかを語る必要があります。
【製紙業界】Cランク(就職偏差値61以上)
【65】トーモク 日本トーカンパッケージ
【64】三菱製紙 ダイナパック 佐川印刷
【63】中越パルプ工業 ザ・パック クラウン・パッケージ
【62】特殊東海製紙 昭和パックス 大和紙器 大塚包装工業
【61】イムラ封筒 大石産業 野崎印刷紙業 日之出紙器工業
段ボール・パッケージ分野の有力企業や、封筒(イムラ)、特殊紙(三菱製紙)など特定分野で高いシェアを持つ専門メーカーが並びます。
BtoBビジネスが中心ですが、各分野で確固たる地位を築く優良企業群です。
自己分析と企業研究をしっかり行い、その企業の専門分野や強みを理解した上で、入社意欲をアピールすることが求められます。
【製紙業界】Dランク(就職偏差値56以上)
【60】古林紙工 ハビックス 光ビジネスフォーム
【59】阿波製紙 中央紙器工業 東海紙器
【58】岡山製紙 大村紙業 児島段ボール
【57】相互印刷 ダイニック テンタック アイパックスイケタニ 伊藤景パツク産業
【56】柳井紙工 四国パック 武田紙器 北陸紙器 五洋パッケージ 博進紙器製作所 マタイ紙工 桐原容器工業所 タイヨーパッケージ 山陽パッケージシステム カネパッケージ ネクスタラッピイ FUJIDAN
地域基盤の製紙メーカーや、特定の用途(産業資材、包装など)に特化したBtoB企業が中心です。
全国的な知名度は高くなくても、特定の業界や地域で不可欠な役割を担っています。
就職活動の基本対策を徹底し、その企業の製品がどのように社会を支えているかを理解し、堅実に業務に取り組む姿勢を示すことが重要です。
【製紙業界】Eランク(就職偏差値50以上)
【55】三隈工業 インベット 杉浦紙工 パーペル 名古屋モウルド 千代田明和ダンボール 上村紙工 泰清紙器製作所 三和段ボール 小林ダンボール 大洋印刷 太平段ボール工業 信和紙工 東洋段ボール 宮崎紙業
各地域に根差した段ボール・紙器メーカーや、紙加工の専門企業が大部分を占めます。
地元での就職を考える学生や、モノづくりに直接携わりたい学生にとっての選択肢となります。
実際に工場見学を申し込むなど、積極的に企業を理解しようとする姿勢と、その地域で働きたいという熱意が評価されます。
【製紙業界】とは
製紙業界と聞くと、皆さんは何を思い浮かべますか?ノートや新聞紙、トイレットペーパーなど、私たちの生活に密着した製品が多いですよね。
製紙業界は、その名の通り「紙」を製造・販売する産業ですが、近年はその枠を超え、木材資源を基にした多様な素材を生み出す化学産業としての一面も強めています。
伝統的な産業でありながら、環境問題への対応や新素材の開発など、常に変革が求められる奥深い業界です。
ここでは、そんな製紙業界の基本的な仕組みや業務内容について、詳しく見ていきましょう。
基本的な仕組み
製紙業界の基本的な仕組みは、木材チップや古紙などの「原料」を調達し、それを「パルプ」(植物繊維)にし、パルプを抄(す)いて「紙」を製造し、最終的に「製品」として出荷・販売するという流れで成り立っています。
このプロセスは非常に大規模な設備(プラント)を必要とするため、典型的な「装置産業」と言われています。
まず、国内外から調達した木材チップを高温高圧で煮て繊維を取り出すか、古紙を溶かしてインクなどを取り除き、パルプを作ります。
次に、このパルプを水と混ぜ、巨大な抄紙機(しょうしき)という機械で薄く広げ、水分を絞りながら乾燥させて紙のシートを作り上げます。
最後に、用途に応じて表面加工を施したり、断裁したりして、新聞巻取紙、印刷用紙、段ボール原紙、ティッシュペーパーなどの最終製品が完成します。
原料調達から製造、物流までが一貫して行われるのが特徴です。
主な役割と業務内容
製紙業界の役割は、単に紙を作ることだけではありません。
第一の役割は、社会生活や経済活動の基盤となる紙製品(情報伝達用の紙、包装用の紙、衛生用の紙など)を安定的に供給することです。
そして第二に、近年重要性が増しているのが、木材という再生可能資源を活用し、環境負荷の低い製品や新しい素材を開発する役割です。
例えば、プラスチックの代替となる紙製パッケージや、木材由来のバイオマス燃料、セルロースナノファイバー(CNF)といった高機能素材の開発などが挙げられます。
業務内容は職種によって様々で、理系であればプラントの運転管理や保守、品質管理、研究開発(R&D)が中心です。
文系であれば、原料調達、製品の営業(法人向けがメイン)、物流管理、企画、人事総務など、幅広いフィールドで活躍の場があります。
業界の現状と今後の動向
製紙業界は今、大きな転換期を迎えています。
ご存知の通り、デジタル化の進展による「ペーパーレス化」の影響で、新聞用紙や印刷・情報用紙の需要は長期的に減少傾向にあります。
一方で、インターネット通販の拡大に伴い、包装用の段ボール原紙の需要は堅調です。
また、衛生意識の高まりから、トイレットペーパーやティッシュなどの家庭紙も安定した需要があります。
こうした中で、各社は生き残りをかけて事業構造の転換を急いでいます。
従来の「紙」に依存するビジネスモデルから脱却し、木材資源を余すことなく活用する「総合バイオマス企業」への変革を目指しているのです。
具体的には、セルロースナノファイバー(CNF)のような高機能材料の開発や、木質バイオマス発電事業への注力、海外市場の開拓(特にアジア)などが、今後の成長の鍵を握っています。
【製紙業界】特徴
製紙業界は、他の業界とは異なるいくつかのユニークな特徴を持っています。
日常生活に不可欠な製品を供給するという安定性を持つ一方で、大規模な設備投資が必要であったり、グローバルな環境問題と密接に関連していたりと、非常にダイナミックな側面も併せ持っています。
企業研究を進める上では、こうした業界特有の事情を理解しておくことが、入社後のミスマッチを防ぐためにも非常に重要です。
ここでは、製紙業界を理解する上で欠かせない、3つの主要な特徴について解説していきます。
これらの特徴が、ご自身の価値観やキャリアプランと合っているか、ぜひ照らし合わせながら読み進めてみてください。
業界の全体像を掴むことで、志望動機をより深く、具体的に考えるヒントが見つかるはずです。
巨大な設備を要する「装置産業」である
製紙業界の最大の特徴は、典型的な「装置産業」であるという点です。
紙を製造するためには、木材チップからパルプを取り出す巨大な釜や、紙を抄くための超大型の抄紙機など、莫大な初期投資を必要とする大規模なプラントが不可欠です。
これらの設備は24時間365日稼働し続けることが多く、一度稼働を停止すると再稼働に多大なコストと時間がかかります。
そのため、新規参入が非常に難しく、市場は既存の大手企業による寡占状態となっていることが多いです。
この特徴は、働く上でも影響を与えます。
例えば、安定した生産体制の維持が至上命題であり、生産技術職や保全(メンテナンス)職の役割が非常に重要になります。
また、設備投資が経営の根幹を握るため、長期的な視点に立った経営戦略が求められる業界でもあります。
環境問題との関連性が非常に強い
製紙業界は、そのビジネスモデル自体が環境問題と密接に結びついています。
主な原料が木材であるため、持続可能な森林経営や原料調達が企業の社会的責任(CSR)として厳しく問われます。
違法伐採された木材を使用しないよう、FSC認証などの森林認証制度に基づいた原料調達がスタンダードになっています。
また、製造プロセスでは大量の水とエネルギーを消費するため、排水処理技術の高度化や、CO2排出量削減、省エネルギー化への取り組みが常に求められています。
一方で、業界全体として古紙リサイクルのシステムを確立しており、リサイクル率が非常に高いのも特徴です。
近年では、プラスチック代替素材の開発やバイオマス発電など、環境問題の解決に貢献するビジネスを積極的に推進しており、社会貢献性の高い業界とも言えるでしょう。
「紙」以外の分野への多角化が進んでいる
「製紙業界」という名前から、紙だけを作っているイメージが強いかもしれませんが、実際には多くの企業が「紙」の枠を超えた事業多角化を積極的に進めています。
これは、ペーパーレス化による紙需要の減少という構造的な課題に対応するためです。
各社は、長年培ってきた木材や繊維(セルロース)に関する技術を応用し、新しい分野に進出しています。
代表的な例が、鉄の5分の1の軽さで5倍の強度を持つとされる新素材「セルロースナノファイバー(CNF)」です。
これは自動車部品や電子機器、化粧品などへの応用が期待されています。
その他にも、木材由来の化学品(化成品事業)、エネルギー事業(バイオマス発電)、さらには土地開発(不動産事業)など、その事業領域は想像以上に多岐にわたっています。
【製紙業界】向いている人
製紙業界は、安定したインフラ産業としての一面と、新素材開発などイノベーションを追求する一面を併せ持っています。
では、どのようなタイプの学生がこの業界で活躍できるのでしょうか。
業界特有のビジネスモデルや働き方を踏まえると、いくつかの明確な「向いている人」の人物像が浮かび上がってきます。
華やかな変化よりも、着実な積み重ねを好む人や、社会基盤を支える仕事にやりがいを感じる人にとっては、非常にマッチする可能性が高いです。
ここでは、製紙業界で特に求められる3つの素養について解説します。
ご自身の性格や強みと重なる部分があるか、自己分析と照らし合わせながら確認してみてください。
モノづくりのプロセスに強い興味がある人
製紙業界は、良くも悪くも「モノづくり」がビジネスの根幹です。
特に技術系の職種(生産管理、品質管理、研究開発など)を志望する場合は、原料から製品が出来上がるまでのプロセスそのものに強い興味や探究心を持てることが不可欠です。
工場では、巨大な機械が24時間稼働し、日々安定した品質の製品を生み出し続けることが求められます。
そのためには、製造工程の細かな変化に気づき、「なぜこうなるのか」を突き詰め、地道な改善を続ける姿勢が必要です。
文系職種であっても、自社製品がどのような技術で作られているかを理解していなければ、顧客に的確な提案はできません。
巨大なプラントが動く様子にワクワクするような、生粋の「モノづくり好き」にはたまらない環境と言えるでしょう。
安定した環境で長期的にキャリアを築きたい人
製紙業界は装置産業であり、新規参入が難しいという特性上、業界内のプレイヤーが比較的固定されています。
また、紙(特に家庭紙や段ボール)は景気変動の影響を受けにくい生活必需品であるため、業界全体として経営が安定している企業が多いのが特徴です。
そのため、IT業界やベンチャー企業のような目まぐるしいスピード感や、短期的な成果主義を求める人には物足りないかもしれません。
しかし、一つの会社に腰を据え、じっくりと専門性を高めながら長期的なキャリアプランを描きたい人にとっては、非常に魅力的な環境です。
福利厚生が手厚く、ワークライフバランスを重視する社風の企業も多いため、安定志向の学生には強くおすすめできる業界です。
社会貢献や環境問題への意識が高い人
先の「特徴」でも触れた通り、製紙業界は環境問題と切っても切れない関係にあります。
持続可能な森林資源の利用、CO2排出削減、水質保全、リサイクルの推進など、事業活動のあらゆる場面で環境への配慮が求められます。
単に利益を追求するだけでなく、「地球環境の保全に貢献したい」「再生可能資源である木材の可能性を追求したい」といった、社会貢献への強い意志を持つ人に向いています。
また、プラスチックごみ問題の解決策として紙素材が再評価されるなど、ビジネスを通じて環境課題の解決に挑むことができるのも、この業界ならではの醍醐味です。
面接などでも、環境問題に対する自分なりの考えを問われることが多いため、日頃から高い意識を持っておくことが重要です。
【製紙業界】向いていない人
一方で、製紙業界のどのような特徴が、人によっては「合わない」と感じる可能性があるのでしょうか。
安定性や社会貢献性といった魅力がある反面、業界の構造や働き方にはいくつかの「向き・不向き」が存在します。
入社後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためにも、ネガティブに聞こえるかもしれない側面もしっかりと理解しておくことが大切です。
ここでは、製紙業界の特性を踏まえた上で、ミスマッチが起こりやすい可能性のある3つのタイプをご紹介します。
これらに当てはまるからといって絶対に向いていないわけではありませんが、ご自身のキャリアにおいて何を優先したいかを考える上での判断材料にしてください。
勤務地(特に都市部)に強いこだわりがある人
製紙業界を志望する上で、最も理解しておくべき点の一つが「勤務地」です。
紙の製造には、広大な土地と大量のキレイな水が不可欠です。
そのため、巨大な製造拠点である工場は、必然的に地方の臨海部や、水源が豊富な山間部などに立地しているケースがほとんどです。
総合職(特に技術系)として採用された場合、キャリアの大部分をこれらの工場(あるいは研究所)で過ごす可能性が非常に高いです。
もちろん、本社(東京や大阪など)や都市部の支社で営業や企画職として働く道もありますが、初期配属が工場であるケースは多いです。
「絶対に都心で働きたい」「トレンドの最前線で刺激を受けながら生活したい」という志向が強い人にとっては、希望するライフスタイルとのギャップが生まれる可能性があるため注意が必要です。
スピード感のある急激な変化を好む人
製紙業界は、数百年の歴史を持つ伝統的な産業であり、装置産業という特性上、ビジネスモデルや組織体制が比較的安定しています。
これは長期的なキャリアを築く上ではメリットですが、裏を返せば、意思決定のスピードが比較的ゆっくりであったり、年功序列的な風土が色濃く残っていたりする企業も少なくない、ということです。
IT業界やベンチャー企業のように、「昨日決まったことが今日変わる」といった目まぐるしいスピード感の中で、若いうちから裁量権を持って新しいことに次々と挑戦したい、というタイプの人には、少し物足りなさや「堅苦しさ」を感じるかもしれません。
着実な改善や安定運用よりも、劇的なイノベーションや変化を強く求める人には、やや不向きな側面があると言えます。
ルーティンワークや地道な作業が苦手な人
特に工場の技術系職種において顕著ですが、製紙業界の仕事には「安定稼働」を支えるための地道な業務が多く含まれます。
例えば、生産管理であれば、日々の生産計画の調整やトラブル対応、品質管理であれば、膨大なデータのチェックや分析、保全であれば、巨大な設備の定期点検やメンテナンスなどです。
もちろん、その中には高度な専門知識や改善の工夫が求められますが、日々の業務の多くは定型的な「ルーティンワーク」や、コツコツとした地道な作業の積み重ねによって支えられています。
常に新しい企画や派手なプロジェクトに携わりたい、単調な作業はできるだけ避けたい、という思考が強い人は、実際の業務内容とのギャップに悩む可能性があります。
【製紙業界】内定をもらうためのポイント
製紙業界は、安定性や社会貢献性の高さから、就活生に根強い人気があります。
特に大手企業の内定を勝ち取るためには、業界特有の事情を踏まえた上で、周到な準備が欠かせません。
ただ漠然と「紙が好きだから」というだけでは、ペーパーレス化という逆風の中でなぜこの業界を選ぶのか、その熱意を伝えるのは難しいでしょう。
重要なのは、「なぜ製紙業界なのか」そして「なぜその企業なのか」を深く掘り下げることです。
ここでは、製紙業界の内定を掴むために、特に意識して取り組むべき3つのポイントについて、具体的な準備方法とともに解説していきます。
ライバルと差をつけるために、何が必要なのかを一緒に確認していきましょう。
業界理解と企業研究の深掘り(志望動機)
製紙業界の選考で最も重要視されるのが、「志望動機の深さ」です。
前述の通り、業界はペーパーレス化という大きな課題に直面しています。
その中で、「なぜあえて製紙業界を選ぶのか」という問いに、説得力を持って答えられなければなりません。
単に「生活に不可欠だから」という理由だけでは不十分です。
「ペーパーレス化が進む中で、貴社が注力している〇〇という新素材(例:CNF)の可能性に惹かれた」「木材という再生可能資源を活かし、環境問題の解決に貢献したい」など、業界の課題を理解した上で、その企業の未来の戦略に自分ごととして共感している姿勢を示すことが重要です。
そのためには、各社のIR情報(決算資料など)を読み込み、どの分野(家庭紙、段ボール、新素材など)に強みや将来性を感じているのかを明確に言語化できるように準備しましょう。
インターンシップや工場見学への参加
製紙業界は装置産業であり、そのビジネスのスケール感や現場の雰囲気は、実際に「見て」みないと分からない部分が非常に大きいです。
可能であれば、各社が実施するインターンシップ(特に工場での実習が含まれるもの)や、工場見学には積極的に参加しましょう。
巨大な抄紙機が動く迫力や、現場で働く社員の方々の熱意を肌で感じることは、何よりの企業研究になります。
また、選考においても「インターンシップで〇〇の業務を体験し、貴社の〇〇という点に魅力を感じた」と語るエピソードは、志望度の高さを裏付ける強力な武器となります。
特に技術系を志望する学生にとっては、自分の専門性が現場でどう活かせるかを具体的にイメージする絶好の機会ですし、文系学生にとっても、製品が作られる現場を知ることは営業や企画の仕事に必ず役立ちます。
アピールすべき経験と関連資格
製紙業界、特に技術系(研究開発、生産技術)を志望する場合、学生時代の専門性が直接的に評価されるケースが多いです。
化学、化学工学、機械、電気電子系などを専攻している学生は、自身の研究内容が製紙プロセスや新素材開発にどう活かせるかを具体的に説明できるようにしておきましょう。
必須ではありませんが、「危険物取扱者」や「エネルギー管理士」といった資格は、プラントで働く上で役立つため、取得していれば知識のアピールになります。
文系職種の場合は、特定の資格よりも、学生時代の経験が重視されます。
例えば、大規模なプロジェクトを動かす装置産業の特性上、「周囲を巻き込み、粘り強く目標を達成した経験(例:サークルやアルバイトでのリーダー経験)」や、地道な改善活動が求められるため「コツコツと努力を継続した経験」などは高く評価される傾向にあります。
【製紙業界】よくある質問
ここまで製紙業界について詳しく解説してきましたが、業界研究を進める中で、皆さんは様々な疑問を感じているかもしれません。
特に、業界の将来性や働き方については、多くの就活生が気になるところですよね。
安定しているイメージはあるけれど、実際のところはどうなのだろう、と不安に思うこともあるでしょう。
ここでは、就活アドバイザーとして私がよく受ける、製紙業界に関する「よくある質問」をピックアップし、Q&A形式でお答えしていきます。
皆さんの疑問や不安を解消し、自信を持って企業研究や選考に臨むための参考にしてください。
Q1. ペーパーレス化が進んでいますが、将来性はあるのでしょうか?
これは最も多く寄せられる質問ですね。
結論から言うと、事業構造の転換に成功している企業には十分な将来性があると言えます。
確かに、新聞用紙や印刷・情報用紙の需要は減少しています。
しかし、製紙業界の製品はそれだけではありません。
EC市場の拡大に伴う「段ボール原紙」や、衛生意識の高まりによる「家庭紙(ティッシュ・トイレットペーパー)」の需要は非常に堅調です。
さらに重要なのは、多くの大手企業が、「脱・紙」への取り組みを加速させている点です。
木材から取り出せるセルロースを活用した新素材(CNF)の開発や、プラスチック代替となる紙パッケージ、バイオマス発電事業など、木材資源を基盤とした「総合バイオマス企業」へと変貌を遂げようとしています。
どの分野に注力している企業なのかを見極めることが重要です。
Q2. 勤務地はやはり地方(工場)が多いのでしょうか?
はい、その可能性は高いと考えておくべきです。
特に理系総合職(生産技術、保全、研究開発など)の場合は、キャリアのスタート、あるいは大半が工場や研究所となるケースが一般的です。
製紙工場は、広大な土地と大量の水を必要とするため、どうしても地方に立地することが多くなります。
文系総合職(営業、企画、人事など)であっても、研修やキャリアの一部で工場勤務を経験することは珍しくありません。
もちろん、営業職は都市部の支社、企画部門は本社(東京・大阪)勤務がメインになることも多いですが、「勤務地は全国どこでもOK」という姿勢の方が、選考では有利に働く可能性が高いです。
地方での生活や、地域社会に根差した働き方に魅力を感じられるかどうかも、この業界とマッチするかどうかの重要なポイントになります。
Q3. 文系出身でも活躍できるフィールドはありますか?
もちろんです。
製紙業界は巨大な装置産業であり、モノを作って売るまでのプロセスが非常に長いため、文系出身者が活躍するフィールドは多岐にわたります。
まず、製品を国内外の顧客(出版社、印刷会社、加工メーカーなど)に販売する「営業」は文系が中心です。
また、主原料である木材チップや古紙を世界中から調達する「原料調達・購買」も重要な仕事です。
その他、生産計画の立案、物流の管理、新事業の企画、そして会社組織を支える人事、総務、経理など、企業の根幹を担う多くの部門で文系出身の社員が活躍しています。
理系のイメージが強いかもしれませんが、文系理系問わず、多様な人材が協力して初めて成り立つ産業なのです。
まとめ
今回は、製紙業界の就職偏差値から、その特徴、働き方、内定獲得のポイントまでを詳しく解説してきました。
製紙業界は、「安定」と「変革」という二つの側面を併せ持つ、非常に奥深い産業です。
ペーパーレス化という逆風を受けながらも、木材という再生可能資源の可能性を追求し、環境問題の解決にも貢献しようとしています。
もしあなたが、社会の基盤を支えるスケールの大きな仕事に携わりたい、あるいは環境問題にビジネスで取り組みたいと考えるなら、製紙業界は非常にやりがいのある選択肢となるはずです。
ぜひ、この記事を参考に企業研究を深め、自信を持ってチャレンジしてください。