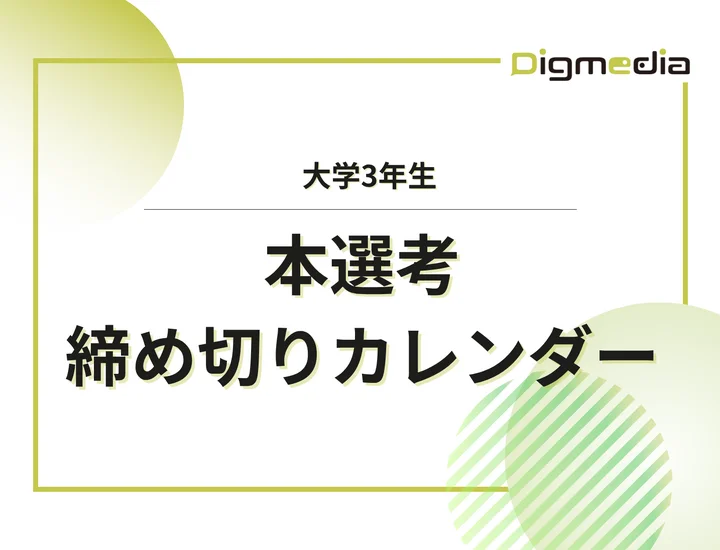HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
【逆質問】すぐ面接が始まる方へ!
逆質問の例を手取り早くまとめましたので、時間がない方はぜひ見てみてくだい!
時間に余裕がある方は、以下の逆質問例を除いた50以上の逆質問をポイントとともに掲載しているのでそちらもぜひ読んでみてください。
・私が入社したら、営業に所属するという認識で合っていますか
・1日の仕事の流れを教えてください
・仕事を通じて、どのようなスキルが磨かれますか
・仕事のやりがいは何ですか
・新卒からマネジメントに上がる人は、早いと何年で上がれますか
・マネジメントに上がった人は、何が評価されて上がったんですか
・5年後、10年後のキャリアとして、営業以外に関わることは可能ですか
→例えば、人事、事業開発、広報など、どのような展望があるのか教えてください
・(人事の)●●さんは、なぜ入社したのですか?魅力に感じていたことを聞かせてください
→AとBが魅力で入社しました
→ありがとうございます。
→Aにおいて、入社前と入社後の違いってありましたか?
・●●さんは将来どのような大人になりたいとお考えですか
・成長できると説明会でありましたが、具体的にどのような人材になれますか?
・●●(営業やエンジニア)をやる上で、覚悟しなければいけないことは何ですか?
【逆質問】逆質問とは?
逆質問とは、面接の終盤で聞かれる質問のことで、「何か質問や聞きたいことはありますか」という言い方をされることが多いです。
就活生側としては、企業に自分が本当にマッチしているのかどうか確認するため、そして最後のアピールの機会として非常に重要です。
ただし、質問の仕方や内容によってはマイナスポイントに繋がることもあるため、相手に良い印象を与えられるよう工夫をする必要があります。
学歴や過去経験などは関係ない!
ガクチカや自己PRなどは、学歴や過去の経験などによって差が生まれてしまうことは少なからずあります。
しかし、逆質問は選考を受ける誰もがしっかりと対策をすればプラスに働く質問ができる貴重な機会の1つです。
したがって、これまでの経験に自信がない人や、これといったアピールポイントがない人は特に力を入れて対策をしましょう。
他の就活生に遅れを取っているかもしれないが、どうしてもその企業に入りたいという強い気持ちを伝えるために、ぜひ時間をかけて対策しましょう。
【逆質問】面接官が逆質問を聞く理由
企業側はなぜ就活生に対して逆質問の時間を設けてくれるのでしょうか。
他の質問にも意味があるように、逆質問にも意図があります。
相手側が何を考えているのか理解しておくことで、質問に対して面接官が本当に聞きたい答えを正しく答えられるようになります。
以下の5点を踏まえた上で逆質問の対策をしましょう。
就活生の志望度を知りたい
逆質問を通じて、企業側は就活生の志望度を知りたいと考えています。
志望度が高ければ、入社前後に限らない長期的な目線での設問をされることが多いです。
なぜならば、志望度が高い企業ほど就活生はしっかりと調査を行い、調べればわかるようなことはすでに知っているからです。
反対に、志望度が高くない就活生は企業研究を行わず、もう考えるための材料がないため、調べればわかるようなことを聞いてしまいます。
いくら優秀な人材でも、志望度が低いと、離職する可能性が高く、向上心を持って取り組まない人材であるとみなし、採用しにくいのです。
準備してきたかを評価
就職後はビジネスマンとして社会に出るため、志望度の高さに関わらず、選考に対して準備をしてくることは当たり前です。
したがって、最低限の準備をしてきたのかを確認されている場合は多いといえます。
企業側も、志望度がどれだけ高い就活生であったとしても、準備ができていなければ仕事に対しても同じような姿勢で臨むと判断し、採用しづらくなってしまいます。
候補者側に話させることでコミュニケーション能力を測る
逆質問では、候補者が自分の関心や疑問を言語化して相手に伝えるスキルが試されます。
特に、質問内容が具体的であり、自社や業務に関連していれば、相手に適切に配慮しつつ話を展開できる能力が評価されます。
また、逆質問は双方向のコミュニケーションを深める場でもあります。
候補者の質問から、話の構成力や情報を引き出す力、さらに自分の考えを的確に伝える力が見られます。
一方的に質問されるだけではなく、質問を通じて自社への理解を深めたいという姿勢を見せることが重要です。
疑問点の解消
面接はそれまでの説明会や面談で出た内容に対する純粋な質疑応答の場でもあります。
説明会や面接などにおいて疑問に思ったことや、公式サイト、パンフレットなどを読んだ際により深く知りたいと思ったことについて質問し、疑問を解消できる場としているのです。
いくら企業側が採用したいと思っていても、就活生側に疑問が多く不安を抱えた状態では、内定を出しても就職してくれる可能性は低いため、あらかじめわからないことは解消してあげたいと考えているのです。
ミスマッチ避けたい
逆質問を通じて、ミスマッチングを避けようと考えている企業も多いです。
なぜならば、就活生側が質問するポイント、つまり着目していることは本人が重視しているポイントを表していることが多いからです。
例えば、福利厚生や働き方を聞いた際は条件を重視して就活をしていると判断します。
特に、モチベーションの高さを重視するベンチャー企業などにおいては、働くことの意欲が低いと判断されることもあります。
このように、企業側が求めている人物と就活生側がなりたい将来像が一致しているかどうかを確認しているのです。
もし一致していない場合、ミスマッチであり長く働いてくれない可能性が高いため、早い段階でマッチしているか確認したいと思っているのです。
【逆質問】確認したいポイント
続いて、逆質問の内容を考える上で確認しておきたいポイントについていくつか紹介します。
以下のポイントを踏まえた上で、あらかじめある程度逆質問について考えておくことで、本番でも緊張せずスムーズに聞きたいことを聞けます。
企業の公式HP
企業の公式サイトは必ずチェックしておきましょう。
目指している企業の公式サイトは、企業そのものが言語化されているものです。
志望企業や企業が属している業界についても詳しく書かれているため、必ず目を通すようにしましょう。
特に印象に残った部分や疑問点はメモで残しておくことをおすすめします。
採用ページなどでは、求める人物像や社長からのコメントなどが記載されていることが多いため、しっかりと確認し、どのような人物像が求められているのかについては必ず覚えておきましょう。
MVV
「MVV」とは、ミッション(Mission)、ビジョン(Vision)、バリュー(Value)の略語です。
まず、ミッションとはその組織が存在する意義や目的について話しています。
これについて理解できれば、各々がその実現に向けて自分は何を目標とすれば良いか考えやすくなり、仕事に注力できます。
続いてビジョンは、目指す理想の姿です。
企業としての使命を達成するためにはどのような組織でなければならないかについて示している部分です。
最後にバリューは、組織の価値観や価値の基準などを示しています。
経営理念や企業理念、行動指針などと混同されがちですが、経営理念は経営をするにあたっての方針や集団のことであり、企業理念はその会社の存在意義自体を表しているものです。
そして行動指針は、経営理念や企業理念を達成するための行動原則をまとめたものであるため、それぞれ異なります。
面接では、「弊社の企業理念についてどう思っているか教えてください」などと聞かれる可能性もあるため、それぞれ区別して覚えておきましょう。
採用ページ
採用ページとは、企業の公式サイトの中に組み込まれているページで、募集要項や給料、福利厚生などを紹介する、新卒や中途を含めた就活生向けに企業側が制作しているページです。
企業側が就活生に確認してほしいポイントを詰め込んでいるため、就活に必要な情報を素早く得ることができます。
社員の声などは、すでに働いている社員がなぜその会社に入ったのか、過去の経験などについて記載されているため、志望動機作成やガクチカ作成、自己PR作成などに活用できます。
逆質問だけでなく様々なものに活用できるため、ぜひ確認しておきましょう。
社員のSNS
もし目指している企業の社員がSNSを利用しているならば、ぜひ確認しておきましょう。
学生にはFacebookはあまり馴染みがないかもしれませんが、社長や社員がよく会社についてやビジネスに関する内容を発信しています。
逆質問の際に、この発信や投稿から質問を考えると企業のことをよく調べていると高評価に繋がる可能性が高いです。
また、近年ではInstagramなど他のSNSで企業情報を発信している企業もあるため、気になるところはフォローする、少なくとも定期的に投稿を見るようにしましょう。
まれにインスタライブなどを活用して質疑応答を行っている企業もあります。
【逆質問】NGな逆質問の回答
逆質問は、面接で志望意欲やコミュニケーション能力を示す重要な場面です。
しかし、不適切な内容や準備不足を感じさせる質問は、面接官に悪い印象を与える可能性があります。
以下にNGな逆質問の例を挙げ、それぞれの理由を解説します。
逆質問がない
面接で逆質問がない場合、面接官に「志望意欲が低い」と見なされる可能性があります。
また、事前準備が不足している印象を与え、企業への理解が浅いと思われることもあります。
逆質問は、企業への関心を示すだけでなく、自分が企業で働くイメージを深めるための大切な機会です。
事前に企業の情報を調べ、自分の志望理由や強みと関連付けた質問を用意しておくと良いでしょう。
たとえば、「入社後の研修制度で大切にしている点は何ですか?」など、企業独自の取り組みに触れる質問が効果的です。
社風、企業理念はどのようなものですか?
「社風や企業理念はどのようなものですか?」という質問は、企業のホームページや採用パンフレットで簡単に確認できる情報です。
そのため、準備不足と見なされる可能性が高く、面接官に悪い印象を与えかねません。
逆質問では、自分が企業について事前に調べたうえで、さらに深掘りしたい点を聞く姿勢が求められます。
たとえば、「御社の〇〇という理念を現場でどのように実現されていますか?」のように具体性を持たせると、企業への理解度や関心の高さが伝わります。
福利厚生はどのようになっていますか?
福利厚生に関する質問は重要ではありますが、面接の場で尋ねる内容としては適切ではないことがあります。
特に、福利厚生だけに関心を持っている印象を与えると、企業での働き方より条件面に重きを置いていると見られることがあります。
福利厚生については、説明会や採用案内で確認できる場合が多く、面接ではより具体的な業務や成長に関連する質問が望ましいです。
たとえば、「働く環境を向上させるために取り組んでいることを教えていただけますか?」など、仕事への意欲が伝わる質問にすることで、印象が大きく変わります。
プライベートの質問
逆質問の内容が思い浮かばず、面接官に対してプライベートな質問をするのは避けるべきです。
たとえば、「休日は何をされていますか?」や「趣味は何ですか?」などの質問は、仕事に関係がないうえに失礼と取られる可能性があります。
面接官はプロとしての時間を割いているため、面接の場にふさわしい質問を用意することが求められます。
質問を考える際は、自分が働く際に知りたい情報や企業について深く理解できる内容を優先しましょう。
企業の価値観や業務の進め方、社員の成長環境など、職場に直結した質問が好まれます。
【逆質問】フェーズごとの対策
逆質問は比較的最終面接に近いフェーズで聞かれることが多いですが、一次面接や二次面接などにおいても実施されることがあります。
面接はフェーズごとに面接官が変わるだけでなく、面接の目的も変わってくることがあるため、それぞれ対策を覚えておきましょう。
一次面接
一次面接においては、基本的なスキルや志望動機を確認することが主な目的です。
一般的には大量の応募者の中からふるいにかけることを目的とされています。
面接官は一次面接において、一般的には人事担当者や採用担当者が面接を行います。
基本的な選考基準に基づいて候補者を評価し、次の選考に進めるかどうかを決定します。
したがって、一次面接においては最低限の企業研究を行っていることが伝わる逆質問や、モチベーションの高さが伝わる逆質問をしましょう。
二次面接
二次面接は、より詳細な情報やスキルを評価するために行われるため、一次面接よりも色々な点に着目して行われます。
企業の文化やチームとのマッチ度や具体的なプロジェクトにおける貢献度などが重視されます。
面接官は一般的には部門のマネージャーやチームリーダー、場合によっては上級管理職など一次面接を担当した人よりも、いわゆる重役と呼ばれる人が担当することが多いです。
専門知識や経験、リーダーシップ能力などについて評価されることが多いため、自分の能力をアピールし、それがどのような場面で活用できるかなどを聞くと良いでしょう。
最終面接
最終面接は文字通り、就活生を採用するかしないかを決める最終的な選考です。
企業と就活生の両方が最終的な決定を行うため、内定を得ることはもちろん、逆質問を通じてその企業が本当に自分に向いているのかを確認することも大切です。
メインの話題は入社への覚悟などであり、この段階ではもはや能力などについて聞かれることはあまりありません。
担当者も通常は役員や経営陣が担当し、企業のビジョンや戦略に関する視点から就活生を評価し、組織全体のマッチングで成長に対する貢献度を判断します。
したがって、自己分析を行っていることはもちろん、企業分析を徹底的に行っていることがよく伝わるような逆質問を行いましょう。
【逆質問】就活のプロに聞いた逆質問例
年間1万人上の就活生の面接やESなどのサポートをしているキャリアアドバイザーや、現人事、元人事、企業側の採用構築を担っている採用コンサルトに「逆質問」に関するアンケートを行った結果50以上の逆質問の例がアドバイス・ポイント付きで集まりました。
分析してみると約7種類の逆質問があったので、ご紹介いたします。
NG例文の回答もあったので、面接を控えている就活生の皆さんは必見です!
面接官本人にしか答えられない逆質問
回答の中で最も多かった種類の逆質問は「面接官本人にしか答えられない逆質問」です。
面接では大前提、面接官がどんな人かを知ることで、志望先の企業で実際に働いている人の像を知ることができるため就活生側にとっても有益な情報を教えてもらえます。
また、自分のことに興味を持ってくれる人は好印象が残るためおすすめです。
18種類の逆質問をアドバイスとともに掲載いたします!
※大前提事前に面接官が誰なのかを知れる方が良い。
1. 〇〇さん(面接官)が御社を選んだ理由はありますか?
2. 〇〇さん(面接官)の入社の(1番の)決め手は何ですか?
3. 〇〇さん(面接官)の目指しているビジョンとそこに向かって今何をしているのか教えてください。
4. 〇〇さん(面接官)は御社で働いていて、どのような時にやりがいを感じますか?
5. 〇〇さん(面接官)の1番のやりがいはなんですか?
6. 〇〇さん(面接官)が現場時代に意識してたことは?
7. 〇〇さん(面接官)がここまでキャリアを積んできた中で、特に意識していたことと行動はどんなことになりますか?
8. 自分は将来〇〇さん(面接官)のように役職につけるような人材になっていきたいと思っているのですが、〇〇さんはどのようなことを意識してお仕事をされていますか?
9. 1年目2年目これをやっておけばよかったということはありますか?
10. 〇〇さん(面接官)が入社後に感じた御社の強みはございますか?
11. 〇〇さん(面接官)が御社に入って成長を感じたタイミングや自身に変化があったタイミングがあれば教えてください。
12. 〇〇さん(面接官)が御社で働く中で変化した価値観を教えてください。
13. 〇〇さん(面接官)が入社して最初にぶつかった壁と、それをどう乗り越えたのか教えてください。
14. 〇〇さん(面接官)が1番大変だったことはなんですか?
15. 部下が失敗したときにどう声かけしますか?
16. 社員の方にしかわからない、会社の魅力はなんですか?
17. 最終選考の際に今後の会社の展望について聞く
18. 社風ってどんな感じですか?
・次回選考の志望動機で使える
・自分の入社理由とマッチしている点に気づける
・自分のこと聞かれて嬉しくない人いない
・〇〇さんと名前を覚えておくのポイント
・目指す方向性が一緒なのかを確認できる
・成長意欲や志望度をアピール
→現状で満足していないことが伝えられる
・役員の方が何をしてきたかを知れる
→自分がそこの役職に就くまでの最短ルートが分かる
・他の企業さんとの比較ができる
・同じ会社で複数人の方に聞くことで会社の雰囲気を感じられる
・説明会ではいいところばかり言うものの、具体的な仕事内容の大変さがわかる
→また乗り越え方を聞くことで、面接対策にもなる
入社後のキャリアアップの逆質問
次に多かった回答の種類は「入社後のキャリアアップの逆質問」です。
「面接官本人にしか答えられない逆質問」と比べて、情報収集できるかつ、自分をアピールできるため、志望度の高い企業での面接では絶対に聞いた方がいい、という声が多かったです。
14種類の逆質問をアドバイスとともに掲載いたします!
1. どのような人がトップを取っていて、その人はどんなキャリアステップを歩んでいるのでしょうか?
2. 御社で圧倒的に成長されてる方はどのような方なのかお伺いしたいです。
3. どのような人が活躍していますでしょうか?
4. どういう人がキャリアアップしてますか?
5. 1番活躍してる方のキャリアアップの例を教えていただきたいです。
6. 現状新卒で成果を出している人のキャリアの積み方と特徴を教えて下さい。
7. 最年少でキャリアアップした例を聞く
8. 御社でキャリアアップしている人はどのような特徴がございますか?
9. 御社で活躍されている方に共通点はございますでしょうか?
10. 御社の新卒で1番活躍している人はどんな人で周りとどんな差がありますか?
11. 御社で最年少で管理職に就かれた方は何歳でしょうか?またその方は入社後どのような活躍をされて今に至ったか詳しくお伺いしたいです。
12. 私は入社してから同期で1番を取りたいと思っています。
13. 現状で新卒で1番の成績を残されている方はどんな方で、何を注力されていますか?
14. 入社後◯年でこういう姿になっていたいがそれは実現可能な環境かどうか。
・成長意欲×入社意欲が伝わる
・御社に貢献したいという思いが届く
・会社にどんな人がいるのかがわかる
・次の面接で使える
・自分の働き方のイメージができる
・どのようにキャリアが積めるのかわかる
・2次選考以降の回答例になる
・就労意欲のアピール
・ミスマッチの確認
・会社に寄せた話ができるようになる
・ただ活躍されている人を聞いているだけではなく、同期で1番になりたいという意欲を見せながら活躍している方の特徴を聞ける
・自己PRに繋がる
入社前の行動の逆質問
「入社前に取る資格あったりするのかな」
「インターンとか必須かな」
「入社前のこと聞いたらやる気ない人だと思われそう」
などと、不安になっている就活生は多いですよね。
以下では、質問をしっかりしながらも志望度の高さもアピールできる逆質問7つを紹介いたします!
1. 入社までにインターンはできますか?
2. 大学生のうちにできることはできますか。
3. 御社で活躍する為にやっておくべき事はありますでしょうか?
4. 自分は未経験スタートなのですが、入社の段階で周りの未経験の同期には差をつけたいし、経験者と肩を並べた状態で入社したいです。
5. 入社までにやったら差をつけられることはありますか?
6. 読んでおいた方がいい本などありますか?
7. 御社に入社するにあたって事前に勉強しておくべきことはございますでしょうか?
・やる気をアピール
・志望度が高いと思わせる
・入社への意欲が伝わる成長意欲
・会社が求める人材の理想像がわかる
成長意欲増し増しの逆質問
ベンチャー企業や大手の中でも成長志向の強い企業では以下のような逆質問が効果的です!
残業や休日出勤の現実を知りたい時もこれらの質問が有効です。
1. 残業はできますか?
2. 休日出勤はできますか?
3. 僕、早く成長したくて、、、照
・労働意欲を見せられる
→あるか?ではなくできるか?と聞くのがポイント
→働きたい貢献したいということが伝わる労働意欲を見せられる
企業研究からの逆質問
企業研究からの逆質問も、アンケートでは多かったです。
企業のHPやSNS、インタビュー記事などからの質問は、人事や面接官に「うちの会社をよく調べてくれているな」「時間を使ってくれているな」という好印象につながるため、有効です!
1. 社長インタビューなどの記事を見て質問
2. 説明会で長く説明していた部分をより深掘る質問
3. 採用ページの〇〇さんもおっしゃってたように、「〇〇」という考え方、文化にとても共感したのですが、実際それを体現するための制度だったり、何か取り組んでることはありますか?
4. 御社のHP、wantedlyを見て〇〇のようなことが書いてあったのですが、、、、、、、、
5. 「こんな記事読んでみたんですけど!・・・」「役員の誰々のフェイスブック・wantedly・記事を見ての質問になるんですが・・・」という枕詞を使う
6. 御社の魅力(強み)として〇〇ができることだとお聞きしたのですが、実際に魅力・強みを体現したエピソードを教えてください。
7. 受ける企業様が他者と差別化を測っている点をHPや説明会で〜と解釈したのですが、〜については〜でしょうか?
・事前準備をしていることをアピール
・御社に興味持って時間使ってますアピール
・企業様が一番推しているポイントに興味をもち、さらに詳しく知りたいのだという印象を与えられる
・会社のことめっちゃ調べてくれてるな、と思わせる
・この子ってめっちゃうちのこと知ろうとしてくれてるじゃん!と思わせる
・人事に聞けばわかるような質問ではなくなる
・入社後のイメージを沸かせるため
・抽象的にではなく、具体的に事業や商材について理解した上での質問をする
入社1年目の逆質問
入社1年目の逆質問は、自分自身がその会社で働いた時のイメージが湧くため、ミスマッチを防ぐことができます。
また、入社後のことを質問することで、採用側には「うちで絵働く未来を考えてくれている」という好印象を残すこともできます。
1. 1年目の具体的な仕事内容を教えてください。
2. 1スケジュールを教えてください。
3. 新卒1年目ではどんな仕事を任せてもらえるのかを知りたいです。
4. 入社してから取り組んだ業務を教えてください。
働くイメージができる
入社後の働き方の理解ができる
1年目から成長意欲をもって働きたいという気持ちが伝わる
自分が経験できる事が知れるから意向が上がる
面接自体への逆質問
面接自体への逆質問は「向上心」をアピールすることができます。
注意点としては、集団面接には向いていません。
他の就活生の面接の時間も使って、自分の回答に関するフィードバックを求めることは「自分勝手」なイメージがついてしまうので、個人面接、かつ時間に余裕がある面接の逆質問で有効です。
1. 〇〇さんから見て僕の印象ぶっちゃけどうですか?改善したほうがいい点はどんな点になりますか?
2. この面接での自分自身の印象や課題点ございますでしょうか?
・課題点を知って改善に取り組む意欲をアピール
【逆質問】この記事のまとめ
今回は逆質問において良い印象を残す方法について、逆質問の定義から面接官が逆質問を聞く理由、どのようなポイントを重視して確認されているのかなどについて紹介しました。
逆質問はあなたが企業について知りたいことを聞けるだけでなく、最後のアピールのチャンスとして非常に重要なものです。
したがって、「質問はないです」などモチベーションが低く感じられるような回答をするのではなく、企業研究をしっかりと行っており、絶対にその企業に入りたいと考えていることが伝わるような質問を行いましょう。
あなたが当落線上にいる場合、逆質問のクオリティがあなたの内定を左右する可能性もあります。
【おまけ】
面接での頻出質問である「尊敬する人」について徹底的に対策したい方はこちら!