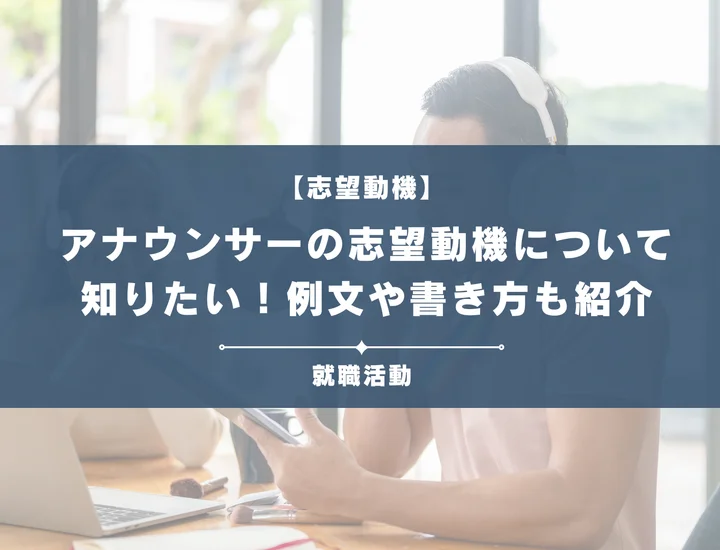HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
- SE(システムエンジニア)の仕事内容
- SEに向いている人の特徴y
- 志望動機を書くポイント
- SEの志望動機の例文
- SE(システムエンジニア)を目指している人
- 選考を通過する志望動機を作成したい人
- 実際に志望動機を作成してみたが不安に思っている人
- 完成度の高い志望動機を作成したい人
SE(システムエンジニア)職に限らず、職種を絞っている人全員が志望動機に一度は悩まされることでしょう。
今回はその中でも人気職種の1つSE職にフォーカスしました。
まずはSEとは何かを理解し、本当に自分が向いているのか考えてみましょう。
自信をもって向いていると言える人はこのまま記事に進んでください。
読み終わるころには立派な志望動機が出来ているはずです。
目次[目次を全て表示する]
はじめに
SE(システムエンジニア)の仕事に興味を持っている人にとって、志望動機の作成は、「どうやって書いたら良いかわからない」と、悩みのタネになるのではないでしょうか。
良い志望動機を作成するには、志望動機に必要な情報を収集することと志望動機の書き方について把握することが大切です。
ここでは、SEの仕事についての情報から、志望動機の作成時に避けたほうが良いNGワード、さらに志望動機の書き方について、例文を交えながらご紹介します。
志望動機を書く際の参考にしてください。
【新卒|SEの志望動機】 SEってどんな仕事?
SE(システムエンジニア)の主な仕事は、ソフトウェアの開発で、プロジェクトの計画からソフトウェアの設計まで、顧客の要望に応えたものを作ることです。
ソフトウェアの開発には、ものづくりに関する知識やスキルのほか、パソコン操作やチームの管理や作業の効率化といったスキルも不可欠になります。
SEの業務について再確認しよう
SEとは、システムエンジニアの略になります。
SE(システムエンジニア)はIT業界の中で最も人気のある職種になっていて、クライアントのニーズに応じてシステムの企画から設計、開発、運用、保守までを一貫して行います。
業務としては、まず始めにクライアントとのミーティングや打ち合わせを行って、クライアントが求めていることを把握します。
そして、そのニーズに対して最適なシステムを選別、考案し、その設計をプログラミングにて行います。
そのシステムを作っただけでは業務は終わらず、SEは、作ったシステムをどう運用していくのか、実際に運用されてから問題が起こっていないか、といったチェックまで幅広くなっています。
SEはIT業界の中でも、システム開発の全ての行程に関わっているため、その分野に関して幅広い知識や技術、経験が必要になります。
また、ニーズを聞き出す能力が求められるため、ビジネスコミュニケーション能力も必要となります。
SEは、IT業界の根幹を支える重要な業種であることがわかりますね。
IT業界の仕事
SE(システムエンジニア)はIT業界の仕事の一種ですが、IT業界にはSEのほかにも、PM(プロジェクトマネージャー)やPG(プログラマー)などがあり、違いがわからないという人も少なくありません。
PMは、プロジェクト全体を管理する職業で、ソフトウェア開発の分野では、顧客とどのようなソフトウェアにするか打ち合わせをして、予算や納期などの決定を担当します(案件定義)。
さらにソフトウェアの開発チームをまとめて、完成まで責任を持つのがPMです。
PMはSEをマネジメントしますので、この点で2つの業務は異なります。
SEは案件定義から参加して、顧客が希望するシステムについて理解します。
それをもとにソフトウェアの基本設定を行い、さらにプログラマーがプログラミングしやすいように、詳細設計を立てていくのです。
一方PGは、SEが作成したソフトウェアの設計書に沿ってプログラミングを担当します。
PGは、設計書の意図を正確に解釈して、コーディングをしたり、単体試験を実施したりするスキルが求められるのです。
ITシステムは、案件定義から始まりプログラミング、そして単体試験を経て、システムの保守運用という一連の流れで成り立っています。
この流れの中でPG、SE、PMは、それぞれの業務を担当する場合がほとんどです。
ソフトウェアの開発はチームで進めるプロジェクトであることがわかります。
PGとは違う?プログラマーよりも上流、設計などの業務
PG(プログラマー)は、設計書に従ってソフトウェアを製造するのが主な仕事です。
SE(システムエンジニア)がソフトウェアの設計者だとすると、PGはソフトウェアの製造者になります。
SEというと、ソフトウェアを製造することが仕事というイメージがあるかもしれませんが、実際に製造に関わっているのは、プログラミング技術を身につけている、プログラマーです。
SEは設計などの業務をこなすため、プログラマーよりも上流に位置すると言われています。
SEは未経験でも就職できる?
SE(システムエンジニア)は文系の、全く未経験の学生でも就職を狙えるのか?という点は、多くの方が気になっているかと思います。
結論からいうと、文系未経験でも、新卒で入社することが十分可能です。
むしろ近年、SEは人手不足が深刻化しており、文系未経験の学生を採用して、十分な研修制度を導入し、優秀な自社エンジニアに育てようという動きが広まりつつあります。
むしろ、経験がなく自社で育てたほうが長く活躍してもらえる、ということで文系未経験に絞って採用をしている企業も、極端な例ですが確認されています。
未経験だからといってあきらめる必要は全くもって無いと言えるでしょう。
SE(システムエンジニア)は、ソフトウェアの開発を担当する職種です。
IT業界には様々な職種がありますが、このSEが最も人気な業種になっています。
エンジニア、という名前がついていますが、その役割は製造だけではなく、その設計から運用保守まで幅広くかかわることがこの業種の特徴になっています。
また近年では文系未経験の学生も積極的に採用する動きが出てきており、人手不足となっている点も特徴と言えます。
【新卒|SEの志望動機】IT業界の概要
初めにSEを目指すにあたって、IT業界を細かく分類するとどのような業界が含まれるのかを確認していきます。
そしてIT業界の現状を踏まえられたら、業界が抱える課題と将来性も理解していきましょう。
IT業界とは
IT業界は日々の生活と密接に結びつき、多岐に渡る分野から成り立つ巨大な業界です。
そのため理解を容易にするため、大きく5つに分類して特徴を解説していきます。
その5つとは、ソフトウェア業界とハードウェア業界、情報処理サービス(SI)業界、インターネット・Web業界、通信インフラ業界です。
それぞれをもう少し深掘りしてみましょう。
ソフトウェア業界は、PCやスマートフォン、タブレットなどで動作するソフトウェアの開発と販売を手がけています。
ハードウェア業界は、PCやモニター、通信機器などの電子機器の開発と販売を行っています。
SI業界は、企業向けのシステム開発案件の受注を行います。
クライアントのニーズに応じて、システムの要件定義やハードウェアの選定から保守点検までを担っています。
インターネット・Web業界は、企業ホームページの作成やECサイトの構築を行っています。
通信インフラ業界は、IT業界の基盤とも言える電話や光ファイバ、Wi-Fiなどの通信回線の提供を行っています。
現代の社会的なインフラを担う重要な役割があります。
分類された業界をさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
https://digmee.jp/article/310651
SEとしての募集のある業界とは
システムエンジニアは、アプリケーションエンジニアや組み込みエンジニア、インフラエンジニアなど専門分野により様々な呼ばれ方をします。
SEの募集が多くあるのは、ソフトウェア業界とハードウェア業界、情報処理サービス(SI)業界、通信インフラ業界です。
ソフトウェア業界にはアプリケーションエンジニアが、ハードウェア業界には組み込みエンジニアが、SI業界にはインフラエンジニアやセキュリティエンジニアが、通信インフラ業界にはネットワークエンジニアがそれぞれ主に求められています。
ただ、企業や参画するプロジェクトにより異なることもあります。
SEについて詳しく知りたい人は、こちらの記事も参考にしてみてください。
https://digmee.jp/article/310579
https://digmee.jp/article/310715
IT業界の現状
IT業界は、これからの社会や働き方やコミュニケーションスタイルの進化において、極めて重要な役割を果たしていきます。
IT業界はICT(情報通信技術)市場に分類され、総務省の令和5年度「情報通信に関する現状報告」によると、情報通信産業の国内総生産は52.7兆円で全産業の9.7%を占めています。
IT業界では5Gや生成AI、ブロックチェーンなど新たな技術が生み出され、社会的・経済的な成長期待が寄せられています。
これらの新技術をサポートする通信インフラの重要性も高まっています。
そのため、政府の後押しも受けて、光ファイバや5Gなど通信インフラの整備が進められています。
また、次世代情報通信インフラBeyond 5G(6G)の実現に向けて、産官学の連携による国際標準化の取り組みも行われています。
情報通信ネットワークの安全性や信頼性の確保が重要で、サイバーセキュリティ人材の育成に注目されています。
総務省,令和5年度「情報通信に関する現状報告」
出典:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/summary/summary01.pdf
IT業界の課題
近年の就活では売り手市場が続き、急速拡大したIT業界でもITスキルを持った人材が不足していることが大きな課題です。
また、IT人材不足も1つの要因である長時間労働も課題となっています。
IT人材不足
少子高齢化による労働人口の減少やIT需要の高まりから、IT人材の不足が危ぶまれています。
2030年にはその人材不足が、約80万人に拡大すると見込まれています。
その対策として、幼少期からのプログラミング学習が取り入れられたり、小中学校での義務教育化、高等学校での必修化が行われています。
企業では、オフショア開発の推進やAIの活用などが進められています。
他にも、新卒の採用では理系や文系など出身学部にかかわらず採用し、入社後にIT人材として育成に取り組む企業も多く見られます。
さらに、社員に対しIT技術の取得を促すリスキリングの機会を提供し既存人材を最大限活用するための試みも広がっています。
経済産業省,2017,「IT分野について」
出典:https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/daiyoji_sangyo_skill/pdf/001_06_00.pdf
長時間労働
長時間労働が問題視され、背景にはIT人材不足と多重下請け構造があります。
IT業界では、多重下請け構造での下請けを担う人材の労働環境悪化が課題となっています。
全てを自社開発できる企業は少なく、得意分野に特化した下請企業に分配することで成り立っています。
これは、元請企業がクライアントと契約したプロジェクトの納期と金額を、みんなで分け合うということです。
そのため、下請企業は制約の多い状況での業務を強いられることが多くなります。
また、大手が受注したプロジェクトが中小企業に引き継がれる過程で、収益性が低くなる傾向があります。
そのため、個々のエンジニアが受け取れる給与額の低下も起きています。
IT業界の将来性
IT業界の未来は明るく、今後も成長を続けるでしょう。
新しい技術が常日頃生み出され、それが既存の業界やビジネスと結びつき新しいビジネスチャンスを創出していくと考えられるからです。
例えば、AIによる業務効率化やIoTを利用したスマート農業や自動運転などです。
AIやIoT、ブロックチェーンなどの新技術が、ビジネスの現場で実用化されるスピードが早まっています。
また、リモートワークの普及が進むことでクラウドサービスも広がりを見せ、これにより職場のDX化がさらに加速しています。
これに伴い、5Gや光通信技術の構築とサイバーセキュリティ、ビックデータの活用など関連技術の需要も増加しています。
IT業界のトレンド
AIやIoT、RPA、クラウド、セキュリティはIT業界を牽引し、未来の革新を生み出す主要なトレンドです。
これらのトレンドがどのように利用されているか理解することは、SEを目指す就活生には不可欠です。
AI
AIとは「人工的に作られた知能」を意味し、人間の知的な能力を模倣してコンピューターが自律的に問題を解決する技術です。
これには、コンピュータが様々なデータを通じてタスクの実行方法や複雑な問題解決を学ぶ手法として、機械学習やディープラーニングなどが含まれます。
AI技術は、画像認識や自然言語処理、予測分析など多岐にわたる分野で応用されています。
身近なものでは、Webサイトのチャットボットや自動運転、スマート家電などに活用されています。
しかしながら、コンピューターが自律的に問題を解決する過程で、倫理的な問題や情報の偏り・バイアス、データセキュリティなどの課題も抱えています。
IoT
IoTとは「Internet of Things(モノのインターネット)」の略で、家電など様々な物理デバイスをインターネットに接続してデータの収集・共有を可能にするシステムを指します。
この技術はスマートホームやウェアラブルデバイス、産業IoTなど多岐にわたる分野で利用されています。
IoTの普及によりデータに基づく素早い意思決定やオペレーションの効率化など、私たちの生活がより便利になるメリットがもたらされています。
特に注目を集めている分野としては、工業IoTがあります。
工場内の機械がネットワークに接続されることで、生産データをリアルタイムで共有・分析し、生産効率の向上をさせています。
RPA
RPAとは「Robotic Process Automation(ロボットによるプロセス自動化)」の略で、ソフトウェアロボットを活用して単純なルーティン作業を自動化する技術のことを指します。
具体的には、入力作業やデータ整理、システム間でのデータ移動などの事務的な業務プロセスを自動化します。
これにより、事務的な定型業務を対象にコスト削減や効率化、エラーの低減などのメリットをもたらします。
さらにAIと組み合わせたエンタープライズRPA(EPA)と呼ばれる方法は、非定型業務も自動化の対象に取り入れる動きが進んでいます。
これにより、多くの企業の人手不足の解消や業務の効率化に役立てられています。
クラウド
クラウドとは、インターネット上でデータの保存や処理などを行う技術です。
これまでのオンプレミス(自社で物理サーバーを持っている状態)とは対照的な方法です。
クラウドのメリットは、サービス内容やデータの量などに応じた使用料を支払うだけなので、初期費用やトータルコストが下がる点にあります。
また、クラウドには企業の需要に応じて、拡張したり縮小したりできる柔軟性を持ったサービス提供が可能です。
多くの企業がクラウドへと移行するトレンドは今後も拡大が見込まれ、クラウドの需要は増す一方です。
クラウドの技術は今後も進化を続け、新しいビジネスモデルやサービスを生み出していくことが予想されます。
セキュリティ
IT技術の急速な進展は、同時にセキュリティリスクも増加させています。
セキュリティは、企業のシステムやネットワーク、データを悪意のある攻撃や不正アクセスから保護するための技術です。
特に、ランサムウェアやフィッシングなどの手口が注目されています。
セキュリティを高めることは、企業のデータ保護とビジネス継続性の確保、顧客の信頼の保持などにメリットがあります。
その一方で、セキュリティ知識のある人材の不足や新しい脅威の出現などの課題にも直面しています。
セキュリティを軽視すると、企業の信頼性を失墜させる可能性があります。
そのため、サイバー攻撃から守るセキュリティ部署を設置する企業も増えています。
【新卒|SEの志望動機】 SEに向いている
通常SE(システムエンジニア)を目指すなら、はじめにPG(プログラマー)に必要なスキルや知識を取得し、PGとして実績を積んでからSEを目指すという流れになります。
しかし、 すべてのPGがSEに向いているとは限らず、プログラミング作業が好きな人は、PGのままでいるほうが無難という場合もあります。
どんな人がSEに向いているのでしょうか。
性格面や過去の経験から、適性について説明します。
性格面
プログラミングだけでなく、ソフトウェアの開発全体に興味があるという人は、SE(システムエンジニア)に向いています。
クライアントと関わることやプログラマーがプログラミングしやすいように設計書を作成するなど、 裏方の役割が多くなりますが、知的探究心を発揮して、顧客が求めるシステムの開発に情熱を注げる人は、SEが適職と言えるでしょう。
システム開発には、設計書を作成するスキルだけでなく、幅広い知識が必要になります。
特定の分野に対する理解を深めようとする勤勉さも必要になります。
過去の経験
自分がSE(システムエンジニア)に向いているかどうかは、過去の経験を振り返ると判断できることがあります。
たとえば学校でイベントを開催する際、イベントの企画や準備など、縁の下の力持ちを担当することが多かったり、そうした仕事にやりがいを見出したりした経験はないでしょうか。
興味のあることについて、理解するまでコツコツと継続して学び続け、身につけたという経験など、 1つのことに向かって地道に続けられるというのも、SE向きの素質と言えます。
SE(システムエンジニア)に向いていると言われる人物像は、知的探求心があり、また1つの目標に向かってコツコツとした作業を問題なくこなせる人物だといえます。
また、幅広い知識とスキルが求められるため、勤勉さもかなり必要になってくる職種になります。
【新卒SEの志望動機】企業が志望動機を問う理由
そもそもなぜ企業は志望動機を聞いてくるのかという点を押さえることが非常に大切です。
志望動機から企業が何を読み取ろうとしているのか理解して準備することで、効果的な志望動機を作成することが可能となります。
志望者の意欲を見るため
企業が志望動機を尋ねる主な理由は、応募者の意欲や熱意を見極めるためです。
志望動機を通じて、その人がどれだけ仕事に対して情熱を持ち、自社で働きたいと思っているのかを評価します。
企業は、単に技術や知識だけでなく、成長意欲が高く、積極的に仕事に取り組むことができる人材を求めています。
そのため、志望動機は応募者が将来企業にどのように貢献できるか、またそのためにどれだけ熱心に取り組む意志があるかを見るための重要な指標となります。
志望者と自社とのマッチ度を測るため
企業が志望動機を問う主な目的の一つは、応募者と自社とのマッチ度を測定するためです。
志望動機を通じて、応募者のビジョンが企業の目指す方向性や価値観とどれだけ一致しているかを評価します。
企業は、自社の文化や理念に合う人材を探しており、応募者が企業のミッションに共感し、その実現に積極的に貢献できるかどうかを見極めたいと考えています。
これは双方にとって最適な関係を築くために非常に重要であり、応募者が将来的に企業での活躍を期待できるかどうかを判断するための基準となります。
新卒SEの志望動機】志望動機を作成する前に
ここからは志望動機を作成するまえに準備しておくべきことをいくつか解説していきます。
これらの準備をしっかりしていないと、折角の志望動機も魅力が半減し、企業からの評価も下がってしまう可能性が高まるので注意しておきましょう。
業界分析
志望動機を作成する前に行う業界分析は、SEなどの職種の仕事内容だけでなく、業界の動向や将来性について深く理解することが重要です。
業界全体の情勢を把握することで、特定の企業が直面している課題や業界内でのその企業の位置づけなどを明確に理解することができます。
そうすることで、より具体的かつ説得力のある志望動機の作成に繋がります。
このプロセスを通じて、志望する業界への関心の深さを示すことができるだけでなく、将来のキャリアに対する明確なビジョンを持つことにも役立ちます。
企業分析
志望動機を作成する前に行う企業分析は、その企業で働きたい理由を深く掘り下げる上で欠かせません。
企業の特色や強み、文化、事業内容、業界内での立ち位置などを理解することで、その企業の独自性や魅力を具体的に捉えることが可能になります。
特に、SEとしてその企業で何を成し遂げたいのか、企業のどの側面に共感し、どのように貢献できるのかを明確にすることが、説得力のある志望動機作成へと繋がります。
企業分析を通じて、自身のキャリアビジョンと企業の目指す方向性がどのように一致するかを見極めることが、成功への鍵となります。
自己分析
志望動機を作成する上で自己分析は不可欠です。
SEを志望する理由や、将来どのように仕事に取り組みたいかについて深く考えることで、自分のキャリアに対する明確なビジョンを描くことができます。
自身の強みや興味がある分野、価値観を再確認し、それがなぜSEの職に適しているのか、具体的にどのような貢献を望んでいるのかを明らかにすることが可能になります。
このプロセスを通じ、自分自身の目指す方向性と、志望する企業が提供する機会がどのようにマッチするかを効果的に伝えられる志望動機を作成できます。
【新卒|SEの志望動機】 なぜSEなのかを考えよう
志望動機には、SE(システムエンジニア)を志望する理由になりますので、「なぜSEを熱望しているのか」という理由を書く必要があります。
そのためには、「なぜSEなのか」を明確にすることが不可欠です。
どのように明確にしていくか、ステップを踏みながら解説します。
ITに触れたきっかけを考える
SE(システムエンジニア)になろうと思ったきっかけが浮かんでこないという場合は、 ITに触れたきっかけを考えてみましょう。
インターネットやアプリ、システムなど、IT技術は身の回りにあふれています。
その中で特に影響を受けたものを探してみましょう。
それが、IT業界に興味を持ったきっかけという場合がほとんどです。
ものづくり経験
SE(システムエンジニア)はどちらかというと、ITを利用するというよりも、利用してもらえるようなシステムを 作る側の仕事です。
たとえばゲームを単に楽しむのは、ITを利用することですが、「大勢の人が楽しめるようなゲームを開発して提供すること」は、作る側になります。
過去にIT業界に関連したものづくりの経験をしたことがないでしょうか。
もしあれば、そのときの気持ちを思い出してみましょう。
ものづくりの経験を通して、大きな達成感を得られた、提供した相手がすごく喜んでくれて、こちらも幸せな気分になった、もっと大掛かりなものを作ってみたくなったなど、自分で体験して感じたことを、 IT業界で作る側に回りたいと思った理由につなげることがポイントです。
2つをかけ合わせて落とし込む
「ITに触れたきっかけ」と、「ものづくりの経験」をすり合わせると、志望動機になります。
ポイントは、 「IT業界で」「技術職として」働きたいと思う理由を作るように意識することです。
「IT業界で技術職としてどのように働いていきたいか」と「IT業界で技術職として、どんなことに挑戦してみたいか」という風に、もう少し噛み砕いてみると、良い志望動機が生まれやすくなります。
たとえば子どもの頃、初めてパソコンに触れたときに、その機能性の高さに感動して、もっといろいろと学びたくなったことが、ITに触れたきっかけとします。
成長してアプリの開発を独学で学び、ある日お金の管理を簡単にしたいという母親のために、お金を管理するためのアプリを開発しました。
自分で苦労しながらなんとか開発できた達成感と、母親が便利だと言ってくれたことに喜びを感じ、もっとシステム開発について知識とスキルを身につけた場合、志望動機は「IT業界ではより多くの人に喜ばれるシステムを開発してみたい」となります。
もし思い浮かばないというのなら、もう一度「ITに触れたきっかけ」と、「ものづくりの経験」に戻り、やり直してみると良いでしょう。
出来上がったら、 「IT業界で働きたい理由」「技術職としてどうなりたいか」ということが、盛り込まれているかどうかチェックします。
志望動機でSE(システムエンジニア)を目指す理由を伝えるためには、まず自分がIT業界に触れたきっかけを考えてみましょう。
そして次に、自身のものづくり経験を出してみて、この2つをかけ合わせてみることで、IT業界で制作側に興味をもった理由を綺麗に組み立てることができるかと思います。
【新卒|SEの志望動機】なぜその企業のSEなのかを考えよう
なぜその企業が良いのかという理由を盛り込めると熱意のアピールになります。
ここでは、具体的には下記を意識して企業研究をすることをおすすめします。
・基本情報
・事業内容
・業績
・経営陣の考え
就活生にとって企業研究は差別化ポイントではないように思えますが重要な項目です。
企業研究が十分にできているからこそ、企業側に効果的なアピールができます。
しっかりとおさえて確実に就活を進めていきましょう。
基本情報をチェック
まずは基本情報のチェックを抜かりなくしておきましょう。
企業理念や事業内容、沿革、取引先などを確認しておくことです。
ほとんどの場合これらは企業の公式Webサイトを確認すればわかります。
どんな社風なのか、どのビジネス領域に強みを持っているのかを確認しておきましょう。
また、SIerであれば元請なのか下請なのか、下請であれば何次請に位置するのかが分かるようにしておきましょう。
こうした基本情報は面接の際、採用担当者から基本情報を聞かれることも少なくありません。
質問に答えられなかったから不採用とはなりませんが、誰でもできることなので準備しておきましょう。
基本的な準備をしっかりできている学生は好印象を持たれます。
事業内容を具体的にチェック
事業内容としてどんなサービスを提供しているのか具体的にチェックしましょう。
ソフトウェアやアプリなどプロダクトがあるのであれば、それが世の中にどのような影響を及ぼしているのか、日常的にどう関わりがあるのかなどを志望動機に入れ込むことができます。
あなたがその事業にどのように関わりたいか、なぜ関わりたいかを志望動機として言えるようにしておきましょう。
企業側としても、採用後どのように活躍してくれるか明確なイメージであれば採用されやすくなります。
基本情報のチェックでは大まかな事業内容は確認できますが、それと合わせて業界地図などを見てIT業界全体の把握もしておいてください。
志望企業の立ち位置を理解することで、IT業界への視野が広がり興味の幅が増えるでしょう。
業績をチェック
志望する企業の業績もチェックしておきましょう。
上場企業であれば、株主や投資家向けにIR情報を出しています。
そこには、売上や利益などの業績に関わる数字や経営計画書などの今後の見通し、目標などを確認することができます。
業績や経営計画書をチェックする目的は、今後の事業の方向性がわかり、求める人物像もイメージしやすくなるためです。
方向性や求める人物像がわかれば、自分が合っているかどうかが確認できます。
志望する企業側のことについてリサーチ不足にならないように意識しましょう。
いくらあなたの人柄が良く、能力が高くても志望企業についてリサーチ不足だと、的外れなアピールをする恐れがあります。
志望企業の業績や経営計画書は一通り目を通しておいてください。
経営陣の考えをチェック
社長や役員クラスの経営陣の考えも確認しておきましょう。
経営理念やIR情報などでも確認できますが、それ以外でもメディアの取材に応じている場合があります。
これらの記事は、企業情報で知る情報よりも一歩踏み込んだ内容だったり、別角度からの情報だったりするため、より理解が深まります。
企業理念はトップの考えをベースに掲げられ、理念が現場に浸透して仕事が進められていきます。
理念に共感することができれば、早期離職の心配はないと言えるでしょう。
ただ、全社員が100%理念を理解して現場に浸透しているかというと、現実的にはなかなか難しい問題です。
本当に理念通り社員が働いているかは社風を確認することをおすすめします。
企業の公式サイトを見てわかる部分もありますが、現地へ行き肌で感じるのが一番確実です。
【新卒|SEの志望動機】SEのアピールポイント3選
この項目では、SE(システムエンジニア)の志望動機でアピールポイントになりやすいポイントを3選ご紹介します。
それぞれのポイントについて、アピールのコツと注意すべきことをまとめています。
いずれもIT業界では必須級で求められるポイントにはなっていますので、積極的にこのポイントをアピールできるようにしておきましょう。
SEのアピールポイント3選
- 好奇心や興味、関心の強さ
- ロジカルシンキング
- 高レベルのコミュニケーション能力
好奇心や興味・関心の強さ
IT業界は、時代の最先端の技術が多く導入されており、その分変化の激しい業界です。
そのため、時代の変化に敏感であるために、好奇心や興味・関心の強さが求められます。
SE(システムエンジニア)の志望動機で好奇心や興味・関心の強さをアピールするコツは、以下の通りです。
好奇心や興味・関心の強さをアピールするコツ
- なぜSEに興味を持ったのかを明確にする
- SEに興味を持ってから学んだことや経験したことを具体的にする
- 将来SEとしてどうなりたいのかを明確にする
SEにどうして興味を持ったのか、その興味からどこまで本気でSEのことを調べたのか、という点は、SEへの志望動機を説明しつつ、好奇心や興味・関心の強さをアピールするために、ぜひ取り入れていきましょう。
ここで「明確に」「具体的に」という点が注意点となっています。
好奇心や興味・関心の強さをアピールするときの注意点
- 主張に根拠があるかを確認すること
- 自分の知識や経験を客観的に見ること
- 書き方や表現があいまいにならないこと
好奇心や興味・関心というのは気持ちの部分になるため、どうしても前のめりになってふわっとした文章にしてしまいがちです。
そこで一歩踏みとどまって、客観的に見て自分の知識や経験を伝えられているか、しっかりストーリーに根拠が示されているか、という点に注意して志望動機を作成することが大切です。
ロジカルシンキング
SE(システムエンジニア)には、クライアントのニーズ解決から逆算して必要なシステムを考えるための、ロジカルシンキングが重要となります。
SEの志望動機でロジカルシンキングをアピールするコツは、以下の通りです。
SEの志望動機でロジカルシンキングをアピールするコツ
- 自分の考え方の過程を明確にする
- 論理的根拠を大切にする
- 客観的な視点を持つ
ロジカルシンキングをアピールするためには、いかに考え方が道筋立てられているかを説明することが必要になります。
ストーリーを話すときにも、自分はどんな根拠をもとにして、どんな仮説を立てて、どんな行動をしたのか、という点を客観的に評価して、順序立てて説明できるようにしましょう。
ロジカルシンキングをアピールするときの注意点
- 主観的にならないこと
- 自分の能力を過大に示さないこと
主観的な考え方を多く含んでしまうと、その考え方の根拠が薄くなってしまいます。
それはロジカルシンキングとはいえません。
あくまで客観的に物事を見て、冷静に的確な道筋立てができることを伝えていきましょう。
高レベルのコミュニケーション能力
SE(システムエンジニア)には、短時間の打ち合わせから真に求められているニーズを聞き出す能力が求められるため、高レベルのコミュニケーション能力が必要になります。
SEの志望動機でコミュニケーション能力をアピールするコツ
- 具体的なエピソードを交えてアピールする
- コミュニケーション能力がSEでどう活きるかをアピールする
- コミュニケーション能力を上げるためにしていることを伝える
コミュニケーション能力は、実際にそれが活きたエピソードを一緒に伝えることが大切になります。
また、なぜコミュニケーション能力がSEで大切になってくるかを理解していることを伝えることも重要です。
そのコミュニケーション能力を、SEの業務にどう活かすのか、またさらにレベルアップするためにどうしていくのか、という点まで伝えられるようにしましょう。
SEの志望動機でコミュニケーション能力をアピールするときの注意点
- コミュニケーション能力を主張しすぎない
- 事実でないことは書かない
SEにおいてコミュニケーション能力はかなり求められますが、それがメインスキルというわけではありません。
コミュニケーション能力を主張しすぎて、そのほかのアピールがおろそかにならないようにしましょう。
「好奇心や興味、関心の強さ」「ロジカルシンキング」「高レベルのコミュニケーション能力」の3つは、SE(システムエンジニア)の志望動機として強いアピールポイントになります。
特に興味関心の強さは、未経験の場合重視されるところになるため、重視して作成してみましょう。
【新卒|SEの志望動機】NGワード集
SE(システムエンジニア)の志望動機を見つけたら、後は文章にするだけですが、志望動機として避けたい表現があります。
知らないうちにSEの志望度を半減させてしまうような言葉を使ってしまうこともありますので、注意が必要です。
特に「手に職をつけたい」「チームワーク」など、良かれと思って使ってしまうケースが多くありますが、 SEの志望動機ではNGワードとなります。
なぜ「手に職をつけたい」と「チームワーク」はNGワードになってしまうのか、その理由についてそれぞれ説明します。
手に職をつけたい
SE(システムエンジニア)は、システム開発に必要な技術を身につける必要があるため、「手に職をつける」という表現は間違っていません。
しかし、「手に職をつけたい」を志望動機のメインに持ってきてしまうと、 企業の採用担当者や面接官は、「ITじゃなくてもいいのでは?」と思ってしまいます。
専門的なスキルが必要な職は数多くあります。
「手に職をつけたい」ということを理由にするなら、 数ある専門職の中で、なぜSEを選んだのか、深く掘り下げて明確にしたことを志望動機にしましょう。
そうすると「手に職をつけたい」というよりも、「システム開発のスキルや知識を武器にしたい」という風に、志望動機は自然に具体化していきます。
「資格取得を目指している」というのも、同じ理由です。
「資格取得なら、ほかの業界でもできるだろう」と、面接官に受け止められてしまうのがオチです。
SEになるために不可欠な資格はありませんが、数ある資格の中でも、 「情報処理技術者試験」や「応用情報技術者(AP)」などの資格を、なぜ取得したのか、その資格をSEとしてどう活かしていきたいかを、具体的に伝えることがポイントになります。
チームワーク
システム開発にはチームワークは不可欠で、チームワークで仕事ができる人材を探す企業も少なくありません。
しかし、チームワークはIT業界に限ったことではなく、重要視している業界はほかにもたくさんあります。
応募が殺到している企業であれば、チームワークを志望動機としてアピールする学生も少なくないでしょう。
志望動機で大切なのは、「なぜSE(システムエンジニア)なのか」を明確に伝えることです。
もしチームワークをアピールしたいなら、「協調性がある」「過去に仲間とプロジェクトを進めた経験がある」など、志望動機ではチームワークがあることを、 さりげなく伝える程度にとどめることが賢明です。
「手に職をつけたい」「チームワークを発揮したい」といった点は、SE(システムエンジニア)の志望動機として押し出すのはNGになります。
この2点はSEではあまり評価去れない点になってくるためです。
ただし、チームワークを発揮する必要のある業務形態をとる企業も存在はしていますので、あくまで企業研究は怠らないようにしましょう。
【新卒|SEの志望動機】志望動機の構成
企業研究の解説をしましたが、それをもとに次は志望動機を作り上げていきましょう。
志望動機には理解しやすく効果的に伝わりやすい構成があります。
・結論
・SEを志望する理由
・志望の根拠となるエピソード
・結論(企業への貢献)
詳しく解説していきます。
結論
就活ではESでも面接においても結論ファーストを意識しましょう。
理由が二つある場合は、先に「私が貴社を志望する理由は2点あります。1点目は~~。2点目は~~。」という風に述べると良いでしょう。
結論を先に述べることで、文章が簡潔になり読み手に伝わりやすくなるという利点に加え、論理性があるという印象を与えることができます。
また、就活の場面のみでなく入社後の上司や同僚への報連相や、お客様とのコミュニケーションの際も結論ファーストが役立ちます。
上司は基本的に複数の案件を抱えて忙しかったり、お客様も忙しい経営者であることも多いでしょうから、結論ファーストを習慣化しておきましょう。
なぜSEを志望するのか
次に、なぜSEを志望するのか簡単に述べましょう。
SEになりたいと思ったきっかけや理由があると思いますので、それを伝えてください。
この場合、「IT業界は市場規模が大きい」や「高い報酬が得られそう」という理由は避ける方が無難です。
なぜなら企業側から「誰でも思いつく理由」「考えが浅い」と思われる恐れがあるからです。
もちろん本音の部分では「稼げそうだから」等という理由があって当然だと思いますが、ここではSEの仕事に関することをアピールする方が良いでしょう。
根拠となるエピソード
上記でSEになりたい理由を述べた後、具体的に詳しくエピソードを述べましょう。
このエピソードが差別化の重要なポイントになります。
上記のSEになりたい理由はどうしても他者と似たようなものになりがちです。
しかし、その根拠となるエピソードは人によって十人十色であり、全く同じエピソードになることはありません。
どのような場面でSEという仕事に影響を受けたのか、なぜ影響を受けたのか、影響を受ける人や出来事は何だったのか整理しておきましょう。
企業の特徴に言及しながら結論
最後にその企業で貢献できることや、入社後にこういう事業に携わりたい、この仕事にチャレンジしたいなど企業の具体的な事業や強みに触れながら締めましょう。
企業研究をした内容がここで活きてきますので、企業の今後の方向性・事業展開と、そこであなたがどう活躍したいか、どう役に立ちたいかをアピールしてください。
その内容が明確で企業側の考えともマッチしていれば「この人と働いてみたい」と思ってもらえるようになります。
【新卒|SEの志望動機】SEの志望動機例文7選
SE(システムエンジニア)の志望動機例について、2例ご紹介します。
あくまで例文ですので、そのまま志望動機に使うのは得策ではありません。
志望動機の書き方の流れやアピールするポイントを掴み、自分の志望動機に反映させるようにしましょう。
志望動機の基本的な流れは、SEを志望することを伝えた後、なぜSEを志望するのか、その理由を続けます。
さらに経験やエピソードを用いて、志望理由を補足し、SEになって挑戦したいことや貢献したいことなどについて述べて締めくくります。
この流れに沿って志望動機を書くと、相手に伝わりやすくなりますので、覚えておきましょう。
例文1
私は貴社でシステムエンジニアを志望します。
もともとものづくりが好きで、何か人や世の中に役立つものを作り出したいと考えたからです。
私がものづくりに目覚めたのは小学生の頃で、親に買ってもらったパソコンに夢中になり、インターネットを使ってイラストなどいろいろなものを作りました。
学校の授業でもものづくりの授業が大好きで、グループのメンバーと楽しみながら課題に取り組んだのです。
学生時代は情報工学を学び、その一環としてIT企業でインターンシップを経験しました。
インターンシップは、システムエンジニアの仕事に具体的に取り組めるという、とても貴重な体験でした。
システムの設計書を作成する達成感や自分が設計したシステムが誰かに喜ばれているというやりがいを感じ、ますますSEになりたいと思うようになったのです。
現在私は応用情報技術者の資格取得を目指しながら、空いている時間を利用してアプリ開発を進めています。
貴社はスタッフが自由にアイディアを出し合い、創造的なアプリを開発できる環境が整っています。
私も貴社のアプリ開発に参加し、社会に貢献できるものを創出したいと考えております。
例文2
私が貴社を志望するのは、システムエンジニアとしてAIの分野で活躍したいと考えたからです。
私は昔から数学が得意で、大学では情報工学を専攻していました。
文系未経験の私は、システムエンジニアになるとは考えていませんでしたが、システムエンジニアになろうと考えたきっかけは、プログラミングの講義でした。
内容がとても面白く、システムエンジニアになるために必要な知識やスキルを身につけたいと、強く思うようになりました。
システムエンジニアはシステムの設計や裏方的な仕事が多く、私の性格にもマッチします。
私は学生時代イベントサークルのメンバーで、表に出るよりも、イベントの段取りを決めて、準備をし、表に出る人をサポートすることが大好きでした。
現在はシステムエンジニアに必要な知識を身につけるため、資格取得に向けて勉強中です。
システムエンジニアに対する情熱と、これまで身につけたスキルを活かして、貴社では顧客が求めるシステム開発に貢献していきたいと考えております。
例文3
私は文系学部の出身で、ITに関しては未経験ですが、過去の、ものづくりを通して課題を解決する、という経験から、システムエンジニア職に興味を持ち、応募をしました。
大学2年生の時に、新入生歓迎会のために部活動の仲間とともに動画制作をして、新入生をなんとかして集めようという計画を立てたのですが、その際に動画編集を主に担当しました。
入部5人を目標に、なんとか私たちの部活に魅力を感じてもらおうと様々な人脈や情報を使って、未経験ながら動画を制作し、その動画が大変好評をいただいて8名の新入部員を抱えることに成功しました。
この経験で私は、何かを計画して制作することで課題を解決できる面白さと、それを可能にした動画制作ツールというシステムにも大変興味を持ち、調べていくうちに、自身でこのシステムを作っていくことで、社会課題の解決の根本的なところに関わることができるのではないかと考えました。
そのため私は、貴社のシステムエンジニア職に応募いたします。
例文4
私は、貴社でシステムエンジニアを志望します。
デジタル化へと移りゆく中で豊かな社会への実現に、私も貢献したいという理由からです。
私は高校時代からウェブサービスの開発を趣味としており、特にユーザーが直面する問題を技術で解決することに喜びを感じています。
ある時、友人から学生向けのイベント情報を一元化するプラットフォームが欲しいという声を聞き、そのニーズを形にするためにウェブアプリを開発しました。
友人からのフィードバックをもとに改善を重ねるプロセスは、大変でしたが楽しい経験でもありました。
また「イベント情報が一目で分かり便利になった」という声は、私の技術が社会に寄与する一瞬となり、SEを志望する大きなきっかけとなりました。
貴社のようなデジタル技術が社会に広く浸透する環境で、一人でも多くの人々に価値を提供するプロダクト作りに貢献したいと考えています。
例文5
私は、システムエンジニアとして貴社に貢献したいと考えています。
私にはIT技術を通じて、多くの企業が抱える課題の解決に貢献したいという希望があります。
IT企業でのインターンシップに参加して、IoTデバイスのセキュリティ課題に取り組む機会がありました。
内容は、セキュリティの専門家から基礎を学び、実際に脆弱性を持つシステムに対するセキュリティテストを行うことです。
この体験を通して、技術的な深みと社会的なインパクトを兼ね備えたセキュリティのフィールドに強く引き寄せられました。
そして、セキュリティに配慮したシステム開発を目指すSEへの強い動機となりました。
このスキルを貴社で発揮し、システムの安全性と信頼性の向上に貢献できることを確信しています。
そして、貴社のチームの一員として、セキュリティ分野での専門知識をさらに深め、多くの企業が抱えるIT課題の解決に取り組んでいきたいと考えています。
例文6
私が貴社を志望した理由は、貴社の強みである組み込み系の開発を通してSEとしてIoT技術に携わりたいという理由からです。
大学の研究室で、クラウド基盤を利用したスマートホームのプロジェクトに取り組みました。
私はプロジェクトリーダーを務め、センサーデータのクラウド上での処理や家電の自動制御のアルゴリズムを担当しました。
このプロジェクトで複雑なシステムをゼロから構築し、チームメンバーをまとめながら目標に到達する喜びと達成感を味わいました。
これがシステムエンジニアとして社会に貢献する魅力を感じ、SEを志望するきっかけとなりました。
プロジェクトリーダーの経験と技術的な知識を活かし、貴社の組み込み系開発チームにおいてもプロジェクトをスムーズに進行させIoT技術の革新に寄与します。
貴社でシステムエンジニアとして、組み込み技術を用いた新しい価値の創造に貢献したいと考えています。
例文7
私は、貴社でシステムエンジニアとして貢献したいと考えております。
私は、全ての人が便利な生活を送れる未来を創造したいという思いがあります。
大学ではAI技術に深く興味を持ち、教育分野での応用に注目していました。
私は友人たちと協力し、AIを活用した個別指導型の学習プラットフォームのプロジェクトをスタートさせました。
このプロジェクトにおいて、AIアルゴリズムの開発やデータ分析を担当しました。
その結果、学生のパフォーマンス改善を実際に達成することができました。
この経験から、技術が個々のニーズにどれだけ密接に寄り添い、大きな価値を提供できるかを身をもって知りました。
これがシステムエンジニアへの道を本格的に志す動機となりました。
AI技術と実社会に応用する経験を基にして、貴社でのプロジェクトにおいても新しい視点とスキルで貢献したいと考えています。
【新卒SEの志望動機】文字別志望動機の書き方
ESなどで志望動機の文字数が具体的に定められている場合も多いです。
そこで文字数別の志望動機の書き方のポイントや注意点についてまとめてみたので是非参考にしてみてください。
自分の志望動機を文字数別でパターン化しておくこともおすすめです。
志望動機200字の書き方
200文字以内の志望動機では、限られたスペースの中で企業への入社希望理由を簡潔かつ明確に伝えることが重要です。
企業の特色や自身が魅力を感じた点を一つ挙げ、それが自分のスキルやキャリア目標とどのように合致しているかを短く、要点を押さえて表現します。
効率的な文章構成と、自分の意欲や企業への貢献意志を具体的に示すことで、短いながらも印象的な志望動機を作成しましょう。
具体的な内容は以下の記事を参考にしてみてください。
志望動機400字の書き方
400文字以内の志望動機は割と多くの企業で採用されている場合が多いでしょう。
400文字以内の志望動機では、まず結論を明確に述べ、次になぜその企業でその職種を志望するのかを根拠となる具体的なエピソードや理由と共に説明します。
最後に再度結論をまとめ、自分の意欲を強調します。
文章の構成は明確にし、要点を簡潔にまとめることがポイントです。
具体的な内容は以下の記事を参考にしてみてください。
志望動機1000字の書き方
1000文字の志望動機は比較的長いので、書くのが難しく感じる方も多いと思います。
しかし、対策をしっかりと準備しておけば怖がる必要は全くありません。
まず、文章を無駄に長くするのは逆効果です。
自身の強みや興味等について具体的なエピソードや理由等を明確にしつつ、一文の長さは適切な長さにすることを意識しましょう。
また企業とのマッチングポイントや志望の根拠を明確に示し、熱意を伝えることが重要です。
冗長な表現を避け、簡潔かつ魅力的に志望動機を表現しましょう。
具体的な内容は以下の記事を参考にしてみてください。
【新卒|SEの志望動機】作成後にやること
最後に、SE(システムエンジニア)の志望動機を作成した後にやるべきことを2つご紹介します。
この2点は、SEだけでなくどんな業界の志望動機においても大切なことになりますので、ぜひ実践してください。
誤字脱字の見直し
まずは、誤字脱字の見直しです。
これは当たり前のことですが、実は就活においてはかなり起こりうるミスとなっています。
エントリーシートは字数が多いこともしばしばあり、書くのに時間がかかったり、労力がかかることも多いですよね。
疲れてくると、人間はミスをしやすくなるものです。
最後の方になればなるほど、自分では最初気が付いていないとんでもない誤字をしていたりするものです。
提出前に必ず2,3回確認して、提出することをこころがけましょう。
おすすめは期日に余裕を持って書いて、書いた1、2日後に落ち着いて見直すことです。
添削
志望動機は、書いた後、第三者に添削をしてもらうようにしましょう。
就職活動において、志望動機はとても重要な項目になります。
そのため、第三者に添削してもらうことで、自分では気が付かなかった誤字脱字を直したり、客観的に文章を見て表現を直したりすることがとても大切なのです。
また、添削をしてもらう第三者は家族や友人ではなく、企業の採用担当者やエージェントをおすすめします。
エージェントは就職活動に精通しており、採用担当者の目線から志望動機を添削してもらうことが可能になっています。
エージェントについて、詳しくは下記からご覧ください。
まとめ
SE(システムエンジニア)の志望動機に必要なポイントについてご紹介しました。
SEは、クライアントが求めるシステムを開発するため、システムの全体を把握し、プログラマーがスムーズに業務を行えるようにシステムを設計するのが仕事です。
自分の性格や過去の経験と照らし合わせながら、SEを志望する理由を明確にすることが、採用される志望動機を書くポイントになります。
どんな職業にも当てはまるようなNGワードを避けて、自分の想いが伝わるような志望動機を書いていきましょう。