
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
食品業界は理系、文系問わず、就活で人気の業界です。
食は生きていくために欠かせず、日々、さまざまな食品を摂取し触れる機会が多いうえ、子どもの頃から実際の商品や企業名に触れてきて馴染みもある分野だからです。
この記事では理系生にとっての食品業界における就職の実態について迫っていきます。
食品業界の概要やジャンル、職種をはじめ、食品業界への就活にあたり、理系の大学生が学ぶべきこと・将来性を解説していきます。
【理系から食品メーカー】概要
食品業界と聞いて、あなたはどんな食品をイメージしますか。
肉や魚、野菜の加工といった原材料をイメージする方もいれば、飲料や菓子などの身近なもの、冷凍食品やレトルト食品などの便利な商品をイメージする方もいるでしょう。
食品原料や加工食品に至るまでさまざまな答えが返ってくるほど、食品業界は幅が広い業界です。
理系生からの人気は高く、就職人気ランキングトップ10には食品業界から5社が選ばれているほどです。
食品業界について、詳しく見ていきましょう。
食品業界にはさまざまなジャンルがある
食品業界には以下のようなジャンルがあります。
代表的なジャンルと、人気企業を列挙してみました。
■飲料
サントリー / コカコーラ
■製粉
日清製粉 / 日本製粉
■冷凍食品
ニチレイ / マルハニチロ
■調味料
キューピー / ハウス食品グループ
■菓子
明治 / ブルボン
■パン
山崎製パン / フジパン
■健康食品
明治 / 雪印メグミルク
■その他
伊藤ハム / 日清オイリオグループ
ジャンルを分けてみても、実際には1つの企業で多角的な商品の生産を行っているのが近年の傾向です。
たとえば、飲料メーカーのサントリーはアルコールをはじめ、ソフトドリンク、皿にはサプリメントの開発も行っています。
調味料メーカーのキューピーはマヨネーズだけでなく、介護食品事業にも乗り出しています。
文系との採用枠の違い
食品メーカーの採用は大きく分けて総合職と技術職に分かれており、理系学生は主に研究開発、生産技術、品質管理などの専門職として採用されます。
文系は営業や事務など総合職での採用が中心となるため、理系と直接競うケースは少なく、専門性を持つ人材として優遇されやすいのが特徴です。
特に大学院生の場合は、修士や博士課程で培った研究経験や分析力が評価され、即戦力として期待されることが多くあります。
また、研究内容が直接業務に関係しなくても、論理的思考力や課題解決力が評価されるため、理系ならではの強みを活かして採用される傾向があります。
そのため、理系学生は学部卒・院卒を問わず、専門職として安定したキャリアを築けるチャンスが広がっています。
インターンシップの重要性
食品メーカーのインターンシップは、本選考に直結する重要な機会として位置づけられています。
実際に社員と一緒に研究や製造現場を体験することで、会社の雰囲気や仕事内容を具体的に理解できるだけでなく、自分の研究テーマがどのように企業で活かせるかを確認するチャンスとなります。
また、インターン中に得た社員からの評価が本選考に影響するケースも多く、早期選考ルートへの案内や内定獲得の近道となることもあります。
理系学生にとっては、研究室配属後の夏季インターンなどで専門知識をアピールできる貴重な機会であり、将来のキャリアを考える上でも参加価値は非常に高いと言えます。
社員との交流を通じて得られる業界の最新情報やキャリアパスの事例も、企業選びの参考になります。
【理系から食品メーカー】職種の紹介
食品業界はジャンルも幅広いうえ、製造過程でさまざまな職種が存在しています。
食品業界にまだ詳しくない方でも、親しみのある業界だけに、ざっと考えてもイメージできるのではないでしょうか。
新しい商品を企画、開発して製造、宣伝、営業をして販売する、新商品の開発のためにはマーケティングも必要ですし、原材料の選定や仕入れも必要です。
ここでは、代表的な職種として以下の5つを見ていきます。
研究開発
生産管理職
商品開発(マーケテイング)
事務系職種
営業職
研究開発
食品業界の研究開発は 商品の開発、既存商品の味の改良をはじめ、原料の選定など幅広い研究や技術開発を行っています。
どんな原材料や調味料を組み合わせれば、味わいや食感が増すか、製品のターゲット層ごとに、どのような味が好まれ、そのためにはどのような味や食感などを追及すれば良いのかも研究対象です。
近年の健康志向の高まりを受け、糖質オフやグルテンフリー、いかに添加物を入れずに製造するかの研究も求められます。
社会問題化している食品ロスの抑制を目指し、賞味期限を延ばすための研究開発も重要な課題です。
生産管理職
生産管理職は食品業界の中でも重要な職種と言えます。
なぜなら、どんなに良い商品を開発しても、製造工程において衛生面で問題が生じた場合や異物混入などが起これば、人の生命にも関わり、重大事故にも発展しかねないからです。
トラブルやリスクを未然回避し、高品質、安全に商品を提供するための製造工程を検討して構築し、監視、改善していくのがメインの役割です。
商品開発(マーケティング)
食品業界の商品開発(マーケティング)職も、 企業利益の追求にあたって重要なポジションを担っています。
食品業界は人々の命の源となる食品を安定供給するために、基本的な食品を製造し続ける使命を担う一方、競合他社も多いため、売れる商品を生み出さなくてはなりません。
時代の変化や好みの多様化など世の中の人のニーズに応えることや売り出し方を考え、売れる商品、生き残る商品を生み出すのが仕事です。
事務系職種
食品業界の事務系職種は多岐に及びます。
商品の受発注に対応することや伝票などを発行する職種や資材や原材料の受発注を管理する部門、事業活動における経理の数値をまとめることや採用計画など事業活動の支援を行う部門もあります。
食品分野では食品衛生法や製造物責任法をはじめ、アレルギー表記やエネルギー表記、特定保健用食品(トクホ)と機能性表示食品の違いなど、守るべきルールも多岐にわたり、法務部門やパッケージ作成部門なども責任重大です。
営業職
食品は引き合いが強く、販売するのは簡単と思われがちですが、営業職の地道な努力が不可欠です。
あなたのお気に入りのお菓子や飲料が、あるお店では売っていても、別のお店では売っていないことも多いのではないでしょうか。
テレビCMを流している有名な商品でも、取り扱っていないお店はあります。
営業職は 卸売店や小売店を地道に回って、自社の商品を置いてくれるよう営業しています。
エリアを決められてスーパーを地道に回って、自ら売り場で商品を目立つところに並べ直すなど、地道な努力が欠かせません。
品質管理・品質保証
品質管理は、製造工程の監視や製品検査を通じて、安全かつ高品質な食品を安定して生産することを目的とする仕事です。
一方、品質保証は製品が顧客に届けられる最終段階で品質を保証する役割を担い、クレーム対応や品質基準の策定などを行います。
理系出身者は、微生物学や化学、分析化学などの専門知識を活かして、食品の安全性を科学的に評価し、製品の信頼性を確保する中心的存在となります。
特に近年は、国際的な品質規格や食品衛生法への対応が求められるため、理系の技術的知識を持つ人材の需要は一層高まっています。
品質を守るだけでなく、新たな検査方法や分析技術を導入する提案力も重要となり、専門性を磨きながら社会的に意義のある仕事ができる点が魅力です。
【理系から食品メーカー】必要な能力
食品メーカーでは、理系の知識や技術が重要視されますが、同時にさまざまな能力が求められます。
以下では、これらの能力を詳しく見ていきます。
知識意欲
食品メーカーでは、製品の開発から生産まで、幅広い知識が求められます。
原材料の特性、食品の安全性、加工技術、さらには法規制まで理解しておくことが必要です。
特に理系出身者は、これらの知識を専門的に深め、現場で活かすことが求められます。
新しい技術や研究成果が次々と登場するため、知識を常にアップデートし続ける意欲が不可欠です。
また、研究開発や品質管理の分野では、問題解決力や実験結果の分析力も必要です。
高い倫理観
食品業界では、消費者の健康と安全が最優先されます。
そのため、企業には厳しい衛生管理が求められ、高い倫理観を持った人材が重視されます。
製造過程での安全性や衛生面に対する徹底した意識は、企業の信頼性にも直結します。
特に、食品の衛生基準や規制は年々厳しくなっており、どれだけ適切にこれらを守り実践しているかが企業の評価に影響します。
そのため、倫理的な判断力と強い責任感を持って業務に取り組むことが重要です。
コミュニケーション能力
食品メーカーでは、取引先やサプライヤー、社内の他部門との連携が不可欠です。
そのため、スムーズなコミュニケーション能力が必須です。
理系出身者は、技術的な知識を持ちながらも、相手にわかりやすく説明する能力が求められます。
さらに、交渉力や調整力も重要で、取引条件の調整や製品仕様の確認など、多くの場面でコミュニケーションスキルが活かされます。
また、食品業界は消費者との距離も近いため、消費者の声を取り入れるための柔軟な対応力も重要です。
課題解決能力
食品メーカーでは、生産ラインでのトラブルや新製品開発時の味や品質の再現など、日々さまざまな課題が発生します。
こうした問題に対して、原因を特定し、最適な解決策を導き出す能力が求められます。
理系学生は研究活動を通じて、仮説を立て、実験や検証を繰り返す中で論理的に問題を整理し、解決策を導く力を自然に身につけています。
この課題解決能力は、製造現場での改善提案や新商品の開発など、あらゆる場面で大きな武器となります。
また、トラブル発生時に冷静に状況を分析し、チームをリードして迅速に対応する力も評価されるため、研究で培った経験を積極的にアピールすることが重要です。
論理的思考力
研究活動で仮説を立て、実験で検証し、結果を分析して結論を導く一連のプロセスは、食品メーカーでの仕事にそのまま活かすことができます。
例えば、製造プロセスの効率化や品質改善、新しい食品素材の開発などでは、膨大なデータを分析し、問題点を構造的に整理する力が不可欠です。
理系学生が持つ論理的思考力は、複雑な課題を整理して本質的な問題を特定し、具体的な改善策を提案する場面で高く評価されます。
さらに、研究を通じて得た数値解析やデータ処理のスキルも、食品メーカーの現場で重宝されるため、選考時に具体的なエピソードを交えて説明すると効果的です。
【理系から食品メーカー】実態とは
理系生の食品業界における就職の実態はどうなっているのでしょうか。
就職人気ランキングトップ10で食品業界から5社が選ばれているほど、 競争率が高い業界です。
理系が文系より有利かというと、必ずしもそうではありません。
食品業界は専門性はそれほど問われず、学部やゼミの内容もあまり関係ありません。
もっとも、成分分析や加工技術の開発など専門知識やノウハウが求められる研究職や、理系の視点が必要になる生産管理職などは、理系生には有利な分野です。
食品業界の選考では、特に人物評価が重視されます。
ジャンルも職種も多岐にわたり、メーカーやブランドのイメージが確立されている企業も多いため、マッチした人物を選びたいためです。
それでも理系生は多少有利になる
就職人気ランキングトップ10で食品業界から5社が選ばれるほど、理系生はもとより、文系の学生からも人気で、競争倍率が高い業界です。
それでも理系生は多少有利になるのは事実です。
ジャンルや志望職種にもよりますが、 食物調理や栄養学などを学んでいれば、研究職において他の就活生に比べて有利になります。
知名度の高い人気メーカーほど、内定を得るためには自分の強みを活かすための自己分析や企業研究が欠かせず、受かるために必要な学びなど努力も欠かせません。
就活コンサルタント木下より

理系生でも知識や技術、専攻だけでなく、人物評価の方が重視されますので、志望する企業がどのような人物を求めているのかをよく研究し、自己PR力も高めておきましょう。
重視されるのは人物評価
食品業界の選考において、重視されるのは人物評価であるのはなぜでしょうか。
特に食品の製造や商品開発(マーケティング)などの分野では、その人が適しているかどうかを見極めて採用される傾向が強いです。
製造分野では高い倫理観やきめ細やかさ、高品質で安全な製品を作る使命感などが必須です。
以前発生した意図的な毒物混入事件はあってはならないことですし、近年増えている異物混入なども企業の信用失墜はもとより、人々の生命や健康にも関わります。
常に安全で品質の安定した商品を製造できる人物が求められます。
自社の製品に愛着とこだわりを持つ人を得たい企業が多いのです。
商品開発(マーケティング)は企業の生命線を担っています。
時代のニーズをキャッチしながら、自社ブランドらしい商品を開発できる人が求められます。
キャリアパスについて
食品業界のキャリアパスはどのようになっているのでしょうか。
就職してからの将来像やキャリアプランについて確認していきましょう。
まず、 理系の研究職は基本的に専門領域で仕事を継続しながら、キャリアを積み重ねていきます。
そのため、高度な専門性が必要となり、大学で学んだ知識や技術を活かしながらも、現場で経験を積み、新たな学びや技術のブラッシュアップを図りながら、時代に即した成分や商品の開発などに取り組んでいくことが求められます。
これに対して、営業職は数年単位でジョブローテーションするケースが一般的です。
営業職のエリアが変わるといった部署内の異動にとどまらず、営業経験を活かして商品開発(マーケティング)職に配置転換されるケースも少なくありません。
具体的な仕事内容と一日の流れ
研究開発職では、午前中に文献調査や実験計画を立案し、午後はサンプル作成や機器分析、データ整理、上司への報告などを行います。
一方、生産技術職では、午前中に製造ラインを巡回して生産データを確認し、午後はトラブル対応や生産効率向上のための会議、技術資料の作成に取り組みます。
このように、職種によって業務内容や一日のスケジュールは大きく異なりますが、いずれも理系出身者が持つ専門知識を活かしながら、日々の改善や開発に挑戦するやりがいのある仕事です。
長期的なプロジェクトに取り組むことが多く、計画性や粘り強さが求められる点も共通しています。
研究テーマとの関連性
大学での研究内容が直接企業の業務に結びつかなくても心配する必要はありません。
確かに微生物学専攻なら発酵食品、化学専攻なら新素材開発など専門が直接活かされる場合もありますが、より重要なのは研究を通じて何を学び、どのような力を身につけたかです。
実験計画の立て方、データ分析の手法、仮説検証のプロセス、粘り強く課題に取り組む姿勢など、研究で培ったスキルは食品メーカーのあらゆる部門で役立ちます。
採用担当者は専門分野の一致だけでなく、課題に取り組む姿勢や論理的思考力を重視するため、研究経験を汎用的なスキルとして伝えることが効果的です。
【理系から食品メーカー】抱える課題
食品業界は理系の知識が活かされる場である一方、独自の課題にも直面しています。
特に、少子化に伴う市場の縮小、競争の激化、品質に対する消費者の期待の高まりなど、解決が必要な問題が多岐にわたります。
以下では、食品業界が抱える主要な課題について詳しく解説していきます。
市場の縮小
少子化が進む日本では、食品市場も縮小の影響を大きく受けています。
特に2019年以降、人口減少に伴い、国内の総消費量が下がることが懸念されています。
消費者の数が減少するため、食品メーカーは販売戦略を見直す必要に迫られています。
市場が縮小する中で、企業は新たな顧客層を開拓するか、既存の顧客の購買頻度や単価を上げるための戦略を取らなければなりません。
また、グローバル市場への展開や健康志向、エコフレンドリーな製品の開発などが求められています。
競争が激しい
食品業界は非常に競争が激しい市場です。
特に、原材料の高騰や物流コストの上昇に伴い、コスト削減と品質維持を両立させることが難しくなっています。
競合他社との差別化を図るためには、価格競争に巻き込まれるのではなく、独自の商品開発や付加価値の提供が求められます。
しかし、低価格戦略に頼りすぎると、利益率が低下し、持続可能な経営が困難になる可能性があるため、価格だけでなく品質やブランド力を強化する必要があります。
品質の水準が高い
食品業界では、消費者が求める品質の水準が年々高まっており、それに応えるための努力が企業に求められます。
消費者は健康志向が高まっており、安全性や衛生面に関する要求が厳しくなっています。
さらに、価格が高騰する中でも、製品の品質は落とせないという難しいバランスが要求されています。
企業は新しい技術を導入して生産工程を効率化し、コストを抑えながらも品質を維持するための取り組みが必要です。
これにより、顧客満足度を高め、ブランドの信頼性を確保できます。
グローバル化への対応
国内市場が少子高齢化により縮小傾向にある中、多くの食品メーカーは海外市場の開拓を成長戦略の柱としています。
理系人材は、海外工場での生産技術指導や各国の規制に対応した製品開発など、国際的な業務で活躍する機会が増えています。
現地の法律や衛生基準に合わせた製造プロセスの設計、新興国向け商品の開発など、専門知識を活かしたグローバルな課題解決が求められる場面も多くあります。
さらに、原材料の調達から製品の流通まで、国際的なサプライチェーンを理解し、安定した供給体制を構築する役割も重要です。
海外工場では現地スタッフとの協力が欠かせないため、異文化コミュニケーションや多国籍チームでのマネジメント力も評価されます。
海外赴任や国際会議への参加など、若いうちから世界を相手に挑戦できる環境が整っていることも、食品メーカーで働く大きな魅力と言えます。
SDGsへの取り組み
食品メーカーは、食品ロス削減やプラスチック使用量の削減、環境負荷の軽減など、持続可能な社会を目指した取り組みを積極的に進めています。
これらの課題を解決するためには、理系の知識や技術が不可欠です。
バイオテクノロジーを用いた新素材の開発や、エネルギー効率を高める生産技術の導入など、理系人材が中心となって進めるプロジェクトも増えています。
さらに、再生可能エネルギーを活用した生産ラインの構築や、排水・排気処理の高度化、省エネ型設備の開発など、環境保全に直結する業務も広がっています。
気候変動や資源枯渇といった地球規模の課題に対し、研究開発や製造工程の改善を通じて持続可能性を実現する役割は年々大きくなっています。
環境問題に取り組みながら社会に貢献できる点は、理系学生にとって大きなやりがいとなるだけでなく、企業価値の向上にも直結します。
消費者や投資家からの注目も高く、自分の研究成果が社会課題の解決に役立つ実感を得られるのも魅力です。
技術革新の動向
近年、食品業界ではAIやIoT、ロボット技術などの導入が急速に進んでいます。
生産ラインの自動化、AIを活用した品質管理、ビッグデータを用いた顧客ニーズ分析など、最先端の技術が競争力を左右する重要な要素となっています。
理系出身者は、これらの新技術を学び、現場に応用する役割を担うことが期待されており、技術革新に対応できる柔軟な発想と実践力が求められます。
具体的には、AIによる味覚分析や消費者データのパターン認識、IoTを活用した製造機器の遠隔監視や故障予測など、データと機械を連携させた高度な取り組みが進んでいます。
また、3Dフードプリンターを活用した新しい食品開発や、スマートファクトリー化による完全自動生産など、研究段階にある先端技術も現場に導入されつつあります。
こうした変化の最前線で活躍できる食品メーカーは、理系学生にとって自らの知識を活かしながら最先端の挑戦を続けられる環境です。
【理系から食品メーカー】将来性を徹底解剖
人々が生きていくためには食は必要不可欠であり、需要が失われることはないため、食品業界は不況にも強いと言われてきました。
ですが、コロナショックのような想定外の事態により、多少環境は変化しています。
消費者向けの食品やステイホーム需要が出た食品はコロナ禍でも好調な一方、飲食店メインの業務用食品メーカーや酒造メーカーなどでは打撃を受け、倒産に至ったケースもあります。
また、少子高齢化に伴う人口減少により、国内の市場規模は減少していくのも事実です。
国内市場の縮小に対応するため、海外展開に力を入れている企業が増えているほか、高齢化に対応する介護食品や長寿社会に健康寿命を延ばす健康食品やサプリメント事業に乗り出す企業も増えています。
【理系から食品メーカー】ES・面接で差をつけるポイント
食品メーカーを志望する理系学生がエントリーシートや面接で他の候補者と差をつけるには、研究で培った専門性や論理的思考力を自分の言葉でしっかりと伝えることが欠かせません。
ここでは、理系ならではの強みの伝え方や面接で聞かれる質問の傾向、研究内容を分かりやすく説明するコツ、逆質問で好印象を残す方法について詳しく解説します。
自己PRでアピールするべき理系ならではの強み
理系学生が持つ強みは大きく分けて三つあります。
一つ目は専門知識です。
大学や研究で学んだ内容が、企業の商品づくりや技術開発に役立つことを伝えられます。
二つ目は論理的に考える力です。
研究で課題を見つけ、仮説を立て、検証する流れを経験しているため、問題を整理して筋道を立てて考える力が自然に身についています。
三つ目は粘り強さです。
実験や分析がうまくいかなくてもあきらめずに工夫し続けた経験は、食品メーカーで新しい商品や技術を作るときにも必ず活きます。
自己PRでは、この三つを自分の研究や学生生活の具体的な出来事と合わせて話すことで、面接官があなたの努力や成果をイメージしやすくなります。
面接で聞かれる質問集
食品メーカーの面接では、研究内容や志望動機に関する質問が中心です。
よく聞かれるのは「研究内容を簡単に説明してください」「なぜ食品メーカーを選んだのですか」「多くの企業の中でなぜ当社を志望するのですか」「入社後に挑戦したい仕事は何ですか」などです。
これらの質問には、研究の内容と食品メーカーを志望する理由をきちんと整理して答えることが大切です。
自分の研究が食品メーカーの仕事にどんな形で役立つのか、会社の特徴と自分の強みがどう重なるのかを、事前にまとめておきましょう。
準備をしておくと、質問に落ち着いて答えられるだけでなく、自分の意欲も自然に伝わります。
研究内容の伝え方のコツ
面接官は理系の専門知識を持っていない場合も多いため、研究を話すときは「分かりやすさ」を一番に考えましょう。
まずは結論から話し、どんな研究をして何が分かったのかを最初に伝えます。
専門用語は使わず、身近な言葉に置き換えて説明することが大切です。
また、その研究が社会や人の生活にどう役立つのかも一言添えると、面接官がイメージしやすくなります。
研究を通じて身につけたデータ分析や課題解決の力、チームで進めた経験なども一緒に伝えると、仕事に直結する力として評価されやすくなります。
逆質問で好印象を与える方法
面接の最後に「何か質問はありますか」と聞かれる逆質問は、会社への興味や入社意欲を示す良いチャンスです。
おすすめなのは「御社が今注力している技術や分野は何ですか」「若手社員が成長するためのサポート制度にはどんなものがありますか」といった内容です。
会社の取り組みや今後の方向性に関する質問は、しっかり企業研究をしていることを伝えられます。
一方で、残業時間や福利厚生の細かい条件ばかりを聞くと、待遇だけを気にしている印象を与えてしまうので注意しましょう。
事前に企業のニュースやホームページを見て気になる点をまとめ、前向きな姿勢が伝わる質問を準備しておくと好印象につながります。
【理系から食品メーカー】よくある質問
食品メーカーを志望する理系学生からは、大学院に進学した方が有利か、食品系以外の学部でも応募できるのか、専門知識をどう活かせるのか、英語力は必要なのかなど、共通した疑問が多く寄せられます。
ここでは、就職活動を始める前に知っておきたい代表的な質問について紹介します。
理系大学院生は有利?
大学院で専門分野を深く学んだ理系学生は、食品メーカーの採用選考で高く評価されます。
特に研究開発職では、大学院での研究計画の立案、実験の設計と実施、結果の分析、論文作成までを一貫して経験したことが強みになります。
これらのプロセスは、企業で新しい製品や技術を開発する際の進め方と多くの共通点があり、入社後に即戦力として活躍できる可能性が高いと判断されます。
ただし学部卒でも、生産技術や品質管理、設備保全など現場に近い職種で活躍する道は十分にあります。
大切なのは、大学院で学んだ知識やスキルを企業でどう活かしたいかを明確に語ることです。
学部卒の場合も、研究で培った問題解決力やデータ分析力を具体的に示すことで、専門性を持つ人材として評価を得られます。
大学院卒か学部卒かに関わらず、自分の強みを整理して伝える準備が選考の鍵となります。
食品系以外の理系出身でも大丈夫?
食品系以外の理系学部を卒業していても、食品メーカーへの就職は全く問題ありません。
化学系の学生であれば、新素材や香料、保存技術の研究開発など幅広い分野で知識を活かせます。
機械系や電気系の学生は、生産設備の設計、ラインの自動化、ロボット導入など生産技術部門で重要な役割を担えます。
情報系の学生は、データ分析や生産管理システムの開発、AIやIoTを活用した生産効率の向上など、今後需要が高まる分野で力を発揮できます。
企業側も多様な専門性を持つ人材を求めており、食品そのものを専攻していなくても、理系として培った実験スキルや論理的思考力、データ解析の経験は強みになります。
面接では、自分の学んだ分野が食品メーカーのどの業務に役立つのかを、具体例を挙げて説明できるようにしておくことが重要です。
専門知識は入社後にどう活かせる?
大学で学んだ知識や研究内容はもちろん役立ちますが、それ以上に評価されるのは研究を通じて得た考え方や姿勢です。
研究では課題を設定し、仮説を立て、実験を繰り返しながら結果を分析する過程を経験します。
この一連の流れは、食品メーカーで新製品を開発したり、生産工程を改善したりする際の基本的な進め方と同じです。
また、研究で培ったデータ処理能力や、失敗しても粘り強く挑戦する姿勢も企業にとって大きな価値があります。
入社後はOJTや研修を通して会社独自の技術や製造ノウハウを学び直しますが、理系学生は問題を論理的に整理して理解する力があるため、習得スピードが速いと評価されます。
大学時代の専門知識に加え、学ぶ力そのものが強みとして認められる点が、理系学生が食品メーカーから高く評価される理由です。
英語力は必須?
英語力が必要かどうかは、企業や職種によって異なります。
国内向けの研究開発や生産技術であれば、入社時点で高い英語力が必須ではない場合も多くあります。
しかし、海外に工場を持つ企業やグローバルに事業を展開する企業では、英語力が重要な評価項目になります。
海外の技術文献を読む、海外研究者との共同研究に参加する、現地スタッフと生産体制を構築するといった場面で、英語による読み書きや会話が欠かせないためです。
将来的にキャリアの幅を広げたいと考えるなら、学生のうちから英語の基礎を身につけておくことは大きな武器になります。
英語力が高ければ、海外研修や海外勤務のチャンスも増え、成長の機会を広げられるでしょう。
現時点で必須ではない場合でも、早めに学び始めることで将来の選択肢を大きく広げることができます。
【食品業界とは?】まとめ
食品業界といっても、食品原料や加工食品を製造するなどジャンルは広く、1つの企業でも多角化が進んでいます。
職種もさまざまで、代表的な職種だけでも、 研究開発、生産管理職、商品開発(マーケティング)、事務系職種、営業職などがあります。
就職人気ランキングトップ10には食品業界から5社が選ばれるほどで競争倍率も高く、採用にあたって文系、理系なども大きく問われません。
ただし、研究職では理系生は専門性を活かせるので有利になります。
とはいえ、全般的に食費業界で重視されるのは人物評価です。
企業が求める人物像を研究し、マッチする人材としてアピールできるよう自己分析や学びを深めていきましょう。

_720x550.webp)


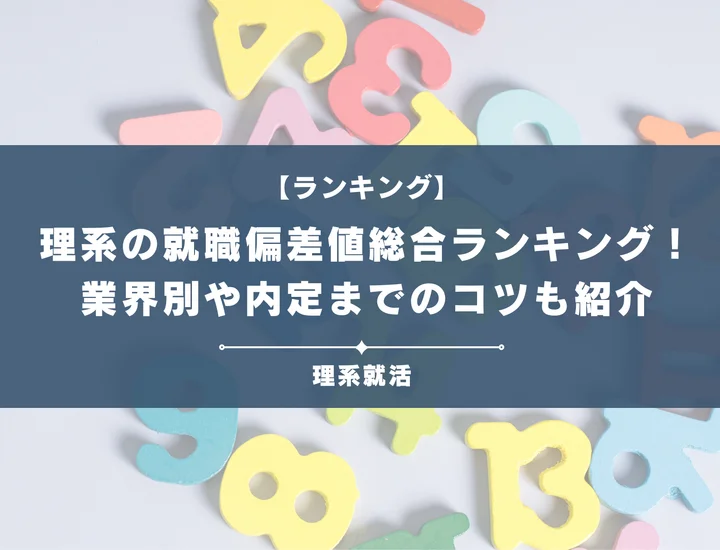






就活コンサルタント木下より
近年では衛生管理の徹底や人材不足を補うためオートメーション化も進んできました。
企業規模にもよりますが、1つの工場や、特定の製造ラインなどを任され、既存の製造システムのチェックと吟味、改良をする場合や新たなシステムを作り出して運用していくケースもあります。