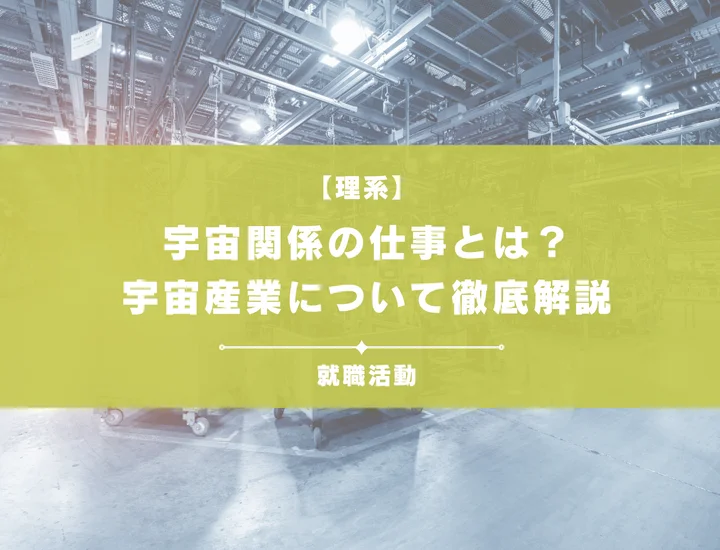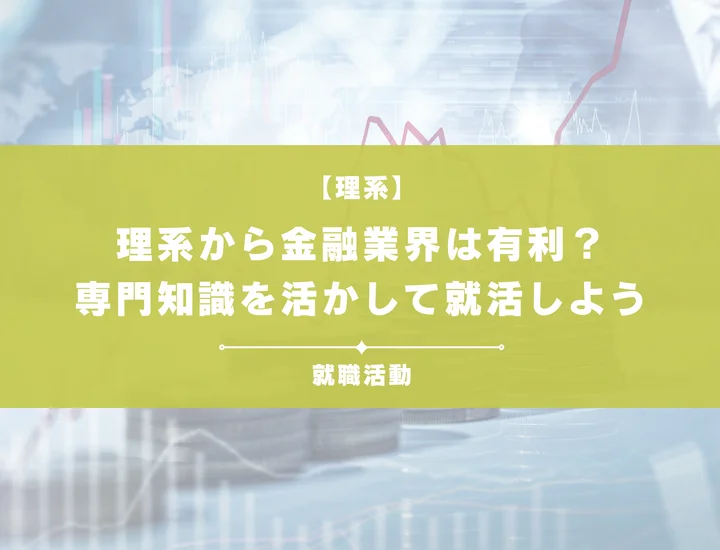HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
日本でのロケット開発や人工衛星の打ち上げ、海外での宇宙飛行士の飛行や民間ロケットでの宇宙旅行など、宇宙業界が賑わっている中、理系生なら宇宙業界の仕事に携わってみたいと考える方も多いのではないでしょうか。
この記事では、宇宙業界への就職の実態についてご紹介していきます。
宇宙業界への就活にあたり、理系生が学ぶべきことや将来性を確認していきましょう。
【宇宙業界の仕事】宇宙業界とは
宇宙業界と言われると、ロケット開発や打ち上げ、有人飛行や宇宙ステーションを思い浮かべる場合や最近であれば、民間ロケットによる民間人の宇宙旅行計画などがイメージされるかもしれません。
宇宙業界の仕事としてロケットの打ち上げ以外にも、 人工衛星の開発やデータ運用・活用などの事業などもあります。
宇宙業界向けの設備や部品の開発や製造、宇宙食などの開発などさまざまな事業があるので、どの分野を選ぶかも理系生の検討課題です。
「宇宙開発」から「宇宙ビジネス」へのシフト
かつて宇宙は国家主導で進められる「宇宙開発」が中心でしたが、現在は民間企業が主役となる「宇宙ビジネス」へと移り変わっています。
背景にはロケット打ち上げコストの低下や人工衛星の小型化といった技術革新があります。
これによりベンチャー企業も参入しやすくなり、宇宙産業の裾野が急速に広がりました。
市場は急成長を遂げており、モルガン・スタンレーは2040年までに世界の宇宙産業市場が1兆ドルを超えると予測しています。
成長をけん引しているのは、衛星データを活用した新しいサービスや、一般人が参加できる宇宙旅行などの新興分野です。
従来の国家プロジェクトに限らず、通信、農業、防災、観光といった幅広い領域で宇宙の技術が利用されるようになりました。
この成長が期待される分野とは
宇宙産業の中でも特に成長が期待されるのが、衛星データ活用、宇宙旅行・居住、デブリ除去の三分野です。
人工衛星から得られる画像や気象データは、農作物の管理や災害時の状況把握、都市計画など多方面で利用されています。
今後は物流や金融といった新しい産業分野にも応用が進むと考えられます。
また宇宙旅行はスペースXやブルーオリジンといった企業によって現実化が進んでおり、将来的には月や火星での居住や資材調達も視野に入っています。
さらに深刻な課題となっているのがデブリ、いわゆる宇宙ゴミの問題です。
役目を終えた人工衛星や破片が増え続ければ、新たな打ち上げや運用に支障をきたす恐れがあります。
そのため除去技術の開発は必須であり、今後大きなビジネスとなる可能性が高いです。
【宇宙業界の仕事】宇宙業界の職種
宇宙業界の事業も幅広ければ、その中で携われる職種もさまざまです。
ここでは特に理系生に向いている職種についてご紹介します。
ロケットや人工衛星、宇宙ステーションなどの設計や開発の仕事、ロケットや人工衛星などの運用の仕事、ロケットや人工衛星をはじめ、宇宙ステーションや宇宙食、宇宙飛行士の装備などの研究、宇宙の仕組みに関する研究など多岐にわたる研究に携わる仕事などが挙げられます。
宇宙業界の仕事内容について、職種ごとに分類しながら紹介していきますので、興味がある職種はあるか、理系学部で学んできたことが活かせそうな職種があるか検討してみましょう。
設計・製造
設計・製造の分野は、宇宙産業を支える基盤となる重要な仕事です。
ロケットや人工衛星を構想し、実際に形にしていく過程では高度な専門知識と正確さが求められます。
設計には構造設計、熱設計、電子回路設計などがあり、骨組みの強度を確保しつつ、極端な温度差や放射線といった宇宙環境に耐えられる仕組みを考えます。
製造・組み立ての段階では、設計図に沿って部品を精密に加工し、組み立てていきます。
ミスが許されない工程のため、品質管理やテストも徹底して行われます。
宇宙空間は過酷で一度打ち上げれば修正が難しいため、設計や製造の正確さがミッションの成否を大きく左右します。
そのため材料工学、機械工学、電子工学など幅広い専門性が活かされる分野であり、理系人材に多くの活躍の場が用意されています。
運用
ロケットや人工衛星は打ち上げた後も、計画通りに稼働し続けなければ意味がありません。
この役割を担うのが運用の仕事です。
地上から24時間体制で監視を行い、異常が発生した際には即座に対応します。
主な業務には軌道計算、データ監視、トラブル対応があります。
軌道計算では衛星の位置を正確に維持するための指示を送ります。
データ監視では膨大な情報をチェックし、機能が正常かどうかを常に確認します。
トラブルが発生した場合は原因を特定し、遠隔操作で修正を行う必要があります。
こうした作業には数学的な計算力、物理学的な知識、システム運用の技術が求められます。
安全で確実なミッション遂行を支えるために欠かせない業務であり、宇宙産業の縁の下の力持ちともいえる存在です。
研究
研究職は、宇宙の未解明な現象を探ると同時に、将来の技術革新を切り開く基礎研究を行います。
分野は天文学や惑星科学にとどまらず、材料工学やロボット工学など幅広い領域に及びます。
天体物理学の研究では銀河やブラックホールの仕組みを探り、宇宙の成り立ちを解明することを目指します。
惑星探査では探査機を開発し、火星や小惑星の表面や大気のデータを分析します。
また新素材の研究では、軽量かつ高耐久な素材を開発し、ロケットや宇宙基地の建設に活用されます。
基礎研究はすぐに成果が見えにくい分野ですが、将来的には新たな産業や生活の発展につながる重要な基盤です。
研究職は好奇心と粘り強さが求められる仕事であり、宇宙産業の未来を支える要となっています。
IT・データサイエンス
宇宙産業においてITとデータサイエンスの役割はますます大きくなっています。
ロケットの制御システムや衛星運用の管理はもちろん、衛星から得られる膨大なデータの分析にIT技術が不可欠です。
ソフトウェア開発ではロケットの飛行制御や衛星データ解析システムを設計します。
データ解析では気象観測や地球環境モニタリングに用いる情報をAIで処理し、農業、防災、物流などの分野に応用します。
また宇宙システムは重要なインフラでもあるため、サイバーセキュリティの確保も欠かせません。
ハッキングや攻撃から衛星や管制システムを守るための技術が求められています。
データサイエンティストやシステムエンジニアなどの専門職の需要は高まっており、情報工学やデータ科学を学んだ理系人材が活躍できる場が急増しています。
地上設備の開発・保守
宇宙産業は宇宙空間だけで成り立つものではなく、地上設備の存在が不可欠です。
ロケットを打ち上げる発射施設や、人工衛星と通信するための大型アンテナ、管制室のシステムなどが整っていなければ運用は成り立ちません。
設備開発ではこうしたインフラを設計・建設し、最新技術を導入して効率化や安全性を高めます。
システム運用では管制室のコンピュータやネットワークを管理し、24時間体制で安定した通信を確保します。
また保守・点検の業務では定期的に設備をチェックし、故障やトラブルを未然に防ぐことが求められます。
地上設備は派手さはないものの、宇宙ビジネスの基盤を支える極めて重要な役割を担っています。
理系の専門知識を活かして、設計、運用、保守の各段階で活躍できる場が広がっており、将来性も高い分野です。
【宇宙業界の仕事】宇宙業界の文系職種とは
宇宙業界というと、理系の専門家が中心という印象を持つ人も多いでしょう。
しかし近年の宇宙ビジネスの拡大に伴い、文系出身者が活躍できるフィールドも広がっています。
ここでは文系人材が担う具体的な仕事の内容を詳しく解説します。
営業・マーケティング
営業やマーケティングの仕事は、宇宙業界の技術やサービスを顧客に届ける重要な役割を担います。
人工衛星の観測データを農業や防災、物流などに応用する提案を行ったり、宇宙関連サービスを一般消費者向けに広めたりするのが主な業務です。
この職種では専門的な内容を分かりやすく説明する力が必要であり、顧客の課題を理解して解決につなげる提案力も求められます。
また、宇宙産業は新規参入企業も多いため、マーケット調査や新しい需要の開拓も大切な仕事です。
理系と連携しながら市場に最適な形でサービスを届ける点が特徴であり、成長性の高い分野で活躍できるのが魅力です。
法務・知財
宇宙ビジネスが拡大するにつれて、法務や知財の重要性は高まっています。
宇宙空間は国家を超えて利用されるため、国際的なルール作りや条約への対応が欠かせません。
企業で働く場合は、自社の契約内容を整備したり、人工衛星やロケットに関連する知的財産を管理したりする業務があります。
特に特許の取得やライセンス契約の調整は、研究開発を進める上で大きな役割を果たします。
また、法務部門はトラブル発生時のリスク対応やコンプライアンスの徹底にも関わります。
知財部門は、自社の技術を守りつつ他社との競争を有利に進めるための戦略を練る役割を担います。
広報・教育
広報や教育の職種は、宇宙への関心を社会に広める役割を担っています。
ロケット打ち上げのライブ配信や研究成果のプレスリリースを作成する広報活動は、宇宙産業への理解や期待感を高めるために欠かせません。
また、子供向けの宇宙教育イベントやワークショップの企画は、次世代の人材育成につながります。
広報ではメディア対応やSNS運用など、一般の人々に興味を持ってもらえる発信力が求められます。
教育活動では専門的な知識をかみ砕いて伝える力や、参加者の関心を引き出す工夫が必要です。
これらの仕事は理系の成果を分かりやすく社会に届ける橋渡しの役割と言えます。
【宇宙業界の仕事】理系学生が学ぶべきこと
宇宙業界に就職したい理系学生が、就活前に大学の授業やゼミ、さらには独自に学んでおくべきことはどんなことが挙げられるでしょうか。
学んでおくべきことは、 どの分野に就職したいかによっても異なります。
財務などの事務系の仕事を除く仕事は、専門知識を持つ理系生が占めているため、どんな仕事をしたいのか、まず検討してみましょう。
宇宙に関する知識やロケット開発のための工学や技術、運行に関する知識や技術など、幅広い分野や職種があるため、興味を持った分野や職種でどんな知識や技術が求められるのか、活用できるのかを考えて、学びを深めることが必要です。
さらに採用に有利に働くよう、ほかの理系生と差別化をするための学びも欠かせません。
理系学生が学ぶべき分野
宇宙業界に就職したいと、大学受験の段階から考え、宇宙科学や宇宙工学といった学部を選んで進学した方もいることでしょう。
そういった方は、その専攻を活かし、学んできたことから職種などを考える場合や逆に志望する職種に就くためには、よりどんな知識や技術を得ておけば良いのかを考えて、能力を上げていくことが必要です。
大学に宇宙をターゲットにした専攻がない場合でも、物理や化学、天文学、機械、電子、電気などの分野が役立ちます。
それらに関わる研究をしておくことは就職に有利になりますので、ロケットや人工衛星開発や運用などに役立つ学問を調べ、どのように役立つかをしっかり検討したうえで、知識や技術を習得しておきましょう。
ほかの理系学生と差別化をするために
宇宙業界を目指す理系生は、そのほとんどが専門知識や技術を習得してアピールしてきます。
宇宙工学や宇宙科学、航空工学など、一般的な理系学部や専攻に秀でる有利な専攻もありますが、機械工学や電気工学など、専門分野とは言えない場合には、ほかの理系生と差別化できる技能を備えておくと有利に働きます。
必須資格などはありませんが、 英語の試験(TOEIC)などは受けておくべきです。
英語力は宇宙業界を目指す理系生にとって、必要不可欠な能力となるので、TOEICの高いスコアはアピール材料になります。
また、理系学生は大学の研究に忙しく、インターンなどに参加している学生が少ない傾向にあるので、時間を作ってOB訪問を実施しておくと有利に働きます。
インターンや研究室で経験を積む
宇宙業界を目指す理系学生にとって、研究室やインターンでの経験は将来のキャリアに直結する大切な要素です。
研究室での活動では、自身の専門分野を深めるだけでなく、チームで研究を進める中で協調性や問題解決能力を磨くことができます。
実験や解析を重ねる過程で課題に直面し、それを克服する経験は企業が重視する実践的な力の証明となります。
また研究成果を学会で発表する経験は、自分の考えを論理的にまとめて伝える力を養う場となり、就職活動において大きな強みになります。
一方でインターンシップは、企業で実際の業務に触れながら、働き方や求められるスキルを理解する貴重な機会です。
特に宇宙業界のインターンは募集数が多くないため、早めに情報を集め、応募の準備を進めることが重要です。
【宇宙業界の仕事】宇宙関連企業に就職するには?企業選びのポイント
宇宙業界と一口に言っても、宇宙に関連する事業を持っている業界はたくさんあります。
ここでは宇宙産業に関わる業界について解説していきます。
メーカー
メーカーは、宇宙産業における「モノづくり」の中心的な役割を担う存在です。
JAXAや三菱重工業といった企業は、ロケットや人工衛星の設計、開発、製造を手がけています。
巨大なプロジェクトの一員として、推進システムや構造設計、通信機器といった高度な技術開発に携わることができます。
宇宙空間は極めて過酷な環境であり、耐久性や信頼性を確保するための精密な技術が求められる点が特徴です。
またロケットの打ち上げや衛星の運用には、多くの研究者や技術者が関わり、チームとして成果を出すことが重要になります。
メーカーで働く魅力は、自らの手がけた技術が実際に宇宙で活躍する瞬間を見届けられることにあります。
ベンチャー
ベンチャー企業は、宇宙ビジネスの最前線で新しい価値を生み出している存在です。
ispaceは月面探査を、アストロスケールはデブリ除去を目指すなど、独自の技術やサービスで世界的に注目されています。
社員数が少ないため、一人ひとりの裁量が大きく、事業立ち上げの初期段階から深く関われるのが魅力です。
大企業のような安定性は少ないものの、その分スピード感のある意思決定や挑戦的なプロジェクトに携わる機会が豊富です。
ベンチャーでは、技術職に限らず企画や広報、資金調達といった幅広い業務を担当することもあり、多様な経験を積めます。
不確実性の高い環境だからこそ、柔軟性や主体性が求められ、自らのアイデアを実現する力が試されます。
新しい市場を切り開くダイナミズムに惹かれる人にとって、ベンチャーは大きな成長の場となります。
IT・コンサルティング企業
ITやコンサルティング企業は、宇宙産業と他業界をつなぐ役割を担っています。
人工衛星から得られる膨大なデータを活用し、農業の効率化や物流の最適化、防災計画の策定など、幅広い分野の課題解決に貢献しています。
また宇宙関連のシステム開発やソリューション提案を通じて、顧客のニーズに合わせた新しいサービスを生み出すことも重要な業務です。
この分野では、ITスキルやデータ分析力に加えて、ビジネス課題を整理し解決に導くコンサルティング力が求められます。
宇宙産業が拡大する中で、異業種との連携が進んでおり、IT企業やコンサルティング企業の存在感はますます大きくなっています。
理系出身者にとっては、技術的な知識を活かしつつ、ビジネス的な視点を磨くことができるキャリアパスが広がっています。
技術と経営の両面から社会に貢献できるのが、この分野の魅力です。
【宇宙業界の仕事】宇宙業界にいくなら海外も見ておくべき
今の宇宙業界はアメリカやロシアを中心に、海外の方が圧倒的に強く、技術も市場も進歩しています。
日本人宇宙飛行士も数々誕生し、宇宙で活躍していますが、有人飛行がアメリカ、ロシアでしか実現していないことからも、日本が後れを取っていることはわかるでしょう。
人工衛星などは日本の技術も評価がされていますが、ロケット開発や有人飛行については、海外のほうが市場規模も技術も日本より上です。
そのため、より高いレベルで学びたいのなら海外での就職も視野に入れましょう。
宇宙業界を目指す方の最高峰であるNASAをはじめ、スペースX、ヴァージン・ギャラクティカなどの民間企業も、技術力を増しています。
海外企業で働く魅力とキャリアパス
宇宙ビジネスの市場は約8割が海外にあり、グローバルな舞台での活躍は大きな魅力です。
SpaceXやBlue Originなどの企業では、世界最先端の技術開発が進められており、直接その現場に携われることは大きな経験となります。
海外企業で働く魅力は、最新技術に触れる機会が豊富なこと、多国籍なチームでの仕事を通じて異文化理解や柔軟な思考を身につけられることです。
また海外での経験は、キャリアアップや転職においても高く評価され、将来的な選択肢を大きく広げてくれます。
プロジェクトの規模も大きく、地球規模の課題解決や新しい宇宙利用の可能性に直結する仕事に携われます。
語学力や専門性が必要にはなりますが、挑戦する価値の高いキャリアパスです。
海外企業で働くために必要なスキルや心構え
海外企業で働くためには、まず英語力が必須です。
単に日常会話ができるレベルではなく、専門的な議論や交渉ができるだけのスキルが求められます。
さらに重要なのが専門性であり、特定の分野で突出した知識や実績を持つことが強みになります。
海外では専門性を武器にチームに貢献できる人材が重視される傾向があります。
また主体性や積極性も欠かせません。
日本に比べて自己主張が求められる場面が多いため、自分の意見をはっきり伝え、積極的に行動する姿勢が評価されます。
多国籍なチームで働く場合、異なる価値観や文化を理解しつつ、自分の考えを柔軟に調整することも大切です。
語学力、専門性、主体性の三つを兼ね備えることで、海外企業でのキャリアを築く道が開けます。
【宇宙業界の仕事】面接で聞かれること・アピールするべきこと
宇宙業界の面接では、単なる憧れや興味を伝えるだけでは不十分です。
なぜその企業を選び、自分の強みをどう活かすのかを具体的に示すことが求められます。
また面接官は知識以上に、熱意や論理性、協調性、主体性といった資質を重視しています。
ここでは面接で問われやすい内容と効果的なアピール方法を解説します。
なぜ宇宙産業で働きたいのか?
面接でよく問われるのが、宇宙産業を志望する理由です。
ここで大切なのは「宇宙が好きだから」という抽象的な答えではなく、なぜその企業、その仕事でなければならないのかを具体的に示すことです。
例えば、ある企業が取り組むロケット開発や衛星データサービスに感銘を受け、自分の専門分野や研究成果とどう結びつけられるかを語ると説得力が増します。
「この企業の特定のプロジェクトに共感し、自分の培った知識や強みで貢献したい」といった形で、自分の経験と企業の事業を関連づけることが重要です。
志望理由を深掘りする際には、事業内容だけでなく企業が掲げる理念や社会的な役割にまで視点を広げると、面接官に強い印象を与えられます。
自分の強みをどう活かすのか?
宇宙業界の面接では、自分の強みをどう活かせるかを具体的に伝えることが求められます。
強みを語る際は単なる性格的特徴ではなく、学生時代の経験を通じて身につけた力を根拠とすることが重要です。
例えば、研究室でのチーム活動の中で意見が対立したとき、冷静に状況を整理し、双方の意見を調整して解決に導いた経験があるなら、それを具体的に説明します。
その上で「この協調性を企業のプロジェクト開発に活かしたい」とつなげることで、面接官に実際の活躍イメージを与えられます。
課題解決能力をアピールする際は、問題の発見から解決までのプロセスを論理的に整理して伝えることが有効です。
宇宙産業では大規模で複雑な課題に取り組むため、これまでの経験がどのように役立つかを具体的に示すことで評価につながります。
面接官がチェックするポイント
宇宙業界の面接では、知識や学歴だけでなく、学生が持つ資質や姿勢が重視されます。
まず大切にされるのは宇宙への熱意です。
「なぜこの業界で働きたいのか」という動機を問うことで、どの程度本気で取り組もうとしているのかを確かめられます。
次に重要なのが論理的思考力です。
宇宙開発は複雑な課題が多く、問題を整理して解決策を導き出す力が必要不可欠です。
さらに、コミュニケーション能力も評価されます。
専門性の高いメンバーと協力して進める場面が多いため、知識を共有しながら円滑に作業を進める力が問われます。
最後に、主体性や行動力も重要です。
自ら課題を見つけ、積極的に取り組む姿勢があるかどうかは、実務で活躍できるかの判断基準となります。
まとめ
宇宙業界は将来性も高く、未知の分野の研究や莫大な費用が投下されるロケットや人工衛星の開発や運用など、理系生にとっては興味深く、やりがいのある仕事が期待できる業界です。
宇宙業界の職種にはロケットや人工衛星の設計・製造をはじめ、運用に携わる仕事、未知なことが多い宇宙やロケット開発、宇宙食や装備などの研究など、幅広い仕事があります。
理系生が学ぶべきこと学んでおくべきことはどの分野に就職したいかによって異なりますが、宇宙科学、物理や化学、天文学、機械、電子、電気などの分野をはじめ、ほかの理系生と差別化をするための英語力やOB訪問での学びもポイントです。
就活にあたっては、日本より技術でも市場開発でも高いレベルにある海外就職も視野に入れましょう。