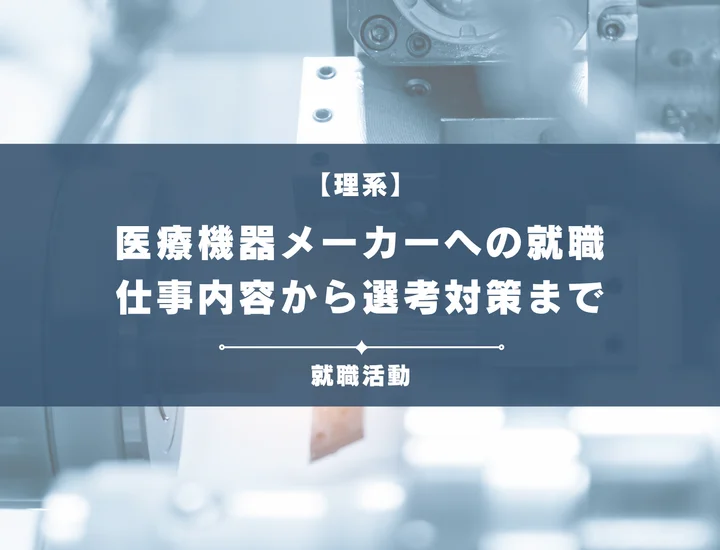HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
【大学院とは】そもそも大学院とは

大学院試験は9〜10月におこなわれる秋入試と、1〜2月におこなわれる春入試があります。
本記事を読まれている大学生の方々は進学について悩んでいる方も多いでしょう。
大学入学前から大学院への進学も視野に入れている方や、学部1〜2年生のうちに院試受験について検討する方もいると思います。
どちらにしても、早めに大学生活のプランを設計して、目標に向かって取り組むのは素晴らしいことです。
今回は、文系・理系ごとに大学院に進学するメリットについて、いくつかの角度からご紹介いたします。
【大学院とは】そもそも大学院とは
そもそも大学院とはどの様な場所なのでしょうか。
大学院とはスペシャリストになる場所です。
大学で学んだことよりも深く学んでいきます。
学費
公立70〜100万程度
私立(文系)0~180万円程度
私立(理系)100~180万円程度
国立大学の場合、一般的には授業料が54万円/年、入学料が28万円となります。
私立大学は、基本的には国公立よりも学費が高くなるケースがほとんどです。
例として、授業料が平均70万円程度/年、入学料が20万円、諸経費が加わります。
参考国立:国立大学法人法施行規則等関係省令について
参考私立:私立大学等の令和元年度入学者に係る学生納付金等調査結果について
【大学院とは】大学院には4つ種類がある!
大学院は大きく分類して4つの種類に分かれます。
学部のある大学院・独立研究学科・専門職大学院・大学院大学といった4つがあります。
それぞれの特色はまったく異なるのです。
そのため、「自分がなんのためにどの大学院を目指すのか」について考える際は重要なポイントです。
どの種類の大学院を卒業したかによって、その後の就職に与える影響も大きく変わります。
それでは、それぞれの特色について、1つずつ確認していきましょう。
①学部をもつ大学院
多くの大学生が進学する一般的な大学院は「学部をもつ大学院」です。
こちらは、大学の学部(学士課程)で学んだ知識を発展・応用させながら、さらに、専門的かつ高度な研究をおこなう学士課程の上級機関です。
文系でいえば、文学部の研究機関である「文学研究科」や法学部の研究機関である「法学研究科」が該当します。
理系では理学部の研究科「理学研究科」などがこれに当たります。
大学の学部課程では、多様な一般教育科目を幅広く学ぶのです。
しかし、研究科へ進むと一気に専門的な内容に絞られるので、自分の選んだ専攻で後悔しないかどうかをよく考えておくことが必要でしょう。
②独立研究科
独立研究科では、さまざまな学部の卒業生を受け入れ、各々がもつ専門性を活かして新たな研究分野を創出しています。
そのため、基礎となる学部組織(学士課程)はなく、他大学出身者が入学してくる割合も比較的高いです。
具体的には、国際的視野でエネルギー・環境問題などの解決に取り組む「エネルギー科学研究科」や、主にビジネスにおける構想力や戦略的な思考を高める「ビジネスデザイン研究科」、ほかにも「情報学研究科」などがあります。
既存の枠にとらわれず、学際性の高さが特徴です。
③大学院大学
大学院大学は、基礎となる学部(学士課程)の大学自体をもたない大学院のみの機関です。
国立の「総合研究大学院大学」、公立の「情報科学芸術大学院大学」、私立の「国際大学」「大宮法科大学院大学」などが該当します。
既存大学から独立した教員、施設、独自の教育と研究目的やプログラムなどを有した機関で、「独立大学院」「独立大学院大学」とも呼ばれます。
そのプログラムは、ほかの大学院と大きく違い、5年一貫性の博士課程が基本です。
④専門職大学院
最後は実務に根ざしたスキルを習得し、高度な専門職人材を養成する場が、専門職大学院と呼ばれる大学院です。
実践的な業務遂行能力を身につけることが目的なため、研究志向の方には不向きでしょう。
特に、産業技術分野での専門職業人材育成を目指しており、一般的な工学系大学院と同じだけの研究員のほか、第一線で活躍してきた実務家教員も配置されているのが特徴です。
すでに社会で活躍している職業人の、さらなる学びの場としての役割も果たしており、社会人入学も多い傾向にあります。
【大学院とは】大学院進学のメリット
それでは、大学院の種類を把握したところで、つぎに大学院へ進学する具体的なメリットを確認しましょう。
なんとなく大学院に進学しても、大切な時間を無駄にしてしまいます。
また、目的と得られるメリットを明確に把握することで、ハードな研究にもめげず、実りある院生生活を送ることができるでしょう。
今回は、就職におけるメリットを中心に、大きく分けて3つご紹介いたします。
身につけられる教養面、就職後の給与面、就職における選択肢の面といった3点です。
高い専門性が身につく
何より、学部卒生よりも最低2年以上はより専門的な研究をするため、高い専門性を見につけられます。
特に理系の場合は、技術職や研究職などで修士以上の学位を求められるケースが多々あります。
大学院進学を視野に入れておかなければ就けない職種もあるのです。
また、興味のある分野をより深く研究することができます。
好きな研究に没頭したい方には最高の時間となるでしょう。
文系の場合も、専攻する分野において詳しい教授など、普段はなかなか出会えない人と出会える可能性もあります。
大学院では学生と教授の距離感が近いので、他大学の教授であっても、同じ専攻分野であれば関わる機会が増えます。
そのような人脈から就職へとつながっていく場合もあり、自分の研究したい分野に没頭することは、専門性が身につくだけではなく、それに関連した人脈も広がるといったメリットがあるでしょう。
初任給が学部卒より高い
高い専門性をもっていることから、就職時の初任給は学部卒より高くなることも、大学院進学のメリットの1つです。
具体例ではトヨタの場合、学部卒では207,000円・院卒では229,000円と約2〜3万円の差があります。
厚生労働省のデータによると、令和元年の学歴別初任給(年収)は、男女合わせたもので学部卒が2,102,000円、院卒が2,389,000円でした。
ただすべての企業で、初任給の設定にこのような差があるとも言い切れません。
同じ年に入社した新入社員の初任給が一律に設定されている企業ももちろんあります。
しかし、IT業界などでは能力における給与設定もメジャーとなりつつある風潮です。
大学院進学を検討する際には、自分のキャリアプランも視野に入れたほうが、後々役立つことも多いでしょう。
理系の場合は就職先の選択肢が増える
理系の場合、大手メーカーであればあるほど、採用時の必須学歴が院卒以上であるケースも多いです。
研究職であれば、修士以上の学歴を求められることも多く、大学院進学前後のタイミングで志望する職種を視野に入れておくことは重要でしょう。
特に、研究開発職や技術職の場合、自身で課題を発見し、その解決までのプロセス構築と実際の研究、問題解決まで遂行する能力が備わっているとして、院卒生は有利になる傾向があります。
そのほか、生産技術や品質管理、セールスエンジニアなどといった職種は、電気・通信系や化学・IT・金融系、農業系や製薬系など、さまざまな業界で必要とされています。
エンジニアやプログラマーなどの専門職も、院卒生に人気です。
大学院時代に身につけた能力をどの分野で活かせるかは、特に理系の場合自分で思っている以上に選択肢が多い可能性もあるといえるでしょう。
【大学院とは】大学院進学のデメリット
メリットがある一方で、大学院へ進学することによるデメリットとは、どのようなことがあるのでしょうか。
学費など費用面での負担が増えることや、学部時代に比べて多忙になることなども考えられます。
今回はこれら以外で、大きく分けて2つのデメリットをご紹介していきます。
社会人経験に関する点と、給与面からは生涯年収の減少という点について、大学院進学のデメリットを掘り下げていきましょう。
大学院へ進学するかどうか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
授業・研究が大変
大学によって変わりますが、大学院は学部時代より研究が多いイメージがあります。
しかし、大学院にも授業がある場合が多数です。
もし通っていた大学の院に進学する場合は先取りできますが、他大学の場合は先取りができません。
研究は増える一方なのに授業はあまり変わらない為大変だと言えるでしょう。
社会人になるのが遅れる
大学院へ進学すると、学部卒生に比べて、社会に出るまで少なくとも2年以上は後れを取ることになります。
長い場合だと約5年間大学院生活を送ることになります。
その間に新卒で入社した学部卒生は新人期間を終え、中堅と呼ばれるポジションに差し掛かっていくでしょう。
もちろん大学院生のあいだは、会社員として働く学部卒生より収入は圧倒的に少ないケースが多く、学部卒生が仕事で結果を出していく姿に挫折してしまう院生もいるようです。
また、社会人としてのマナーは現場で実践しながら学ぶことも多いです。
その点から院生は、年齢の割に社会経験が少ないという点はデメリットになるといえます。
しかし、それが一概に悪いとも言い切れません。
院生としての期間に十分な価値はあるので、社会人になるのが遅れることをデメリットととらえるかは人によるでしょう。
生涯年収が減る
前述の通り、社会人としてのスタートが遅れるため、生涯年収としては一般的に、学部卒の場合よりも減ってしまう傾向があります。
初任給は院卒の場合のほうが高いことはわかりました。
しかし、大学院時代の2〜5年間にかかる学費やその他諸経費を考えると、先に働いている学部卒の方が収入は多くなるのです。
ただ、もちろんこのような場合だけではなく、キャリアを積むにつれて院卒生の給与はどんどん上がっていくケースも多くあります。
途中で転職などといった出来事があれば、院卒であっても給与が減る可能性もあり、これも人によって異なる部分が大きいです。
どのみち、社会人としてのスタートが早く、大学院分の学費がかかっていない学部卒の方が、生涯年収の見込みとしては多くなるでしょう。
【大学院とは】理系と文系で行くべきかどうかが変わる!?
ここまで、大学院進学におけるメリットとデメリットをそれぞれ確認してきました。
さまざまな観点から、主にメリットのほうが多く目についた方も多いかと思います。
ただ、理系のほうが進学へするメリットが多くあるように感じた方が多いかもしれません。
文系の場合は、実際のところ大学院進学におけるメリットは、どの程度あるのでしょう。
ここからは、理系と文系それぞれの立場から、進学におけるメリットを再度確認していきます。
理系生は行ったほうがよい
文部科学省の平成30年度の調査によると、理学部と工学部の大学院進学率は約40%となっています。
つまり、就職者とほぼ同等の割合で大学院へ進学する卒業生がいます。
やはり専門分野でさらに深く研究を続けることで、就職で有利になりやすいのが理系の特徴です。
経済的な条件などをクリアできるようであれば、理系生は大学院へ進学するほうがよいでしょう。
また、大手企業の場合、研究職などであれば採用条件が院卒(修士以上)であることもあるのです。
メーカーでの研究職を志望する場合は、大学院へ進学したのち、学校推薦で就職が決まる例もあるので、院試受験はほぼ必須と考えたほうがよいでしょう。
しかし、さまざまな事情から進学が難しい状況の方もいると思います。
できるだけ早い段階から就職への展望をもち、進学が必要かどうか、可能かどうかといった情報を集めることも大切でしょう。
文系生は行かなくてもいい場合がある
なお、文系の場合は、理系ほど大学院への進学が就職に与える影響は大きくありません。
文系院生として身につけた専門性を活かせる職場は、一般的には少ないのです。
そのうえ、就活時には学部卒生より年齢が高くなるため、採用されにくくなる可能性もあるのです。
一般企業への就職を考えている文系生であれば、大学院への進学は重要でないのです。
本記事をここまで読んで、進学について悩んでいる方は、一度研究室に見学へ行ってみることをおすすめします。
そこで授業のレベルに不安を覚えたり、就職への不安が少しでも頭に浮かんだりするようであれば、進学しないほうがよいでしょう。
しかし、「どうしても好きな分野の勉強を続けたい」「なんらかの目的が明確にあり進学したい」という場合は、思い切って院試を受けるのをおすすめします。
【大学院とは】大学院に進学すべき人とは?
さまざまな背景を知ったところで、実際に大学院へ進学すべき人とは、どのような人のことなのでしょうか。
決して安くはない学費を払ってまで進学しても、なんとなくで進学してしまったのであれば、それは時間の無駄です。
大学院での研究を意義あるものにして、さらに就職へもプラスの影響を与えてこそ、進学した意味があるといえます。
下記のような明確な理由をもってこそ、大学院への進学が意味のあるものになるといえるでしょう。
大学院でやりたいことがはっきりしている人
研究すること自体が楽しいと感じていて、なおかつ自分の研究したい分野が明確になっている人は、ぜひ大学院へ進学しましょう。
院生はやることもたくさんありますが、多くの場合でメインは研究です。
それが苦痛に感じるようであれば、挫折してしまう可能性も高くなり、状況によっては心身を病んでしまうこともあり得ます。
自分の研究したい分野がはっきり定まっていて、その分野のプロフェッショナルを目指して専門性を高めたいという人には絶好の場です。
研究開発系の職業を志望する場合も、研究分野を絞った就職へ向けての準備期間として、院生生活を送ることができます。
このように、やりたいことや目的が明確な人こそ、大学院へ進学すべきでしょう。
キャリアチェンジしたい人
もしくは、キャリアチェンジしたい人にも大学院進学はおすすめです。
たとえば、大学では農学部だったけれど、就職を見越して工学研究科へ進むという人や、やりたいことを実現するために、より踏み込んだ研究をしようと他大学の大学院へ進む人もいます。
このように、就職のために違う分野を専攻する、または、単純に学びたいことが変わった場合にも進学は適切といえるでしょう。
本格的なスキルや専門知識を身につけることは就職にとってもちろん有利です。
もちろん、これから需要が増えそうな分野を先取りして専攻しておくことも、未来の自分のためになります。
大学までは自分の興味を専攻して、大学院で仕事をしていくための土台作りのために別の分野を研究したい、という人にもおすすめです。
【大学院とは】就職するか院に行くか迷っている人
これからの人生に大きく関わる選択です。慎重に検討しましょう。
就職と大学院進学を並行して準備しよう
大学卒業後就職するか大学院に進学するかどちらを選択しても良いように並行して準備しておくという手もあります。
就活をしたくないから院に行く場合には注意が必要
就活に失敗したからといって大学院に進学すると就職の幅が広がる可能性もありますが、安易に大学院進学を決めてしまうと失敗してしまうこともあります。
【大学院のメリット】修士と博士の違い
大学院に進学することは、自分の専門性を高めたり将来の進路を広げたりするうえで、大きな意味を持ちます。
大学院には主に修士課程と博士課程の2つがあり、それぞれの目的や期間、就職先には明確な違いがあります。
ここでは、修士課程と博士課程の違いについて、期間・目的・就職面の観点から詳しくまとめます。
修士課程とは
修士課程は、大学卒業後に進む大学院の課程で、期間はおよそ2年間です。
この課程では、学部時代に学んだ知識をさらに深め、自分の専門分野における理解を広げることが目的となります。
研究に取り組む中で、論理的思考やデータの読み取り、文献調査、発表など、社会に出てからも活用できる実践的なスキルが身につきます。
また、研究だけでなく、グループワークや学会での発表を通じて、協調性やプレゼン能力も鍛えられます。
修了後は、企業の研究開発職や専門職、エンジニアなど、学部卒よりも高い専門性を求められる職種に就職する人が多くなります。
博士課程とは
博士課程は、修士課程を修了した後に進むことが一般的で、通常3年間の期間が設けられています。
この課程の目的は、独立した研究者として、自らの力で新たな知見を生み出すことです。
既存の研究を学ぶだけでなく、自分自身で問いを立て、仮説を立てて検証し、成果を論文という形で発表するところまでを求められます。
そのため、高い集中力と忍耐力、そして長期的に物事に取り組む姿勢が必要です。
世界で初めての発見を目指す研究もあり、まさに学問の最前線に立つことになります。
博士号を取得することで、大学教員や研究機関の研究員など、専門性の高い分野でのキャリアが開かれます。
それぞれの期間と目的
修士課程の期間は一般的に2年間で、学部時代に得た知識をさらに深めていくことが中心になります。
この中で、論文執筆や実験、文献調査などを通じて、専門性と研究能力を高めていきます。
目的は、既存の研究を理解し、その知見を応用・発展させる力を養うことです。
社会に出てから専門性を活かして働きたい人にとっては、非常に実用的なステップとなります。
一方、博士課程は、修士課程を終えた人がさらに3年かけて進むことが多く、自立した研究者として新たな価値を生み出すことが求められます。
学術界の最前線で成果を出すことが目的で、最終的には学位論文を提出し、厳しい審査を通過する必要があります。
修士が知識を深める場であるのに対し、博士は知識を創り出す場であるという違いが明確です。
就職における違い
修士課程を修了すると、多くの企業が設けている修士採用枠に応募することができます。
学部卒よりも高い専門性を評価され、研究開発職やエンジニア、システム設計、データ分析などの分野で採用される傾向があります。
また、初任給が学部卒よりも高めに設定されている企業も多く、キャリアのスタート時点から専門性を活かせることが魅力です。
一方、博士課程修了者は、さらに高度な知識と研究能力を活かす職種に進むことが多くなります。
大学や研究機関でのポストを目指す人も多いですが、民間企業でも新事業開発、技術戦略、コンサルタントといった専門性の高い職務で活躍できます。
ただし、博士号を必要とする職種は限られていることもあり、進学前から将来の進路について明確な計画を立てておくことが重要です。
【大学院のメリット】海外の大学院という選択肢も
大学院進学を考える際、日本国内の大学院だけでなく、海外の大学院という選択肢も視野に入れることで、将来の可能性を大きく広げることができます。
ここでは、海外大学院に進むメリット・デメリット、そして具体的な準備ステップについて解説します。
海外大学院のメリット・デメリット
海外大学院の最大の魅力は、世界中から集まった優秀な学生や研究者とともに学び、最先端の研究や実践的な教育に触れられることです。
グローバルな環境の中でディスカッションを重ねることで、視野が広がり、国際的な課題に対する理解も深まります。
また、英語での発表や論文執筆を経験することで語学力が向上し、将来のキャリアでも強みとして活かすことができます。
実際、外資系企業やグローバル展開している企業では、海外大学院出身者の知見や語学力が高く評価される傾向があります。
一方で、デメリットとしては、授業料や生活費などの費用が高額になることがあり、奨学金の獲得や資金計画が重要になります。
留学準備のステップ
海外の大学院に進学するには、早い段階から準備を始めることが非常に重要です。
まず最初に行うべきは、希望する専攻分野や学びたい研究テーマに強い大学をリサーチし、国や地域の生活環境も含めて比較検討することです。
その次に必要なのが語学力の強化です。
多くの大学ではTOEFLやIELTSのスコアが出願条件となっており、一定の基準を満たさなければなりません。
これらのスコアは準備に時間がかかるため、早めに勉強を始め、複数回の受験も見越しておくと安心です。
さらに、推薦状や志望理由書、成績証明書などの出願書類も必要になります。
どの書類も正確で具体的な内容が求められるため、十分な準備期間を確保し、内容に磨きをかけることが大切です。
【大学院進学のメリットは?】まとめ
本記事では、大学院進学におけるメリットについて、さまざまな視点からご紹介いたしました。
理系か文系かによって大学院の価値基準が少しずつ違うことや、就職時におけるメリットとデメリットの両方を知ることができたと思います。
今、大学院進学について悩んでいる学部生の方は、理系であれば少しでも進学を視野に入れ、文系であれば進学に対する熱量を確認するための行動を起こすことが大切でしょう。
進学と就職のどちらを選択したとしても後悔することのないよう、また、時間を無駄にすることがないよう、本記事を参考にぜひじっくり検討してみてください。