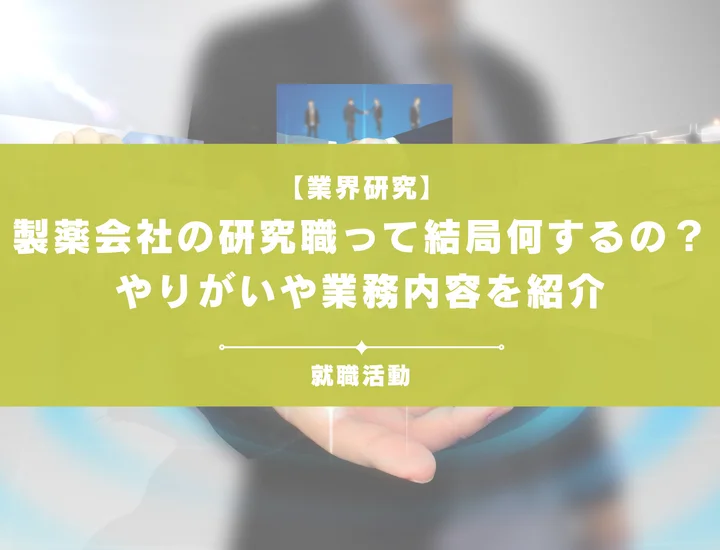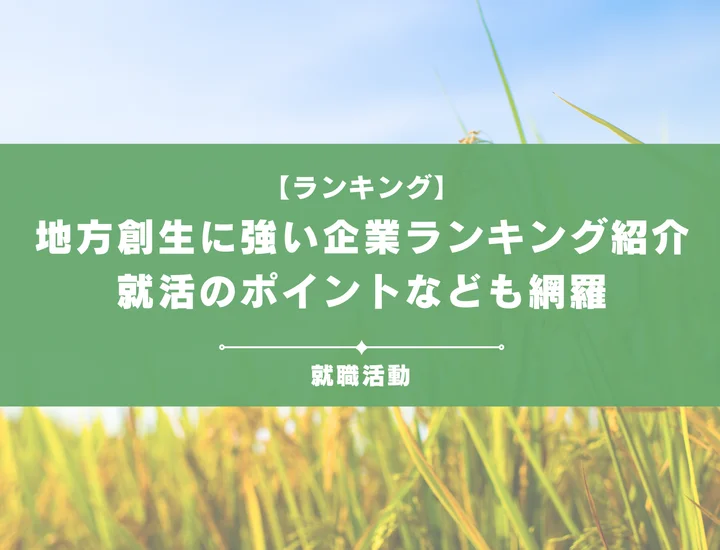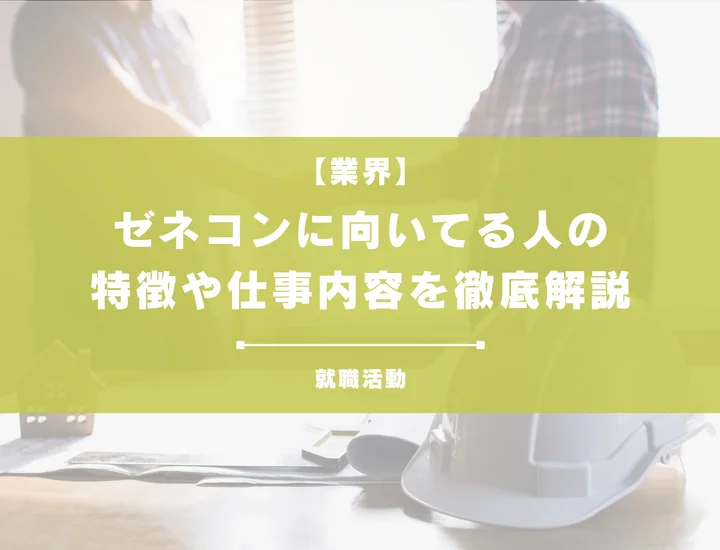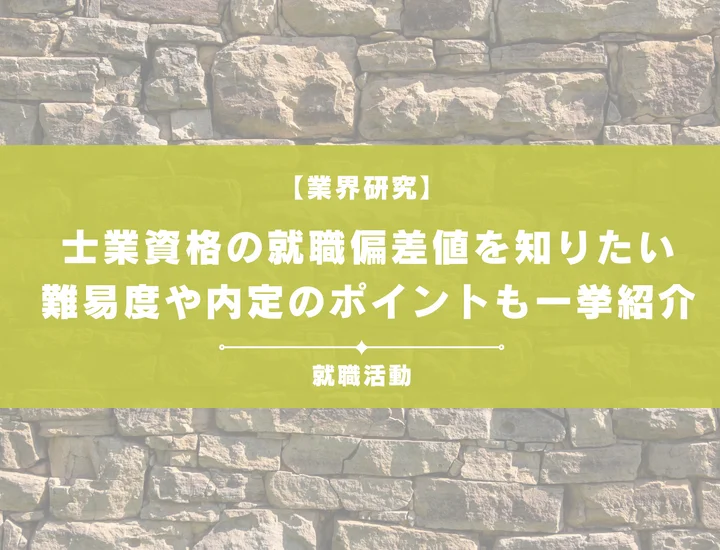HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
製薬会社の中でも研究職は、現在進行中でもある新型コロナのワクチン開発で世界中の注目を集めました。
日本では外資系の大手製薬会社も多いですが、国内の製薬会社も健闘しています。
新型コロナが発症してから飲む薬の国産薬の開発などが取り上げられたことが記憶に新しい方も多いのではないでしょうか。
そのほかにも先行品より価格を抑えられるジェネリック薬品の製造などでも、国内の製薬会社は頑張っています。
また、処方箋不要で購入できる医薬部外品も数多く開発されています。
目次[目次を全て表示する]
【製薬会社の研究職】製薬会社の研究職の仕事内容
製薬会社では、創薬と並行して体を蝕む多くの病気やその原因、病気をもたらすウイルスや菌などがどう体内の細胞に侵入してどう振る舞うのか、など病気のメカニズムについても研究を積み重ねることが要求されます。
新型コロナではかねて研究されていたmRNAワクチンという、これまでと異なる方法でワクチンを迅速に製造することが叶いました。
また、研究職は、いつも有効な成分を求めて、植物などが生成する特殊なたんぱく成分などについて研究しています。
その仕事の内容はトライ&エラーの繰り返しと、発想力が要求されます。
基礎研究
「基礎研究職」は、文字通り、病気に関する基本的な知識や新しい発見から、創薬のための仮説を立て、実験や分析を繰り返す仕事です。
時に、有名科学雑誌などに投稿された論文などをヒントに新薬が開発ができるかの研究、実験、検証、という科学的なアプローチが求められます。
臨床試験や認定までの期間も考え、数年先を見据えた研究が必要になることが多いようです。
中には、基礎研究だけで商品化に至らない場合もありますが、その研究が別の病気の薬で活きることもあり、決してないがしろにするべきではありません。
また、新しい薬成分の発見や開発も大切です。
多くはたんぱく質の分子結合を解析して、その組み合わせを変えることで菌やウイルス、異常な細胞に効果をもたらすようになることを考えます。
その意味では、化学式を理解できる知識は必要です。
応用研究
基礎研究とともに募集されることが多い「応用研究」職は、基礎研究で発見された実験結果や仮説などをベースに、それを製薬会社の商品である薬とするための職種です。
応用研究職は会社によって呼び名が異なる場合もありますが、患部やターゲットのウイルスや菌へ確実に、安全に薬効成分を届ける化合物を生成しなければなりません。
これが「探索研究」です。
動物などを使った「非臨床試験」も応用研究職の担う仕事で、企業が利益を出す薬を見つける研究を担います。
探索研究
応用研究職が基礎研究からあがってきた研究結果をもとに行う「探索研究」では化学的な知識、既存の薬に対する知識、これまで試してきた自社研究や応用研究の知識などが要求されます。
すでに効果が明らかになっており、認証を受けている薬の情報は重要です。
確実で効果的な薬効成分を分子レベルで明らかにし、構成元素やたんぱく質の構造などを追求していきます。
また、時には自社製品の効力をより強くすることも必要とされます。
売れている製品は、会社を支える大きな柱になるからです。
これも基礎研究をもとに行われます。
応用研究では、成分を分析しているうち、たまたま新しい薬効成分を見つけてしまうこともあり、化学の面白さもあると言えるでしょう。
本来狙っていた目的とは異なる病気に効果的な薬効成分は、長い時間を経て改めて見直されることもあります。
非臨床試験
応用研究で成分が確定された薬剤の効果を実際にマウスや猿などの動物を使って、毒性も含めて確認するのが「非臨床試験」です。
薬の成分を投与した細胞を培養した実験から始まることもあります。
マウスは子孫への影響も見ることができる、次の代が早く生まれる動物でもあり、遺伝子への影響なども含めて効果を観察するのに適しています。
予想より効果が出ない場合などは、化合物の生成から見直さなければなりません。
また、確実に薬がターゲットの患部へきちんと届いているのかも見る必要があります。
試行錯誤が必要なのが非臨床試験であり、より効果を発揮する化合物と投与量を見定めることが必要です。
最近ではiPS細胞などの実際の難病や再生不能とされてきた臓器や体パーツなどへの応用も盛んに研究されています。
他業界の研究職との違い
iPS細胞は京都大学の山中伸弥教授らが発見しましたが、大学は基本的に基礎研究を行います。
大学と企業が手を組んでその先の応用研究へ進む場合もありますが、基本的に製薬会社は民間企業で利益をあげなければならず、患者が多い病気や症状に効果がある製品やサービスの研究が優先です。
iPS細胞は未来の医療を大きく転換する可能性を秘めているため、特殊な例と言えるでしょう。
基礎研究は、ほかの業界でもある職種であり、文部科学省でも「基礎研究は主に「真理の探究」、「基本原理の解明」や「新たな知の発見、創出や蓄積」などを志向する研究活動である。」と定義を記載しています。
実はノーベル賞の受賞者からもその重要性が私的されている分野です。
ほか業界では、新製品開発の基礎研究から、既存商品の改良、新しいサービスなどの開発なども行われています。
【製薬会社の研究職】研究職と開発職の違いは?
製薬会社における研究職と開発職は、しばしば同じ職種と誤解されがちですが、その役割と業務内容には明確な違いがあります。
研究職は新たな薬の可能性を探求する職種で、主に基礎研究や薬の初期発見に関わります。
この段階では、化合物のスクリーニングや疾患のメカニズム解明、有効成分の同定など、薬の候補となる物質の発見とその効能の評価を行います。
一方、開発職は研究職によって見出された薬の候補が人間に投与された際の安全性や有効性を確認する臨床試験を担当し、製品化に向けたプロセスを管理します。
開発職の仕事は、臨床試験の設計から実施、データの分析、そして製造販売承認の取得に至るまで、製品の市場投入に必要な一連の手続きを進めることです。
したがって、研究職が「薬の可能性を見出し、試験する」段階に対し、開発職は「その薬が実際に市場で使用されるための安全性を確認し、製品化する」役割を果たしています。
これら二つの職種は製薬業界において互いに連携し、新薬開発の成功に不可欠な役割を担っています。
開発職の仕事内容
製薬会社の開発職は、研究職とは異なり、直接的な実験業務を行わず、新薬の臨床試験を進める役割を担います。
この職種では、新薬が人間に投与された場合の安全性や効果を確認するため、臨床試験の計画立案から実施、データ収集、分析までの一連のプロセスを管理します。
具体的には、臨床試験を実施する医療機関や医師との連携、試験の進行管理、試験結果の分析、そして新薬の製造販売承認申請に必要な資料作成が含まれます。
また、製品の承認審査を行う規制当局であるPMDA(医薬品医療機器総合機構)との密接なコミュニケーションも開発職の重要な業務です。
開発職には、バイオテクノロジー、医学、薬学、化学、農学など、幅広い理系の専門知識が求められます。
これらの知識を背景に、新薬の臨床試験を効率的かつ効果的に進め、社会に必要とされる安全で有効な医薬品を提供することが、開発職の最終的な目標です。
理系学部出身者が多いこの職種では、専門知識を生かし、新薬開発の架け橋として活躍することが期待されています。
その他の違い
製薬会社における研究職と開発職の違いは、業務内容だけに留まらず、働く環境や服装にも見られます。
研究職は新薬の基礎研究や初期開発を行うため、一般的には自然環境が豊かで、水質の良い地方に位置する研究所で働くことが多いです。
これに対し、開発職は臨床試験の管理や製品化に向けた活動を行うため、アクセスの良い都心部のオフィスが多いです。
また、規制当局とのやり取りが頻繁なため、企業本社に近い場所での勤務が一般的です。
服装に関しても差異があります。
研究職は実験室での作業が主なため、安全を考慮した白衣を着用するのが通常です。
一方で、開発職は外部との打ち合わせやプレゼンテーションもあるので、背広やビジネスカジュアルなど、よりフォーマルな服装が求められることもあります。
これらの違いは、各職種の業務の性質と、それぞれの職務が企業内および業界内で果たす役割に基づいています。
【製薬会社の研究職】向いている人
製薬会社の研究職は、高度な専門性が求められると同時に、社会への影響力も大きい仕事です。
就職活動を進めるうえで、自分の性格や志向がこの職種に適しているかを見極めることは非常に重要です。
ここでは、製薬会社の研究職に向いている人の特徴について解説していきます。
研究分野を極めたい
製薬会社の研究職は、自らの専門分野を深く追求し続けたいという志向を持つ人に向いています。
大学や大学院で学んだ知識をそのまま活かすことができる職種であり、研究内容は高度かつ専門的です。
たとえば薬理学、生化学、有機化学など、自分の専攻分野と企業の研究テーマが一致すれば、学生時代の知識や実験経験を即戦力として活かすことが可能です。
日々の実験や解析を通して粘り強く取り組む姿勢が求められるため、地道な作業を苦にせず、目の前の課題に丁寧に向き合える人に適しています。
社会貢献をしたい
製薬会社の研究職は、開発した薬が患者の命や健康を守るという非常に大きな社会的意義を持つ仕事です。
たとえば新型コロナウイルスや希少疾患など、未解決の医療課題に対して治療薬を開発することで、人々の生活を根本から支えることができます。
このように、科学的なアプローチを通じて社会貢献を果たしたいという意識を持っている人には、強いやりがいを感じられる職種です。
自らの研究が製品として世の中に出るまでには長い時間がかかることもありますが、それでも粘り強く研究を続ける情熱と使命感が求められます。
探求心が強い
新しい薬の創出は、未知の現象を解明することから始まります。
なぜこの病気が起こるのか、どうすれば治療できるのか、その根源的な問いに対して強い好奇心を持てることが大切です。
世界中の論文を読み込み、学会に足を運んで最新の知見を吸収し、自らの知識を常に更新し続ける学習意欲が求められます。
まだ誰も知らない答えを自分が見つけたい、そんな純粋な探求心が、長く険しい研究開発の道を照らす光となるでしょう。
粘り強く課題に取り組める人
医薬品の研究開発は、成功よりも失敗がはるかに多い世界です。
何百回、何千回と試行錯誤を繰り返しても、思うような結果が出ないことは日常茶飯事です。
しかし、その一つひとつの失敗の中にこそ、次へのヒントが隠されています。
なかなか成果が出なくても諦めず、冷静に原因を分析し、別の角度からアプローチを試みる。
そんな粘り強さと精神的な強さが、製薬会社の研究職として大きな成果を生み出す上で不可欠な資質といえます。
【製薬会社の研究職】働くメリット
製薬会社の研究職は、高度な専門知識を活かして社会に貢献できる職種であり、多くの就活生から注目を集めています。
理系の学生にとって、自分の学びをそのまま活かせる点や、待遇面の魅力などが大きなポイントです。
ここでは、製薬会社の研究職で働くことによる代表的な2つのメリットについて解説していきます。
年収が高い
製薬会社の研究職は、同じ研究職の中でも比較的年収が高い職種に分類されます。
実際に、20代で平均400万円前後、30代では550万円前後とされており、これは他のメーカー系研究職などと比較しても高水準です。
その背景には、高度な専門性と長期的な研究開発が求められる点があります。
新薬の開発には多大なコストと時間がかかり、その成果が企業の利益を大きく左右するため、研究職の貢献度も高く評価されています。
また、業界自体がグローバル市場を持ち、収益性が高いため、賞与や手当も充実しているケースが多いです。
大学の研究内容を活かせる
製薬会社の研究職は、大学や大学院で学んできた研究内容をそのまま業務に活かせる点も大きなメリットです。
薬学部や理学部、農学部、生命科学系などの専攻で得た知識や実験技術を、製品開発や基礎研究に直結させることが可能です。
たとえば、細胞培養、動物実験、薬効評価、構造解析など、学生時代の研究経験が即戦力として期待されます。
これは、新たにゼロから学ぶ必要が少なく、専門性をさらに深めていける環境とも言えます。
自身の専門性を最大限に活かせる
大学院で何年もかけて探求してきた専門知識や研究経験を、そのまま仕事に直結させられるのが、研究職の大きな魅力です。
自分が情熱を注いできた分野の知識を活かし、新しい医薬品の種を見つけ出すという使命は、大きな自己実現につながります。
企業の持つ豊富な資金や最新の設備を使い、学生時代にはできなかった規模の大きな研究に挑戦できることも、研究者にとってこの上ない喜びとなるでしょう。
健康や命に貢献できるやりがい
自分たちの研究が、いつか画期的な新薬として世に出て、病気に苦しむ世界中の人々を救うかもしれない。
製薬会社の研究職は、そんな大きなやりがいを感じられる仕事です。
研究の成果が製品として患者さんの元に届くまでには長い年月がかかりますが、自らの仕事が人々の健康や命に直接貢献できるという実感は、何物にも代えがたいモチベーションになります。
社会に対する貢献度の高さを常に感じながら働ける点が魅力です。
【製薬会社の研究職】平均年収
製薬会社の研究職は一種の技術職でもあります。
しかも、直接、その研究が会社の利益に結び付かないことも考えられます。
その平均年収は20代で約400万円、30代で550万円と、比較的高い年収です。
大手や、グローバル展開している外資系の研究職ではさらに高い年収になることもあります。
40代以上では平均800万円代と、研究で積み重ねてきた知見とチームをまとめる力なども評価されます。
最近は製薬業界で会社のM&Aも目立ち、合併・吸収を得て外資系の会社になるケースも見られるようになってきました。
そうなると英語力が必要になることや評価がシビアになることもあります。
より高い年収の会社への転職を見据えるのであれば、英会話、英語での書類作成などができる程度の語学能力を身につけておきましょう。
開発職との平均年収の違い
では研究職と開発職で平均年収はどちらのほうが高いのでしょうか。
仕事内容はまったく異なっていますし、求められるスキルも違っています。
しかし、平均年収は開発職と研究職はほぼ同じです。
どちらも商品になるかもしれない製品を生み出すまでの職種という共通性があります。
基礎研究職と開発職よりも平均年収が高いのは、実際に病院や薬局、ドラッグストアなどを回る営業・販売職です。
とはいえ、他業界の研究職よりもはるかに高い年収であることは確かです。
【製薬会社の研究職】必要なスキル
製薬会社の研究職では、専門的な知識や技術力だけでなく、職場での円滑な連携やグローバルな情報収集・発信のためのスキルも重要です。
研究者として成果を上げるためには、日々の業務を支える複数の能力をバランスよく備えていることが求められます。
ここでは代表的な2つのスキルについて詳しく解説します。
コミュニケーション能力
製薬会社の研究開発は、複数の研究員がチームで進めるのが一般的です。
ひとつの研究テーマに対してさまざまな分野の専門家が集まり、それぞれの知見を活かして進めていくため、密なコミュニケーションが不可欠です。
意見のすり合わせやデータの共有、進捗報告などが日常的に発生するため、自分の考えをわかりやすく伝える力が求められます。
また、研究成果を他部署や経営層にプレゼンする場面も多く、論理的かつ簡潔に説明する力も重要です。
対話を通じて円滑な連携を図れる人ほど、チーム内で信頼を得て活躍しやすくなります。
語学力
グローバル展開が進む製薬業界では、英語による情報収集と発信が日常的に求められます。
最新の研究論文や技術情報は英語で発表されることが多く、これらを正確に読み取るリーディング力は必須です。
さらに、国際学会での発表や海外の研究者との共同研究、海外支社とのやり取りなど、スピーキングやライティングの能力も求められる場面があります。
TOEICや英検などのスコアが参考にされる場合もあるため、学生のうちから語学学習に取り組んでおくと安心です。
語学力があることで、より広いフィールドで活躍できるチャンスが広がります。
分析力
研究活動においては、仮説を立て、実験を計画し、得られた膨大なデータの中から真実を見つけ出すプロセスが不可欠です。
この過程で重要になるのが分析力です。
実験結果を客観的に評価し、成功や失敗の要因を論理的に考察する力。
そして、その考察に基づいて次の一手を的確に判断する力が求められます。
複雑に絡み合った情報の中から本質を見抜き、研究を正しい方向へ導くための羅針盤となるスキルです。
修士・博士課程まで修了していること
製薬会社の研究職を目指す上で、修士または博士課程の修了は、実質的な応募条件となっていることがほとんどです。
学部卒の知識だけでは、人体のメカニズムや薬の作用を深く理解し、独創的な研究を進めることは難しいと判断されるためです。
大学院での研究活動を通じて培われる、高度な専門知識、論理的思考力、そして研究者としての課題解決能力が、企業での研究活動のスタートラインとなります。
【製薬会社の研究職】研究職のやりがい
製薬会社の研究職のやりがいは、有機化学が好きな人にとってその研究に打ち込めることが何よりでしょう。
それ以上に、新たな薬や細胞から臓器まで幅広い人体に関して意外な発見があることも魅力です。
ウイルスや病原菌の弱点を見つけることも大切な研究でしょう。
研究職は先にも述べた通り、最新の論文や独自の発想をヒントに追試験を行い、確実であれば、それをもとに数年先を見据えた研究を始めます。
その段階で思わぬ効用が見つかることもあり、研究の面白さも味わえるはずです。
研究の成果が確認できた時
自分が関わって研究を重ねた成果が応用研究、臨床試験を経て認められ、多くの人を助けることになれば、それはこのうえない喜びとなります。
試験段階で試行錯誤し、さらにブラッシュアップされ、予想より大きな成果をあげることにつながっても同じです。
それこそが研究職の醍醐味と言えます。
また、サル痘に天然痘のワクチンが効くことが報道されているように、新しい病気に対してこれまで別の症状に使用限定されていた薬がほかの症状に効果がある例は少なくありません。
これは認可の問題でもあるのですが、医療の現場で医師が処方することがあります。
それが大きな病気ではなく、命には関わらないが不快な症状に効果がある薬などが実際に使われています。
こうした効果は、研究者にとっても嬉しい結果です。
社会的地位が高いと認識した時
現在の医療は、手術よりも薬を用いて症状を抑える方法がメインです。
それだけに、製薬会社の社会貢献度は高く、効果的な薬によって症状がコントロールできている人が多くいます。
最も顕著なのは高血圧やメタボリックシンドロームに関連する薬でしょう。
また、がん治療はいまだ人類にとって難しい病気ですが、がん細胞のみをターゲットにする薬も開発されています。
それらの薬は、すべて基礎研究から始まっています。
そして、もっと画期的な方法はないか、まだ薬が発見されていない病気に効果的な薬効成分はないのかを探す「創薬」に日々向かい合う研究職は、社会的な地位も高い、と言えるでしょう。
「製薬会社で研究職をしている」というだけで、頭のいい人、自分も飲んでいる、使っている薬の会社で研究しているんだ、と感謝されることもあるはずです。
身近な人に体の不具合を相談された時
製薬会社に務めているというと、親兄弟や親族、知人などから体に何か気になる症状があると相談されることが多いようです。
研究職では、その会社が扱っている薬や症例などについても知っています。
大学時代に学んだ知識もあります。
また、職場で見聞きする症例などもあるでしょう。
相談を受けた時は、その知識で答えることができ、最新の公開されている論文のことも教えてあげられます。
最新論文ではかかりつけ医でも知らないことがあり、病気で悩んでいる人にとって希望が見える朗報です。
また、現在の処方薬や治療法を聞いて誤りを指摘したりもできることでしょう。
民間療法に頼っている方からも相談があるかもしれませんが、症状に効く成分を含んでいる食べ物よりも、その成分を抽出して効果的に吸収されるようにした薬のほうがベストであることも伝えられます。
そうして感謝されると、この道を選んで良かったと感じるようです。
【製薬会社の研究職】就くためにやるべきこと
製薬会社の研究職は採用倍率が非常に高い難関です。
内定を勝ち取るために、学生時代から計画的に行動することが重要になります。
ここではやるべきことを紹介します。
インターンへの参加
企業のウェブサイトだけでは分からない、研究の現場の雰囲気や社風を肌で感じられるのがインターンシップです。
社員の方々と共に働き、研究開発のリアルな流れを体験することで、その企業への理解が格段に深まります。
仕事内容への理解はもちろん、自分の研究内容や能力をアピールする絶好の機会にもなります。
入社後のミスマッチを防ぎ、志望動機に説得力を持たせるためにも、積極的に参加すべきです。
OB・OG訪問の活用
実際にその企業で働く先輩社員から、直接話を聞けるOB・OG訪問は、極めて価値の高い情報収集の手段です。
仕事の具体的なやりがいや大変な点、職場の人間関係といった、説明会では聞けない本音の情報を得ることができます。
また、自身の研究テーマがその企業でどう活かせるかなど、選考を有利に進めるための具体的なアドバイスをもらえる可能性もあります。
人脈を頼りに、積極的に機会を作りましょう。
徹底した企業研究
多くの製薬会社の中から、なぜその企業を志望するのかを明確に語るためには、徹底した企業研究が欠かせません。
各社がどのような疾患領域に力を入れているか、いわゆる創薬パイプラインはどうなっているか、最近の論文発表やニュースリリースなどを深く読み込みましょう。
その上で、自分の専門性や将来のビジョンが、その企業の方向性とどう合致するのかを具体的に示すことが、熱意の証明となります。
【製薬会社の研究職】薬学部を卒業していないと就職できない?
製薬会社への就職に際して、必ずしも薬学部出身である必要はありません。
企業はその時点で求めている専門性を持った人材を採用するため、幅広い学問背景の持ち主がチャンスを得ることができます。
特に、有機化学の深い知識と技術は、製薬業界で高く評価されるケースが多いです。
さらに、分析化学や物理化学など、製品の開発や品質管理に不可欠な知識を持つ人材も求められています。
もちろん、薬理学やバイオテクノロジーなどの分野は薬学部出身者にとって有利な場合もあります。
また化学や生物学の基礎知識を有することが、多くのポジションでの応募資格となり得ることもあります。
したがって、製薬業界では多様なバックグラウンドを持つ人材が活躍の機会を見出せるため、特定の学部出身でなくても問題ありません。
特に理系であれば、自分の専門知識や技能を活かして貢献できる可能性が広がっていると思っていいでしょう。
おわりに
製薬会社の研究職は、まさに研究者らしい仕事が味わえる仕事です。
就職してすぐは、スポイトでいくつもの試験管やペトリ皿に対象の細胞や成分を入れていく仕事や、遠心分離機にかけたりといった地道な仕事が続くでしょうが、これは大学の研究室でもやる作業で、欠かせない手順です。
その中で研究リーダーの考えや作業目的を聞くことは、自分にとっても新たな知見となります。
もちろん会社の意向で行う研究もあり、一定分野しか研究を行わない会社もあり、職場ごとにカラーが異なります。
新たな、副作用の少ない画期的な薬を開発することを目的に研究職を目指してください。