
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
【大学3年生必見】AI模擬面接ツールで面接対策しよう
就活で必ず通る「面接」。ただ面接対策ってどうやってやるのだろう、と何から始めればいいのか悩んだり、進め方がわからなかったりと、意外とハードルが高いです。
そこで、今回「いつでもどこでもAI模擬面接ツール」をご用意しました。
頻出問題から変わった問題までAIが人事目線で添削するので、すきま時間であなたの面接力をあげることができます。
メンバー登録後すぐに使用可能なため、ぜひあなたもこの「AI模擬面接ツール」を活用して選考通過率を上げましょう!
※画像の質問はイメージです。
目次[目次を全て表示する]
【ガクチカの深掘り質問】深掘り質問とは?
これから面接を受ける就活生の人は、面接に向けてさまざまな対策をすることになるでしょう。
特にその選考でも注意してほしいのが、面接官からの深掘り質問です。
深掘り質問とは、要するに就活生が話した内容について、さらに色々聞いていくことを指します。
つまり、どんな質問をされても良いように、あらかじめ自分の中でイメージしておかなければいけません。
一次面接と二次面接の違い
企業の面接には、大きく分けて一次面接と二次面接があります。
企業によっては三次面接もありますが、一般的には二次面接まであるケースが多いでしょう。
この2つの大きな違いは、相手から質問される内容です。
その人に対する基本的な質問
→ES(エントリーシート)で書いたことを元に質問
【例えば】
ガクチカ・志望動機・自己PR・長所短所
一次面接で聞いた内容を元にする発展的な質問
→口頭で伝えたもの伝えたものをどんどん深掘りで質問
【例えば】
尊敬する人が誰なのか?
入社後はどんな仕事をしていきたいのか?
人生で一番努力したことは何か?
一次面接の内容を踏まえた上で深掘り質問をされることが多いため、二次面接の際には常に意識しておいてください。
そもそもガクチカの書き方や構成がわからない方へ
ガクチカの書き方について、そもそもまだ何もわからない人も少なくないでしょう。
そんな人は、先にガクチカの書き方から勉強する必要があります。
以下の記事で詳しく紹介していますので、ぜひこちらの内容にも目を通しておいてください。
【ガクチカの深掘り質問】企業が深掘りする理由
企業が面接でガクチカを深掘りする理由には、単に経験を確認するだけでなく、その背景にある価値観や能力を把握する意図があります。
これにより、応募者が自社で活躍できるか、信頼できるかを総合的に判断するのです。
以下では、企業がガクチカを深掘りする具体的な理由を解説します。
虚偽の判定
企業がガクチカを深掘りする主な理由の一つは、応募者の経験や成果が真実であるかを確かめるためです。
虚偽や誇張が含まれている場合、面接の詳細な質問に対する回答で矛盾が生じる可能性があります。
こうした矛盾が発覚すると、入社後の信頼性に疑念を抱かれるだけでなく、「顧客やチームに迷惑をかけるリスクが高い」と判断されることもあります。
深掘りは、最低限「嘘をつかない信頼できる人材」を確保するための重要なプロセスと言えます。
企業はこの過程を通じて、応募者が本当に話している内容を実際に経験し、学び取ったのかを確認しています。
人柄や価値観を知りたい
企業がガクチカを深掘りすることで、応募者の価値観や考え方を明らかにすることができます。
たとえば、「なぜその行動を選んだのか」「どんな判断基準で行動したのか」といった質問を通じて、応募者が大切にしているものを知ることができます。
これにより、応募者がどのような働き方を望み、どんな価値観に基づいて行動するのかが見えてきます。
さらに、この価値観が自社の文化や業務スタイルに合致するかどうかを判断するための指標となります。
応募者の価値観が自社の考え方と合っている場合、長期的に活躍してもらえる可能性が高まります。
自社とマッチするかの確認
深掘り質問を通じて、企業は応募者の経験が自社の業務にどのように活かせるかを確認します。
たとえば、取り組みのテーマや行動スタイル、背景などを聞くことで、応募者が入社後に自社で成果を上げられるかを判断します。
ガクチカの中で得た学びやスキルが、自社の業務内容や価値観と一致している場合、即戦力としての期待が高まります。
逆に、応募者の行動や思考が自社の事業と大きく乖離している場合、ミスマッチを懸念する材料になることもあります。
このプロセスを通じて、応募者と自社の適性を見極めています。
論理的思考力があるかを確かめたい
企業は、応募者がどのように課題を分析し、解決に向けて行動したのかを深掘りすることで、論理的思考力を確認します。
たとえば、問題に直面した際に状況を正確に把握し、合理的な判断を下し、成果に結びつけたプロセスに一貫性があるかを見ています。
また、この一連の流れが実際の業務で必要とされるPDCAサイクルを適切に回せるかの指標となります。
入社後、業務における課題に直面した際も、自分の力で解決策を導き出せる能力があるかどうかを企業は注視しています。
具体的な事例を交えて論理的に説明できると、評価が高まるでしょう。
【ガクチカの深掘り質問】面接のための5つの対策方法
実際に面接官から深掘り質問をされてしまうと、つい焦ってしまってうまく答えられない人もいるでしょう。
そんな人に向けて、具体的にどんな対策をしていけば良いのかを、5つに分けて紹介します。
もし難しいなと悩んでいる場合は、ぜひ積極的に実践してみてください。
1. 自己分析・企業分析の徹底
まず深掘質問に対してうまく答えられないタイプの人に多いのが、自己分析や企業分析が足りていないパターンです。
どんな人もESを書く時点で取り組んでいるかもしれませんが、もう一度改めて取り組むようにしてみてください。
きちんと時間をかけて、細かく分析していれば、どのような形で深掘りされたとしても焦って変なことを口にすることはほとんどなくなるはずです。
ちなみに、前述した企業が深掘り質問で評価するポイントも、きちんと自己分析や企業分析ができていれば、自然と対策になるでしょう。
だからこそ、時間の許す限り何度も分析をして、何を聞かれてもスラスラ答えられるようになっておいてください。
2. ガクチカのエピソード整理
ガクチカのエピソードではさまざまな出来事を伝えることになると思いますが、面接官の多くは細かいところまで聞いてくる傾向があります。
なぜなら、就活生のことを少しでも深く知りたいと考えるからです。
また、エピソードの中でおかしな点がないかどうかを見るために、深掘り質問をすることも少なくありません。
そのため、最初から最後までつじつまが合うように、今からガクチカのエピソードをきちんと整理しておくのがおすすめです。
もし整理の仕方がわからない場合は、「結論・背景・目的や課題、困難・プロセス・結果・学び」に細分化した上で、考えるようにしてみてください。
そうすれば、ただ頭の中だけで考えるよりも、綺麗にわかりやすく整理できるはずです。
3. 「なぜ?」の繰り返し
面接官が深掘り質問をするのは、就活生の核心的な部分に迫りたいと思うからです。
そのため、どんな些細なことであろうと、当たり前のように「なぜ?」と聞いてきます。
だからこそ、何もかもに疑問を持たれてしまうものだと、あらかじめ思っておいた方が良いでしょう。
例えば、アルバイトを頑張ったことをガクチカとして伝える際に、背景として「売上が低迷していた」と伝えた場合、面接官は「なぜ低迷していたのですか?」と聞いてくる可能性があります。
なぜなら、そもそも就活生本人が原因を理解しているのかどうかを、そこで理解しておきたいからです。
そのことをわかった上での経験なのか?それともわからない状況での経験なのか?によって、評価の仕方に大きく変わってくるため、これは必ず聞かれるものだと思っておいて良いでしょう。
就活生の核となる部分がわかれば、企業側も自社との相性を計りやすくなるため、どんなエピソードを話す場合でも起こりうることだと考えておいてください。
- どのような手順で物事を進めたのか
- 何がモチベーションとなったのか
- どのようなことに苦労したのか
- 継続できた理由は何か 取り組んだことで自分自身にどのような変化があったのか
- 今、過去に戻れるならどのようなアプローチをとるのか
4. 模擬面接
ここまで紹介した内容は1人でできる面接対策ですが、できることなら実際の面接を想定した模擬面接もやっておく方が良いでしょう。
なぜなら、その方が本番をイメージしやすくなるからです。
どれだけ頭の中だけで対策していたとしても、いざ面接になると緊張で焦ってしまう人は少なくありません。
だからこそ、周りの人に協力してもらいながら、模擬面接を試してみてください。
ただし大事なのは、模擬面接に協力してもらう相手は誰でも良いわけではないことです。
例えば同じ学生の友達や家族よりも、就活の知識が豊富な相手に頼むようにした方が良いでしょう。
その理由は、模擬面接をした際にどこが良くてどこが悪いのかを、判断しやすくなるからです。
そのため、就活エージェントを活用したり、キャリアセンターの先生のような、就活のプロを相手に練習したりするのがおすすめです。
ちなみに、就活エージェントは無料でさまざまな相談にも乗ってくれるサービスなので、どんな人でも気軽に利用できる画期的なサービスになっています。
5. 録画・録音
面接対策をする際には、その内容はもちろんのこと、根本的に自分の姿勢や話し方などにも、注目する必要があります。
なぜなら、面接では直接面接官と向かい合ってコミュニケーションをとることになるからです。
例えば、どんなに良いことをアピールできたとしても、声が小さければ相手が聞き取れない可能性があります。
つまり、せっかくのアピールが台無しになるかもしれません。
だからこそ、自分が面接をしている時の姿を、自分自身でも客観的に把握しておいてください。
手元のスマートフォンでも良いので、その様子を撮影して何度も確認するようにしましょう。
自分で話している時には気づかなかった自分の悪いところが、この段階で初めてわかるかもしれません。
NEW!!『あなたのガクチカ』に対する深掘り質問生成ツール【完全無料】
ガクチカの深掘り対策を徹底して行いたい就活生必見!
この度、DigmediaからAIの最新ツールとして、「AIガクチカ深掘り質問ツール」をリリースいたしました。
「あなたのガクチカ」に特化した面接での想定質問を最低でも15個以上生成できます。
完全無料で利用できるため、ぜひ、ガクチカの対策に活用してみてください!
【ガクチカの深掘り質問】よくある質問
ではガクチカに関することや、深掘り質問に関することについて、よくある初心者の質問に答えていきます。
これから初めて就活をする人ほど、さまざまな疑問を抱いているかもしれませんので、ぜひここで解消しておいてください。
疑問1. ガクチカは何分で話せばいいの?
まずガクチカを面接官から聞かれた際に、どれくらいの時間を使えば良いのかわからない人もいるでしょう。
結論からいうと、特にこれといった決まりはありません。
ただし、長すぎると相手がすべて理解できない可能性があるため、基本はESや履歴書で書いた内容通りのことだけを、ここで完結に話すようにしてください。
イメージとしては、大体1分程度でOKです。
面接会場は自分のことをアピールする場所ですが、一方的に話し続けるよりも、お互いにバランスよく会話のキャッチボールをした方が、より相手に伝えたいことが伝わりやすくなりますし、好印象を持ってもらいやすくなります。
疑問2. 深掘り質問に対する回答は何分で話せばいいの?
簡単な質問から、徐々に深掘り質問に移っていくことになりますが、その際にどれくらいの時間をかけるのが良いのか疑問を抱く人も少なくありません。
もちろん決まり自体はありませんが、大体30秒~1分くらいを目安に考えていれば良いでしょう。
あくまでも面接官が一度で理解できるように、わかりやすく完結に伝えることが大切です。
相手が聞いていないことまで話し始めてしまうと、面接のテンポが悪くなってしまうため、それだけでもマイナスな印象を持たれるおそれがあります。
だからこそ、どんな深掘り質問をされることがあったとしても、その質問内容に答えることだけを意識するようにしておいてください。
その方が、むしろ自分自身にとっても負担が少なくなるため、変なミスをしてしまうリスクもなくなるでしょう。
疑問3. ガクチカはどこまで話せばいいの?
ガクチカを聞かれた際には、先ほどと同じように1分くらいでまとめられるような内容を話してください。
つまり、結論や背景、困難、課題や結果などを、全部この1分間に凝縮して伝えるのが理想です。
そうすればどんな面接官も、あまり聞き返すことなくあなたのガクチカエピソードを理解してくれるでしょう。
ちなみに、ガクチカを伝える際には、最後に入社後の活躍についてもアピールするのがベストですが、そこまで言ってしまうと1分をオーバーしてしまうおそれがあります。
そのため、無理をして一度に何もかも伝える必要はありません。
入社後の活躍については、後々面接官から聞かれることも多々あるため、その際に改めて伝えるようにしてみると良いでしょう。
疑問4. 回答が似たり被っても大丈夫?
面接官の質問の中には、同じようなことを聞いてるんじゃないかと思うようなパターンもあるでしょう。
例えば「取り組む際に注意したことは?」と「取り組む際に工夫したことは?」という質問に対して、つい同じことを答えてしまう人もいるかもしれません。
しかし、面接官が同じ回答になるようなことを、何度も聞くようなことはありません。
つまり、似たような回答を2回以上してしまうのは、基本的にNGだと思っておいてください。
一見同じような質問に聞こえることでも、実は全然違うことを聞こうとしています。
前述した例でいえば「取り組む際に注意したこと」に関して、そこで「工夫したことは何なのか?」といったニュアンスで聞いていることを、認識してもらえればOKです。
このように考えることができれば、自然と違う解答ができるでしょう。
疑問5. 言葉に詰まってしまったらどうしたらいい?
面接にまだ慣れていないうちは、つい言葉が詰まってしまうケースも珍しくありません。
特に深掘り質問は自分が想定していないような内容になっていることもあるため、言葉が出ずにしばらく黙ってしまう人もいるでしょう。
どうしてもそんな状況に陥りそうになった場合は、一旦面接官に対して「大変恐縮ですが、それは今の段階ではわからないです」と、素直に伝えるようにしてください。
その方が、ただ黙っているよりも、良い印象を残しやすくなります。
とはいえ、言葉が詰まるのはどのみち準備不足だと思われてしまうため、今からしっかり対策をしておくべきポイントだといえるでしょう。
ちなみに行き詰ってしまった際に、絶対にやってはいけないNG行動があります。
それは、単純に固まってしまうことだけではなく、変な嘘をついてしまうことです。
面接官は就活生が口にする言葉に対して、頻繁に深掘り質問をしてくる傾向があります。
そのため、嘘を一度でもついてしまうと、余計に深掘り質問に対応できなくなるため、最終的には嘘をついていることがバレてしまう危険が出てくるでしょう。
また、質問とはあまり関係のない話をダラダラと話し始めてしまうのもNGです。
面接官が聞きたいこととは異なる話をしたところで何も良い結果は残らないため、余計なことはしないようにしてください。
【ガクチカの深掘り質問】ガクチカ特化質問集&回答例文
の深掘り質問一覧_800xAuto.webp)
ガクチカのエピソードを伝えた際やエントリーシートを読まれたときに、選考担当者(面接官)からどんな質問をされることが多いのかを理解していれば、どのように対応すれば良いのか対策しやすくなるでしょう。
そこでここからは、実際によくある質問のパターンと、それぞれの質問別に回答例を、詳しく紹介します。
これさえ押さえておけば、深掘り質問をされたとしても対応しやすくなるでしょう。
また、深掘り質問の対策をする前にガクチカ自体を作成したい方はこちらのツールをご利用ください!
1. 大学時代に力を入れたことを教えてください
まず多くの面接官が口にするのが、学生時代に力を入れたことを教えてほしいという質問です。
ここからスタートする企業は決して少なくありませんので、すぐに答えられるようにしておいてください。
ここでのポイントは、まずできるだけ時間をかけすぎないようにすることです。
大体1分くらいを目安にすると、相手に伝わりやすい説明がしやすくなるでしょう。
また、その際には「結論・背景・目的や課題・プロセス・結果・学び」の順番で話せるようになるのが重要です。
この流れを意識するだけで、丁寧な答え方ができるようになります。
私が学生時代に力を入れたことは、約1年半続けている人材業界でのテレアポの長期インターンです。
社会人になる前にインターンとして社会に出て、現状の自分のキャパシティーと可能性を見出すために参加しました。
この期間において、私は「インターン生の中で一番のインターン生になる」という目標を掲げて活動に励みました。
しかしながら、初月、目標未達に終わってしまい組織貢献ができず、目標とはほど遠い状態でした。
そのため、課題を見出すために、自分の取得率やキャンセル率、通話時間などを先輩インターン生や社員の数字と比較して分析を行い、一番改善できる点は取得率にあると分かり、取得率の向上を目標に取り組みました。
具体的には先輩のログを聞いて自分のトークに落とし込んだり、未取得時は積極的にフィードバックをもらいに行き、そこでの学びをロープレで実践し、自分の後輩にも発信するなどしてアウトプットを行いました。
その結果、初月以降の月で120%以上の達成と、インターン生・社員史上最多件数の取得、インターン組織の中でリーダーへの昇格という成果を残すことができました。
この経験から、目標を達成するための現状分析と行動力の大切さを学びました。
2. なぜそれに取り組もうと思ったのですか
さまざまな質問の中でも、なぜ取り組もうと思ったのかは、非常によく聞かれる内容です。
先ほどの例文のように、ガクチカの内容を話した際にそのまま伝えていることもあるかもしれませんが、それでも聞いてくることがあります。
なぜなら、他にも具体的に聞きたいポイントがあるからです。
例えば、先ほどの回答例では「現状の自分のキャパシティーと可能性を見出したいから」と答えていますが、面接官によっては「他の選択肢がある中で、なぜ選んだのか」を聞きたいケースもあります。
そのため、自分が既に伝えていたことでも、他に回答を求められる可能性があることを覚えておいてください。
では先ほどの例文を前提に、回答例を紹介します。
きっかけは、学生気分からの卒業をしたかったからです。
インターンの他にもアルバイトやサークルで様々なことに取り組んできましたが、どれも学生区分として処理されているものであり、その活動内容も社員とは区別された学生専用のものでした。
どこかで大学生としての甘えがあり、それを払拭するため、また社会人として働く覚悟を持つために、長期インターンを始めました。
3. 解決前の問題点や困難について教えてください
そもそも課題を見つける上で、現状を分析できる能力は必要不可欠です。
この質問をすることで、面接官はその人の課題発見力だったり、主体性がある人材なのかどうかを判断できます。
どのようなジャンルの仕事においても必要不可欠な要素だといえるため、当たり前のように聞かれるものだと思っておいた方が良いでしょう。
取得率という課題を見出す前は、なんとしてでも目標件数を取得するために、コール数を増やしたり、出勤数を増やすなどの行動量は担保できていましたが、トークの部分ではフィードバックをもらいに行ったり、自分のログを聞いていなかったなど、PDCAサイクルをうまく回せていなかったため、セールスとしての質が低くなっていました。
4. なぜそれが問題だと思いましたか
今までの経験でさまざまな問題にぶつかってきたかもしれませんが、そもそもなぜそれが問題であることだと認識したのかを、この質問から問われることがあります。
例えば今回の例文を踏まえると、キャンセル率だったり通話時間なども、課題として考えられるポイントになってくるでしょう。
だからこそ、面接官はその中でも取得率に対して焦点を当てているのかを、疑問に思うのです。
キャンセル率や通話時間の課題も取得率が向上すれば解決に近づく課題だと判断したからです。
キャンセルについては、取得率、つまりトークの質を上げて参加したいと思わせるトークができれば自然とキャンセル率も低下し、通話時間に関しても長々と話して相手の感度が下がることを考えると、端的にニーズの回収とネック回収ができれば、通話時間も短くなり、取得率も向上すると考えました。
5. その問題は本当に対処すべきものでしたか
面接官は、その問題に対して本当に対処しなければいけなかったのかまで聞こうとします。
なぜなら、4つ目の回答例の内容について、本当にそれが正しいことだったのかどうかを分析しているのか、きちんと確認しておきたいからです。
そのため、自分が実際に課題に対してアプローチした結果、どう思ったのかを取り入れながら答えてみると良いでしょう。
はい、私はそう考えます。
セールスは件数を稼ぐことではなく、自社商材を、個々の顧客のニーズやネックに合わせて提案し、自社のサービスが顧客の満足度を高めることが本質だと上司から教わりました。
その観点から考えると、ニーズ回収や提案など、セールスの本質が問われるのはトークの部分であり、取得率の低さという課題は対処すべき問題だったと考えています。
実際に取得率の向上に努めることで自然とキャンセル率が低下したり、通話時間も短くなってコール数も増えました。
6. その問題に対してどのような解決策を実施しましたか
さまざまな課題に対して、主に自分がどのように解決してきたのかを、さらに掘り下げてくることもあります。
そのため、最初に伝えた解決策について、具体的に何をどうしたのかを思い出しながら、事細かくその時の様子を伝えていきましょう。
主に3つの策を徹底的に実施しました。
1つ目は、先輩のログを聞いて自分のトークに落とし込むことです。
先輩のトークでは「であればちょうどよかったんですけど」や「ご安心ください」などのキラーフレーズがあることや、断られても、顧客の返しを深掘りして潜在ニーズを引き出したりするなどの取得のための工夫がいくつもありました。
その中でも自分の話し方やトークの型に合うものを含ませて自分のトークの質を上げました。
2つ目は未取得時に積極的にフィードバックをもらいに行き、そこでの学びをロープレで実践し、アウトプットの機会を増やすことです。
3つ目は発信をすることです。
具体的には隣の席の人との会話の中で「この1時間であと2件とります」などと自分に保険をかけられないように1コール1コールを大切に稼働しました。
7. 他にどのような解決策を考えましたか
当時の考え方に沿って、自分なりに解決策を考えて行動してきたかと思いますが、他にも何か候補となる解決策を考えなかったのかどうかも、面接官によっては気になるところでしょう。
人によっては他に何も思いつかなかったことを話してしまう場合がありますが、何も考えられなかったことをただ伝えても、プラスの評価にはつながりません。
だからこそ、他に候補がなかった人は、今からでも良いので当時を思い出しながら、何か他に解決策がなかったのかどうかを、1つ以上考えておくのが良いでしょう。
他には、同じインターン生のトークをモニタリングすることや自分が取得できる案件にどのような傾向があるのかを分析する、などの解決策を考えました。
8. なぜその中でこの解決策を実施したのですか
いくつかある解決策の候補を伝えた際には、もちろんその中からなぜエピソードで伝えた内容の解決策を実践したのかまで、深く掘り下げて聞いてくるでしょう。
自分がどんなことを重視して最終的に1つの解決策に絞ることになったのかを、できるだけ詳しく説明してください。
先ほど挙げた2つの策に関して、同じインターン生のトークを聞くことでみんながどのようにセールスしているのかを知ることはできますが、そのトークの質がいいという保証はないと考えました。
また、取得できてる案件の分析に関しては、プラス面のさらなる向上よりも、マイナスになっている部分を底上げした方が最終的な数字が上がると考え、先に話した3つの施策を実施しました。
9. この取り組みで工夫した点はなんですか
ガクチカの内容や結果自体は、もちろんアピール材料として大事な要素です。
しかし、厳密にいえば、人によって何に対してどんな努力を重ねてきたのかは全然違ってくるでしょう。
だからこそ、面接官はさまざまな取り組みの中で、どんな工夫をしてきたのかを明確に素人します。
施策をしながらPDCAを回すことを意識しました。
施策を考え、実行して終わりだと、目標である取得率の向上にたどり着いているかが確認できないため、その後のプロセスとして数値の側的やそこからの考察を大切に取り組みました。
10. もう一度同じことを取り組む場合どのようにしますか
ここまでの話の内容を踏まえた上で、もし今の自分だったらどうするのかまで聞いてくることがあります。
なぜなら、その経験や結果があったからこそわかることが、何かしらあるはずだからです。
おそらくあなたも、ガクチカを通じてさまざまな学びや気づきがあったことでしょう。
そのため、事前にそのシーンをイメージして話す内容を考えておくことも重要です
もう一度当時の取得率向上に取り組む場合、スピード感を意識して取り組みます。
以前はちょうど繁忙期に当たっていたため、よりスピード感を意識すればより多くの件数を獲得できていたかと思います。
11. この取り組みから学んだことを教えてください
面接官は最後に改めて、これまでの経験から得た学びを聞こうとするでしょう。
特に学生時代に力を入れていたことであれば印象に残っているはずですので、1つだけではなく多くの学びがあることが考えられます。
もし何も思いつかない場合は、今だからこそわかることを学びとして、ここで伝えるようにしてみてください。
この経験から、行動を起こす前に現状を分析を行い、現状の自分にはどのアクションが適切なのかを考えて、実際に行動に移すことが目標達成に近づくと学ぶと同時に、最初のうちは知識量や質に関してまだまだな部分があるため、行動量や泥臭さのような部分も大切にしていく必要があると学びました。
12. その学びをどのようにして弊社に活かせますか
ガクチカのアピールをした際には、ほぼ間違いなくといっても過言ではないくらい、自社でその経験をどう活かせるのかまで聞いてきます。
その理由は、本当に自社に迎え入れるメリットがあるのかどうかを、できるだけ明確にしたいからです。
だからこそ、これまでの経験を踏まえた上で、自分ならどんなことがその会社で実現できるのか?そして、どんなことに取り組んでいきたいのか?などを、ここでアピールしていきましょう。
ちなみに、ここでは必ずしもすごいことを伝える必要はありませんので、何も貢献できるイメージがまだ沸いていない場合は、伸びしろがあることをアピールするようにしてください。
この経験から得た分析力や行動力は、御社での営業職において、市場分析や顧客のニーズ分析に活かします。
また、その要望に素早く対応し、主体的に新規顧客の獲得をすることで貢献できると考えています。
13. その組織の中でどんな存在でしたか
就活生が、その組織の中でどのような役割だったのかを、具体的に掘り下げてくるケースもあります。
なぜなら、きちんと自分の役割を理解して行動できていたのかどうかを、面接官は判断したいからです。
以下にそれぞれの役割の特徴を紹介しますので、きちんとそれに沿ったアピールができるようにしておいてください。
・リーダー
自分を中心に、他のメンバーを引っ張っていく
・モチベーター
文字通り、周りの人のやる気を高めたり、維持したりする
・サポート役
他の人が円滑に行動できるように、率先してサポートに徹する
・相談役
同僚や後輩が悩んだ際に、いつでも相談に乗ってあげたり、場合によっては解決まで導く
・まとめ役
チーム全体の意見を聞いて、それをうまくまとめる
・分析役
さまざまな状況を踏まえ、今何が大切なのかを常に分析して行動する
・アイディアマン
何かに取り組む際に、人にはないような意見やアイデアを生み出す
・ムードメーカー
場の雰囲気を、常に明るく保つ
・切り込み役
どんなにつらくて難しいことでも、自ら率先して行動する
・危機管理役
何事においても、リスクを瞬時に察知できる
・調整役
自分だけではなく、周りのメンバー1人1人の関係性も円滑にできるようにサポートする
今回は組織で課題に取り組んだわけではないのですが、自らが主体性を持って行動したり、施策で良かったことをみんなに共有するなどをしていたため、他のインターン生の成長意欲を刺激するモチベーターのような存在だったと思います。
14. 周りからどんな人(存在)だと言われることが多いですか
基本的に自己PRをする時は、すべて自分の目線からさまざまな経験を話すことになるでしょう。
だからこそ、面接官によっては、就活生に関する客観的な意見についても知りたいと考えます。
そのため、周りから自分はどのように思われているのか?どんな評価をもらっていたのか?を、具体的に話せるようにしてください。
周りの人からは嬉しいことに努力家や真面目と言われることが多いです。
ただ自分の中では目標や課題に縛られて柔軟に考えることが苦手だとおもているので、物事を多角的に見ることを習慣付けています。
15. 「5W1H」
自己PRの際には「サークルで~」や「地域予選で~」のように、抽象的な表現を使ってしまうこともあるでしょう。
その際に覚えておいてほしいのが、必ずといっても良いほど1つ1つの文言に対して具体的に聞いてこようとします。
例えば「どんなサークルですか?」や「どこの地域予選ですか?」のように聞いてくる面接官は、決して少なくないはずです。
また、5W1Hによって評価の仕方も大きく変わってきます。
例えば「アルバイト先でバイトリーダーをしていました」というアピールをする場合でも、同じアルバイトスタッフが自分を含めて2~3人しかいなければ、せっかくバイトリーダーをアピールできてもインパクトが小さくなってしまうおそれがあるでしょう。
【ガクチカの深掘り質問】面接の回答のコツと注意点
就職活動においては、どれだけ優れた経験をしていても、伝え方を間違えるとその価値が正しく評価されません。
面接官が注目しているのは「何をしたか」だけでなく、「どう考え、どんな工夫をしたか」という過程です。
ここでは、評価されるガクチカや面接回答をつくるために意識すべき5つのポイントを、就活生に向けてわかりやすく解説します。
結論から論理的に話すことを意識する
面接では、話の最初に結論を述べることが非常に重要です。
「私は〜〜な経験をしました」と結論から話すことで、相手はその後の話の方向性を理解しながら聞くことができます。
逆に、経緯や背景を長く語ったあとにようやく結論が出てくる話し方では、聞き手に「結局何が言いたいのか」が伝わらず、集中力を失わせてしまいます。
結論→理由→具体例→学びという順で構成することで、話に一貫性と説得力が生まれます。
これは論理的思考力の証明にもつながり、社会人としての資質をアピールする絶好の機会になります。
普段からこの話し方を意識しておくことで、他の質問にも柔軟に対応できるようになります。
背景や過去の状況を分かりやすく伝える
面接で自分の経験を話すとき、当時の状況や背景を相手が理解できるように丁寧に説明することが欠かせません。
自分にとっては当たり前だった環境やルールも、面接官には未知の世界です。
たとえば、所属していた団体の規模や自分のポジション、取り組んだ課題の重要性など、必要な情報を端的に説明するだけで、話の解像度は大きく上がります。
話が一方通行にならないよう、相手の反応を見ながら補足する意識も持ちましょう。
過去の自分の経験は、他人にとって「知らない物語」です。
だからこそ、情景が頭に浮かぶような説明を意識して話すことで、相手の共感や理解を得やすくなります。
なぜそう考えたのかを丁寧に伝える
面接で評価されるのは、単なる成果や行動だけでなく、「なぜその行動を選んだのか」という思考の背景です。
面接官は、あなたの考え方や価値観、判断基準を知るために深掘り質問をしてきます。
その際に「どうしてその選択をしたのか」「どんな点を重視して決めたのか」を自分の言葉で説明できることが大切です。
たとえば、「時間が限られていたので効率を優先した」など、選択の裏にある自分なりの考えを述べることで、相手はあなたの人柄を具体的にイメージできます。
表面的な出来事の羅列にとどまらず、行動の動機や判断軸を掘り下げて伝えることが、面接での信頼や納得感につながります。
成果は数字を用いて定量的に伝える
努力や成果を伝える際には、抽象的な表現ではなく、可能な限り数字を用いて説明することが重要です。
たとえば、「たくさん練習した」では説得力に欠けますが、「毎日2時間、半年間続けた」と言い換えるだけで、努力の量が明確に伝わります。
数字には説得力があるので、採用担当者がイメージしやすくなり、比較もしやすくなるため、評価につながりやすくなります。
また、面接官から「具体的にはどのくらいですか?」と再度聞かれる手間を減らすことにもなります。
目標値や改善率、担当件数など、少しでも数字に置き換えられる要素があれば積極的に活用しましょう。
専門用語は誰でも伝わるように言い換える
専門用語や特定分野の知識を含む話題を伝える際には、相手の理解度を意識した表現に変えることが重要です。
面接官はあなたの分野の専門家ではない可能性も高いため、難解な言葉や略語をそのまま使うと内容が伝わらず、印象が悪くなることもあります。
たとえば「KPIを管理していました」と言う代わりに、「目標の数字を日々チェックして改善策を考えていました」と言い換えると、ぐっとわかりやすくなります。
理解しやすさは、コミュニケーション能力の一部と見なされます。 相手に寄り添った言葉を選ぶことで、伝える力の高さも評価されます。
【ガクチカの深堀り質問】面接の際の基本的な伝え方
ガクチカを効果的に伝えるためには、基本的な構成をしっかりと押さえておくことが重要です。
結論から始まり、背景や課題、成果、そして学びといった要素を順序立てて説明することで、面接官に分かりやすく伝えることができます。
以下では、それぞれのポイントを詳しく解説します。
1. 結論「私のガクチカ=〇〇」
ガクチカを語る際は、最初に結論を述べることが重要です。
「私のガクチカは〇〇です」と明確に伝えることで、面接官は話の全体像を把握しやすくなります。
結論が曖昧だと、話の焦点がぼやけ、面接官に興味を持ってもらいにくくなります。
また、結論は簡潔でインパクトのある内容にすることが望ましいです。
たとえば、「アルバイトで売上を2倍にした経験」「部活動でチームを県大会に導いた経験」など具体的な成果を含めると、面接官の印象に残りやすくなります。
2. 背景「なぜ力を入れようと思ったのか」
結論を述べた後は、その経験に力を入れた背景を説明します。
たとえば、なぜその活動に取り組むことを決めたのか、どのような動機があったのかを具体的に述べるとよいでしょう。
背景の説明は、応募者の価値観や考え方を知る重要なポイントとなります。
同じ題材でも、動機や背景は人それぞれ異なるため、具体的なエピソードを交えて話すと説得力が増します。
背景をしっかりと伝えることで、行動の意味や意図が面接官に伝わりやすくなります。
3. 目的・目標・課題・困難
背景を述べた後は、その活動を通じて達成しようとした目的や目標、直面した課題について触れます。
たとえば、「売上を前年比10%アップさせるため」「チーム全員の技術を底上げするため」など、明確な目的を伝えることが大切です。
また、その目的を達成するためにどのような課題があったのかを具体的に説明することで、活動の難易度や意義を伝えることができます。
目的や課題が曖昧だと、取り組みの本質が伝わらないため注意が必要です。
4. 達成/解決するための過程
課題をどのように乗り越えたのか、具体的な行動や工夫を説明します。
たとえば、「売上向上のために商品の陳列方法を工夫した」「メンバー全員と面談を行い、課題を明確化した」など、実際の取り組みを細かく伝えることが大切です。
この部分では、応募者の行動力や問題解決能力が評価されます。
具体的な行動に一貫性があると、面接官に信頼感を与えることができます。
また、自分が主体的にどのような役割を果たしたのかも忘れずに伝えましょう。
5. その結果(成果)
取り組みの結果として得られた成果を明確に述べます。
たとえば、「売上を前年比20%向上させた」「チームを県大会準優勝に導いた」など、具体的な数値や結果を含めると説得力が高まります。
成果だけでなく、それが周囲や組織にどのような影響を与えたのかも補足すると良いでしょう。
また、成功した場合だけでなく、失敗した場合も「何を学んだのか」「次にどのように活かしたのか」を説明することで前向きな印象を与えることができます。
6. 学び・入社後への紐付け
最後に、その経験を通じて得た学びやスキルを、入社後どのように活かしたいかを伝えます。
たとえば、「課題解決力を活かし、御社の顧客対応に貢献したい」「チームをまとめる力を活かし、プロジェクトの成功に尽力したい」など、具体的に紐づけることが大切です。
この部分で入社後のビジョンが明確に示されると、企業側に「一緒に働きたい」と思わせることができます。
ガクチカを通じて、どのように企業に貢献できるかをしっかりとアピールしましょう。
自信を持って面接に臨もう!
今回はガクチカを面接で話す際に、どんな答え方をすれば良いのか?その対策方法は何なのか?などを、詳しく紹介しました。
何もわからない状態で面接に臨むのは、どうしても不安がよぎることでしょう。
しかし、本記事の内容を理解した上で対策すれば、そんな不安もきっとなくなるはずです。
人によってはどうしても入社したい企業が既に決まっていると思いますので、夢を実現するためにも、今からきちんと準備しておくようにしましょう。
おまけ
面接でよく聞かれる「尊敬する人は誰ですか?」についても対策したい方はこちら!


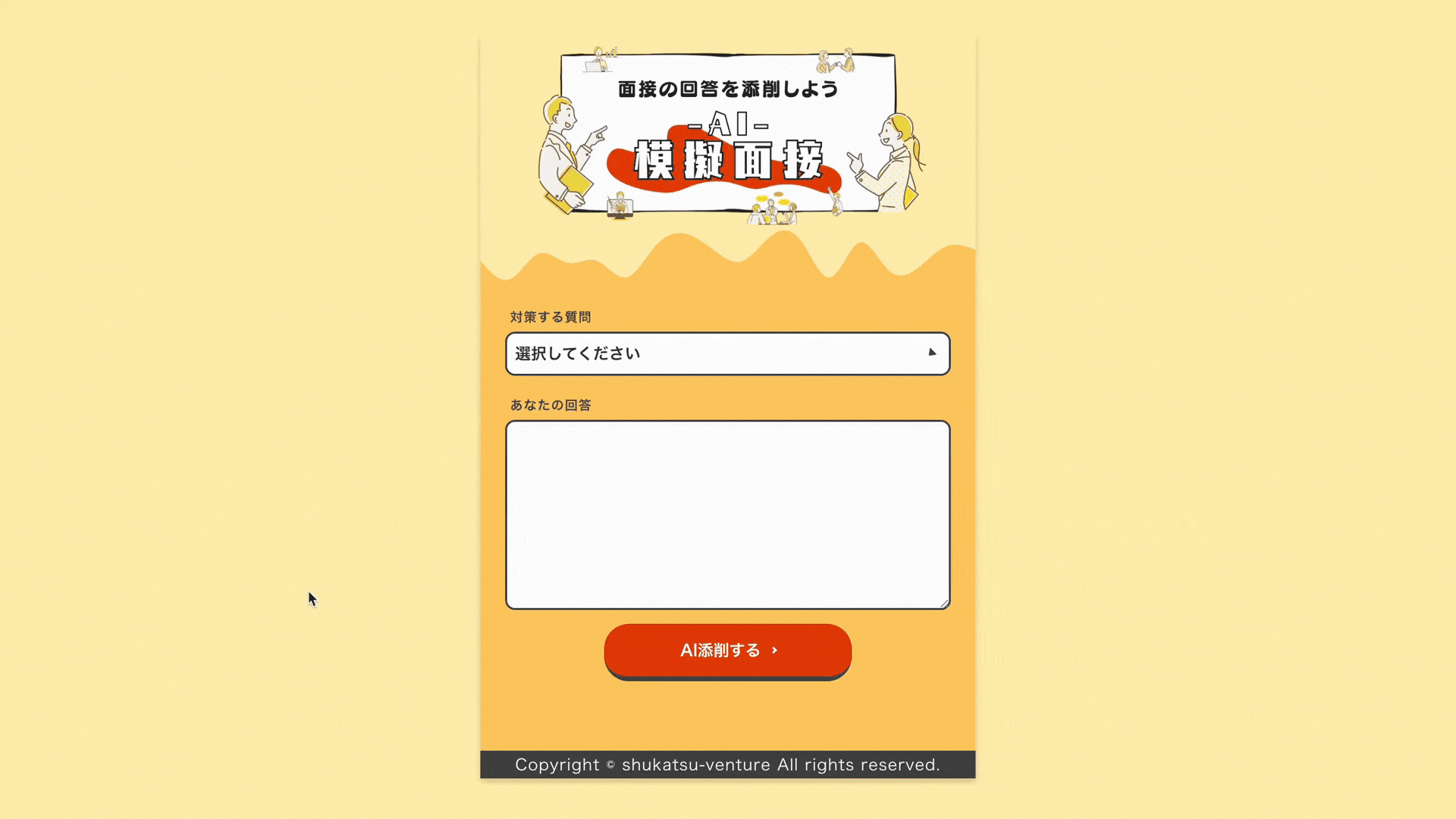
_720x550.webp)


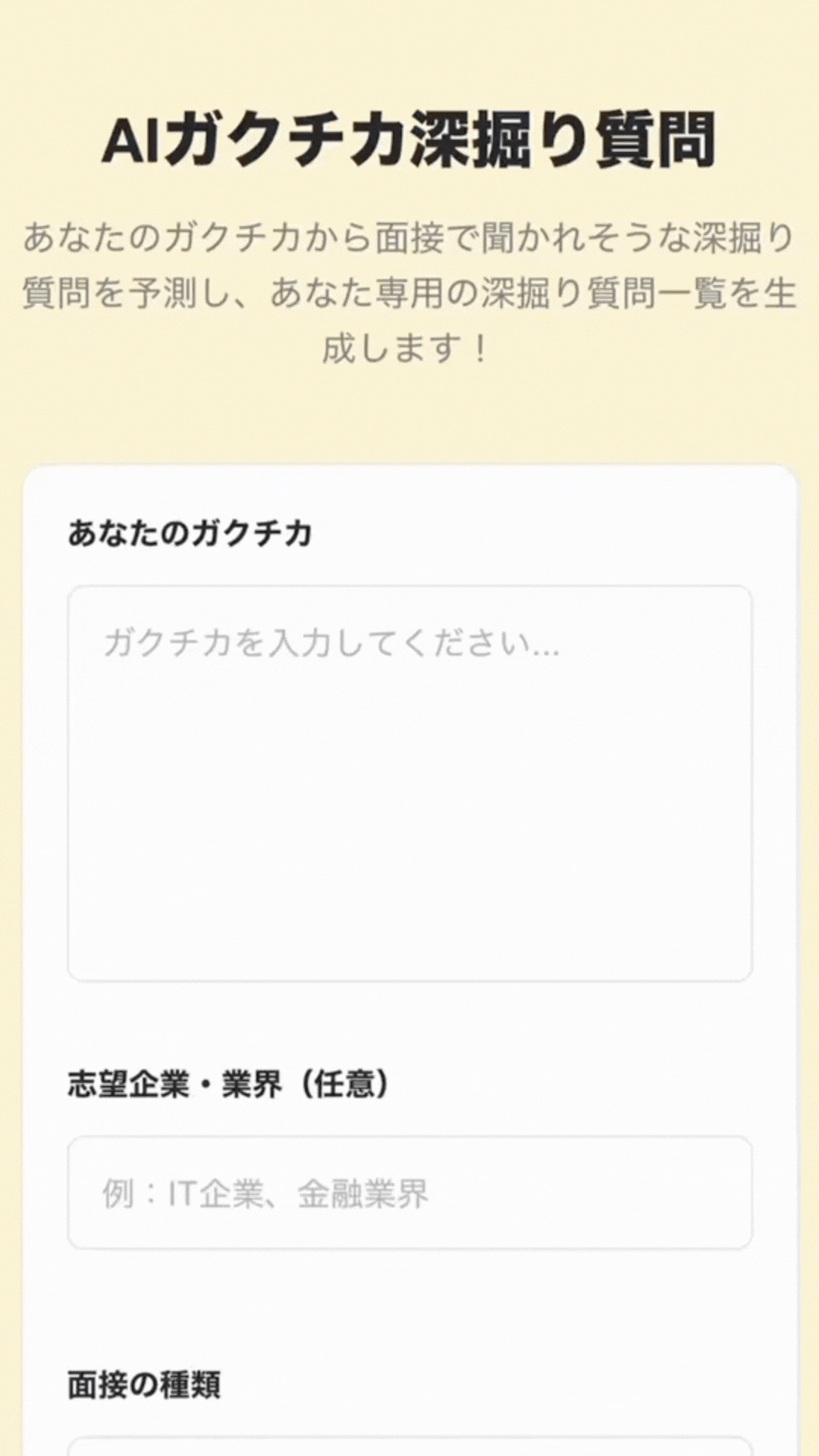
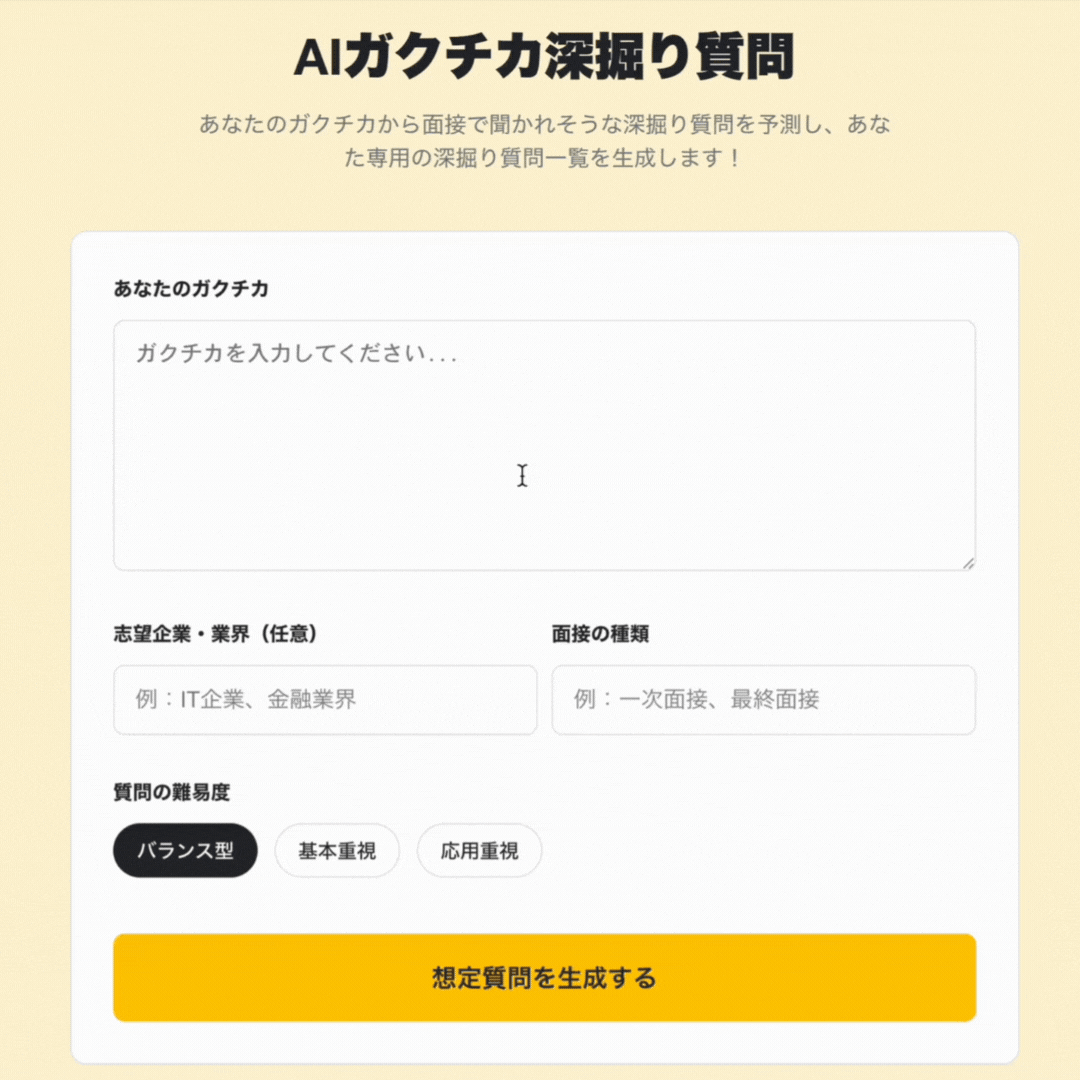
_720x550.webp)


_720x550.webp)








