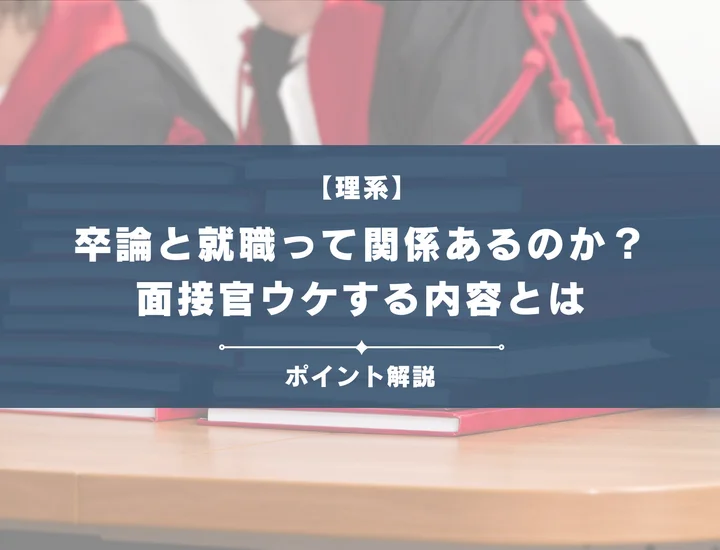HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
理系分野の専門知識を活かすキャリアとして、研究職は多くの学生が憧れを抱く魅力的な選択肢です。
最先端の技術開発に携わり、人類のまだ知らない新たな発見を追求する姿は、知的な探究心を持つ人にとって大きな魅力でしょう。
しかし、その華やかなイメージの裏には、乗り越えるべき多くの困難も存在します。
本記事では、理系研究職の仕事内容や役割といった基本から、仕事の厳しさ、そしてそれを上回るやりがいまで、多角的に詳しく解説します。
研究職とは?仕事内容と役割を解説
研究職は、科学技術の発展や新しい知識体系の構築を目的として、自らの専門分野に関する研究活動を遂行する仕事です。
その活動領域は、純粋な真理探究を目指す「基礎研究」から、実用化を視野に入れた「応用研究」、そして製品化に繋げる「開発研究」まで多岐にわたります。
未知の現象を解明し、社会や人々の生活に貢献する新たな価値を創造することが、研究職に課せられた重要な使命といえるでしょう。
研究職の定義
研究職とは、科学的なアプローチに基づき、これまで知られていなかった新事実の発見や、社会に役立つ新しい技術の創出を専門とする職種です。
研究活動は、大きく「基礎研究」と「応用研究」の二つのフェーズに大別されます。
基礎研究は、直接的な利益や実用化を目的とせず、自然界の法則や未知の現象を解明し、学術的な真理を探究することに主眼を置きます。
この段階での発見が、後の技術革新の種となることも少なくありません。
一方、応用研究は、基礎研究によって得られた知見や原理を基に、社会で実用化するための具体的な技術や製品に結びつけることを目的とします。
いずれの研究フェーズにおいても、課題に対して仮説を立て、実験による検証を行い、得られたデータから考察を導き出すという地道なプロセスを粘り強く繰り返すことが求められます。
企業研究職と大学の研究機関の違い
企業に所属する研究職と、大学や公的研究機関に所属する研究職とでは、その目的や環境が大きく異なります。
企業の研究は、最終的に自社の利益に貢献することが最大の目的です。
そのため、市場のニーズや将来的な事業化を強く意識した研究テーマが設定され、限られた期間と予算の中で成果を出すことが求められます。
成果は特許として権利化されることが多く、競争優位性の源泉となります。
一方、大学や公的研究機関では、学術的な真理の探究や、公共の福祉に貢献するような長期的な視点での研究が主となります。
研究テーマの自由度は企業よりも高い傾向にありますが、その活動資金は国からの運営費交付金や、競争的に獲得する外部の研究資金に依存します。
そのため、研究成果を論文として発表し、学術界からの評価を得ることや、研究費を獲得するための能力も極めて重要になります。
開発職との違いとは
研究職と開発職は、しばしば混同されがちですが、製品が世に出るまでのプロセスにおいて担う役割が明確に異なります。
研究職が「0から1」を生み出す、つまり新しい原理や技術のシーズ(種)を発見する仕事であるのに対し、開発職はそのシーズを基に「1を10」や「100」にする、つまり製品として量産・実用化するための具体的な設計を行う役割を担います。
研究職には、常識にとらわれない発想力や未知の課題に対する深い探究心が求められます。
それに対し開発職には、既存の技術を応用し、コスト、品質、安全性、生産性といった様々な制約条件をクリアしながら、市場の求める製品を形にするための高度な設計能力や課題解決能力が求められるのです。
両者は密接に連携しながら、ものづくりを進めていきます。
理系研究職がきついといわれる理由5選
理系研究職は、知的好奇心を満たせるやりがいの大きい仕事である一方、その道のりは決して平坦ではありません。
華やかなイメージや憧れだけでは乗り越えられない厳しい側面も数多く存在します。
ここでは、多くの研究者が経験する「きつい」と感じる現実について、代表的な5つの理由を掘り下げて解説します。
成果が出るまで時間かかる
研究活動は、短期間で目に見える結果が出ることは稀です。
一つのテーマに対して、仮説の設定、実験計画の立案、膨大な試行錯誤、データ分析、考察という非常に時間のかかるサイクルを何度も繰り返します。
数ヶ月から数年単位で地道な努力を続けても、必ずしも期待した成果が得られるとは限りません。
成果が全く見えない暗いトンネルの中を、ひたすら歩き続けるような期間が長く続くと、精神的なプレッシャーや焦りが心に重くのしかかります。
長期的な視点を持ち、結果が出ない状況でも信念を持って根気強く研究に取り組む姿勢が不可欠です。
競争が激しい
研究の世界は、常に国内外の研究者との熾烈な競争にさらされています。
同じ研究テーマに取り組むライバルは世界中に存在し、いかに早く、より質の高い成果を出し、世界初の手柄を立てるかが問われます。
論文発表のスピード競争や、それを巡る査読者とのやり取り、特許の出願競争は熾烈を極めます。
また、研究活動を継続するための予算獲得競争も年々激化しています。
質の高い研究計画書を作成し、プレゼンテーションで評価を得なければ、研究自体を始めることすらできません。
常に最新動向を追い、競争に勝ち続けるプレッシャーは相当なものです。
失敗の繰り返しに耐える忍耐力が必要
研究活動と失敗は、切っても切れない関係にあります。
むしろ研究とは、失敗の積み重ねそのものといえるかもしれません。
立てた仮説が実験によって否定されることは日常茶飯事であり、何百、何千という失敗の中から、ごく稀に一つの成功や新たな発見の糸口が見つかるのが実情です。
そのため、一つ一つの失敗に落胆するのではなく、その原因を冷静に分析して次への糧とする強靭な精神力、そして何度でも立ち上がる忍耐力が求められます。
思い描いた結果が得られない状況が続いても、モチベーションを高く維持し続けること自体が、研究者の重要な能力の一つです。
年収が思ったほど高くない
高度な専門性が求められる研究職ですが、その専門性に見合った高い年収が必ずしも保証されているわけではありません。
特に、博士号を取得した後の若手研究者の多くがキャリアの最初に就く「ポスドク(博士研究員)」は、1〜3年程度の任期付き雇用であることが多く、収入面でも不安定な立場に置かれがちです。
民間企業の研究職は比較的高収入を期待できますが、それでも成果主義が厳しく、プレッシャーも大きいです。
アカデミア(大学や公的研究機関)では、准教授や教授といった安定したポストは非常に限られており、そこに至るまでの道のりは長く険しいのが現実です。
海外論文の読解で語学力が必須
科学技術の世界において、最先端の研究成果のほとんどは、国際的な学術雑誌に英語の論文として発表されます。
そのため、自身の研究分野における最新の動向を正確に把握し、研究の方向性を決めるためには、英語論文を迅速かつ正確に読み解く高度な読解力が不可欠です。
また、国際学会での研究発表や質疑応答、海外の研究者との共同研究におけるメールやオンライン会議など、英語でのコミュニケーション能力が求められる場面も日常的に発生します。
語学に苦手意識があると、研究者として活動する上で大きなハンデとなり得ます。
理系研究職のやりがいとは?
研究職の厳しい側面について解説しましたが、もちろんそれを上回る大きなやりがいと魅力が存在します。
多くの困難を乗り越えた先に待っている喜びや達成感こそが、研究者を惹きつけてやまない醍醐味です。
ここでは、多くの研究者が仕事の中に感じる、かけがえのないやりがいについて解説します。
未知な課題へのワクワク感
研究職の最大の魅力は、世界中の誰もまだ解明していない謎や、解決されていない課題に、人類の代表として挑戦できることです。
「この現象の根本原因は何か」「どうすればこの課題を解決できるのか」という純粋な知的好奇心を満たしながら仕事を進めることができます。
自分の立てた仮説が実験で証明され、人類の知の地平線をわずかでも広げられた瞬間は、何物にも代えがたい喜びです。
まるで壮大な知のパズルを解き明かすような、常に新鮮なワクワク感が伴うのが研究という仕事の醍醐味です。
社会の進歩に貢献できる
自身の研究成果が、目に見える形で社会の進歩に貢献できる点も、大きなやりがいの一つです。
開発した新しい医薬品が、これまで治療が難しかった病気の患者さんを救うかもしれません。
発明した画期的な材料が、エネルギー問題や環境問題の解決に大きく貢献するかもしれません。
自分の仕事が、人々の生活をより豊かに、より安全にし、より良い未来を創造する一助となっているという実感は、大きな誇りと使命感をもたらしてくれます。
社会的な意義の大きい仕事に携われることが、研究職の大きな魅力なのです。
専門性を高めることができる
研究職は、自分が選んだ特定の分野において、誰よりも深い知識と高度な技術をとことん追求できる仕事です。
日々、世界中から発表される最先端の論文を読み、新たな実験手法を学び、試行錯誤を繰り返す中で、自身の専門性は着実に、そして際限なく高まっていきます。
ひとつの道を究めるスペシャリストとして、その分野の第一人者、いわば「生き字引」のような存在になれる可能性も秘めています。
自身の知的な成長を日々実感しながら、常に新しい挑戦を続けられる環境は、学ぶ意欲の高い人にとって最高の職場といえるでしょう。
成果が形になったときの達成感
長期間にわたる地道な努力と、数えきれないほどの失敗を乗り越えて、研究がようやく実を結んだ瞬間の達成感は筆舌に尽くしがたいものがあります。
苦労して得られたデータが論文として権威ある学術雑誌に掲載されたとき、開発した技術が特許として認められたとき、そしてそれが製品として世に出て多くの人々に使われたとき。
その喜びは、それまでの苦労をすべて吹き飛ばすほどのインパクトがあります。
困難な道のりであった分、成果が具体的な「形」になったときの感動は計り知れず、これが次の困難な研究へと向かう大きなモチベーションとなります。
研究職におすすめの業界
理系の専門知識を活かせる研究職は、化学、製薬、機械、ITといった、さまざまな産業界で活躍の場が広がっています。
各業界で求められる専門性や研究内容は異なり、それぞれのカルチャーも多様です。
ここでは、研究職が多く活躍している代表的な業界を挙げ、その特徴や研究内容について紹介します。
化学・素材系の研究職
化学・素材メーカーは、伝統的に理系研究職が活躍してきた代表的な業界です。
スマートフォンや自動車に不可欠な高機能樹脂、鮮やかな発色を持つ有機ELディスプレイ材料、半導体の性能を左右する電子材料、航空機の軽量化に貢献する炭素繊維など、あらゆる工業製品の根幹を支える新素材・新技術の研究開発を担います。
川上産業として、社会全体の技術革新を支える重要な役割を果たしています。
近年では、環境負荷の少ないサステナブルな材料開発や、二酸化炭素の分離・回収技術といった、地球規模の課題解決に貢献する研究も活発です。
製薬・バイオ系の研究職
製薬会社やバイオテクノロジー関連企業の研究職は、人々の健康や生命に直接貢献するという、極めて大きな使命を帯びた仕事です。
その中心的な役割は、病気のメカニズムを解明し、治療に役立つ新しい医薬品の候補物質を探し出す「創薬研究」です。
候補物質の探索から動物実験、そして臨床試験へと進むプロセスは十数年かかることもあり、非常に根気が求められます。
また、iPS細胞を用いた再生医療、遺伝子治療、がんの早期発見を可能にする診断薬の開発など、最先端の生命科学技術を駆使した研究開発が日夜行われています。
電機・自動車・機械系の研究職
電機・自動車・機械系のメーカーは、日本のものづくり産業を牽引する重要な業界です。
研究職は、数年先の未来を見据え、次世代の製品やサービスを生み出すための基盤技術や先進技術の研究開発を担います。
具体的には、AI技術を駆使した自動運転システム、次世代通信規格(6G)に対応したデバイス、より現実に近い体験を提供するVR/AR技術、工場の生産性を劇的に向上させるスマートファクトリー関連技術など、そのテーマは社会の動向を色濃く反映し、多岐にわたります。
ソフトウェアとハードウェアの知識を融合させた研究開発がますます重要になっています。
IT・AI・データサイエンス系の研究職
第四次産業革命の中核をなすIT・AI分野では、研究職の需要が急速に高まっています。
GAFAMに代表される巨大IT企業やスタートアップにおいて、AI(人工知能)の新たなアルゴリズム開発、大量のデータを分析して未来予測や意思決定に役立てるデータサイエンス、より自然な対話を実現する自然言語処理、高精度な画像認識技術など、社会のあり方を根本から変える可能性を秘めた研究が進められています。
情報科学系のバックグラウンドを持つ人材が中心となり、様々な産業分野との連携も活発です。
理系研究職に向いてる人の特徴
研究職として大きな成果を出し、キャリアを築いていくためには、専門知識や技術力だけでなく、その人の持つ性格的な特性やマインドセットも大きく影響します。
高い専門性を求められる厳しい環境の中で、継続的にパフォーマンスを発揮できる人には、いくつかの共通した特徴が見られます。
興味をもち続けられる好奇心がある人
研究職に最も不可欠な資質は、まるで子供のように「なぜ?」と問い続けられる、尽きることのない好奇心です。
目の前の現象に対して当たり前だと思わずに疑問を持ち、その本質的なメカニズムを解明したいという強い知的な欲求が、長く困難な研究活動を続ける上での原動力となります。
論文を読んだり、実験をしたりといった日々の業務を、タスクとしてこなすのではなく、自らの知的好奇心を満たすための探求活動として心から楽しめる人が研究職に向いています。
地道な作業でもコツコツ続けられる
研究活動の現実は、華やかな発見の瞬間よりも、その裏側にある膨大な量の地道な作業によって成り立っています。
関連する過去の論文を何十本も読み込む文献調査、単純作業の繰り返しとなる実験の準備や後片付け、試薬の精密な計量、緻密な実験ノートの記録、膨大なデータの整理など、根気のいる作業が大部分を占めます。
こうした一見すると単調な作業にも、その重要性を理解し、真摯に向き合い、手を抜かずにコツコツと努力を続けられる誠実さと忍耐強さが不可欠です。
論理的思考力がある
研究は、極めて論理的な思考プロセスの連続です。
まず、既存の事実やデータから課題を抽出し、それを説明するための一貫した仮説を立てます。
次に、その仮説が正しいかどうかを客観的に検証するために、バイアスを排除した最適な実験計画を論理的に設計し、実行します。
そして、得られた結果(データ)という客観的な事実に基づいて、感情や思い込みに流されることなく冷静に分析・考察し、妥当な結論を導き出します。
このように、物事を体系的に捉え、筋道を立てて矛盾なく考えを組み立てる論理的思考力は、研究者にとって根幹をなす必須スキルです。
結果が出なくてもやり続けることができる
研究活動において、失敗は避けて通れないどころか、むしろ日常です。
立てた仮説のほとんどは、無情な実験結果によって否定されるのが現実です。
思うような結果が何ヶ月、場合によっては何年も出ないことも珍しくありません。
このような逆境においても「このアプローチが駄目だと分かったことも一つの成果だ」と前向きに捉え、気持ちを切り替えて次の戦略を考えられる精神的なタフさが求められます。
すぐに諦めず、目標に向かって粘り強く、楽観的に努力を続けられる人が、最終的に大きな成功を手にすることができるのです。
理系が研究職に就くために必要な学歴は?
研究職という専門性の高いキャリアを目指す理系学生にとって、学歴は自身の専門性や能力を証明するための重要な指標となります。
一般的に、より高度な研究開発に携わるためには大学院への進学が有利に働きます。
ここでは、学部卒、修士卒、博士卒それぞれのキャリアの違いや、専攻がどの程度影響するのかについて解説します。
学部卒・修士卒・博士卒の違い
企業の技術系職種において、学部卒と大学院卒とでは期待される役割が異なることが一般的です。
学部卒の場合、研究開発の最前線というよりは、開発、生産技術、品質管理といった製造現場に近い部署に配属されることが多いです。
企業の研究職の応募資格は、修士課程修了以上としている場合がほとんどです。
修士卒は、2年間の研究活動を通して研究の基礎的な進め方や専門知識を習得した「研究のプレイヤー」として期待されます。
一方、博士卒は、特定の分野で極めて高度な専門知識と、自律的に研究テーマを立案・遂行する能力を持つ「研究のプロフェッショナル」として、より難易度の高いテーマや将来の研究リーダー候補として採用される傾向が強くなります。
専攻はどこまで影響するのか?
研究職の採用においては、企業の事業内容や研究開発の方向性と、学生が大学で学んできた専攻分野との親和性が非常に重視されます。
化学メーカーであれば化学・材料科学系、製薬会社であれば薬学・生命科学・農学系、電機メーカーであれば電気電子・情報・物理系といったように、専門性が事業に直結する分野での採用が基本となります。
自身の専攻で培った専門知識や研究経験を、その企業でどのように活かし、貢献できるのかを具体的にアピールすることが、選考を突破する上で極めて重要な鍵となります。
語学力やプログラミングなどの汎用スキルも重要
高度な専門知識に加えて、分野を問わず役立つ汎用的なスキルを身につけておくことは、研究者としてのキャリアの可能性を大きく広げます。
特に、世界の最新の研究成果をリアルタイムで収集し、国際的な場で議論するために、英語論文を読みこなし、コミュニケーションが取れる語学力は、現代の研究者にとって必須のスキルです。
また、近年では、大量の実験データを効率的に解析したり、複雑な現象をシミュレーションしたりするために、Pythonなどのプログラミングスキルや統計学の知識が専門分野を問わず求められています。
これらのポータブルスキルは、自身の専門性をさらに輝かせる強力な武器となります。
研究職の就活で知っておくべきこと(ES・面接対策)
研究職を志す就活生にとって、専門性をどう伝えるかや企業への志望理由をどう示すかは重要な課題です。
研究概要のまとめ方や志望動機の深掘り、さらには面接での逆質問など、準備次第で評価は大きく変わります。
単に研究内容を説明するだけではなく、自分の強みと企業が求める人物像を結びつけることが大切です。
ここでは研究職の就活で押さえておくべき具体的なポイントを解説します。
研究概要の書き方のポイント
研究概要を書く際に大切なのは、相手が短時間で理解できる形に整理することです。
まず結論から述べ、研究テーマと目的を最初に明確に示します。
次に、その研究がなぜ必要なのかを背景や現状の課題とともに簡潔に説明します。
その上で、自分が研究の中で具体的に取り組んだことを詳しく記すことが重要です。
実験の工夫や方法の改善など、成果に至るまでのプロセスを示すことで、問題解決力や主体性を伝えられます。
また得られた結果をまとめるだけではなく、その研究が社会や業界にどのように役立つのかを最後に述べると効果的です。
研究の意義を客観的に示すことで、専門性をアピールしながら説得力のある自己紹介につながります。
なぜその企業で研究したいのかを明確にする
研究職の面接では必ず問われるのが、その企業を志望する理由です。
重要なのは、企業の研究分野や技術と自分の研究テーマをどう結びつけるかという点です。
企業が掲げる技術や理念、将来のビジョンを理解した上で、自分の研究で培った知識や経験をどう活かせるかを説明する必要があります。
単なる憧れや一般的な志望理由ではなく、具体的にどんな成果を目指したいのかを語ると説得力が増します。
また入社後にどのような研究を進めたいか、どんな形で社会に貢献したいかを描けると印象はより強まります。
自分の強みと企業の強みを重ね合わせて伝えることで、双方の相性を示すことができ、研究職としての熱意も効果的に伝わります。
面接で差をつける逆質問の具体例
面接の最後に聞かれる質問は、自分の関心や意欲を伝える重要な場面です。
単なる形式的な質問ではなく、相手の経験や企業独自の取り組みに関する内容を準備すると印象が良くなります。
例えば今後の研究開発で注力する技術分野や、チームで大切にしている価値観について尋ねることで、企業の方向性に興味を持っている姿勢を示せます。
また自分の研究内容を入社後にどう活かせるかを尋ねれば、前向きに貢献したい意欲を伝えられます。
重要なのは調べればわかることを聞くのではなく、自分が真剣にその企業で働きたいと考えていることが伝わる質問にすることです。
逆質問は準備次第で評価を大きく高められるため、事前に複数の質問を用意しておくと安心です。
研究職のキャリアパスと将来性
研究職と聞くと、ひたすら研究だけを続けるイメージを持つ人も少なくありません。
しかし実際には、研究で培った専門知識やスキルを土台に、さまざまなキャリアパスが広がっています。
組織をまとめる立場に進む人もいれば、一つの分野を深め続ける道を選ぶ人もいます。
また大学での研究活動や起業といった新しい挑戦につなげることも可能です。
ここでは代表的な研究職のキャリアパスを紹介します。
マネジメント職へのキャリアアップ
研究職で経験を積んだ後、研究チームを率いるリーダーや研究部門の管理職に進む道があります。
この場合、単に技術を磨くだけではなく、組織全体を動かす力が求められます。
具体的には、プロジェクトの進捗を管理し、研究方針を決め、予算を計画し、チームメンバーを育成するなど多面的な役割を担います。
研究者としての深い知識に加えて、コミュニケーション能力やリーダーシップ、事業全体を見渡す視点が必要になります。
特に企業研究においては、研究成果を事業化につなげることが重視されるため、経営との橋渡し役を果たす存在として期待されます。
技術力だけでなく、人をまとめる力や戦略的に物事を考える力を兼ね備えることで、大きな責任を担うポジションへキャリアを広げることができます。
技術専門職としての道
マネジメントではなく、自らの専門分野を極め続ける道を選ぶ研究者もいます。
この場合、組織の中で特定の分野を深掘りし、最先端の研究成果を出し続けることが求められます。
企業によっては「フェロー」や「主席研究員」といった専門職の役職が用意されており、高度な専門性を持つ人材として処遇されます。
このキャリアを選ぶ人は、自分の研究を社会に還元したいという強い思いを持ちながら、研究の第一線で成果を積み重ねていきます。
また社外の学会や国際的な研究ネットワークでの発信を通じて、その分野を牽引する役割を果たすこともあります。
研究を究める道は、社会にとって新しい技術や価値を生み出す源泉であり、専門性を高めたい人にとって魅力的な選択肢です。
大学研究者や起業家という選択肢
研究職のキャリアは、企業内だけに限られません。
大学に進んで研究者として活動する道もあり、ここでは企業とは異なり、より自由なテーマに取り組むことが可能です。
基礎研究を進めながら論文を発表し、後進の育成に携わることは学術界ならではのやりがいです。
一方で、起業という形で研究成果を社会に実装する道を選ぶ人もいます。
自ら会社を立ち上げ、研究で得た知見を活かして新しい製品や技術を世に送り出す挑戦です。
この場合、ビジネスモデルの構築や資金調達、マーケティングなど研究以外の知識も求められますが、その分大きな影響を与えられる可能性があります。
大学研究者や起業家という選択肢は、研究で培った力を新たな形で社会に還元する道として注目されています。
まとめ
本記事では、理系研究職の仕事内容から、その厳しさ、そしてそれを上回る大きなやりがいまでを多角的に解説しました。
研究職は、成果が出るまで時間がかかり、熾烈な競争に常にさらされるなど厳しい側面がある一方で、人類の未知に挑戦するワクワク感や、社会の進歩に貢献できるという、何物にも代えがたい魅力を持つ仕事です。
この記事が、研究職というキャリアの多面的な姿を理解し、ご自身の進路を考える上での一助となれば幸いです。