
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
エントリーシート(ES)で頻出の「最近気になるニュース」という質問。
単なる時事問題の知識を問うているのではなく、あなたの情報感度や思考力、人柄まで見られています。
他の就活生と差をつけるには、戦略的なニュース選びと論理的な文章構成が不可欠です。
この記事では、企業がこの質問をする意図から、具体的なニュースの選び方、避けるべき話題、さらには情報収集に役立つツールや業界別の例文まで、網羅的に解説します。
この記事を読めば、「気になるニュース」の質問はもう怖くありません。
万全の準備で、あなたの魅力を最大限にアピールしましょう。
目次[目次を全て表示する]
【気になるニュース es】企業が聞く理由
企業がESで「気になるニュース」を質問するのは、単にあなたの時事知識を知りたいからだけではありません。
その回答から、あなたの情報感度や価値観、物事に対する洞察力など、多角的な側面を評価しようとしています。
この質問の裏にある企業の意図を正しく理解することが、的確なアピールへの第一歩です。
ここでは、企業がこの質問を通して何を確認しようとしているのか、その主な理由を3つのポイントに分けて詳しく解説します。
これらのポイントを押さえることで、企業が求める人物像を意識した回答を作成できるようになるでしょう。
情報収集力の確認
現代のビジネス環境は、日々目まぐるしく変化しています。
そのため、企業は自社の事業を取り巻く社会の動向や最新技術、競合の動きなどを常に把握し、迅速に対応していく必要があります。
就活生に「気になるニュース」を問うことで、普段からどれだけアンテナを高く張り、世の中の出来事に注意を払っているか、その情報収集の姿勢と能力を見極めようとしています。
特定のニュースをただ知っているだけでなく、その背景や関連情報まで含めて多角的に情報を集め、自分なりに整理・分析できているかが評価のポイントとなります。
日常的にニュースに触れ、情報を主体的にインプットする習慣があることをアピールすることが重要です。
社会的意識の高さの確認
企業は社会の一員として、利益追求だけでなく、社会貢献やコンプライアンス遵守といった社会的責任(CSR)を果たすことが求められています。
そのため、自社の社員にも、社会で起きている様々な問題に関心を持ち、自分事として捉えることのできる高い倫理観や当事者意識を期待しています。
あなたがどのようなニュースに関心を持つかによって、環境問題、人権問題、地域活性化といった社会的な課題に対する意識の高さや、その価値観が自社の理念と合致しているかを確認しています。
単に経済ニュースだけでなく、より広い視野で社会全体を見渡していることを示すことで、人間的な深みやバランス感覚のある人材だと評価されるでしょう。
就活生の感性の確認
同じニュースに触れても、どこに注目し、何を感じ、どう考えるかは人それぞれです。
その「感じ方」や「考え方」には、その人の持つ独自の感性や価値観、物事の本質を見抜こうとする洞察力が表れます。
企業は、あなたが選んだニュースとその考察から、あなたの個性や人柄、そして潜在的なポテンシャルを読み取ろうとしています。
他の人とは違うユニークな視点や、物事を深く掘り下げて考える力、あるいは課題解決に向けたポジティブな姿勢などを示すことができれば、面接官に強い印象を残すことができます。
あなたならではの感性を大切にし、自分らしい言葉で意見を述べることが、効果的な自己アピールにつながります。
【気になるニュース es】ニュースの選び方
「気になるニュース」という設問で評価を高めるためには、戦略的なニュース選びが欠かせません。
数あるニュースの中から何を選ぶかによって、あなたの印象は大きく変わります。
重要なのは、「あなたらしさ」と「企業との関連性」を両立させることです。
ここでは、ESで書くべきニュースを選ぶ上で特に意識したい4つの基準を具体的に解説します。
これらのポイントを参考に、あなたという人材の魅力を最大限に引き出し、採用担当者の心に響くニュースを選び出しましょう。
一年以内のニュースを選ぶ
「最近気になるニュース」という質問に対して、数年前の出来事を挙げるのは適切ではありません。
情報の鮮度は、あなたの社会に対する関心の高さを示す重要な指標です。
目安として、原則として設問に答える時点から遡って「一年以内」のニュースを選ぶようにしましょう。
これにより、あなたが継続的に情報収集を行っているアクティブな人材であることを示せます。
特に、数ヶ月以内に報じられた話題であれば、よりタイムリーな印象を与えられます。
ただし、古すぎるニュースがNGなだけで、数ヶ月前のニュースでも、その後の続報に触れたり、現在の状況と結びつけて論じたりすることで、深い理解度をアピールすることが可能です。
志望する企業や業界に関連するものを選ぶ
最も効果的なアピールにつながるのが、志望する企業や業界に直接的・間接的に関連するニュースを選ぶことです。
例えば、メーカー志望なら新しい技術や素材、サプライチェーンに関するニュース、金融志望なら金融政策やフィンテックの動向などが挙げられます。
これにより、業界研究をしっかりと行っていること、そしてその業界で働くことへの強い意欲と当事者意識を示すことができます。
企業のウェブサイトで公開されているプレスリリースや中期経営計画などを読み込み、企業が今どのような課題に直面し、どこへ向かおうとしているのかを把握した上でニュースを選ぶと、より的を射た内容になり、入社後の活躍イメージを持たせやすくなるでしょう。
自分の意見を持てるニュースを選ぶ
他人の受け売りや、ニュースの概要を要約しただけの内容では、あなたの魅力は伝わりません。
企業が知りたいのは、そのニュースに触れて「あなた自身が何を考えたか」です。
「なぜそのニュースが気になったのか」「その出来事についてどう思うか」「自分ならどうするか」といった、あなた自身の意見や考察を深められるテーマを選びましょう。
そのためには、単に興味深いというだけでなく、自分の過去の経験や学んできたこと、将来の目標などと結びつけて語れるニュースが理想的です。
自分の言葉で、論理的に、そして情熱を持って語れるニュースこそが、あなたらしさを最も効果的に伝えられる最高のテーマとなります。
【気になるニュース es】避けるべきニュース
ニュース選びはアピールの絶好の機会ですが、テーマによってはかえってマイナスの印象を与えてしまうリスクも伴います。
特に、個人の思想信条やプライベートに深く関わる内容は、ビジネスの場にふさわしくないと判断される可能性があるため注意が必要です。
ここでは、ESや面接で「気になるニュース」として取り上げるべきではない代表的なテーマを3つ紹介します。
これらのトピックを避けることは、不必要な誤解や対立を生まず、スムーズなコミュニケーションを築くための重要なマナーと心得ましょう。
宗教や政治に関わるニュース
宗教や政治に関する話題は、個人の価値観や信条が色濃く反映されるため、非常にデリケートなテーマです。
採用担当者とあなたの考えが異なっていた場合、無用な対立や気まずい雰囲気、あるいは思想的な偏りに対する懸念を生む可能性があります。
特定の政党や宗教団体を支持、あるいは批判するような内容は、ビジネスにおける客観性や協調性を疑われるリスクがあるため、絶対に避けましょう。
たとえ社会的に大きな話題となっていたとしても、自らこのテーマに踏み込む必要はありません。
あくまでビジネスパーソンとしての適性を見られていることを意識し、中立的で誰もが客観的に議論できるテーマを選ぶのが賢明です。
芸能関係のニュース
芸能人の結婚やスキャンダル、エンターテインメントのゴシップといった話題は、多くの人の関心を集めますが、ESのテーマとしては不適切です。
これらのニュースは、社会や経済に与える影響が限定的であり、ビジネスへの関心や社会人としての意識の高さを示すことにはつながらないからです。
話が盛り上がる可能性はあっても、それはあくまで私的な会話の領域です。
企業の採用選考という公的な場では、あなたの仕事に対する姿勢や思考力を示すことが求められています。
芸能ニュースを選んでしまうと、「社会問題への関心が薄い」「仕事とプライベートの区別がついていない」といったマイナスの評価を受ける可能性が高いでしょう。
個人的なニュース
「気になるニュース」という質問は、あくまで社会で起きている出来事について問うものです。
「友人が結婚した」「サークルの大会で優勝した」といった、あなたやあなたの身の回りの出来事は、ここで答えるべき「ニュース」ではありません。
これらは自己PRやガクチカ(学生時代に力を入れたこと)で語るべきエピソードであり、設問の意図を理解していないと判断されてしまいます。
企業の採用担当者は、あなたの社会に対するアンテナの感度を知りたいのであって、あなたのプライベートな日記に興味があるわけではありません。
必ず、新聞やテレビ、信頼できるニュースサイトなどで報じられている公共性のある出来事の中からテーマを選びましょう。
説明しかできない浅いニュース
ニュース選びで陥りやすい失敗が、ただ概要を説明するだけで終わってしまう浅いニュースを選ぶことです。
例えば「新商品が発売された」「〇〇選手が優勝した」といった事実だけを述べても、自分の考えや視点がなければ評価にはつながりません。
企業が知りたいのはニュースそのものではなく、それを通じて就活生がどのように考え、どのような価値観を持っているかという点です。
浅いニュースしか扱えない場合、面接官に「調べていない」「思考が浅い」と受け止められる可能性があります。
選ぶ際は、背景や影響を自分なりに分析できるテーマを意識することが重要です。
【気になるニュース es】情報収集に役立つ媒体
質の高い回答を作成するためには、日頃からの質の高い情報収集が欠かせません。
世の中には多種多様な情報媒体が存在しますが、それぞれに特性があり、就職活動においては目的に応じて使い分けることが重要です。
ここでは、信頼性が高く、ビジネスに関連する深い情報を得るために特に役立つ4種類の媒体を紹介します。
これらの媒体を複数組み合わせて活用することで、多角的な視点を養い、自分なりの意見を構築するための強固な土台を築くことができます。
毎日の生活の中に、意識的に情報収集の時間を取り入れてみましょう。
新聞
新聞は、最も信頼性の高い情報源の一つです。
政治、経済、国際、社会、文化など、幅広い分野のニュースを網羅的に提供しており、社会全体の動きをバランス良く把握するのに最適です。
特に、日本経済新聞(日経新聞)は、ビジネスパーソンの多くが購読しており、企業の動向や経済指標に関する詳細な情報が豊富です。
記事は、専門の記者が取材と裏付けに基づいて執筆しているため、情報の正確性が担保されています。
また、一面や社説を読むことで、その時々の重要なテーマや世の中の論調を知ることができます。
電子版であれば、キーワード検索で関心のある業界の記事を効率的に集めることも可能です。
テレビニュース
テレビニュースは、映像と音声で情報を伝えてくれるため、複雑な内容でも直感的に理解しやすいというメリットがあります。
特に、現場の雰囲気や人々の表情、実際の製品などが映像で示されることで、ニュースへの理解が深まり、記憶にも残りやすくなります。
夜に放送される経済ニュース番組、例えばテレビ東京系列の「ワールドビジネスサテライト(WBS)」などは、その日の経済の動きをまとめて解説してくれるため、効率的な情報収集に役立ちます。
また、ドキュメンタリーや特集番組では、一つのテーマを深く掘り下げており、問題の背景や構造を体系的に理解する上で非常に有用です。
ニュースアプリやサイト
スマートフォンやPCで手軽に情報を得られるニュースアプリやサイトは、移動中や隙間時間の活用に非常に便利です。
速報性に優れており、常に最新の情報をキャッチアップすることができます。
多くのアプリでは、自分の興味のある分野やキーワードを登録することで、関連ニュースを効率的に集める「パーソナライズ機能」が備わっています。
また、「NewsPicks」のように、専門家のコメントと共にニュースを読むことができるサービスは、一つの出来事に対する多角的な視点を養うのに役立ちます。
ただし、情報の信頼性にはばらつきがあるため、運営元が確かな報道機関のサイトやアプリを選ぶことが重要です。
ビジネス雑誌
週刊や月刊のビジネス雑誌は、タイムリーな話題を深掘りした特集記事が魅力です。
『週刊東洋経済』や『週刊ダイヤモンド』などは、特定の業界や企業について、独自の視点から鋭い分析を行っており、業界研究に非常に役立ちます。
企業の財務状況や力関係、今後の課題などが図やグラフを用いて分かりやすく解説されているため、新聞やニュースだけでは得られない深いインサイトを得ることができます。
また、「業界地図」のような書籍も出版しており、業界全体の構造を俯瞰的に理解するのに最適です。
気になる業界の特集が組まれている際は、ぜひ手に取ってみることをお勧めします。
【気になるニュース es】おすすめのニュースアプリ・サイト・番組
日々の情報収集を効率的かつ効果的に進めるためには、自分に合ったツールを見つけることが大切です。
世の中には数多くのニュースメディアがありますが、特に就職活動を意識するなら、経済やビジネスに強く、信頼性の高いものを選ぶべきです。
ここでは、多くのビジネスパーソンや就活生に利用されている、おすすめのニュースアプリ、サイト、テレビ番組を5つ厳選して紹介します。
それぞれの概要、メリット、デメリットを詳しく解説するので、自分の目的やライフスタイルに合わせて活用してみてください。
日本経済新聞
日本経済新聞(日経新聞)は、日本の経済を中心に、政治、国際、社会、マーケット情報などを幅広く報じる、国内最大手の経済新聞です。
企業動向や金融政策、テクノロジーに関する記事が豊富で、多くのビジネスパーソンにとって必須の情報源とされています。
朝刊・夕刊の紙媒体のほか、電子版(日経電子版)では速報やオリジナル記事、専門家による解説なども充実しています。
最大のメリットは、情報の信頼性と網羅性の高さです。
企業のIR情報や政府の発表など、一次情報に近い正確な情報を得ることができます。
また、志望企業や業界の動向を深く掘り下げるのに最適で、ESや面接で語るネタの宝庫です。
日経を読んでいること自体が、ビジネスへの関心の高さを示すアピールにもなります。
電子版は検索性が高く、過去記事の閲覧も容易です。
有料であることがデメリットとして挙げられます。
学生向けの割引プランもありますが、無料で利用できるニュースアプリに比べると金銭的な負担は大きくなります。
また、経済に関する専門的な内容が多いため、読み慣れていないうちは難しく感じることがあるかもしれません。
経済以外のニュース、特に文化やエンタメ関連の情報は比較的少ない傾向にあります。
ワールドビジネスサテライト
ワールドビジネスサテライト(WBS)は、テレビ東京系列で平日の夜に放送されている経済ニュース番組です。
「経済を“池上彰さんばりに”わかりやすく伝える」をモットーに、その日の経済ニュースやマーケットの動き、企業の最新の取り組み、ヒット商品の裏側などを深く掘り下げて伝えます。
個人投資家から経営者まで、幅広い層に支持されています。
映像を使って解説してくれるため、複雑な経済の仕組みや最新技術も直感的に理解しやすいのが大きな利点です。
企業の最前線で働く人々の生の声や、製品・サービスの実際の様子を見ることができるため、ニュースをより身近に感じられます。
トレンドや注目されているテーマを効率良く把握でき、ESで語るべき話題を見つけるきっかけにもなります。
TVerなどでの見逃し配信もあり、時間を問わず視聴可能です。
放送時間が平日の夜遅く(22時〜)であるため、リアルタイムでの視聴が難しい場合があります。
また、ニュースの網羅性という点では新聞に劣り、放送時間内に扱える情報量には限りがあります。
速報性よりも、一つのテーマを掘り下げて解説するスタイルなので、その日の出来事を網羅的に知りたい場合には、他の媒体と組み合わせるのが良いでしょう。
東洋経済オンライン
『週刊東洋経済』を母体とする、日本最大級のビジネスニュースサイトです。
経済・金融ニュースはもちろんのこと、独自の視点から企業の内情や業界の課題に鋭く切り込んだ調査報道・特集記事に定評があります。
大企業の経営問題から、就職活動、キャリア、教育まで、幅広いテーマを扱っています。
無料で読める記事が非常に多いのも特徴です。
独自の切り口と深い分析力が最大の魅力です。
「就職四季報」のデータに基づいた企業分析記事や、業界の裏側に迫るレポートなど、他では読めない質の高い情報が手に入ります。
表面的なニュースだけでなく、その背景にある構造的な問題を理解するのに役立ち、ESや面接で深みのある意見を述べるための強力な武器になります。
無料でアクセスできる記事が多いのも、学生にとっては大きなメリットです。
広告の表示が多いと感じるユーザーもいるかもしれません。
また、一部の記事は有料会員(週刊東洋経済の定期購読者など)でないと全文を読むことができません。
速報性を追求するよりも、一つのテーマを掘り下げたコラムや特集記事が中心なので、最新のニュースを追いかけたい場合は、他の速報系メディアとの併用が推奨されます。
ダイヤモンド・オンライン
概要 ビジネス雑誌『週刊ダイヤモンド』のオンラインメディアです。
企業の経営戦略、財務分析、業界レポートなど、ビジネスの核心に迫る記事を数多く配信しています。
特に、業界の勢力図や企業の盛衰を分析した特集記事には定評があり、多くの経営層やビジネスパーソンに読まれています。
時事ニュースからライフスタイルまで、硬軟織り交ぜたコンテンツを提供しています。
業界や企業を分析する「マクロな視点」と、個人のキャリアやスキルアップに役立つ「ミクロな視点」の両方から情報を提供している点が強みです。
業界研究に役立つ詳細なレポートが多く、志望業界の力学や将来性を理解する上で非常に有用です。
信頼性の高い情報源として、ESで述べる意見の根拠とすることができます。
無料会員登録で読める記事も多く、コストパフォーマンスが高いメディアです。
東洋経済オンラインと同様に、全ての記事を読むためには有料会員登録が必要になる場合があります。
サイトの構成上、自分の探している情報にたどり着くまでに少し時間がかかると感じる可能性もあります。
こちらも速報ニュースよりは、分析や解説に重きを置いたメディアと言えるでしょう。
NewsPicks
経済ニュースを専門家のコメントと共に読むことができる、ソーシャル型のニュースサービスです。
国内外の90以上のメディアから供給されるニュースに加え、独自の編集部が制作するオリジナル記事も配信しています。
各業界の著名人や専門家(プロピッカー)がニュースを解説しており、ユーザーはそれらのコメントを参考にしながら理解を深めることができます。
最大のメリットは、一つのニュースに対して多様な視点や意見に触れられることです。
専門家の解説を読むことで、ニュースの背景や本質的な意味を短時間で深く理解できます。
これにより、自分自身の意見を形成する上でのヒントを得やすくなります。
気になる専門家をフォローすることで、自分の関心分野の情報を効率的に収集することも可能です。
就活生向けのコミュニティや特集もあり、情報交換の場としても活用できます。
無料で利用できる範囲では、読める記事やコメントに制限があります。
全ての機能を利用するには有料のプレミアムプランへの登録が必要です。
また、コメントはあくまで個人の見解であるため、中には偏った意見や不正確な情報が含まれている可能性もゼロではありません。
複数のコメントを比較検討し、情報を見極めるリテラシーが求められます。
【気になるニュース es】PREP法で書く!ESの型
エントリーシートで「気になるニュース」について書く際、ただ情報を羅列するだけではあなたの思考力や論理性を伝えることはできません。
説得力のある文章を作成するには、適切な構成を用いることが極めて重要です。
ビジネスシーンでの報告や提案で多用されるフレームワークの中でも、特にESにおいては、最初に結論を述べて分かりやすさを重視する「PREP法」が最適です。
以下で、PREP法がなぜ有効なのか、そしてその具体的な構成要素について詳しく解説していきます。
この型に沿って書くことで、誰が読んでも分かりやすく、論理的な文章を効率的に作成できます。
PREP法(プレップほう)とは、Point(結論)、Reason(理由)、Example(具体例・概要)、Point(結論の再提示)という4つの要素の頭文字を取った文章構成モデルです。
最初に要点(結論)を伝えることで、読み手は何についての話なのかを即座に理解でき、その後の内容が頭に入りやすくなります。
次にその結論に至った理由と、裏付けとなる具体的なニュースの概要やデータを示し、最後に改めて結論を述べて締めくくることで、主張の一貫性と説得力を高めることができます。
特に文字数に限りがあるESにおいて、要点を簡潔かつ論理的に伝えるのに非常に効果的な手法です。
この構成を意識するだけで、文章の分かりやすさが飛躍的に向上し、採用担当者にあなたの思考プロセスをクリアに伝えることができるでしょう。
①結論
まず最初に、「私が最近最も気になったニュースは、〇〇です」というように、あなたが選んだニュースが何であるかを明確に述べます。
これに加えて、「なぜなら、このニュースは貴社(〇〇業界)の将来に大きな影響を与えると考えるからです」といった形で、なぜそのニュースが重要だと考えるのか、その核心的な理由(主張)も一言で添えるのがポイントです。
この冒頭部分で、文章全体のテーマと方向性を読み手に提示します。
結論を最初に持ってくることで、採用担当者は「この就活生は〇〇について、こういう視点で論じようとしているのだな」と瞬時に理解でき、その後の文章をスムーズに読み進めることができます。
インパクトのある書き出しで、相手の興味を引きつけましょう。
②概要と理由
次に、結論で示したニュースがどのようなものなのか、その概要を客観的かつ簡潔に説明します。
いつ、どこで、何が起きたのか(5W1H)を意識して、誰が読んでも理解できるように記述します。
ただし、ニュースの詳細を長々と書く必要はありません。
あくまで、後の自分の意見につなげるための前提情報を共有する程度に留めましょう。
そして、そのニュースのどの点に注目し、なぜそれを「気になる」と感じたのか、その理由を具体的に述べます。
「この技術の進展が、既存のビジネスモデルを根底から変える可能性を秘めている点に興味を持ちました」のように、自分自身の問題意識と結びつけて理由を説明することで、あなたの視点が明確になります。
③意見や考察
ここが最も重要な部分であり、あなたらしさをアピールする最大のチャンスです。
そのニュースを受けて、あなた自身が何を考え、どう感じたのか、独自の意見や考察を自由に展開します。
例えば、そのニュースが社会や志望業界にどのような影響を与えるか、その出来事の背景にある課題は何か、今後どのような展開が予測されるか、といった視点から論じることができます。
さらに、「この課題に対して、自分であれば貴社の〇〇という技術やサービスを活用して、このように貢献できるのではないか」といった形で、自分の強みや企業への貢献意欲と結びつけると、より説得力が増し、入社後の活躍イメージを具体的に持たせることができます。
④今後の展望
最後に、これまで述べてきた内容を総括し、改めて自分の主張や結論を繰り返して締めくくります。
冒頭の結論(Point)と同じ内容を繰り返すだけでなく、「このニュースの動向を今後も注視し、変化に対応できる人材として貴社で活躍したいです」といったように、将来への意欲や企業への貢献の意思を表明する形で締めると、非常に前向きな印象を与えることができます。
また、「この課題解決は、〇〇という新たなビジネスチャンスを生み出すと考えます」のように、ニュースから見出した未来の可能性について言及するのも良いでしょう。
文章全体に一貫性を持たせ、力強く締めくくることで、あなたの主張が採用担当者の記憶に残りやすくなります。
【気になるニュース ES】周りと差をつけるESにするには?
多くの就活生が「最近気になるニュース」を書く中で、ただ事実を説明するだけでは他と差がつきません。
企業が知りたいのは、ニュースを通じてあなたがどのように考え、行動や価値観に結びつけているかという点です。
周囲と差をつけるためには、自分の経験や学びと関連付けたり、具体的なデータを用いて説得力を高めたり、自分の意見を主体的に形成する工夫が必要です。
論理的でオリジナル性のある回答こそ、採用担当者の印象に残ります。
自分の経験や学びと結びつける
「気になるニュース」を取り上げる際、事実を並べるだけでは印象に残りません。
大切なのは、自分自身の経験や学びと関連付けて語ることです。
例えば、環境問題のニュースに触れる場合、大学で学んだゼミでの研究内容と結びつけることで、自分なりの関心の深さや理解度を伝えられます。
また、アルバイトやボランティアで感じた課題と関連付ければ、実体験に基づく意見として説得力が増します。
こうした関連付けは、単なるニュース解説ではなく、あなた自身の価値観や行動原理を示すことにつながります。
ESでは「なぜそのニュースが自分にとって重要なのか」を意識し、経験や学びと絡めて具体的に述べることが、他の就活生との差別化に直結します。
数字やデータを用いて説得力を高める
回答に客観性と説得力を持たせるためには、ニュースの背景や影響を数字やデータで補足することが効果的です。
例えば「円安が気になる」と述べる際に「2022年10月には1ドル=150円台と、32年ぶりの水準に達した」と具体的な数値を示せば、表現に信頼性が加わります。
データは必ず一次情報や信頼できる報道機関から引用することが重要です。
信頼できる情報ツールでないと、不確実な情報を用いることになります。
また、数字を使う際はただ引用するのではなく「この状況が今後企業経営に与える影響を考えると、~と感じた」と自分の考えに結びつけることがポイントです。
数値を根拠に加えることで、論理性と具体性が高まり、読み手に納得感を与える回答に仕上がります。
自分の意見を持つための工夫
質の高い回答を作るには、自分の意見を形成する工夫が不可欠です。
まず、多角的に情報を収集することが大切です。
同じニュースでも新聞、テレビ、アプリ、専門誌など複数の媒体で確認すれば、異なる立場や視点を比較できます。
その上で、背景や原因を調べ、過去の類似事例と照らし合わせることで理解が深まります。さらに、日々の出来事について感想を書き出したり、友人と議論したりする習慣を持つと、自分の考えを整理する力が磨かれます。
重要なのは自分はどう感じ、どんな行動につなげたいかを明確にすることです。
単なる概要の説明に留まらず、主体的に意見を形成する姿勢を示すことで、就活において他の学生との差を生み出すことができます。
【気になるニュース es】業界別参考例文集
ここでは、これまでに解説した「ニュースの選び方」と「PREP法」を踏まえて、具体的な業界別の例文を紹介します。
各業界の動向や課題に関連するニュースを取り上げ、論理的な構成で自身の考えを述べることで、業界への深い理解と高い意欲をアピールしています。
これらの例文はあくまで一例です。
あなた自身の言葉で、あなたならではの視点を加えることが最も重要です。
例文の構成や視点の置き方を参考に、自分だけのオリジナルな回答を作成してみてください。
商社
私が最近最も気になったニュースは、「資源大手による次世代エネルギーへの投資加速」です。
特に、従来の化石燃料だけでなく、グリーン水素やアンモニア、CCUS(二酸化炭素回収・利用・貯留)技術への大規模な投資が発表されたことは、総合商社のビジネスモデルが歴史的な転換点を迎えている象徴だと感じました。
このニュースが報じているのは、単なるエネルギーシフトではありません。
気候変動という地球規模の課題に対し、資源供給の担い手であるメジャー企業が事業の核を移行させようとする強い意志の表れです。
私がこのニュースに注目したのは、資源の安定供給という従来の使命を果たしつつ、脱炭素社会の実現という新たな価値を創造しようとするダイナミックな動きに、総合商社の未来の姿が重なって見えたからです。
この動きは、世界中に張り巡らされたネットワークと、大規模プロジェクトを動かすノウハウを持つ総合商社にとって、絶大なビジネスチャンスだと考えます。
既存のエネルギーインフラを活用しながら、水素やアンモニアのサプライチェーンをゼロから構築していく。
その壮大な挑戦において、多様な産業に精通し、異なるプレイヤーを繋ぎ合わせる貴社のコーディネート能力は不可欠です。
私は、こうした社会課題の解決と新たなビジネスの創造を両立させるトレーディングの最前線に身を置き、次世代エネルギーの普及に貢献したいと強く考えております。
このニュースの動向を追い続け、貴社の一員として新しい時代の潮流を創り出すことに挑戦したいです。
金融
私が最近最も気になったニュースは、「日本銀行によるマイナス金利政策の解除と、それに伴う金融市場の変動」です。
長年続いた異次元緩和からの転換点であり、今後の日本経済、そして金融機関の経営に計り知れない影響を与える歴史的な決定だと考え、強く関心を持ちました。
この政策変更は、金利のある世界への回帰を意味し、銀行にとっては貸出収益の改善が期待される一方、保有する国債の価格下落リスクや、企業の資金調達コスト増加による貸し倒れリスクの増大といった課題もはらんでいます。
私が注目したのは、この大きな環境変化の中で、金融機関に「真の目利き力」がこれまで以上に問われるようになるという点です。
金利が正常化する過程で、企業の成長性や事業内容をより深く、そして正確に評価し、適切なリスクテイクを行う能力が収益を大きく左右すると考えます。
私は、この変革期こそ、金融機関が本来の役割を発揮する絶好の機会だと捉えています。
特に貴行は、早くから企業のDX支援や事業承継コンサルティングに力を入れており、単なる資金供給者にとどまらないソリューション提供能力に強みをお持ちです。
金利上昇局面に不安を抱える中小企業に対し、財務改善の提案や新たな成長戦略の策定をサポートすることで、より強固な信頼関係を築き、持続的な成長を共に目指すことができると考えます。
私も貴行の一員として、変化する金融環境の中で顧客に寄り添い、的確なソリューションを提供することで日本経済の活性化に貢献したいです。
コンサルティング
私が最近最も気になったニュースは、「国内における生成AIのビジネス活用と、それに伴う人材育成の課題」です。
多くの企業が業務効率化や新規事業創出を目指して生成AIの導入を急ぐ一方で、それを使いこなし、価値を最大化できる人材が不足しているという現状に、コンサルティングファームが果たすべき役割の大きさを感じました。
このニュースは、単なる技術トレンドではなく、企業の競争力を根本から左右する経営課題であることを示唆しています。
生成AIを導入しても、プロンプトエンジニアリングのスキルや、AIの出力を批判的に吟味しビジネスに結びつける能力がなければ、宝の持ち腐れとなってしまいます。
私がこの問題に注目したのは、テクノロジーの導入と組織・人材の変革は常に一体であり、このギャップを埋めることこそが、今後のDX推進における最大の成功要因になると考えたからです。
クライアント企業の課題解決を使命とするコンサルタントにとって、この状況は大きなビジネス機会です。
単にAIツールの導入を支援するだけでなく、クライアントの業務プロセスを深く理解した上で、具体的な活用方法を定義し、社員向けの研修プログラムを設計・実行する。
さらには、AI活用を前提とした新しい組織体制や評価制度の構築まで踏み込んで提案することが求められます。
特に、業界や業務に関する深い知見を持つ貴社であれば、机上の空論ではない、実効性の高い変革をリードできると確信しております。
私も貴社の一員として、テクノロジーと経営の両面からクライアントに貢献し、企業の持続的な成長を支援していきたいです。
IT
私が最近最も気になったニュースは、「企業のサイバーセキュリティ対策における『ゼロトラスト』モデルへの移行加速」です。
リモートワークの普及やクラウドサービスの利用拡大により、従来の境界型防御モデルが通用しなくなり、全てのアクセスを信頼せずに検証するという考え方が標準になりつつある点に、ITインフラの大きなパラダイムシフトを感じました。
このニュースが示すのは、「社内は安全、社外は危険」という従来の前提が崩壊したという事実です。
標的型攻撃やランサムウェアの巧妙化が進む中、企業の重要な情報資産を守るためには、より高度で動的なセキュリティ対策が不可欠です。
私がこのテーマに注目したのは、ゼロトラストの実現が単一の製品導入で完結するものではなく、認証基盤、デバイス管理、ネットワーク監視など、複数の要素を組み合わせた包括的なアーキテクチャ設計を必要とする複雑な課題である点です。
この課題に対し、貴社はクラウドからネットワーク、セキュリティまで幅広いソリューションをワンストップで提供できる強みをお持ちです。
顧客企業のシステム環境や業務実態を深く理解した上で、最適な製品を組み合わせ、円滑な移行を支援するSIer(システムインテグレータ)としての役割は、今後ますます重要になると考えます。
特に、セキュリティは経営リスクに直結するため、高度な技術力とコンサルティング能力が求められる領域です。
私は、大学で学んだ情報セキュリティの知識を活かし、貴社のエンジニアとして、お客様が安心して事業に集中できる堅牢なIT環境の構築に貢献したいです。
マスコミ
私が最近最も気になったニュースは、「フェイクニュースや偽情報の拡散に対するプラットフォーム事業者の対策強化と、表現の自由とのバランスを巡る議論」です。
特に、大規模言語モデルによって精巧な偽情報が生成されやすくなった現状に対し、社会インフラであるメディアやプラットフォーマーがどう向き合うべきかという問題に強い関心を抱きました。
この問題の根深さは、単なる技術的な対策だけでは解決できない点にあります。
ファクトチェックの強化やAIによる検知は重要ですが、それが行き過ぎると、正当な言論や表現までをも萎縮させてしまう「検閲」につながりかねません。
私がこのニュースに注目したのは、情報の信頼性を担保するというメディアの根源的な使命と、多様な意見が共存する健全な言論空間を守るという社会的責任の間で、難しい舵取りが求められているからです。
この課題に対して、長年にわたり信頼と実績を積み重ねてきた貴社のような伝統的メディアが果たすべき役割は非常に大きいと考えます。
一次情報への丁寧な取材に基づいた質の高い報道を堅持することはもちろん、なぜその情報が信頼できるのか、その背景やプロセスを透明性高く示すことで、情報の受け手である市民のリテラシー向上に貢献することが重要です。
また、プラットフォーマーと連携し、建設的な議論を促進する場を設計していくことも、新たな使命になるのではないでしょうか。
私は、こうした新しい時代のジャーナリズムのあり方を模索し、人々がより良い意思決定をするための「信頼の礎」となる情報を届ける仕事に、貴社で挑戦したいと考えています。
メーカー
私が最近最も気になったニュースは、「世界的な半導体サプライチェーンの再編と、国内での生産拠点新設の動き」です。
経済安全保障の観点から、これまで海外に依存していた先端半導体の国内生産能力を高めようという動きが活発化していることに、日本の製造業の未来を左右する大きな転換点を感じました。
このニュースは、単なる工場誘致の話にとどまりません。
自動車、家電、産業機械など、あらゆる製品の頭脳となる半導体の安定確保は、メーカーの競争力そのものに直結します。
私がこの動向に注目したのは、国内に最先端の製造拠点が生まれることで、素材や製造装置、さらにはそれらを利用する貴社のような最終製品メーカーに至るまで、幅広い産業で技術革新や新たなビジネスチャンスが生まれる可能性を秘めている点です。
例えば、貴社が開発する次世代製品において、これまで入手が難しかった高性能な半導体を、国内のパートナー企業と共同で早期段階から設計・開発できる可能性があります。
これにより、製品の性能を飛躍的に向上させるだけでなく、開発リードタイムの短縮や、サプライチェーンの寸断リスク低減にも繋がり、事業の安定性と収益性の両方を高めることができると考えます。
私は、こうした変化の時代においてこそ、メーカーの技術者が果たすべき役割は大きいと信じています。
貴社の一員として、新しい技術を積極的に取り入れ、世の中を驚かせるような革新的な製品を生み出すことで、日本のものづくりの復活に貢献したいです。
インフラ
私が最近最も気になったニュースは、「激甚化・頻発化する自然災害と、デジタル技術を活用した次世代の防災・減災システム(スマート防災)の構築」です。
特に、AIによる被害予測や、ドローンを活用した被災状況のリアルタイム把握、5G通信網を利用した情報伝達など、最新技術が人々の命と暮らしを守るために活用され始めている点に強い関心を抱きました。
このニュースは、気候変動という大きな課題に対し、社会インフラのあり方そのものを見直す必要性を示唆しています。
従来の頑丈な堤防や避難施設といった「ハード対策」に加え、ITを活用して被害を最小限に抑える「ソフト対策」の重要性が飛躍的に高まっています。
私が注目したのは、これらのスマート防災システムが真に機能するためには、電力、通信、交通といった様々なインフラが、災害時にも途切れることなく安定的に連携し続けることが大前提となる点です。
この点において、社会の根幹を支えるエネルギーインフラを担う貴社の役割は極めて重要です。
災害に強い分散型電源の普及を促進したり、被災状況に応じて電力供給を最適化するスマートグリッドを構築したりすることで、防災システム全体のレジリエンス(強靭性)を高めることができます。
これは、人々の安全を守るだけでなく、災害からの迅速な復旧を可能にし、日本経済全体の安定にも繋がる、非常に社会的意義の大きな取り組みだと考えます。
私も貴社の一員として、社会に不可欠なインフラを支えるという使命感と誇りを持ち、最新技術を取り入れながら、より安全・安心な社会基盤の構築に貢献していきたいです。
人材
私が最近最も気になったニュースは、「企業の『リスキリング(学び直し)』支援の本格化と、ジョブ型雇用への移行の動き」です。
DXの進展や産業構造の変化に対応するため、企業が主体となって従業員のスキルアップを後押しし、専門性に基づいた人材配置を進める動きに、日本の働き方が大きく変わろうとしていることを感じました。
このニュースは、終身雇用や年功序列といった従来の日本型雇用の前提が崩れ、個人と企業の関係が「相互依存」から「自律的な選択」へと変化していることを象ेंしています。
企業にとっては、事業戦略に合わせて必要な人材を確保・育成することが、個人のキャリアにとっては、市場価値の高い専門性を身につけ続けることが、共に重要になります。
私がこのテーマに注目したのは、この大きな変化の中で、企業と個人の最適なマッチングを実現する人材サービスの役割が、これまで以上に重要になると考えたからです。
この変革期において、貴社が展開されているような、単なる求人情報の提供にとどまらない、個人のキャリアプラン相談や、企業の組織開発コンサルティングといった多角的なサービスは、社会にとって不可欠なインフラとなります。
特に、どのようなスキルを学ぶべきか悩む個人と、どのような人材が必要か模索する企業との間に立ち、双方にとって最適な「学びと成長の機会」を繋ぐ役割は、大きな価値を生み出すと考えます。
私も、人々のキャリアの可能性を広げ、企業の成長を支援することに強いやりがいを感じています。
貴社の一員として、変化の時代の「働く」を支え、個人と組織の双方に貢献していきたいです。
まとめ
「最近気になるニュース」という質問は、あなたの情報感度、思考力、そして企業や社会への関心の高さを示す絶好のアピールの機会です。
重要なのは、企業の意図を理解し、志望業界と関連の深い、自分の意見が語れるニュースを選ぶこと。
そして、PREP法を用いて、結論から先に述べる論理的な構成で記述することです。
日頃から信頼できる媒体で情報収集を行い、ニュースの背景や社会への影響まで自分なりに考える習慣をつけましょう。
この記事で紹介した選び方、書き方、そして業界別例文を参考に、あなただけの説得力ある回答を作成し、採用担当者にあなたの魅力を最大限に伝えてください。

_720x550.webp)
_720x550.webp)
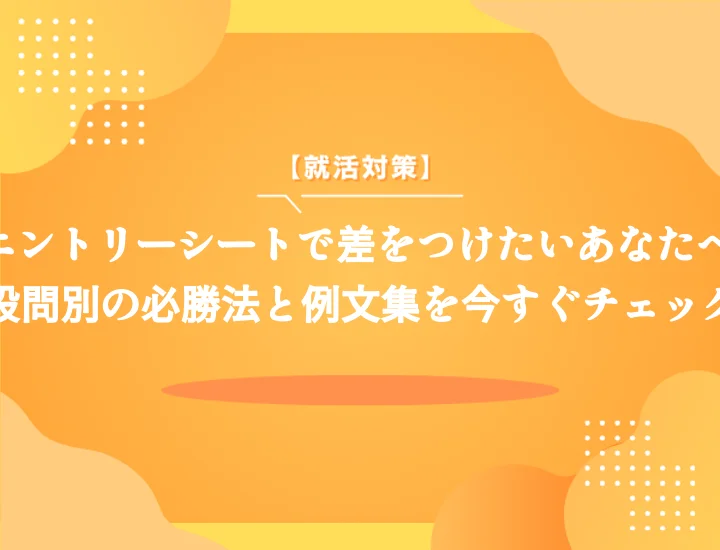
_720x550.webp)





