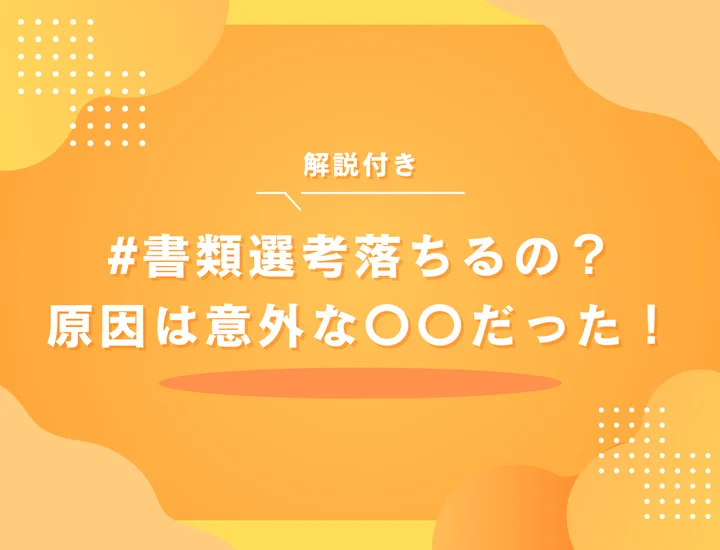HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
就活において、年々注目度が高まっているのが早期選考のエントリーシート(ES)の通過率です。
本選考に比べ、行動力のある学生が集まるため難易度が高いといわれますが、通過できれば内定に直結するチャンスや、人事からのフィードバックなど多くのメリットが存在します。
一方で、準備不足で挑めば本選考に挑戦できないリスクもあるため、戦略的な対策が必須です。
本記事では、早期選考の概要から通過率を上げる方法、業界別の例文、面接対策まで徹底的に解説します。
目次[目次を全て表示する]
【ESの通過率を上げよう!】そもそも早期選考とは?
まず理解すべきは、早期選考は「本選考の前倒し」ではなく、独自の狙いを持つ採用活動である点です。
企業は優秀な学生を他社に先駆けて確保するため、夏〜秋から接触を始め、限られた枠で採用を行います。
そのため、通過すれば大きなメリットがありますが、一方で通過率は低くなるのが現実です。
ここでは「本選考との違い」「企業側の目的」「スケジュール感」を解説し、早期選考の全体像を整理します。
本選考との違い
本選考との違いは大きく3つあります。
1つ目は実施時期です。
本選考が3月以降に本格化するのに対し、早期選考は夏のインターン直後から秋にかけて実施されます。
2つ目は採用枠の少なさです。
全体の数%程度、数名〜数十名に限られることが多く、狭き門となります。
3つ目は選考内容の厳しさです。
応募者は情報感度が高く、インターン経験豊富な層が多いため、求められるESや面接の完成度は本選考より高い傾向にあります。
つまり、早期選考は準備を重ねてきた学生が一気に抜け出せるチャンスである一方、準備不足では太刀打ちできない舞台なのです。
早期選考が行われる理由と目的
企業が早期選考を実施する最大の目的は、優秀な学生を他社に先んじて確保することです。
特に競争の激しい業界では、早い段階で志望度の高い学生と接点を持ち、自社への魅力を伝えることで内定辞退を防ぐ狙いがあります。
また、早期に一定数の内定者を出すことで、本選考での応募者殺到を避け、採用活動のリソースを効率化できるというメリットもあります。
学生にとっても、早い段階でフィードバックを得てその後の対策に活かせるという利点があり、双方にとって価値のある機会となっています。
早期選考のスケジュール
早期選考のスケジュールは業界や企業で異なりますが、準備期間を含めると大学3年生の春から始まっています。
特に外資系コンサルや投資銀行は最も早く、大学3年生の夏〜秋にES提出・面接を実施し、年内に内定が出揃うことも珍しくありません。
大手金融やメーカーでは秋〜冬にかけて選考が本格化し、年明けには内定が出る場合があります。
このスケジュール感を把握し、自己分析や企業研究を逆算して進めることが、早期選考に参加するための絶対条件といえるでしょう。
【ES】早期選考のエントリーシートの通過率は?
次に気になるのが、早期選考のES通過率です。
具体的な数字は企業ごとに異なり公表もされませんが、一般的に本選考よりも低いのが現実です。
ただし、インターンシップでの評価や特筆すべき実績を持つ学生は通過しやすい場合もあります。
ここでは「全体的な傾向」と「通過しやすいケース」の2つの側面から見ていきましょう。
一般的には低い
早期選考のES通過率は、具体的な数値こそ不明ですが、体感的には10〜20%程度、難関企業ではそれ以下ともいわれます。
特に大手・外資系企業では倍率が数十倍〜数百倍になることも珍しくありません。
その理由は、応募者のレベルが非常に高いことに加え、採用枠が極端に少ないからです。
早期選考は「優秀な学生層の中で、さらに上位層を選ぶ」という厳しい場であるため、ESの完成度や志望動機の具体性を極限まで高めなければ、次のステップに進むことは困難です。
通過しやすいケースもある
一方で、明確な強みを持つ学生は通過しやすい傾向にあります。
例えば、志望企業での長期インターンシップで成果を出した学生や、研究活動で学会発表などの実績がある学生は高く評価されます。
企業は「早期に行動できる主体性」や「客観的な実績」を重視するため、突出したエピソードは強力な武器になるのです。
また、過去に企業のインターンに参加し、社員から高い評価を得て顔と名前を覚えられている学生も、選考で有利に働くことがあります。
つまり、早期から積極的に行動し、企業との接点を作ってきたかが通過率を左右します。
【ESの通過率を上げよう!】早期選考のエントリーシートを突破する人の特徴
早期選考は誰でも突破できるわけではありません。
自己分析の深さ・企業への熱意・主体性・早期接点の活用・文章力の高さという5つの要素を兼ね備えている学生が通過しやすい傾向にあります。
ここでは具体的に、選考を突破する学生の共通点を紹介します。
自己分析の深さが圧倒的
通過する学生は、自己分析が徹底されています。
単に「リーダー経験がある」と書くのではなく、その経験を通じて何を考え、何を学び、その結果どのような価値観が形成されたのかまで深く掘り下げています。
そして、その価値観や強みを、入社後にどう活かせるのかを具体的に言語化できるのです。
自己理解の深さが、志望動機や自己PRに説得力をもたらし、他の学生との明確な差別化につながります。
「なぜこの会社でなければならないか」の熱意が強く明確
志望動機が浅いと、早期選考ではすぐに見抜かれます。
企業は「練習目的の学生」を避けたいからです。
通過する学生は、企業の事業内容やビジョン、IR情報まで読み込み、「他社ではなく、なぜ御社なのか」を自身の言葉で明確に語ります。
企業の独自の強みや社員の言葉に触れ、自分の将来像と重ね合わせて「ここで働きたい」という熱意を伝えることで、人事担当者の心を動かすのです。
早期から行動する「主体性」をアピールできている
早期選考では「早くから動ける学生=主体性がある」と高く評価されます。
通過者は、大学1、2年生の段階から情報収集やインターンシップ、OB・OG訪問などを積極的に行い、その経験を具体的に語ることができます。
特に「現状に満足せず、自ら課題を見つけて行動し、周囲を巻き込みながら成果を上げた」という経験は、主体性と行動力をアピールする上で非常に有効です。
インターンなどの「早期接点」を最大限に活かしている
インターンシップや座談会での経験を、ESに効果的に落とし込める学生は非常に有利です。
企業は「自社との接点を通じて、学生の志望度がどう高まったか」「学びをどう今後に活かそうとしているか」を見ています。
「〇〇様がお話しされていた『挑戦を支える文化』に共感し、自分の〇〇という強みが活かせると確信した」など、具体的なエピソードを交えて書ける人は、志望度の高さを明確に示すことができます。
文章の完成度が非常に高い
早期選考では、大量のESが短時間で選別されます。
そのため、文章の完成度が低いと、内容を読まれる前に落とされる可能性があります。
通過する学生のESは、誤字脱字がゼロであることはもちろん、PREP法などを用いた論理的な構成で、誰が読んでも分かりやすい文章に仕上がっています。
内容が良くても伝わらなければ意味がないため、簡潔かつ具体的に伝える文章力が求められます。
【ES】エントリーシートの通過率を上げる方法
通過率を高めるには、戦略的な書き方が必要不可欠です。
結論ファーストで分かりやすく伝え、具体性のあるエピソードで独自性を示し、入社後の活躍をイメージさせることが重要です。
これらのポイントを意識すれば、人事の目に留まるESとなり、通過率は格段に上がります。
結論ファーストで伝えたいことを明確にする
採用担当者は数百枚以上のESを短時間で読むため、結論が後回しだと印象が薄くなってしまいます。
冒頭で「私の強みは〇〇です」「私が貴社を志望する理由は〇〇です」と明確に書き出すことで、読み手にストレスを与えません。
まずシンプルかつ端的に結論を伝え、その後に具体的なエピソードを補足するという流れを徹底しましょう。
この構成は、論理的思考力が高いというアピールにも繋がります。
早期選考ならではの特別感や具体性を示す
「この学生は本気だ」と思わせるには、自分だけのエピソードに基づく具体性が重要です。
インターンシップで感じた課題意識や、座談会で心に響いた社員の言葉などを盛り込むと、説得力が格段に増します。
誰でも書けるような抽象的な志望動機ではなく、「だからこそ御社でなければならない」という、あなた自身の体験に基づいた熱意を伝えることが、その他大勢から抜け出すための鍵となります。
入社後の展望を加える
企業は「採用後にどう活躍してくれるか」という未来の姿を見ています。
ESの締めくくりとして、「入社後は〇〇の分野で専門性を高め、将来的には貴社の新規事業に挑戦したい」など、具体的なキャリアプランを伝えることで入社意欲の高さを示せます。
自分の強みを活かして、どのように会社に貢献していきたいかを長期的な視点で語ることで、企業側もあなたを採用するメリットを具体的にイメージできます。
【ESの通過率を上げよう!】早期選考を受けるメリット
早期選考には、ライバルが動き出す前に一歩リードし、就職活動を有利に進めるための多くのメリットが存在します。
特に「①早期内定による精神的安定」「②選考経験値の獲得」「③個別フィードバックの可能性」「④入社意欲の強力なアピール」は、その後の就活全体を左右するほどの大きな利点です。
早期内定がもらえることによる安心感
最大のメリットは、早い段階で内定を得られる可能性があることです。
卒業までの進路が確定することで、就活の大きなプレッシャーから解放され、精神的に非常に安定します。
この「内定を持っている」という余裕は、その後の選考に計り知れない好影響をもたらします。
「ここがダメでも次がある」と思えることで、面接で過度に緊張することなく、本来の実力をリラックスして発揮できます。
結果として、より評価の高い本命企業や、挑戦的な企業にも自信を持って臨めるため、選択肢が大きく広がるのです。
本番で活きる「選考経験値」を誰よりも早く積める
早期選考は、本命企業の本選考に向けた最高の練習の場となります。
多くの学生が初めての面接に戸惑う中で、ES作成からWebテスト、グループディスカッション、複数回の面接という一連の流れを早期に経験できることは、圧倒的なアドバンテージになります。
特に面接では、独特の緊張感や、予想外の質問への対応力が養われます。
「失敗しても本番ではない」という気持ちで臨めるため、自分の弱点や改善点を冷静に分析し、次に活かすことができます。
この「場数」と「トライ&エラー」の経験が、本選考での通過率を格段に引き上げます。
人事から成長に繋がる手厚いフィードバックを得られる可能性
応募者が殺到する本選考では、一人ひとりに丁寧なフィードバックをすることは物理的に困難です。
しかし、比較的応募者数が少ない早期選考では、人事担当者から「どこが評価され、どこに改善点があったか」という貴重なフィードバックを得られる場合があります。
特に外資系企業やベンチャー企業では、学生の成長を促す文化が根付いていることも多く、「君の〇〇という強みは、もっと具体的に話すと魅力的になる」といった具体的なアドバイスをもらえるケースも少なくありません。
このフィードバックを元に軌道修正することで、その後の就活を有利に進めることができます。
行動力そのもので「入社意欲の高さ」をアピールできる
数ある企業の中から自社を見つけ出し、早い段階で応募するという行動そのものが、「情報感度が高く、主体的に動ける優秀な学生」という評価に直結します。
企業側は、こうした学生を「将来の幹部候補」や「成長意欲の高い人材」として注目します。
特に、「なぜ早期選考に応募したのですか?」という質問に対し、企業のビジョンや事業内容と自身のキャリアプランを結びつけて熱意を語ることができれば、他のどの学生よりも強い入社意欲を印象付けることが可能です。
主体性とスピード感は、現代のビジネスで不可欠な資質であり、それ自体が強力なアピール要素になるのです。
【ESの通過率を上げよう!】早期選考を受けるうえでのリスク
メリットが多い一方で、早期選考には注意すべきリスクも存在します。
準備不足のまま挑戦してしまったり、一度の失敗で本選考への道が閉ざされたりする可能性もゼロではありません。
これらのリスクを正しく理解し、慎重に企業を選ぶことが、後悔しないための重要なポイントとなります。
準備不足のまま臨んでしまうことがある
スケジュールが早い分、自己分析や企業研究が不十分なままESを提出してしまう学生は少なくありません。
しかし、早期選考はレベルの高い応募者が集まるため、浅い志望動機や自己PRでは高倍率を突破することは極めて困難です。
「とりあえず受けてみよう」という気持ちで臨むと、貴重な機会を無駄にしてしまうだけでなく、企業にネガティブな印象を与えかねません。
短期間でも集中して準備する覚悟が必要です。
企業によっては本選考を受けられないことがある
早期選考に落ちた場合、同じ企業の本選考に再応募できないケースがあることは、必ず知っておくべきリスクです。
企業によっては「早期選考で不合格=自社とのマッチ度が低い」と判断するためです。
特に第一志望群の企業に対して準備不足のまま応募し、本選考のチャンスまで失ってしまうのは最悪のシナリオです。
挑戦する企業が本選考への再応募を許可しているか、事前に必ず確認しましょう。
自己分析に充てる時間が減ってしまう
早期選考に時間と労力を集中させるあまり、就活の土台である自己分析に十分な時間を確保できなくなる場合があります。
自分自身の価値観や強みを深く理解しないまま選考に進むと、ESの内容が表面的になったり、面接で一貫性のない回答をしてしまったりする原因になります。
早期選考への挑戦と、腰を据えた自己分析をいかに両立させるか、計画的なスケジュール管理が求められます。
【ESの通過率を上げよう!】業界別ガクチカ参考例文集
ここでは早期選考で通用するガクチカ例文を業界別に紹介します。
金融・商社・広告・人材・メーカーそれぞれで評価されるポイントを意識した内容です。
自身の経験を整理し、自分だけの魅力的なエピソードを作成するための参考にしてください。
金融
私は大学の投資ゼミで、指導教官も未経験だった「ESG投資」に関する共同研究プロジェクトに注力した。
当初は情報が乏しく分析が難航したが、私は率先して海外の論文や企業のサステナビリティレポートを読み込み、独自の評価指標を作成した。
その指標に基づき、メンバーと議論を重ねて選定した5つの銘柄は、最終的に模擬投資大会で他のチームを大幅に上回るリターンを記録し、最優秀賞を受賞した。
この経験から、未知の分野でも主体的に情報を収集し、データを基に論理的な結論を導き出す力を培った。
この分析力は、常に変化する市場の中で顧客に最適なソリューションを提供する金融業界で必ず活かせると考えている。
商社
私は30カ国以上の留学生が所属する国際交流サークルの副代表として、年間最大のイベントである「国際フードフェスティバル」の企画運営に注力した。
最大の課題は、文化や価値観の違いから生じるメンバー間の対立だった。
私は各国の代表者と個別に面談を重ね、全員が納得できる共通のゴールとして「来場者数前年比150%」を設定した。
その上で、各国の食文化の魅力を最大限に活かす企画を共に考え、全員の主体性を引き出すことに成功した。
結果、イベントは過去最高の来場者数を記録し、多様なバックグラウンドを持つメンバーをまとめ上げ、一つの目標に向かって推進する調整力とリーダーシップを培った。
広告
私は所属するダンスサークルの単独公演で広報責任者を務め、SNSを活用した集客戦略に注力した。
前年の公演が客席の半分しか埋まらなかった課題に対し、私はターゲットを「ダンス未経験の大学生」に再設定し、Instagramで「ダンス講座」や「舞台裏紹介」といった参加型のコンテンツを企画・実行した。
投稿時間やハッシュタグを徹底的に分析し、改善を繰り返した結果、サークルのアカウントのフォロワーは3ヶ月で3倍に増加。
公演チケットは発売当日に完売し、サークル史上初の快挙を成し遂げた。
この経験から、ターゲットのインサイトを深く理解し、的確な情報発信で人の心を動かす企画力を学んだ。
人材
私は個別指導塾のアルバイトリーダーとして、生徒の学習意欲向上と講師の指導力標準化に注力した。
担当教室の課題は、生徒の成績が担当講師の力量に左右されてしまう点だった。
そこで私は、全講師の指導方法をヒアリングし、成績上位の生徒を担当する講師のノウハウを体系化した独自の研修マニュアルを作成した。
さらに、講師間の情報交換を活性化させるための定期的なミーティングを導入した結果、教室全体の平均点が半年で15点向上し、退塾率も大幅に低下した。
この経験から、個人の成長を支援することが組織全体の成果に繋がることを学び、人の可能性を引き出すことに強いやりがいを感じている。
メーカー
私は大学の研究室で、環境負荷の少ない次世代バッテリーに関する研究に注力した。
目標としたのは、従来素材よりもエネルギー効率を20%向上させることであったが、実験は失敗の連続だった。
私は数百本に及ぶ先行研究の論文を読み込み、指導教官や他大学の研究者にも積極的に意見を求め、粘り強く試行錯誤を繰り返した。
その結果、新たな化合物を添加するという独自のアプローチを発見し、目標を上回る25%の効率向上を達成した。
この成果は学会でも評価された。
この経験を通じて、困難な課題に対しても諦めずに真因を追求し、成果を出す探究心と粘り強さを培った。
【ESの通過率を上げよう!】業界別自己PR参考例文集
次に、早期選考に活用できる自己PR例文を紹介します。
金融・商社・広告・人材・メーカーの5業界で求められる強みを意識し、具体的なエピソードを盛り込んでいます。
自身の強みを最も効果的にアピールするための参考にしてください。
金融
私の強みは「複雑な情報を構造化し、課題の本質を特定する分析力」である。
この強みは、大学のゼミで取り組んだ地域経済の活性化に関する研究で発揮された。
当初、データが膨大で議論が発散していたが、私は経済指標や人口動態などのデータを多角的に分析し、「産業構造の偏り」と「若年層の流出」という2つの本質的な課題を特定した。
この分析を基にチームの議論の方向性を定め、具体的な政策提言に繋げることができた。
この経験で培った分析力は、顧客の財務状況や市場動向を正確に読み解き、最適な金融ソリューションを提案する上で必ず活かせると考えている。
商社
私の強みは「文化や価値観の異なる相手とも信頼関係を築き、目標達成に導く交渉力」である。
この強みは、ベトナムでの1ヶ月間のボランティア活動で、現地NPOと共同で衛生改善プロジェクトを推進した経験で培われた。
当初、現地の慣習の違いから計画が全く進まなかったが、私は粘り強く対話を重ね、相手の意見を尊重する姿勢を示すことで徐々に信頼を得た。
最終的には、彼らの協力を得て井戸の設置を成功させることができた。
この経験で得た異文化理解力と交渉力は、世界中の多様なパートナーと協働し、新たなビジネスを創出する商社の仕事でこそ活かせると確信している。
広告
私の強みは「常識にとらわれず、人を惹きつける新しいアイデアを生み出す企画力」である。
私は大学の広報誌制作サークルで、従来の紙媒体からWebマガジンへの移行を企画・実行した。
当初は反対意見も多かったが、私は読者層である学生のライフスタイルを分析し、SNSでの拡散を前提とした動画コンテンツやインフルエンサーとのタイアップ企画を提案した。
その結果、Webマガジンの月間PVは紙媒体時代の10倍以上となり、学内での認知度を飛躍的に高めることに成功した。
この経験で培った、ターゲットの心を動かす企画力は、クライアントの課題を解決する広告業界で大きく貢献できると考えている。
人材
私の強みは「相手の立場に寄り添い、潜在的なニーズを引き出して成長を支援するサポート力」である。
私は大学のキャリアセンターで、後輩の就職活動相談に乗る学生チューターとして活動した。
単にアドバイスをするのではなく、対話を重ねる中で後輩自身が気づいていない強みや価値観を引き出すことを心掛けた。
その結果、担当した10名全員が、それぞれ最も納得できる企業から内定を獲得できた。
人の可能性を引き出し、その人が輝ける場を見つけることに大きなやりがいを感じており、この強みは求職者と企業の双方にとって最良のマッチングを実現する人材業界でこそ最大限に発揮できると考える。
メーカー
私の強みは「目標達成のために、どんな困難な状況でも粘り強く試行錯誤を続けられる探究心」である。
私は学生時代にプログラミングを独学で習得し、学内のビジネスコンテストで最優秀賞を受賞したアプリを開発した。
開発過程では、幾度となく予期せぬエラーに直面したが、その度に専門書や技術ブログを読み込み、徹夜でコードを修正し続けた。
この粘り強さがなければ、完成には至らなかった。
この「最高の製品を世に出すためなら、どんな努力も惜しまない」という姿勢は、技術の力で人々の生活を豊かにするメーカーのエンジニアとして働く上で、最も重要な資質であると考えている。
【ESの通過率を上げよう!】早期選考 面接対策
早期選考はESだけでなく、その後の面接も非常に重要です。
ESで示唆したポテンシャルや熱意を、対面でより具体的に伝えることが通過率向上に繋がります。
特に「志望度の高さ」「主体性」「将来の展望」の3点を、自信を持って語れるように準備しましょう。
「なぜこの会社でなければならないのか」を深く語れるようにする
面接官が最も知りたいのは、あなたの志望度の高さです。
ESの内容をなぞるだけでなく、「なぜ同業他社ではなく、この会社なのか」を、自身の経験や価値観と結びつけて具体的に伝える必要があります。
「〇〇という事業の将来性に惹かれた」「〇〇様のような社員の方々と共に働きたい」など、その企業だからこその理由を熱意を持って語ることで、本気度が伝わり、高い評価を得られます。
完成度よりも主体性と行動力をアピールする
早期選考の段階では、学生がビジネススキルを完璧に備えているとは企業も考えていません。
それよりも「現状に満足せず、自ら課題を見つけて行動できるか」というポテンシャルや主体性を重視します。
学生時代の経験の中で、指示を待つのではなく、自ら考え、周囲を巻き込みながら何かを成し遂げたエピソードを具体的に語ることが重要です。
スピード感のある行動力は、どの業界でも高く評価される要素です。
入社後のキャリアプランを伝え、長期的な貢献意欲を示す
企業は、あなたが入社後にどのように成長し、会社に貢献してくれるかという将来性を見ています。
「入社後はまず〇〇の分野で専門性を高め、将来的にはリーダーとしてチームを牽引したい」など、具体的で実現可能なキャリアプランを語ることで、長期的に活躍する意欲を示しましょう。
企業の事業展開や求める人材像と、自身のキャリアプランを重ね合わせて話すことで、企業とのマッチ度の高さをアピールできます。
まとめ
早期選考のESは通過率が低い一方で、準備をすれば大きなチャンスを掴める絶好の機会です。
自己分析の深さ、企業への熱意、そして具体的な行動力を示すことで、通過率は確実に高められます。
さらに、業界別の傾向に合わせたガクチカや自己PRを準備すれば、競争率の高い早期選考でも十分に突破可能です。
本記事で解説したメリットとリスクを理解し、効果的な早期選考対策を行いましょう。

_720x550.webp)