
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
就職活動において、多くの学生が重要視する条件の一つが、土日休みという働き方です。
ワークライフバランスを大切にする価値観が広まる中で、週末にしっかりと休息を取り、プライベートな時間を確保したいと考えるのは自然なことでしょう。
この記事では、なぜ土日休みの仕事が人気なのかという理由から、具体的な業界や職種、そして就職活動を成功させるための注意点やコツまでを網羅的に解説します。
【土日休みの仕事】なぜ人気がある?
土日休みの仕事が多くの就活生から支持されるのには、明確な理由があります。
それは単に二日間休めるというだけでなく、その休日が土曜日と日曜日であることに大きな価値があるからです。
プライベートの充実が、仕事への活力にもつながるという考え方が浸透している現代において、土日休みがもたらすメリットは計り知れません。
ここでは、その人気の理由を3つの側面から深掘りしていきます。
ワークライフバランスを取りやすい
土日休みの最大の魅力は、仕事とプライベートの生活を明確に区別し、メリハリのある毎日を送りやすい点にあります。
平日は仕事に集中し、週末は趣味や自己啓発、友人との交流、家族サービスなど、自分の時間を存分に楽しむことができます。
特に、毎週決まった曜日に二連休が確保されているため、小旅行やイベント参加など、計画的な予定を立てやすいのが大きなメリットです。
不規則なシフト制の仕事と比べて、生活リズムが整いやすく、心身ともにリフレッシュする時間を確実に持てるため、長期的に安定して働き続ける上での基盤となります。
社会的なスケジュールに合わせやすい
友人や家族との時間を大切にしたい人にとって、土日休みは非常に重要です。
多くの企業や学校、公的機関は土日を休日としているため、友人との約束や結婚式などのイベント、家族との外出といった予定の多くが土日に集中する傾向にあります。
自分が土日休みであれば、こうした社会的なカレンダーに自然とスケジュールを合わせることができ、大切な人たちとの時間を犠牲にすることなく、円滑な人間関係を築きやすくなります。
また、銀行や役所での手続きなども、平日の業務時間内に行う必要があるため、平日勤務であることは社会生活を送る上でもメリットが大きいといえるでしょう。
精神的・体力的な安定がある
規則正しい生活リズムは、心と体の健康を維持する上で非常に重要です。
平日に働き、土日に休むというサイクルは、体内時計を整えやすく、安定した睡眠パターンを確保することにつながります。
毎週決まったタイミングで休息が取れるという安心感は、精神的な余裕を生み出し、仕事のストレスを溜め込みにくくします。
5日間働けば必ずリフレッシュできる週末が来るという見通しがあることで、仕事へのモチベーションも維持しやすくなります。
このように、予測可能なスケジュールは日々の生活に安定感をもたらし、長期的なキャリアを築いていく上での心身の健康を支える大切な要素となるのです。
【土日休みの仕事】多い業界・職種
土日休みの仕事を探す際には、どのような業界や職種にその傾向が強いのかを知っておくことが効率的です。
一般的に、企業を相手にビジネスを行うBtoBの企業や、官公庁の開庁日に合わせて業務を行う業界では、カレンダー通りの休日を設定している場合が多く見られます。
ここでは、土日休みを実現しやすい代表的な業界を3つピックアップし、それぞれの特徴や具体的な職種について解説します。
メーカー(事務・総合職)
自動車、電機、食品、化学など、様々な製品を製造するメーカーは、土日休みの仕事が多い代表的な業界です。
特に、法人向けの製品を扱っているBtoBメーカーは、取引先企業の営業日に合わせてカレンダー通りの稼働となることがほとんどです。
工場の生産ラインは24時間稼働の場合もありますが、本社や支社で働く事務職、企画、人事、経理といった総合職は、基本的に土日休みとなります。
営業職も、個人消費者向けでなければ、平日に法人顧客を訪問し、土日は休むというスタイルが一般的です。
安定した経営基盤を持つ大手メーカーも多く、福利厚生が充実している点も魅力といえるでしょう。
IT・通信業界
IT・通信業界も、職種によっては土日休みを実現しやすい業界です。
特に、法人向けのシステム開発やソフトウェア提供、Webサービスなどを手掛ける企業では、クライアント企業の営業日に合わせてプロジェクトが進行するため、土日を休日とするのが一般的です。
システムエンジニアやプログラマー、Webデザイナー、ITコンサルタントといった職種がこれに該当します。
ただし、データセンターの運用保守やネットワーク監視など、24時間365日の対応が求められる一部の職種ではシフト制が採用されているため注意が必要です。
多くの企業で柔軟な働き方が導入されており、将来性も高い成長業界として人気があります。
金融・保険業界
銀行、証券、保険といった金融業界は、基本的にカレンダー通りの営業となるため、土日休みの仕事が中心です。
株式市場が平日のみ開かれていることや、主な顧客である法人企業が平日に活動していることがその理由です。
個人の顧客を対象とする銀行の窓口業務では、一部土曜日に営業している店舗もありますが、法人営業や融資、商品企画、資産運用、システム部門といった本部の職種は、完全に土日休みであることがほとんどです。
高い専門性が求められる一方で、安定した給与水準や充実した福利厚生が魅力であり、就活生からの人気も常に高い業界です。
【土日休みの仕事】文系でも目指しやすい職種
土日休みの仕事は、文系の学生が持つコミュニケーション能力や企画力、管理能力を活かせる職種に数多く存在します。
専門的な理系の知識がなくても、企業の根幹を支える重要な役割を担うことができ、安定したキャリアを築くことが可能です。
ここでは、特に文系の学生が目指しやすく、かつ土日休みを実現しやすい代表的な職種を3つご紹介します。
自分の興味や強みと照らし合わせながら、キャリアの選択肢を広げてみてください。
事務・総務・人事職
企業の円滑な運営を支える事務、総務、人事といった管理部門の仕事は、文系出身者が活躍しやすく、かつ土日休みが基本となる代表的な職種です。
これらの職種は、社員が働く平日の日中に業務が集中するため、カレンダー通りの勤務体系となります。
事務職はデータ入力や書類作成、電話応対などを通じて各部署をサポートし、総務は備品管理や社内イベントの企画運営、人事では採用活動や労務管理などを担います。
いずれの仕事も、正確な事務処理能力や、社内外の人々と円滑にやり取りするコミュニケーション能力が求められ、文系の学生が持つ素養を大いに活かせるフィールドです。
広報・マーケティング職
自社の製品やサービスの魅力を世の中に伝え、ブランド価値を高める広報やマーケティングの仕事も、文系学生に人気の職種です。
これらの職種も、企業の戦略立案や企画業務が中心となるため、基本的には土日休みとなります。
広報は、プレスリリースの作成やメディア対応、SNS運用などを通じて社会との良好な関係を築きます。
マーケティングは、市場調査やデータ分析に基づき、販売戦略や広告宣伝の企画立案を行います。
どちらも、社会のトレンドを読み解く力や、説得力のある文章を作成する能力、そして創造的な発想力が求められ、知的好奇心が旺盛な文系学生にとって非常にやりがいのある仕事です。
公務員・独立行政法人
安定した働き方を実現したいと考えるなら、公務員や独立行政法人の職員も有力な選択肢です。
市役所や県庁などの地方公務員、国の省庁で働く国家公務員の多くは、土日祝日が休みの完全週休2日制です。
窓口業務や行政サービスの提供は、住民や企業が活動する平日に合わせて行われるため、勤務体系が非常に安定しています。
また、博物館や研究機関などの独立行政法人も、同様に土日休みが多い傾向にあります。
法律や経済、教育など、大学で学んだ専門知識を直接活かせる分野も多く、社会に貢献したいという強い意志を持つ文系学生にとって、非常に魅力的な働き方といえるでしょう。
【土日休みの仕事】理系向けの職種紹介
理系の学生が持つ専門知識や論理的思考力は、土日休みが基本となる多くの技術系職種で高く評価されます。
特に、BtoBを中心とするメーカーやIT業界には、最先端の技術に触れながら、安定した生活リズムで働くことができるポジションが豊富に存在します。
ここでは、理系のバックグラウンドを活かせる代表的な土日休みの仕事を3つ紹介し、その魅力と役割について解説します。
研究職・開発職(メーカー系)
メーカーにおける研究職や開発職は、理系学生の専門性を最も直接的に活かせる仕事の一つです。
新製品の基盤となる基礎研究や、既存製品の改良、新たな生産技術の開発などを担います。
これらの仕事は、長期的な視点での実験やデータ分析が中心となるため、基本的に土日休みの勤務体系が取られています。
平日に集中して研究開発に取り組み、週末にリフレッシュするというメリハリのある働き方が可能です。
化学、物理、生物、情報、機械など、大学での研究内容を活かし、世の中にない新しい価値を生み出したいという探究心の強い人にとって、大きなやりがいを感じられる職種です.
ITエンジニア・システム開発職
IT業界のエンジニア職も、理系出身者が活躍する代表的な土日休みの仕事です。
特に、法人向けの業務システムやアプリケーションを開発するSIerや、自社サービスを開発するWeb系企業では、プロジェクトのスケジュールが平日の稼働を前提に組まれるため、土日休みが基本となります。
プログラミングによるコーディングはもちろん、システムの設計や要件定義といった上流工程では、物事を構造的に捉える論理的思考力が不可欠であり、理系の素養が存分に活かされます。
技術の進歩が速い業界であるため、常に新しい知識を学ぶ意欲が求められますが、その分、自身の成長を実感しやすい魅力的な仕事です。
建設コンサル・インフラエンジニア
社会の基盤となるインフラを支える建設コンサルタントやインフラエンジニアも、理系向けの専門職です。
主な業務は、道路や橋、ダムといった公共インフラの調査、計画、設計であり、発注者である官公庁の開庁日に合わせて業務が進められるため、土日休みが一般的です。
ただし、現場での調査や工事の進捗によっては、まれに休日出勤が発生する可能性もあります。
土木や建築、環境といった分野の専門知識を活かし、地図に残るような大きなプロジェクトに携われるのが最大の魅力です。
社会貢献性が非常に高く、安定した需要があるため、長期的な視点でキャリアを築きたい理系学生にとって有力な選択肢となるでしょう。
【土日休みの仕事】探すときの注意点
土日休みの仕事は魅力的ですが、求人情報を見る際にはいくつかの注意点があります。
言葉の定義を正しく理解していなかったり、例外的な勤務形態を見落としていたりすると、入社後に理想とのギャップを感じてしまう可能性があります。
後悔しない企業選びのために、ここでは土日休みの仕事を探す上で特に気をつけるべき3つのポイントを解説します。
これらの知識を身につけ、求人情報の裏側まで読み解く力を養いましょう。
「完全週休2日」と「週休2日」の違いを理解する
求人情報で最も注意すべきなのが、完全週休2日制と週休2日制の違いです。
この二つは似ているようで、意味が全く異なります。
完全週休2日制は、毎週必ず2日間の休日がある制度を指します。
例えば、土日休みや、水日休みなどがこれに該当します。
一方、週休2日制は、1ヶ月の間に週2日の休みがある週が少なくとも1回以上ある制度のことです。
つまり、月のうち3週間は週休1日で、1週間だけ週休2日というケースも週休2日制と表記できてしまいます。
土日休みを絶対条件とするならば、必ず完全週休2日制(土日)と明記されているかを確認することが非常に重要です。
繁忙期やシフト例外に注意
完全週休2日制(土日)と書かれていても、年間を通じて常に休みが保証されるとは限りません。
業界や職種によっては、特定の繁忙期や例外的なケースで、土日に出勤が必要になる場合があります。
例えば、企業の経理部門であれば年度末や決算期、IT業界であれば大規模なシステムリリースの直前、メーカーの営業職であれば新製品の発表イベントなどで、休日出勤を求められる可能性があります。
また、職種によっては、お客様対応のために交代で土日に出勤する当番制を設けている企業もあります。
面接やOB訪問の際に、休日出勤の頻度や、その場合の振替休日の取得状況について具体的に質問しておくことが大切です。
残業や有給消化率も併せて確認
土日に休めるかどうかだけでなく、平日の働き方や他の休暇制度についても確認することが、本当の意味でのワークライフバランスを実現する上で重要です。
たとえ土日に休めても、毎日終電まで残業するような生活では、心身ともに疲弊してしまいます。
企業の平均的な残業時間や、36協定の内容について調べておきましょう。
また、有給休暇の消化率も大切な指標です。
制度として有給休暇があっても、実際には取得しにくい雰囲気の職場も存在します。
企業の口コミサイトを参考にしたり、面接で質問したりすることで、社員がどれだけ休暇を自由に取得できているか、その実態を把握するよう努めましょう。
【土日休みの仕事】年収や将来性は?
土日休みという働き方を選ぶ際、多くの人が気になるのが年収やキャリアの将来性でしょう。
働きやすさと経済的な安定や成長性を両立させることは、キャリアプランを考える上で非常に重要なテーマです。
ここでは、土日休みの仕事における年収の傾向や、今後のキャリアパス、そして社会的な動向について解説します。
自分の理想とするライフプランと照らし合わせながら、長期的な視点で考えてみましょう。
平均年収は350〜500万円台が中心
土日休みの仕事の年収は、業界や企業規模、職種によって大きく異なりますが、新卒から数年間の若手社員の場合、平均的には350万円から500万円台が中心的なレンジとなります。
例えば、安定した経営基盤を持つ大手メーカーや金融機関では、初任給から比較的高水準であり、福利厚生も手厚い傾向にあります。
一方、中小企業や一部のITベンチャーなどでは、初任給は平均的でも、その後の成果やスキルアップに応じて大きく昇給する可能性があります。
土日休みという条件だけで年収が決まるわけではなく、あくまでその企業が属する業界の給与水準や、個人の専門性が大きく影響することを理解しておきましょう。
年功序列よりも成果重視の企業も多い
かつての日本企業は年功序列型の給与体系が主流でしたが、現代では、特に土日休みの仕事が多いIT業界や専門職の世界では、年齢に関係なく個人の成果やスキルを評価する成果主義の企業が増えています。
このような環境では、若手であっても高いパフォーマンスを発揮すれば、早くから昇進したり、大幅な年収アップを実現したりすることが可能です。
逆に、ただ在籍しているだけでは給与は上がりにくいという厳しさもあります。
土日休みという安定した基盤の上で、平日は自己投資やスキルアップに励み、専門性を高めていくという主体的な姿勢が、将来的な年収アップにつながる鍵となるでしょう。
働き方改革で増えている業界もチェック
近年、政府が推進する働き方改革の影響で、これまで土日休みが少なかった業界でも、労働環境の改善が進んでいます。
例えば、かつては長時間労働や休日出勤が多いイメージだった建設業界や、土日も営業が当たり前だった不動産業界の一部でも、完全週休2日制を導入する企業が増加傾向にあります。
これは、人材確保や定着率向上のために、魅力的な労働条件を整える必要性が高まっているからです。
今後は、これまで選択肢に入れていなかった業界にも、土日休みで働けるチャンスが広がっていく可能性があります。
固定観念に縛られず、幅広い業界の最新の動向をチェックすることが重要です。
【土日休みの仕事】向いている人・向いていない人
土日休みという働き方は多くの人にとって魅力的ですが、その安定したリズムがすべての人に合うわけではありません。
自分の性格や価値観、ライフスタイルと働き方が合致しているかを見極めることは、長期的に満足度の高いキャリアを築く上で不可欠です。
ここでは、土日休みの仕事に向いている人と、そうでない人の特徴を対比させながら、自分に合った働き方を見つけるためのヒントを解説します。
向いている人:計画的・安定志向タイプ
土日休みの仕事に最も向いているのは、計画的に物事を進めるのが好きで、安定した生活を求めるタイプの人です。
毎週決まった曜日に休日があるため、趣味や旅行、資格の勉強など、プライベートの予定を数週間先、数ヶ月先まで具体的に立てることができます。
このような予測可能な生活リズムは、精神的な安心感にもつながります。
また、仕事とプライベートのオンとオフを明確に切り替えたいと考えている人にも最適です。
平日は仕事に全力で取り組み、週末はしっかりと心身を休ませるというメリハリのある生活を送りたい人にとって、土日休みは理想的な働き方といえるでしょう。
向いていない人:刺激・変化を求めるタイプ
一方で、単調なリズムや決まったスケジュールに退屈さを感じてしまう、刺激や変化を求めるタイプの人には、土日休みの仕事が物足りなく感じられるかもしれません。
例えば、平日の空いている時間に外出したり、世間が働いている時に休むことに優越感を感じたりする人にとっては、シフト制の仕事の方が魅力的に映るでしょう。
また、接客業や販売業のように、土日の賑わいの中で働くことにやりがいを感じる人もいます。
自分の仕事の成果が、週末の来客数や売上といった形でダイレクトに表れることに喜びを感じるタイプであれば、あえて土日が出勤となる仕事を選ぶのも一つの選択です。
自分の生活リズムと合う働き方を見極める
最終的に大切なのは、世間一般の価値観に流されるのではなく、自分自身がどのような生活リズムを心地よいと感じるかを見極めることです。
土日休みのメリットと、シフト制勤務のメリットを比較検討し、自分のライフプランや大切にしたい価値観と照らし合わせてみましょう。
例えば、友人と予定を合わせることを最優先するなら土日休み、混雑を避けて趣味を楽しみたいなら平日休みが中心の仕事、というように、自分なりの判断基準を持つことが重要です。
自己分析を深め、自分にとって本当に豊かな人生とは何かを考えることが、最適な働き方を見つけるための第一歩となります。
【土日休みの仕事】就活を成功させるコツ
土日休みの仕事は人気が高いため、多くの就活生がライバルとなります。
その中で内定を勝ち取るためには、戦略的な就職活動が不可欠です。
やみくもに応募するのではなく、効率的に情報を収集し、企業が求める人物像を理解した上でアピールすることが重要になります。
ここでは、土日休みの仕事を見つけ、選考を有利に進めるための具体的なコツを3つご紹介します。
これらのポイントを実践し、理想の働き方を手に入れましょう。
企業研究は“働き方”軸で進める
土日休みを重視する場合、企業研究の段階から働き方に焦点を当てることが大切です。
企業の事業内容や業績だけでなく、休日制度や残業時間、福利厚生といった労働環境に関する情報を重点的に収集しましょう。
特に、求人票の休日欄は注意深く確認し、完全週休2日制(土日)であるかを必ずチェックします。
企業の採用サイトにある社員紹介のページで、休日の過ごし方について語られている部分も参考になります。
働きやすさを企業の魅力として積極的に発信している企業は、社員を大切にする文化が根付いている可能性が高く、狙い目といえるでしょう。
就活サイトで「完全週休2日」で絞り込み
大手就活サイトやナビサイトを利用する際は、検索機能を最大限に活用しましょう。
多くのサイトには、休日制度に関する絞り込み検索の機能が備わっています。
ここで、週休2日制ではなく、必ず完全週-休2日制の項目にチェックを入れて検索することが、効率的に企業を探すための基本です。
さらに、土日祝休みというキーワードを追加したり、年間休日120日以上といった条件で絞り込んだりすることで、より自分の理想に近い企業をリストアップすることができます。
膨大な求人情報の中から、自分の希望に合わない企業を最初から除外することで、企業研究やエントリーシート作成に集中する時間を確保できます。
OB・OG訪問で実際の勤務実態を聞く
求人情報や企業の公式発表だけでは分からない、リアルな勤務実態を知るために最も有効な手段が、OB・OG訪問です。
実際にその企業で働いている先輩社員に、休日の取りやすさや、平日の残業の実態、有給休暇の消化状況など、聞きにくいことを直接質問してみましょう。
部署による働き方の違いや、繁忙期の具体的な様子など、内部の人でなければ分からない貴重な情報を得られる可能性があります。
誠実な姿勢で質問すれば、多くの先輩は就活生のために親身になって答えてくれるはずです。
ここで得たリアルな情報は、企業選びの最終判断を下す上で、何よりも信頼できる材料となります。
【土日休みの仕事】よくある質問(FAQ)
土日休みの仕事を探す中で、多くの就活生が抱く共通の疑問があります。
休日制度の言葉の定義や、残業の実態、年収との関係など、気になる点は多いでしょう。
ここでは、そうしたよくある質問を3つ取り上げ、分かりやすく解説します。
正しい知識を身につけ、不安を解消した上で、自信を持って就職活動に臨みましょう。
「完全週休2日制」と「週休2日制」はどう違いますか?
この二つの言葉は、休日を考える上で最も重要な違いがあります。
完全週休2日制とは、毎週必ず2日間の休日がある制度のことです。
土日休みとは限りませんが、1年を通して毎週2日の休みが保証されています。
一方、週休2日制は、1ヶ月の間に、2日休める週が少なくとも1回はある制度を指します。
つまり、月の残りの週は休日が1日だけという可能性もあるため、毎週必ず2日休めるわけではありません。
土日休みを希望する場合は、求人情報で完全週休2日制(土日)と明記されているかを必ず確認する必要があります。
この違いを理解しておくことは、入社後のミスマッチを防ぐための第一歩です。
土日休みの仕事でも残業はありますか?
土日休みであることと、平日の残業の有無は別の問題です。
完全週休2日制の企業であっても、残業が全くないとは限りません。
残業時間は、業界や職種、企業の文化、そして個人の仕事の進め方によって大きく異なります。
IT業界のプロジェクトの納期前や、メーカーの繁忙期など、特定の時期に残業が増えることもあります。
企業を選ぶ際には、休日制度だけでなく、月間の平均残業時間も併せて確認することが重要です。
企業の口コミサイトを参考にしたり、OB・OG訪問や面接の場で、残業の実態や36協定の運用状況について質問したりすることで、平日の働き方をより具体的にイメージできるでしょう。
土日休みで年収が高い仕事はありますか?
土日休みでありながら、高い年収を目指せる仕事は数多く存在します。
年収は、休日制度よりも、業界の収益性や企業の規模、そして個人の専門性によって決まる部分が大きいからです。
例えば、総合商社や外資系コンサルティングファーム、大手金融機関、収益性の高いメーカーなどは、土日休みが基本でありながら、平均年収も高いことで知られています。
また、IT業界のエンジニアや専門職も、高いスキルを身につければ、若いうちから高収入を得ることが可能です。
働きやすさと高い報酬を両立させたい場合は、休日制度という条件だけでなく、どの業界でどのような専門性を磨いていくかという視点を持つことが重要になります。
まとめ
この記事では、土日休みの仕事が人気である理由から、具体的な業界や職種、探す際の注意点、そして就活を成功させるコツまで、幅広く解説してきました。
土日休みという働き方は、ワークライフバランスを重視する現代において、非常に魅力的な選択肢です。
しかし、言葉の定義を正しく理解し、残業や繁忙期の実態まで含めて企業を研究することが、入社後のミスマッチを防ぐ鍵となります。
自分の価値観やライフプランと向き合い、本記事で得た知識を活用して、納得のいくキャリア選択を実現してください。

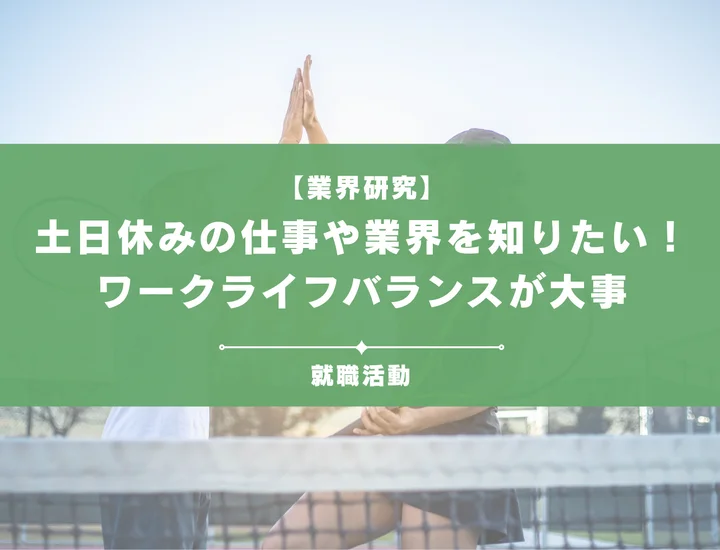

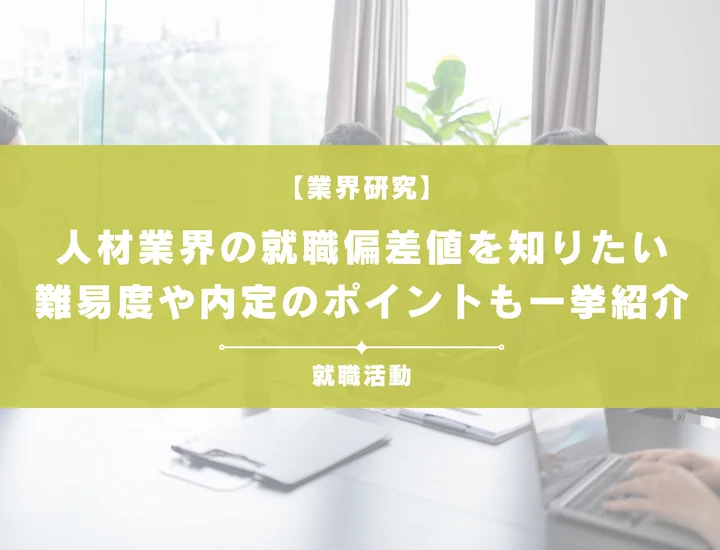

_720x550.webp)




