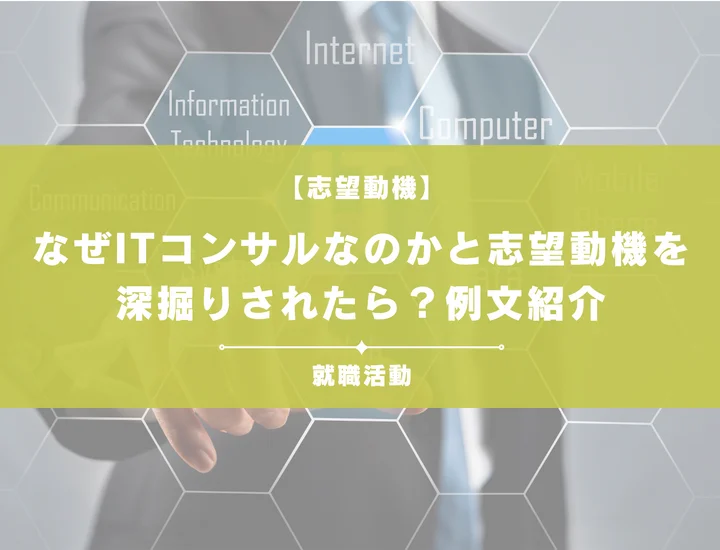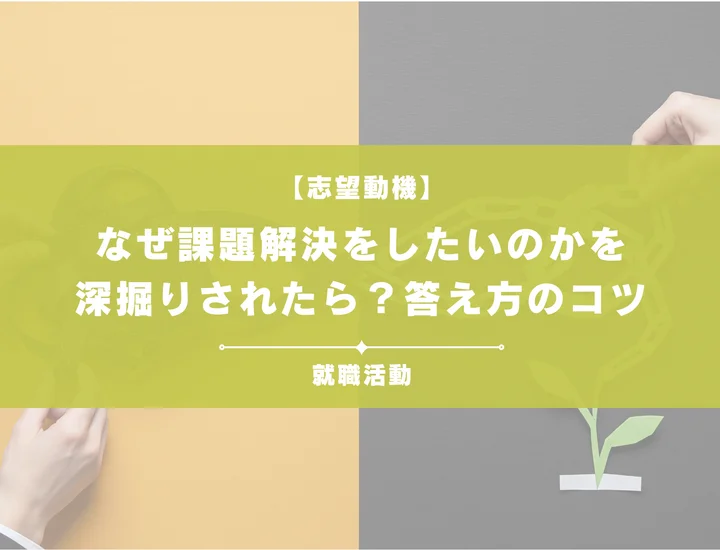HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
本記事では、面接で問われるなぜITコンサルかの意図を起点に、職種理解、自社との相性、将来性の示し方を体系的に解説します。
是非、ご自身の就活の参考にしてください。
【なぜITコンサルなのか】なぜ面接官は「なぜITコンサル?」と聞くのか
ITコンサルタントを志望する学生に対して、面接官が最初に確認する質問の一つがなぜITコンサルなのかという問いです。
この質問は単なる興味や憧れを探るものではありません。
志望者がどれだけ職種を理解しているか、企業との相性があるか、そして入社後に活躍できるかを見極める大切な判断材料です。
表面的な答えではなく、自分の考えを明確に語ることが評価につながります。
業界・職種への理解度
ITコンサルタントは、企業の課題を整理し、解決策を提案し、実行まで導く役割を担います。
単に技術に詳しいだけではなく、業務や組織構造を理解し、経営目線で考える力が求められます。
そのため、面接官は志望者が職種の本質を理解しているかを見極めようとします。
言葉の響きだけで志望しているのか、それとも実際の仕事を理解しているのかが重要です。
SEや一般的なエンジニアとの違いを理解し、自分がなぜこの仕事を選ぶのかを自分の言葉で語る必要があります。
この理解が浅いと、説得力のある志望理由を伝えることはできません。
自社とのマッチ度
ITコンサルタントを志望する学生は多いですが、企業が注目しているのはその中でもなぜ自社なのかという点です。
ITコンサルティングの領域は企業によって得意分野や進め方が大きく異なります。
業界全体への理解だけではなく、自社の特徴をきちんと把握しているかどうかが問われます。
企業が持つ強みや価値観と、自分がやりたいことが一致しているかを確認したいのです。
志望動機の中で、自分の目指す姿と企業の方向性が自然に重なっていると、面接官に強い印象を与えることができます。
逆に、表面的な内容では意欲が伝わりません。
企業研究を丁寧に行い、自分の思いや経験と結び付けて語ることが鍵となります。
将来のポテンシャル
ITコンサルタントは、入社してから学び続けることが求められる職種です。
面接官は、今持っている知識や技術よりも、成長し続ける姿勢を重視しています。
業務の中では、技術力だけでなく論理的な思考力、課題解決力、自律的な行動力が必要になります。
そのため、志望者が過去の経験から何を学び、それを今後どう活かしていくのかを知ろうとします。
知識を一方的に語るよりも、成長意欲を明確に示すことが大切です。
困難な課題にも前向きに取り組む姿勢を伝えられれば、将来性を高く評価される可能性が高まります。
この質問は、単なる志望動機ではなく、自分の可能性を示す絶好の機会です。
【なぜITコンサルなのか】そもそもITコンサルとは
ITコンサルタントという職種は、ITを軸に企業の課題解決を支える重要な役割を担っています。
単なる技術者ではなく、経営と現場の両方を理解し、課題を整理し、戦略を実行に移す橋渡し役です。
また、システムエンジニアや他のコンサルタントと比べても立ち位置や役割が大きく異なります。
この違いを正しく理解することで、自分の志望理由をより深く説明できるようになります。
仕事内容
ITコンサルタントの仕事は、クライアント企業の課題を明らかにし、その解決策をITの力で実現することです。
まず、経営層や現場担当者へのヒアリングから始まり、業務の流れやシステムの現状を詳しく分析します。
売上の伸び悩みや業務効率の低下など、経営上の課題の根本原因を見極め、解決のための戦略を立てます。
そのうえで、システムの導入や改善、運用の支援までを一貫して行います。
単なるシステムの提案ではなく、企業が目指す成果に向けて並走するのが特徴です。
現場の声と経営目標をつなぎ、実行可能な計画を形にする役割を担っています。
SEとの違い
ITコンサルタントとシステムエンジニアでは、担当する工程と責任の範囲が異なります。
ITコンサルタントは、なぜシステムが必要なのか、何を解決すべきなのかという目的を定義する最上流の部分を担当します。
一方、システムエンジニアは、その目的を実現するために、どのようにシステムを作るかを設計・開発する役割を担います。
つまり、ITコンサルタントはビジネスの成果に責任を持ち、システムエンジニアは技術的な完成度に責任を持ちます。
この違いから、ITコンサルタントには技術力だけでなく、課題を整理し戦略を立てる力や、顧客との対話力が求められます。
他のコンサルとの違い
ITコンサルタントと戦略コンサルタントなどの他分野との大きな違いは、扱う内容の具体性にあります。
戦略コンサルタントは企業全体の方向性や事業戦略といった抽象的で広いテーマを扱います。
一方、ITコンサルタントはITを活用するという具体的な手段に特化しています。
経営方針を踏まえ、どのようなIT投資を行い、どう実行に移すのかを計画し、推進していきます。
戦略を実際のアクションに変える専門性を持ち、実行フェーズまで深く関わるのが特徴です。
この実行力があるからこそ、多くの企業にとって欠かせない存在となっています。
【なぜITコンサルなのか】文系・未経験でも活躍できる3つの理由
ITコンサルタントという職種は、理系出身者やIT経験者だけが活躍できる仕事ではありません。
実際には、文系やIT未経験の人材も多くの企業で第一線で活躍しています。
その理由は、この仕事に求められる力が、専門知識だけに限られないからです。
特に、人との対話力、課題を整理する力、そして学ぶ姿勢があれば、しっかりと成長することができます。
ここでは、その具体的な3つの理由を解説します。
コミュニケーション能力が求められるから
ITコンサルタントの仕事では、最初にクライアントが抱える課題を正確に理解することが欠かせません。
そのためには、経営層や現場担当者の話を丁寧に聞き取り、曖昧な要望を明確な課題として整理する力が必要です。
さらに、エンジニアや他部門との連携も重要なため、立場の異なる人とスムーズに意思疎通ができる力が求められます。
相手の意図を汲み取り、複雑な内容を分かりやすく伝えることができれば、文系であっても十分に活躍できます。
ITコンサルタントは技術を使う仕事であると同時に、人との対話で価値を生み出す仕事でもあります。
この力は学生時代の研究発表やアルバイト経験、課外活動などを通じて培うことが可能です。
論理的思考力が重要だから
ITコンサルタントは、課題の本質を見抜き、解決までの筋道を組み立てる力が求められます。
技術知識以上に大切なのが、状況を整理し、問題を分解し、最も効果的な解決策を導き出す論理的思考力です。
これは文系の学生でも十分に身につけられる力であり、レポートや論文の構成、発表準備などの経験が活かせます。
ITコンサルタントは単なるシステム導入担当ではなく、経営課題の解決を担う立場です。
仮説を立て、検証し、筋道を立てて説明する力があれば、プログラミング経験がなくても成果を出せます。
この力は、入社後の実務でも非常に高く評価されます。
入社後の研修制度が充実しているから
多くのコンサルティングファームでは、新卒社員が未経験であることを前提に研修制度を整えています。
入社直後からITの基礎、業界構造、課題解決の進め方、資料作成のスキルなどを段階的に学ぶことができます。
研修は実務に直結する内容が多く、座学だけでなく演習やチーム演習も含まれているのが特徴です。
そのため、入社時点でITスキルがなくても問題ありません。
必要なのは、新しい知識を吸収し、実践の中で成長する姿勢です。
努力を積み重ねれば、文系・未経験でも確実にプロフェッショナルとして活躍できる環境が整っています。
【なぜITコンサルなのか】成し遂げたいこととITコンサルの繋げ方
ITコンサルタントを志望する際、よくある失敗の一つが「やりたいこと」と「ITコンサル」という職種のつながりがあいまいなまま話してしまうことです。
単なるイメージや憧れでは説得力が不足してしまいます。
一方で、自分の価値観を明確に言語化し、ITを手段として結び付けることができれば、面接官に強い印象を残すことができます。
ここでは、3つのステップでその考え方を整理します。
自己分析をしてやりたいことの軸(動詞)を見つける
まず、自分の中にある根本的な価値観を明確にすることが重要です。
業界名や職種名ではなく、自分がどのような行動をしたいのかという動詞に注目します。
社会の課題を解決したい、人の挑戦を支援したい、非効率な作業を効率化したいなど、自分の原動力となる想いを掘り下げていきます。
この軸が曖昧なままだと、志望動機が企業研究の受け売りのようになりがちです。
逆に、自分のやりたいことが明確であれば、どんな職種であっても筋の通った話をすることが可能になります。
自分の言葉で動機を説明できるようになることが、説得力の第一歩です。
その手段がなぜITなのか
次に、見つけた動詞を実現するために、なぜITという手段が適しているのかを考えます。
ITは人の力だけでは届かない範囲にまで影響を広げることができます。
効率化という軸を持っている人であれば、ITを活用することで一部の業務改善にとどまらず、組織全体のプロセスを変えることができます。
スピードや拡張性、データに基づいた客観性など、ITが持つ特性を自分の軸と結びつけることで、より具体的な志望理由に変わります。
この段階を丁寧に整理することで、ただの興味ではなく、目的意識のある志望動機を伝えることが可能になります。
その中でもなぜコンサルなのか
最後に、ITを使う立場の中でも、なぜコンサルタントを選ぶのかを言語化します。
事業会社であれば、自社の業務改善やサービス開発に専念する形になりますが、コンサルタントはさまざまな業界や企業に関わることができます。
多様な課題に向き合い、外部の専門家として客観的な立場から支援できる点が大きな特徴です。
幅広い経験を積みながら、課題解決の力を高めていける環境であることを、自分の軸と重ねて語ることが大切です。
志望動機の中でこの一貫性をしっかり描ければ、面接官に明確な意志と将来性を伝えることができます。
【なぜITコンサルなのか】志望動機の考え方
ITコンサルタントの志望動機を作るときに最も重要なのは、なぜその職種を選び、なぜその企業を志望するのかを一貫性を持って伝えることです。
あいまいな印象を与える志望動機は、他の学生との差別化ができず、説得力も弱くなります。
一方で、自分の価値観と企業の特徴をしっかりと結び付ければ、短い言葉でも強い印象を残すことが可能です。
ここでは、志望動機を組み立てるための4つの考え方を解説します。
成し遂げたいことは何か
志望動機を考えるうえで、まず整理すべきなのは自分が何を成し遂げたいのかという軸です。
この軸が曖昧だと、どんなに言葉を並べても本気度が伝わりません。
自分のやりたいことを業界名ではなく、動詞で表すのが効果的です。
社会の課題を解決したい、人の挑戦を支援したい、働く環境を効率化したいなど、自分の根本的な価値観を掘り下げます。
この軸が定まれば、ITコンサルという職種のどこに魅力を感じているのかが自然と見えてきます。
面接では、この軸を端的に伝えることで、あなたの考えの一貫性を示すことができます。
なぜその会社なのか
志望動機で差をつける大きなポイントが、この会社を選んだ理由です。
ITコンサルの仕事は多くの企業が担っていますが、企業ごとに強みや文化は大きく異なります。
金融業界に強い、デジタル化支援の実績がある、社会課題の解決を重視しているなど、特徴をしっかりと理解することが大切です。
また、説明会や座談会で実際に話を聞いた社員の人柄や働き方に惹かれたなど、リアルな体験を加えると説得力が増します。
単なる企業紹介ではなく、自分の価値観との接点を言語化することで、志望理由がより具体的になります。
原体験とつなげる
志望動機を深めるためには、自分の過去の経験と志望理由を結び付けることが効果的です。
ゼミやアルバイト、サークル活動など、自分が主体的に取り組んだエピソードを思い出します。
そこで発揮した力や得た学びを、ITコンサルタントの仕事にどう活かせるのかを整理します。
例えば、コミュニケーション力を活かして多様な立場の人と調整した経験や、論理的に課題を分析して改善策を考えた経験などです。
このような原体験を交えると、抽象的な志望理由ではなく、あなたにしか語れない具体的なストーリーになります。
将来性を示す
最後に、将来像を語ることで志望動機をさらに強いものにできます。
企業は、入社時点での能力だけでなく、長期的に成長できる人材かどうかを重視しています。
ITコンサルとして身に付けたいスキルや、挑戦したい業界、目指したい立場などを明確に言語化します。
短期的な目標と中長期的なキャリアビジョンをセットで話すと、本気度と計画性が伝わります。
また、企業の成長分野と自分の将来像が重なっていれば、説得力は一段と高まります。
志望動機の結論として、自分の成長と企業への貢献を両立させたメッセージを伝えることが大切です。
【なぜITコンサルなのか】志望動機の例文
ITコンサルタントの志望動機では、漠然とした表現ではなく、自分の想いや経験を明確に言葉にすることが大切です。
なぜITを手段として選んだのか、なぜコンサルタントという立場で働きたいのか、そして何を成し遂げたいのかを一貫して伝えることで、説得力のある内容になります。
ここでは、社会課題解決タイプ、特定業界への貢献タイプ、身近な課題発見・改善タイプという三つの視点から、実践的な志望動機の例文を紹介します。
社会課題解決タイプ
例文
私は社会全体に影響を与える仕事に携わりたいと考えています。
その中でもITは、社会課題の解決に大きな力を発揮できる手段だと強く感じています。
大学時代、地域の高齢者向けイベントの運営に携わり、デジタル機器を使いこなせないことが日常生活の不便さに直結している現状を目の当たりにしました。
この経験から、ITを活用することで社会の仕組みそのものを変え、多くの人の生活をより豊かにできると実感しました。
ITコンサルタントとして働くことで、一企業の改善にとどまらず、社会全体に波及する変化を生み出せる点に強い魅力を感じています。
私は課題の本質を捉え、最適な解決策を提案し、実行まで支える立場として、幅広い分野で貢献できる人材を目指します。
将来的には、公共分野や医療など社会性の高い領域で、大きなインパクトを与えるプロジェクトを担えるよう成長していきたいと考えています。
特定業界への貢献タイプ
例文
私は医療分野にITを活用し、現場の負担軽減とサービスの質向上に貢献したいと考えています。
大学時代、医療機関でのボランティア活動を通じて、多くの現場ではシステムが複雑で使いづらく、スタッフが本来の業務以外の部分に多くの時間を取られている現状を知りました。
こうした非効率を改善することで、患者と医療従事者の双方にとってより良い環境をつくることができると感じました。
ITコンサルタントであれば、システムの導入や改善を単なる技術提供にとどめず、現場の業務全体を見直す立場から課題解決に関わることができます。
医療という社会的に重要な分野で、自分の提案が形となり、人の命を支える現場を変えていくことに大きなやりがいを感じています。
将来的には、医療分野の課題解決に特化した専門性を高め、プロジェクトをリードできる人材を目指したいです。
身近な課題発見・改善タイプ
例文
私は日常の中で感じる小さな不便を、仕組みの改善によって解決することに強い関心があります。
大学で所属していた学生団体では、イベント管理の業務が属人的で、情報共有に多くの時間がかかっていました。
この課題を解決するため、タスク管理ツールを導入し、運用フローを整理する仕組みを提案したことで、全体の作業効率が大きく向上しました。
この経験を通じて、ITには人の手間を減らし、より価値のある活動に集中できる環境をつくる力があると実感しました。
ITコンサルタントとして働くことで、自分の視点で課題を発見し、それを改善につなげる仕事ができると考えています。
特別な分野に限らず、日常的な業務改善から大規模な仕組み改革まで関われる点に強く惹かれています。
将来的には、多様な業界の課題に向き合い、より多くの人の働き方を変える提案ができる人材を目指したいです。
【なぜITコンサルなのか】企業研究の軸
ITコンサルといっても、企業ごとに得意とする業界や技術領域、働き方や社風は大きく異なります。
なんとなく有名だからという理由では、志望理由が浅くなりがちです。
自分の関心や価値観に合った企業を見つけることで、面接でも一貫した志望動機を伝えられるようになります。
ここでは、企業研究を進める際に意識すべき3つの軸を紹介します。
得意な業界で絞る
ITコンサル企業は、それぞれ得意とする業界を持っています。
金融、製造、通信、医療など、特定の業界で豊富なプロジェクト実績を積み上げている企業は、その分野に特化した課題解決の知見やノウハウを持っています。
自分が将来的に関わりたい領域が明確な場合、その業界に強い企業を選ぶことで、入社後の成長機会が広がります。
企業の公式サイトに掲載されている導入事例やケーススタディは、業界の強みを知る有効な手がかりです。
自分の興味と企業の専門分野が重なるかを確認することで、より説得力のある志望理由を組み立てることができます。
特異な技術で絞る
ITコンサル企業は、業界だけでなく技術面でも得意領域が分かれています。
クラウド導入、データ分析、基幹システム、サイバーセキュリティなど、企業によって専門性のある技術領域が異なります。
自分が将来的にどのような技術で課題解決に関わりたいのかを考えることで、企業研究の方向性がはっきりします。
技術的な強みを理解したうえで企業を選ぶと、志望動機もより具体的になります。
企業の採用ページや技術ブログ、実績紹介などを調べることで、どの領域に強いのかを把握できます。
技術の方向性と自分の志向が合致していれば、入社後のキャリア形成にも一貫性が生まれます。
企業のカルチャーやキャリアパスで絞る
長く働き続けるには、企業の文化や働き方との相性も重要です。
同じITコンサル企業でも、若手のうちから大きな裁量を与える環境と、専門性をじっくり磨く環境では、得られる経験が大きく異なります。
また、グローバル案件に携わるチャンスがあるかどうかも、企業によって差があります。
OBやOG訪問、インターンシップなどを活用することで、社風や働き方を具体的に知ることができます。
自分がどのような環境で最も力を発揮できるのかを明確にすることが、入社後のミスマッチを防ぐポイントになります。
【なぜITコンサルなのか】面接時の伝え方
ITコンサルタントを目指す学生にとって、面接は志望度と適性をしっかりと伝える最大のチャンスです。
どれだけ自己分析や企業研究を重ねても、それを面接で伝えられなければ意味がありません。
面接官が短時間であなたの考えを理解し、評価できるように話すためには、話の構成を整理することが大切です。
ここでは、面接で効果的に想いを伝えるためのシンプルかつ強力なフレームワークを紹介します。
結論
最初に自分の考えを簡潔にまとめた結論を伝えることが、面接では非常に重要です。
話の冒頭で「自分がなぜITコンサルを志望しているのか」を明確に示すことで、面接官はこの先の話を理解しやすくなります。
また、長い説明から入るよりも、最初にゴールを提示することで話に筋が通り、説得力が増します。
この段階では、志望動機の要点を短く、かつ印象に残るように話すことがポイントです。
例えば、自分の軸として大切にしている価値観や、ITを活用して実現したいことなど、核となるメッセージを一言で伝えることが効果的です。
明確な結論から話を始めることで、面接官との認識をそろえ、話の流れをつくることができます。
根拠
結論を伝えた後は、その考えに至った理由を具体的に説明します。
大切なのは、一般論ではなく自分自身の経験をもとに語ることです。
ゼミ活動やアルバイト、サークルでの取り組みなど、過去の経験を通じてなぜITコンサルという職種に関心を持ったのかを丁寧に話します。
例えば、課題を発見して改善策を考えた経験や、ITを活用してチーム全体の効率を高めた経験などです。
原体験を交えることで、あなたの話にリアリティと説得力が加わります。
また、単なる成功体験ではなく、課題や苦労をどう乗り越えたかまで伝えると、成長意欲も伝わりやすくなります。
展望
最後に、自分がその企業でどのように貢献していきたいのかを語ることで、面接の印象を強く残すことができます。
企業は学生の現在のスキルだけでなく、入社後にどう成長し、活躍していけるかを見ています。
そのため、自分の強みや価値観を踏まえて、具体的なキャリアの方向性を語ることが重要です。
企業の得意領域や強みに共感し、そこに自分の想いを重ねる形で話すと効果的です。
また、短期的な目標と中長期的な目標をセットで語ることで、本気度と計画性を伝えることができます。
最後を自信を持って締めくくることで、面接官にあなたの熱意と意欲が強く印象付けられます。
【なぜITコンサルなのか】よくある質問
ITコンサルタントを目指す就活生の多くは、仕事内容やキャリアのイメージに不安や疑問を抱えています。
実際、ITコンサルという職種は具体的なイメージを持ちにくく、情報も断片的になりがちです。
ここでは、学生からよく寄せられる代表的な質問に対して、実際の働き方やキャリアの考え方を踏まえて分かりやすく解説します。
業界理解を深めることで、自信を持って面接や企業選びに臨むことができます。
残業は多いですか
ITコンサルタントの働き方はプロジェクトの進行状況によって大きく変わる場合があります。
特に納期直前や大規模な案件が重なる時期は、業務量が増える傾向にあります。
一方で、近年は業界全体で働き方改革が進み、長時間労働を前提とするような働き方は見直されつつあります。
企業によっては、残業時間の管理を徹底し、生産性を高める取り組みを進めているところも少なくありません。
また、リモートワークの普及や業務効率化ツールの導入も進んでおり、従来のイメージよりも柔軟な働き方が可能になっています。
時間の使い方に対する意識が高まっているため、成果を出すための工夫が求められる環境です。
英語や資格は必要ですか
英語や資格は必須ではありませんが、持っていると大きな強みになります。
特に英語力は、海外の最新情報にアクセスしたり、グローバルプロジェクトに携わったりする際に活用できます。
IT業界は海外とのつながりが強いため、語学力を活かせる場面も多くあります。
資格についても、入社時点で専門的なものが必要なわけではありませんが、ITパスポートや基本情報技術者試験などを取得しておくと、基礎知識の理解や学習意欲のアピールにつながります。
これらは志望度を示す材料としても有効です。
また、入社後に研修制度を通じて必要なスキルを身につける環境が整っている企業も多いので、前向きに取り組む姿勢が評価されます。
キャリアパスはどのようなものがありますか
ITコンサルタントのキャリアパスは、多様で柔軟性が高いのが特徴です。
多くの企業では、まずアナリストとして現場で経験を積み、その後コンサルタント、マネージャーとステップアップしていく流れが一般的です。
一定の経験を積んだ後は、企業内でパートナーを目指す道もあれば、事業会社の経営企画や新規事業に転職するケースもあります。
また、コンサルティングで得た課題解決力や論理的思考力は、どの業界でも通用するスキルです。
そのため、将来的に独立や起業の道を選ぶ人も珍しくありません。
まとめ
就活は準備と一貫性が鍵です。
自分の軸を定め、なぜITで、なぜコンサルで、なぜその会社かを筋道立てて語れれば評価は高まります。
本記事を参考に、企業研究と原体験の言語化、面接の型づくりを今日から始め、納得の内定に近づきましょう。