
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
【大学3年生必見】AI模擬面接ツールで面接対策しよう
就活で必ず通る「面接」。ただ面接対策ってどうやってやるのだろう、と何から始めればいいのか悩んだり、進め方がわからなかったりと、意外とハードルが高いです。
そこで、今回「いつでもどこでもAI模擬面接ツール」をご用意しました。
頻出問題から変わった問題までAIが人事目線で添削するので、すきま時間であなたの面接力をあげることができます。
メンバー登録後すぐに使用可能なため、ぜひあなたもこの「AI模擬面接ツール」を活用して選考通過率を上げましょう!
※画像の質問はイメージです。
目次[目次を全て表示する]
【面接でのガクチカ】学生時代に力を入れたこと
学生時代に力を入れたこと、いわゆるガクチカは、新卒採用の面接において非常に重要な質問とされています。
これは、応募者の価値観や物事への取り組み方を深く知るための鍵となるからです。
しかし、多くの就活生が、自己PRとの違いが曖昧であったり、そもそもどのような経験を話すべきか悩んだりするポイントでもあります。
面接官は、必ずしも華々しい実績を求めているわけではありません。
本記事では、ガクチカの基本的な定義や、自己PRとの明確な違い、そして面接官が本当に評価しているポイントについて詳しく解説していきます。
ガクチカと自己PRの違い
ガクチカとは、学生時代に力を入れたことの略称です。
面接やエントリーシートで頻繁に問われる質問の一つであり、多くの就活生が準備に悩みます。
一方で、自己PRは、ご自身の強みや長所を企業に対してアピールするものです。
この二つの最も大きな違いは、焦点の当て方にあります。
ガクチカは、ある特定の経験におけるプロセスや、困難を乗り越えた過程での思考を問われます。
それに対して自己PRは、ご自身の持つスキルや特性そのものが、入社後にいかに貢献できるかを説明するものです。
ガクチカは過去の具体的な行動事実、自己PRは未来の貢献可能性を示すものとして区別すると良いでしょう。
ガクチカはすごい実績だけではない
ガクチカのテーマを選ぶ際、多くの就活生が全国大会での優勝や長期インターンでの売上達成といった、華々しい実績が必要だと考えがちです。
しかし、面接官は必ずしも結果の大きさだけで評価しているのではありません。
むしろ重視しているのは、その実績に至るまでのプロセスです。
目標に対してどのような課題意識を持ち、それを解決するためにどう考え、実際に行動したのか、そしてその経験から何を学んだのかを知りたいと考えています。
したがって、アルバイトやサークル活動、学業といった日常生活における一見地味に思える経験でも、ご自身の思考や人柄が明確に示されていれば、それは十分に面接官の評価を得られるガクチカとなります。
【面接でのガクチカ】採用担当者の5つの意図
面接官がガクチカについて質問するのには、明確な理由が存在します。
単に学生時代の思い出話を聞きたいわけではありません。
その回答の背後にある応募者の本質的な特性や、企業との適合性を知ろうとしています。
採用担当者は、ガクチカというエピソードを通じて、応募者のさまざまな側面を評価しようと試みています。
ここでは、その主な5つの意図について、それぞれ詳しく解説していきます。
この意図を理解することで、どのような点を強調して話すべきかが見えてくるはずです。
1. モチベーションの根源はどこか
採用担当者は、応募者がどのような状況や目標に対して意欲を燃やすのか、そのモチベーションの根源を知りたいと考えています。
人が高いパフォーマンスを発揮する原動力はそれぞれ異なります。
困難な課題に直面したときに、それを乗り越えようと奮起するタイプなのか、あるいは周囲と協力することに喜びを見出すタイプなのか、その源泉を探っています。
入社後も高い意欲を持って仕事に取り組める人物かどうかを判断するために、学生時代の経験における熱意の源を確かめようとしています。
2. 人柄や価値観が自社と合うか確認
ガクチカで語られるエピソードは、応募者の人柄や大切にしている価値観が色濃く反映される部分です。
企業にはそれぞれ独自の社風や文化、行動指針があります。
採用担当者は、そのエピソードから垣間見える応募者の特性が、自社の環境やチームの雰囲気と適合するかどうかを慎重に見極めています。
どれほど優秀な能力を持っていたとしても、組織の価値観と大きく異なっていては、入社後に双方にとって不幸な結果になりかねません。
企業が求める人材像と、応募者の人柄がどの程度一致するかを確認しています。
3. 一貫性があるか確認
面接官は、ガクチカの質問を通じて、応募者の話に一貫性があるかどうかも確認しています。
多くの場合、事前に提出されたエントリーシート、いわゆるESにもガクチカは記載されています。
面接では、そのESの内容をさらに深く掘り下げる形で質問されます。
その際に、ESに書かれた内容と口頭での説明に矛盾が生じていないか、または誇張されすぎていないかを評価しています。
ご自身の経験を論理的に説明できるか、自己分析が正確になされているかという、信頼性や一貫性を確かめる意図があります。
4. 培ってきた専門性のレベルを測る
ガクチカのテーマがゼミの研究や長期インターン、あるいは特定の資格取得である場合、採用担当者はそこで培われた専門性やスキルの具体的なレベルを測ろうとしています。
応募者が学生時代をどのように過ごしたかは、その取り組みの深さからもうかがい知ることができます。
特に専門職や技術職の採用においては、その分野に関する知識や経験が、入社後に直接業務で活かせるかを評価します。
その経験から、仕事で活かせる学びをどの程度得ているのかを判断しようとしています。
5. 分かりやすく伝える能力があるか見極める
ガクチカを話す過程そのものが、応募者のコミュニケーション能力を評価する対象となります。
ご自身が経験した複雑な状況や、その時の思考、そして具体的な行動を、面接官という第三者に分かりやすく伝えられるかを見ています。
仕事においては、上司や同僚、顧客など、さまざまな関係者と意思疎通を図る場面が頻繁にあります。
自身の経験を順序立てて整理し、相手に伝わるように説明できるかという、論理的な考えに基づいた伝達能力があるかを見極めています。
【面接でのガクチカ】ESと面接の違い
エントリーシート、いわゆるESと面接では、ガクチカに求められる役割が根本的に異なります。
ESにおけるガクチカの役割は、限られた文字数の中でご自身の経験の概要を論理的に伝え、面接官に関心を持ってもらうことです。
いわば、ご自身という人物の設計図や予告編のようなものです。
一方で、面接におけるガクチカは、その設計図を基に、より具体的なエピソードやご自身の人柄を伝えるプレゼンテーションです。
ESでは書ききれなかった行動の背景にある思考や、困難に直面した時の感情、そしてそれをどう乗り越えたのかという生の情報を、対話を通じて伝える場となります。
ESの内容をただ丸暗記して話すのではなく、内容に深みと具体性を加えて説明することが重要です。
【面接でのガクチカ】テーマ選びの基準3つ
ガクチカとして面接で話すエピソードを選ぶ作業は、非常に重要です。
どのようなテーマを選ぶかによって、面接官に伝わるご自身の印象が大きく変わるからです。
単に実績の大きさを誇示するのではなく、ご自身の本質的な強みや人柄が伝わるテーマを選ぶ必要があります。
ここでは、ガクチカのエピソードを選ぶ際に意識すべき、3つの重要な基準について解説します。
これらの基準を満たすテーマを選ぶことで、より説得力のあるガクチカを構成することができるようになります。
1. 自分らしさが表せる
第一の基準は、そのエピソードがご自身の個性や人柄、価値観といった自分らしさを明確に表せるものであることです。
面接官はガクチカを通じて、応募者がどのような人物なのかを知りたいと考えています。
たとえ平凡な経験であっても、ご自身がどのような動機で行動し、何を考え、何を感じたのかが具体的に語られていれば、それは他の誰でもないご自身の物語として面接官の心に響きます。
周りの学生が選ぶような派手なテーマに流されることなく、ご自身の内面が最もよく表現できるエピソードを選ぶことが重要です。
2. 他の人にもわかりやすい
第二の基準として、その経験の背景を知らない他の人にもわかりやすく伝えられる内容であることが挙げられます。
面接官は、応募者が所属していたサークルやゼミ、アルバイト先の特有の事情や専門用語を知りません。
そのような前提知識がない相手に対しても、どのような状況で、何が課題であり、どのように行動したのかを論理的に説明できる必要があります。
これは、ご自身の経験を客観的に分析できているか、そして他者に分かりやすく伝える伝達能力があるかどうかの評価にもつながります。
3. 志望先の求める人物像をアピールできる
第三の基準は、そのエピソードを通じてアピールできる強みが、志望先の企業が求める人物像と合致していることです。
ガクチカは単なる思い出話ではなく、ご自身の能力がその企業でどのように活かせるかを示す絶好の機会です。
例えば、企業が協調性を重視しているのであれば、チームで協力して課題を乗り越えた経験が適しているでしょう。
ご自身の経験を、企業が求める能力や資質と結びつけてアピールすることで、入社後の活躍を具体的にイメージさせることが可能になります。
【面接でのガクチカ】テーマがない方向けの見つけ方
学生時代に力を入れたことと言われても、特別な経験がなくテーマが見つからないと悩む就活生は少なくありません。
しかし、面接官は必ずしも華々しい実績を求めているわけではありません。
重要なのは、ご自身の思考や行動のプロセスです。
日常のささいな出来事や、過去の経験を異なる視点から見直すことで、ご自身らしさを伝えるエピソードは必ず見つかります。
ここでは、ガクチカのテーマを発見するための具体的な8つの方法を紹介します。
1. 目標達成のために努力した経験を振り返る
ご自身がこれまでに設定した目標と、その達成に向けて努力した経験を思い出してみてください。
それは、学業の成績向上や資格の取得、あるいはサークル活動での目標など、どのようなものでも構いません。
大切なのは目標の大小ではなく、その目標に対してどのように計画を立て、どのような困難を乗り越えて努力を続けたのかという過程です。
そのプロセスの中に、ご自身の強みや人柄が示されています。
2. 失敗や困難を克服した経験を振り返る
成功体験だけでなく、失敗や困難を経験し、それを克服した過程も強力なガクチカのテーマになります。
むしろ企業は、課題に直面した際の対応力や精神的な粘り強さを高く評価します。
なぜその失敗が起きたのかを分析し、解決するためにどのような行動を起こし、最終的に状況をどう改善させたのかを整理します。
その困難を乗り越えるプロセス自体が、ご自身の課題解決能力を証明する貴重なエピソードとなります。
3. 日常生活での取り組みを振り返る
特別な活動経験がないと感じる場合は、ご自身の日常生活での取り組みに目を向けてみてください。
例えば、アルバイトでの地道な業務改善、学業での毎日の予習復習の継続、あるいは家事や健康管理といった当たり前のことです。
一見すると地味に思えることでも、ご自身なりに工夫した点や、長期間継続するために努力したことがあれば、それは立派なアピールポイントです。
継続性や真面目さといった人柄を伝えることができます。
4. 個人的な興味関心を振り返る
ご自身が個人的に興味を持って深く追求したことも、ガクチカのテーマとして有効です。
それは趣味や学習、創作活動など、どのような分野でも構いません。
重要なのは、なぜそれに興味を持ったのかという動機と、どのようにしてその関心を深めていったのかというプロセスです。
ご自身の探究心や、好きなことに対する熱意を具体的に示すことで、面接官に主体性や情熱を伝えることができます。
5. 周囲から評価された経験を振り返る
ご自身の長所や強みは、自分自身よりも周囲の人が気づいている場合があります。
過去に友人や家族、アルバイト先の先輩などから評価された経験や、感謝された出来事を振り返ってみてください。
ご自身では当たり前だと思って行動していたことが、客観的に見ると貴重な強みである可能性があります。
第三者からの評価は、ご自身の長所を裏付ける客観的な視点として、説得力のあるエピソードにつながります。
6. 企業が求める人物像から逆算する
戦略的にテーマを見つける方法として、応募先企業が求める人物像から逆算する手法もあります。
まず、企業の採用ページや説明会資料から、どのような人材が求められているかを把握します。
次に、その特性に合致するご自身の過去の小さな経験を探します。
企業が求める要素とご自身の経験を結びつけることで、志望動機に一貫性を持たせ、効果的にご自身をアピールすることが可能になります。
7. 第三者へ相談する
自己分析に行き詰まった場合は、信頼できる第三者に相談することも有効な手段です。
ご家族や友人、大学の先輩、あるいはキャリアセンターの職員など、ご自身をよく知る人に話を聞いてもらうとよいでしょう。
ご自身では気づかなかった強みや、忘れていた過去のエピソードを指摘してくれる可能性があります。
客観的な視点を取り入れることで、ご自身の新たな側面を発見し、ガクチカのテーマを見つけるきっかけになることがあります。
8. これから何かに取り組む
もし面接までにまだ時間に余裕があるのであれば、これから何かに新しく取り組むことも一つの選択肢です。
それは資格の勉強を始めることでも、新しいアルバイトやボランティア活動に参加することでも構いません。
重要なのは、目的意識を持って行動を起こすことです。
その行動力や主体性そのものが、ガクチカのエピソードとなり得ます。
過去の経験に固執せず、未来に向けて行動することも考えてみてください。
【面接でのガクチカ】NGテーマ
ガクチカのテーマ選びは、ご自身の強みをアピールする上で重要ですが、中には面接官にマイナスの印象を与えかねない、避けるべきテーマも存在します。
良かれと思って選んだエピソードが、かえって評価を下げる原因になることもあるため、慎重な判断が求められます。
ここでは、面接の場でガクチカとして話すには適していない代表的なNGテーマを5つ紹介します。
これらのポイントを理解し、ご自身の経験が該当していないかを確認してみてください。
1. 虚偽や過度に誇張されたの内容
面接でご自身を良く見せたいという気持ちは分かりますが、事実ではない虚偽の内容や、実績を過度に誇張して話すことは絶対に避けるべきです。
面接官は数多くの学生と対話してきた経験から、話の不自然な点や矛盾に気づきやすいものです。
特に、深掘り質問を重ねられるうちに嘘が露呈してしまえば、能力以前に、ご自身の人間性や誠実さへの信頼を根本から失うことになります。
等身大のご自身を誠実に伝えることが最も重要です。
2. 自己中心的な内容
その経験が、ご自身の利益や都合だけを追求した自己中心的な内容になっていないか注意が必要です。
企業は組織であり、他者と協力して共通の目標に向かう協調性や貢献意欲を重視します。
例えば、ルールを無視して個人の成果を上げた、あるいは周囲の意見を聞かずに物事を進めたといったエピソードは、チームワークを乱す可能性があると判断されます。
ご自身の行動が、結果として周囲や組織にどのような良い影響を与えたのか、という視点を持って説明することが求められます。
3. 高校以前の経験
ガクチカで問われる学生時代とは、基本的に大学生活を指します。
高校以前の経験を話すこと自体が即座に不合格になるわけではありませんが、面接官が知りたいのは、より現在の応募者に近い大学時代の取り組みや成長です。
高校時代の話は、現在の人柄との関連性が薄いと判断されたり、大学時代に何も取り組まなかったのではないかと懸念されたりする可能性があります。
特別な理由がない限り、大学入学以降の経験からテーマを選ぶのが無難です。
4. ネガティブな内容
失敗や困難を乗り越えた経験は、ご自身の課題解決能力や精神的な強さをアピールする良いテーマになり得ます。
しかし、その話が他者への不平不満や、環境への愚痴だけで終わっている場合、それはネガティブな内容と受け取られます。
面接官が知りたいのは、困難な状況をどのように分析し、そこから何を学んで次に活かしたのかというポジティブな側面です。
単なる苦労話や、他責的な姿勢が透けて見える内容は、評価を下げる原因となります。
5. 個人の成果を強調する内容
ご自身が努力して得た個人の成果をアピールすること自体は、決して悪いことではありません。
しかし、その説明が終始ご自身の能力や努力の範囲に留まり、周囲との関わりが見えない場合、協調性に欠ける人物だと評価される可能性があります。
企業での仕事は、多くの場合チームで進められます。
ご自身の成果を語る際にも、その過程で周囲とどのように連携したのか、あるいはチーム全体にどのような貢献をしたのかという視点を加えることが重要です。
【面接でのガクチカ】7段階構成のフレームワーク
面接でガクチカを伝える際は、ご自身の経験を分かりやすく、論理的に構成することが不可欠です。
どれほど素晴らしい経験であっても、話の順序が整理されていなければ、面接官にご自身の強みや人柄を正しく伝えることはできません。
ここでは、ご自身の経験の価値を最大限に引き出し、面接官に伝わりやすくするための、基本となる7段階の構成(型)について詳しく解説します。
この流れに沿ってエピソードを整理することで、誰が聞いても理解しやすい、説得力のあるガクチカが完成します。
1. 結論「何に最も力を注いだか」
まず最初に、ご自身が学生時代に最も力を注いだ活動が何であったかを、簡潔に一言で述べます。
面接官は多くの応募者と対話するため、話の要点を先に知りたいと考えています。
例えば、飲食店のアルバイトにおける接客品質の改善です、といった具体的な結論を冒頭で示すことで、面接官はこれから始まる話の全体像を即座に把握できます。
これにより、その後の説明が格段に理解しやすくなり、スムーズな対話の土台が整います。
2. 動機「なぜ取り組んだのか」
次に、なぜその活動に力を入れようと思ったのか、具体的な動機やきっかけを説明します。
面接官は、ご自身がどのような状況で主体性を発揮するのか、その人柄や価値観の源泉に関心を持っています。
例えば、サークル活動であれば、チームの課題を解決したいという問題意識から始めたのか、あるいはご自身のスキルアップのために始めたのか、その理由を明確にします。
この動機が、ご自身の行動の説得力を裏付ける重要な要素となります。
3. 目標「どんな目標を掲げたか」
その活動に取り組むにあたり、ご自身がどのような目標を掲げていたのか、あるいはどのような状態を目指していたのかを具体的に示します。
この目標設定の理由や基準を明らかにすることで、ご自身の思考の深さや基準の高さを伝えることができます。
例えば、アルバイトでの新人教育において、新人の早期離職率を半減させるという具体的な目標を設定した、といった内容です。
明確な目標を示すことで、次の課題部分がより際立ちます。
4. 課題「どのような壁があったか」
掲げた目標を達成する過程で、どのような困難や課題、いわゆる壁に直面したのかを説明します。
ここで重要なのは、課題を他責にせず、客観的に分析している姿勢を見せることです。
例えば、サークル運営において、メンバー間の意識の差が大きく、参加率が低迷していた、といった具体的な状況を説明します。
この課題が具体的であればあるほど、それを乗り越えるために行った次の行動の価値が高まります。
5. 行動「どう考え何を実行したか」
面接官が最も重視する部分の一つが、直面した課題に対して、ご自身がどのように考え、何を具体的に実行したのかという行動のプロセスです。
ここでは、ご自身の主体性や思考力を示すことが求められます。
なぜその行動を選んだのか、他にはどのような選択肢を検討したのか、その背景にある考えを明確にします。
例えば、メンバーの意識の差を埋めるために、個別のヒアリングを全員に実施した、といった具体的な行動を説明します。
6. 結果「どのような変化や成果が出たか」
ご自身の行動の結果、その課題や状況がどのように変化したのか、どのような成果につながったのかを述べます。
可能であれば、サークルの参加率が30パーセント向上した、といった定量的な数字を用いて示すと説得力が増します。
しかし、数字で示せない場合でも、チームの雰囲気が改善された、あるいは後輩から感謝された、といった定性的な変化や、ご自身が得た内面的な成長でも構いません。
行動が結果に結びついたことを示します。
7. 展望「学びと入社後の活かし方」
最後に、その経験全体を通して何を学び取ったのかを総括し、その学びを入社後にどのように活かしていきたいかという展望を述べます。
この部分は、ご自身の経験を未来の貢献へとつなげる重要な締めくくりです。
例えば、多様な意見を調整し、一つの目標に導いた経験から得た傾聴力と提案力を、貴社の営業職においても発揮したい、といった形で結びます。
これにより、企業への貢献意欲を強くアピールすることができます。
【面接でのガクチカ】話す時のポイント
素晴らしい経験を準備しても、それが面接官に伝わらなければ評価につながりません。
面接は一方的な発表の場ではなく、対話の場です。
ご自身の経験の価値を正確に、かつ魅力的に伝えるためには、いくつかの技術的なポイントを意識する必要があります。
特に、話の長さや構成、準備の仕方が重要です。
ここでは、面接本番でガクチカを話す際に押さえておきたい、3つの具体的なポイントについて詳しく解説していきます。
1. 回答時間は1分程度
面接官から特に時間の指定がない場合、ガクチカの最初の説明は1分程度にまとめるのが理想的です。
面接官は多くの質問を通じて、限られた時間で応募者の全体像を把握したいと考えています。
話が冗長になりすぎると、要点をまとめる能力が低いと判断される可能性があります。
先に解説した7段階のフレームワークを活用し、伝えたい核心部分を1分程度で簡潔に説明できるよう、事前に練習しておくことが重要です。
詳細はその後の深掘り質問で補足していく意識を持ちましょう。
2. PREP法を用いる
1分間の最初の説明(7段階構成)が終わった後、面接官からは多くの深掘り質問がされます。
その短い質問に対して回答する際に、PREP法と呼ばれる構成を用いると非常に効果的です。
PREP法とは、Point(結論)、Reason(理由)、Example(具体例)、Point(結論の再強調)の頭文字を取ったものです。
面接官の質問の意図に対して、まず結論から簡潔に答えることで、論理的かつ明確な回答が可能になります。
7段階構成とこのPREP法を、場面に応じて使い分けることが重要です。
3. 丸暗記は控える
準備したガクチカを、一言一句そのまま丸暗記して本番に臨むことは推奨されません。
丸暗記した文章を読み上げるような話し方では、ご自身の熱意や人柄が伝わりにくくなります。
また、途中で言葉に詰まると頭が真っ白になり、会話が不自然になる危険性もあります。
面接は対話の場です。
7段階構成の各ステップで伝えたい要点、いわゆるキーワードだけを覚えておき、当日は面接官の反応を見ながらご自身の言葉で柔軟に話すことを心がけてください。
【面接でのガクチカ】頻出深掘り質問8個
ガクチカの最初の説明を終えると、面接官からはその内容に対してさらに踏mこんだ質問、いわゆる深掘り質問がされます。
この深掘りこそがガクチカ面接の本質であり、応募者の思考の深さや人柄、経験の解像度を確かめるための重要なプロセスです。
面接官は、応募者がご自身の経験をどれだけ客観的に分析し、そこから何を学んだのかを知ろうとしています。
ここでは、ガクチカの面接で頻繁に問われる8個の代表的な深掘り質問と、その背景にある意図について解説します。
ガクチカについての深掘り質問をもっと対策したい方はこちらの記事をご覧ください。
1. その取り組みをなぜ始めようと思ったのか、理由を教えてください
この質問は、ガクチカの7段階構成で説明した動機部分を、さらに具体的に確認するためのものです。
面接官は、ご自身がどのような状況で主体性を発揮するのか、その価値観やモチベーションの源泉に強い関心を持っています。
単に周りに流されたのではなく、ご自身の意思としてなぜそれを選んだのか、その背景にある問題意識や好奇心を明確に伝えることが重要です。
ご自身の内面的な動機を具体的に説明することで、行動の説得力が高まります。
2. あなたが取り組んだ活動の魅力を知らない人にも伝わるように説明してください
この質問の意図は、ご自身の専門分野や所属していたコミュニティ特有の事柄を、前提知識のない相手にどれだけ分かりやすく伝えられるか、いわゆる説明能力を測ることにあります。
ここでは、専門用語や内部の常識を避け、その活動の本質的な面白さや社会的な意義などを、客観的な視点で簡潔に説明する能力が求められます。
ご自身の経験を論理的に整理し、相手の視点に立って伝える力が試されています。
3. その活動で掲げた目標となぜその目標を設定したのか理由を教えてください
面接官は、ご自身がどの程度の基準で物事に取り組む人物なのかを知るために、目標設定の背景を尋ねます。
単に目標を達成した事実だけでなく、なぜその目標を掲げたのか、その基準の高さや計画性を重視しています。
例えば、過去の基準を踏襲したのか、あるいはご自身でより高い目標を設定したのか、その思考プロセスを説明することが求められます。
ご自身の主体的な意思決定の基準を示すことが重要です。
4. 活動を進める上であなたが直面した最大の困難は何でしたか
この質問は、ご自身がどのような状況を困難と感じるのか、そしてそのプレッシャーにどう向き合うのかというストレス耐性や課題の捉え方を知るためのものです。
ここでは、困難な状況を他責にせず、ご自身の課題としてどう受け止めたのかを述べることが重要です。
単に事実を羅列するのではなく、その時に感じた率直な思いや、それを乗り越えようとした姿勢を示すことで、ご自身の精神的な粘り強さや人柄を伝えることができます。
5. 取り組みの中で課題を発見したきっかけや背景について教えてください
この質問は、ご自身の問題意識の高さや、当事者意識を持って物事に取り組む姿勢を確認するために行われます。
誰かから指示された課題ではなく、ご自身で状況を分析し、主体的に問題点を発見した経験は高く評価されます。
現状維持に満足せず、常により良い状態を目指してアンテナを張っていたことを示すエピソードが求められます。
課題に気づいた具体的なきっかけや背景を説明することで、ご自身の視座の高さが伝わります。
6. どのように乗り越え最終的にどのような結果になったか教えてください
この質問は、直面した困難や発見した課題に対して、ご自身が具体的にどのような行動を起こしたのか、そのプロセスと結果の因果関係を明確にするためのものです。
面接官は、精神論ではなく、論理的な思考に基づいた具体的な解決策に関心を持っています。
なぜその行動を選んだのか、他に選択肢はなかったのか、そしてその行動が最終的にどのような成果につながったのかを、順序立てて説明することが求められます。
7. 経験を通して反省点や当時に戻れるとしたら改善したい点を教えてください
この質問の意図は、ご自身の経験を客観的に振り返り、冷静に分析できているかを確認することにあります。
成功体験であっても、必ず何かしらの反省点や改善の余地は存在するはずです。
面接官は、完璧な成功談よりも、失敗を認め、次に活かそうとする謙虚さや改善意欲を評価します。
他責にすることなく、ご自身の判断や行動の何が足りなかったのか、そして今ならどう改善するかという未来志向の視点で答えることが重要です。
8. 取り組みから得た学びとそれを入社後にどのように活かすか教えてください
これは、ガクチカの総括として最も重要な質問の一つです。
面接官は、ご自身が具体的な経験をどれだけ汎用性のある学びとして抽象化できているか、そしてそれを社会人としてどう活かそうとしているかを知りたいと考えています。
その経験から得た学びが、応募先企業の業務内容や求める人物像とどのように結びつくのかを具体的に示す必要があります。
ご自身の入社後の活躍イメージを面接官に持たせることができるかどうかが問われています。
【面接でのガクチカ】深掘りは3系統しかない
先ほどの8個の質問例をはじめ、面接で想定される深掘り質問は無数にあるように思え、不安になるかもしれません。
しかし、どのような角度から問われたとしても、面接官が知りたい本質は、突き詰めるとたった3つの系統に分類することができます。
この3つの型を理解しておけば、知らない質問が来たとしても、その意図を瞬時に見抜き、落ち着いて対応することが可能になります。
ここでは、その3つの系統について、それぞれ詳しく解説します。
1. 動機
第一の系統は、ご自身の行動の源泉である動機に関する質問です。
これには、なぜその活動を始めようと思ったのか、なぜその目標を設定したのか、といったご自身の価値観や物事の捉え方を問うものが含まれます。
面接官は、ご自身がどのような状況で主体性を発揮し、何に情熱を感じる人物なのか、その根源的な部分を知ろうとしています。
ご自身の内面的な動機を明確にすることで、行動全体の一貫性と説得力が高まります。
2. プロセス
第二の系統は、目標達成や課題解決に至るまでの具体的なプロセス、すなわち過程に関する質問です。
これには、最大の困難は何か、どのように課題を発見したか、どう乗り越えたのか、といったご自身の思考力や行動力を問うものが該当します。
面接官は、ご自身が困難な状況に直面した際、それをどのように分析し、論理的に考え、具体的な行動に移したのかという、再現性のある問題解決能力を知りたいと考えています。
3. 学び
第三の系統は、その経験全体を通した学びや、それを未来にどう活かすかという、いわゆる展望に関する質問です。
反省点は何か、その経験から何を得たのか、入社後にどう活かすか、といったご自身の内省力や成長意欲を問うものが含まれます。
面接官は、過去の経験を単なる思い出で終わらせず、そこから教訓を引き出し、次の行動に活かせる人物かどうかを評価しています。
この部分で、ご自身の成長可能性を強くアピールできます。
【面接でのガクチカ】答えにくい意地悪な深掘りへの最強の切り返し方
面接官からの深掘り質問の中には、あえて圧力をかけたり、ご自身の弱点や失敗を厳しく指摘したりするような、答えにくい質問が含まれることがあります。
これらの質問の多くは、応募者のストレス耐性や、予期せぬ事態への対応力を確かめる明確な意図があります。
ここで動揺したり、感情的になったりすることは評価を下げてしまいます。
最強の切り返し方とは、まず指摘された事実やご自身の至らなかった点を、一度冷静かつ謙虚に受け止める姿勢を見せることです。
その上で、単に謝罪や言い訳に終始するのではなく、なぜその事態が起きたのかを客観的に分析し、そこから何を学び、現在はどのように改善しているのかを論理的に説明することです。
この一連の対応が、ご自身の課題解決能力や誠実さ、そして打たれ強さと成長意欲を証明する絶好の機会となります。
【面接でのガクチカ】テーマ別例文
ここでは、ガクチカの具体的なテーマ別例文を紹介します。
多くの学生が経験するアルバイトやサークル活動といった、一見すると平凡に思えるテーマであっても、伝え方次第で面接官から高く評価されます。
重要なのは実績の大きさではなく、ご自身が課題に対してどのように向き合い、どう考えて行動したのかというプロセスです。
ここでは、評価されるOK例文と、評価されにくいNG例文を比較しながら、その明確な違いと改善ポイントを詳しく解説していきます。
例文1. 飲食店アルバイト
私が学生時代に力を入れたことは、飲食店のホールバイトにおけるクレーム削減です。 お客様からのご指摘が多い状況を改善したいと思い、クレーム件数の半減を目標にしました。 課題はスタッフ間の情報共有不足だと考え、ホールとキッチンの連携確認フローを新たに導入することを提案し、実行しました。 その結果、クレーム件数は前月比で三割減少し、お客様からの評価も改善しました。 この経験から学んだ、主体的に課題を発見し周囲を巻き込む力を、貴社の業務においても活かしたいと考えています。
私が学生時代に力を入れたことは、飲食店のホールアルバイトです。 大学入学時から三年間、同じお店で継続して勤務しました。 主な業務は、お客様のご案内、注文の受付、料理の配膳、そしてレジ業務です。 最初は仕事に慣れず大変でしたが、諦めずに努力した結果、時給も上がり、新人スタッフの指導も任されるようになりました。 この経験を通して、ビジネスマナーや継続することの大切さ、そして忍耐力を身につけることができました。
NG例文は単なる業務報告であり、ご自身の主体的なプロセスが見えません。
OK例文は、7段階の構成(結論・動機・目標・課題・行動・結果・展望)が明確に含まれています。
NG例文を改善するには、新人指導を任された際の具体的な課題や、ご自身の工夫、そしてその学びを入社後にどう活かすのかという視点を加えることが不可欠です。
例文2. 塾講師アルバイト
私が学生時代に力を入れたことは、塾講師のアルバイトで担当生徒の苦手科目を克服させたことです。 当初、生徒が勉強自体に苦手意識を持つ状況を改善したいと考えました。 そこで、生徒の定期試験の点数を平均点以上にすることを目標に定めました。 課題は、生徒の理解度を把握せず一方的に指導していたことでした。 私は生徒専用の学習計画を作成し、小テストで理解度を可視化、間違えた箇所は根本まで遡って教え方を変えました。 結果、生徒は平均点を15点上回り、勉強への意欲も向上しました。 この経験で得た、相手の課題を分析し解決に導く力を、貴社の業務でも活かしたいと考えています。
私が学生時代に頑張ったことは、塾講師のアルバイトです。 2年間、中学生を対象に数学を教えていました。 生徒の成績が上がるように、カリキュラムに沿って熱心に指導しました。 授業の準備は大変でしたが、生徒から分かったと言われることにやりがいを感じていました。 このアルバイトを通じて、人に教えることの難しさや、責任感を持って物事に取り組む姿勢を学びました。
NG例文は、業務内容と抽象的な感想に留まっており、ご自身がどのように工夫したのかが見えません。
OK例文は、7段階の構成に沿って、生徒の成績を上げるための具体的な課題分析と行動プロセスが明確です。
NG例文を改善するには、例えば熱心に指導とは具体的に何をしたのか、生徒の成績が上がらないという課題に対してどのような工夫(例えば、授業の進め方の変更)をしたのか、その主体的な行動を加えることが不可欠です。
例文3. サークル活動(役職なし)
私が学生時代に力を入れたことは、テニスサークルにおいて役職のない一般メンバーとして、新入生の定着率向上に貢献したことです。 私自身が入部時に馴染めず苦労した経験から、同様の理由で辞める後輩を減らしたいと思いました。 そこで、新入生の定着率を前年の5割から8割に引き上げることを目標にしました。 課題は新入生同士や先輩との交流機会が不足していることだと考えました。 私は同期や先輩に働きかけ、新入生と先輩がペアになるメンター制度の導入を提案し、自らも率先して交流の企画・運営を行いました。 結果、新入生が縦横の繋がりを持つ機会が増え、定着率も目標の8割を達成できました。 この経験で培った、立場に関わらず主体的に課題を見つけ周囲を巻き込む力を、貴社の業務でも活かしたいです。
私が学生時代に力を入れたことは、テニスサークルでの活動です。 役職には就いていませんでしたが、週3回の練習には真面目に参加し、皆勤賞をもらいました。 活動を通じて、体力もつきましたし、多くの友人を作ることができました。 先輩や後輩とも良好な関係を築き、イベントの準備なども手伝いました。 このサークル活動を通して、継続することの大切さや、チームで活動するための協調性を学ぶことができたと考えています。
NG例文は、真面目に参加した、手伝ったという受動的な活動報告に留まっています。
役職がない場合、この受け身の姿勢が特にマイナスに映りがちです。
OK例文は、7段階の構成に沿って、役職がない立場でも自ら課題を見つけて行動したという明確な主体性を示せています。
NG例文を改善するには、役職がない立場だからこそ、チームのためにどのような主体的な工夫(例えば、練習方法の改善提案、後輩への積極的な声かけなど)を発揮したのか、その具体的な行動と学びを加えることが不可欠です。
例文4. サークル活動(イベント運営)
私が学生時代に力を入れたことは、サークルのイベント運営リーダーとして、参加率の向上を実現したことです。 従来の参加率が5割程度と低い状況を改善し、より多くの仲間と交流を深めたいと考えました。 そこで、次回のイベント参加率を8割に引き上げることを目標に設定しました。 課題は、告知が一方的でイベントの魅力が伝わっていなかった点だと分析しました。 私は告知方法をSNSでの一斉送信から、魅力を伝えるポスター作成と個別の声がけに変更し、参加者のニーズもヒアリングしました。 結果、参加率は目標の8割を達成し、イベントも非常に盛況となりました。 この経験で培った、相手のニーズを汲み取り主体的に企画実行する力を、貴社の業務でも活かしたいです。
私が学生時代に力を入れたことは、サークルのイベント運営です。 リーダーとして、半年前から会場の手配や予算管理、当日の司会進行などを担当しました。 メンバー間の意見調整が非常に大変でしたが、当日は大きなトラブルもなく無事に終えることができました。 イベントが成功し、皆が楽しんでくれて本当に良かったです。 この経験を通じて、計画性を持って物事を進めることの大切さや、チームで協力することの重要性を学びました。
NG例文は、大変だった、良かったという感想が中心で、ご自身が直面した課題や、それをどう解決したのかという具体的な行動が見えません。
OK例文は、7段階の構成に沿って参加率の低さという明確な課題に対し告知方法の変更という具体的な行動プロセスが示されています。
NG例文を改善するには、メンバー間の意見調整が具体的にどう大変だったのか、その対立を解消するためにご自身がリーダーとしてどのような主体的な工夫をしたのか、その行動と学びを加えることが不可欠です。
例文5. ゼミでの研究
私が学生時代に力を入れたことは、ゼミの研究における文献調査です。 研究テーマに関する日本語の先行研究がなく、海外論文の分析が必要な状況でした。 私は、教授と相談し、海外論文50本の精読を目標に定めました。 課題は専門用語の翻訳と情報整理でした。 そこで、毎日2本読む計画を立て、用語リストを作成しながらデータベース化を進めました。 結果、計52本を分析して論文を完成させ、教授からも網羅性を評価されました。 この経験で培った、地道な情報収集力と計画実行力を、貴社の業務でも活かしたいと考えています。
私が学生時代に力を入れたことは、ゼミの研究です。 研究室に毎日通い、コツコツと実験を続けました。 テーマが難しく、なかなか良いデータが出ずに大変でしたが、諦めずに努力しました。 教授や先輩の助けも借りながら、最終的には卒業論文を提出することができました。 この経験を通じて、忍耐力や継続力が身についたと思います。
NG例文は、研究が大変だったという感想に留まり、ご自身が具体的に何をしたのかが見えません。
OK例文は、7段階の構成に沿って先行研究がないという課題に対し計画的な読解とデータベース化という主体的な行動が明確です。
NG例文を改善するには、良いデータが出ないという課題に対し、ご自身がどのように仮説を立て直し、実験方法を具体的にどう工夫したのか、その試行錯誤のプロセスを加えることが不可欠です。
例文6. 資格取得勉強
私が学生時代に力を入れたことは、日商簿記2級の資格取得に向けた勉強です。 自身の専門知識を体系的に学びたいという動機から、半年後の試験で90点以上での合格を目標に設定しました。 課題はアルバイトと両立しながらの学習時間の確保でした。 そこで、毎日3時間の学習時間を捻出する計画を立て、朝と通学時間を活用し、間違えた問題は全てノートにまとめ反復学習を徹底しました。 結果、92点で無事合格でき、目標を達成しました。 この経験で培った計画実行力と継続力を、貴社の業務でも活かしたいと考えています。
私が学生時代に力を入れたことは、資格取得の勉強です。 日商簿記2級の資格を取ろうと思い、独学で勉強しました。 専門用語が多く、理解するのが非常に大変でしたが、諦めずに毎日コツコツと勉強を続けました。 その結果、試験にも無事合格することができました。 この経験から、目標に向かって努力し続けることの大切さを学びました。
NG例文は、「大変だった」「合格できた」という事実と感想が中心で、どのように学習を進めたのかというプロセスがありません。
OK例文は、7段階の構成に沿って「学習時間の確保」という明確な課題に対し「具体的な計画と実行」という主体的な行動が示されています。
NG例文を改善するには、なぜその資格を選んだのか(動機)、学習を進める上で直面した具体的な課題(例:モチベーション維持)、それをどう工夫して乗り越えたのかを加えることが不可欠です。
例文7. 長期インターン(マーケティング)
私が学生時代に力を入れたことは、長期インターン先でのSNS経由のウェブサイト流入数を増加させたことです。 当初、担当メディアの流入数が伸び悩んでおり、その状況を改善したいと考えました。 そこで、3ヶ月でSNS経由のセッション数を2倍にすることを目標に定めました。 課題は、発信内容がフォロワー層のニーズと一致していないことだと分析しました。 私はインサイトデータを分析してペルソナを再設定し、A/Bテストを繰り返して投稿内容と時間を最適化しました。 結果、セッション数は3ヶ月で2.1倍を達成し、売上にも貢献できました。 この経験で培ったデータ分析力と仮説検証能力を、貴社の業務でも活かしたいです。
私が学生時代に力を入れたことは、マーケティング会社での長期インターンです。 半年間、社員の方の指導のもと、SNSの投稿作成やデータ集計、リサーチ業務などを担当しました。 実際のビジネスの現場は厳しく大変でしたが、とても勉強になりました。 この経験で、ビジネスマナーやマーケティングの基礎知識が身についたと思います。
NG例文は、インターンで担当した業務内容を並べただけで、ご自身がどのように考え行動したかという主体性が見えません。
OK例文は、7段階の構成に沿って流入数という明確な課題に対し、A/Bテストといった具体的な行動プロセスが示されています。
NG例文を改善するには、マーケティングインターンという環境で、ご自身がどのような仮説を立て、それをどう検証し、成果に結びつけたのか、その主体的な思考プロセスを加えることが不可欠です。
例文8. 長期インターン(営業)
私が学生時代に力を入れたことは、営業の長期インターンにおける成約率の向上です。 当初は成約率が低く、チームに貢献できていない状況を改善したいと考えました。 そこで、チーム平均である成約率15パーセントの達成を目標に定めました。 課題は、マニュアル通りの提案に終始し、お客様の潜在的なニーズに応えられていないことでした。 私は、一方的に話すことをやめ、まずお客様の課題を徹底的にヒアリングする対話形式に切り替え、提案内容を個別に最適化しました。 結果、成約率18パーセントを達成し、目標を超えることができました。 この経験で培った傾聴力と課題解決のための提案力を、貴社の営業職でも活かしたいです。
私が学生時代に力を入れたことは、営業の長期インターンです。 社員の方に同行して商談を学んだり、テレアポ業務や資料作成の手伝いをしたりしました。 最初は緊張してうまく話せませんでしたが、社員の方のサポートのおかげで、徐々に慣れることができました。 この経験を通じて、営業という仕事の大変さや、ビジネスマナーを学ぶことができました。
NG例文は、インターンで経験した業務内容の紹介に留まり、ご自身が主体的に取り組んだ成果が見えません。
OK例文は、7段階の構成に沿って成約率という明確な課題に対し、提案方法の変更という具体的な行動プロセスと成果が示されています。
NG例文を改善するには、営業インターンという環境で、ご自身がどのような目標を掲げ、その達成のために主体的に工夫したのか(例:テレアポのトーク改善)を加えることが不可欠です。
例文9. 読書習慣
私が学生時代に力を入れたことは、毎朝1時間の読書習慣を定着させたことです。 当初、知識不足からゼミの議論に参加できない悔しさを感じ、インプットの必要性を痛感しました。 そこで、半年間で100冊読了することを目標に定めました。 課題は、朝が弱く三日坊主になってしまう自己管理の甘さでした。 私は、まず15分から始める、前夜に読む本を決めておく、SNSで進捗を報告するという3つのルールを設け、学習を可視化しました。 結果、半年間で102冊を読了し、ゼミでも主体的に発言できるようになりました。 この経験で培った自己管理能力と継続力を、貴社の業務でも活かしたいと考えています。
私が学生時代に力を入れたことは、毎朝の早起きです。 もともと朝が弱かったのですが、大学生活を充実させたいと思い、早起きに挑戦しました。 最初は大変でしたが、徐々に慣れていき、最終的には毎朝6時に起きることができるようになりました。 この経験を通じて、自分を律することの大切さや、継続することの難しさを学びました。
NG例文は、「早起きできた」という事実報告に留まり、そのプロセスや目的が不明確です。
OK例文は、7段階の構成に沿って「知識不足の解消」という明確な動機と、習慣化のための具体的な工夫(行動)が示されています。
NG例文を改善するには、なぜ早起きが必要だったのか(目的)、早起きを継続するために直面した具体的な課題(例:二度寝)と、それを乗り越えるためにご自身がどう工夫したのかを加えることが不可欠です。
例文10. ボランティア活動
私が学生時代に力を入れたことは、地域の子ども食堂における運営改善です。 当初、食材の寄付が不安定でメニューが固定化している状況を改善したいと考えました。 私は、安定的な食材確保と地域住民の認知度向上を目標に定めました。 課題は、広報活動が既存の繋がりに依存していることだと考えました。 そこで私は、近隣の商店街や農家へ直接訪問して協力をお願いする広報チームを立ち上げ、SNSでの情報発信も担当しました。 結果、寄付先が新たに10件増加し食材が安定、子どもたちからもメニューが豊富になったと喜ばれました。 この経験で培った、課題特定力と周囲を巻き込む実行力を、貴社の業務でも活かしたいです。
私が学生時代に力を入れたことは、子ども食堂でのボランティア活動です。 大学2年生の時から1年間、週に1回参加し、子どもたちへの食事の提供や学習支援を行いました。 最初は緊張しましたが、子どもたちの笑顔を見ることにやりがいを感じました。 この活動を通じて、社会貢献の大切さや、人との繋がりの温かさを学ぶことができました。
NG例文は、「参加した事実」と「やりがいを感じた」という抽象的な感想に留まっており、ご自身が主体的に取り組んだプロセスが見えません。
OK例文は、7段階の構成に沿って「食材の不安定さ」という明確な課題に対し、「広報チームの立ち上げ」という具体的な行動プロセスと成果が示されています。
NG例文を改善するには、ボランティア活動の中で直面した具体的な課題(例:子どもが心を開いてくれない、運営が非効率だった)に対し、ご自身がどのように考え、主体的に工夫したのかを加えることが不可欠です。
【面接でのガクチカ】まとめ
本記事では、面接におけるガクチカの基本的な定義から、ESとの違い、具体的な7段階の構成、そして頻出する深掘り質問への対策まで、網羅的に解説してきました。
ガクチカに求められるのは、必ずしも華々しい実績ではありません。
ご自身が経験したことに対して、どのような課題意識を持ち、どう考え行動したのか、その主体的なプロセスを論理的に伝えることが最も重要です。
この記事で紹介したフレームワークや例文を参考に、ご自身の経験を整理し、自信を持って面接本番に臨んでください。

_720x550.webp)
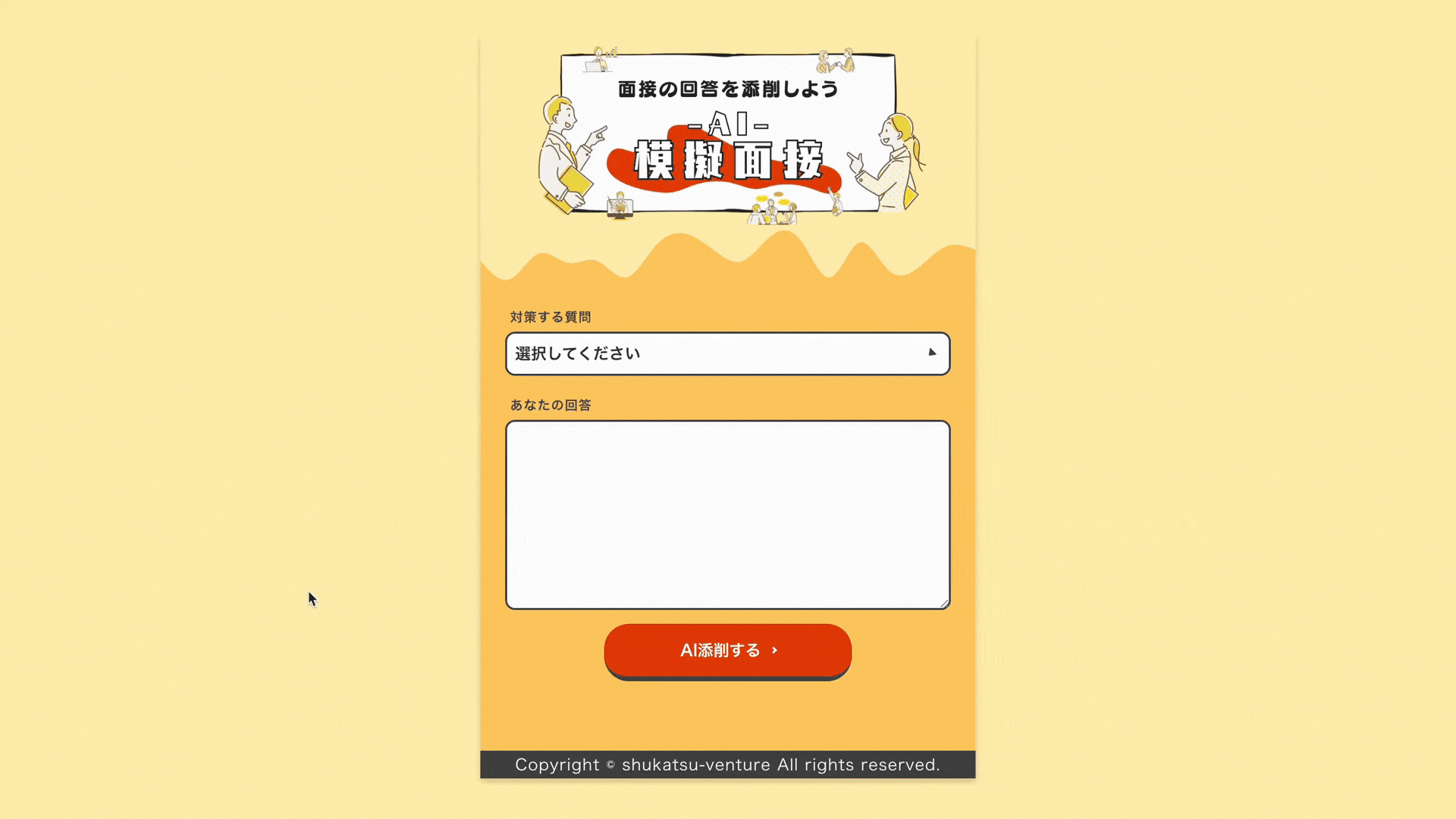





_720x550.webp)




_720x550.webp)



_720x550.webp)






伊東美奈
(Digmedia監修者/キャリアアドバイザー)
伊東美奈
(Digmedia監修者)
自己PRと強みの違い
ガクチカと自己PRの違いを理解する上で、自己PRと強みの違いについても明確にしておくことが重要です。
強みとは、ご自身が持つ長所や優れた能力そのものを指します。
例えば、継続力がある、分析力が高い、といった要素がこれに該当します。
一方で自己PRとは、それらの強みの中から、応募先企業が求める人物像に合致するものを選択し、具体的なエピソードを用いて論理的にアピールする行為、またはその内容全体を指します。
つまり、強みは自己PRを構成するための材料であり、自己PRは強みを効果的に伝えるためのプレゼンテーションと言えます。
自身の強みを正しく認識し、それを自己PRとして昇華させることが求められます。