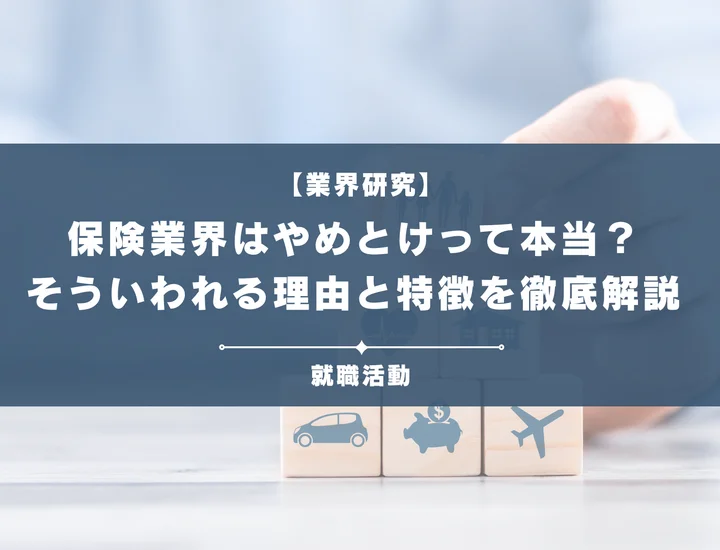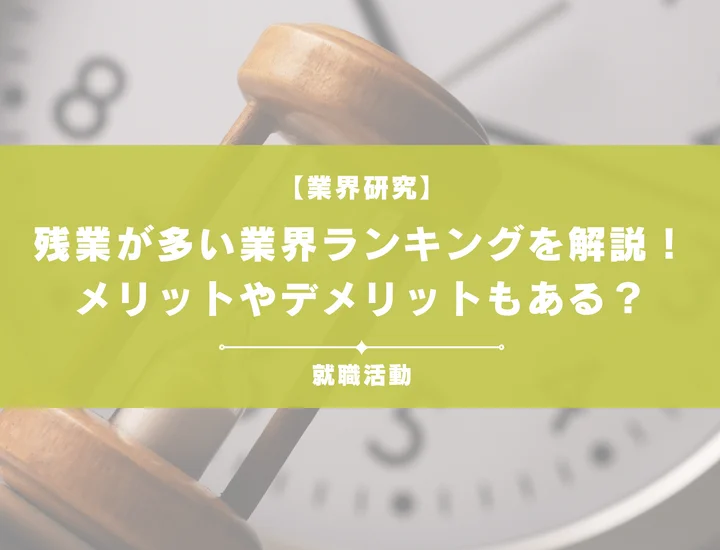HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
就職活動を進める中で、「保険業界はやめとけ」という言葉を耳にしたことはありませんか?安定しているイメージがある一方で、ネガティブな評判も多く、実態がわからずに不安を感じている就活生も多いと思います。
この記事では、なぜ保険業界がそのように言われるのか、その理由と実際の仕事内容、そしてこの業界で輝ける人の特徴まで、元アドバイザーの視点から詳しく解説していきます。
目次[目次を全て表示する]
【保険業界やめとけ】やめとけと言われるのは本当?
「保険業界はやめとけ」という言葉、気になりますよね。
これは、一部の側面だけが切り取られて広まっている可能性がありますが、完全に事実無根というわけでもありません。
特に営業職では、成果が求められる厳しさや、時には知人にも営業する必要があるといった話が、「きつい」というイメージにつながっています。
しかし、保険は人々の生活を守る重要な社会インフラであり、大きなやりがいを感じられる仕事でもあります。
大切なのは、ネガティブな情報だけに惑わされず、業界の構造や多様な職種を正しく理解することです。
【保険業界やめとけ】保険業界の仕事内容
保険業界と聞くと、多くの人が「営業」の仕事を思い浮かべるかもしれませんね。
確かに営業は花形の仕事の一つですが、保険という仕組みを支えるためには、実に多様な業務が存在します。
保険は、万が一の事態に備えて多くの人がお金(保険料)を出し合い、困った人が出たときにそのお金(保険金)で支える「相互扶助」の精神で成り立っています。
この仕組みを円滑に動かすため、新しい保険商品を生み出す「企画・開発」、集めた保険料を安全かつ効率的に増やす「資産運用」、そして保険金を正しく迅速に支払う「支払い査定」など、専門性の高いさまざまな仕事が連携しています。
営業職以外にも、あなたの強みを活かせるフィールドが広がっているかもしれないのです。
この記事では、保険業界の具体的な仕事内容を、大きく4つのカテゴリーに分けて詳しく見ていきましょう。
業界の全体像を掴むことで、自分がどこに興味を持てるかが見えてくるはずです。
生命保険と損害保険の基本的な違い
まず押さえておきたいのが、保険業界が大きく「生命保険(生保)」と「損害保険(損保)」に分かれている点です。
生命保険は、人の生死に関わるリスクに備えるもので、例えば死亡保険、医療保険、がん保険、個人年金保険などがあります。
契約期間が数十年にわたることも多く、個人のライフプランに深く寄り添うのが特徴です。
一方、損害保険は、モノや財産に関わる偶然の事故による損害に備えるものです。
自動車保険、火災保険、地震保険、旅行保険などがこれにあたります。
こちらは契約期間が1年更新など比較的短く、企業活動や日常生活のリスクを幅広くカバーします。
就職活動では、自分が「人の人生」と「モノや財産の守り」のどちらにより強い関心があるかを考えることが、最初のステップになります。
保険商品の企画・開発
保険会社は、社会の変化や人々の新しいニーズに応えるために、常に新しい保険商品を開発しています。
これが「商品開発」部門の仕事です。
例えば、近年の健康志向の高まりを受けて「歩いた歩数に応じて保険料が安くなる健康増進型保険」が生まれたり、IT技術の進展で「スマートフォンの画面割れを補償する保険」が登場したりしています。
この仕事では、世の中のトレンドや潜在的なリスクを敏感に察知するアンテナが必要です。
また、新しい商品が保険の仕組みとして成り立つか、保険料はいくらに設定すべきかを計算する「アクチュアリー」という数理の専門家とも連携します。
自分のアイデアが形になり、世の中の役に立つという大きなやりがいを感じられる仕事です。
営業(リテール・法人)
保険業界のイメージを形作っているのが「営業」です。
営業も、対象によって大きく二つに分かれます。
一つは「リテール営業(個人営業)」で、一般の個人や家庭に対して保険を提案します。
いわゆる「生保レディ」や「ライフプランナー」と呼ばれる人たちがこれにあたり、お客様の将来設計や不安を聞き出し、最適な保険プランを設計します。
もう一つは「法人営業」で、企業が抱えるさまざまなリスク(例えば、工場の火災リスクや従業員の退職金準備など)に対して、保険でどう備えるかを提案します。
どちらもお客様との信頼関係を築くことが何よりも重要です。
特に個人営業は成果(契約件数)が厳しく問われることも多く、「きつい」と言われる理由の一つですが、お客様から「あなたのおかげで助かった」と直接感謝される機会が最も多い仕事でもあります。
資産運用(アセットマネジメント)
保険会社は、お客様から預かった膨大な保険料を、将来の保険金支払いに備えて安全かつ効率的に運用しています。
これが「資産運用」部門の仕事です。
保険会社は、国内有数の「機関投資家」であり、株式や債券、不動産など、国内外のさまざまな対象に投資を行っています。
この部門では、経済や金融市場の動向を深く分析し、長期的な視点で安定したリターンを目指すことが求められます。
金融の専門知識が必須であり、まさにプロフェッショナルの世界です。
私たちが支払う保険料が安易に減らないよう、「守り」と「攻め」のバランスを取りながら運用するという、社会的な責任が非常に重い仕事と言えるでしょう。
【保険業界やめとけ】保険業界の主な職種
保険業界の仕事内容が多岐にわたることが見えてきたところで、次に具体的な「職種」に焦点を当ててみましょう。
業界研究を進めると、「営業」以外にも「アンダーライター」や「アクチュアリー」といった、あまり聞き馴染みのない専門職の名前が出てくるはずです。
これらの職種が、保険という仕組みを根底から支えています。
例えば、営業担当者がお客様から契約の申し込みをいただいても、そのリスクが適正かどうかを判断する専門家がいなければ、保険は成り立ちません。
また、そもそも保険料がいくらであるべきかを決める数理のプロも必要です。
保険業界は、こうした多様な専門家たちの連携プレーで動いています。
ここでは、保険業界を代表する5つの職種を紹介します。
それぞれの役割と求められるスキルを理解することで、自分がどの分野で力を発揮できそうか、より具体的にイメージできるでしょう。
営業(ライフプランナー・代理店営業)
保険業界の最前線に立つのが営業職です。
生命保険会社では、お客様一人ひとりの人生設計(ライフプラン)に寄り添うことから「ライフプランナー」と呼ばれることもあります。
お客様の家族構成や将来の夢、不安などを丁寧にヒアリングし、必要な保障を提案します。
一方、損害保険会社では、保険代理店(保険を専門に扱う販売店)に対して自社の商品を提案し、販売をサポートする「代理店営業(ホールセール)」が中心となることが多いです。
高いコミュニケーション能力と信頼関係構築力が求められます。
成果が数字として表れやすいためプレッシャーもありますが、お客様や代理店から直接感謝されるやりがいも大きい職種です。
アンダーライター(保険引受)
「アンダーライター」は、保険の「引受(アンダーライティング)」を専門に行う職種です。
営業担当者がお客様から預かってきた保険契約の申し込みに対し、そのリスクがどの程度あるかを医学的な知見や過去のデータに基づいて審査・判断します。
例えば、健康状態に不安がある方でも、条件付きで契約を引き受けられるか、あるいは残念ながらお断りせざるを得ないかを決定します。
保険会社全体の収益性(リスク管理)を左右する非常に重要な役割です。
公平かつ客観的な判断力が求められ、医務的な知識や専門知識を常に学び続ける必要があります。
健全な保険制度を守る「最後の砦」とも言える仕事です。
アクチュアリー(保険数理人)
「アクチュアリー」は、保険業界における最高峰の専門職の一つと言われます。
数学や統計学、確率論といった高度な数理的手法を用いて、保険商品の開発や保険料の算定、会社の決算(保険金支払いに備えた準備金の計算)などを行います。
将来のリスクを予測し、それを「数字」に落とし込む仕事です。
例えば、「この保険商品は、将来どれくらいの保険金支払いが発生しそうか? だから保険料はいくらにすべきか?」を計算します。
資格取得の難易度は非常に高いですが、その分、保険会社の経営戦略における中核を担う存在として重宝されます。
論理的思考力と数字に対する強さが不可欠です。
損害サービス(アジャスター)
「損害サービス」部門は、保険事故が発生した際に、その対応を行う仕事です。
特に損害保険会社において重要な役割を担います。
例えば、自動車事故が起きた際、お客様からの連絡を受け付け、事故状況の確認、修理工場の手配、そして保険金の算定と支払いまでを迅速かつ公正に行います。
この部門で活躍する専門職が「アジャスター(損害調査員)」です。
事故に遭って不安なお客様に寄り添い、精神的な支えとなる役割も担います。
時には示談交渉など難しい場面もありますが、保険の真価が問われる瞬間であり、「人の役に立ちたい」という想いを最も強く実感できる仕事の一つです。
商品開発
先ほどの「仕事内容」でも触れましたが、「商品開発」も重要な専門職種の一つです。
市場のニーズや社会環境の変化を分析し、新しい保険商品を企画・立案します。
この職種では、単にアイデアを出すだけでなく、関連部署(アクチュアリー、営業、システム部門など)と連携し、商品を世に送り出すまでの全プロセスを管理します。
マーケティングの視点と、保険事業としての採算性を両立させるバランス感覚が求められます。
自分が企画した商品がヒットし、多くの人々の安心につながった時の達成感は格別です。
変化の激しい現代社会において、常に新しい価値を生み出し続けることが期待される、クリエイティブな仕事です。
【保険業界やめとけ】保険業界がきついとされる理由
さて、ここからは「保険業界はやめとけ」と言われる具体的な理由、つまり「きつい」と感じられがちな側面について、正直にお話ししていきます。
業界を問わず、どんな仕事にも大変な面はありますが、保険業界には特有の厳しさがあるのも事実です。
特に新卒で入社した場合、多くの人が「営業職」に配属される可能性が高く、そこで直面する壁が「きつい」というイメージにつながっているケースが多いです。
しかし、これらの「きつさ」は、見方を変えれば大きな成長の機会でもあります。
どのような点が大変なのかをあらかじめ知っておくことは、入社後のギャップを防ぐために非常に重要です。
自分がその環境に適応できそうか、乗り越えられそうかを冷静に判断する材料にしてください。
営業ノルマ(成果主義)のプレッシャー
保険業界、特に営業職において「きつい」と言われる最大の理由が、営業ノルマ(目標数字)のプレッシャーです。
多くの保険会社では、個人の営業成績が給与や昇進に直結する成果主義を採用しています。
毎月、あるいは四半期ごとに設定された目標を達成するために、常に行動し続ける必要があります。
目標を達成できた時の達成感や報酬は大きいですが、未達成が続くと精神的な負担は小さくありません。
特に新人のうちは、なかなか契約が取れずに悩むことも多いでしょう。
数字に追われる環境が苦手な人にとっては、このプレッシャーが最もきついと感じる点です。
顧客からのクレームや厳しい対応
保険は、お客様の「万が一」や「不安」に寄り添う商品です。
そのため、時にはお客様から厳しいご意見やクレームを受けることもあります。
例えば、保険金の支払いに関して、「思っていた内容と違う」「なぜ支払われないのか」といったお叱りを受ける場面です。
また、営業活動においても、保険に良いイメージを持っていないお客様から、冷たい態度を取られたり、話を全く聞いてもらえなかったりすることも日常茶飯事です。
人のネガティブな感情に直接触れる機会が多いため、精神的なタフさが求められます。
感情をうまく切り替える自己管理能力がないと、心が疲弊してしまう可能性があります。
継続的な自己研鑽(勉強)の必要性
保険商品は非常に複雑で、法律(保険業法)や税制、社会保障制度とも密接に関連しています。
また、これらの制度は頻繁に改正されます。
そのため、保険のプロフェッショナルとしてお客様に最適な提案をし続けるには、入社後も絶えず勉強し、知識をアップデートし続ける必要があります。
ファイナンシャル・プランナー(FP)などの関連資格の取得を必須としている会社も多いです。
お客様の人生に関わる重要なアドバイスをするわけですから、生半可な知識は許されません。
自ら進んで学び続ける姿勢がなければ、すぐに時代遅れになってしまい、お客様の信頼を失うことにもなりかねません。
(特に生保)知人・友人への勧誘プレッシャー
これは特に生命保険の個人営業において、昔からよく聞かれる話です。
新人の頃は、営業先を自分で開拓するのが難しいため、研修の一環として、まず身近な家族や親戚、友人・知人に保険の話をするよう指導されることがあります。
もちろん、すべての会社がそうではありませんし、最近ではこうした手法を見直す動きもあります。
しかし、大切な友人関係をお金や仕事に結びつけることに抵抗を感じる人は多いでしょう。
結果として、「友達をなくすのではないか」という不安や罪悪感を感じてしまい、精神的にきつくなってしまうケースがあります。
人間関係(同僚との競争)
成果主義の環境は、同僚との関係にも影響を与えることがあります。
同じチームのメンバーであっても、営業成績においては「ライバル」となります。
お互いに切磋琢磨して成長できるポジティブな面もありますが、成績の差が人間関係のギスギスにつながることもないとは言えません。
特に、お客様(営業先)の取り合いになったり、成績が良い人が優遇されるような雰囲気の職場だったりすると、ストレスを感じるかもしれません。
チームワークよりも個人の成果が重視される環境が、人によっては「きつい」と感じる要因になります。
残業や休日出勤の可能性
営業職の場合、お客様の都合に合わせて動くことが基本となります。
個人のお客様であれば、仕事終わりの夜間や土日に商談のアポイントが入ることが多くなります。
また、法人営業であっても、決算期前やイベント時などは多忙になりがちです。
損害サービス部門も、大きな事故や災害が発生した際は、昼夜を問わず対応に追われることがあります。
ワークライフバランスを重視する人にとっては、こうした不規則な働き方や、プライベートの時間が確保しにくい点が「きつい」と感じられるかもしれません。
会社や部署によって実態は大きく異なるため、OB・OG訪問などで実情を確認することが重要です。
保険業界の現状・課題
保険業界が直面している「きつさ」は、個人の働き方だけでなく、業界全体の構造的な変化とも深く関連しています。
かつては「安定産業」の代表格とされてきた保険業界ですが、現在は大きな変革期を迎えています。
国内市場の成熟や、これまでにない新しいリスクの登場など、従来のビジネスモデルだけでは立ち行かなくなっているのが実情です。
就職先として考える上では、こうした業界全体の「今」と「これから」を理解しておくことが欠かせません。
ここでは、保険業界が現在抱えている主な「現状と課題」を3つの側面から解説します。
これらの課題をどう乗り越えようとしているかが、企業選びの重要なヒントになります。
人口減少(少子高齢化)と国内市場の縮小
日本国内の人口が減少し、特に少子高齢化が進んでいることは、保険業界にとって非常に大きな課題です。
なぜなら、保険の主な顧客層である生産年齢人口(働く世代)が減れば、新規の保険契約数が伸び悩むのは避けられないからです。
特に、死亡保障などを中心としてきた生命保険会社にとっては深刻な問題です。
一方で、高齢者が増えれば、医療保険や介護保険のニーズは高まりますが、同時に保険金の支払いも増加します。
国内市場が縮小していく中で、どう新たな収益源を確保するかが、各社の喫緊の課題となっています。
超低金利の長期化による運用難
保険会社は、お客様から預かった保険料を「資産運用」することで収益の一部を得ている、と先ほど説明しました。
しかし、日本では長期間にわたって超低金利政策が続いています。
これは、銀行にお金を預けてもほとんど利息がつかないのと同じで、保険会社も、国債など安全とされる資産で利益を上げることが非常に難しくなっていることを意味します。
かつては高い利回りを約束できた「貯蓄型」の保険商品も、今では魅力を失いつつあります。
よりリスクを取った海外資産や新しい投資先を開拓する必要に迫られており、資産運用部門の重要性がますます高まっています。
異業種からの参入とInsurTech(インシュアテック)の台頭
これまでは国からの「免許」が必要で参入障壁が高かった保険業界ですが、近年はIT技術(FinTech)を活用した新しいプレイヤーが次々と登場しています。
これが「InsurTech(インシュアテック)」と呼ばれる動きです。
例えば、IT企業が手軽に入れる「スマホ保険」を提供したり、AIを活用して保険相談を自動化したりするサービスが出てきています。
従来の保険会社にはなかったスピード感や、デジタル技術を駆使した利便性を武器に、顧客を奪おうとしています。
既存の保険会社も、デジタル化への対応(DX)が遅れれば競争力を失うという危機感を持っており、異業種との提携やシステム投資を急いでいます。
保険業界の今後の動向
業界が多くの課題を抱えていると聞くと、将来性に不安を感じるかもしれません。
しかし、課題があるということは、それだけ「変革」の余地があるということです。
保険業界は今、まさに生き残りをかけて、これまでの常識を覆すような新しい取り組みを始めています。
「保険」という社会に不可欠な仕組みを守りつつ、どう進化させていくか。
ここが、これから入社する若い世代の皆さんに期待されている部分でもあります。
AIやビッグデータの活用、あるいはグローバルな視点など、新しい風を吹き込むチャンスが広がっています。
ここでは、保険業界が今後どのような方向に進んでいくのか、その「未来図」を3つのキーワードで解説します。
自分がこの変化の中でどんな役割を果たしたいかを想像してみてください。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進
保険業界の課題であった「異業種からの参入」に対抗し、また業務効率を抜本的に改善するために、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が急務となっています。
これまでの保険手続きは、対面での説明や、分厚い書類への記入・押印など、アナログな部分が多く残っていました。
しかし今後は、AIチャットボットによる顧客対応の自動化、スマートフォンアプリでの契約手続きの完結、AIによる保険金支払いの迅速な査定などが一気に進んでいくでしょう。
これにより、お客様の利便性が向上するだけでなく、営業担当者や事務担当者も、より付加価値の高い仕事(コンサルティングなど)に集中できるようになります。
パーソナライズド保険と「予防」へのシフト
IT技術やビッグデータの活用は、保険商品のあり方そのものも変えようとしています。
これまでは、年齢や性別などで区分された画一的な保険が主流でした。
しかし今後は、個人の健康状態や運転履歴、ライフスタイルといった詳細なデータに基づき、その人に最適化された「パーソナライズド保険」が主流になるでしょう。
例えば、ウェアラブル端末で取得した健康データに応じて保険料が変わる商品などです。
さらに、保険の役割は、事故や病気が起きた後に「補償」するだけでなく、事故や病気が起きないように「予防」する領域へと広がっています。
健康増進プログラムの提供などがその一例です。
海外市場への展開
国内市場の縮小という課題に対応するため、多くの大手保険会社は、積極的に海外市場へと活路を見出しています。
特に、経済成長が著しいアジア諸国などは、保険の普及がこれから本格化する市場として非常に魅力的です。
すでに現地の保険会社を買収(M&A)したり、合弁会社を設立したりして、グローバルな事業展開を加速させています。
将来的には、海外駐在員として現地のビジネスを牽引するようなキャリアパスも現実的になっています。
国内の安定した基盤を持ちつつ、グローバルな舞台で活躍したいと考えている人にとって、保険業界は大きな可能性を秘めたフィールドと言えるでしょう。
【保険業界やめとけ】保険業界に向いている人
ここまで保険業界の仕事内容、きつい側面、そして将来性について見てきました。
これらの情報を踏まえて、結局のところ、どのような人が保険業界で活躍できるのでしょうか。
「やめとけ」という言葉を鵜呑みにせず、自分自身の特性と業界が求める人物像がマッチするかどうかを見極めることが大切です。
保険は「人」が「人」のために提供するサービスであり、AIやデジタル化が進んでも、その本質は変わりません。
むしろ、複雑な人生の不安に寄り添う「人間力」の価値は、ますます高まっていくでしょう。
ここでは、保険業界、特に営業職や顧客対応の最前線で力を発揮できる人の特徴を5つ挙げます。
自分に当てはまる項目があるか、自己分析と照らし合わせながら確認してみてください。
人助けや誰かの役に立つことにやりがいを感じる人
保険の根本にあるのは「相互扶助」、つまり「困ったときはお互い様」という助け合いの精神です。
営業職であれば、お客様の人生設計を一緒に考え、万が一の時の不安を取り除くことが仕事です。
損害サービスであれば、事故に遭って動揺しているお客様を支え、生活の再建を手助けします。
「お金」という形で直接的に人助けができる仕事は、そう多くありません。
お客様から「あなたのおかげで安心できた」「あの時、保険に入っていて本当に良かった」と心から感謝された時、何物にも代えがたいやりがいを感じられる人は、この業界に非常に向いています。
コミュニケーション能力が高く、信頼関係を築ける人
保険は目に見えない商品であり、契約期間も長期にわたることが多いため、最終的には「誰から入るか」が決め手になることがほとんどです。
そのため、お客様の心を開き、本音の不安や希望を引き出す高い傾聴力が求められます。
また、難しい保険の内容を、お客様の知識レベルに合わせて分かりやすく説明する力も必要です。
初対面の人とも臆せずに話し、長期的に良好な関係を築いていける「人懐っこさ」や「誠実さ」は、保険業界で働く上で最強の武器になります。
人と話すのが好きで、信頼関係を築くプロセスを楽しめる人に向いています。
精神的なタフさ(ストレス耐性)がある人
「きついとされる理由」でも述べた通り、保険業界の仕事、特に営業職はプレッシャーとの戦いです。
営業ノルマの達成、お客様からのクレームや厳しいお断り、事故対応の緊迫感など、精神的な負担がかかる場面は少なくありません。
失敗したり、断られたりしても、それを引きずらずに「次頑張ろう」と気持ちを切り替えられるタフさが求められます。
物事を楽観的に捉え、ストレスを上手に発散できるセルフコントロール能力がある人は、この業界で長く活躍できる可能性が高いです。
逆境をバネに成長できる人とも言えるでしょう。
粘り強さと継続力がある人
保険の営業は、種をまいてすぐに芽が出る仕事ではありません。
お客様との関係をじっくりと温め、信頼を得て、初めて契約につながります。
一度断られたとしても、定期的に情報提供を続けることで、数年後にお客様の状況が変わったタイミングで「あの時のあなたから」と声がかかることもあります。
目先の成果が出なくても諦めず、コツコツと努力を続けられる「粘り強さ」が成功の鍵を握ります。
地道な活動を継続することの大切さを理解し、それを実行できる人は、必ず大きな成果を掴むことができるでしょう。
学習意欲が高く、自己成長を続けられる人
保険商品は、税制や社会保障制度と密接に関連しており、これらの法律や制度は毎年のように変わります。
また、医療の進歩や新しいリスクの登場に合わせて、保険商品自体も進化し続けます。
お客様に常に最新かつ最適な情報を提供するためには、入社後も常に学び続ける意欲が不可欠です。
FP(ファイナンシャル・プランナー)資格の勉強はもちろん、経済や金融、医療に関するニュースにもアンテナを張る必要があります。
新しい知識を吸収することに喜びを感じ、自分を高め続けることに貪欲な人は、プロフェッショナルとして成長し続けられるでしょう。
【保険業界やめとけ】保険業界に向いていない人
一方で、残念ながら保険業界の風土や仕事内容が、本人の特性と合わないケースもあります。
「やめとけ」と言われてしまう背景には、こうしたミスマッチが起きてしまい、早期に離職する人が一定数いることも事実です。
自分の「苦手」や「避けたいこと」を直視するのも、就職活動における大切な自己分析です。
もし、ここで挙げる特徴に強く当てはまると感じるなら、保険業界を選んだとしても、入社後に苦労する可能性が高いかもしれません。
ただし、これはあくまで「傾向」です。
部署や職種によっては当てはまらないこともあるので、一つの参考として冷静に受け止めてください。
ノルマや数字で評価されるのが極度に苦手な人
保険業界、特に営業職は、成果(契約件数や保険料)が数字としてはっきりと表れ、それが評価に直結する世界です。
「数字に追われる」というプレッシャーが常にかかります。
もちろん、プロセスを評価してくれる上司や文化もありますが、最終的に求められるのは結果です。
もし、数字で他人と比較されたり、目標達成のために行動を管理されたりすることに強いストレスを感じるのであれば、この業界はきついかもしれません。
自分のペースで、プロセスを重視して働きたいという志向が強い人には、向いていない可能性があります。
人から断られることに強い恐怖を感じる人
営業活動において、お客様から「必要ありません」「他で入っています」と断られることは日常茶飯事です。
むしろ、話を聞いてもらえることの方が少ないくらいです。
その一つひとつのお断りに対して、「自分自身が否定された」と深く落ち込んでしまう人は、精神的に持たないかもしれません。
保険の営業は、お客様のニーズやタイミングが合わなければ成約しないのが当たり前です。
「今回はご縁がなかっただけ」と割り切り、次のお客様へとアプローチを切り替えられる「鈍感力」もある程度は必要です。
お金や万が一(死・病気)の話に抵抗がある人
保険は、お客様の「お金」と「万が一の不幸(死亡、病気、事故)」に真正面から向き合う商品です。
お客様の家計の状況や貯蓄額といったデリケートな情報を聞き出し、最悪の事態を想定して「もしご主人が亡くなられたら、奥様の生活費は…」といった話を具体的にする必要があります。
こうしたシビアな話題を切り出すことに強い抵抗を感じたり、お金の話を「いやらしい」と感じてしまったりする人には、務まらない仕事です。
お客様の人生を守るために必要なことだと割り切れないと、踏み込んだ提案ができません。
安定志向が強すぎる人(変化を好まない人)
かつては「安定」の代名詞だった保険業界ですが、今は「大変革期」にあると説明しました。
DXの推進、InsurTechの台頭、商品サイクルの短期化など、これまでのやり方が通用しなくなってきています。
入社後も常に新しい知識を学び、新しい営業手法やデジタルツールに適応していく必要があります。
「一度入社すれば安泰」「ルーティンワークだけをこなしたい」という強い安定志向や、変化を好まない保守的な姿勢では、これからの保険業界で活躍し続けるのは難しいでしょう。
チームプレーよりも個人での作業を好む人
営業職は個人の成果が問われる一方で、保険の仕事は多くの部門との連携で成り立っています。
営業担当者が契約を預かっても、アンダーライターの審査が通らなければ成立しません。
事故が起きれば、損害サービス部門と連携して対応します。
また、営業所内でも、上司や先輩、事務スタッフと情報を共有し、助け合いながら目標達成を目指します。
「自分一人で完結する仕事がしたい」「人との連携は最小限にしたい」という志向が強い人は、組織の中で働くことにストレスを感じるかもしれません。
保険業界に行くためにすべきこと
保険業界のリアルな姿が見えてきたでしょうか? 「きつい」側面も理解した上で、それでも「人の役に立ちたい」「専門性を身につけたい」と、この業界への挑戦意欲が湧いてきた人もいると思います。
もし本気で保険業界を目指すなら、学生のうちから準備しておくべきことがあります。
保険業界は、金融という専門領域でありながら、新卒採用においては「ポテンシャル」を重視する傾向が強いです。
しかし、業界への理解度や熱意を示すための「行動」は、選考において確実にプラスに働きます。
ここでは、保険業界の就活を突破するために、今から取り組むべきことを3つのステップで解説します。
「なぜ保険業界なのか」を自分の言葉で語れるようになることがゴールです。
徹底した業界・企業研究(生保・損保・代理店の違い)
まずは「保険業界」という大きな括りではなく、その中身を細かく理解することから始めましょう。
最低限、「生命保険」と「損害保険」の違いを自分の言葉で説明できるようになる必要があります。
それぞれの商品特性やビジネスモデル、営業スタイル(個人向けか代理店向けか)は大きく異なります。
さらに、特定の会社に属さず複数の保険会社の商品を扱う「保険代理店(ほけんの窓口など)」という業態もあります。
それぞれのメリット・デメリットを比較し、自分がなぜその分野(例えば「生保」)を、そしてなぜその会社(例えば「A生命」)を志望するのか、ロジックを組み立てられるように深く研究してください。
関連資格(FPなど)の勉強・取得
学生時代に保険関連の資格が必須というわけではありませんが、学習意欲と業界への本気度を示す上で、ファイナンシャル・プランナー(FP)資格の勉強は非常に有効です。
特にFP3級は、保険だけでなく、年金、税金、資産運用、不動産など、お金に関する幅広い基礎知識を学べるため、就活の面接ネタとしても役立ちます。
保険は「お客様のライフプラン全体」を考える仕事であり、FPの知識は入社後も必ず役立ちます。
資格取得そのものが目的ではなく、その過程で得た知識をどう活かしたいかを語れることが重要です。
インターンシップやOB・OG訪問への参加
最もリアルな情報を得る方法は、やはり現場で働く人の生の声を聞くことです。
多くの保険会社がサマーインターンやウィンターインターンを実施しています。
営業同行やグループワークを通じて、仕事の難しさややりがいを肌で感じる絶好の機会です。
また、大学のキャリアセンターなどを通じてOB・OG訪問を積極的に行いましょう。
「やめとけと言われるが、実際どうなのか」「一番きつかった経験は何か」「それでも仕事を続ける理由は何か」といった、ネットには書かれていない本音を聞き出すことで、志望動機に圧倒的な具体性と熱量が生まれます。
【保険業界やめとけ】適性がわからないときは
ここまで読んでみて、「自分は向いているかもしれないし、向いていないかもしれない…」と、適性がわからずに悩んでしまう人もいるでしょう。
それは当然のことです。
働いた経験がない中で、自分と業界の相性を完璧に見極めるのは難しいものです。
そんな時は、一人で悩まずに客観的な視点を取り入れることが大切です。
Digmediaが提供しているような「適職診断ツール」を活用してみるのも一つの手です。
いくつかの質問に答えるだけで、自分の性格や価値観がどのような仕事に向いているのか、統計的なデータからヒントを得ることができます。
また、最も重要なのは「自己分析」を深めることです。
自分が過去にどのような時にやりがいを感じ、どのような時にストレスを感じたかを具体的に書き出してみましょう。
その上で、大学のキャリアセンターの相談員や、就活エージェントといった「プロ」に壁打ち相手になってもらうのも非常に有効です。
第三者の視点からフィードバックをもらうことで、自分では気づかなかった強みや適性が見えてくるはずです。
おわりに
「保険業界はやめとけ」という言葉の裏にある、仕事の厳しさと、それを上回る大きなやりがい。
その両面を理解していただけたでしょうか。
保険は、目に見えない「安心」を売る仕事であり、人の弱さや不安に深く寄り添う仕事です。
プレッシャーや学ぶべきことの多さは、間違いなく「きつい」です。
しかし、だからこそ「あなたに任せたい」とお客様から信頼を得られた時の喜びは計り知れません。
ネガティブな情報だけで判断せず、ぜひインターンや説明会で、自分の目で確かめてみてください。
この記事が、あなたの納得のいく業界研究の一助となれば幸いです。