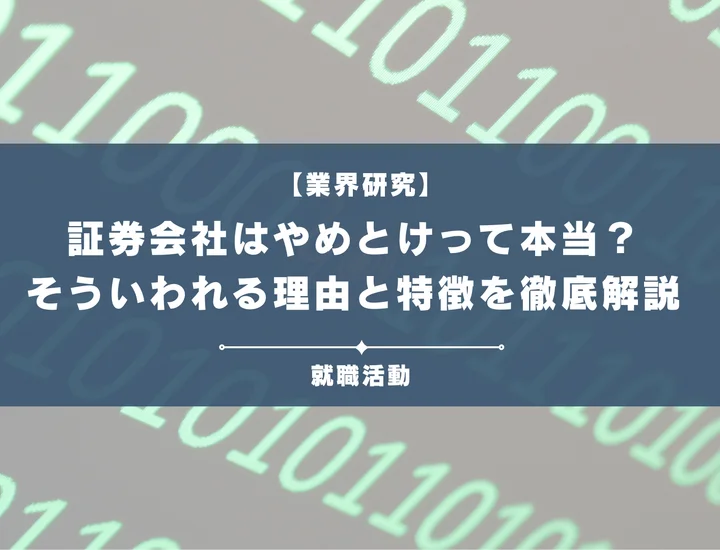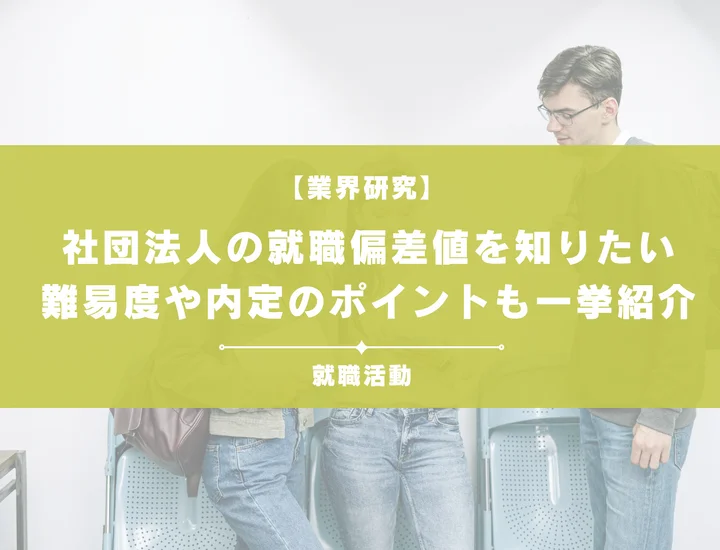HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
就職活動を進める中で、「証券会社はやめとけ」という言葉を耳にしたことはありませんか?高給与でエリートなイメージがある一方、ネガティブな評判も多く、実態がどうなのか気になっている人も多いはずです。
この記事では、なぜ証券会社が「やめとけ」と言われるのか、その理由や仕事のリアルな内容、そしてどんな人が向いているのかを徹底的に解説していきます。
業界研究の一環として、ぜひ参考にしてくださいね。
目次[目次を全て表示する]
【証券会社やめとけ】やめとけと言われるのは本当?
「証券会社はやめとけ」。
これは、残念ながら一部の事実を含んだ言葉です。
金融という人々の資産を扱う重要な仕事である反面、非常に厳しいノルマや成果主義の世界であることは間違いありません。
数字(営業成績)が人格とまで言われるようなプレッシャーの中で、精神的に疲弊してしまう人がいるのも事実です。
また、市場は常に動いているため、早朝からの情報収集や顧客対応で労働時間が長くなりがちな側面もあります。
こうした厳しい環境が、「やめとけ」と言われる大きな理由になっているんですね。
【証券会社やめとけ】証券会社の仕事内容
証券会社と聞くと、株の売買をしているイメージが強いかもしれませんが、その役割は「金融仲介機能」として非常に多岐にわたります。
企業が事業を拡大するために必要な資金(株式や債券)を市場から調達するお手伝いをしたり、個人投資家が資産を増やすための投資(株式、投資信託、債券など)のサポートをしたりするのが主な仕事です。
いわば、経済活動における血液(=お金)の流れをスムーズにする重要なパイプ役ですね。
このセクションでは、証券会社が具体的にどのような仕事をしているのか、大きく4つの部門に分けて詳しく見ていきましょう。
それぞれの部門が専門性を持ち、連携しながら日本の経済を根底から支えています。
リテール(個人向け営業)
リテール部門は、個人のお客様に対して資産運用の提案を行う、いわば証券会社の「顔」とも言える仕事です。
お客様の自宅や職場を訪問したり、店舗窓口で相談に乗ったりしながら、株式、債券、投資信託といった金融商品を販売します。
「貯蓄から投資へ」という国のスローガンにもあるように、近年はNISAなどの制度も追い風となり、資産運用への関心が高まっています。
しかし、お客様の大切な資産を預かるため、大きな責任が伴います。
市況(市場の状況)によっては、お客様の資産が減ってしまうこともあり、その際のクレーム対応や精神的なプレッシャーは相当なものです。
一方で、お客様のライフプラン(老後の資金、子どもの教育費など)に寄り添い、信頼関係を築きながら資産形成をサポートできた時の喜びは、何物にも代えがたいやりがいとなります。
高いコミュニケーション能力と誠実さが求められる仕事ですね。
ホールセール(法人向け営業)
ホールセール部門は、機関投資家と呼ばれるプロの投資家(銀行、生命保険会社、年金基金、海外のヘッジファンドなど)や、一般事業法人を顧客とする仕事です。
リテール部門が個人を相手にするのに対し、ホールセールは「プロ対プロ」の取引であり、扱う金額の桁も格段に大きくなります。
例えば、機関投資家に対しては、自社のリサーチ部門が分析した情報や投資アイデアを提供し、株式や債券の売買注文を受けます。
また、事業法人に対しては、資金調達のニーズはないか、余剰資金をどう運用するか、あるいは為替リスクをどう回避するかといった高度な金融ソリューションを提供します。
この分野で活躍するには、経済や金融に関する深い専門知識はもちろん、国内外の市場動向を常にキャッチアップし続ける情報感度、そして大口の取引をまとめるためのタフな交渉力が不可欠です。
投資銀行部門(IBD)
投資銀行部門(IBD: Investment Banking Division)は、企業の資金調達やM&A(企業の合併・買収)を専門に手掛ける部門です。
証券会社の仕事の中でも、特に花形と呼ばれることの多い分野ですね。
主な仕事は二つあります。
一つは、企業が株式を新たに発行(IPO:新規株式公開)したり、債券を発行したりする際の「引受業務(アンダーライティング)」です。
証券会社が企業の財務状況などを厳しく審査し、適切な発行価格を算定、そしてそれを投資家に販売します。
もう一つは「M&Aアドバイザリー業務」で、企業が他社を買収したり、自社を売却したりする際に、戦略立案から相手探し、交渉、契約締結までを一貫してサポートします。
企業の経営戦略に深く関わるため、高度な財務分析能力、法務知識、そして何より激務に耐えうる体力と精神力が求められます。
プロジェクトが成功した際の達成感は非常に大きいですが、その分、求められるスキルセットも非常にハイレベルです。
リサーチ部門
リサーチ部門は、経済や金融市場、個別企業などを専門的に分析・調査し、その結果をレポートにまとめて発信するのが仕事です。
この部門には、経済全体を分析する「エコノミスト」、株式市場や為替市場の動向を予測する「ストラテジスト」、そして個別の企業や業界を分析する「アナリスト」などが所属しています。
彼らが作成するレポートは、リテール部門やホールセール部門の営業活動における重要な情報源となったり、機関投資家が投資判断を下す際の参考にされたりします。
市場の未来を予測するという非常に難易度の高い仕事であり、地道なデータ収集と鋭い分析力、そして自らの分析結果を論理的に説明する能力が必要です。
リサーチ部門の分析力の高さが、その証券会社の信頼性やブランド価値に直結するとも言え、専門性を極めたい人にとっては非常に魅力的なキャリアパスとなるでしょう。
【証券会社やめとけ】証券会社の主な職種
証券会社には、先ほど紹介した仕事内容を遂行するために、様々な職種が存在します。
一般的に就活生の皆さんがイメージしやすいのは「営業職」かもしれませんが、それ以外にも高度な専門職が数多くあります。
例えば、企業の財務を分析する専門家、市場の動向を予測する専門家、あるいは膨大な取引を処理・管理する専門家などです。
自分の強みや興味がどの職種で活かせるかを考えることは、証券会社への就職活動において非常に重要です。
ここでは、証券会社を代表する5つの職種を紹介します。
それぞれの役割や求められるスキルを理解することで、証券会社の全体像がよりクリアになるはずですよ。
営業職(リテール・ホールセール)
証券会社の職種として最もイメージしやすいのが営業職でしょう。
これは「リテール営業」と「ホールセール営業」の二つに大別されます。
リテール営業は、主に個人のお客様を担当します。
全国の支店に配属され、お客様の資産運用に関する相談に応じ、株式や投資信託などの金融商品を提案・販売するのが主な業務です。
新規顧客の開拓も重要で、いわゆる「飛び込み」や「テレアポ」を行うこともあります。
一方、ホールセール営業は、機関投資家や事業法人といったプロの顧客を担当します。
扱う金額が非常に大きく、高度な金融知識や市場分析に基づいたソリューション提案が求められます。
どちらの営業職も、会社の収益に直結する重要な役割であり、厳しいノルマが課されることが一般的です。
成果が給与に反映されやすいため、若いうちから高収入を目指せる可能性がありますが、その分プレッシャーも大きい職種です。
投資銀行バンカー
投資銀行バンカーは、投資銀行部門(IBD)に所属し、企業の資金調達(株式や債券の発行)やM&A(合併・買収)のアドバイザリー業務を専門に行う職種です。
企業の経営トップ層と直接対話し、その経営戦略の根幹に関わる非常にダイナミックな仕事です。
例えば、ある企業が新しい工場を建てるための資金をどう集めるか、あるいはライバル企業を買収すべきか、といった重大な意思決定をサポートします。
この職種には、高度な財務・会計知識はもちろん、法務や税務に関する知識、そして何よりクライアントである企業のビジネスを深く理解する力が求められます。
プロジェクトは数ヶ月から数年に及ぶこともあり、その間は長時間労働が常態化するほど激務ですが、社会に与えるインパクトの大きさと報酬の高さから、就活生にも非常に人気の高い職種の一つです。
アナリスト/ストラテジスト
アナリストやストラテジストは、リサーチ部門に所属する専門職です。
アナリストは、特定の業界や個別企業を深く分析し、その企業の将来性や株価が「買い」か「売り」かを評価する「レーティング」を決定し、レポートを作成します。
例えば、「自動車業界担当アナリスト」は、EV化の動向や各社の新車販売状況などを徹底的に調査します。
一方、ストラテジストは、株式市場全体や為替、金利といったマクロ経済の大きな流れを分析・予測します。
彼らの分析レポートは、社内の営業部門やトレーダー、さらには社外の機関投資家にとって重要な投資判断材料となります。
非常に高い分析能力と論理的思考力、そして自らの見解を明確に伝える表現力が求められる、まさに知的な専門職と言えるでしょう。
トレーダー/ディーラー
トレーダーやディーラーは、市場(マーケット)部門に所属し、実際に金融商品の売買を行う職種です。
ディーラーは、証券会社自身の資金(自己勘定)を使って株式や債券などを売買し、利益を追求します。
市場のわずかな変動を読み取り、瞬時に売買判断を下すため、極めて高い集中力と決断力、そして何よりも市場の変動に対する強い精神的なタフさが求められます。
一方、トレーダーは、主に顧客(特に機関投資家)から受けた売買注文を、市場で最も有利な条件で執行(取引を成立させること)する役割を担います。
どちらも市場の最前線でダイナミックに動くため、緊張感は非常に高いですが、自分の判断が直接収益に結びつくやりがいのある仕事です。
近年はAIによる自動売買も増えていますが、複雑な取引や市場の急変時には依然として人間の判断が重要とされています。
ミドル・バックオフィス(リスク管理・法務など)
営業部門や投資銀行部門といった「フロントオフィス」が収益を稼ぐ部門であるのに対し、ミドルオフィスやバックオフィスは、その活動を支え、管理する重要な役割を担います。
ミドルオフィスには、フロントオフィスが行う取引のリスクを分析・監視する「リスク管理部門」や、法令遵守(コンプライアンス)を徹底させる「法務・コンプライアンス部門」などがあります。
証券会社が扱う金融商品は社会的な影響が大きいため、少しのミスや不祥事が会社の信用を大きく損なうことになりかねません。
そのため、彼らのチェック機能は不可欠です。
一方、バックオフィスは、顧客の口座管理や、売買が成立した後の決済業務、資金の入出金管理など、日々の膨大な事務処理を正確に行う部門です。
どちらも会社の根幹を支える「守り」の部門であり、高い専門性と正確性、誠実さが求められます。
【証券会社やめとけ】証券会社がきついとされる理由
証券会社が「やめとけ」と言われる背景には、その仕事の特性上、避けて通れない「きつさ」があります。
高給与やエリートといった華やかなイメージの裏で、多くの社員が日々プレッシャーと戦っています。
もちろん、この「きつさ」を乗り越えた先にある成長や達成感こそが証券会社の醍醐味だと言う人もいます。
しかし、就職活動の段階で、どのような「きつさ」が存在するのかを具体的に知っておくことは、入社後のミスマッチを防ぐために非常に重要です。
ここでは、証券会社がきついとされる代表的な理由を6つ挙げ、それぞれ詳しく解説していきます。
自分にとって許容できる範囲のきつさか、冷静に判断する材料にしてください。
厳しいノルマと成果主義
証券会社、特にリテール営業部門において「きつい」と言われる最大の理由が、この厳しいノルマと成果主義です。
多くの証券会社では、社員一人ひとり(あるいは支店ごと)に、月間や四半期ごとの目標数値(ノルマ)が設定されます。
例えば、「投資信託の販売額〇〇万円」「新規顧客獲得〇〇件」といった具体的な数字です。
このノルマの達成度が、ボーナスや昇進・昇格に直結します。
成果を出せば若いうちから高い報酬を得ることができますが、逆にノルマが未達の状態が続くと、上司からの厳しい叱責を受けたり、社内での居心地が悪くなったりすることもあります。
常に数字に追われるプレッシャーは想像以上のものであり、成果が全ての文化に馴染めない人にとっては、非常に精神的な負担が大きい環境と言えるでしょう。
精神的なプレッシャーの大きさ
証券会社の仕事は、お客様の大切な資産を預かるという点で、常に大きな精神的プレッシャーが伴います。
特にリテール営業の場合、自分が勧めた金融商品が値下がりし、お客様の資産が減ってしまうことは日常的に起こり得ます。
その際、お客様から厳しいお叱りを受けたり、不信感を抱かれたりすることもあります。
顧客の損失が自分の責任のように感じてしまう真面目な人ほど、精神的に追い詰められやすい傾向があります。
また、投資銀行部門では、数百億円規模のM&A案件を担当することもあり、そのプロジェクトが失敗すれば会社に甚大な損失を与える可能性があるというプレッシャーもあります。
「失敗が許されない」という緊張感の中で常に高いパフォーマンスを発揮し続ける必要があるため、強靭なメンタルが求められるのです。
長時間労働と不規則な勤務
証券会社の勤務時間は、一般的な企業と比べて長くなる傾向があります。
特に営業職の場合、株式市場が開く朝9時よりもずっと早く出社し、前日の海外市場の動向や最新ニュースをチェックし、朝礼で共有する必要があります。
日中は顧客対応や取引に追われ、市場が閉まる15時以降にようやく事務作業や翌日の準備、上司への報告などを行います。
さらに、顧客の都合に合わせて夕方や土日に商談が入ることも少なくありません。
また、投資銀行部門やリサーチ部門も、大型案件の締め切り前や決算発表シーズンなどは、連日深夜までの残業や休日出勤が常態化することも珍しくありません。
ワークライフバランスを重視したい人にとっては、この労働環境が「きつい」と感じる大きな要因となるでしょう。
常に学び続ける必要性(知識・市況)
金融業界は、法律や税制の改正、新しい金融商品の登場、そして日々刻々と変動する国内外の経済情勢など、変化のスピードが非常に速い業界です。
そのため、証券会社の社員は、入社後も常に新しい知識をインプットし続ける必要があります。
例えば、営業職であれば、お客様に適切な提案をするために、経済ニュースはもちろん、担当する企業の業績や新商品の特徴まで、幅広くアンテナを張っておかなければなりません。
また、証券外務員資格をはじめ、ファイナンシャル・プランナー(FP)や証券アナリストなど、キャリアアップのために取得すべき資格も多く存在します。
知的好奇心があり、自ら学ぶことが好きな人にとっては刺激的な環境ですが、逆に勉強が苦手な人や、一度覚えた知識だけで仕事をしたい人にとっては、この「学び続ける」環境が大きな負担となるでしょう。
顧客の損失=クレームのリスク
これは精神的なプレッシャーとも関連しますが、証券会社の仕事、特に営業職においてクレームのリスクは常につきまといます。
投資には必ずリスクが伴い、「元本割れ(投資した金額より資産が減ること)」の可能性があります。
営業担当者は、商品を販売する際にそのリスクを十分に説明する義務がありますが、実際に顧客が損失を被った場合、「あんな商品は勧めてほしくなかった」「説明が不十分だった」といったクレームに発展することがあります。
お客様の大切な資産を減らしてしまったという罪悪感に加えて、厳しい言葉を浴びせられることは、精神的に非常にこたえます。
顧客の利益を第一に考え、誠実に対応する姿勢がもちろん大前提ですが、それでも市場の変動によってクレームが発生してしまう可能性をゼロにすることはできず、これが「きつい」と感じる点です。
規制やコンプライアンスの厳しさ
金融商品は、一歩間違えれば顧客に大きな損害を与えたり、不公正な取引(インサイダー取引など)につながったりする危険性を持っています。
そのため、証券業界は金融商品取引法をはじめとする厳しい法律やルールによって厳しく規制されています。
社員は、これらの法令や社内ルール(コンプライアンス)を徹底して遵守しなければなりません。
例えば、顧客への商品説明の方法、取引の記録、情報の管理など、あらゆる業務プロセスにおいて細かいルールが定められています。
万が一、ルール違反が発覚すれば、本人だけでなく会社全体が厳しい行政処分を受ける可能性もあります。
「ルールだから守る」という高い規範意識と、事務作業の正確性が求められ、この厳格さが窮屈で「きつい」と感じる人もいるかもしれません。
証券会社の現状・課題
証券業界は今、大きな変革期の真っ只中にあります。
かつては、株式の売買手数料が主な収益源でしたが、インターネット証券の台頭による手数料の低価格化競争や、顧客のニーズの変化により、従来のビジネスモデルが通用しなくなりつつあります。
まさに今、業界全体が「どう変わっていくべきか」を模索している段階です。
こうした現状を理解することは、証券会社が今後どのような人材を求めているのかを知る上でも重要です。
ここでは、証券会社が直面している主な現状と課題を3つの視点から解説します。
古いイメージだけにとらわれず、業界の「今」を正確に把握しましょう。
ネット証券の台頭と手数料自由化
証券業界の現状を語る上で欠かせないのが、SBI証券や楽天証券といったネット証券の急速な台頭です。
従来の対面型証券会社(野村證券や大和証券など)が人によるコンサルティングを強みとしてきたのに対し、ネット証券は、インターネット上で取引が完結する手軽さと、何より「売買手数料の安さ」を武器に顧客層を拡大してきました。
特に2023年以降、大手ネット証券が相次いで国内株式の売買手数料を無料化したことは、業界に衝撃を与えました。
これまで手数料収入に大きく依存してきた従来の証券会社は、収益構造の根本的な見直しを迫られています。
単に商品を売るだけではネット証券との価格競争に勝てないため、付加価値の高いサービスをどう提供するかが大きな課題となっています。
顧客本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティー)への転換
過去の証券業界では、残念ながら、顧客の利益よりも会社の利益(手数料稼ぎ)を優先するような営業スタイルが問題視されることもありました。
しかし、金融庁は近年、「顧客本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティー)」を強く推進しています。
これは、金融機関が、専門家として顧客の最善の利益を考えて行動すべきという原則です。
具体的には、顧客のニーズやリスク許容度を十分に把握せず、手数料の高い商品ばかりを勧めるのではなく、顧客の長期的な資産形成に本当に役立つサービスを提供することが求められています。
この方針転換は、証券会社の営業スタイルに大きな影響を与えています。
かつてのような「ノルマ達成のために何でも売る」という姿勢は許されず、いかに顧客との信頼関係を築き、長く付き合っていくかという視点が重要になっており、現場の社員にも意識改革が求められています。
FinTech(フィンテック)の進展と異業種参入
FinTech(フィンテック)とは、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、IT技術を使った新しい金融サービスを指します。
例えば、AIが自動で資産運用のアドバイスを行う「ロボアドバイザー」や、スマートフォンを使った決済サービスなどがこれにあたります。
こうしたテクノロジーの進展は、証券業界にも大きな影響を与えています。
これまで人間が行っていた単純な事務作業や、一部のデータ分析はAIやRPA(ロボットによる業務自動化)に代替されつつあります。
また、IT企業や通信キャリアなど、全く異なる業種から金融サービスに参入するケースも増えており、業界内の競争はますます激化しています。
証券会社は、こうしたテクノロジーをいかに活用して業務を効率化し、新しいサービスを生み出していくかという課題に直面しています。
証券会社の今後の動向
現状と課題を踏まえ、証券業界は今後どのように変化していくのでしょうか。
手数料競争やFinTechの波は、証券会社にとって「危機」であると同時に、新しいサービスを生み出す「チャンス」でもあります。
「やめとけ」と言われるような旧来の体質から脱却し、より顧客に寄り添い、専門性を高める方向へと業界全体がシフトしています。
この変化の波を捉えることは、証券会社で働く上での将来性を見極めることにもつながります。
ここでは、証券業界の今後の主な動向を3つのキーワードで読み解いていきます。
未来の証券パーソンに求められる姿が、ここから見えてくるはずです。
対面営業から資産コンサルティングへのシフト
ネット証券の台頭により、単に株を売買するだけならネットで十分、という時代になりました。
この流れを受けて、従来の対面型証券会社が今後ますます注力していくのが、「モノ(金融商品)売り」から「コト(コンサルティング)売り」への転換です。
つまり、手数料の高い商品を一方的に勧めるのではなく、顧客一人ひとりのライフプランや家族構成、資産状況を深くヒアリングし、その人に最適な資産配分や相続・事業承継対策まで含めた総合的な「資産コンサルティング」を提供するという方向性です。
これからの営業職には、金融知識はもちろんのこと、顧客の潜在的な悩みやニーズを引き出す高い傾聴力と、信頼関係を築く人間力がこれまで以上に求められるようになります。
AIにはできない、人間ならではの付加価値を提供できるかが鍵となります。
テクノロジー活用(AI、RPA)による業務効率化
FinTechの進展は、業務のあり方を大きく変えつつあります。
証券会社のバックオフィスでは、これまで人間が手作業で行っていた口座開設の事務処理や、膨大なデータのチェック作業などにRPA(ロボットによる業務自動化)が導入され、大幅な効率化が進んでいます。
また、リサーチ部門ではAIが市場データを分析してレポート作成を補助したり、営業部門ではAIが顧客の取引履歴を分析して最適な商品を提案するのをサポートしたりするシステムも開発されています。
テクノロジーによって単純作業から解放されることで、社員はより高度な判断が求められる業務や、顧客との対話といった人間にしかできない仕事に集中できるようになります。
今後は、こうしたテクノロジーを使いこなすITリテラシーも、証券会社の社員にとって必須のスキルとなっていくでしょう。
NISA拡充などによる資産運用ニーズの高まり
今後の証券業界にとって大きな追い風となっているのが、「貯蓄から投資へ」という国の政策です。
2024年から大幅に拡充された新しいNISA(少額投資非課税制度)は、これまで投資に馴染みのなかった層にも関心を集めており、個人の資産運用ニーズは確実に高まっています。
また、長引く低金利や将来の年金不安から、「自分でお金を育てなければならない」という意識も広まってきました。
こうした社会的な背景は、証券会社にとって大きなビジネスチャンスです。
増大する資産運用ニーズに対して、いかに分かりやすく、安心して利用できるサービスを提供できるかが、今後の証券会社の成長を左右します。
特に、若年層や投資未経験者層をいかに取り込んでいくかが重要なテーマとなっており、デジタル技術を活用した新しいアプローチも活発になっています。
【証券会社やめとけ】証券会社に向いている人
ここまで証券会社の仕事内容や「きつい」とされる理由、今後の動向について解説してきました。
それを踏まえて、一体どのような人が証券会社で活躍できるのでしょうか。
厳しい環境であることは事実ですが、それ以上に大きなやりがいや成長、高い報酬を得られる可能性も秘めているのがこの業界です。
大切なのは、業界の特性と自分の価値観や強みがマッチしているかを見極めることです。
ここでは、証券会社に向いている人の特徴を5つご紹介します。
自分に当てはまる項目があるか、自己分析と照らし合わせながらチェックしてみてください。
数字や成果に強いこだわりを持てる人
証券会社は、良くも悪くも「数字」が全ての成果主義の世界です。
営業職であれば販売額や契約件数、投資銀行部門であれば案件の成約数など、あらゆる業務が具体的な数字(成果)によって評価されます。
この環境を楽しめるかどうかが、適性を判断する上で最も重要なポイントかもしれません。
目標達成のために何をすべきかを逆算して考え、行動に移せる人、そして何より「絶対に目標を達成する」という強い意志と、成果に対する貪欲さを持っている人は、証券会社で大きく成長できる可能性が高いです。
逆に、結果よりもプロセスを評価してほしい、数字に追われるのは苦手だという人には、かなり厳しい環境に感じられるでしょう。
高いストレス耐性と精神的なタフさがある人
証券会社の仕事は、厳しいノルマ、市場の変動、顧客からのクレーム、長時間労働など、日常的に様々なプレッシャーにさらされます。
特に顧客の資産を預かるという責任の重さは、他の業界ではなかなか経験できないレベルのものです。
市場が暴落してお客様の資産が大きく減少した時でも、冷静さを失わず、誠実に対応し続けなければなりません。
失敗したり、叱責されたりしても、それを引きずらずに「次こそは」と前を向ける精神的なタフさ、いわゆる「ストレス耐性」が不可欠です。
プレッシャーを成長のバネとして捉えられるような、強靭なメンタルを持っている人が向いていると言えます。
知的好奇心が旺盛で学び続けられる人
金融の世界は、日進月歩です。
新しい金融商品が次々と生まれ、国内外の経済情勢は日々変動し、法律や税制も変わっていきます。
証券会社でプロフェッショナルとして活躍し続けるためには、これらの変化を常にキャッチアップし、学び続ける姿勢が絶対に必要です。
経済ニュースや新聞を読むことはもちろん、専門書を読んだり、資格取得の勉強をしたりといった自己研鑽を、仕事と並行して続けていかなければなりません。
経済や社会の動きに対して常にアンテナを張り、「なぜこうなるんだろう?」「もっと知りたい」と感じられるような、知的好奇心が旺盛な人にとって、証券会社の仕事は非常に刺激的で面白いものに感じられるはずです。
高い倫理観と責任感を持てる人
証券会社は、顧客の大切な資産を預かり、時には企業の将来を左右するような重要な情報(インサイダー情報)にも触れる機会があります。
そのため、社員一人ひとりに極めて高い倫理観とコンプライアンス(法令遵守)意識が求められます。
自分の利益や会社の利益のために、顧客に不利益な取引を勧めたり、ルールを破ったりすることは絶対にあってはなりません。
「顧客の最善の利益のために行動する」という誠実さと、「社会のインフラを支えている」という強い責任感を持って仕事に取り組める人でなければ、顧客からも市場からも信頼を得ることはできません。
真面目で、ルールをきっちり守れる誠実な人こそが、最終的にこの業界で長く活躍できるのです。
コミュニケーション能力と交渉力が高い人
証券会社の仕事の多くは、対人折衝です。
リテール営業であれば、顧客のニーズを深く理解し、複雑な金融商品を分かりやすく説明する能力が必要です。
ホールセール営業や投資銀行バンカーであれば、プロの投資家や企業の経営トップといった手強い相手とも対等に渡り合い、自社の提案を受け入れてもらうための高度な交渉力が求められます。
また、社内においても、リサーチ部門やバックオフィス部門など、様々な部署と連携しながら仕事を進める必要があるため、円滑な人間関係を築くコミュニケーション能力は必須です。
単に話が上手いということではなく、相手の立場や意図を正確に汲み取り、論理的に自分の意見を伝え、相手を動かす力が重要になります。
【証券会社やめとけ】証券会社に向いていない人
一方で、証券会社の特性がどうしても自分の性格や価値観と合わない、という人も当然います。
先ほど挙げた「向いている人」の特徴と逆のタイプ、と言えば分かりやすいかもしれません。
「やめとけ」と言われる厳しい側面が、自分にとって許容範囲を超えてしまうと感じる場合は、無理に目指す必要はありません。
自分の適性に合わない環境で働くことは、自分自身を苦しめることになってしまいます。
入社後のミスマッチを避けるためにも、どのような人が証券会社に向いていないのか、その特徴をしっかり理解しておきましょう。
プレッシャーに弱く、精神的に落ち込みやすい人
証券会社は、日常的にノルマや成果、顧客からのクレームといった強いプレッシャーにさらされる環境です。
数字が未達だった時に上司から厳しく叱責されたり、顧客に損失を出させてしまったりした際に、それを重く受け止めすぎてしまい、精神的に落ち込んでしまう人は注意が必要です。
もちろん、反省は必要ですが、その失敗を引きずって次の行動に移せないと、この業界で働き続けるのは難しいかもしれません。
ストレスを感じると体調を崩しやすい、一度落ち込むとなかなか立ち直れない、人からの評価を気にしすぎる、といった自覚がある人は、証券会社のストレスフルな環境が合わない可能性が高いです。
数字や成果よりもプロセスを重視したい人
「結果(数字)が全て」という成果主義の文化が証券会社の特徴です。
もちろん、成果を出すためのプロセス(行動量や工夫)も評価されないわけではありませんが、最終的には「ノルマを達成したか否か」が最も重視されます。
そのため、「たとえ結果が出なくても、頑張った過程を認めてほしい」「チームで協力しながら、じっくりと物事を進めたい」といった価値観を強く持っている人にとっては、違和感を覚える場面が多いかもしれません。
競争よりも協調を重んじるタイプや、目先の数字よりも長期的な視点でのやりがいを最優先したい人は、他の業界の方が自分の良さを発揮できる可能性があります。
安定志antiでワークライフバランスを最優先したい人
証券業界は、景気の変動や市場の動向によって業績が大きく左右されるため、必ずしも「安定」しているとは言えません。
また、先述の通り、早朝からの情報収集や顧客対応、大型案件の対応などで長時間労働になりやすい傾向があります。
もちろん、近年は働き方改革が進み、以前よりは改善されていますが、それでも他の業界と比べるとハードワークであることは否めません。
「絶対に定時で帰りたい」「プライベートの時間を何よりも大切にしたい」というワークライフバランスを最優先する人にとっては、証券会社の働き方はミスマッチになる可能性が高いでしょう。
お金や経済の動きに興味が持てない人
証券会社の仕事は、良くも悪くも「お金」と「経済」に直結しています。
日々のニュースで報じられる株価の変動や金利の動向、企業の業績などに全く興味が持てないという人にとっては、この仕事は苦痛でしかないでしょう。
お客様に金融商品を提案するにも、経済の動向をリサーチするにも、その背景にある経済の仕組みや社会情勢への理解が不可欠です。
また、常に新しい情報を学び続ける必要があるため、そもそも経済や金融に対する知的好奇心がなければ、知識のインプット自体が大きな負担になってしまいます。
普段から経済ニュースを全く見ない、お金儲けの話に嫌悪感がある、という人は、正直なところ向いていないと言わざるを得ません。
ルーティンワークを好む人
証券会社の仕事は、市場の変動や顧客のニーズ、法改正など、常に変化にさらされています。
昨日まで正しかった戦略が、今日には通用しなくなることも珍しくありません。
そのため、毎日決まった手順で、決まった作業をこなす「ルーティンワーク」を好む人には不向きな環境です。
むしろ、変化を予測し、その変化に柔軟に対応しながら、常に新しい知識や手法を取り入れていく必要があります。
安定した環境で、マニュアル通りの仕事を正確にこなしたいという志向性の人は、証券会社の目まぐるしい変化のスピードについていくのが難しいかもしれません。
証券会社に行くためにすべきこと
証券会社の厳しい側面を理解した上で、それでも「挑戦したい!」と決意した方もいるでしょう。
その覚悟は非常に素晴らしいです。
証券会社は、高い専門性とタフさが求められる分、新卒で入社できれば非常に速いスピードで成長できる環境であることも事実です。
では、証券会社の内定を勝ち取るためには、学生時代にどのような準備をしておくべきでしょうか。
ここでは、選考を有利に進めるために、特に重要となる4つの対策について解説します。
ライバルに差をつけるためにも、できることから始めてみましょう。
経済・金融の基礎知識と時事ニュースの習得
証券会社の選考では、面接やグループディスカッションで、最近の経済ニュースについて意見を求められることが非常に多いです。
例えば、「最近気になる経済ニュースは?」「日経平均株価が上昇している要因は何だと思う?」といった質問です。
これらに答えるためには、付け焼き刃の知識では通用しません。
まずは、経済学部でなくても、金融や経済の入門書を1冊読んでみることをお勧めします。
その上で、日本経済新聞(日経新聞)の電子版などに毎日目を通し、世の中の動きにアンテナを張る習慣をつけましょう。
単にニュースを知っているだけでなく、「自分はこう思う」という自分なりの考えを整理しておくことが大切です。
証券外務員資格の取得(または学習)
証券外務員資格は、証券会社に入社して金融商品の営業活動を行うために必須となる資格です。
実は、この資格は学生のうちに取得することも可能です(一種・二種)。
選考の時点で必須としている企業は稀ですが、もし取得していれば、志望度の高さと入社後の即戦力性をアピールする強力な材料になります。
また、仮に取得まで至らなくても、「現在、証券外務員資格の取得に向けて勉強中です」と伝えるだけでも、業界への本気度を示すことができます。
資格の勉強を通じて、金融商品の基本的な仕組みや関連法規を学べるため、業界研究が深まるというメリットもあります。
インターンシップへの参加と企業研究
証券会社の仕事は、外から見ているだけではなかなか実態が掴みにくいものです。
そこで強くお勧めしたいのが、インターンシップへの参加です。
特に、営業職の仕事を体験できるようなプログラムに参加すれば、社員の方の雰囲気や仕事の進め方、職場のリアルな空気感を肌で感じることができます。
「きつい」と言われる側面も含めて、自分に合うかどうかを判断する絶好の機会です。
また、企業研究も重要です。
野村證券、大和証券といった独立系大手、SMBC日興証券などの銀行系、SBI証券などのネット系など、証券会社によって強みや社風は全く異なります。
「なぜ他の証券会社ではなく、御社なのか」を明確に言えるよう、各社の特徴を徹底的に比較分析しておきましょう。
「なぜ証券会社か」を深掘りした志望動機作成
証券会社の面接官が最も知りたいのは、「なぜ、きついと分かっていながらも、銀行や保険ではなく、あえて証券会社を志望するのか?」という点です。
「給料が高いから」「成長できそうだから」といった漠然とした理由だけでは、間違いなく選考を通過できません。
自分自身の過去の経験(例えば、部活動で高い目標を達成した経験、アルバイトで数字にこだわった経験など)と結びつけ、「証券会社の○○という仕事を通じて、社会の△△という課題を解決したい」といった具体的なロジックを組み立てる必要があります。
成果主義の厳しさやプレッシャーを受け入れた上で、それでも成し遂げたいことは何か、自己分析を徹底的に深掘りして、あなただけの志望動機を練り上げてください。
【証券会社やめとけ】適性がわからないときは
ここまで証券会社のリアルな姿を解説してきましたが、「きつい面も分かったけれど、結局自分に向いているのかどうか、まだ確信が持てない…」と悩んでいる方もいるかもしれませんね。
それは当然の悩みです。
就職活動は、自分でも知らなかった自分の可能性や適性を見つける旅でもあります。
もし適性がわからないと不安に感じたら、一度立ち止まって、客観的な視点で自分を見つめ直してみるのがおすすめです。
例えば、Digmediaが提供しているような「適職診断ツール」を活用してみるのも一つの手です。
いくつかの質問に答えるだけで、あなたの性格や価値観がどのような仕事に向いているのか、統計的に示してくれます。
証券会社が向いているという結果が出るかもしれませんし、意外にもっと別の業界に適性があることが分かるかもしれません。
また、自己分析をもう一度やり直してみることも重要です。
「なぜ」を5回繰り返すような深掘りや、友人や家族に「私ってどんな人間に見える?」と他己分析をお願いしてみるのも良いでしょう。
自分一人で抱え込まず、ツールや周りの人の力を借りながら、自分の軸を明確にしていくことが、後悔しない企業選びにつながりますよ。
おわりに
「証券会社はやめとけ」という言葉の裏にある、仕事の厳しさと、それを上回るやりがいや成長環境について、理解を深めていただけたでしょうか。
証券会社は、確かにタフさが求められる職場ですが、日本の経済を根幹から支えるという大きな使命と、成果が正当に評価されるダイナミズムを持った魅力的な業界でもあります。
大切なのは、情報を鵜呑みにするのではなく、その実態を理解した上で、「自分はそこで挑戦したいのか」を真剣に考えることです。
この記事が、あなたの業界研究と自己分析の一助となれば幸いです。
あなたの就職活動を心から応援しています。