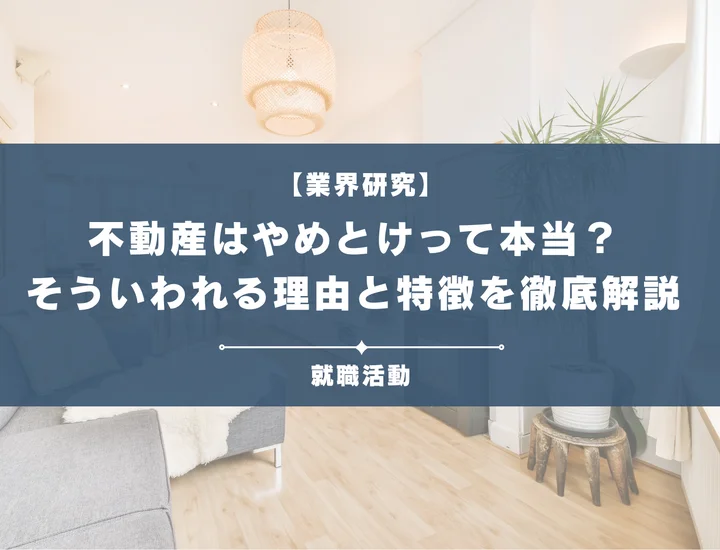HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
就職活動、順調に進んでいますか?業界研究を進める中で、「不動産業界」に興味を持った人も多いかもしれませんね。
ただ、ネットで検索すると「不動産業界 やめとけ」なんていう、ちょっと不安になるキーワードも目に入ってくるかと思います。
この記事では、そんな不動産業界のリアルな姿を、良い面も大変な面も包み隠さずお伝えしていきます。
目次[目次を全て表示する]
【不動産業界やめとけ】やめとけと言われるのは本当?
「不動産業界はやめとけ」という言葉、一度は耳にしたことがあるかもしれませんね。
これは、半分本当で半分は誤解、といったところでしょうか。
確かに、営業ノルマが厳しかったり、お休みが不規則だったり、扱う金額が大きいために責任が重かったりと、「きつい」と感じられる側面があるのは事実です。
でも、それはどの業界にも言えること。
不動産業界が特にそう言われやすいのは、良くも悪くも**「成果主義」がはっきりしている**ことや、お客様の「一生モノの買い物」に立ち会うプレッシャーがあるからかもしれません。
大切なのは、その「きつさ」の正体をしっかり理解すること。
そして、その先にあるやりがいや魅力が、自分にとって価値があるかどうかを見極めることです。
【不動産業界やめとけ】不動産業界の仕事内容
不動産業界と一口に言っても、その仕事内容は本当にさまざまです。
皆さんがパッと想像するのは、お部屋探しを手伝ってくれる「賃貸仲介」や、新築マンションを売る「販売」の営業かもしれませんね。
でも実は、それだけじゃないんです。
街のシンボルになるような大きなビルを企画・開発する仕事、すでにある建物の価値を維持・向上させる管理の仕事、土地を仕入れる仕事など、不動産という大きな資産を軸に、多岐にわたるビジネスが展開されています。
例えば、私たちが普段利用する商業施設も、オフィスビルも、住んでいるマンションも、すべて不動産業界の誰かの仕事によって成り立っています。
業界の全体像を知ることは、自分がどの分野で輝けるかを見つける第一歩です。
「やめとけ」という言葉の裏にある、多様な仕事を理解すれば、もしかしたら「これこそやりたい!」と思える分野に出会えるかもしれませんよ。
ここでは、代表的な4つの仕事内容を詳しく見ていきましょう。
開発(デベロッパー)
不動産業界の花形とも言われるのが、この「開発」の仕事です。
デベロッパーと呼ばれる企業が中心となり、ゼロから街づくりを仕掛けたり、大規模な再開発プロジェクトを手掛けたりします。
具体的には、まずプロジェクトのコンセプトを考え、そのために必要な土地を探して仕入れます(用地仕入)。
その後、どんな建物を建てるか設計会社と打ち合わせ、建設会社に工事を発注し、建物が完成するまでのスケジュールや予算を管理します。
完成後も、商業施設であればテナントを誘致したり、オフィスビルとして貸し出したりと、長期的な視点で街の価値を創造する仕事です。
非常にスケールが大きく、地図に残る仕事とも言われます。
その分、関わる人も多く、多額の資金が動くため、高度な調整能力とビジネスセンスが求められる、やりがいも責任も大きな仕事ですね。
販売(分譲マンション・戸建て)
これは、デベロッパーが開発した新築の分譲マンションや、ハウスメーカーが建てた新築の戸建て住宅をお客様に販売する仕事です。
モデルルームや住宅展示場に来場されたお客様に対して、物件の魅力や周辺環境、資金計画(住宅ローンなど)について詳しく説明し、購入の決断を後押しします。
お客様にとっては、人生で最も大きな買い物の一つになることがほとんど。
そのため、単に物件の知識が豊富なだけでなく、お客様のライフプランや将来の夢に寄り添い、不安を解消しながら信頼関係を築く力が不可欠です。
契約が成立した時の達成感はもちろんですが、お客様から「あなたのおかげで理想の住まいに出会えた」と感謝されることが、何よりのやりがいになるでしょう。
高額な商品を扱うため、成果がインセンティブ(報奨金)として給与に反映されやすいのも特徴です。
仲介(売買・賃貸)
「仲介」は、不動産を「売りたい人・貸したい人」と「買いたい人・借りたい人」を繋ぐ、橋渡し役の仕事です。
大きく分けて「売買仲介」と「賃貸仲介」の二つがあります。
売買仲介は、中古マンションや戸建て、土地などの売買をサポートします。
賃貸仲介は、アパートやマンションの賃貸物件を探しているお客様に、希望に合うお部屋を紹介し、契約までをサポートします。
皆さんが一人暮らしを始めるときにお世話になるのが、この賃貸仲介ですね。
どちらの仕事も、お客様のニーズを正確に把握するヒアリング能力や、多くの物件情報の中から最適な提案をする情報収集力・提案力が問われます。
特に売買仲介は、法律や税金などの専門知識も必要となり、お客様の資産に関わる責任の重い仕事です。
人と人を繋ぎ、新しい生活のスタートを支える、社会貢献性の高い仕事と言えます。
管理(ビル・マンション)
建物は、建てて終わりではありません。
その建物が安全で快適な状態を保ち、資産価値を維持・向上できるように管理・運営していくのが「管理」の仕事です。
具体的には、マンションの管理組合の運営をサポートしたり、オフィスビルのオーナーに代わってテナントの募集や賃料の交渉を行ったりします。
また、清掃、警備、設備の定期点検などの実務を行う会社を手配し、管理することも重要な役割です。
表舞台に立つ仕事ではありませんが、建物の「当たり前」を支える、非常に重要な仕事です。
何かトラブルが起きた際には迅速に対応する必要があり、多くの関係者と調整を行う場面も多いため、地道な努力と調整能力が求められます。
長期的に建物と向き合い、その価値を高めていくことにやりがいを感じる人に向いている分野ですね。
【不動産業界やめとけ】不動産業界の主な職種
不動産業界の仕事内容が見えてきたところで、次にそこで働く「職種」について具体的に見ていきましょう。
業界が多岐にわたる分、職種もさまざまです。
もちろん、最もイメージしやすいのは「営業職」でしょう。
お客様と直接関わり、契約を目指す、まさに不動産ビジネスの最前線です。
しかし、それ以外にも、プロジェクト全体を動かす「開発職」や、建物の価値を守る「管理職」、そして会社全体を支える「事務職」など、多様な専門性を持った人たちが活躍しています。
自分がどんな働き方をしたいのか、どんなスキルを活かしたいのかによって、選ぶべき職種は変わってきます。
例えば、人と話すのが得意なら営業職、コツコツと物事を進めるのが得意なら管理職や事務職、大きなプロジェクトを動かしたいなら開発職、といった具合です。
自分の強みとキャリアプランを照らし合わせながら、どの職種が自分に合っているか考えてみてください。
営業職(カウンターセールス・法人営業)
不動産業界の営業職は、主に個人のお客様に対応する「カウンターセールス(BtoC)」と、企業を相手にする「法人営業(BtoB)」に分かれます。
カウンターセールスは、賃貸仲介の店舗でお部屋探しをしたり、モデルルームで新築マンションを販売したりする仕事です。
お客様の夢や希望を直接聞き、実現するお手伝いをします。
一方、法人営業は、オフィスビルのテナント誘致、企業向けの不動産売買仲介、不動産活用のコンサルティングなどを行います。
扱う金額が非常に大きくなることも多く、企業の経営戦略に関わる提案をすることもあります。
どちらの営業も、成果が給与に直結しやすい「インセンティブ制度」を導入している企業が多く、実力次第で若いうちから高収入を目指せるのが大きな魅力です。
ただし、その分、成果に対するプレッシャーも大きい職種と言えます。
開発職(用地仕入・企画)
開発職は、デベロッパーなどで活躍する職種で、街づくりや大規模プロジェクトの起点となる仕事です。
中心的な業務は「用地仕入」と「企画」です。
用地仕入は、マンションや商業施設を建てるための土地を探し出し、地権者(土地の持ち主)と交渉して土地を購入する仕事です。
情報収集力や粘り強い交渉力が求められます。
企画は、仕入れた土地にどのような建物を建てれば収益が最大化するか、市場のニーズや将来性を見据えてコンセプトを立案する仕事です。
設計事務所や建設会社など、多くの専門家と協力しながらプロジェクトを推進していくため、リーダーシップや高度な調整能力が必要とされます。
自分のアイデアが形になり、街の風景を創り出していくスケールの大きな仕事であり、大きなやりがいを感じられる職種です。
管理職(プロパティマネジメント)
ここでの「管理職」とは、役職のことではなく、「プロパティマネジメント(PM)」と呼ばれる専門職種のことです。
主な仕事は、オーナー(ビルの持ち主)から委託を受けて、オフィスビルや商業施設、マンションなどの収益性を最大化するために運営・管理することです。
具体的には、テナントの募集(リーシング)、賃料の交渉や契約管理、建物の修繕計画の立案、コスト削減の提案など、経営的な視点を持って不動産を運営します。
オーナーへの報告や提案、テナントとの交渉、清掃や警備など実務を行う協力会社との調整など、関わる相手が非常に多いのが特徴です。
地道な管理業務と経営的な戦略立案の両方が求められる、専門性の高い職種です。
安定した収益を生み出し、不動産の資産価値を守り高める、縁の下の力持ち的な存在ですね。
事務職(営業サポート・バックオフィス)
不動産業界の事務職も、他の業界と同様に重要な役割を担っています。
大きく分けると、営業担当者のサポートを行う「営業事務(営業サポート)」と、会社全体の運営を支える「バックオフィス」があります。
営業事務は、物件情報のデータ入力、契約書類の作成、お客様からの電話応対など、多忙な営業担当者がスムーズに仕事を進められるようサポートします。
不動産特有の専門用語や契約の流れを理解する必要があり、縁の下の力持ちとして営業成果に貢献します。
バックオフィスは、人事、総務、経理、法務など、会社組織に不可欠な機能です。
特に不動産業界では、扱う金額が大きく、法律(宅建業法など)も複雑なため、経理や法務の専門知識が非常に重要とされます。
どちらも、正確な事務処理能力と、社内外との円滑なコミュニケーション能力が求められる職種です。
【不動産業界やめとけ】不動産業界がきついとされる理由
さて、ここからは「やめとけ」と言われる理由、つまり不動産業界の「きつい」とされる側面について、具体的に掘り下げていきます。
業界研究では、キラキラした面だけでなく、こうしたリアルな部分を知っておくことが、入社後のミスマッチを防ぐために非常に重要です。
「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためにも、しっかりと目を通してください。
不動産業界の厳しさは、主に「成果主義」「時間的な拘束」「専門知識の習得」の3つの側面に集約されることが多いです。
ただし、これらは裏を返けば「成長できる環境」や「高収入の可能性」にも繋がっています。
自分にとって、それが乗り越えられる「壁」なのか、それとも耐え難い「デメリット」なのか。
自分の価値観と照らし合わせながら、冷静に判断する材料にしてくださいね。
営業ノルマが厳しい
不動産業界、特に営業職において「きつい」と言われる最大の理由が、この「営業ノルマ」でしょう。
多くの不動産会社では、月ごとや四半期ごとに、契約件数や売上金額の目標(ノルマ)が設定されています。
賃貸仲介であれば「月〇件の契約」、売買仲介や販売であれば「〇円の売上」といった具合です。
このノルマの達成度が、給与(インセンティブ)や昇進に直結するため、常に数字に追われるプレッシャーがあります。
目標を達成できなければ、上司からの厳しい指導があったり、給与がなかなか上がらなかったりすることも。
成果がはっきりと数字で表れるため、精神的なタフさが求められるのは間違いありません。
ただ、裏を返けば、成果を出せば出すだけ評価され、若くして高いポジションや高収入を得られる可能性も秘めているということです。
休日が不規則(土日出勤)
不動産業界、特に個人のお客様を相手にする賃貸仲介や売買仲介、新築販売の営業職は、土日祝日が主な勤務日となります。
なぜなら、お客様が物件の内見やお部屋探しのために動けるのが、週末や休日だからです。
そのため、休日は「火曜日・水曜日」など、平日に設定されていることが一般的です。
友人と予定が合わせにくくなったり、土日開催のイベントに参加しにくくなったりすることは覚悟しておく必要があります。
また、お客様の都合に合わせて、平日の夜遅くに商談が入ったり、休日に急な対応が必要になったりすることもあります。
プライベートと仕事のバランスを重視する人や、カレンダー通りの休みを希望する人にとっては、この勤務形態が大きなネックになるかもしれません。
成果主義・実力主義の風土
不動産業界は、年功序列よりも「成果主義・実力主義」の風土が色濃い業界です。
これは、営業ノルマが厳しいこととも直結しています。
年齢や社歴に関わらず、営業成績が良い人が評価され、昇進し、高い給与を得ることができます。
20代で店長になったり、同年代の平均年収を大きく上回る収入を得たりすることも夢ではありません。
これは、上昇志向が強く、自分の実力で勝負したい人にとっては大きな魅力でしょう。
しかし、その反面、成果が出なければ評価されにくいというシビアな環境でもあります。
同期がどんどん昇進していく中で、自分だけが取り残されるといった焦りを感じることもあるかもしれません。
安定した環境でコツコツと働きたい人にとっては、プレッシャーに感じる場面が多いでしょう。
覚えるべき専門知識が多い
不動産は、非常に専門性の高い分野です。
お客様の大切な資産や生活を扱うため、営業担当者も幅広い知識を身につける必要があります。
例えば、物件の知識はもちろん、「宅地建物取引業法(宅建業法)」や民法、建築基準法といった法律の知識は必須です。
また、売買仲介や販売では、住宅ローンに関する金融知識や、不動産取得税・固定資産税といった税金の知識も求められます。
これらの専門知識は、一度覚えれば終わりではなく、法改正や税制改正に合わせて常に最新情報を学び続ける「アップデート」が必要です。
入社後も、休日や業務時間外に勉強する努力が求められるでしょう。
知的好奇心旺盛な人には向いていますが、勉強が苦手な人にとっては、この継続的な学習が大きな負担になるかもしれません。
クレーム対応など精神的負担
不動産の仕事は、お客様の人生の大きな決断に関わる仕事です。
扱う金額が数千万円、時には数億円と非常に大きいため、お客様の期待も大きく、それだけ責任も重くなります。
例えば、賃貸では「入居してみたら設備が壊れていた」、売買では「聞いていた話と違う欠陥が見つかった」など、契約後にトラブルが発生することもゼロではありません。
また、高額な買い物であるがゆえに、お客様の要望が細かかったり、交渉がシビアになったりすることも日常茶飯事です。
こうしたお客様からのクレームや厳しい要求に、冷静かつ誠実に対応する精神的な強さが求められます。
人の感情に左右されやすい人や、プレッシャーに弱い人にとっては、こうした精神的な負担が「きつい」と感じる大きな要因になるでしょう。
不動産業界の現状・課題
不動産業界の「きつさ」を理解したところで、次はもう少し視野を広げて、業界全体の「今」と「これから」を見ていきましょう。
どんな業界にも、追い風と向かい風があります。
不動産業界は、私たちの生活に欠かせない「衣食住」の一つを担う重要な産業ですが、社会の変化とともに大きな変革期を迎えています。
例えば、皆さんもニュースで耳にする「少子高齢化」や「人口減少」は、不動産業界にとって非常に大きなテーマです。
また、デジタル技術の進化は、古い慣習が残ると言われてきたこの業界にも、確実に変化をもたらしています。
こうした現状や課題を理解しておくことは、皆さんが業界で長期的に活躍していくための「地図」を手に入れるようなものです。
ここでは、特に重要な3つのポイントに絞って解説しますね。
人口減少と空き家問題
日本が直面している最大の課題の一つが「人口減少」と、それに伴う「少子高齢化」です。
人が減れば、当然ながら必要とされる住宅の数も減っていきます。
特に地方都市では、この影響が顕著に表れ始めており、全国的に「空き家」が増加していることが深刻な社会問題となっています。
総務省の調査では、全国の空き家は約849万戸(2018年時点)にも上り、今後も増加が見込まれています。
これまでの不動産業界は、新しい建物をどんどん建てて供給する「フロー型」のビジネスが中心でしたが、これからはそうはいきません。
今ある建物をどう活用していくか、どうすれば空き家を減らせるか、という「ストック型」の視点がますます重要になってきています。
これは業界にとって大きな課題であると同時に、新しいビジネスチャンスが生まれる領域でもあります。
デジタル化(不動産テック)への対応
不動産業界は、他の業界に比べて「アナログ」な部分が多く残っていると言われてきました。
例えば、契約書は紙が当たり前、物件の案内は必ず現地に行く、といった慣習です。
しかし、近年では**「不動産テック(Real Estate Tech)」と呼ばれる、IT技術を活用した新しいサービス**が急速に普及しています。
例えば、VR(仮想現実)で物件を内見できる「VR内見」や、AIが最適な物件を提案してくれるサービス、インターネット上で契約手続きが完結する「電子契約」などです。
こうしたデジタル化の波は、業務を効率化するだけでなく、お客様の利便性を大きく向上させます。
この変化に対応できる企業と、旧態依然としたやり方に固執する企業とでは、今後の競争力に大きな差が開くでしょう。
就活生の皆さんにとっても、企業がどれだけDX(デジタルトランスフォーメーション)に積極的かは、将来性を測る重要な指標になります。
法律・税制改正への迅速な対応
不動産ビジネスは、法律や税制と密接に結びついています。
例えば、先ほども触れた「宅建業法」や「建築基準法」、そして不動産に関わる税金(固定資産税、不動産取得税、相続税など)です。
これらの法律や税制は、社会情勢や政策の変化に応じて、毎年のように改正が行われます。
例えば、住宅ローン減税の制度変更や、2024年から始まった相続登記の義務化などは、お客様の不動産取引に直接的な影響を与えます。
不動産会社は、これらの変化をいち早くキャッチアップし、正確な情報をお客様に提供する責任があります。
法改正への対応が遅れることは、企業の信頼を失うことにも繋がりかねません。
常に最新の情報を学び続ける姿勢が、業界全体として求められており、これが業界の「きつさ」の一因であると同時に、プロフェッショナルとしての専門性を高める要因にもなっています。
不動産業界の今後の動向
業界が抱える課題が見えてくると、「不動産業界って、将来性はあるの?」と不安になるかもしれませんね。
でも、安心してください。
課題があるということは、そこに新しいニーズやビジネスチャンスが生まれるということです。
不動産業界は、私たちの生活基盤を支える重要な産業であり、その役割がなくなることはありません。
ただし、その「形」は確実に変わっていきます。
人口が減る中で、ただ新しいものを作り続ける時代は終わりました。
これからは、IT技術を駆使して業務を効率化したり、今ある建物の価値を再発見して活用したり、あるいは日本の枠を超えて海外に目を向けたりと、より賢く、より柔軟な発想が求められます。
ここでは、不動産業界の「これから」を形作る、3つの重要なトレンドについて解説します。
DX化による業務効率化
不動産業界の今後の動向として、最も注目されているのが「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の進展です。
先ほどの「不動産テック」とも関連しますが、単にITツールを導入するだけでなく、ビジネスモデルそのものを変革していく動きが加速しています。
例えば、AIを活用した賃料査定や不動産価格の予測は、ベテラン営業マンの「勘」に頼っていた部分をデータで補完し、より精度の高い提案を可能にします。
また、顧客管理システム(CRM)を導入することで、お客様のニーズをきめ細かく把握し、長期的な関係性を築くことも容易になります。
こうしたDX化は、営業活動の効率化やコスト削減に直結します。
今後は、データをいかに活用できるかが企業の競争力を左右すると言っても過言ではありません。
ストック型社会への移行(リノベーション市場)
「フロー(新築供給)からストック(既存住宅の活用)へ」という流れは、今後の不動産業界を語る上で欠かせないキーワードです。
人口減少と空き家問題という課題に対し、今ある建物を修理・改修して長く使い続ける「リノベーション」や「リフォーム」の市場が非常に活発になっています。
古いマンションや戸建てを購入し、自分好みの内装に全面的に作り変えるといったニーズは、特に若い世代で高まっています。
また、単に綺麗にするだけでなく、耐震性を高めたり、断熱性能を向上させて省エネ化したりと、建物の「付加価値」を高める提案が重要です。
新築の販売・仲介だけでなく、このリノベーション市場に強みを持つ企業は、今後ますます存在感を増していくでしょう。
Z世代の価値観と住まい
皆さんのような「Z世代」の価値観の変化も、不動産業界に影響を与えています。
かつては「マイホームを持つこと」が大きな目標でしたが、現代では「所有」よりも「利用」を重視するシェアリングエコノミーの考え方が広まっています。
例えば、家具・家電付きのサブスクリプション型住居や、コワーキングスペースが併設されたシェアハウスなど、新しい形の住まい方が次々と登場しています。
また、環境への配慮(サステナビリティ)を重視する傾向も強く、省エネ性能の高い住宅(ZEH:ゼッチなど)への関心も高まっています。
不動産業界は、こうした新しい世代のライフスタイルや価値観を敏感に察知し、それに応える商品やサービスを開発していく必要があります。
【不動産業界やめとけ】不動産業界に向いている人
ここまで、不動産業界の仕事内容、きつい側面、そして将来性について詳しく見てきました。
さまざまな側面を知った上で、「もしかしたら自分にもできるかも?」あるいは「やっぱり大変そう…」と感じたかもしれませんね。
業界の特性が、自分の性格や価値観と「合う」か「合わない」かは、長く働き続ける上で非常に重要です。
「やめとけ」と言われる業界でも、水が合う人にとっては、これ以上ないほどやりがいを感じられる場所になります。
逆に、どんなに人気のある業界でも、合わない人にとっては苦痛になってしまいます。
ここでは、不動産業界、特に営業職などを中心に、「こんな人が向いている!」という特徴を5つ挙げてみます。
自分がいくつ当てはまるか、チェックしてみてくださいね。
高いコミュニケーション能力を持つ人
不動産業界の仕事、特に営業や開発、管理の仕事は、常識にとらわれず多様な人々と関わることが求められます。
お客様はもちろん、物件のオーナー、地権者、設計会社、建設会社、金融機関、弁護士や司法書士といった専門家まで、その相手は多岐にわたります。
年齢や立場、価値観もさまざまな人たちと信頼関係を築き、時には利害関係を調整し、交渉をまとめ上げなければなりません。
単に「話すのが得意」というだけでなく、相手のニーズを正確に汲み取る「聞く力」や、難しい専門用語を分かりやすく伝える「説明力」、そして何より「この人なら任せられる」と思わせる誠実さや人柄が重要です。
人と接することが好きで、異なる意見を調整することにやりがいを感じる人には最適の環境です。
成果が正当に評価されたい人
不動産業界は、成果主義・実力主義の風土が強いと説明しました。
これは、「自分の頑張りが、給与やポジションとして正当に評価されたい」と考える人にとっては、非常に魅力的な環境です。
年齢や社歴に関係なく、成果を出せばインセンティブ(報奨金)として給与に反映されますし、昇進のスピードも早いです。
若いうちから責任ある仕事を任されたり、高収入を実現したりすることも夢ではありません。
「安定」よりも「挑戦」を好み、数字という明確な結果で自分の価値を証明したいという強い上昇志向を持つ人にとって、不動産業界は格好の舞台となるでしょう。
逆に、安定した給与や年功序列の環境を好む人には、プレッシャーに感じるかもしれません。
知的好奇心が高く、勉強熱心な人
不動産業界でプロフェッショナルとして活躍するためには、継続的な学習が不可欠です。
法律(宅建業法、民法など)、税金(固定資産税、相続税など)、金融(住宅ローン)、建築など、覚えるべき専門知識の範囲は非常に広いです。
さらに、これらの法律や制度は頻繁に改正されるため、常に最新情報をキャッチアップし続ける必要があります。
お客様の数千万円もの資産を扱う仕事ですから、「知りませんでした」では済まされません。
知的好奇心が高く、新しい知識を学ぶことに喜びを感じる人、あるいは自分の専門性を高めるために努力を惜しまない勉強熱心な人でないと、この業界で長く活躍するのは難しいでしょう。
学生時代に「宅建(宅地建物取引士)」の勉強を始めてみるのも、適性を見る良い試金石になりますよ。
ストレス耐性が高く、切り替えが早い人
不動産業界の仕事、特に営業職は、プレッシャーとの戦いでもあります。
営業ノルマへのプレッシャーはもちろん、お客様からのクレームや厳しい要求、あるいは大きな金額を扱うことへのプレッシャーなど、精神的な負荷がかかる場面は少なくありません。
また、契約が直前でキャンセルになるなど、自分の努力ではどうにもならない事態に直面することもあります。
そうした時に、落ち込んだまま引きずってしまうのではなく、「仕方ない、次!」と気持ちを素早く切り替えられるタフさが求められます。
ストレス耐性が高く、困難な状況でも冷静さを失わずに前向きに行動できる人は、この業界で大きく成長できる可能性を秘めています。
【不動産業界やめとけ】不動産業界に向いていない人
「向いている人」の特徴を見て、自分には当てはまらないかも…と感じた人もいるかもしれませんね。
それは決して悪いことではなく、自分に合わない環境を早期に知ることも、就職活動では非常に大切なことです。
無理して合わない業界に入っても、結局は自分も会社も不幸になってしまいますから。
ここでは、逆に「不動産業界にはあまり向いていないかもしれない人」の特徴を挙げてみます。
「向いている人」の裏返しになる部分も多いですが、改めて自分自身の性格や希望する働き方と比べてみてください。
これらの特徴に多く当てはまるからといって、絶対にダメというわけではありませんが、入社後に苦労する可能性が高いことは覚悟しておいた方が良いかもしれません。
安定志向で、ノルマが苦手な人
不動産業界は「成果主義」が基本です。
毎月の営業ノルマ(目標)が設定され、その達成度が評価や給与に直結します。
そのため、常に数字に追われる環境が苦手な人や、競争することに強いストレスを感じる人には、厳しい環境かもしれません。
「給与はそこそこで良いから、精神的なプレッシャーなく安定して働きたい」「成果よりも、頑張ったプロセスを評価してほしい」といった安定志向や協調性を重視する人は、ノルマ達成が最優先される風土に馴染めず、苦しさを感じる可能性があります。
もちろん、不動産業界の中にも事務職など、比較的ノルマのプレッシャーが少ない職種もありますが、営業職を目指す場合は特に注意が必要です。
土日祝日をしっかり休みたい人
これは非常に分かりやすいポイントですね。
先にも述べた通り、不動産の営業職(特に個人向け)は、お客様の都合に合わせて土日祝日に働くのが基本で、休みは平日(火・水など)になることがほとんどです。
そのため、「友人と休みを合わせて遊びたい」「家族との時間は土日に確保したい」「カレンダー通りの休みじゃないと嫌だ」という人には、働き続けるのが難しい業界です。
また、お客様の都合で休日に電話がかかってきたり、急な対応が必要になったりすることもあります。
プライベートの時間と仕事の時間をきっちり分けたい、という価値観を強く持っている人にとっては、大きなストレス源になるでしょう。
顧客との深い関係構築が苦手な人
不動産の仕事は、高額な商品を扱うがゆえに、お客様との関係性が非常に重要です。
「物件が良いから買う」だけでなく、「この人が言うなら信頼できるから買う」という側面が非常に強いのです。
そのためには、お客様の家族構成や将来の夢、時にはお金の話まで、深く踏み込んだコミュニケーションが必要になります。
初対面の人とでも臆せず、相手の懐に飛び込んで信頼関係を築いていく力が求められます。
人と話すのは好きでも、表面的な付き合いは得意だが、深く関わるのは苦手という人や、お客様の人生に深く踏み込むことに抵抗がある人は、営業職としては成果を出しにくいかもしれません。
ルーティンワークを好む人
不動産業界の仕事は、毎日が変化と挑戦の連続です。
特に営業職は、日々新しいお客様と出会い、異なる物件を扱い、時には予期せぬトラブルにも対応しなければなりません。
また、開発職も、プロジェクトごとに条件が全く異なり、常に新しい課題解決が求められます。
「毎日同じ時間に会社に来て、決められた作業を淡々とこなしたい」といったルーティンワークを好む人にとっては、変化が激しく、常に臨機応変な対応が求められる不動産の仕事は、疲弊してしまうかもしれません。
逆に言えば、マニュアル通りの仕事ではなく、自分の裁量で工夫しながら仕事を進めたい人にとっては、非常に刺激的な環境と言えますね。
不動産業界に行くためにすべきこと
ここまで読んでみて、「きつい部分もあるけれど、やっぱり不動産業界に挑戦してみたい!」と感じた方へ。
その決意を、心から応援します!不動産業界は、大変な分だけ、大きなやりがいと成長が得られる場所です。
では、夢を実現するために、学生のうちから何をしておくべきでしょうか。
不動産業界の選考では、他の業界と同様に「なぜ、うちの会社なのか」に加えて、「なぜ、不動産業界なのか」を深く問われます。
「やめとけ」と言われることも多い業界だからこそ、「それでも自分はこの業界で働きたい」という熱意と覚悟を、具体的な行動で示すことが重要です。
ここでは、選考を有利に進めるために、ぜひ取り組んでほしい3つのことを紹介します。
業界研究と企業研究の徹底
まずは基本中の基本ですが、業界研究と企業研究を徹底的に行いましょう。
「不動産業界」と一口に言っても、**「開発(デベロッパー)」「販売」「仲介」「管理」**など、ビジネスモデルは全く異なります。
三井不動産や三菱地所のような総合デベロッパーを目指すのか、オープンハウスグループのような販売・仲介に強みを持つ会社なのか、あるいは大東建託のような賃貸管理がメインの会社なのか。
自分がどの分野に興味があるのかを明確にし、それぞれの分野でトップを走る企業の特徴や強み、社風などを徹底的に比較してください。
企業のIR情報(投資家向け情報)や中期経営計画に目を通すと、その会社が今何に力を入れ、将来どこを目指しているのかが分かり、志望動機を深めるのに非常に役立ちますよ。
「宅建」資格の勉強
不動産業界への就職において、最も強力な武器の一つが**「宅地建物取引士(宅建)」**の資格です。
これは不動産取引の専門家であることを証明する国家資格で、宅建業法上、不動産会社は従業員の5人に1人以上の割合で宅建士を設置する義務があります。
そのため、企業側も宅建取得者や、取得見込みの学生を高く評価します。
学生のうちに取得しておけば、入社への熱意と、法律などを学ぶ知的能力を同時にアピールできます。
合格率は15〜17%程度と難関ですが、それだけに価値があります。
仮に選考までに合格できなくても、「合格を目指して勉強中です」と伝えるだけでも、本気度を示す材料になります。
まずはテキストを買って、独学でも勉強を始めてみることを強くお勧めします。
長期インターンシップへの参加
もし可能であれば、不動産会社の長期インターンシップに参加してみましょう。
1dayや数日間の短期インターンでは、会社説明やグループワークが中心で、リアルな仕事内容までは分かりにくいものです。
しかし、数ヶ月単位の長期インターンであれば、営業同行や実際の事務作業など、社員に近い立場で仕事を体験できる可能性があります。
そこで、自分が「向いている人」の特徴に当てはまるか、あるいは「きつい理由」として挙げたことに耐えられそうか、肌で感じることができるはずです。
また、「なぜ自分は不動産業界で働きたいのか」という志望動機も、実体験に基づいた、より説得力のあるものになるでしょう。
机上の空論ではない、自分だけのリアルなエピソードは、面接で何よりの強みになりますよ。
【不動産業界やめとけ】適性がわからないときは
ここまで不動産業界のリアルな姿をお伝えしてきましたが、「向いているとも思うし、向いていないとも思う…」「結局、自分がこの業界でやっていけるのか自信がない」と悩んでしまう人もいるかもしれませんね。
それは当然のことです。
まだ働いた経験がないのですから、自分の「適性」がどこにあるかなんて、分からなくて当たり前です。
そんな時は、一人で抱え込まずに、客観的な視点を取り入れることをお勧めします。
例えば、Digmediaが提供しているような「適職診断ツール」を活用してみるのも一つの手です。
いくつかの質問に答えるだけで、自分の性格や価値観が、どんな仕事や業界に向いているのかを分析してくれます。
もちろん、診断結果が全てではありませんが、自分では気づかなかった強みや、意外な業界との相性が見えてくるかもしれません。
また、大学のキャリアセンターで相談したり、私たちのような就活アドバイザーに話してみたりするのも良いでしょう。
自己分析を深掘りすることで、自分が仕事に何を求めているのか(高収入か、安定か、やりがいか、ワークライフバランスか)という「軸」が明確になり、不動産業界が自分にとってベストな選択なのか判断しやすくなりますよ。
おわりに
「不動産業界はやめとけ」という言葉の裏にある、仕事の多様性、きつい側面、そして将来性まで、詳しく解説してきましたが、いかがでしたか?不動産業界は、確かに厳しい一面もありますが、人の人生に深く関わり、街を創り、大きな金額を動かすという、他では味わえないダイナミックなやりがいがある仕事です。
大切なのは、ネガティブな情報だけで判断停止するのではなく、その実態を正しく理解し、自分の価値観と照らし合わせること。
この記事が、あなたの業界研究の一助となり、後悔のない選択をするためのヒントになれば、これ以上嬉しいことはありません。
あなたの就職活動を、心から応援しています。