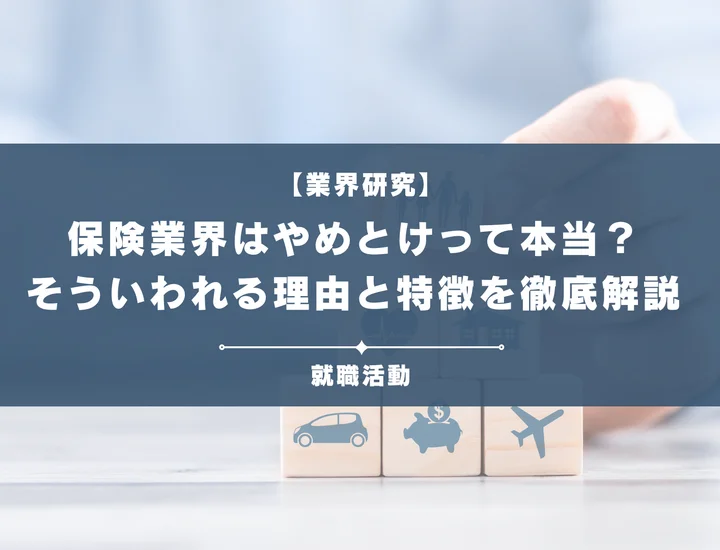HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
この記事では、この「就職偏差値」という切り口から、身近でありながら奥深い「文具業界」について徹底的に解説していきます!
目次[目次を全て表示する]
就職偏差値とは
就職偏差値とは、主にインターネット上で使われる、企業の入社難易度をランキング形式で示した俗語的な指標です。
予備校の偏差値になぞらえ、人気や選考の難しさなどから、就活生などが独自に作成・共有しています。
ただし、公的な統計データではなく、客観的な基準や根拠が明確でない主観的な評価も多いため、あくまで参考情報の一つとして捉えるのが一般的です。
文具業界の就職偏差値ランキング
それでは、さっそく文具業界の就職偏差値ランキングを見ていきましょう。
ノート、ペン、ファイルなど、私たちの生活に欠かせない製品を扱うこの業界には、安定した経営基盤を持つ優良企業が数多く存在します。
このランキングは、Digmedia編集部が各社の採用人気や事業規模、入社難易度などを総合的に判断して独自に作成したものです。
あなたの知らない優良企業が見つかるかもしれませんよ。
ただし、偏差値がすべてではないことも忘れずに、広い視野で企業研究を進めるきっかけにしてくださいね。
【文具業界】Aランク(就職偏差値70以上)
【70】スリーエムジャパン
ポスト・イットなどで知られる世界的な化学・電気素材メーカーです。
文具は事業のほんの一部であり、実質的には外資系トップメーカーとしての採用難易度です。
高い専門性や実績、ビジネスレベルの英語力、そしてグローバル企業で働くための論理的思考力が不可欠です。
【文具業界】Bランク(就職偏差値66以上)
Bランク以降の就職偏差値を見るには会員登録が必要です。
無料登録すると、Bランク以降の就職偏差値をはじめとした
会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。
登録はカンタン1分で完了します。会員登録をして今すぐ文具業界の就職偏差値をチェックしましょう!
【69】カシオ計算機 大塚商会
【68】コクヨ 日本能率協会マネジメントセンター
【67】三菱鉛筆 パイロットコーポレーション リシュモンジャパン(モンブラン部門)
【66】オカムラ アスクル
コクヨ、三菱鉛筆、パイロットといった業界のリーディングカンパニーに加え、大塚商会(オフィス商社)やオカムラ(オフィス家具)、カシオ(電子機器)など、文具・オフィス関連の大手が集結しています。
知名度、安定性、待遇いずれも高水準で、人気が集中します。
各社の文具事業以外(空間デザイン、ソリューション提案など)も含めた幅広い事業内容への深い理解と、そこで何を成し遂げたいかを明確に示す必要があります。
【文具業界】Cランク(就職偏差値61以上)
【65】ぺんてる 内田洋行
【64】ゼブラ イトーキ セメダイン バンダイナムコクラフト BICジャパン
【63】サクラクレパス キングジム シャチハタ ニチバン パイロットインキ
【62】トンボ鉛筆 ステッドラー日本 パイロットファインテック コクヨMVP コクヨ工業滋賀
【61】ナカバヤシ リヒトラブ キングコーポレーション
キングジム、ぺんてる、ゼブラ、サクラクレパスなど、特定分野で高いブランド力とシェアを持つ専門メーカーが中心です。
「この製品が好き」という学生も多く、倍率は高くなりがちです。
製品への愛着に加え、その製品がどのように市場に流通し、どのような戦略で売られているのか(BtoB、BtoC)を理解した上での志望動機が求められます。
【文具業界】Dランク(就職偏差値56以上)
【60】セーラー万年筆 マルマン サンスター文具
【59】全日本文具協会 プラチナ万年筆
【58】東京文具工業連盟 中部文具工業協同組合 大阪文具工業連盟 日本ノート ショウワノート
【57】セキセイ デザインフィル 兵庫ナカバヤシ 島根ナカバヤシ
【56】クツワ クラウングループ ユニオンケミカー カール事務器 馬印 オープン工業 マインドウェイブ
万年筆やノート、学童文具など、特定の製品カテゴリーで強みを持つ老舗・中堅企業や、業界団体、大手メーカーの地域生産拠点が並びます。
デザインフィル(ミドリ)のように、熱心なファンを持つ企業も含まれます。
就職活動の基本となる自己分析と企業研究を徹底することが重要です。
その企業の製品のどこに魅力を感じているのかを具体的に説明し、入社後の貢献意欲をアピールする必要があります。
【文具業界】Eランク(就職偏差値50以上)
【55】日本白墨工業 寺西化学工業 一ツ橋ノート ナガサワ文具センター
寺西化学工業(マジックインキ)や日本白墨工業(チョーク)など、ニッチな分野で圧倒的なシェアを持つBtoB主体のメーカーや、地域の有力な文具専門店が中心です。
全国的な知名度は高くなくても、業界内で確固たる地位を築く優良企業が多いのが特徴です。
企業の歴史や製品の強みを深く理解し、なぜそのニッチな分野で働きたいのかを明確に伝えることが、選考突破の鍵となります。
【文具業界】とは
「文具業界」と聞くと、皆さんは何を思い浮かべますか?ノートやペン、消しゴムなど、学生生活でお世話になったアイテムが頭に浮かぶかもしれませんね。
しかし、文具業界の守備範囲はそれだけにとどまりません。
オフィスで使われるファイルやコピー用紙、さらにはオフィス家具や空間デザインに至るまで、働く環境を支えるBtoB(法人向け)ビジネスも非常に大きな柱となっています。
BtoC(個人向け)とBtoB(法人向け)の両面から、私たちの「学び」と「働く」を支える、身近でありながら奥深い産業、それが文具業界です。
基本的な仕組み
文具業界の基本的なビジネスモデルは、製品がメーカーから消費者の手に届くまでの「流通」が鍵を握っています。
まず、「メーカー」(例:コクヨ、パイロットなど)が商品を企画・製造します。
次に、それらの商品は「卸売業者(問屋)」に集められ、そこから全国の「小売店」(文房具専門店、書店、スーパー、コンビニ、量販店など)に配送されます。
そして、私たち消費者が小売店の店頭で購入するという流れが伝統的な形です。
しかし近年は、メーカーが自社のECサイトで直接消費者に販売する「D2C」や、Amazonなどの大手ECプラットフォームでの販売が急速に拡大しています。
また、オフィス向け通販の「アスクル」や「カウネット(コクヨ系)」のように、BtoBに特化した流通網も確立されており、複雑な流通チャネルが共存しているのが特徴です。
主な役割と業務内容
文具メーカーには、多様な職種があります。
まず「商品企画・マーケティング」は、市場のトレンドや消費者の隠れたニーズを分析し、「こんな文具があったら便利だ」という新しい商品のアイディアを形にする仕事です。
次に「研究開発」は、より書きやすいインクや、より消しやすい消しゴムの素材など、製品の根幹となる技術を生み出します。
「デザイナー」は、商品の機能性だけでなく、見た目の美しさや使いやすさを追求し、魅力的なデザインを施します。
そして「営業」は、生み出された商品を卸売業者や小売店に提案し、一人でも多くの人に届けるための販売戦略を立て実行します。
BtoB営業の場合は、企業の総務担当者に対してオフィス環境全体のソリューション提案を行うこともあります。
この他にも、効率的な生産体制を管理する「生産管理」など、多くの専門家が関わって一つの商品が作られています。
文具業界のBtoBとBtoC
文具業界を理解する上で、BtoC(個人向け)とBtoB(法人向け)の違いを把握しておくことは非常に重要です。
BtoCは、私たちが普段文具店などで目にする、個人消費者向けのビジネスです。
この分野では、学生向けのヒット商品(例:消せるボールペン、高機能シャープペンシル)を生み出すためのトレンド分析やマーケティングが重要になります。
一方、BtoBは、企業や官公庁、学校などを対象としたビジネスです。
代表的なのは、コクヨなどが手掛けるオフィス家具や内装、システム構築を含む「オフィス空間のトータル提案」です。
また、アスクルのようなオフィス用品通販サービスもBtoBの代表例です。
この分野では、単に商品を売るのではなく、顧客の「業務効率化」や「コスト削減」といった課題を解決するソリューション提案力が求められます。
多くの大手文具メーカーは、この両方の側面を持っており、どちらに強みを持つ企業なのかを見極めることが企業研究の第一歩となります。
【文具業界】特徴
文具業界には、他の業界とは異なるいくつかの際立った特徴があります。
まず、筆記具やノートといった「定番商品」が多いため、景気変動の影響を受けにくく、需要が比較的安定している点が挙げられます。
その一方で、国内市場は少子化やデジタル化の影響を受け、「成熟市場」と言われています。
そのため、多くの企業が単なる「モノ」売りから、空間デザインやソリューション提案といった「コト」売りへとビジネスモデルの変革を迫られています。
また、日本の文具の品質は海外でも高く評価されており、グローバル展開を加速させている企業が多いのも、この業界の大きな特徴と言えるでしょう。
安定した需要と成熟市場
文具業界の最大の特徴は、需要が非常に安定していることです。
鉛筆やノート、ボールペンは、学生生活やビジネスシーンで必ず必要とされるため、景気が悪化しても需要がゼロになることはありません。
このような「ディフェンシブ産業」としての側面は、企業経営の安定性に直結し、就活生にとっても大きな魅力となります。
しかしその一方で、国内市場は少子化による学童人口の減少や、デジタル化の進展によるペーパーレス化の影響を受け、全体としては「成熟市場」となっています。
つまり、国内で爆発的に市場が成長することは期待しにくい状況です。
そのため、各社は「高くても欲しくなる」ような高付加価値商品の開発(例:高級筆記具、デザイン性の高い手帳)や、次に挙げるデジタル化への対応、海外展開などで、生き残りを図っています。
デジタル化との融合と競争
「ペーパーレス化」という言葉に象徴されるように、デジタル化の波は文具業界にとって大きな「脅威」であると同時に「チャンス」でもあります。
タブレット端末やスマートフォンの普及により、紙に書く機会が減っているのは事実です。
しかし、それに対抗するように、デジタルとアナログを融合させた新しい文具が次々と開発されています。
例えば、スマホで撮影するとキレイにデジタル化できるノートや、専用ペンで書いた内容がそのままデータ化されるスマートパッドなどです。
また、デジタル機器が普及したからこそ、「手書き」の良さ(思考の整理、記憶の定着)や、万年筆などで「書くこと自体を楽しむ」文化が再評価されている側面もあります。
デジタル化とどう共存し、新しい価値を生み出していくかが、現代の文具業界の大きなテーマとなっています。
グローバル展開の加速
成熟しつつある国内市場とは対照的に、多くの文具メーカーが活路を見出しているのが「海外市場」です。
特にアジア諸国では、経済成長に伴い教育熱が高まり、高品質な文具の需要が急増しています。
「Made in Japan」の文具は、「高品質・高機能・壊れにくい」として海外で絶大な人気を誇っており、例えばパイロットの「フリクション」やゼブラの「マイルドライナー」などは、世界的なヒット商品となっています。
三菱鉛筆やコクヨなども海外売上比率が高く、グローバル展開を積極的に進めています。
国内の安定した基盤を持ちつつも、成長市場である海外に挑戦できる環境は、グローバル志向の学生にとって大きな魅力と言えるでしょう。
【文具業界】向いている人
文具業界は、安定性やモノづくりへの関心から、毎年多くの就活生が志望する人気の業界です。
しかし、「文具が好き」という気持ちだけでは、内定を勝ち取り、入社後に活躍し続けるのは難しいかもしれません。
この業界で本当に輝けるのは、「好き」を原動力に、地道な努力を惜しまず、時代の変化を捉えて新しい価値を提案できる人です。
ここでは、文具業界の仕事、特に伝統的なメーカーで求められる人物像について、具体的な特徴を3つ挙げて解説します。
自分自身の強みと照らし合わせながら、読み進めてみてください。
モノづくりや企画に情熱を持てる人
文具は、私たちの日常に最も近い「モノ」の一つです。
だからこそ、その「モノ」自体に強いこだわりと情熱を持てる人が求められます。
「なぜこの商品は使いやすいのか」「もっとこうすれば便利になるはずだ」と、普段から消費者の目線で物事を考え、改善点を見つけるのが好きな人は、商品企画や開発の仕事で才能を発揮できる可能性が高いです。
また、文具は機能性だけでなく、デザインや世界観といった「感性」も非常に重要です。
トレンドや人々のライフスタイルの変化を敏感にキャッチし、「これが欲しかった!」と思わせるような新しいアイディアを形にすることにワクワクする人にとって、文具業界は最高の舞台となるでしょう。
地道な努力を継続できる人
文具業界は、一見すると華やかなヒット商品に目が行きがちですが、その裏側は非常に地道な活動によって支えられています。
特に営業職の場合、新規開拓よりも、既存の卸売業者や小売店を定期的に訪問し、新商品の案内や売り場のメンテナンス、在庫管理などを行う「ルート営業」が中心となるケースが多いです。
こうした仕事は、日々のコツコツとした信頼関係の構築が何よりも重要であり、すぐに大きな成果が出るとは限りません。
また、研究開発職も、望んだ成果が出るまで何度も実験を繰り返す粘り強さが求められます。
派手さよりも堅実さ、一発逆転よりも継続的な努力を大切にできる人が、文具業界では長く活躍できる傾向にあります。
変化に対応し、新しい価値を提案できる人
「安定」と「成熟」が特徴の文具業界ですが、現在は「デジタル化」という大きな変革期を迎えています。
ペーパーレス化が進む中で、「紙やペンの価値とは何か」が根本から問われています。
このような時代だからこそ、従来の常識にとらわれない柔軟な発想が不可欠です。
例えば、デジタルツールと文具をどう組み合わせるか、ECサイトでの新しい販売方法をどう確立するか、あるいは海外市場で日本の文具をどう広めていくか。
「文具=紙とペン」という枠組みを超え、学び方や働き方そのものを豊かにする新しい「価値」を提案しようと挑戦できる人こそ、これからの文具業界が本当に必要としている人材です。
【文具業界】向いていない人
一方で、文具業界の特性が、あなたのキャリアプランや働き方の希望と合わない可能性もあります。
ミスマッチは、入社後に「こんなはずじゃなかった」と後悔する最大の原因になります。
ここでは、あくまで「傾向として」文具業界の伝統的な企業風土と合わない可能性が高い人の特徴を3つ挙げます。
もちろん、これはあなたの適性を否定するものではなく、企業選びの軸を再確認するための一つの材料として、冷静に自己分析するために役立ててください。
大きな変化やスピード感を最優先する人
文具業界は、その安定性と引き換えに、比較的おだやかな企業風土を持つことが多いです。
IT業界やベンチャー企業のように、数ヶ月単位で事業環境が激変したり、ドラスティックな組織変更が頻繁に行われたりすることは稀です。
伝統的な商習慣や年功序列的な雰囲気が残っている企業も少なくありません。
そのため、「常に最先端の技術に触れていたい」「スピード感を持ってどんどん新しいことに挑戦したい」「若いうちから大きな裁量権が欲しい」という志向性が強い人は、業界のゆったりとした時間の流れや、意思決定のプロセスに、もどかしさや物足りなさを感じてしまう可能性があります。
BtoBのビジネスに興味が持てない人
「文具が好き」という志望動機で入社した学生が、最初に直面しやすいギャップがこれです。
多くの学生は、文具店の店頭に並ぶカラフルなBtoC(個人向け)商品をイメージして入社します。
しかし、多くの大手文具メーカーでは、売上の半分以上をオフィス家具や事務用品といったBtoB(法人向け)ビジネスが占めているケースが少なくありません。
BtoBの営業は、企業の総務担当者などに対して、コスト削減や業務効率化といった課題解決の提案が中心となります。
「かわいい文具の企画がしたい」という憧れだけで入社すると、地道な法人営業やオフィス家具の知識を覚えることに、興味を見出せないかもしれません。
国内市場だけで完結したい人
「安定した国内需要」は文具業界の魅力ですが、裏を返せば「国内市場は成熟している」ということです。
そのため、業界大手のほとんどが、成長の活路を「海外展開」に求めています。
日本の高品質な文具は海外で非常に人気があり、すでに海外売上比率が半分を超える企業も存在します。
総合職として入社した場合、本人の希望に関わらず、将来的に海外営業を担当したり、海外赴任を命じられたりする可能性は十分にあります。
「英語は苦手」「内向き志向で、慣れた日本でずっと働きたい」という考えが強い人にとっては、グローバル化のプレッシャーが負担になるかもしれません。
【文具業界】内定をもらうためのポイント
文具業界は、その安定性や製品の身近さから、BtoC消費財メーカーの中でも特に人気の高い業界です。
競争率が高いからこそ、「文具が好き」という熱意だけではライバルに差をつけることはできません。
大切なのは、その「好き」という気持ちを、いかに「ロジカルな志望動機」や「企業で活かせる強み」に変換できるかです。
ここでは、文具業界の内定をぐっと引き寄せるために、就活生が今すぐ取り組むべき具体的なポイントを、段階的に解説していきます。
徹底的な準備こそが、内定への一番の近道です。
なぜ文具業界か?を徹底的に深掘る(志望動機)
面接で最も重要視されるのが、志望動機です。
文具業界を志望する学生の多くが「文具が好きだから」と答えますが、採用担当者はその一歩先を聞きたがっています。
「なぜ、数ある消費財(食品、化粧品、日用品)の中で、文具でなければならないのか?」この問いに、自分の経験や価値観を交えて答える必要があります。
例えば、「デジタル化が進む現代だからこそ、手書きの持つ思考整理の価値を広めたい」「高品質な日本の文具を通して、海外の子供たちの教育環境を支援したい」など、あなた自身の「課題意識」と文具業界がどう結びつくかを明確にしましょう。
「好き」を「使命感」や「問題意識」に昇華させることが、説得力のある志望動機を作る鍵となります。
「好き」を「分析」に変える企業研究
「御社の消せるボールペン、愛用しています!」というアピールは、熱意は伝わりますが、それだけでは不十分です。
内定を掴む学生は、「なぜその商品がヒットしたのか」を自分なりに分析しています。
例えば、「他社製品と比較した際の優位性は何か」「どのようなターゲット層に、どのような機能が刺さったのか」「私なら、この技術を応用して次はこんな商品を提案したい」というレベルまで踏み込みましょう。
そのためには、実際に文具店に足を運び、売り場のレイアウトやPOP、競合製品の並びを自分の目で確かめる「フィールドワーク」が不可欠です。
「消費者」の視点から「ビジネス」の視点へ。
この切り替えが、企業研究の質を格段に上げます。
インターンシップやOB・OG訪問で、現場のリアルな情報を得るのも非常に有効な手段です。
求められる「継続力」と「提案力」のアピール
文具業界、特にメーカーでは、「地道な努力を継続できる力」と「変化に対応し新しい価値を生み出す提案力」が求められます。
「継続力」については、前述の通り、ルート営業や緻密な研究開発がビジネスの根幹にあるからです。
学生時代の部活動、アルバEイト、学業などで、困難な状況でもコツコツと努力を続け、成果を出した経験を具体的にアピールしましょう。
一方で、「提案力」も不可欠です。
デジタル化の波や成熟市場という課題に対し、自ら問題を発見し、解決策を考えて実行した経験(例:アルバイト先での業務改善提案)は、高く評価されます。
資格については、必須のものはありませんが、海外展開に積極的な企業が多いため、TOEICのスコアなど語学力は明確なアピールポイントになります。
【文具業界】よくある質問
ここまで文具業界について詳しく解説してきましたが、就活生の皆さんからは、まだ解決しきれない不安や疑問の声が聞こえてきそうです。
特に、「業界の将来性」や「入社後のキャリア」については、多くの人が気になるところでしょう。
このセクションでは、就活生から特によく寄せられる3つの質問に、就活アドバイザーとして率直にお答えしていきます。
ネガティブに見える情報も包み隠さずお伝えするので、ぜひ業界理解を深める参考にしてください。
Q. ペーパーレス化で将来性はないのでは?
A. これは最も多く寄せられる質問ですが、結論から言えば「将来性はある」と断言できます。
確かに、デジタル化の進展で「紙の使用量」は減少傾向にあり、従来の事務用品は苦戦している側面もあります。
しかし、業界全体が「なくなる」ことはありません。
なぜなら、各メーカーが「事業の多角化」で対応しているからです。
例えば、デジタルと融合したスマート文具の開発、手書きの価値を再提案する高級筆記具や手帳市場の活性化、さらにはコクヨのようにオフィス空間全体をデザインするソリューション事業へのシフトなど、ビジネスモデルそのものを変革させています。
また、海外、特にアジア市場はまだまだ成長しており、日本品質の文具の需要は非常に旺盛です。
変化に対応し続ける限り、将来性は十分にある業界です。
Q. 営業は「御用聞き」が多いって本当?
A. この質問の背景には、「地味なルート営業は嫌だ」という本音が隠れているかもしれませんね。
確かに、文具業界の営業は、古くからの取引先である卸売業者や小売店を定期的に訪問する「ルート営業」が基本となるケースが多いです。
その意味では、既存の顧客との関係性を地道に築く「御用聞き」的な側面があることは事実です。
しかし、現代の営業はそれだけではありません。
単に注文を取るのではなく、小売店のデータ(POSデータなど)を分析し、「今、この地域ではこの商品が売れているから、棚のこの位置に置きませんか?」といった売り場全体のコンサルティングを行う「提案型」の営業が主流になっています。
また、BtoBのオフィス営業では、顧客の課題をヒアリングし、文具や家具を含めたソリューションを提案する高度なスキルが求められます。
Q. 企画やマーケティング職に就けますか?
A. 「ヒット商品を生み出したい」という夢を持って、企画職やマーケティング職を志望する学生は非常に多いです。
しかし、多くの文具メーカーでは、新卒でいきなりこれらの花形部門に配属されるケースは極めて稀です。
その理由は、現場を知らない人間が良い企画はできない、という考え方が根強いからです。
ほとんどの場合、まずは「営業職」としてキャリアをスタートします。
営業として、「なぜこの商品は売れないのか」「現場の小売店は本当は何に困っているのか」というリアルな市場の声を肌で感じる経験こそが、将来的に売れる商品を生み出すための財産になると考えられています。
もちろん、ジョブローテーション制度や社内公募制度を設けている企業も多いので、営業でしっかりと成果を出した上で、企画職へ挑戦するというキャリアパスが一般的です。
まとめ
文具業界は、「安定」という強固な基盤を持ちながら、「デジタル化」や「グローバル化」という大きな変革の波の真っただ中にあります。
それは、「伝統」と「革新」の両方を体感できる、非常にエキサイティングなフィールドだとも言えます。
この記事で解説した「就職偏差値」は、あくまで現時点での人気度を示す目安に過ぎません。
大切なのは、あなたが文具を通して「誰に、どんな価値を届けたいか」を真剣に考えることです。
「文具が好き」という純粋な気持ちを原動力に、ぜひ企業研究を深め、あなただけの熱い志望動機を練り上げてください。