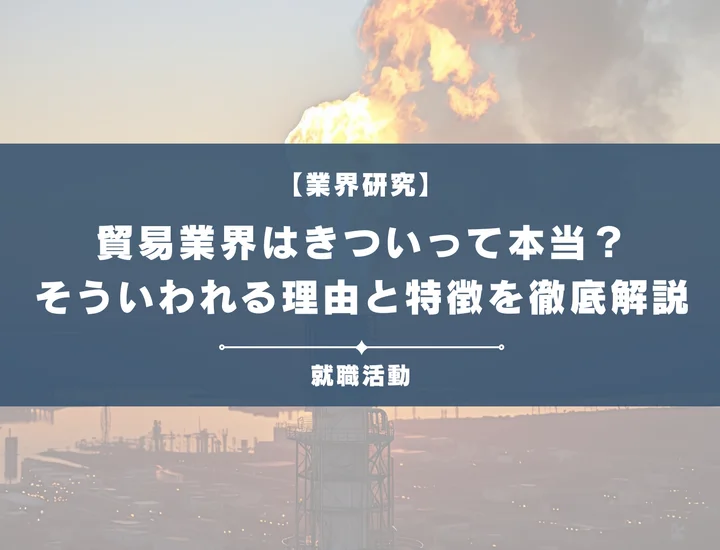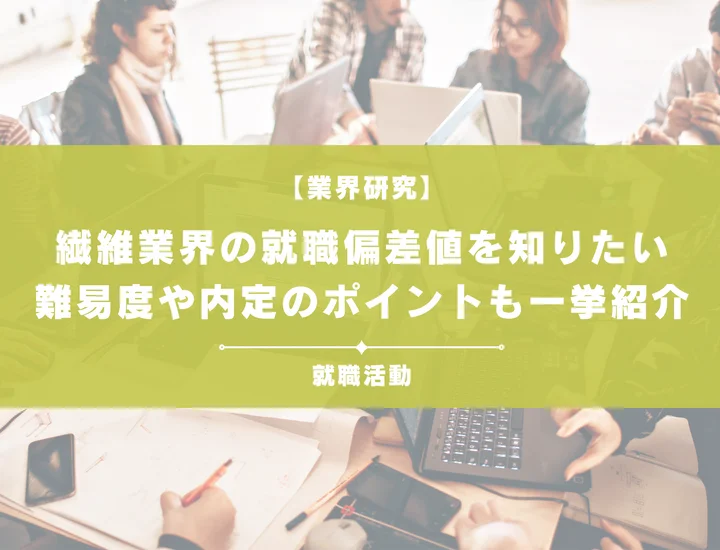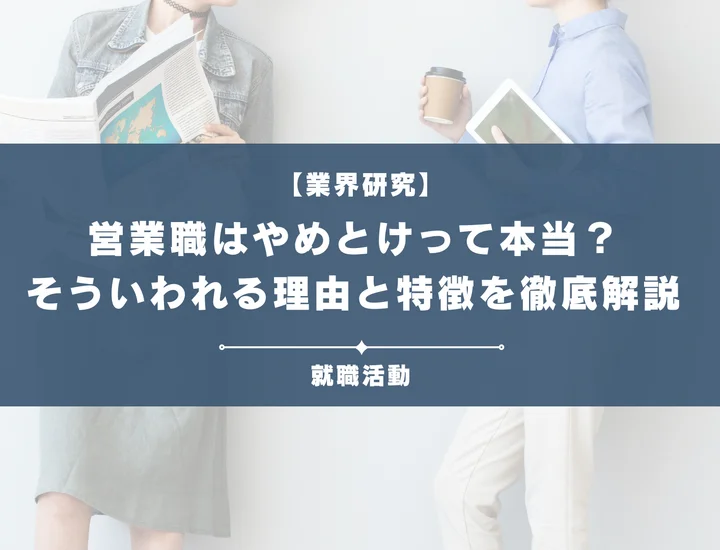HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
この記事では、貿易業界のリアルな仕事内容から、きついと言われる理由、そしてこの業界で輝ける人の特徴まで、詳しく解説していきます。
あなたの業界研究の一助になれば幸いです。
目次[目次を全て表示する]
【貿易業界はきついのか】貿易業界はきつい?
「貿易業界はきつい」というイメージは、確かによく耳にします。
世界を相手にする仕事ですから、時差の問題や複雑な手続き、予期せぬトラブルなど、大変な側面があるのは事実です。
しかし、それがすべてではありません。
グローバルな物流を支えるという大きなやりがいや、専門知識が身につく面白さもあります。
大切なのは、きついという側面にだけ目を向けるのではなく、その実態を正しく理解し、自分に合っているかどうかを見極めることです。
この先で、貿易業界の具体的な仕事内容や大変さの理由を一緒に見ていきましょう。
【貿易業界はきついのか】貿易業界の仕事内容
貿易業界と一口に言っても、その仕事内容は多岐にわたります。
共通しているのは、国境を越えたモノの流れ、つまり「輸出」と「輸入」に関わるあらゆる業務を担うということです。
例えば、海外の取引先と商談をまとめたり、必要な書類を作成したり、船や飛行機の手配をしたり、税関を通るための手続き(通関)を行ったりします。
これらの業務は、一つの会社がすべて行う場合もあれば、商社、メーカー、船会社、フォワーダー(乙仲)、通関業者などが分業している場合も多いです。
社会のインフラとして、世界中の経済活動を根底から支える重要な役割を担っています。
また、近年ではEコマースの拡大に伴い、小口の国際輸送のニーズも増えており、仕事の幅はさらに広がりを見せています。
輸出業務(モノを海外へ送る手続き)
輸出業務は、文字通り日本の製品を海外の顧客へ送り届けるまでの一連の手続きを担当します。
具体的には、海外の買い手(輸入者)との間で売買契約を結ぶところからスタートします。
契約内容に基づき、商品を生産・調達し、船や飛行機の予約(ブッキング)を行います。
同時に、インボイス(送り状)やパッキングリスト(梱包明細書)といった船積書類を作成し、税関に対して輸出申告を行います。
許可が下りたら商品を港や空港の保税地域に運び込み、コンテナに詰めて船積み(または飛行機への搭載)をします。
商品発送後は、代金を回収するための為替手続きなども行います。
国内法だけでなく相手国の法律や規制も関わるため、正確な知識と慎重な作業が求められる仕事です。
輸入業務(海外からモノを受け取る手続き)
輸入業務は、輸出業務と逆の流れで、海外の製品を日本国内に受け入れるための手続きを行います。
まず、海外の売り手(輸出者)と売買契約を結び、商品を発注します。
商品が相手国から発送されると、船会社や航空会社から船積書類が送られてきます。
この書類をもとに、商品が日本に到着する前に税関に対して輸入申告を行います。
申告内容が審査され、関税や消費税を納付して輸入許可が下りて初めて、商品を国内に引き取ることができます。
食料品や化学品など品目によっては、関税法以外の法律(食品衛生法、薬機法など)に基づく許可や承認も必要となり、手続きはさらに複雑になります。
迅速かつ正確に商品を顧客へ届けるため、スケジュール管理と関係各所との連携が鍵となります。
乙仲(フォワーダー)業務(輸送・通関の手配)
乙仲(おつなか)、または現代的な呼称であるフォワーダーは、荷主(輸出者や輸入者)からの依頼を受け、国際輸送に関するあらゆる実務を代行する専門業者です。
自社で船や飛行機といった輸送手段を持たず、船会社や航空会社、トラック業者などを組み合わせて、最適な輸送ルートや方法をプランニングし、手配します。
具体的には、船や飛行機のスペース予約、港湾や空港での荷役作業の手配、トラックによる国内輸送の手配、通関手続きの代行、船積書類の作成サポートなど、その業務は非常に広範囲にわたります。
物流のプロフェッショナルとして、荷主のニーズに応えつつ、コスト削減やリードタイム短縮を実現することが大きなミッションです。
複雑な国際物流を円滑に進めるための「調整役」と言えるでしょう。
【貿易業界はきついのか】貿易業界の主な職種
貿易業界には、その複雑な業務を支えるために様々な職種が存在します。
商社やメーカーの貿易部門で働く場合もあれば、フォワーダーや通関業者、船会社といった物流の専門企業で働く場合もあります。
代表的な職種としては、顧客との窓口となり商談を進める「営業」、輸出入の手続きに必要な書類作成や手配を担う「貿易事務」、そして国家資格を持ち税関手続きを専門に行う「通関士」などが挙げられます。
これらの職種は密接に連携しながら、一つの「モノの流れ」を完成させていきます。
自分がどのポジションで強みを発揮したいのか、具体的な職種を知ることで、業界への理解が深まるはずです。
貿易事務(書類作成と手続きの専門家)
貿易事務は、輸出入に関わる一連の事務手続きを担当する職種です。
商社、メーカー、フォワーダーなど、貿易に関わる多くの企業で必要とされています。
主な仕事は、インボイスやパッキングリスト、船荷証券(B/L)といった多種多様な貿易書類の作成やチェック、内容の確認です。
また、船会社や航空会社への輸送スペースの予約、通関業者への通関依頼、運送会社への配送手配、銀行での決済手続きなども行います。
基本的にはオフィス内でのデスクワークが中心ですが、海外の取引先や関係各所とメールや電話(主に英語)でやり取りすることも頻繁にあります。
正確な書類作成とスケジュール管理が物流全体のスムーズな流れを左右するため、非常に重要な役割を担う専門職です。
営業(海外・国内の取引先との窓口)
貿易業界における営業は、既存の取引先との関係を維持・強化したり、新規の取引先を開拓したりする役割を担います。
商社やメーカーであれば、自社が取り扱う商品を海外に売り込んだり(輸出)、海外から優れた商品を買い付けたり(輸入)するための商談を行います。
フォワーダーであれば、荷主(輸出入を行う企業)に対して、自社の国際輸送サービスを提案します。
いずれの場合も、高いコミュニケーション能力が求められます。
特に海外営業の場合は、語学力はもちろんのこと、異なる文化や商習慣を理解し、相手と信頼関係を築く力が不可欠です。
単にモノを売る・運ぶだけでなく、市場の動向を分析したり、新たなビジネスチャンスを見つけ出したりすることも重要な仕事です。
通関士(輸出入申告のプロフェッショナル)
通関士は、貿易業界における唯一の国家資格であり、輸出入申告のスペシャリストです。
モノを輸出入する際、必ず税関長の許可を得る必要がありますが、この税関への申告手続きは非常に専門的で複雑です。
通関士は、荷主(企業)に代わって、輸出入する品物が「何の品物で、数量・価格はいくらか」などを申告書にまとめ、税関に提出します。
この際、関税法や関連法規に基づき、品物を正確に分類(HSコードの特定)し、適切な関税・消費税額を算出します。
もし申告内容に誤りがあれば、追徴課税や罰則の対象となる可能性もあるため、極めて高い専門性と責任感が求められます。
主に通関業者やフォワーダーに所属し、日本の貿易を法律面から支える重要な役割を果たしています。
【貿易業界はきついのか】貿易業界がきついとされる理由
さて、ここからは多くの就活生が気になる「貿易業界がきつい」とされる具体的な理由について掘り下げていきます。
グローバルな仕事である特性上、他の業界とは異なる種類の大変さが存在するのは確かです。
例えば、世界中の取引先とやり取りするため、時差に合わせた対応が求められたり、天候や国際情勢といった自分たちではコントロールできない要因に振り回されたりすることも少なくありません。
また、扱っているモノが国境を越えるため、各国の法律や複雑な手続き、専門用語を常に学び続ける必要もあります。
こうした環境の変化への対応力や、プレッシャーのかかる場面での判断力が求められる点が、「きつい」と感じられる主な要因かもしれません。
時差と納期に追われるプレッシャー
貿易の仕事は、国内だけでなく海外の取引先や関係会社と常に連携して進めます。
相手がヨーロッパやアメリカであれば、日本とは昼夜が逆転しているため、日本の業務時間外に連絡が入ったり、緊急の対応を求められたりすることも日常茶飯事です。
また、物流は「納期厳守」が絶対です。
船や飛行機の出発スケジュールは決まっており、それに間に合わせるために書類を準備し、手続きを完了させなければなりません。
わずかな遅れが、その後の輸送スケジュール全体に影響し、顧客に多大な迷惑をかけてしまう可能性があります。
常に時間に追われ、複数のタスクを同時並行で処理しなければならないプレッシャーは、この仕事の大変な側面の一つです。
専門知識の習得と法規制のキャッチアップ
貿易実務は非常に専門性が高い分野です。
インコタームズ(貿易条件の国際ルール)やL/C(信用状)といった貿易特有の用語やルールの理解はもちろん、関税法、外為法(外国為替及び外国貿易法)など、関連する法律の知識も欠かせません。
さらに、これらの法律や規制は、国際情勢や各国の政策によって頻繁に改正されます。
例えば、特定の国からの輸入品に対する関税が急に変更されたり、輸出入が禁止される品目が追加されたりすることもあります。
常に最新の情報をキャッチアップし、実務に反映させ続ける必要があるため、継続的な学習が苦手な人にとっては「きつい」と感じられるでしょう。
突発的なトラブル対応と責任の重さ
貿易の現場では、予期せぬトラブルがつきものです。
例えば、「悪天候で船が遅延する」「港がストライキで機能しない」「通関で貨物がストップする」「輸送中に商品が破損した」など、その種類は様々です。
こうしたトラブルが発生すると、納期遅れや追加コストが発生し、顧客に大きな損害を与えかねません。
そのため、トラブル発生時には、迅速な状況把握と関係各所(船会社、顧客、社内関係者など)との調整、そして最適な解決策の実行が求められます。
一つのミスが大きな金銭的損失や信用の失墜につながる可能性があるという、責任の重さも、この仕事の厳しさと言えます。
【貿易業界はきついのか】貿易業界の現状・課題
貿易業界は、常に世界の動きと直結しているため、その時々の国際情勢や技術革新の影響をダイレクトに受けます。
現在は、グローバル化がスタンダードとなる一方で、企業間の競争はますます激しくなっています。
特に物流コストの変動は、企業の収益に直結する大きな問題です。
また、長年の紙ベースのアナログな業務が根強く残っている業界でもあり、デジタル技術を活用した業務効率化(DX)が他の業界に比べて遅れている点も大きな課題とされています。
さらに、パンデミックや地域紛争など、予測困難な地政学リスクが世界中のモノの流れ(サプライチェーン)を不安定にさせる要因となっており、これにいかに対応していくかが問われています。
グローバル競争の激化と物流コストの変動
世界経済のグローバル化に伴い、貿易業界での競争は国境を越えて激化しています。
特にフォワーダー業界では、価格競争だけでなく、輸送のスピード、サービスの質、きめ細かな対応力など、総合的な力が問われるようになっています。
また、近年は原油価格の高騰や、パンデミック後のコンテナ不足、特定の航路の混雑などにより、海上運賃や航空運賃が不安定に変動しています。
物流コストの上昇は、荷主であるメーカーや商社のコスト負担を増大させるため、いかに効率的で安定した輸送ルートを確保し、コストを抑えた提案ができるかが、業界で生き残るための重要な鍵となっています。
DX(デジタルトランスフォーメーション)化の遅れ
貿易業界は、歴史的に「紙の書類」でのやり取りが非常に多い業界です。
インボイス、パッキングリスト、船荷証券など、多くの重要書類が今も紙やPDFで扱われ、それを人間が確認し、別のシステムに手入力するといった非効率な作業が残っています。
このようにデジタル化が遅れている(DXの遅れ)ことは、業界全体の大きな課題です。
AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用した業務自動化や、ブロックチェーン技術を使った関係者間での安全な情報共有など、効率化の余地は大きいものの、多くの関係者が関わる複雑なプロセスであるがゆえに、標準化やシステム導入がなかなか進まないという側面があります。
地政学リスクとサプライチェーンの脆弱性
貿易は、世界の平和と安定があってこそ円滑に行われます。
しかし、特定の国や地域での紛争、政治的な対立、感染症のパンデミックといった「地政学リスク」が発生すると、モノの流れは瞬く間に寸断されます。
例えば、特定の航路が通れなくなったり、特定の国との輸出入が制限されたりすると、世界中のサプライチェーン(供給網)が混乱します。
近年、特定の国に生産拠点を集中させることのリスクが浮き彫りになり、多くの企業がサプライチェーンの見直しを迫られています。
貿易業界は、こうした予測困難なリスクにいかに迅速に対応し、安定的な物流を維持できるかという難題に常に向き合っています。
【貿易業界はきついのか】貿易業界に向いている人
ここまで貿易業界の仕事内容やきついとされる理由を見てきましたが、もちろん大変なことばかりではありません。
むしろ、その大変さの中に大きなやりがいを見いだせる人にとっては、非常に魅力的な業界です。
では、具体的にどのような人が貿易業界に向いているのでしょうか。
まず大前提として、世界を舞台に働きたいという強い思いがあることが挙げられます。
その上で、国籍や文化の異なる多様な人々と円滑に物事を進めていく調整力や、地道な作業を正確にやり遂げる忍耐力も求められます。
グローバルな環境での挑戦にワクワクする人にとって、貿易業界は最適なフィールドとなるでしょう。
異文化コミュニケーションを楽しめる人
貿易の仕事は、海外の取引先やパートナーとのやり取りが不可欠です。
メールや電話、商談などで日々接するのは、育ってきた環境や文化、価値観、そして商習慣が日本とは全く異なる人々です。
時には、こちらの常識が通じず、交渉が難航することもあるでしょう。
そうした文化の違いを「壁」として捉えるのではなく、「違い」として受け入れ、リスペクトし、その上で共通のゴールを目指して粘り強く対話できる人が向いています。
単に語学ができるだけでなく、相手の背景を理解しようとする姿勢と、異文化コミュニケーションそのものを楽しめる好奇心が非常に重要です。
調整力と交渉力に自信がある人
貿易のプロセスは、社内の関連部署、顧客、船会社、航空会社、通関業者、倉庫業者など、非常に多くの「人」が関わって成り立っています。
輸出入がスムーズに進むかどうかは、これら関係者との利害やスケジュールを調整する能力にかかっています。
特にトラブルが発生した際は、それぞれの立場や主張がぶつかり合うことも少なくありません。
そんな時、冷静に状況を分析し、優先順位をつけ、関係者が納得できる着地点を見つけ出し、協力を仰ぎながら物事を前に進める「調整力」が求められます。
また、価格や納期、条件面で自社や顧客の利益を守るための「交渉力」も、営業職などを中心に必須のスキルとなります。
地道な確認作業を厭わない人
貿易の仕事は、グローバルで華やかなイメージがある一方で、その実務は非常に地道な作業の連続です。
特に貿易事務や通関士の仕事は、膨大な量の書類作成とチェックが中心となります。
契約書、インボイス、B/Lなどの書類に記載された品名、数量、金額、日付などに一つでもミスがあると、通関が保留になったり、代金決済ができなかったりと、重大なトラブルに直結します。
そのため、細かい数字やアルファベットの羅列を見比べ、細心の注意を払って何度も確認する作業を、コツコツと正確にやり遂げられる忍耐強さと責任感が不可欠です。
派手な仕事でなくても、物流を支える土台作りにやりがいを感じられる人が向いています。
【貿易業界はきついのか】貿易業界に向いていない人
一方で、貿易業界の特性が残念ながら「向いていない」と感じられる人もいます。
これは能力の問題ではなく、あくまで「適性」の問題です。
例えば、突発的な変化に対応するのが極度に苦手な人や、決められたことだけをコツコツとやりたい人にとっては、日々状況が変わる貿易の現場はストレスに感じるかもしれません。
また、仕事内容の部分でも触れた通り、この業界は継続的な学習が必須です。
新しい知識やスキル、特に語学の習得に対して抵抗感がある場合、キャリアアップが難しくなる可能性もあります。
自分の価値観や働き方の希望と、業界の特性がマッチしているかを冷静に判断することが大切です。
プレッシャーに弱く、臨機応変な対応が苦手な人
貿易業界は「きついとされる理由」で挙げたように、納期やスケジュールのプレッシャーが常にかかる仕事です。
また、天候、政治情勢、輸送機関のトラブルなど、予測不能な事態が日常的に発生します。
こうした予期せぬ変化に対して、「どうしよう」とパニックになってしまう人や、強いストレスを感じてしまう人には、厳しい環境かもしれません。
トラブルが起きても冷静さを保ち、「今できる最善策は何か」を考えて柔軟に軌道修正できる臨機応変さが求められます。
決められたマニュアル通りに進まない事態を楽しめるくらいの胆力が求められる場面も多いです。
定型的なルーティンワークだけを好む人
もちろん、貿易事務のように定型的な書類作成業務もありますが、業界全体としては変化の連続です。
取引先も違えば、扱う商品も、輸送ルートも、適用される法律も案件ごとに異なります。
また、トラブル対応も典型的なルーティンワークとは言えません。
毎日同じ時間に、同じ手順で、同じ作業だけを繰り返したいという志向が強い人にとっては、刺激が多すぎると感じるかもしれません。
もちろん、正確な事務処理能力は重要ですが、それ以上に状況の変化に応じて自ら考え、判断し、行動することが求められる業界です。
新しい知識や語学の学習意欲が低い人
貿易業界で働き続ける限り、「学び」に終わりはありません。
国際情勢の変化に伴い、法規制は毎年のように改正されます。
新しい輸送技術やITシステムも次々と登場します。
そして何より、グローバルに仕事をする上で語学力(特に英語)は必須のツールです。
入社時に完璧である必要はありませんが、仕事を通じて、あるいは自主的に、常に自分の知識やスキルをアップデートし続ける意欲が不可欠です。
学生時代の勉強で終わりにしたい、新しいことを覚えるのは億劫だと感じる人にとっては、常にインプットを求められる環境が負担になる可能性があります。
【貿易業界はきついのか】貿易業界に行くためにすべきこと
貿易業界が自分に向いているかもしれない、挑戦してみたいと感じた皆さんへ。
では、就職活動に向けて具体的に何を準備すれば良いのでしょうか。
もちろん、学生時代にしかできない経験を積むことも大切ですが、貿易業界を目指す上で特に有利に働く「準備」がいくつかあります。
それは、この業界で働く上での「土台」となる部分です。
例えば、グローバルなコミュニケーションの基盤となる語学力や、専門知識の基礎を身につけておくことです。
これらは入社後のスタートダッシュを助けるだけでなく、選考の場でも「本気でこの業界を目指している」という熱意を伝える強力な武器になります。
語学力(特にビジネス英語)を磨く
貿易業界において、英語は「できれば良い」スキルではなく、「必須」のツールです。
海外の取引先とのメールのやり取り、電話会議、商談、そして何より貿易書類の多くは英語で作成されます。
学生のうちに、TOEICで一定のスコア(目安として700点以上、企業によりますが)を取得しておくことは、選考でのアピールに繋がります。
ただし、スコアだけでなく、実際に使える英語力、特に「読む・書く」能力を鍛えておくことが実務では非常に重要です。
ビジネスメールの書き方を学んだり、英語のニュース記事を読んだりするなど、実践的な学習を心がけると良いでしょう。
貿易関連の資格取得で知識を証明する
貿易業界は専門性が高いため、その基礎知識を持っていることを客観的に証明できる資格は、就活において大きな強みとなります。
代表的なものに「貿易実務検定」があります。
この資格の勉強をすることで、貿易の流れ全体像や、専門用語、基本的な法律(関税法など)を体系的に学ぶことができます。
面接で「なぜ貿易業界なのか」を語る際にも、資格取得のために努力したという事実は、あなたの熱意と適性を裏付ける具体的なエピソードとなります。
他にも、通関士(難関ですが)、IATAディプロマ(航空貨物)など、目指す職種に合わせて関連資格を調べてみることをお勧めします。
業界・企業研究で具体的な仕事をイメージする
「貿易業界」と一口に言っても、その中には商社、メーカー(の貿易部門)、フォワーダー(乙仲)、船会社、航空会社、通関業者、倉庫業者など、様々なプレーヤーが存在します。
それぞれの立ち位置や役割、ビジネスモデルは全く異なります。
自分が貿易のどの部分に携わりたいのか、例えば「世界中から面白い商品を見つけてきたい(商社)」のか、「モノの流れを最適にコーディネートしたい(フォワーダー)」のかを明確にする必要があります。
各企業の強みや社風を徹底的に調べ、インターンシップに参加するなどして、入社後に「こんなはずではなかった」というミスマッチを防ぐことが何よりも大切です。
まとめ
貿易業界は、確かに時差や納期、トラブル対応など「きつい」側面もありますが、それ以上に世界経済を支えるダイナミズムと、国境を越えた人々を繋ぐ大きなやりがいがある仕事です。
必要な知識やスキルは多いですが、それらは努力次第で身につけることができます。
もしあなたが、異文化の中で調整力を発揮することや、地道な努力で大きな物流を支えることに魅力を感じるなら、この業界はあなたの可能性を大きく広げてくれる場所になるはずです。
ぜひ、深い業界研究を通じて、あなたの「挑戦したい」という気持ちを確かめてみてください。
応援しています。