
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
面接では、単にスキルや経験を評価するだけでなく、応募者の人柄や企業との適性も見極められます。
そのため、面接でどのような質問がされるのか、企業が何を知りたいのかを理解することが重要です。
この記事では、面接でよく聞かれる質問の意図や答え方のポイントを詳しく解説していきます。
【面接でされる質問】企業が面接を実施する目的とは
企業が面接を実施する目的を理解することで、面接に向けた準備がしやすくなります。
企業は、単に応募者のスキルや経験を確認するだけではなく、面接を通してさまざまな要素を見極めています。
ここでは、企業が面接を行う目的について詳しく説明していきます。
自社の求める人材なのか確かめるため
企業が面接を行う最も重要な目的は、応募者が自社の求める人材に合致しているかを確認することです。
企業ごとに求める人物像は異なり、主体性やリーダーシップを重視する企業もあれば、チームワークや協調性を重視する企業もあります。
そのため、面接官は質問を通じて応募者の考え方や人柄を知り、自社の環境で活躍できるかを見極めています。
例えば、「あなたがこれまでに挑戦したことは何ですか?」という質問では、積極性や粘り強さが評価のポイントになります。
社会人として基本的なマナーがあるか見るため
面接では、応募者のスキルや適性だけでなく、社会人としての基礎的なマナーが身についているかも確認されます。
社会人としてのマナーには、挨拶の仕方、敬語の使い方、話し方、時間を守る姿勢、相手への礼儀などが含まれます。
これらの基本的なマナーが欠けていると、いくら能力が高くても、職場で円滑に業務を進めることが難しいと判断される可能性があります。
例えば、面接の際に遅刻をする、身だしなみが整っていない、挨拶ができないといった行動は、社会人としての意識が低いとみなされる要因になります。
【面接でされる質問】質問される順番
面接において質問される内容には一定の流れがあります。
一般的には「自己紹介→志望動機→自己PR→その他の質問→逆質問」という順番で進むことが多いです。
この流れを事前に理解しておくことで、面接に向けた準備を効率よく進めることができます。
ここでは、それぞれの質問の意図や対策について詳しく解説します。
自己紹介
自己紹介は、面接の冒頭で聞かれることがほとんどです。
第一印象を決定づける重要な質問であり、短時間で自分の特徴を簡潔に伝えることが求められます。
特に、話が長すぎると面接官の印象に残りにくくなるため、「氏名」「大学名・学部」「簡単な経歴」「志望する理由や強み」などを明確に伝えることがポイントです。
また、話す際には明るくハキハキとした口調を意識し、面接官に好印象を与えられるようにしましょう。
志望動機
志望動機は、企業を志望した理由だけでなく、業界全体を志望した理由まで伝えることが重要です。
企業側は、応募者がなぜその業界・企業を選んだのか、どのような価値観を持っているのかを知りたがっています。
そのため、志望動機を伝える際は、「業界の魅力→企業の特徴→自分の適性」という流れで話すと、論理的でわかりやすくなります。
また、「貴社の〇〇に共感し、〇〇の点で貢献できると考えています」といった形で、企業の特徴に触れることが大切です。
自己PR
自己PRは、自分の強みをアピールする場面ですが、単に能力や性格的な特徴を提示するだけでは評価されません。
企業側は「その強みが自社でどう活かせるのか」を知りたがっています。
そのため、「結論→具体的なエピソード→その強みをどう活かせるか」という流れで話すと、説得力のある自己PRになります。
例えば、「私の強みは〇〇です。大学では〇〇の活動を通じて、〇〇を実践し、〇〇の成果を上げました。この経験を活かし、貴社の〇〇の業務で貢献したいと考えています。」といった形でまとめると良いでしょう。
学生時代頑張ったことは何ですか?
面接官が学生時代の経験(ガクチカ)を質問するのは、「応募者がどのように物事に取り組んできたのか」を知りたいからです。
企業は、応募者の行動特性や課題解決能力を見極めるために、この質問をします。
回答の際には、「結論→背景→具体的な行動→結果→学び」の順で話すと、伝わりやすくなります。
また、単に成功体験を語るのではなく、困難をどのように乗り越えたのかを強調することで、より評価されやすくなります。
長所と短所を教えてください
面接官が長所と短所を聞く理由は、「自己分析ができているかどうか」「企業の求める人物像とマッチしているか」を知るためです。
長所を伝える際は、企業の業務に活かせる点を強調し、短所については「克服のための努力」をセットで話すことが大切です。
例えば、「私の長所は〇〇です。大学では〇〇の経験を通じて、この強みを活かして〇〇に取り組んできました。一方で、短所は〇〇ですが、〇〇の方法で克服するよう努力しています。」といった形で話すと、ポジティブな印象を与えることができます。
失敗経験を教えてください
面接官が失敗経験について質問するのは、「意欲的に努力した経験があるのか」「失敗をどのように乗り越えたのか」「そこから何を学んだのか」を知るためです。
企業は、失敗を経験したこと自体ではなく、それをどのように捉え、成長につなげたのかを重視しています。
また、失敗の内容は業務に大きな影響を与えるような重大なものではなく、努力の過程で乗り越えたエピソードを選ぶのが適切です。
最後に質問はありますか
面接の終盤では、企業側から「何か質問はありますか?」と逆質問を求められます。
これは、応募者が企業に対してどの程度の関心を持っているかを確認するための質問です。
逆質問をする際は、「企業のビジョンや業務内容に関する質問」や「入社後のキャリアについての質問」をすると、意欲が伝わります。
逆質問をせずに終わってしまうと、企業への関心が低いと思われる可能性があるため、最低でも2つは準備しておくと良いでしょう。
【面接でされる質問】質問に答えるための準備
面接で適切に質問に答えるためには、事前の準備が欠かせません。
自分自身のことを理解し、企業や業界についての知識を深めることで、自信を持って受け答えができるようになります。
ここでは、面接の準備として必要な3つのステップについて解説していきます。
自己分析をする
面接で的確に答えるためには、まず自己分析を行い、自分の強みや価値観を明確にしておくことが大切です。
自己分析を通じて、自分の長所や短所、これまでの経験から得た学び、将来の目標などを整理することで、面接での回答に説得力を持たせることができます。
例えば、自己PRをする際には、自分の強みを明確にし、その根拠となるエピソードを具体的に語る必要があります。
単に「私はリーダーシップがあります」と言うだけではなく、「〇〇の活動でリーダーとして〇〇に取り組み、〇〇の成果を出した」といった形で具体的に伝えることが重要です。
企業・業界分析をする
自己分析と同じくらい重要なのが、企業・業界分析です。
企業が行う事業や理念、業界の動向を理解していないと、面接での受け答えに説得力がなくなり、知識不足と判断されてしまう可能性があります。
企業分析では、企業の公式ホームページや採用ページを確認し、事業内容や理念、競合他社との差別化ポイントなどを把握しておくことが重要です。
また、企業が求める人物像についても事前に調べ、それに沿った回答を準備することで、面接官に「この人は自社に合っている」と思わせることができます。
声に出して練習する
準備が整ったら、実際に声に出して練習をすることをおすすめします。
話す内容が頭の中で整理されていても、声に出して話してみると意外と言葉に詰まったり、うまく説明できなかったりすることがあります。
そのため、面接本番でスムーズに話せるように、事前に何度も練習を重ねることが大切です。
効果的な練習方法として、模擬面接を行うことが挙げられます。
友人や家族、キャリアセンターの担当者に面接官役をお願いし、実際の面接のような形式で質問に答えることで、本番の雰囲気に慣れることができます。
【面接でされる質問】質問に答える際の注意点
面接で質問に答える際には、単に正しい内容を伝えるだけでなく、話し方や伝え方も重要です。
どれほど優れた経験を持っていても、話が冗長になったり、説得力のない伝え方をしてしまうと、面接官に良い印象を与えることはできません。
ここでは、面接での受け答えの際に注意すべき3つのポイントについて詳しく解説していきます。
簡潔に短く話す
面接では、要点を簡潔にまとめて話すことが求められます。
話が長すぎると、要約力や論理的思考能力が欠けていると判断され、悪い印象を与える可能性があります。
また、面接官は1日に多くの学生と面接を行うため、一人ひとりの話を長時間じっくり聞くことはできません。
限られた時間の中で、自分の強みや経験を的確に伝えることが重要です。
嘘をつかない
面接では、正直に話すことが最も重要です。
面接官は多くの学生を見てきているため、話の整合性が取れていない場合や、不自然なエピソードにはすぐに気づきます。
また、仮に嘘がバレなかったとしても、入社後に期待されるスキルや経験が実際には備わっていないとわかった場合、ミスマッチが生じ、働き続けることが難しくなってしまう可能性があります。
特に、ガクチカや自己PRのエピソードを誇張しすぎることには注意が必要です。
面接では、誠実さが評価されることを忘れず、自分の本当の経験や考えを正直に伝えることが重要です。
PREP法を用いる
面接では、話の構成を意識することが重要です。
特に、ビジネスの場でよく用いられる「PREP法」を活用すると、伝えたいことを分かりやすく整理し、論理的に話すことができます。
PREP法とは、「Point(結論)→ Reason(理由)→ Example(具体例)→ Point(再結論)」の順番で話を組み立てる方法です。
このフレームワークを活用することで、要点を的確に伝えることができ、面接官に論理的思考力があると評価されやすくなります。
【面接でされる質問】面接についてよくされるQ&A
面接に関して、学生が抱きやすい疑問は多くあります。
事前に知っておくことで、不安を減らし、スムーズに選考に臨むことができます。
ここでは、特に多くの学生が気にする「面接結果の通知時期」と「面接の到着時刻」について詳しく解説していきます。
面接の結果はいつ知れるのか
面接の結果が通知される時期は、企業や選考の段階によって異なりますが、一般的には面接後1週間から2週間程度で通知されることが多いです。
ただし、企業によっては3日以内に結果を出すところもあれば、最終面接などの重要な選考では1か月近くかかる場合もあります。
結果通知のタイミングが遅れる理由はいくつかあります。
一つは、応募者全員の面接が終了してから結果を決定するため、スケジュールの都合で時間がかかることがある点です。
また、最終選考では社内での意思決定に時間を要するため、通常より長引くケースが見られます。
面接には何分前に会場についておくべきか
面接会場への到着時刻は、適切なタイミングを考慮することが重要です。
基本的には、約束の時刻の10分前には会社の建物内に到着しておくことが望ましいとされています。
ただし、企業のオフィスビルに早く着きすぎた場合、エントランスで長時間待機するのは避けた方が良いでしょう。
特に、オフィスの受付が狭い場合や、他の応募者と同じタイミングで来社する可能性がある場合、早すぎる到着は企業側に負担をかけてしまうこともあります。
まとめ
面接は単なる質疑応答ではなく、自分をアピールする重要な場です。
適切な準備を行い、企業の求める人物像を意識しながら、自分の強みを伝えることが成功のカギとなります。
自信を持って臨み、面接官に良い印象を与えられるよう心がけましょう。




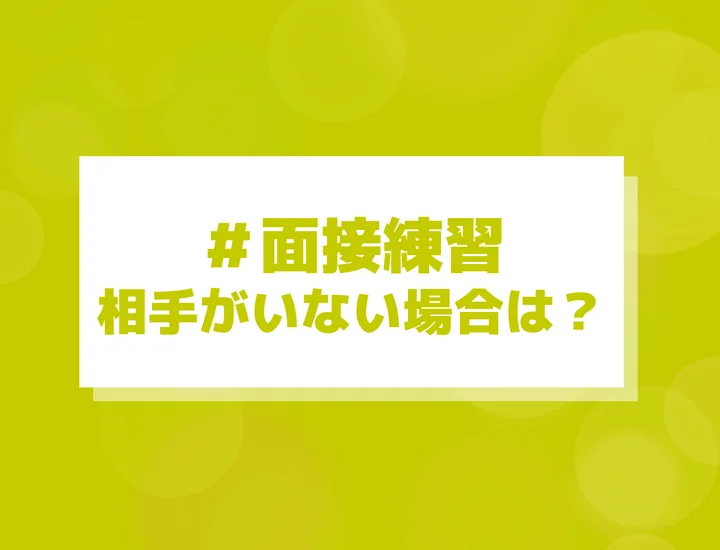

と相性が良い性格とは?仕事・恋愛の相性やおすすめの職業も紹介 (1)_720x550.webp)





