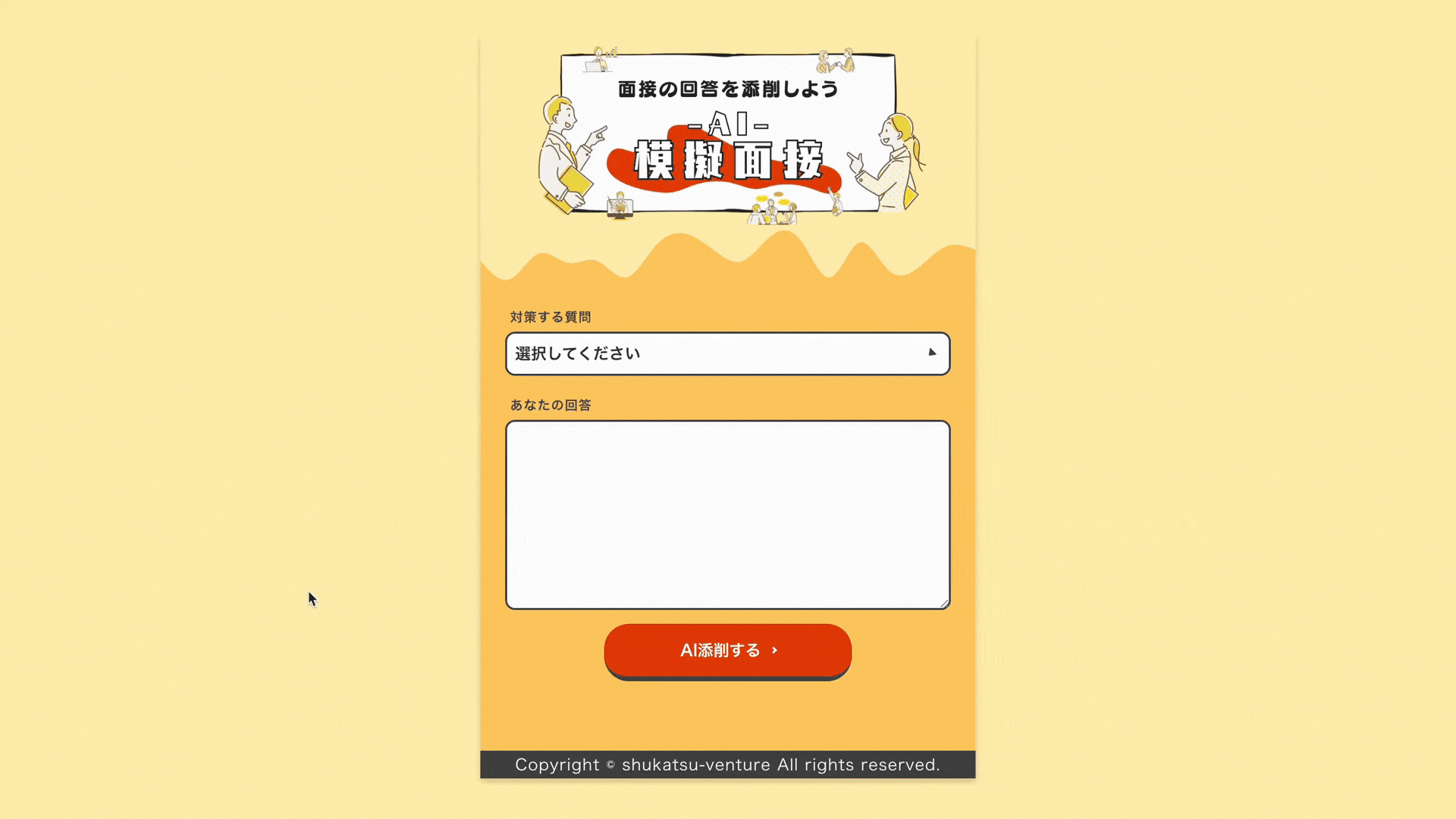HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
【大学3年生必見】AI模擬面接ツールで面接対策しよう
就活で必ず通る「面接」。ただ面接対策ってどうやってやるのだろう、と何から始めればいいのか悩んだり、進め方がわからなかったりと、意外とハードルが高いです。
そこで、今回「いつでもどこでもAI模擬面接ツール」をご用意しました。
頻出問題から変わった問題までAIが人事目線で添削するので、すきま時間であなたの面接力をあげることができます。
メンバー登録後すぐに使用可能なため、ぜひあなたもこの「AI模擬面接ツール」を活用して選考通過率を上げましょう!
※画像の質問はイメージです。
今回は面接でガクチカ[学生時代に頑張ったこと]などを答える際の回答時間の目安を紹介します。
目安を紹介するといっても、1分とか2分とか変に決めつけないほうが良いです。
変に決めつけてしまうと、回答の幅を狭めてしまい、なかなかスムーズに回答しにくくなってしまうからです。
なるべく臨機応変に対応できるような回答方法を紹介していきますので、ぜひ今一度面接の方法を見直してみてはいかがでしょうか。
目次[目次を全て表示する]
【面接ガクチカ何分?】ガクチカはどれくらいの時間で答えるのが適切?
まずは面接ではどれくらいの時間で答えるのが良いかを考えてみます。
大前提として、時間はこれくらいと決めつけてしまわないほうが良いです。
決めつけてしまうと、窮屈な回答になってしまい、相手に気持ちが伝わらない可能性があるのです。
時間が決まっている回答ほど、パターン化しやすいので、熟練の面接官には見抜かれてしまう可能性があるでしょう。
また、集団面接の場合や個人面接の場合によっても違ってくるのです。
場合によって変わる
ガクチカなどの回答時間の目安は1分程度と言われています。
しかし、必ず1分で終えなければならないわけではなく、それよりも短い場合もありますし、長くなることもあるでしょう。
このように臨機応変な対応が求められるのが面接の場なのです。
また、ある程度、面接官から聞かれることは予測できますが、完全に聞かれることは予測できません。
特定の答えに対して、なんらかの問いで切り返される可能性もあるので、問答のパターンは無限にあると言えるでしょう。
そのため、1分でこれを説明するというように固定観念を持ってしまうと、思わぬ質問に焦ってしまう可能性もあります。
その結果、どんどん崩れていってしまう可能性もありますので、臨機応変な対応を心がけるようにしましょう。
集団面接の場合
面接の回答時間がどのくらいかについては、集団面接の場合によっても違います。
集団面接でのポイントは、わかりやすく伝えたいことを適切に答えることが重要になってきます。
集団面接の場合は、面接官もたくさんの人を審査しなければならないので、余裕がありません。
そのため、個人面接よりもより要点を押さえて、相手にわかりやすいように答える必要があるでしょう。
ただし、できる限り簡潔に伝える必要はありますが、個性はしっかりと発揮したいところです。
集団面接で目立つことができなければ、集団に埋もれてしまう程度の才能と思われてしまう可能性があります。
簡潔かつ目立つというのはなかなか難しいことですが、集団面接では重要になってくるので、覚えておきましょう。
また、集団面接で相手の質問の意図を瞬時に理解する対応力も求められるでしょう。
個人面接の場合
個人面接の回答時間ですが、長さよりも自分のアピールという点に重点を置いてはいかがでしょうか。
個人面接では、目的がしっかりとしていなければ、どうしても冗長的になってしまいます。
しかし、とにかく自分をしっかりと伝えるという目的を持って臨めば、相手の意図を理解して、自分をしっかりと伝えられるはずです。
面接で重要なのは、きれいに整った面接をすることではなく、自分の良さや人間性を正確に相手に伝えることなのです。
また、そういった伝え方をするほうが相手に熱意も伝わりやすくなっています。
また、あまりに長くしてしまうと、最初の方にいったことが相手に伝わらない可能性があります。
そのため、個人面接とはいえ、1番自分が伝えたいことを強調して、しっかりと伝わるようにしましょう。
カジュアル面談の場合
カジュアル面談は、選考というよりも企業と就活生の相互理解を目的とした「情報交換」の場として行われることが多いです。
服装や雰囲気も比較的ラフで、会話形式で進行されるのが一般的です。
とはいえ、内容は本格的な面接に近いこともあり、「学生時代に力を入れたこと」などの定番質問を軸に、自然な流れで深掘りされるケースが少なくありません。
そのため、質問に対しては結論を端的に述べ、その後のやり取りで補足していくスタンスが適しています。
ベンチャー企業などの場合
ベンチャー企業にもよりますが、一般的にはそこまで格式ばった面接になることは少ない傾向になっています。
なぜなら、何事においても新しい考え方を持って行動していきたいと考えている社長やスタッフが多いからです。
そのため、どちらかといえばフランクな会話形式で面接が進むことになるでしょう。
基本はお互いがリラックスをした状態で自然に会話をすることになるため、あまり時間を意識する必要はありません。
ただし会話の中で思わぬ質問が投げかけられることも多々ありますので、何を聞かれても良いように準備しておく必要はあるでしょう。
自分が事前に書いたガクチカを何度も読み返して、どのような質問をされる可能性があるのかを、ある程度想定しておいてください。
面接スタイルが分からない場合
とはいえ、応募する企業によって面接スタイルはバラバラです。
特に何も指示をしてこない場合は、どのように対応していけば良いのか悩むでしょう。
そんな時は、一旦結論だけ伝えてみるのがポイントです。
もし面接官が気になった場合は、そこからさまざまな質問が飛んでくるようになります。
すると自然な会話につながりやすくなるため、気づいた頃にはスムーズに面接が進んでいることも珍しくありません。
どうしても何から話していけば良いのか難しいと考えている人は、これだけ意識しておくのも良いでしょう。
まずは1分・300字程度を目安に作成しよう
面接でのガクチカは、1分程度で簡潔に話せるように準備するのが基本です。
1分間に話せる文字数の目安は約300~400字とされており、構成を意識して伝えることで、相手にわかりやすく印象を残すことができます。
しかし、緊張によって話すスピードが速くなりがちな学生も多いため、話す際には早口にならず、落ち着いて内容を伝える練習が必要です。
あらかじめメモや原稿を作成して、自分の言葉で何を伝えたいのか整理しておくことがポイントです。
構成としては、結論→背景→取り組み→結果→学びの順にまとめることで、論理的でスムーズな伝え方になります。
まずは300字前後を目安に文章を作り、声に出して練習しておくと安心です。
集団面接や短時間の選考では、「1分以内で簡潔に説明してください」といった時間指定がされる場合があります。
このようなケースでは、冗長な説明は避け、要点を絞った回答が求められます。
そのため、普段から自分のガクチカを話すのにどのくらいの時間がかかるかを測り、内容をコンパクトに収める練習をしておくことが大切です。
特に長く話しすぎる癖がある人は、構成の中でもどこまで話すか、何を省くかをあらかじめ決めておくと安心です。
基本的に面接でガクチカを伝える際に、何分で伝えなければいけないのかを意識しすぎる必要はありません。
しかし、1分につきどれくらいの文字数を伝えることができるのかは、きちんと把握しておいた方が良いでしょう。
なぜなら、どれくらいの時間を使って自己PRをするのかを意識する企業も少なくないからです。
なお一般的には、大体1分あたり250字程度の内容を話すことができるようになっています。
もちろん人によって個人差はあるので一概にはいえませんが、この数字を目安にガクチカをまとめておくのが良いでしょう。
【面接ガクチカ何分?】ガクチカで企業が見ているポイント
企業はガクチカを通じて、その人のさまざまな側面を見ようとします。
では一体、どんなところに注目されることが多いのでしょうか?
ここからは、企業がよく見ているポイントを4つ紹介します。
パーソナリティ(人柄)が自社にマッチしているか
まず企業が気になるのが、そもそもどんな人間なのか?ということです。
学歴や職歴も採用基準にはなりますが、企業によってはそれよりもパーソナリティな部分で相性が良いのかどうかを重視することがあります。
そのため、ガクチカを伝える際には、自分がどんな考え方を持って頑張ってきたのか?どんな価値観を持って行動してきたのか?などを、きちんと伝えるようにしましょう。
そうすれば、あなたのことを欲しいと思ってくれる可能性がグンと上昇します。
ただし、あくまでも一緒に居たいと思ってもらうことが重要ですので、企業側の価値観や考え方に合致した内容である必要はあるでしょう。
だからこそ、あらかじめ調べた上で面接に臨まなければいけません。
モチベーションの源泉がどこにあるか
企業はその人が、どのような場面で頑張れるのかも、ガクチカから見定めています。
つまり、モチベーションの源泉を知ろうとするのです。
どんな企業も長く一緒に働いていきたいと考えていますので、努力を続けられる人材を積極的に採用します。
そのため、ガクチカを伝える際には、なぜ自分が努力できたのかもきちんと伝えるようにしましょう。
例えば「人が喜ぶ姿を見るのが好きだったから頑張れた」のような内容でもかまいません。
ただし、企業が求めていないことは伝えないようにしてください。
なぜなら、自社でモチベーションを維持させるのが難しいかもしれないと思われてしまうおそれがあるからです。
そうなると採用される可能性は低くなってしまうため、注意が必要です。
過去の経験から学ぶことができるか
ガクチカを聞く際に、企業が意識するのが、その人がどんな学びを得ているのかです。
そのため、単純に過去の経験を話し続けるだけではなく、自分がどのように成長できたのかまで伝えるように意識しましょう。
どんな企業も成長できる人材を探し求めているため、その過程がしっかり伝われば、きっとポテンシャルの高い人材だと認識してもらえるはずです。
同じミスを繰り返しそうな人を採用したいとは誰も思ってくれませんので、その辺についても常に考えながら、面接官にガクチカを伝えるようにしてみてください。
論理的思考力と話の一貫性があるか
企業が注目しているのは、ガクチカの内容だけではありません。
面接を通じて、論理的かつ一貫性のある話し方ができているかも見られています。
論理的思考力とは、物事を整理し、わかりやすく伝える力のことです。
たとえば、何をどこから話せば伝わるか、話の流れに矛盾がないかを意識できているかが重要です。
一貫性のない話し方は説得力に欠け、評価が下がることもあります。
面接では、内容に加えて「どう伝えるか」を意識し、筋の通った話し方を心がけましょう。
【面接ガクチカ何分?】ガクチカの構成
ガクチカをうまく企業に伝えるためには、きちんと構成を作っておく必要があります。
そこで意識してほしいのが、PREP法を用いることです。
ここからはPREP法に沿って、押さえておくべき4つのポイントを紹介します。
まず大事なのが、結論ファーストを意識することです。
つまり、最初からいきなりガクチカ(今まで頑張ってきたこと)のエピソードを話し始めるのではなく、いきなり結論から伝えるようにしましょう。
なぜなら、結論を先に伝えないと、相手に長時間モヤモヤさせてしまうおそれがあるからです。
話がうまい人ならうまく相手を惹きつけられるかもしれませんが、そうじゃない人だと途中で飽きられたり、適当に聞き流されたりするおそれがあります。
そのため、最初に結論を伝えた上で、それに関するガクチカのエピソードを話し始める方が、相手に理解してもらいやすいといえるでしょう。
結論を伝えたあとは、なぜそんな結論になったのか?といった、具体的な理由について説明していきます。
基本的にどんな面接官も、あなたが口にしたことに対してさまざまな疑問を抱くと考えておいてください。
そのため、相手から聞かれる前に自分がなぜそんな活動をすることにしたのかを、きちんとわかりやすく伝えるようにしましょう。
そこから自分がどんなことに対して興味を持つのか?何に対して関心があるのか?などが明確にわかるので、うまくいけばこの段階でアピールにつながることも出てきます。
ここまで話したら、いよいよ本格的にガクチカのエピソードへ移ることになります。
その際に重要なのは、単純に経験したことだけを伝えないようにすることです。
あくまでも面接の場で話すことですので、面接官に良い印象を持たれるようなエピソードを伝えなければいけません。
例えば、その経験を通じてどんな成果を得ることができたのか?どのような学びを得ることができたのか?まで、事細かく伝えましょう。
また、自分がどんな考え方を持って取り組んでいたのかも、この段階で話すことが大切です。
あなたのことをできる限り理解してもらう必要がありますので、ただの経験談では終わらないように注意してください。
エピソードを伝え終えたあとは、再度ここで結論を明確にしましょう。
そして忘れないでほしいのが、これまでの経験を踏まえた上で、どのように自分が会社で貢献していけるのかどうかを伝えることです。
いかに自分のことを採用したいと思わせることができるのかが勝負ですので、実際に会社で働いている様子を、相手にイメージさせるようにしてください。
それができれば、あなたのことを採用しても良いと思ってもらえる可能性が上がります。
ただし、エピソードまでの話で時間をたくさん使っている場合は、カットしても問題ありません。
面接官はさまざまな質問をしてくることが多いため、その際にあらためてアピールすればOKです。
【面接ガクチカ何分?】作成のコツ
面接では話す時間の目安は1〜2分程度であることが多く、内容の構成や伝え方によって印象が大きく左右されます。
限られた時間の中で魅力的に自分を伝えるには、話の順序やエピソードの選び方を工夫し、聞き手にわかりやすく届けることが重要です。
以下では、ガクチカ作成時に意識したい4つのポイントを詳しく解説します。
結論ファーストを意識する
面接では最初に「何を話すのか」が伝わるかどうかが非常に重要です。
そのため、話の冒頭で「私が学生時代に力を入れたのは○○です」といったように、結論から伝える構成が効果的です。
いきなり具体的なエピソードや背景から話し始めると、聞き手は何の話なのか分からず、理解が遅れてしまいます。
結論ファーストの構成は、話の方向性を明確に示すだけでなく、自分の論理性や説明力も伝えることにつながります。
話の核心が先にあることで、その後の内容に耳を傾けてもらいやすくなります。
エピソードを深堀り、質問への対策をする
面接では、ガクチカの内容に対して深掘りの質問がされることが一般的です。
そのため、エピソードの背景や行動の動機、工夫した点、失敗とその克服など、細かい部分まで具体的に説明できるよう準備しておくことが必要です。
あらかじめ「なぜそうしたのか」「その時どう感じたか」「その結果何を得たのか」といった視点から振り返り、自分の考えや行動に一貫性を持たせることで、面接官からの質問にも自信を持って答えることができます。
準備不足が見えると印象は大きく下がるため、エピソードを単なる話題で終わらせず、深みのある内容に仕上げることが大切です。
アピールポイントは1つに絞る
1つのエピソードの中であれもこれもと詰め込んでしまうと、どれも中途半端な印象になり、結局何を伝えたいのかが伝わりにくくなってしまいます。
そのため、ガクチカでは「自分の強みを1つに絞って伝える」ことが基本です。
たとえば、「主体性」「協調性」「粘り強さ」などから1つを選び、その強みが最も発揮された経験を中心に語ることで、印象に残りやすい自己PRになります。
強みを明確にすることで、面接官が「この人は○○な人だ」と判断しやすくなり、短い時間でも効果的なアピールが可能になります。
構成を意識して作成する
どんなに良い経験をしていても、構成が整っていなければ説得力は弱くなってしまいます。
PREP法(結論→理由→具体例→結論)やSTAR法(状況→課題→行動→結果)といった型を使うことで、情報を順序立ててわかりやすく伝えることができます。
構成を意識することで、「なぜそう行動したのか」「何を考えたのか」「どんな成果を得たのか」が明確になり、自分の強みや価値観の裏付けにもつながります。
特に限られた面接時間では、無駄なく伝えるために構成の工夫が必要不可欠です。
一貫性のある流れを意識することで、面接官に伝わる内容がぐっと整理され、印象にも残りやすくなります。
【面接ガクチカ何分?】面接での話し方のポイント
まだ面接に慣れていない人だと、面接でうまく話せる自信がないかもしれません。
そのため、ここでは面接で常に意識してほしい話し方のポイントも、詳しく紹介します。
これでどんな人でも、相手に良い印象を与えられるようになるでしょう。
面接官がメモをしやすいように話す
一般的に面接官は、単純に話を聞くだけではなく、その話を手元にあるメモやパソコンなどでまとめながら耳を傾けます。
そのため、相手がメモをしやすいように話すことも、心がけておくと良いでしょう。
なぜなら、その方が気遣いのできる人間だと思ってもらいやすいからです。
だからこそ、相手の手元の動きを見ながら、間合いをうまく調節することを考えましょう。
ちなみに面接官がなぜメモをするのかというと、他の社員や上司と情報を共有する必要があるからです。
特に面接は2次、3次と繰り返すことも珍しくないため、その都度面接官は情報を整理しようとします。
抑揚をつけて話す
面接でガクチカを話す際には、抑揚をつけることも意識することが大切です。
つまり、一定のペースで淡々と伝えないようにしましょう。
その理由は、具体的にどこで何を伝えたいのかが、相手にとってわかりにくくなってしまうおそれがあるからです。
例えば、エピソードの内容を説明する際には、どこを強調するべきなのかを明確にしておきましょう。
そして、その部分に感情を込めながら話すことが大事です。
そうすれば途中で飽きさせることもありませんし、きちんと伝えたいことを理解してもらえます。
また、できることなら声だけではなく、腕でその時の状況や感情を表現してみるのも良いでしょう。
ジェスチャー1つでよりわかりやすくなることもありますので、ますます良いアピールができるかもしれません。
エピソードは全てを伝える必要はない
ガクチカのエピソードは、できるだけ詳しく話した方が、相手に疑問を持たせずに済みます。
しかし、だからといって相手にとって不要な情報まで伝える必要はありません。
なぜなら、冗長的な印象を抱かれてしまうおそれがあるからです。
確かに深掘りすることは大切ですが、相手が必要としていないことまで伝えても、それは何もアピールになりません。
また、あまり深掘りしすぎると、そのあとで自分が想定しているような質問が飛んでこない可能性も出てきます。
すると予想外の質問が来てしまうかもしれませんので、場合によってはうまく対処できないこともあるでしょう。
そのため、質問をしてほしい部分をあえて深掘りせずに話す、といったテクニックを使うことも意識しておくのがおすすめです。
話しの聞き取りやすさを意識する
面接では「話の内容を正しく伝える」ことが最も重要です。
そのためには、ただ声が大きくはっきりしているだけでは不十分です。
一文を短く区切って話したり、要所で間をとったりすることで、相手が話を理解しやすくなります。
また、難解な言葉を避けて平易な表現を使う、主語と述語を明確にするなど、言葉の選び方も聞き取りやすさに大きく影響します。
話の構成が整理されていて、情報の順番が自然であれば、面接官はスムーズに内容を把握できます。
意識すべきなのは「伝えたいこと」だけでなく、「どうすれば相手に伝わるか」です。
そのために話し方のテンポや言葉の明瞭さにも気を配ることが大切です。
【面接ガクチカ何分?】面接時に長すぎる・短すぎる場合に与える影響と対処法
長い分には言いたいことが伝わるので良いのではないかと思っている人もいるのではないでしょうか。
しかし、長いから伝わるというのは間違いで、簡潔な内容のほうが圧倒的に伝わりやすくなっています。
また、長い場合は面接官が飽きてしまう可能性もあります。
さらに、物事を簡潔に伝える能力がないと思われてしまう可能性があり、コミュニケーション能力不足のレッテルを貼られてしまう可能性もあるのです。
このように長すぎだったり、極端に短すぎだったりする場合にはリスクがあるのです。
長すぎる場合
回答が長すぎる場合の問題点を考えてみたいと思います。
長すぎる場合は、やはり面接官が飽きてしまうか、言語能力不足と思われてしまう可能性があります。
長すぎる場合は、面接官が飽きる可能性があります。
特に危険なのが、面接官の意図を理解しない回答を長く続けてしまうことです。
これでは面接官は得るものがないと早々に真剣に聞くのをやめてしまう可能性があるのです。
意図が合っていれば、長いと思いながらも、聞いてくれる可能性は高いですが、くれぐれも意図を理解しない長い回答は避けるようにしましょう。
意図を理解できなければ、合格するのはかなり難しくなってしまうでしょう。
面接の回答が長すぎる場合は、コミュニケーション能力が不足していると思われてしまう可能性があります。
簡潔にまとめる能力がないということは、相手とコミュニケーションを取る力がないということになってしまうので、チームワークや接客が重視される業界においては、致命的になってしまう可能性があります。
短すぎる場合
回答が長すぎるのはいけませんが、短すぎるのもいけません。
短すぎることによっても、別の悪い評価を下されてしまう可能性がありますので注意してください。
面接においては面接官の印象値は重要です。
そして、短すぎる回答は面接官の印象に残らない可能性があります。
短い回答よりも、長い回答の方が、面接官の感性に引っかかる可能性は増えるのです。
逆に、短すぎる回答では、そういったことも難しいでしょう。
そのため、長すぎるのはいけませんが、適度な長さは必要になってくると言えます。
最低限、興味を持つタイミングを与えるくらいの長さは必要になってくるのです。
長すぎる場合もコミュニケーション能力を疑われてしまう可能性がありますが、短い場合も同様です。
また、短すぎる場合はコミュニケーション能力不足だけではなく、思考能力に問題があると思われてしまう可能性があります。
特定の質問に対する回答が短すぎると、質問の意図を理解して、それを広げる能力が低いと思われてしまいやすいのです。
そう思われてしまわないためにも、質問の意図を理解するとともに、適度な長さで答えるようにしましょう。
また、場合によってはそもそもやる気がないと思われてしまう可能性もあります。
これでは受かるものも受からなくなってしまうでしょう。
面接官の質問に対して答える際、回答はこの長さであっているだろうか?と心配になることがあると思います。
そういった心配は、面接の場数を踏むことで解消されていくことが多いです。
面接に慣れていくことで、この面接官は長めに答えたほうがやりやすそうだなや、短めに答えさせて会話のように進める方が好きなんだなといったことが分かるようになっていきます。
緊張するような面接の場面で、自分の人間性が伝わるように話せるようになったり、臨機応変な対応力を身に着けたりするには、ひたすら面接の場数を踏むことにつきます。
企業の面接官だと緊張してしまうという場合は、友人や先輩と面接練習をするのもよいかもしれませんね。
ここまでの内容を理解していれば、おそらく面接で困ることはないでしょう。
しかし、どれだけイメージできたとしても、実際に面接の場に行くとパニックになってしまう可能性があります。
もし面接においてまだ不安を抱いている場合は、就活エージェントを利用するのも良いでしょう。
就活エージェントとは、就活におけるサポートをしてくれる、とても便利なサービスです。
ここでは面接対策もきちんと対応してくれますし、何より無料でアドバイスが受けられるので、利用して損はありません。
以下におすすめの就活エージェントを紹介しておきますので、ぜひ利用してみてください。
まとめ
面接での回答の際の目安がわかったのではないでしょうか。
1分程度という目安はあるものの、あまりこれにとらわれないようにしましょう。
また、長すぎても、短すぎても悪い評価になってしまう可能性があり、最悪の場合はコミュニケーションのできない人、能力の低い人と思われてしまう可能性があります。
このように思われてしまったら、合格は難しくなってしまいますので、数少ないチャンスを逃さないためにも、自分なりの面接必勝法を組み立てておく必要があります。
まずは簡潔に自分の良さを伝える工夫をしてみましょう。
また、面接の「尊敬する人は誰ですか」などの質問にも一貫性のある回答ができるとなおいいです。
そちらも対策したい方はこちらをご活用ください。

_720x550.webp)