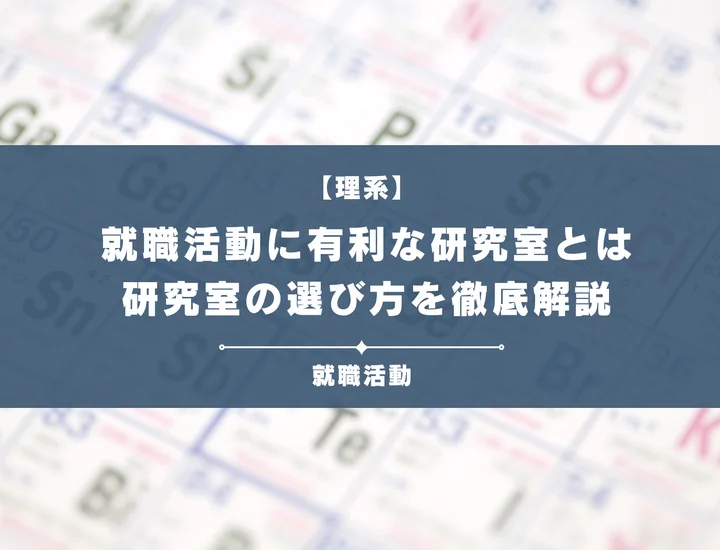HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
 理系学生にとって、研究室選びは大きな関心事です。
理系学生にとって、研究室選びは大きな関心事です。
研究室選びは、残りの大学生活のみならず就職にも関わることなので、慎重に選ぶべきです。
それでは研究室選びに失敗しないためには、どうすればよいのでしょうか。
この記事では研究室を選ぶ際のチェックポイントや、注意すべき「ブラック研究室」について詳しくご紹介します。
まだやりたいことがみつからず、将来どのような職業に就職するかが決まっていない人も研究室を選ぶ基準にしてみてください。
【研究室の選び方】研究室選びは理系生にとって重要!
理系学生にとって研究室選びは非常に重要なものです。
ここではなぜ研究室選びが理系学生にとって大事なのかを解説します。
周りの友達が選んでいるからなんとなくという考えでは、将来後悔することになるかもしれません。
あくまで自分に合うかどうかを基準に考えるべきです。
研究室に入ってからの生活や卒業後の将来についてピンときていない人は、この記事を読んで今から考えるようにしましょう。
研究室は就職に直結する
どの研究室を出ているかどうかは、就職に大きな影響があります。
具体的にはどのような内容の研究を行っていたか、どのようなレベルの研究を行っていたか、だれのもとで研究をしていたかなどが考慮されます。
このように就職に有利な研究室と、反対に不利な研究室が存在するため研究室は慎重に選ぶ必要があるのです。
自分が就職したい業界が決まっている人は、その業界の内容により近い研究室を選ぶようにしましょう。
とくに研究職を志している人は、実験手法や解析技術・経験が求められることがあります。
その研究室が有している設備にも注目することをおすすめします。
また研究室によっては企業との共同研究を行っていたり、教授が企業とのつながりがあったりする場合があるため、事前の情報収集は欠かさないようにしましょう。
研究室が変わると全てが変わる
研究室選びによって卒業までの大学生活や将来の進路など、さまざまなことが大きく変わります。
これは研究室ごとに研究に充てる時間や資金、ルールや指導方針などが異なるからです。
研究室のルールは基本的に教授が決定しているため、教授の考えや人柄でその研究室の雰囲気が決まるといっても過言ではありません。
研究室に入ってから苦労しないためにも、自分の研究に対する考えややる気の度合いがその研究室や教授と合っているかを確認しましょう。
またチームを組むか、個人で研究を行うかなどの研究形態もその研究室次第です。
自分がやりたい研究ができる研究室かどうかを事前に見極めることも大事です。
チームを組む場合は自分の意志と関係なく、行う作業が定められてしまう可能性もあります。
研究室は変えられる?
「研究室に入ったけれど、自分とは合わないからやめたい」と思ったときに、研究室を変えられるのでしょうか。
実は、条件によりますが研究室は変えられます。
それでは条件とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。
まず研究室によっては定員が決まっているところがあります。
とくに成績順で研究室に入れる学生を決めている場合は、ある水準以上の成績が必要です。
さらに新しい研究室に移ることは、新しい内容を学びなおさなければならないことです。
このようにある程度のハードルがあることは覚悟する必要があります。
そのうえで研究室を移りたい場合は、指導教員や専攻長に相談しましょう。
【研究室の選び方】失敗しない研究室の選び方
もちろん興味のある研究内容かどうかで研究室を選ぶという考えもありますが、それだけでは後悔が残るかもしれません。
さまざまな視点から研究室を知り、選択することが大事です。
ここではどこに着目して研究室を選べば失敗しないかについてご紹介します。
どんな教授か?
研究室を選ぶ際、教授との相性に着目することが重要です。
なぜなら研究をはじめるとその研究室にこもりっぱなしになることがあるからです。
とくに教授と協力して共同研究を行う場合は、さらに教授との相性が影響します。
いざ研究室に入ってから大きなストレスを抱えないためにも、教授の人柄や考え方を事前にたしかめておきましょう。
おすすめの方法はやはり事前に研究室訪問を行うこと、研究室の先輩に様子を聞くことです。
大学院に行くなら教授は重要
さらにその研究室で修士課程への進学を考えている場合、とくに教授は重要なポイントです。
学士過程で1年間・修士課程で2年間と考えると、その教授とは3年間の付き合いとなります。
今までの大学生活と同じ長さの時間、一緒に研究を行うことを念頭においてみてください。
教授の人柄は研究のモチベーションにも関わっていきます。
途中で投げ出さずに卒業できるかどうかを想像してみましょう。
コアタイムはどれくらいか?
コアタイムとは、それぞれの研究室で定められている研究に費やす時間のことです。
言い換えると「最低限この時間帯は研究室にいてください」という拘束時間を指しています。
コアタイムは研究室ごとに大きく異なるものです。
週に一度のゼミに出席すれば、あとは自由に研究をしてよいとする研究室もある一方、朝から晩まで研究室にいなければならない研究室もあります。
自分がそのコアタイムでやっていけるかどうかを考えておきましょう。
研究テーマはなにか?
研究室によって、扱っている研究テーマはさまざまです。
自分がその研究テーマに興味をもてるかどうかはモチベーションにも関わるためたいへん重要です。
「興味のあるテーマがみつからない」という場合は「自分が苦手に思う作業がない」ことを基準に、研究室を選ぶという手もあります。
動物が苦手な人が生態学の研究室に進んだり、パソコンが苦手な人が数理モデルを扱う研究室に進んだりすると、入ってからストレスを感じる可能性が高いでしょう。
就職実績はどのようなものか?
卒業後に就職を考えている場合は、その研究室の過去の就職実績を確認することをおすすめします。
なぜなら担当教員によって推薦してもらえる業界や企業に違いがあるからです。
自分が希望する企業とのつながりのある研究室や教員を選べたら、卒業前の就職活動がグンと楽になります。
事前にしっかりリサーチすることが必要です。
直接教員に聞きにくい場合は、その研究室の先輩に相談するとよいでしょう。
研究実績(論文など)はあるか?
研究室に入り今後のためにもなんらかの成果を出したいという人は、その研究室の研究実績を確認しましょう。
具体的には論文がきちんと更新されているかをみるとわかりやすいのです。
これはその研究室の研究レベルを知る尺度にもなります。
もっともおすすめなのが、先輩の卒業研究発表会に参加することです。
先輩が研究室で実際に1年間過ごして出た成果をダイレクトに知れるため、研究室選びの指標にしやすいでしょう。
先輩に聞いてみよう
これまでご紹介してきた研究室選びのポイントですが、直接教授や教員に聞くことに抵抗を感じる人も多いのではないでしょうか。
とくに就職に関することは、教授によっては反感を買ってしまう場合もあるので注意が必要です。
迷ったときは、その研究室の先輩に聞きましょう。
先輩は実際にその研究室で1年間過ごしており、このような生の声がもっとも信憑性が高いといえます。
情報戦に勝ち抜くためにも、先輩を味方につけておくのがおすすめです。
【研究室の選び方】ブラック研究室って何?
研究室選びをするなかで気をつけておきたいのが「ブラック研究室」です。
ブラック研究室とは「所属している学生が正当な研究を行えない状態の研究室」のことです。
そもそも大学教授という存在は「教員」であると同時に「研究者」でもあります。
もちろん学生への教育を熱心にしている教授もいますが、一方で研究者として学生をかえりみない教授もいます。
ひどい場合研究室の学生を、自分の研究の駒として雑務ばかりさせるケースがあることも事実です。
このような研究室に入ることを避けるためにも、先輩から情報を集めることは必須といえるでしょう。
ここではこのブラック研究室がいったいどのようなものなのか、その特徴をふたつご紹介します。
教育してもらえない
ブラック研究室において、学生が十分な教育を受けられないケースがあります。
これは教授が多忙すぎて学生にかまう時間がない、教授が自分の研究のことしか考えておらず学生を労働力として雑務のみさせているなどの原因が考えられます。
研究室で十分な教育を受けられないと、大学院進学や就職活動において大きなハンデを背負うことになるでしょう。
違和感を覚えたら周りの教員や先輩に一度相談するようにしましょう。
研究実績が伴わない
ブラック研究室と呼ばれる研究室のなかには、コアタイムに対する研究実績が伴わない研究室があります。
もちろん「研究」という性質上、根気強く真実を追い求めることは必要ですが、度を超えている場合には注意が必要です。
研究実績が伴わないことの原因には学生への教育不足や資金、設備面での問題が考えられます。
研究をはじめる前に、その実現可能性を今一度確認しましょう。
研究実績が伴わないと卒業論文を書けず、学位取得にも影響が現れます。
【研究室の選び方】研究室と就活の関係とは
研究室での活動は、理系学生の就職活動において大きな強みとなります。
専門知識やスキルだけでなく、課題解決のプロセスや人とのつながり、時間管理の経験など、社会に出てからも活かせる力が培われます。
しかし、就職活動では単に研究内容を説明するだけでは十分ではありません。
どのようにそれをアピールするか、また研究室のネットワークやスケジュール管理をどう活用するかが、就職活動の結果を左右します。
研究で培った専門知識を就活でアピールするには
理系学生が就職活動で研究経験を活かすためには、研究のテーマや成果だけでなく、そこから得られたスキルや行動力を明確に伝えることが重要です。
研究過程で直面した問題をどのように分析し、解決策を見出したのかは、論理的思考力や課題解決能力の証拠となります。
また、学会発表や論文作成を通して培った専門知識は、志望企業の事業や製品と関連付けて話すことで説得力が増します。
さらに、研究を他者に分かりやすく説明するプレゼンテーション能力は、ビジネス現場で不可欠な力です。
これらを総合的に整理し、面接やエントリーシートで具体的なエピソードとして盛り込むことで、研究経験を企業が求める人材像に結び付けることができます。
研究室のOB・OGや教授との繋がりを就活で活かすには
研究室の人脈は、理系学生にとって貴重な就職活動の資源です。
OB・OG訪問では、実際に働いている人から仕事内容や職場環境、求められるスキルを直接聞くことができます。
これにより企業理解が深まり、選考で説得力のある志望動機を作ることが可能です。
また、教授は企業とのつながりを持っている場合が多く、推薦状や直接の紹介を通して採用に有利に働くこともあります。
ただし、このような協力は日頃からの信頼関係が前提です。
研究に真剣に取り組み、積極的にコミュニケーションを取ることで、教授や先輩からの支援を得やすくなります。
人脈を有効活用するためには、就活の段階で関係を深めておくことが欠かせません。
研究と就活のスケジュールを両立させるには
修士課程や学部4年生の就職活動は、研究の山場と重なりやすく、計画的な時間管理が必要です。
まず、研究のピーク時期と就活の本格化する時期を把握し、あらかじめ年間スケジュールを立てましょう。
教授とは定期的に進捗や就活の状況を共有し、面接や企業訪問のために研究を一時的に離れる必要がある場合も理解を得られるようにします。
また、エントリーシートの作成や面接練習は実験の合間や移動時間など隙間時間を活用して進めると効率的です。
スケジュール管理の工夫は、研究の質を落とさず就職活動も進めるために欠かせません。
両立に成功すれば、時間配分や優先順位付けの能力も企業にアピールできる強みとなります。
【研究室の選び方】研究室のタイプ別:就職への影響と選び方
研究室の選び方は、大学生活の研究活動だけでなく、その後のキャリアにも大きく影響します。
同じ学部や専攻であっても、研究室ごとの特色によって得られる経験やスキルは異なります。
そのため、自分の将来像や興味に合わせて研究室を選ぶことが重要です。
ここでは、タイプ別に研究室の特徴と、それが就職活動にどのような影響を与えるかを解説します。
企業との共同研究が多い研究室
企業との共同研究が盛んな研究室では、学術的な知識だけでなく、実社会での課題解決スキルを身につけることができます。
共同研究では企業が直面する具体的な課題に取り組むため、現場のニーズや業界の動向を理解する機会が多く得られます。
その経験は、研究テーマが企業の事業内容と密接に関連している場合、共同研究先への就職や同業界での採用に有利に働くことがあります。
また、研究の過程で企業担当者と直接関わるため、ビジネス上のコミュニケーション能力や実務感覚も養われます。
基礎研究がメインの研究室
基礎研究を中心とする研究室は、長期間にわたり特定の分野を深く掘り下げる環境が整っています。
理論の構築や新しい知見の発見など、学問的価値の高い研究を行うことが多く、論理的思考力や課題解決力を徹底的に鍛えることができます。
このような経験は、アカデミアや大手企業の研究開発部門など、高度な専門性が求められる職種を志望する際に強みとなります。
一方で、成果がすぐに実用化されることは少ないため、忍耐力や継続力が必要です。
研究分野を極めたい人や、学問的な深さを武器に将来のキャリアを築きたい人に適しています。
卒業生の進路が幅広い研究室
卒業生が多様な業界や職種に進んでいる研究室は、特定の分野に縛られずキャリアの選択肢を広げられる環境です。
このような研究室では、学生が多様なテーマに取り組む傾向があり、幅広いスキルや知識を得ることができます。
就職活動の際には、研究を通じて培った分析力、計画力、プレゼンテーション力など、汎用性の高いスキルが評価されます。
業界を絞り切れていない段階の学生や、将来的に複数の分野で活躍する可能性を残したい学生にとって魅力的な選択肢です。
【研究室への選び方】研究テーマ選びの重要性
研究室や研究テーマを選ぶ際には、単なる興味や成績だけでなく、その選択理由や背景までを意識することが重要です。
就職活動では、面接官が研究内容の専門性そのものよりも、テーマを選んだきっかけや動機、そこから得られた経験や学びを重視する傾向があります。
自分の考え方や取り組み姿勢を伝えるためにも、選択に至るまでの経緯や、自ら工夫した点を明確にしておくことが大切です。
なぜそのテーマを選んだか
面接では研究の詳細な成果よりも、そのテーマを選んだ理由や背景が評価されます。
テーマを選ぶ過程には、興味関心だけでなく、社会的な課題や将来のキャリアを意識した視点が含まれていることが望ましいです。
自分がどのような思考で選択を行ったのかを説明できることで、計画性や問題意識の高さを示すことができます。
また、選択後にどのような課題に直面し、どのように取り組んできたのかを具体的に話すことで、努力の過程や粘り強さもアピールできます。
研究と企業を結びつける
研究を就職活動で活かすためには、その内容が企業の事業や製品にどう役立つかを考える視点が必要です。
分野が直接関係しない場合でも、研究で身につけた課題発見力、分析力、問題解決の方法などは多くの職種で評価されます。
面接で話す際には、研究で取り組んだテーマと企業の事業領域を結びつけ、自分のスキルがどのように応用できるかを示すことが大切です。
事前に企業研究を行い、自分の研究内容と結びつくキーワードや課題を見つけておくことで、説得力のあるアピールにつながります。
【研究室の選び方】研究室選びは慎重に!
研究室選びは理系生にとって大きなイベントであり、慎重さが求められます。
なぜなら就職活動や自身の大学4年生の生活にも関わってくるからです。
就職活動の面では、教授ごとに企業とつながっているケースがあります。
卒業の際に学校推薦を利用したいと考えている人は事前に情報を集めておきましょう。
学校推薦を利用しない場合でも、就職を考えている業界にもっとも近い研究室を選ぶとよいでしょう。
また研究室ごとに決められているコアタイムやルールによって、大学4年生の生活は大きく左右されます。
研究にかける熱量も研究室ごとに異なるため、自分に合うかどうかを基準に研究室を選ぶことをおすすめします。
【研究室の選び方】まとめ
ここまで理系生の研究室の選び方や、気になるブラック研究室の実態について解説していきました。
研究室選びは情報戦ともいわれます。
就職についてコアタイムや研究形態、研究室の雰囲気などチェックすべき項目は多くあります。
このような情報を教授に直接聞くことに抵抗がある人も多いでしょう。
この場合はその研究室で実際に1年間過ごしてきた先輩の生の声を聞くことをおすすめします。
きちんと事前に情報を集めて、入ってから後悔しない研究室選びをしましょう。