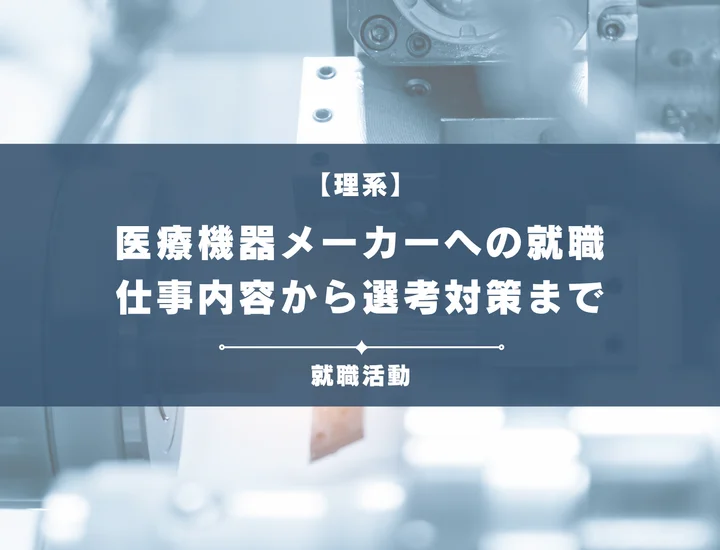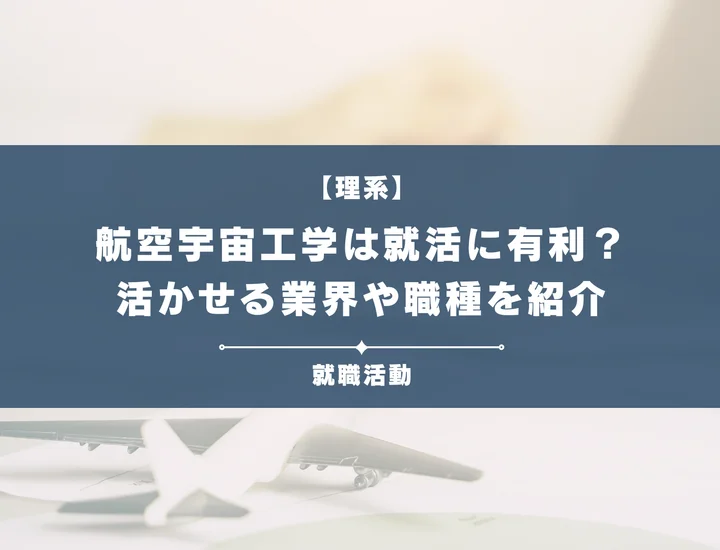HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
卒論は、ただ書いて終わりではありません。
完成には製本化やプレゼンも必要となり、ギリギリの提出では余裕もなくなってしまいます。
まずは卒論を書き始める時期や、研究を始める時期について考え、余裕のあるスケジュールを組み立てましょう。
普段から考察するくせをつけておけば、執筆の段階で慌てることもありません。
そのため執筆に入るまでの準備が、完成の肝となります。
今回は卒論にかかる時間や時期ごとのスケジュールなどを、詳しく解説していきましょう。
ぜひともポイントを押さえて、余裕をもって卒論を仕上げてみてください。
【卒論完成までの時期感を紹介】卒論完成までにはやるべきことが2つある!
卒論を完成させるためには、卒業研究の製本化と審査員を前にしたプレゼンの2種類を、3月までに終える必要があります。
なぜ3月までに卒論を完成しなければならないのでしょうか。
それは、提出日が1月下旬から3月中旬までと決められている学校が多いからです。
また卒論の提出では製本化した卒論と、プレゼンテーションの両方に合格しないと卒業認定がされません。
そのため卒論の提出には上記の2つを、3月までにこなす必要があると覚えておきましょう。
卒業研究を製本化する
卒業研究は製本化が必要となります。
卒論は文字として書くだけではなく、20ページほどの本として提出する必要があるからです。
なぜ製本化が必要かといえば、ファイル化したときの文字のずれなどを防ぐためです。
卒論をWordなどで書く学生も多いものでしょう。
しかしファイル形式を間違えれば、文字のずれやページに収まりきらないなどの問題が生じます。
特にoffice系のソフトを使った場合は、問題が生じる可能性は高くなります。
使用しているパソコンの環境に左右されるため、文章の区切りなどがおかしくなる可能性も高いといえるでしょう。
そこで印刷をしておけば、どんな環境でも論文を読めるようになるため、卒論は製本化するように学校で決められています。
また卒論は長い文章です。
製本化するときには、レイアウトに注意が必要です。
せっかく製本化しても読みづらくなってしまえば、そもそもの意味がなくなってしまうでしょう。
審査員の前でプレゼンする
卒論を完成させるためにはスライドを作成し、審査員の前でプレゼンをする必要があります。
なぜなら製本化とプレゼンが終わってからでないと、卒業認定がされないからです。
卒論を書き始める時期は、研究所や学校によっても違います。
もし提出時期があやふやな場合は、所属する研究所の先輩に聞いてみるのがおすすめです。
自分の研究内容の進み具合によっても時期は変わりますが、論文を先生にチェックしてもらう時間も考慮しましょう。
なかには卒論の提出だけで、卒業認定される学校もあります。
しかし多くの場合、審査員を前にしたプレゼンも含まれています。
スライド作成などの作業時間も同時に考えたうえで、卒論の完成時期は3月までに終えておきましょう。
もちろん、プレゼンの内容によっては卒業認定されないので、内容も大切です。
【卒論完成までの時期感を紹介】卒論完成までの流れ
卒論完成までの理想的な流れは、4月から研究を開始し、テーマを決めましょう。
そして研究計画を立て、事前研究を経て、10月の中間発表を終えるのが前半期です。
中間発表以降の理想的な流れは10月に実験計画を立て、実験と分析を繰り返しながら11月に卒論の執筆を開始することです。
そのあとも分析や考察を経て、2月までにはプレゼン用の資料も作成しておきましょう。
2月の段階で卒論が完成していれば、スムーズに卒業できます。
ただこちらはあくまで理想像です。
以下に卒論完成までの流れを月ごとにご紹介しますので、参考にしてみてください。
4月:研究室配属とテーマ決定
この時期は、研究室選びと卒論テーマの決定が主なタスクになります。
まずは大学の研究室一覧や教員の研究紹介を調べ、興味のある分野を絞っていきます。
過去の卒論テーマや研究内容を調べることで、研究室の方向性が見えてきます。
指導教員との面談を通じて研究の具体的な内容や進め方を確認し、自分に合った研究室を選ぶことが重要です。
テーマが決まったら研究計画書を作成し、目的や方法、スケジュールを明確にして提出します。
この段階で先行研究にも目を通しておくと、テーマへの理解が深まります。
配属とテーマ決定は今後の研究活動の土台となるため、慎重に取り組んでいきましょう。
5月〜7月:研究に慣れる
この時期は、卒論に必要な基礎力を身につける大切な準備期間です。
実験や調査をスムーズに進めるために、研究手法や使用する機器の扱いを習得することが求められます。
教員や先輩からの指導を受けながら、実験の流れ、データの取り方、事故を防ぐための注意点などを学びます。
あわせて文献調査も進め、先行研究の把握や理論背景の理解に努めましょう。
重要な論文にはマーカーを引いたり、要点をノートに整理したりすると、後々役立ちます。
研究ノートの記録は、実験条件や気づき、トラブルの対処なども含めて詳細に書き残すことがポイントです。
中間報告の準備も始まるため、研究の目的や進捗、得られた結果を他人に伝える訓練も兼ねて、プレゼン力を意識するようにしましょう。
この段階で基礎を固めておくことで、後の研究活動がスムーズに進みます。
8月〜9月:大学院入試
この時期は大学院入試が行われる重要な期間であると同時に、卒論の研究も本格化するため、時間の使い方が鍵となります。
志望する大学院の入試日程や出願書類、過去問などの情報収集を早めに行い、効率よく対策を進めましょう。
また、面接試験や小論文がある場合は、指導教員や先輩にアドバイスをもらいながら準備を進めると安心です。
一方で、卒論テーマに基づいた実験や調査も同時に始まります。
研究室によってはこのタイミングで本格的なデータ収集に入るため、スケジュール管理が非常に重要になります。
時間の制約が厳しくなるため、無駄のない行動を意識し、優先順位をつけて作業を進めることが求められます。
もし研究が遅れている場合は、指導教員に進捗状況をこまめに報告し、軌道修正のアドバイスを受けるようにしましょう。
9月〜10月:繁忙期
9月から10月にかけては、卒論の山場ともいえる繁忙期に突入します。
この期間は本格的にデータの収集と解析を行い、得られた結果をもとに考察を進めることになります。
実験データの整理はもちろん、グラフ化や統計処理などを行い、論理的に妥当な結論を導き出すスキルが問われます。
必要であれば、統計ソフトやプログラムを使いこなすための勉強も並行して行うとよいでしょう。
また、研究内容と先行研究との違いや、自身の研究から得られた新たな知見についても明確にしておくことが大切です。
この時期には論文の構成も同時に検討し始める必要があります。
序論から結論に至るまで、どのような流れで読み手に伝えるかを意識して、全体の構成を固めていきましょう。
11月〜1月:卒論に取りまとめる
いよいよ卒論提出に向けた仕上げの時期に入ります。
これまでに得られたデータや考察を基に、卒論本文の執筆を本格的に進めましょう。
序論では研究の背景と目的を明確にし、方法では手順や使用機器、条件を丁寧に記述します。
結果ではデータを正確に提示し、考察では先行研究との比較や自分の仮説との整合性を論じます。
引用する文献の形式や図表の配置にも注意を払い、読みやすい論文を目指してください。
執筆後は何度も推敲し、誤字脱字や文法のミスを見逃さないようにします。
また、自分の論理が第三者に伝わるかどうかを確認するためにも、指導教員だけでなく、友人や研究室の仲間に読んでもらうことも有効です。
さらに、この時期には卒論発表会の準備も必要になります。
スライドの作成、要点の整理、質疑応答の対策など、プレゼンテーションスキルも求められます。
2月〜3月:研究の引き継ぎ
卒論提出と発表を終えた後も、研究室での役割はまだ残っています。
2月から3月にかけては、後輩への引き継ぎや研究室の整理といった「締めくくり」の業務が重要になります。
自分が行ってきた研究内容や使用した実験手順、注意点、工夫した点などをまとめておくことで、次年度の学生がスムーズに研究を始めることができます。
口頭で説明するだけでなく、データファイルや研究ノート、マニュアルなどを整理し、後輩が活用しやすい状態にしておくと親切です。
また、使用した機器や器具を丁寧に清掃し、故障や破損があれば修理や報告を行うようにしましょう。
研究室の備品管理や共有スペースの整理整頓も、この時期に済ませておくのが理想です。
さらに、卒業に向けた事務手続きや成績処理、卒業証書の申請なども忘れずに確認しておく必要があります。
【卒論完成までの時期感を紹介】卒論提出まではどのくらい時間がかかるの?
卒論完成には個人差もありますが、2ヶ月ほどはかかるでしょう。
ただ日ごろから考察に慣れておけば、早く執筆を終えられます。
ほとんどの研究所では、夏休みごろにテーマが決まります。
だからといってテーマが決定するまで遊んでしまうと、いざテーマが決まっても執筆の準備に入れません。
なかには提出ギリギリまで実験をする人もいますが、そうなると2ヶ月での完成は難しいでしょう。
少しでも勉強するくせをつけ、卒論完成までの時間を有意義に使ってください。
卒論完成には2ヶ月ほどかかる!
卒論完成は、一般的に2ヶ月ほど時間がかかるといわれます。
そのためスケジュール管理を行い、卒論の執筆時間も計画に入れておくのがおすすめです。
卒論を書き始める時期の目安も、逆算すると2ヶ月ほど前からになります。
卒論の締め切りが近づくと、周りでもそわそわする人は増えますが、焦らずにしっかりと卒論を仕上げましょう。
なかには締め切りの1~1.5ヶ月前がおすすめという方もいます。
ただなんらかのアクシデントがあることを想定すれば、余裕をもって執筆を始めたほうがよいのは間違いありません。
特に理系の場合は実験が難航して、スケジュールがずれ込む可能性は高いでしょう。
実験の失敗もアクシデントの1つなので、余裕をもってスケジュールを組めば、卒論が未完成などの失敗も防げます。
日ごろの考察で効率的に書ける!
卒論を書くのには時間もかかりますが、普段から準備をおこたらなければそう難しいものではありません。
日ごろから結果をまとめるようにすれば、効率よく書けるようになります。
卒論は書式などのルールが大学によっても違います。
ただ日ごろから研究時に論文を読む、先輩の論文を読むなどして、考察するくせをつけておけば卒論を効率的に進められるでしょう。
卒論を書くうえで大切なのは、内容を自分で考えることに尽きます。
得られた実験結果からどのような考察ができるか、またどのような結論に至るのかなど常に考えておきましょう。
また必要なデータを整理しておけば、提出の1ヶ月前から始めて1週間もかからず書けるようになります。
普段から大学を学びの場と考え、準備をおこたらないようにしましょう。
【卒論のスケジュール】卒論執筆のコツ
構成を明確にする
卒業論文を書くうえで、全体の構成を明確にすることは非常に重要です。
論文の基本的な流れである「序論→先行研究→方法→結果→考察→結論」を意識し、各章でどのような情報を提示し、何を主張するのかを具体的に整理しておくことで、執筆中に話の軸がぶれにくくなります。
特に論理的な流れを重視する理系の論文では、論の順序や因果関係が明確であることが読みやすさに直結します。
構成案を紙に書き出したり、マインドマップで視覚化するのも有効です。
構成を丁寧に準備しておくことで、卒論執筆が計画的かつ効率的に進みやすくなります。
参考文献を整理する
卒業論文では、信頼性のある文献を根拠に論を展開することが求められます。
そのため、早い段階から関連文献を収集・整理しておくことが重要です。
文献情報は、著者名、タイトル、雑誌名、巻号、ページ数、発行年などの書誌情報を正確に記録しましょう。
これにより、参考文献リストの作成時に時間を取られることなくスムーズに対応できます。
引用元が不明になったり、誤った文献を記載してしまうリスクも減ります。
整理には、ZoteroやMendeleyなどの文献管理ツールを活用するのも効果的です。
図表の準備
実験や調査によって得られたデータを視覚的に示す図表は、論文における説得力を高める重要な要素です。
グラフや表を使うことで、読み手がデータの傾向や比較結果を直感的に理解しやすくなります。
図や表には必ず番号とタイトル(キャプション)をつけ、どのような内容を示しているかを明確に記述する必要があります。
また、本文中では図表を参照しながら適切に解説を加えることが求められます。
早めにデータの整理と図表の作成を進めておくことで、執筆段階での作業負担を軽減できます。
執筆計画を立てる
卒論は分量が多く、内容も専門的であるため、計画的に執筆を進めないと締切直前に追い込まれてしまうリスクがあります。
そのため、いつまでにどの部分を仕上げるかといった執筆スケジュールを事前に立てておくことが不可欠です。
たとえば「◯月第1週までに序論」「◯月第2週までに先行研究部分」というように、週単位や日単位で目標を設定すると進捗管理がしやすくなります。
また、推敲や指導教員への確認にかかる時間も考慮し、余裕を持ったスケジューリングが大切です。
Googleカレンダーなどを使って可視化すると、全体の進行状況を把握しやすくなります。
【卒論のスケジュール】卒論発表のコツ
発表時間と内容の調整
卒論発表では、限られた時間内で自身の研究成果を的確に伝えることが求められます。
まず最優先すべきは、発表時間の厳守です。
例えば「10分間」という制限があるなら、必ずその時間内に収まるよう、事前に何度も練習を行いましょう。
発表内容をすべて詰め込もうとすると、話が早口になったり、聞き手に伝わらなかったりする可能性があります。
そのため、全体を要約し、伝えたいメッセージや結論、研究の意義など「一番伝えるべきポイント」を明確にして話す構成が重要です。
スライド作成のポイント
スライドは「見やすく、伝わりやすく」を基本に作成しましょう。
文字は大きめにし、フォントも読みやすいものを選びます。
背景と文字色のコントラストにも注意し、暗い背景には明るい文字、明るい背景には濃い文字を使うなど、視認性を高めましょう。
情報を詰め込みすぎないことも重要です。
一つのスライドに詰め込むと聞き手の理解が追いつかなくなります。
図表やグラフを適切に活用することで、視覚的に情報を伝えることができます。
特にデータの傾向や比較を示す場面では、文章よりグラフの方が効果的です。
発表原稿の作成と練習
発表を成功させるためには、スライド内容に基づいた発表原稿の準備が欠かせません。
全文を丸暗記する必要はありませんが、話の流れや重要なキーワードを整理しておくことで、本番でも落ち着いて話すことができます。
スライドに記載したキーワードをもとに、聞き手にわかりやすく説明を加えるスタイルがおすすめです。
また、話すスピード、声の大きさ、抑揚、間の取り方などにも気を配りましょう。
一人で練習するだけでなく、友人や研究室のメンバーの前で模擬発表を行うことで、より実践的な練習ができます。
質疑応答への準備
質疑応答の時間は、発表内容をより深く掘り下げたり、聞き手の理解を確認したりする貴重な機会です。
そのため、発表内容に関連する質問を事前に想定し、しっかりと答えを準備しておきましょう。
よくある質問としては「なぜその方法を選んだのか」「他の研究との違いは何か」「結果の解釈は妥当か」などが挙げられます。
模擬質問を指導教員や研究室の先輩にしてもらうことで、より実践的な対策になります。
質問された際には、緊張しても慌てず、丁寧に返答することを心がけましょう。
【卒論完成までの時期感を紹介】まとめ
卒論を完成させるためにすべきこと、どれくらいの時間が必要か、また時期によって考えるスケジュール例などご紹介しました。
卒論は卒業するために必要ですが、卒業認定をもらうには、ただ書くだけでは不十分です。
卒論を完成させるには、本文の内容を充実させる必要があります。
同時に製本化する点や、プレゼンが必要になる点にも注意が必要です。
ギリギリに卒論を書き上げるのでは、プレゼンなどもおろそかになってしまうでしょう。
ぜひとも卒論の完成までのスケジュールも考え、より効率的に卒論を書いてみてください。