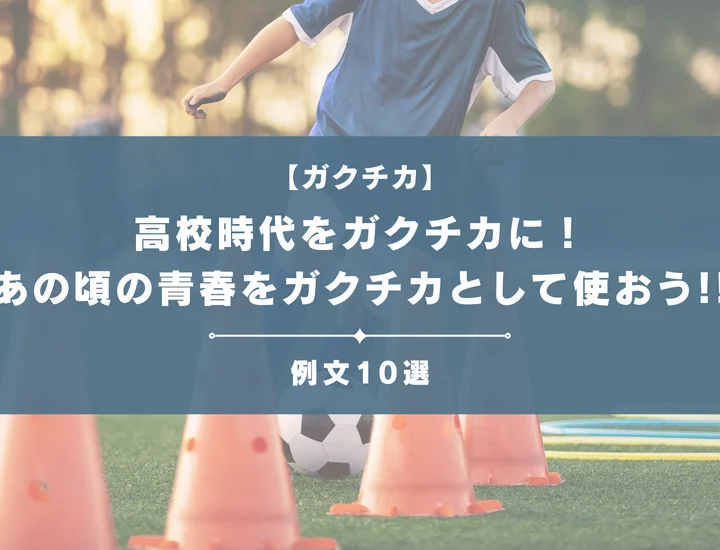HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
「学業との両立に関するエピソードはガクチカになるのでしょうか?」 「就活で企業からガクチカを聞かれる理由って?」 「どのようにしてガクチカを作ればいいの?」 このように、「学業との両立」がガクチカになるのか知りたいと考えている人も多いのではないでしょうか。
本記事では、ガクチカを企業に聞かれる理由やガクチカを作る時の流れ、ガクチカを作る時の注意点などを紹介しています。本記事を読むことで、どのようにしてガクチカを作れば良いのか把握できるでしょう。
また、「学業との両立」をガクチカにする場合の例文も紹介するため、学業との両立でガクチカを考える参考にできます。
「学業との両立」のエピソードはガクチカになるのかどうか知りたい人は、ぜひ本記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。
【学業との両立をガクチカに】「学業との両立」のエピソードはガクチカになる?

「学業との両立」をベースにガクチカを考えようとしている人の中には、学業との両立エピソードがガクチカとして使えるのかどうか知りたいという人も多いでしょう。結論から述べると、「学業との両立」のエピソードは十分ガクチカになります。
企業がガクチカを聞く理由は後述しますが、自分の強みを企業へアピールできる題材が「学業との両立」ならば、それを使っても全く問題ないでしょう。
【学業との両立をガクチカに】「学業との両立」からアピールできる強み
学業との両立からアピールできる具体的な強みは下記3点があげられます。
・計画性
・行動力
・視野の広さ
この3点は就活のみならず、社会人として働く際も非常に役立ちます。
1つのことに集中して努力することはもちろん大事ですが、何かを両立することはとても大変なことです。
学業との両立をガクチカにすることに自信を持って進めていきましょう。
詳しく解説していきます。
計画性
まず計画性があることです。
ここでいう計画性とは「目標に対して実現できる計画を立てる」と理解いただいて構いません。
例えば、アルバイトで月5万円稼ぎたければ、時給1500円だと約34時間働く必要があります。
働ける日時をスケジュールに割り振っていきます。
ものごとを同時並行で行うとなると、このように計画をうまく立てなければ両立できません。
また、意外かもしれませんが計画性のある人は「力の抜き方」がうまいです。
具体的には、どうすれば挫折せずやり抜けるか、ダラダラできる時間はどれだけあるか等も考えます。
現実的に目標達成する計画を立てるのが得意なのです。
計画性はどんな仕事をする上でも大事で社会人の必須スキルともいえるため、ガクチカとして十分な強みになります。
行動力
両立がうまい人は行動力もあります。
やりたいことが複数あっても実際に行動にうつせる人は多くありません。
計画を立てるまでは得意でも、行動するのは面倒だという方は多いです。
何かものごとを両立できているということは行動できている証拠だといっても過言ではありません。
行動力がある人は試行錯誤を繰り返して成長していける人が多いです。
なぜなら、行動より得られる経験値が最も「気づき」が生まれやすく、自分の実力になっていくからです。
計画を実行すると想定より時間がかかったり失敗することもありますが、それを糧に試行錯誤しながら成長していくのです。
どこの会社も共通しているのは、成長できる人材を必要としていることです。
成長するための行動力のある人はどんな場面でも戦力になります。
視野の広さ
両立できる人は「視野の広さ」があります。
1点集中で打ち込んでいると視野が狭くなりがちですが、複数のことに熱量をもって取り組むと広い視野を持てて、柔軟な思考ができやすいのです。
両立できる人は、複数のことに取り組もうとすると、熱意だけでは目標を達成できないということも理解しています。
1ヶ月ほどの短期目標であれば熱量と行動量で何とか乗り切れますが、数ヶ月から年単位の目標では無理です。
目標を成し遂げようとする情熱と、どうすれば目標を達成できるか考える冷静さが必要になってきます。
冷静でいられる一面があるので、視野を広く持つことができるのです。
柔軟な発想は職種を問わず様々な場面で役立ちますので、視野の広さは大きな強みになります。
【学業との両立をガクチカに】ガクチカを企業に聞かれる理由

面接の際には、企業が学生時代のエピソードについて尋ねてくるケースが多いです。このように、企業がガクチカについて尋ねてくる理由としては、就活生の人柄を知りたいという理由があります。
また、就活生の人柄や人物像を知ることで、自社が求めている人物像にマッチしているかどうか見極めることにも繋がるでしょう。ここではガクチカを企業に聞かれる理由を紹介していくため、参考にしてみてはいかがでしょうか。
人柄や人間性を知りたいから
企業がガクチカを聞くのは、ガクチカを尋ねることで「なぜ学ぼうと思ったのか」、「どのようにして課題を乗り越えたのか」といったことを深掘りでき、就活生の人柄や人間性を知れることが理由です。
企業は就活生の人間性を重視して採用活動を行っているケースも多いです。就活生の人間性や実際に頑張ったことについて知ることで、企業も自社で活躍してくれそうな人材を見極めやすくなるでしょう。
また、学生側にとってもガクチカについて話すことで、面接官に自身の人柄を伝えやすいというメリットがあります。
求めている人材か見極めたいから
コストを掛けて採用した人材が自社とミスマッチだった場合、企業にとっても学生にとってもメリットがありません。そのため、企業がガクチカを聞く理由としては、自社で長く働いてくれるような人材であるかどうかを見極めたいという理由もあります。
ガクチカのエピソードについて聞くことで人柄について知ることができるため、その人材が自社にマッチした人材なのかどうかも判断しやすくなるでしょう。
【ガクチカとの両立をガクチカに】ガクチカを作る時の流れ

これからガクチカを書くという人の中には、どのような流れで書けばよいのかわからず困っているという人もいるのではないでしょうか。ガクチカを書く場合は、6つの工程に沿って書いていくことで論理的な文章が構築できます。
やみくもに文章を書くよりも、相手にとってわかりやすい順序で記載すれば、同じような内容でも評価されやすくなるでしょう。ここではガクチカを作る時の流れを紹介していくため、参考にしてみてください。
最初に結論を述べる
ガクチカを書く場合は、まず「学生時代に何に取り組んだのか」という結論から述べるようにしましょう。ガクチカに限らず、文章を作成する場合は結論ファーストにすることで、相手にわかりやすく伝えられるようになります。
また、面接官が話の大枠をイメージできるように、端的に結論を伝えるようにしましょう。なお、ガクチカには明確な目標を掲げて取り組んだことや、目標に対してどのように考え、行動したのかを感じられるような経験を選択すると、面接官に良い印象を与えやすいです。
具体的なエピソードを付け加える
具体的にどのような状況だったのか伝えることで、面接官も就活生の考え方や取り組み方などを理解できます。
また、価値観についても理解を深められるため、入社後にどのように活躍してくれるのかといったイメージも膨らむでしょう。課題を解決するためにどのような行動をとったのか説明することで、ファクトベースのガクチカになってしまうことも避けられます。
経験した問題を述べる
どのような問題や課題があったのかを述べましょう。面接官は、仕事で問題(失敗やミス)が起きた時にどう考え、どう対処する人材なのかをガクチカなどの経験を聞いて判断したいと考えていることが多いです。
目標を達成する上での課題となっていることを伝えることで、どの程度のことを困難だと感じるのか面接官に伝えられるでしょう。また、経験した問題だけでなく、なぜその問題を困難だと感じたのかまで伝えましょう。
問題を解決するためにした行動を伝える
先に述べた問題や困難を解決するために、どのような行動をとったのか述べましょう。ここでの行動は、必ずしも目標を達成したエピソードである必要はありません。
しかし問題の本質がどこにあったのか、なぜそのアプローチを選んだのかは説明する必要があります。
どのような結果を残したか伝える
前述のことに取り組んだことにより、どのような結果を残したのかを述べましょう。掲げている目標を達成できたかどうか、問題となっていたことを解決できたかどうかという結果を説明します。
結果からどう貢献できるかを伝える
ガクチカによって学んだことを活かして、どのようにして会社に貢献できるかを伝えましょう。企業がガクチカに付いて尋ねるのは、ガクチカから得た経験を活かして自社で活躍してほしいためです。
そのため、単にガクチカの結果を述べるのではなく、ガクチカで得たリーダーシップやコミュニケーション能力を入社後どのように活かせるのか、企業側の目線になって伝えるようにしましょう。
【学業との両立をガクチカに】ガクチカを作る時の注意点

ここまで紹介したとおり、学業との両立に関するエピソードを基にガクチカを作ることは可能です。ただし、学業との両立をガクチカにするためには、どのようにして努力したのかという点において他の学生と差別化することが必要不可欠です。
ここではガクチカを作る時の注意点を紹介いたします。他の学生との差別化をはかるエピソードを作る参考にしてみてください。
何を学んだかをしっかり伝える
学業について話す場合、面接官によっては「学生である以上学業に力を入れるのは当然」と判断される可能性もあります。そのため、学業との両立について話すのであれば、具体的に何を学び、何を得たのかまで伝えることを意識しましょう。
このように何を学んだかまでしっかりと伝えることで、「学業に力を入れることは大学生にとって当然」という認識を持たれることを防げるでしょう。
両立の難しさを伝える
学業との両立をガクチカにする就活生は多いため、中途半端なエピソードでは他の学生の中に埋もれてしまう可能性があります。そのため、両立することが難しいことだったということや、両立させた自身の努力まで伝えることが大切です。
両立の難しさをうまく伝えるには、客観的な評価や数値を織り交ぜながら説明するのが効果的です。また、周りから褒められたということもエピソードに盛り込むと良いでしょう。
【学業との両立をガクチカに】「学業との両立」をガクチカにする時の例文

ここでは最後に、「学業との両立」をガクチカにする時の例文を2種類紹介していきます。どのようにしてガクチカを書けばよいのかわからない人は、ぜひ参考にしてみてください。
部活との両立の場合
私が学業と部活を両立しようと考えたきっかけは、部活に力を入れ過ぎて一時的に成績が落ちてしまったことが理由です。
大学2年生のとき、私は学業に面白みを感じず、陸上部で成績を出すことに面白みを見出しのめり込んでしまいました。その結果、通年でとっていた授業の評価が落ちてしまいました。
このまま授業の評価は最低限にして、陸上部の成績を上げることに集中するか悩んだこともありましたが、自分の実力と将来を冷静に考え、学業も両立できるようにしようと決心しました。
通学中や部活の休憩中など空いた時間に常に授業の復習をするようにし、わからなかったところは教授に聞くようにしました。その結果、講義への興味・関心を深めることができ、陸上をしているのと同様に楽しさを見出すことができました。
両立できたおかげで、陸上では後輩から頼られる存在に、学業では教授とコミュニケーションをとれたおかげで倍率の高かった人気ゼミへはいることができました。
アルバイトとの両立の場合
私は自分で学費を稼がなければいけなかったため、日中は学業、夜からはアルバイトの時間にあてていました。学業とアルバイトの両立は精神的、体力的にも疲れるものだと想像すると思います。
しかし、アルバイト先では仲間とコミュニケーションをとり、連携できるようにすることと、雑談を通して精神的な辛さはそんなに感じませんでした。そして、自分の体調管理を徹底することで体力的な問題を乗り切ることができました。
また、授業では講義の内容をノートにまとめて、できるだけ1回で理解できるように工夫しました。その結果、学業とアルバイトを両立することができたと感じています。
留学との両立の場合
留学経験は就活において差別化できる強みと言えるでしょう。
昔と比べて留学経験のある学生が増えてきたとはいえ、海外経験や現地の人たちとのコミュニケーションができることは、大きな戦力になります。
しかし、留学と大学の学業との両立は本当に大変です。
留学を志望される学生は、一旦休学をしてでも留学をするといった方は少なくありません。
大変だからこそ工夫すべき点は多く、それがガクチカとしてアピールできるのです。
留学との両立において、注力すべき点は多くありますが、カギとなるのが「時間管理」でしょう。
大学4年間でどのタイミングで留学に行くべきか、就活との兼ね合いはどうするか、短期か長期か等を考える必要があります。
時間管理のスキルは、入社後も複数のプロジェクト案件を同時平行するのに非常に役立ちます。
資格取得との両立の場合
資格取得と両立されている方もいらっしゃると思います。
勉強という観点では同じような方向性なので、両立しやすく目標も達成しやすいでしょう。
しかし、どうしても飽きてしまいやすく、どちらかがおろそかになってしまいがちなのも事実です。
資格によっては簡単に挑戦できるものもあるため、簡単にあきらめてしまう人も多いでしょう。
そんな中で集中力を保つために工夫したことなどを書くと効果的です。
モチベーションがあるかどうかによって継続する力も目標達成する確率も変わってくるでしょう。
なぜその資格取得を目指しているのか、自分のモチベーションは何なのかを説明できると説得力のあるガクチカになります。
趣味との両立
趣味と両立している人は多いでしょう。
留学や資格取得と違い、両立できている人が多いので就活においてはそんなに差別化できるのか気になる方もいらっしゃるでしょう。
結論から言いますと、単なる趣味をしていた程度ではガクチカとしては弱いですし、差別化という程ではありません。
しかし、何かの大会に参加したり記録を成し遂げるために努力してきたのであればガクチカとして十分にアピールできます。
例えば、ダンスであればイベントやオーディションがありますし、筋トレであれば目標とする体重や、バーベルの重量などがあります。
また、目標についても簡単に成し遂げられそうなものではなく、少し困難なものに挑戦しているかどうかも重要です。
ボランティア活動の両立
ボランティア活動に力を入れてきた方も多いでしょう。
ボランティアと言っても短時間でできるものもあれば長期に及ぶものもあり様々です。
中には外国に行かなければできないこともあります。
そういった活動をするには、制約が少ない大学生時代だからこそできることではあります。
しかし、学生の本文である学業をおろそかにしてはなりません。
そのために工夫したことや、ボランティア活動が学業に活かされた経験があれば書きましょう。
例えば、大学の授業に福祉・ボランティアに関するものもあります。
授業内容を実際に実践してみたり、自分が行ったボランティア活動の内容が授業の理解を深めたりといったことが考えられます。
ガクチカで学業と両立したことをアピールしよう

学業と両立したエピソードであっても、自身の強みや魅力を伝えられるエピソードであればガクチカにすることは十分可能です。
ぜひ本記事で紹介したガクチカを企業に聞かれる理由やガクチカを作る時の流れ、注意点などを参考に、学業との両立でガクチカを作ってみてはいかがでしょうか。




_720x550.webp)