
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。

エントリーシートはインターンシップや就活で書く機会が多く、その中でも定番の質問に「自己PR」「ガクチカ」「志望動機」などがあります。
しかし、「挑戦したこと」について聞いてくる企業も非常に多く、その対策が必要です。
この記事ではこの「挑戦したこと」や「人生で一番挑戦したこと」について、挑戦したことの種類や企業がこの質問を聞いてくる理由を最初に説明し、ポイントや構成、例文まで詳しく説明していきます。
挑戦したこと特化の作成ツール!

◇ 一貫性のある構成で、読み手に伝わりやすい
◇ 客観性が伝わる内容で、信頼されるESに!
◇ 書きやすい文章テンプレートで簡単作成
目次[目次を全て表示する]
【挑戦したことをESに書く!】多くの企業が挑戦経験を重視する理由
就職活動やインターンシップの際、ESや面接の場において「自己PR」や「志望動機」と並んで頻繁に聞かれる質問に、「挑戦したこと」または「人生で一番挑戦したこと」があります。
企業の採用担当者は、学生時代にどのような困難に直面し、それをどのように乗り越えたかを知りたいと考えています。
例えば、インターンシップでは大手企業のニトリ、日本航空がこの質問をエントリーシートで必須項目としており、就活の本選考でも大手飲料メーカーのサントリーなどが同様の質問をしています。
これら人気企業の選考を通過するためには、「挑戦したこと」に対する適切な準備が必須です。
- ニトリ
- 三菱商事
- 日本航空(JAL)
- ソニー
- リクルート
- トヨタ自動車
困難を乗り越える力の確認
企業が「挑戦したこと」を重視する理由の一つは、あなたの困難を乗り越える力を評価するためです。
社会では、常に予期せぬ問題や課題が発生します。採用担当者は、そのような状況において、あなたがどのように対応し、解決策を見つけたかを知りたがっています。
特に、挑戦を通じて得た経験や教訓、どのように周囲と協力しながら解決に導いたのかといった具体的なエピソードが重要です。
これにより、あなたの粘り強さや問題解決能力が浮き彫りとなり、困難に直面した際でも諦めずに取り組む姿勢が評価されるポイントとなります。
成長意欲の高さの確認
挑戦経験を通じて、自分がどれだけ成長してきたかをアピールすることは非常に重要です。
企業は、従業員の成長が企業全体の発展につながると考えており、成長意欲のある人材を求めています。
あなたが挑戦した結果、どのようなスキルを身につけ、どのような教訓を得たのかを具体的に示すことで、入社後の成長ポテンシャルを強くアピールすることができます。
特に、失敗を乗り越えた経験や、新しい視点を得たエピソードは、あなたの自己改善能力を証明する好材料です。
また、挑戦を通じて得た成長は、自分自身だけでなく、今後の会社への貢献を裏付ける力となるため、面接やESでのアピールポイントとして強力です。
企業のイノベーション推進に貢献できるかの確認
多くの企業がイノベーションを推進し、変化に対応する柔軟な人材を求めています。
挑戦を通じて得た経験は、あなたがその企業の変革や革新にどう貢献できるかを示す重要な要素です。
特に、新しいアイデアや解決策を生み出す能力があることを示せば、企業はあなたを将来の革新的なリーダー候補として評価するでしょう。
挑戦の中でリスクを恐れず、積極的に取り組んだ姿勢や、自ら新しい手法を試みた経験は、企業の中でイノベーションを推進する際に大いに役立つ力とみなされます。
このような姿勢は、企業が求める価値観と一致し、より多くのチャンスを得るための大きな武器となるでしょう。
今までになかった新しいアイデアや方法を取り入れて、製品やサービス、仕事のやり方を改善することです。企業が成長し、競争力を保つためにとても大切で、変化を起こす力を意味します。簡単に言えば、より良いものを生み出すための「革新」です。
【重要】ガクチカとの違い
「挑戦したこと」と「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」は似ているようで、企業が見ているポイントが大きく異なります。
ガクチカでは、どのような行動をとり、どんな成果を出したかという「結果」や「スキル」の部分が評価の中心です。
一方で「挑戦したこと」は、困難にどう立ち向かい、どのように考えて行動したかという“姿勢”や“成長過程”が重視されます。
たとえば、ガクチカは「チームをまとめ大会で優勝した」という結果を示すのに対し、挑戦したことは「意見の対立を乗り越えるために、どんな工夫をしたか」という過程を掘り下げる形です。
企業はこの違いを通じて、あなたの価値観や行動原理を見極めています。
そのためESで差別化するには、「成果中心のガクチカ」と「姿勢・学び中心の挑戦」を明確に書き分け、挑戦を通じて得た成長の実感を伝えることが重要です。
【挑戦したことをESに書く!】挑戦したことの種類
「挑戦したこと」とは、現状に甘んじず、自ら成長のために選んだ行動や、あえて困難に立ち向かう経験を指します。
就職活動では、挑戦を通じて得た経験やスキルを明確に伝えることで、企業が求める人物像とのマッチングを図ることができます。
挑戦の種類はさまざまであり、それぞれが異なる力や姿勢を示します。以下に、「挑戦したこと」の具体例を紹介します。
人生で一番挑戦したこと
「人生で一番挑戦したこと」は、企業が応募者の価値観や行動力、思考のクセを見極めるために重視する質問の一つです。
特別な成果を出しているかどうかよりも、挑戦に対する姿勢や、そこに込めた想い、努力の過程がどうだったかを知ることに主眼が置かれています。
そのため、この質問では「なぜその挑戦をしようと思ったのか」という動機や背景を丁寧に説明することが重要です。
また、挑戦する中で直面した困難や壁に対して、どのように考え、どう行動したのかというプロセスを伝えることで、あなたらしさや粘り強さが伝わります。
結果が成功だったか失敗だったかに関わらず、自分の成長をどう実感したかや、今後の行動にどう活かしているかまで含めて話すと、面接官にも強い印象を残すことができます。
苦手分野にもあきらめず取り組む
「苦手分野にもあきらめず取り組む」ことは、自分にとって不得手な分野や課題に対しても逃げずに向き合う姿勢を示します。
特に総合職など、幅広い業務が求められる職種においては、この資質が重要です。
例えば、苦手な教科や不得意な役割においても、時間をかけて克服しようと努力した経験は、自分の限界を超えて成長しようとする姿勢の証です。
企業は、このような「苦手分野への挑戦」を通じて得た忍耐力や成長力に注目し、困難な場面でも継続して努力できる人材を評価します。
未知の領域への挑戦
「未知の領域への挑戦」とは、これまで経験のない分野や未開拓の業務に対して積極的に挑むことを指します。
変化が激しいビジネスの現場では、状況に応じて柔軟に新しいことに取り組む姿勢が求められるため、このような姿勢が特に重視されます。
例えば、新たな分野の勉強を始めたり、これまでにないプロジェクトに参加した経験は、順応性や意欲をアピールする材料となります。
このような挑戦ができる人は、変わりゆく業務環境においても臨機応変に対応し、企業の成長を支える存在として期待されます。
高い目標に向けて前向きに挑む
「高い目標に向けて前向きに挑む」ことは、達成が困難な課題や大きなプレッシャーの中でも、くじけずに挑戦し続ける力を示します。
企業は、会社の発展や新しい目標を達成するために、このような挑戦心のある人材を求めています。
たとえば、タイトなスケジュールや難しい目標を抱える中でやり遂げた経験は、強い意志と課題解決力を証明するものです。
この姿勢を持つ人材は、企業から「どんな環境でも前向きに取り組める力を持っている」として高く評価されるでしょう。
【27卒必見】「挑戦したこと」のESを今すぐ作成しよう!
今「挑戦したこと」の回答を作らなきゃいけないのに、作成が上手くいかない。
そんなとき、10分で内定に近づくESが作れればと思いませんか?
今回は、質問に答えるだけで回答が10分で作成できるES作成ツールをご紹介いたします。
1000名以上の就活生が活用したES作成ツールを今だけプレゼントいたします。
様々な業界、職種のESに対応してますので、少しでも楽にESを作成したいと思っている方は、こちらのボタンから利用してみてください。
【挑戦したことをESに書く!】企業が求める「挑戦」とは?
先ほど紹介した「挑戦したことの種類」では、人生で一番の挑戦や苦手分野への挑戦、未知の領域への挑戦など、さまざまな形の挑戦を紹介しました。
ここで重要なのは、企業がどのような意図で「挑戦したこと」を質問しているかを理解することです。
企業は、あなたがどんな挑戦を選んだかだけでなく、その過程でどんな考えを持ち、どんな姿勢で行動したかを見ています。
つまり、「挑戦したことの種類」はあなたの個性を示す入り口であり、そこから見える価値観や成長力こそが評価の本質です。
ここからは、企業が“挑戦”というテーマに込める本当の意図を理解し、より深く伝わる書き方のポイントを解説していきます。

現状に対する問題意識と主体性
企業が「挑戦」のエピソードから見ている重要なポイントの一つが、「現状に対する問題意識と主体性」です。
現状に甘んじることなく、「もっと良くするためにはどうすべきか」「この課題を解決したい」といった問題意識を持ち、それを他人任せにせず、自ら具体的な行動を起こせるかどうかが問われます。
指示されたことをこなすだけでなく、自ら課題を発見し、その解決に向けて当事者意識を持って取り組んだ経験は、変化の激しい現代のビジネスシーンで不可欠な資質です。
あなたがどのような点に問題意識を感じ、それを解決するためにどんな一歩を踏み出したのか、その主体的な姿勢を具体的に伝えましょう。
計画性と実行力、そして創意工夫
目標を掲げて挑戦する際、その実現可能性を高めるのが「計画性」です。
企業は、あなたが目標達成に向けて、どのようなステップや戦略を考え、具体的な計画に落とし込めるかを見ています。
しかし、計画だけでは不十分です。
その計画を最後までやり遂げる「実行力」があってこそ、成果に繋がります。
仕事においても、目標設定から計画、実行というプロセスは基本であり、この力は高く評価されます。
さらに、計画通りに進まない困難に直面した際、諦めずに状況を打開しようとする「創意工夫」も重要です。
既存のやり方にとらわれず、新しい視点やアイデアで課題を乗り越えた経験は、あなたの問題解決能力を示す好材料となるでしょう。
結果から学ぶ内省力と成長力
挑戦した結果が成功であれ失敗であれ、企業が最も重視するのは「その経験から何を学び、次にどう活かそうとしているか」という「内省力と成長力」です。
挑戦を単なる経験で終わらせず、なぜそのような結果になったのか、成功要因や失敗要因を客観的に分析し、そこから具体的な教訓や改善点を見つけ出す姿勢が求められます。
そして、その学びを今後の自身の行動指針や、入社後の業務にどのように活かしていきたいと考えているのかまでを示すことで、あなたが継続的に成長できる人材であることをアピールできます。
この「経験から学び、成長する力」こそ、企業が将来を託せる人材かを見極める上で非常に大切なポイントです。
【挑戦したことをESに書く!】エピソードの見つけ方
ESで「挑戦したこと」を書くときに多くの就活生が悩むのが、「どの経験を選べば良いのか」という点です。
企業はあなたがどのような環境で、どんな目的を持って行動したかを重視しています。
そのため、まずは自分の過去の経験を幅広く整理し、挑戦の意識を持って取り組んだ瞬間を見つけ出すことが重要です。
さらに、その経験を「挑戦のタイプ」や「企業の求める人物像」と結びつけることで、より説得力のあるエピソードに仕上げることができます。
以下では、エピソードを見つけるための具体的なステップを3つに分けて解説します。
大学生活の経験をジャンル別に整理する
まずは、大学生活の中で「自分が少しでも頑張った」「頭を使った」「工夫した」と感じる経験を、とにかく全て書き出してみましょう。
それは、部活動、アルバイト、ゼミ、ボランティア、インターン、趣味などどんな経験でも構いません。
ポイントは、成果の大小ではなく自分が主体的に動いた経験をリストアップすることです。
書き出す段階では、取捨選択をせずに量を意識しましょう。
一覧化することで、自分の行動パターンや価値観の傾向が見えてきます。
そこから「挑戦した背景」「課題にどう向き合ったか」を整理すると、ESで伝えるエピソードの核が明確になります。
この作業は、自分の経験を“ただの出来事”から“意味のある挑戦”に変える第一歩です。
「3つの挑戦タイプ」に当てはめてみる(高い目標/苦手克服/未知の領域)
挑戦したことを整理する際は、「高い目標に向かった挑戦」「苦手分野の克服」「未知の領域への挑戦」という3つのタイプに分類してみましょう。
このフレームを使うことで、エピソードの方向性が明確になり、文章に一貫性を持たせやすくなります。
1つの経験が複数のタイプに当てはまることもありますが、どの切り口で語れば最も自分らしさが出るかを意識して選びましょう。
たとえば、アルバイトで売上改善に挑んだ場合、「高い目標」にも「苦手克服」にも該当します。
どの視点から語るかを決めることで、挑戦の意図が明確になり、読み手の印象に残るESになります。
この作業によって、単なる「出来事」が目的と意志のある「挑戦」へと変化し、あなたの強みをより具体的に伝えることができます。
企業の求める人物像に結び付ける
エピソードが決まったら、次はそれを志望企業の求める人物像と結び付けて整理しましょう。
同じ経験でも、A社では「リーダーシップ」、B社では「粘り強さ」といった具合に、評価される観点は異なります。
たとえば、課題解決を重視する企業には「課題を発見し、解決策を考えた力」を、挑戦を推奨する企業には「自ら行動を起こした姿勢」を強調するのが効果的です。
また、企業理念や業界特性を理解して書くことで、あなたの経験がより“再現性のある強み”として伝わります。
エピソードを企業に合わせて微調整することで、あなたの挑戦経験は単なる自己紹介ではなく、採用担当者が「一緒に働きたい」と思える説得力のある物語へと変わるのです。
【挑戦したことをESに書く!】人事を引き付ける構成
エントリーシートで「挑戦したこと」を書く際に、最も重要なのは読み手である人事に伝わる構成で書くことです。
どんなに良い経験をしていても、話の流れが整理されていないと魅力が半減してしまいます。
そこで活用すべきが、論理的かつ簡潔に伝わるPREP法(Point・Reason・Example・Point)です。
この構成を使うことで、挑戦内容の意図や成長過程を明確に伝えることができ、読み手に一貫した印象を与えます。
以下では、PREP法の基本を詳しく解説しながら、実際に「挑戦したこと」を効果的に構成するための4ステップを紹介します。
PREP法とは、「Point(結論)→ Reason(理由)→ Example(具体例)→ Point(再主張)」の順で伝えるフレームワークです。
この手法を用いることで、文章に論理性と説得力が生まれ、限られた文字数の中でも要点を明確に伝えることができます。
特にESでは採用担当者が数多くの応募書類を短時間で読むため、冒頭で結論を伝えることが印象付けの第一歩になります。
さらに、理由や具体例を加えることで内容に厚みが出て、最後にもう一度結論を示すことで記憶に残る構成に仕上がります。
このPREP法は、ESだけでなく面接やプレゼンでも応用可能な基本スキルです。
次の4ステップでは、PREP法を使って「挑戦したこと」を構築する具体的な流れを紹介します。
① 結論:私が挑戦したことは〇〇です
ESでは最初に結論を明確に伝えることが不可欠です。
冒頭で「私が挑戦したことは〇〇です」と書くことで、採用担当者にテーマを一瞬で理解させることができます。
この部分では、経験の概要を簡潔に述べるだけでなく、挑戦の本質や目的が一文で伝わるように意識することが大切です。
たとえば「アルバイトで売上改善に挑戦しました」ではなく、「顧客満足度を高めるために、売上改善の仕組みづくりに挑戦しました」と書くと意図が明確になります。
「何を目的に挑戦したのか」が伝わるだけで、文章の説得力と深みが格段に上がります。
② 経緯・動機:なぜ、それを「挑戦」だと感じたのか
次に、なぜその経験を「挑戦」と感じたのかを説明します。
ここでは、あなたの価値観や思考の背景を示すことが大切です。
たとえば、「苦手なことにあえて取り組んだ」「周囲に反対されても挑戦した」など、自分にとってハードルの高い状況を具体的に描きましょう。
この部分は、あなたの人間性や行動原理が最も表れるパートでもあります。
「なぜその挑戦を選んだのか」という理由を丁寧に説明することで、読み手はあなたの動機に共感しやすくなります。
挑戦の意義や目的が伝わると、ES全体の印象が格段に良くなります。
③ 困難と工夫:課題に対して、どう考え行動したか
この段階では、挑戦の中で直面した「壁」と、その乗り越え方を具体的に説明します。
企業が注目しているのは、結果よりも困難に直面したときの思考力・行動力・粘り強さです。
「何が問題だったのか」「原因をどう分析したのか」「どのような工夫をしたのか」を論理的に整理して書きましょう。
特に工夫の部分では、「自分なりに考えて行動した」プロセスを具体的に描くことで、主体性が伝わります。
単なる努力ではなく、「どのように課題を解決したのか」を説明できると、採用担当者に強い印象を残すことができます。
④ 結果と学び:経験から何を得て、どう活かすか
最後に、挑戦の結果とそこから得た学びを述べます。
結果が成功でも失敗でも問題はなく、重要なのは経験を通じてどんな気づきを得て、今後にどう活かすのかという点です。
「挑戦を通じて努力の継続が成果に繋がることを学んだ」「チームで協力する重要性を実感した」など、学びを具体的に表現しましょう。
また、学んだことを入社後にどう活かしたいかまで書くと、ビジネスへの再現性が伝わり、評価が高まります。
締めくくりとして「この経験を活かし、今後も困難に挑み続けたい」とまとめると、ポジティブで印象的な結論になります。
【挑戦したことをESに書く!】業界別の評価ポイント
挑戦したことについての設問は、業界ごとに評価されるポイントが異なります。
ここでは、大手企業で過去に聞かれたことのある設問を用いて、業界別の評価ポイントについてご紹介します。
業界によって設問のニュアンスも異なるので、そちらも要チェックです。志望業界や企業の設問と評価ポイントを確認し、何が求められているのかを知ってから選考対策を進めましょう。
また、以下のような共通の評価ポイントもあるので、ポイントを抑えて挑戦したことの文章を作成するようにしましょう。
共通の評価ポイント
| 評価観点 | 説明 |
|---|---|
| 課題設定力 | 「何に挑戦したか」が具体的かつ他人に伝わるように整理されているか。 |
| 主体性 | 他人に言われたのではなく、自分の意思で課題に取り組んでいるか。 |
| 工夫・改善力 | ただ行動するだけでなく、課題に対して自ら工夫・改善を試みているか。 |
| 再現性(伸び代) | 社会人になっても同じように課題に向き合い、成長できそうか。 |
コンサル
例:アクセンチュア、デロイト、野村総合研究所
- 論理性(課題の把握と行動の整合性)
- 実行力・改善力(PDCA回せているか)
- チームワークと責任感
コンサル業界では、「困難をどう乗り越えたか」というプロセスが最も重視されます。
単に結果を出した経験ではなく、どのように課題を発見し、仮説を立て、実行し、改善していったかという一連の思考プロセスが評価の核心です。
さらに、変化に柔軟に対応できるか、自ら情報を収集し状況を打開する主体性も問われます。
チームでの立ち位置や周囲との協働性も重要視され、個人プレーよりも「組織を動かした」経験が好印象です。
したがって、「何をやったか」よりも「なぜそれに挑戦したのか」「どう考えて動いたのか」のロジカルな説明ができることが求められます。
総合商社
例:三菱商事、伊藤忠商事、住友商事
- 大きなスケールの経験(部活・留学・組織運営など)
- 困難の本質理解とタフネスリーダーシップ or 全体最適視点
総合商社では、大規模かつ多様なステークホルダーを巻き込むビジネスを展開するため、挑戦経験には「スケール感」や「影響力」が求められます。
単なる成果報告ではなく、自らがどのように組織や周囲を巻き込み、困難な局面を打開していったのかが重視されます。
学生団体、留学、長期インターン、体育会活動など、長期かつ複雑な目標に挑戦した経験が評価されやすく、「挫折→学び→工夫→再挑戦」といった成長の軌跡が見えるエピソードが好まれます。
また、目標達成のために行動を選択し、リーダーシップや統率力を発揮した経験は特に高評価につながります。
広告・マスコミ
例:電通、博報堂、NHK
- 独自性と企画性(自分ならではの視点があるか)
- 表現力と熱意物事への没頭経験(本気度)
広告・マスコミ業界では、「誰かの心を動かすこと」に挑んだ経験が評価されます。
重視されるのは、成果や数字よりも「想い」や「独自の視点」で、自ら何を感じ、どう行動し、どんな工夫をしたかというストーリー性です。
人と違う視点から課題を見つけ、それに対して表現・発信した経験や、情熱を持って取り組んだ活動が評価されやすくなります。
例えば、イベント企画や映像制作、SNS運用など、何かを「つくり・伝え・広めた」経験が説得力を持ちます。
感性や表現力に加え、「共感を得る力」や「継続的な熱量」も重視される傾向があります。
IT・インフラ
例:NTTデータ、楽天、富士通
- 論理性(課題の把握と行動の整合性)
- 実行力・改善力(PDCA回せているか)
- チームワークと責任感
IT・インフラ業界では、「問題解決に向けた論理的アプローチ」と「地道な改善の積み重ね」が重視されます。
挑戦した経験が、計画性・論理性をもって実行され、途中で発生した課題にも柔軟に対応しているかが見られます。
プログラミング、データ分析、インフラ整備といった分野に限らず、サークルやバイトでの業務改善、イベントの効率化など、地道に工夫を続けた経験が評価対象となります。
重要なのは、技術や作業の単純な記述ではなく、「なぜ改善が必要だったか」「どうアプローチしたか」を明確に説明し、PDCAが回っているかを示すことです。
メーカー
例:トヨタ、味の素、パナソニック
- 継続力・粘り強さ
- 課題解決力と工夫
- 組織の中での役割理解
メーカー業界では、「粘り強さ」と「現場での工夫・試行錯誤」が評価されます。
ものづくりの現場では一度の挑戦で成果が出ることは少なく、何度もトライ&エラーを繰り返す力が求められるため、短期間の成功体験よりも、継続的な努力が見える経験が好まれます。
たとえば、研究、部活動、地域活動などで時間をかけて課題に向き合い、小さな工夫を積み重ねて改善につなげた経験は高評価になります。
また、現場での人間関係や、周囲との連携、組織のなかでの自分の役割への理解があると、実際の職場に置き換えやすく、評価につながりやすいです。
金融
例:三菱UFJ銀行、東京海上日動、野村證券
- 数値目標に向けた粘り強さ
- 顧客志向・誠実さ
- プレッシャー耐性と責任感
金融業界では、「成果への執着心」と「信頼される誠実な行動」が求められます。
営業ノルマや厳格なルールのある業界だからこそ、挑戦経験においては「目標をどのように設定し、どのように達成したか」を明確に語れることが重要です。
また、数字へのこだわりや、プレッシャーの中で粘り強く努力した経験は好まれます。
たとえば、営業目標の達成、部活でのレギュラー争い、受験や資格取得など、目に見えるゴールに対し継続的に努力したエピソードが評価されます。
あわせて、組織や顧客に信頼されるための行動・姿勢を示せるとより説得力が増します。
【挑戦したことをESで書く!】参考例文集
ここでは、実際に大手企業のESで出題された「挑戦したこと」に関する質問をもとに、参考となる例文を紹介します。
各質問には、企業ごとに重視しているポイントが異なり、求められる「挑戦」の定義や視点もさまざまです。
例文を通して、どのように課題を設定し、どんな工夫や姿勢で取り組んだのかを具体的にイメージしてみましょう。
また、自分の経験を当てはめる際は、ここで紹介する構成や表現の流れを参考に、あなた自身の挑戦ストーリーに置き換えることが効果的です。
三菱商事①
大学の学園祭実行委員として、前年比2倍となる来場者数1万人という目標を掲げ挑戦しました。
SNS広報を中心に活動していましたが、学生以外の層への認知不足で集客は伸び悩んでいました。
地域住民の参加が鍵と考え、商店街との協働イベントを企画しました。
反対意見もある中で、顧客層データや地域イベントの参加者推移を元に説得を続け、協賛を獲得しました。
スタンプラリー企画を実施し、当日は1万2千人が来場。地域全体を巻き込む成功につながりました。
困難な状況でも分析と周囲を巻き込む行動が成果を生むと実感しました。
三菱商事②
ゼミの企業研究プロジェクトでチームを率い、発表会で最優秀賞を獲得した経験です。
当初は意見が発散し、議論の方向性が定まりませんでした。
私はまず個別面談でメンバーの考えや得意分野をヒアリングしました。
目的と手段を整理し、全員の認識を統一しました。
Trelloやクラウド共有を導入し作業効率も大幅に改善。
進捗共有会では相互評価を行い責任感を引き出しました。
結果、論理的で説得力ある発表として最優秀賞を受賞しました。
三井物産
1年間の英国留学中、多国籍チームのリーダーとしてプロジェクトを成功させた経験です。
議論の進め方や価値観の違いにより衝突が頻発し、プロジェクトは停滞しました。
私はまず個々の文化的背景を理解するため1対1の対話を重ねました。
文化紹介会を企画し相互理解を深めた上で、強みに応じた役割分担を提案しました。
最終発表では多様な視点を融合した提案として最高評価を獲得しました。
異文化環境でのリーダーシップと協働の重要性を学びました。
伊藤忠商事
大学バスケットボールサークルのキャプテンとして、大会初優勝に導いた経験です。
当初は連携不足や意欲低下が課題でした。
私は「勝つ喜びを共有したい」という情熱から練習体系の改革を行いました。
試合動画の分析から戦術と練習を紐付け、早朝トレーニングも率先して実施しました。
次第にメンバーも主体的に取り組み、創部以来初の優勝を達成しました。
情熱と率先垂範がチームを動かすと確信した経験です。
アクセンチュア
飲食店のアルバイト時代、コロナ禍で売上が半減した店舗の再建に挑戦しました。
過去データ分析から、常連客の来店頻度減が根本原因と特定しました。
LINE公式アカウントを活用したクーポン施策を提案しましたが、当初は抵抗もありました。
売上回復シミュレーションを提示し粘り強く説得し導入を実現。
運用後は効果測定と改善を継続し、リピーター率は30%→55%に上昇しました。
データ分析と周囲を巻き込む力を学んだ経験です。
野村総合研究所(NRI)
市場分析プロジェクトで、100人規模のアンケート調査を企画・実行した経験です。
仮説を裏付ける公開データがなく議論は停滞していました。
私は一次データ収集が必要と判断し、調査を提案しました。
設問設計からフォーム作成、SNS募集、統計分析まで主体的に行いました。
得られたデータで仮説を深く再検証し、実務的価値が高いと評価されました。
課題発見と行動の重要性を学びました。
トヨタ自動車
半年でTOEICを300点伸ばし800点を達成した経験です。
英語が苦手でしたが、キャリアのため必要と痛感し挑戦を決意しました。
自己分析でリスニングが弱点と特定し、毎日シャドーイングを行いました。
聞き取れない箇所を分析し改善を継続しました。
友人とオンライン勉強会を開き互いに励まし合いました。
最終的に820点を取得し、分析と継続の重要性を学びました。
サントリーホールディングス
コロナ禍で前例のない「完全オンライン文化祭」を成功させた経験です。
中止ムードの中、「学生生活の思い出を守りたい」という思いでオンライン開催を提案しました。
配信機材や著作権、企画設計など課題が山積みでした。
専門チームを組織し進捗管理を徹底しました。
当日の回線トラブルにも代替プランで対応し全企画を完遂しました。
満足度90%以上を達成し、挑戦を恐れない実行力を学びました。
味の素
陸上部で大怪我を乗り越え自己ベストを更新した経験です。
肉離れにより長期離脱し精神的にも大きく落ち込みました。
それでも基礎トレーニングを地道に継続しました。
復帰後はフォーム分析アプリを活用して課題を特定し修正しました。
仲間の支えもあり、復帰戦で自己ベストを0.4秒更新しました。
逆境でも諦めず努力する粘り強さを得ました。
東京海上日動火災保険
ボランティア団体で清掃イベントの再建を主導した経験です。
マンネリ化し参加者が減少していました。
私は地域との連携不足が課題と考え、関係強化を提案しました。
中学校や自治会に協力を依頼し地域一体の体制を築きました。
意見衝突もありましたが、共通目的を粘り強く伝え続けました。
当日は前年の2倍以上の参加者が集まり成功を収めました。
リクルート
飲食店のアルバイトで、学生スタッフの離職率改善に取り組んだ経験です。
新人が孤立しやすい点が定着率低下の根本原因と特定しました。
教育体制が属人化している実態をヒアリングで把握しました。
チェックリスト型OJT制度と新人マニュアルを提案しました。
メンター制度も導入し心理的支援体制を構築しました。
結果、3ヶ月以内の離職率が半減しチームワークも向上しました。
【挑戦したことをESに書く!】文字数別例文
エントリーシートでは、企業によって求められる文字数が異なります。
400字や600字のように詳しく書ける場合もあれば、200字以内で簡潔にまとめる場合もあります。
どの文字数であっても、重要なのは「結論・経緯・工夫・学び」の流れを崩さずに伝えることです。
以下では同じ内容を文字数ごとに調整した例文を紹介します。
それぞれの字数でどのように要点を取捨選択すればよいかを意識しながら、自分の挑戦エピソードを最適な形で表現してみましょう。
400字
私は大学1年から続けているカフェのアルバイトで、ピーク時の提供遅れを改善するために体制改革に挑戦しました。
当時は案内担当が厨房の進捗を把握せずに入店案内を続けることで、20分以上の遅延やミスが発生していました。
私は原因を「現場間の情報共有不足」と分析し、ホールと厨房の連携方法を見直すことを提案。
具体的には、案内時に厨房の状況を確認し、混雑時は案内間隔を調整するルールを導入しました。
最初は「回転率が下がる」と反対もありましたが、自ら率先して実行し、結果として提供時間を平均4分短縮。
この経験を通して、課題を可視化し、現場を巻き込みながら改善を進める力を身につけました。
600字
私は大学1年から続けているカフェのアルバイトで、週末の提供遅れを改善するために業務体制を改革した経験があります。
当時は、ホールが厨房の状況を把握せずに案内を進めてしまうことで、ピーク時には20分以上の提供遅延やミスが多発していました。
私はその原因を「情報共有不足」にあると分析し、ホールと厨房の連携を強化する仕組みづくりに挑戦しました。
具体的には、案内前に厨房の提供状況を確認するルールを設け、混雑度に応じて案内間隔を調整する運用を導入。
また、スタッフ間で進捗を共有できる簡易ボードを設置し、状況を可視化することで連携ミスを防ぎました。
当初は「回転率が下がる」との懸念もありましたが、実際に運用してみると提供スピードが安定し、ミスも減少。
結果、ピーク時の提供時間は平均4分短縮され、顧客満足度アンケートでも高評価を得ました。
この経験から、課題を数値で捉え、現場全体を巻き込みながら改善策を形にする実行力の重要性を学びました。
今後も現状に満足せず、自ら課題を発見し、行動で変化を生み出せる人材を目指していきます。
200字
私はカフェのアルバイトで、ピーク時の提供遅れを改善する体制づくりに挑戦しました。
ホールが厨房の進捗を把握できず案内を進めていたことが原因だったため、状況に応じて案内間隔を調整する運用を提案しました。
反対意見もありましたが、自ら実践して効果を可視化した結果、提供時間を平均4分短縮。
この経験を通じて、課題を分析し、周囲を巻き込みながら改善を実現する行動力を身につけました。
【挑戦したことをESに書く!】NG例文集
「挑戦したこと」をテーマにしたESでは、書き方を誤ると意図せず評価を下げてしまうケースがあります。
特に注意すべきは、内容が抽象的すぎる・協調性が感じられない・成果を誇張しすぎるという3つのパターンです。
これらの共通点は「読み手があなたの姿を具体的にイメージできない」という点にあります。
以下ではそれぞれのNG例文を紹介し、どこが問題で、どのように改善すれば高評価につながるのかを詳しく解説します。
文章の「伝わり方」を意識することで、同じ経験でも説得力を大きく高めることが可能です。
①具体性がなく抽象的な例文
私は、大学生活の中で多くの挑戦を経験しました。
困難な状況でも諦めずに取り組む姿勢を大切にし、常に前向きに努力を続けてきました。
特に、グループ活動やアルバイトでは、チームの一員として目標達成に貢献できるよう意識して行動しました。
失敗もありましたが、そこから多くの学びを得て、どんな環境でも柔軟に対応できる力を身につけたと思います。
私は、挑戦を通して人とのつながりの大切さを学び、困難を乗り越える粘り強さを得ることができました。
今後もこの経験を活かし、社会人として成長していきたいと考えています。
②協調性がなく自己中心的な例文
私は、ゼミ活動で自分の意見を貫き通した経験があります。
研究テーマを決める際に、他のメンバーは賛成しませんでしたが、私の案が最も効果的であると考え、強く主張しました。
最終的には私の提案が採用され、結果的に良い成果を得ることができました。
この経験から、どんな状況でも自分の意見を曲げず、信念を持って行動することの大切さを学びました。
グループワークや議論では周囲の意見に流されず、自分の考えを貫く姿勢を常に意識しています。
私は、リーダーとして自分の意見を正しいと信じて最後までやり抜くことが挑戦の本質だと思っています。
就活コンサルタント木下より

この例文の問題点は、「協調性の欠如」が強く伝わってしまう点です。
挑戦した内容自体は悪くありませんが、他者の意見を尊重せずに自分の主張を通しただけでは、組織で働く資質が疑われます。
改善するには、「他者の意見も踏まえたうえで、自分の考えを論理的に説明し、納得してもらった」といった協働の姿勢を入れることが大切です。
また、「最終的にメンバーの協力で成果が出た」と結ぶことで、チーム意識のある人物として印象を良くできます。
「主張の強さ」ではなく「柔軟なリーダーシップ」を意識した表現に変えましょう。
③成果の自慢話になっている例文
私は、アルバイト先で売上を前年比150%まで伸ばすことに成功しました。
自分の提案したキャンペーンが採用され、実施初月から売上が大幅に上がりました。
社員からも高く評価され、表彰も受けました。
その後も、自分のアイデアを次々に実践し、店舗の中心的な存在として活躍しました。
私はどんな環境でも結果を出す自信があります。
挑戦を通じて、行動力と実行力を証明することができたと思います。
どの職場においても同様に成果を出せると確信しています。
就活コンサルタント木下より

この例文の問題は、「成果」に偏りすぎて過程や周囲との関わりが見えない点です。
数字や表彰を強調しすぎると、自慢話のような印象を与えやすくなります。
改善のポイントは、「なぜその成果を出せたのか」「どう工夫したのか」を中心に据えることです。
また、「チームと連携しながら改善を進めた」「顧客の声を反映して提案した」など、周囲との協働を描くことで謙虚さと実行力が両立します。
成果は最後に“結果としてついてきた”とする構成に変えると、より好印象な挑戦エピソードになります。
【挑戦したことをESに書く!】よく聞かれる質問
「人生で一番挑戦したこと」は、エントリーシートや面接で頻出の質問です。
この質問を通じて企業は、あなたがどんな価値観で行動し、困難にどう向き合ってきたかを知ろうとしています。
ただ挑戦内容を伝えるだけでなく、動機や背景、乗り越えるために工夫した点、そこから得た学びまでを一貫して語ることが求められます。
ここでは、このテーマに関連して実際によく聞かれる質問と、その意図や答え方のポイントについて紹介します。
これまで最も挑戦したことは何ですか?
この問いではあなた自身が直面した課題に対してどのように取り組み乗り越えたのかを聞きたい質問になっています。
大学のグループプロジェクトで、チーム内の意見がまとまらず、進行が遅れていたことがありました。私は積極的に意見を聞き、全員が意見を出しやすい環境を作るように心がけました。具体的には、定期的にミーティングを開き、進行状況を共有し、メンバーそれぞれが責任を持つような役割分担を行いました。その結果、プロジェクトは予定通りに進み、チーム全体が協力して成果を出すことができました。この経験から、コミュニケーションとリーダーシップの重要性を学びました。
困難な直面に直面した時に都のように対処し乗り越えましたか?
この問いでは問題解決能力やトラブルでの冷静な対処スキルを知りたい問いとなっています。
アルバイトで予期しないトラブルが発生し、急遽業務の改善を求められる場面がありました。スタッフが足りない中で、通常業務をこなすだけでなく、新たな対応方法を考えなければならなかったため、冷静に業務を優先順位ごとに整理し、最も重要な問題から解決策を講じました。また、上司と相談しながら、チーム全員で協力して進めるよう呼びかけました。その結果、トラブルは早期に解決し、業務が円滑に進むようになりました。この経験を通じて、問題解決能力とチームワークの重要性を学びました。
自分が挑戦したことで、予想以上の成果を出せた経験はありますか?
この問いでは、あなたの努力や工夫が知りたい問いとなっています。
大学のサークルで、年度末のイベントを担当した際、当初は予算が限られており、集客に不安がありました。そこで、SNSを活用してイベントの魅力を伝えたり、スポンサーを募ったりすることを提案しました。SNSでの積極的な告知や、イベントの内容をより魅力的にアピールした結果、予想以上の来場者数を達成しました。この経験を通じて、限られた資源でも工夫次第で大きな成果を上げられることを実感しました
【挑戦したことをESに書く!】注意点
「挑戦したこと」をテーマにしたESでは、内容そのものだけでなく、伝え方や姿勢にも注意が必要です。
どんなに素晴らしい経験でも、誇張された表現や責任転嫁の姿勢が見えると、信頼性や人間性に疑問を持たれてしまう可能性があります。
また、専門用語が多すぎると、面接官が理解しづらく印象が薄れてしまうことも。
企業は「挑戦」そのものよりも、その経験から何を学び、どう行動したかを重視しています。
本章では、信頼を損なわずに魅力を伝えるための3つの注意点を解説します。
嘘や誇張をしない
ESで最も避けるべきなのが、実際よりも過剰に盛ったエピソードを書くことです。
「インパクトを出したい」と思って誇張してしまうと、面接時に具体的な質問をされた際に矛盾が生じ、信頼を失う結果につながります。
企業は、派手な成果よりも、あなたがどのように課題を分析し、どう行動したのかを見ています。
「小さな成功でも自分なりに工夫した」「困難を乗り越えた過程に価値がある」と誠実に語る方が評価されやすいです。
特に、数字や役職などは裏付けを持たせ、面接で具体的に説明できる範囲にとどめましょう。
等身大の経験こそが、あなたの成長と信頼を最も伝える武器になります。
他責や環境のせいにはしない
挑戦経験を語る際に、「周囲が協力してくれなかった」「環境が悪かった」といった他責的な表現は避けましょう。
企業は、困難に直面したときにどんな姿勢で臨んだかを見ています。
他者や環境のせいにしてしまうと、主体性や前向きさに欠ける印象を与えてしまいます。
たとえトラブルがあったとしても、「その中で自分ができることを模索した」「課題を解決するために工夫した」と書くことで、成長意欲を伝えられます。
挑戦とは、逆境をどう捉え、どう乗り越えたかを示す場面です。
困難を自分ごととして考える姿勢が、採用担当者の信頼を得る最大のポイントです。
専門用語は避ける
研究・サークル・インターンなど、専門的な活動を題材にする際は、専門用語の使いすぎに注意しましょう。
特に理系学生やIT分野では、技術用語を並べることで「難しいことをしている」と伝えたくなるものですが、相手が理解できなければ魅力は半減します。
採用担当者は必ずしもその分野の専門家ではありません。
「誰が読んでも内容が伝わるか」を意識し、専門用語は簡単な説明を添えることが大切です。
例:「Pythonで自動化」→「業務効率化のため、プログラムを使って作業を自動化」と言い換えるだけで伝わりやすくなります。
ESは知識を示す場ではなく、あなたの思考力と伝達力を評価する場だと意識しましょう。
【挑戦したことをESに書く!】まとめ
この記事では、「人生で一番挑戦したこと」をテーマに、エントリーシート(ES)で高評価を得るための書き方や伝え方を詳しく解説してきました。
挑戦内容の種類や企業がこの質問を重視する理由、エピソードの選び方やPREP法を活用した構成方法、さらに実際によく聞かれる質問への答え方や高評価の例文・NG例文まで幅広く紹介しました。
重要なのは、自分の挑戦を通じて「どのように考え」「どう行動し」「何を学んだのか」を一貫して伝えることです。
企業はその経験を通じて、あなたの価値観やポテンシャル、自社とのマッチ度を見極めています。
この記事を参考に、伝えたい強みが明確に伝わるガクチカをぜひ完成させてください。


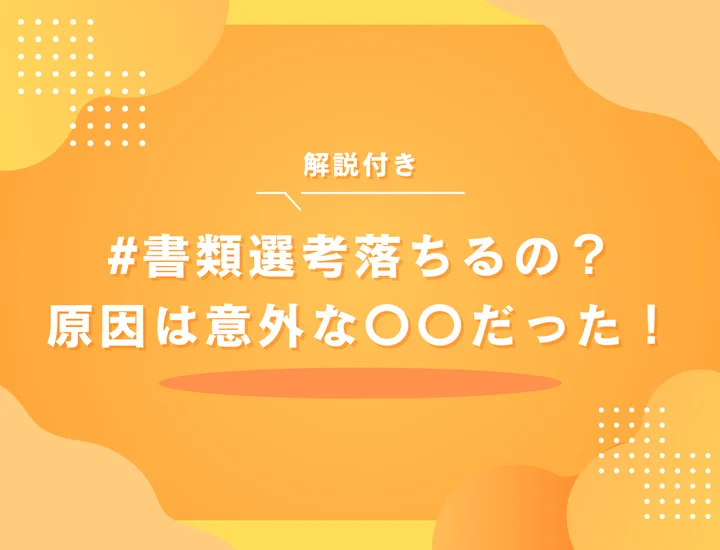







就活コンサルタント木下より
この例文の問題は、「何に挑戦したのか」「どんな困難があったのか」が曖昧な点です。
挑戦のテーマが抽象的すぎるため、採用担当者は状況をイメージできません。
改善するには、「目的・行動・結果」を明確にすることが重要です。
たとえば「アルバイトで来店数減少を改善した」「ゼミ発表で代表として運営を担った」など、具体的な行動を中心に書くことで説得力が増します。
また、「努力した」「成長した」といった抽象的な表現は、数字や成果を交えて具体化すると評価が上がります。
読み手に「あなたがどんな行動を取ったのか」を一文で伝える意識を持ちましょう。