
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
就職活動が始まったものの、まだ志望動機を書いたことがなく「どう書いたらいいのか分からない」と不安に感じていませんか?
まだざっくりと「建設業界を受けてみようかな」としか考えていなくても大丈夫です!
この記事ではそんなあなたのために、志望動機の書き方や書く前の準備、書く時のポイントなどを具体的に紹介していきます。
建設業界と志望動機の書き方の両方への理解を一緒に深めていきましょう!
目次[目次を全て表示する]
【建設業界の志望動機】建設業界とは
まずはそもそもあなたが目指している「建設業界とは」どのようなことをしているのかを説明していきます。
建設業界とは建築や土木工事など、様々な建設に携わる業界のことを指します。
駅前の大きな商業施設を建設したり、道路やダムの建築など、社会経済に与える影響がとても大きな業界と言えます。
また商業施設や道路の建設・建築をすることで、その地に雇用を生み出し地域経済の発展にも貢献できる業界でもあります。
ここではさらにそれを細分化した「建築」と「土木」についての深掘りと、「建設業界と建築業界の違い」を詳しく説明していきます。
建築
建設業界における「建築」という言葉は、あなたが住んでいる一軒家やマンションの他、大型商業施設やオフィスビルなどの建物を設計・建設する分野のことを指しています。
つまり、あなたが普段の生活で触れる機会が多い建物の構造や機能性、耐久性を考え、それを形にする分野ということになります。
そのため、専門的知識を持った建築家や設計士が家主やオーナー、クライアントの要望を聞き、それを形にすることがメインのお仕事です。
美しい造形だけでなく、その機能性や耐久性、再現性の高さなどが評価されやすい分野と言えます。
多くの就活生が建設業界という言葉でイメージするのはこの分野ではないかと思います。
土木
一方では「土木」とは道路や橋、ダムやトンネルなどの社会インフラに大きな影響を与えるものを建築する分野のことを指します。
こちらの土木は景観的な美しさなどのデザイン性ではなく、安全を第一に考えた効率的な設計が求められる分野です。
そのため、地盤工学や構造工学の知識や経験が必要不可欠であると言えます。
また、その土地の地形や環境に配慮する必要もあり、1つの建設物を完成させるのには多くの時間がかかることも特徴の1つと言えます。
建築と土木は手がける建築物に違いはあれど、多くの人々に影響を与えるという点では同じです。
どちらも責任感とやりがいのある仕事と言えるでしょう。
建設業界と建築業界の違い
建設業界と建築業界は、しばしば混同されがちですが、明確な違いがあります。
建設業界は建物や橋、道路などのインフラの建設を含む広範囲な分野をカバーしています。
この業界は土木工事や重工業的なプロジェクトも含め、多岐にわたる作業と技術を要求されます。
一方で、建築業界は具体的に建物の設計、建設、改修に特化しており、住宅、商業施設、公共建築物などの建築物に関連する業務が主な焦点です。
例えば、建設業界の会社がダムや高速道路の建設を手がける一方で、建築業界の会社はオフィスビルやマンションの設計と建設を専門としています。
これらの違いを理解して就活の準備しておくことは、将来仕事のミスマッチを防ぐためにも非常に重要です。
建築業界については以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
建設業界のビジネスモデル
建設業界のビジネスモデルは、クライアント(発注者)との契約を基にプロジェクトを遂行することで成り立っています。
クライアントが提示した要件に基づき、設計、施工、引き渡しまでを一貫して担い、その過程で得た利益が収益の主軸です。
一般的には、プロジェクトごとに予算やスケジュールが設定され、それに従い業務が進行します。
近年では、環境に配慮した建設やデジタル技術を活用した効率化が注目され、建設業界のビジネスモデルも変化しています。
【建設業界の志望動機】おもな魅力
建設業界で働く中で実感できるやりがいや魅力について解説します。
建設業界はインフラ構築をするという意味でも非常にダイナミックで、魅力的な要素が多い業界なので、興味のある方は自信を持って目指してください。
社会貢献ができる
建設業界は、社会に直接的な貢献を行うことができる点で大きな魅力を持っています。
この業界のプロジェクトには、道路、橋、病院、学校などの生活基盤となる重要な施設が含まれます。
これらの施設は日々の生活に不可欠であり、それを構築することで地域社会の発展に寄与し、人々の生活の質を向上させることができます。
このように、建設業界での仕事は、目に見える形で社会に影響を与えるため、多くの人々にとってやりがいを感じる分野です。
やりがいを感じやすい
建設業界で働く魅力の一つは、形として目に見える成果が残ることで、非常に大きなやりがいを感じることができます。
建設された橋、ビル、住宅などは、数十年、あるいはそれ以上にわたって使用され、多くの人々の生活や活動を支える基盤となります。
自分が関わったプロジェクトが街を形作ることや、地域社会の発展に貢献する橋や道路として機能し続けることは、大きな誇りとなります。
例えば、新しい公共交通システムの建設に携わることで、都市の交通問題を解決に導くなど、その影響は次世代にまで及びます。
業界全体で需要が高い
建設業界は、政府からの公共事業投資を含む大規模なプロジェクトに直接関与することが多く、需要が安定して高い業界といえます。
特にインフラ整備や都市開発、災害復興など、社会の基盤を支えるプロジェクトは長期的な需要が見込まれています。
また、近年ではSDGsや環境保全への関心が高まる中、環境に配慮した建設や再生可能エネルギー関連のプロジェクトが増加しており、新たな成長分野として注目されています。
スキルや資格次第で年収が上がる
建設業界では、専門的なスキルや資格が給与やキャリアアップに直結するという特徴があります。
たとえば、一級建築士や施工管理技士といった資格を取得すると、責任の大きいプロジェクトを任される機会が増え、それに応じて収入も大幅に向上する可能性があります。
また、多くの企業が社員のスキル向上を目的とした資格取得支援制度を整備しており、努力次第でキャリアアップが望める環境が整っています。
さらに、営業職では成果が給与に反映される歩合制を採用している企業も多く、高収入を得ることも可能です。
【建設業界の志望動機】具体的な職種と業種
建設業界のことが大まかに理解できたところで、次は「建設業界の職種」について説明していきます。
ここでは代表的な職種として「営業職」「事務職」「技術職」「技術開発職」「施工管理」「統計職」の6つの職種を順番に説明していきます。
あなたが何をしたいのか、どの仕事が向いているのかを確認しながら見てみて下さい。
主な業種
建設業界にはさまざまな業種があり、それぞれの役割が明確に分かれています。
ここでは、ゼネコンとサブコンの特徴や業務内容について詳しく説明します。
ゼネコン(総合建設業者)は、大規模な建築物やインフラの建設を統括する企業です。
建築プロジェクトの企画、設計、施工、管理までを一括して請け負うため、建設業界の中心的な存在となっています。
具体的には、商業施設、マンション、オフィスビル、橋梁、道路など、多岐にわたるプロジェクトを手掛けます。
また、ゼネコンは協力会社や下請け企業と連携しながら、全体の工程管理を行う役割も担っています。
施工管理や品質管理、安全管理など幅広い業務を統括するため、高度な専門知識と調整力が求められます。
サブコン(専門工事業者)は、ゼネコンが統括する建設プロジェクトの一部を担当する企業です。
電気設備、空調設備、配管工事、内装工事など、特定の分野に特化した工事を請け負います。
ゼネコンが全体のマネジメントを行うのに対し、サブコンはその指示のもとで専門技術を活かし、各種設備の設置や施工を行います。
また、サブコンは施工技術の向上に重点を置き、最新技術の導入や省エネ対策などを積極的に進めています。
プロジェクトごとに異なる条件に対応しながら、安全性や品質を確保する役割も果たしています。
主な職種
ここからは建設業界における主な職種について解説します。
職種のよって同じ建設業界でもかなり仕事内容や求められる素質などが変わるので、チェックしておきましょう。
建設業界の代表的な職種の1つ目は「営業職」です。
建設業界における営業職の仕事とは、オーナーやクライアントなどから依頼を受ける窓口であり、よき相談相手になることです。
それだけでなく、自社製品の提案を行い新規契約を獲得したり、関連部署とのやりとりを行うことでプロジェクトがスムーズに進むよう調整することも大切な業務の1つです。
社内外問わず多くの人と関わる職種であるため、コミュニケーションに長けた人が向いている職種と言えるでしょう。
建設業界の代表的な職種の2つ目は「事務職」です。
事務職と聞くと一見地味に思えるかもしれませんが、建設現場と事務所を繋ぐ大切な職種の1つです。
建設現場の資材などの発注や労務管理など、建築現場での作業に大きく関わるものの管理を担当しており、遠場への貢献度はとても大きいと言えます。
この事務職には経理や人事などの専門性の高い分野も含まれているため、企業を運営していく上で必要不可欠な職種と断言できます。
建設業界の代表的な職種の3つ目は「技術職」です。
文字通り技術が求められる職種で、建物や道路、ダムなどの建築物のデザインや設計、プロジェクトのスケジュール管理などを担当しています。
そのため、この職種は専門的な知識を持っている設計士や建築家、土木技術者などが担当することが多いと言えます。
技術職は建築物の土台である設計を担当するため、責任感があり基本に忠実な人が向いている職種と言えるでしょう。
建設業界の代表的な職種の4つ目は「技術開発職」です。
この技術開発職は今ある技術をさらに発展させることで、より安全な建物を効率的に建築する方法を日々考えています。
この技術開発職は専門的な知識に加え、現場での経験も求められるため、入社直後に配属になる可能性は低いと言えます。
しかし、大学で現場の経験があったり、建築士の資格を保有している場合はその限りではありません。
建設業界は日々技術革新が起こっている業界のため、その流れに取り残されないことも重要と言えます。
建設業界の代表的な職種の5つ目は「施工管理」です。
この施工管理職の主な仕事内容は建設現場の管理を行うことです。
建設現場では多くの人がいて、同時に複数の作業が行われているため常にその状況を把握しておく必要があります。
また、建設現場での事故は大きな被害に繋がるため、絶対に事故を起こしてはいけません。
そのために施工管理職の人が作業工程や人員の配置などをしっかりと確認し、必要に応じた指示を出すことが必要と言えます。
また、製品の品質基準が十分であるかの確認をするのも施工管理職の大切な仕事の1つです。
建設業界の代表的な職種の6つ目は「統計職」です。
統計職と聞いてすぐにピンとくる就活生はまだまだ少なく、すぐに分かった就活生はしっかりと業界研究ができていると言えます。
この統計職の主な業務内容は建物に関するあらゆる情報やデータを分析し、整理することです。
これらのデータを元に作業工程や建設費用などのコストについての意思決定を行うため、とても重要な職種と言えます。
また、プロジェクトの効率化やコスト削減の方法を検討する際にも活用されるため、全従業員に影響を与える職種と言っても過言ではありません。
【建設業界の志望動機】求める人物像4選
建設業界では、複雑なプロジェクトを多くの関係者と協力しながら進めるため、特定の能力や素養が求められます。
問題解決能力や協調性、クリエイティブ能力、推進力など、これらの資質を持つ人材が業界で活躍できると考えられています。
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
問題解決能力が高い
建設業界では、プロジェクト進行中にさまざまな問題が発生することが少なくありません。
そのため、問題を迅速に解決する能力が求められます。
さらに、問題を解決するだけでなく、未然に問題を発見し、リスクを管理する能力も重要です。
日常的に課題を見つけ、それに対して改善策を考える姿勢が必要とされます。
また、問題解決には論理的な思考力だけでなく、現場での柔軟な対応力も求められます。
たとえば、予算の制約や突発的なトラブルに対処する場面では、冷静かつ迅速に対応できる人が重宝されます。
建設業界における問題解決能力は、プロジェクト全体の成功を左右する重要な要素です。
協調性がある
建設業界では、1つのプロジェクトに複数の職種や専門分野の人々が関わります。
そのため、円滑なコミュニケーションを図りながらチーム全体をまとめる協調性が欠かせません。
特に、施工管理者やプロジェクトマネージャーとして働く場合、関係者間の調整や連携を円滑に進める能力が求められます。
さらに、現場では異なる職種の人々が協力して働くため、意見を尊重しつつ、効率的に業務を進める力が必要です。
チームでの目標達成に向けて他者と協力できる人は、建設業界で高く評価されます。
協調性をアピールする際には、過去の経験をもとに、具体的にどのようにチームに貢献したかを述べることが効果的です。
クリエイティブ能力がある
建設業界では、新しいものを生み出す創造力が重要です。
時代のニーズを敏感に捉え、新しいアイデアを形にする能力が求められます。
例えば、環境に配慮した建築設計や、スマートシティの実現に向けた革新的な提案が挙げられます。
このようなクリエイティブな視点を持つ人材は、業界で重宝されます。
また、デザインや設計に限らず、施工方法やプロジェクト管理の効率化といった分野でも創造力が発揮されます。
これからの建設業界では、従来の方法にとらわれず、新しい発想を積極的に取り入れることが求められるため、自身のクリエイティブな一面をアピールすることが効果的です。
推進力がある
建設業界では、チーム一丸となってプロジェクトを進めるために推進力が重要です。
特に、大規模なプロジェクトでは、計画を確実に遂行するためのリーダーシップや決断力が求められます。
推進力がある人材は、目標に向かってプロジェクトを前進させる中心的な役割を担います。
たとえば、予期せぬ問題が発生した場合でも、冷静に状況を分析し、次のステップを明確に示す力が必要です。
さらに、チームメンバーのモチベーションを高めるスキルも推進力の一部といえます。
このような能力を持つ人は、建設業界のさまざまな場面でリーダーシップを発揮し、プロジェクトの成功に貢献することが期待されています。
【建設業界の志望動機】実際に書く前に
建設業界の職種への理解が深まったところで、次は「志望動機を書く前に」準備しておきたいことを説明していきます。
ここでは必ず実施して欲しいこととして「業界研究」「企業研究」「自己分析」の3つを説明していきます。
これらは志望動機だけでなく自己PRやガクチカでも活用できるため、しっかりと確認して下さいね。
業界研究
志望動機を書く前に必ず実施して欲しいこと1つ目は「業界研究」です。
あなたが興味のある建設業界の現状をしっかりと把握しておきましょう。
建設業界全体の規模、その中での企業の立ち位置、現状の景気や業界の将来性などを把握しておくことで企業選びの基準がはっきりと見えてくるはずです。
また、業界全体の問題点や課題を把握しておくことで、面接などの選考時に活用できることもあります。
企業研究
志望動機を書く前に必ず実施して欲しいこと2つ目は「企業研究」です。
あなたが興味のある企業や受けようと考えている企業を中心に、企業理念や将来のビジョン、社風などを深掘りしていきましょう。
ここで注意して欲しいのが、順番は業界研究→企業研究でないと理解しにくいということです。
業界全体のことを大まかにでも把握してから、その中の1つに焦点をあてるという順番でないと、企業を選ぶ基準が不安定になってしまうためです。
自己分析
志望動機を書く前に必ず実施して欲しいこと3つ目は「自己分析」です。
「就職活動の前に自己分析しておくべきだよ」という言葉を軽く考えていませんか?
「自分のことは自分が一番知っている」と思っているかもしれませんが、案外そうでもありません。
自分の人生を振り返り、自分と向き合う機会はそう多くありません。
就職活動を良いきっかけと考えて、本当の自分を見直すことを強くおすすめします。
あなたの思いがけない一面にきっと出会えるはずです。
【建設業界の志望動機】聞かれる理由
一度原点に立ち戻り、そもそも「志望動機を聞かれる理由」は何かを説明していきます。
ここでは特に見られているポイントとして「企業とのマッチ度を図るため」と「熱意を見るため」の2つのポイントに焦点をあてて説明していきます。
企業とのマッチ度を図るため
志望動機を聞かれる理由の1つ目は「企業とのマッチ度を図るため」です。
志望動機からあなたの就活の軸や価値観、人柄を汲み取ることで、あなたと企業の相性を判断しています。
あなたがどんなに優秀な人材であっても、企業との相性が悪ければ職場で活躍することは難しいと言えます。
また、企業の価値観や社風に合わない環境にい続けることは想像以上に苦痛です。
企業との相性を選考中に確認することは、あなたにとっても大切なことだと断言できます。
熱意を見るため
志望動機を聞かれる理由の2つ目は「熱意を見るため」です。
企業の採用担当者は当然ですが、熱意を持って選考に挑んでくる人材と共に仕事をしたいと考えています。
熱意の伝え方は人それぞれですが、エントリーシートで熱意を伝える場合はこの志望動機の内容を充実させることをおすすめします。
業界・企業研究をしっかりと行い、同業他社との違いをしっかりと認識している上に職種への理解も深い就活生は熱意があると判断される傾向にあります。
志望動機で熱意を伝えるためには事前の準備がとても大切だと言えるでしょう。
【建設業界の志望動機】差別化するコツ
次は「ありきたりな志望動機にしないために」意識するべきことを説明していきます。
志望動機は企業を受ける理由と一緒に「自分の強みをアピールする」「具体的なエピソードを盛り込む」という認識を持っておくことで、あなたらしい文章にすることが可能です。
自分の強みをアピールする
ありきたりな志望動機にしないためには「自分の強みをアピールする」ということを意識しておきましょう。
ここではアピールすることで大きなプラス評価に繋がる傾向にある強みとして「責任感」「対応力」「向上心」「コミュニケーション能力」を説明していきます。
責任感
建設業界でプラス評価に繋がりやすい強み1つ目は「責任感」です。
建設業界では住居だけでなく商業施設や道路、ダムなどの社会インフラに関わるものに携わります。
そのため、多くの人の暮らしや安全を守るために1つひとつの仕事に責任感を持ち取り組む姿勢がとても大切です。
全ての職種に共通してこの責任感は必要なため、受ける職種問わず好印象を与えることができる強みだと言えます。
対応力
建設業界でプラス評価に繋がりやすい強み2つ目は「対応力」です。
建設業界ではオーナーやクライアントからの要望を受け建物を設計・デザインし、実際に着工します。
その際、急なデザイン変更などの要望が発生することもあり、それに柔軟に対応する必要があります。
また、建設現場では日々人員の変更や作業の進捗状況、資材の在庫数などによって作業工程を組み直したり変更したりすることもあり、それに素早く対応する必要もあります。
そのため、トラブルやアクシデントに対応し、素早く解決に導く対応力が求められます。
向上心
建設業界でプラス評価に繋がりやすい強み3つ目は「向上心」です。
建設業界は日々技術革新が起こる程に業界全体が進むスピードが早い業界です。
そのため、常に新しい情報や技術を学ぶための向上心がないとついていくことは難しいと言っても過言ではありません。
特に技術職や技術開発職に携わる場合、常に情報をキャッチできるようにアンテナを立てておく必要があります。
向上心を持ち自発的に学ぶことができることをアピールできれば、大きなプラス評価に繋がることは間違いありません。
コミュニケーション能力
建設業界でプラス評価に繋がりやすい強み4つ目は「コミュニケーション能力」です。
多くの就活生が勘違いしていることですが、このコミュニケーション能力が生きる職種は営業職だけではありません。
建設現場と事務所を繋ぐ事務職、設計やプロジェクトの管理をする技術職、データを分析する統計職の人であってもコミュニケーション能力は必須の能力です。
チームでプロジェクトを進めることが多いため、仕事を円滑に進めるためには多くの人と連携する必要があります。
積極的に自分からコミュニケーションを取ることができることをアピールできれば、確実に内定に一歩近づくことができると言えます。
具体的なエピソードを盛り込む
ありきたりな志望動機にしないためには、あなたの「具体的なエピソードを盛り込む」ことを意識しましょう。
企業の採用担当者は就職活動の期間中に数多くの志望動機に目を通すことになります。
その中で印象に残るためにはあなたらしさが伝わるような、オリジナリティ溢れる文章にする必要があります。
そのためには他の就活生には書けない、あなた独自のエピソードを文章に盛り込む必要があります。
このエピソードを具体的に書くためには自己分析をしっかりと行っておく必要があるため、事前に取り組んでおきましょう。
【建設業界の志望動機】おすすめの書き方
次は具体的な「志望動機の書き方」を説明していきます。
構成をはっきりさせることが重要であることは先ほど説明しましたので、ここではその構成の仕方に焦点をあてていきます。
構成の順番通りに「結論:どうしてこの企業を志望したか」「根拠:その企業を志望するに至った経緯」「入社後のイメージ:入社後どのように活躍したいか」の3つに分けて詳しく説明していきます。
結論:どうしてこの企業を志望したか
志望動機を書く時はまず「結論:どうしてこの企業を志望したか」を書きましょう。
結論を最初に書くことであなたが一番伝えたいことが明確になり、結論迷子になることを防いでくれます。
また結論から述べることで後の展開を企業の採用担当者に想像させることができ、話が頭に入ってきやすい状態を作ることができます。
この結論部分はダラダラと書かずに一文にまとめ簡潔に伝えるように意識しておきましょう。
根拠:その企業を志望するに至った経緯
結論が書けたら次はそれを補足する「根拠:その企業を志望するに至った経緯」を書いていきましょう。
この根拠の部分はあなたの過去のエピソードを絡めながら具体的に書くことで、文章の説得力を上げることができます。
具体的にために意識したいことが、文章を簡潔かつ定量的に書くことです。
大学◯年生の時や〇〇年に起きた、〇月にあったなど、数字で書くことで文章がより具体的になり、想像しやすくなります。
入社後のイメージ:入社後どのように活躍したいか
結論、根拠が書けたら最後に「入社後のイメージ:入社後どのように活躍したいか」を書きましょう。
ここで大切なことは、自分の強みを活かしてどう活躍していきたいかを具体的に述べることです。
そのためには自己分析と企業研究が欠かせない要素になってきます。
ここの内容が具体的である程、あなたの熱意が伝わりやすくなります。
その上、再現性の高い内容で書くことができると「一緒に働いてみたい!」と思わせることができるはずです。
【建設業の志望動機】建設業界の志望動機を作成する際の3つのポイント
建設業界の志望動機を作成する際には、単に働きたい理由を述べるだけでなく、業界や企業、職種について深く理解した内容を盛り込むことが重要です。
以下では、志望動機をより説得力のあるものにするための3つのポイントを解説します。
作成後の最終チェックとしても活用してください。
①建設・設計・土木、各々の現状と今後の動向を把握する
建設業界は多岐にわたる分野で構成されており、建設、設計、土木といったそれぞれの分野で異なる役割や課題を持っています。
そのため、自分がどの分野でどのように働きたいのかを明確にするためにも、現状と今後の動向を把握することが重要です。
例えば、DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展や、環境配慮型の建築技術が注目されている現状を踏まえた内容を志望動機に盛り込むと、説得力が増します。
また、分野ごとの動向を理解することで、志望企業がどのような課題に取り組んでいるのかを知るきっかけになります。
これにより、業界全体の視点から自身がどのように貢献できるかを具体的に述べることが可能となります。
②志望企業の独自の施策を理解して志望動機に反映する
志望動機を作成する際には、志望する企業が持つ独自の施策やビジョンを理解し、それを反映させることが重要です。
例えば、その企業が取り組んでいる環境配慮型のプロジェクトや、新しい建築技術の導入、地域密着型の事業展開など、他社と差別化されるポイントを志望動機に織り込むと、説得力が大きく向上します。
さらに、企業の公式ウェブサイトやニュースリリースを通じて、企業が掲げるビジョンや目標を調査し、それに共感する理由を具体的に述べることで、志望の強さをアピールできます。
このように、企業の特徴に基づいた志望動機を作成することで、選考担当者に好印象を与えることが可能です。
③自分がどのように貢献できるのか明記
志望動機では、「自分の強み」と「企業が求める人材像」を結びつけることが重要です。
単に「○○が得意です」と述べるだけでなく、それが企業の業務や事業にどのように活かせるのかを説明しましょう。
例えば、「コミュニケーション能力が高い」とアピールする場合、「顧客との関係構築に強みを活かし、売上向上に貢献したい」と具体化すると説得力が増します。
また、過去の経験やエピソードを交えて説明すると、よりリアリティのある志望動機になります。
④志望する職種の仕事内容を理解して志望動機を作成する
建設業界には、設計、施工管理、営業などさまざまな職種が存在します。
志望動機を作成する際には、自分がどの職種で働きたいのか、具体的にどのようなキャリアを歩みたいのかを明確に伝えることが重要です。
職種の仕事内容をしっかりと理解し、それに基づいて自分のスキルや経験がどう活かせるかを述べることで、具体性のある志望動機が完成します。
例えば、「施工管理職を通じて、プロジェクト全体を効率的に進行させるスキルを磨きたい」といった明確な目標を述べると、企業側に意欲が伝わります。
さらに、その職種に求められる能力を調査し、自分の強みと関連付けてアピールすることで、説得力が増します。
【建設業の志望動機】不適切な内容2点
建設業界への志望動機を書く際には、特定の内容が不適切とされる場合があります。
表面的な理由だけでなく、他業界や企業にも通用するような汎用的な理由では、説得力に欠けると判断される可能性があります。
以下では、不適切な内容を2点挙げ、その回避方法について解説します。
「建設業界で働く人がかっこいいから」など表面的な理由のみの内容
「建設業界の仕事がかっこいい」「大きな建物を作るのが憧れ」という表面的な理由だけでは、選考担当者に好印象を与えることは難しいです。
企業が求めるのは、その仕事を通じて応募者が何を成し遂げたいのか、どのような価値を提供できるのかという具体的な内容です。
志望動機を書く際には、業界や企業について深く調査し、その企業でしかできない仕事や挑戦したい課題を挙げることが重要です。
「企業の地域再生プロジェクトに感銘を受け、その一員として貢献したい」というように、具体的かつ熱意を感じられる内容にすることが求められます。
建設業界のみならず他の業界・企業・職種にも言える内容
「社会に貢献したい」「人々の生活を支えたい」などの志望理由は一見良い内容に思えますが、他の業界や企業、職種でも通用する一般的な表現では、建設業界を選んだ理由が伝わりません。
選考担当者は、なぜ建設業界でなければならないのかを知りたがっているため、業界や企業に特化した内容を盛り込むことが重要です。
具体的には、「地域の災害復興支援に取り組む建設業界の取り組みに共感し、自分の設計スキルを活かして支援したい」といったように、建設業界でしか実現できない目標を述べる必要があります。
これにより、志望理由が明確になり、説得力のある内容に仕上げることができます。
【建設業界の志望動機】業種別例文
建設業界の志望動機の書き方やアピールするべきポイントが分かり、「ちょっと書いてみようかな」と感じている頃ではないでしょうか。
しかし、頭では理解できているもののいざ書こうとしても上手く書けないものです。
そこで最後に建設業界の「業種別例文」を用意しました。
ここでは先ほど紹介した代表的な職種である「営業職」「事務職」「技術職」「技術開発職」「施工管理」「統計職」の6つの例文を紹介していきます。
建設業界の営業職の志望動機
私は多くの人々が安心して楽しめる場所に携わりたいと思い貴社を志望しました。
就職活動を始める際に軸として考えているのが、多くの人の笑顔を創造することです。
そこで一番最初に思いついたのが地元にある◯〇という大型商業施設であり、調べてみると貴社が建設したことが分かり興味が湧きました。
説明会に参加すると〇〇分野に特化していることや将来のビジョン、具体的な職種についての理解が深まり、その一員として働きたいと思うようになりました。
私は学生時代にサークルの代表をしており、コミュニケーション能力には自信があります。
この強みを活かし、営業職として多くの顧客の信頼を獲得し、貴社の発展に貢献したいと考えております。
建設業界の事務職の志望動機
私は社会のインフラを支える仕事がしたいと思い貴社を志望いたしました。
私はインフラの中でも特に重要なのは道路だと考えています。
その理由は道路なくして私たちの生活は維持できませんし、発展もないと感じているためです。
そう考えている中、貴社が道路の建設・施工に強みを持っていることを説明会で知り、私もそのサポートをしたいと強く感じました。
また、貴社の掲げている環境に最大限配慮した物作りをすることにも強く共感いたしました。
私は学生時代にしていた居酒屋のアルバイトの経験から、様々な状況に対応することに慣れています。
この強みである対応力を活かし、事務職として現場と事務所を繋ぐ仕事に就きたいと考えています。
建設業界の技術職の志望動機
私は人々が見ただけで感動するモノづくりに携わりたいと考え貴社を志望しました。
私は趣味でサッカー観戦に出かけるのですが、その際貴社が手がけた〇〇スタジアムを見てその美しさに感動しました。
それと同時に、私も見ただけで感動するような建造物を作る仕事に就きたいと感じました。
貴社は業界内でもデザイン性や機能性に優れた建造物を作ることを得意としており、私のしたいことを体現していると感じました。
私は学生時代にデザインの勉強をしており、大学3年生の時には500通の応募がある建造物デザインコンテストで優勝経験があります。
このスキルや経験を活かし、見た人を感動させるような建造物の建設に挑戦したいと考えております。
建設業界の技術開発職の志望動機
私は建設業界の仕組みを変えたいと思い貴社を志望しました。
貴社が建設業界の中であらゆることに先行して取り組んでいることに感銘を受けました。
私の父は建設業界で仕事をしており、現場で作業中に事故にあった経験があります。
その際に父が言っていた現場は常に危険と隣り合わせだという言葉が忘れられません。
しかし、貴社が取り組んでいる作業の効率化・デジタル化を進めればそのような危険な作業を大幅に削減できると感じています。
私は学生時代にAi技術の研究を行い、学内の論文大会で優勝した経験があります。
この技術力を活かすことで、建設業界の仕組みを変えることができると信じており、貴社でそれを成し遂げたいと考えております。
建設業界の施工管理の志望動機
私は地図に載るような建造物に携わりたいと思い貴社を志望しました。
私の小さい頃からの夢は自分で建てたものが地図に掲載されることです。
その思いを胸に就職活動をしている中で、貴社がダム建設に強みを持っていることに興味を持ちました。
ダムは実家の近くにもあり、よく近くまで散歩していたことを思い出しました。
それに加え、河川の水量の調整や貯水など、あらゆる場面で私たちの生活に影響を与えている建造物であることを再認識できました。
私は大学時代に部員150人いる部活動で主将を務めており、マネージメント能力には自信があります。
入社後はこのスキルを活かし、施工管理職として安全な現場の実現に貢献したいと考えております。
建設業界の統計職の志望動機
私は強みであるデータ分析のスキルを活かし、街の発展に貢献したいと考え貴社を志望しました。
私の地元には大きな駅ビルがあり、その施設ができてから駅で降りる人が増え、街に活気が生まれました。
その結果移り住んでくる人も増え、さらに活気が生まれるという好循環を目の当たりにしました。
その駅ビルというのが貴社が建設した〇〇です。
先日の説明会でビルを建てる際には多くのデータを元に分析した情報が欠かせない要素の1つであると知りました。
私は研究室での経験から、多くの情報を分析し成果に繋げることができます。
この能力を活かし、多くの街の発展に貢献できる建造物を世の中に作り出していくサポートをしたいと考えております。
【建設業の志望動機】NG例文
以下では建設業界の志望動機におけるNG例文を3つ紹介します。
それぞれNG観点も簡単に解説しているので、是非参考にしてください。
NG例①
私は、人々の生活を支える建物をつくる仕事に携わりたいと考えています。
幼い頃から建築に興味を持っており、建物が完成するまでの過程を知るのが好きでした。
そのため、大学では建築学を学び、施工管理の知識を深めました。
貴社の事業内容を拝見し、多くの建築プロジェクトに携わっていることを知り、私もその一員として貢献したいと考えています。
現場での経験を積みながら、施工管理のスキルを高め、多くの人々の役に立つ仕事をしていきたいです。
また、貴社の研修制度が充実していることにも魅力を感じています。
成長し続けられる環境の中で、技術を磨き、建設業界の発展に貢献したいと考えています。
NG例②
私は、モノづくりに携われる仕事がしたいと考えています。
昔から手を動かして何かをつくることが好きで、大学ではものづくりの基礎を学びました。
特に、建設業は大規模なモノづくりができる分野であり、自分の手がけたものが形として残る点に魅力を感じています。
また、チームで協力しながら進める仕事にも興味があり、多くの人と関わりながら仕事ができる点にやりがいを感じます。
貴社は長年にわたり数多くの建設プロジェクトを手掛けており、業界内でも高い評価を受けていると伺いました。
私もその一員としてモノづくりに貢献し、技術を磨いていきたいと考えています。
将来的には、さらに知識を深め、より多くのプロジェクトに携わりたいです。
就活コンサルタント木下より

この例文は建設業でなくても良いようにみえる表現が多く、なぜ建設業なのか、具体的な理由が不明です。
他の業界でも当てはまる内容はできるだけさけましょう。
NG例③
私は、社会の発展に貢献できる仕事がしたいと考え、建設業界を志望しました。
インフラ整備や建築物の建設は、人々の暮らしを支える重要な役割を担っており、大きなやりがいを感じられる仕事だと思っています。
また、現場での業務を通じて、技術を身につけながら成長していける環境にも魅力を感じました。
貴社は多様な建築プロジェクトに携わっており、幅広い経験を積むことができるため、私もその一員として貢献したいと考えています。
将来的には、より多くの現場を経験し、施工管理やプロジェクトマネジメントにも関わることで、自分のスキルを向上させていきたいです。
貴社での仕事を通じて、社会に貢献しながら自己成長を続けていけるよう努力してまいります。
就活コンサルタント木下より

なぜ建設業なのか明確な理由がない文章になっており、またどの建設会社でも言える内容で特定の企業に対しての動機になっていません。
また、具体的にどのような経験を積みたいのかもしっかり書くといいでしょう。
まとめ
建設業界はオフィスビルや商業施設だけでなく、道路やダムなどの社会インフラを支える建造物にも携われる業界です。
かつては危険でキツいイメージが先行して志望する就活生が少なくなっていた時期もありますが、技術革新もあり近年は人気の業界の1つとなっています。
そのため、志望動機はしっかりと考え対策する必要があり、業界・企業研究や自己分析を事前に取り組む必要があると言えます。
構成は結論・根拠・入社後のイメージの3つに分けることで、相手に伝わりやすい文章を作ることができます。
あなたの経験や印象的な出来事を上手く活用し、独自性のある志望動機を作って行きましょう!







_720x550.webp)

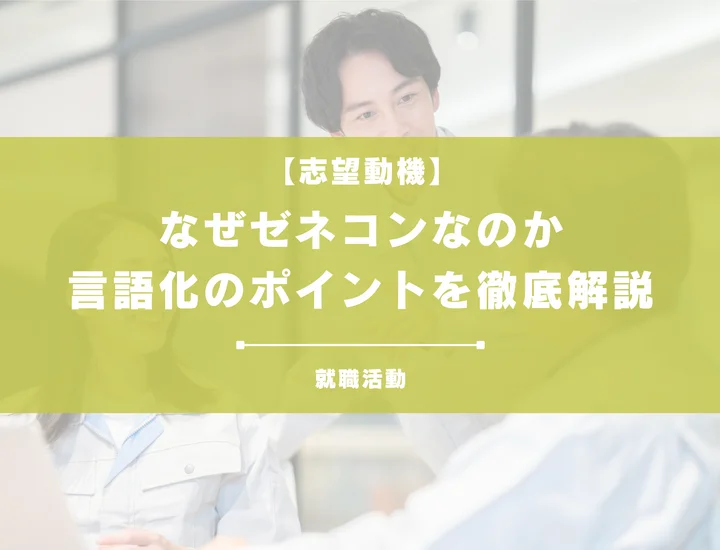






就活コンサルタント木下より
この文章はどの企業でも当てはまる内容になっており、抽象的で説得力に欠けます。
企業との結びつきが弱く、志望動機が不明瞭な点も改善ポイントです。