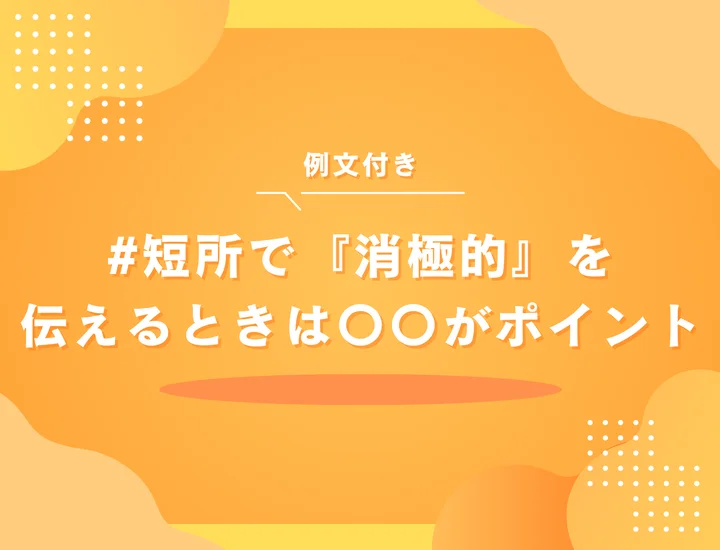HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
自己PRは、就職活動において自分自身の価値や魅力を企業に伝える重要な場面です。
数ある強みの中でも、「相手の立場に立って考える力」は一見すると当たり前に聞こえるかもしれませんが、実はあらゆる職種・業界で求められる本質的な能力のひとつです。
人と関わる仕事が多い現代社会では、相手の気持ちや背景をくみ取りながら適切に行動できる人材が重宝されます。
とはいえ、この力は言葉だけでは抽象的になりやすく、「本当にアピールになるのか?」と不安に感じる人も少なくありません。
ですが、具体的なエピソードや成果と結びつけることで、「相手を思いやるだけでなく、それを行動に移し、成果を上げた人」という印象を与えることが可能です。
【相手の立場に立って考える力で自己PR】「相手の立場に立って考える力」は自己PRにしても良いのか
「相手の立場に立って考える力」を自己PRで使うことに対して、不安を感じている就活生も少なくありません。
「ただの優しさに見えないか」「他の人と内容がかぶってしまわないか」など、当たり前に思われてしまうのではないかと懸念する気持ちはよく理解できます。
しかし、実際にはこの力は、表現や伝え方によって非常に強い自己PRに変えることができます。
なぜなら、相手の気持ちや状況を理解し、それに基づいて行動を変えられるという能力は、単なる性格的な優しさにとどまらず、論理的な判断力や観察力、コミュニケーション力といった複数のスキルと結びついているからです。
【相手の立場に立って考える力で自己PR】「相手の立場に立って考える」とは
「相手の立場に立って考える」という行動は、単に優しさや気配りを意味するだけではありません。
この力の本質は、相手の感情や状況を的確に読み取り、そこに自分の考えや行動を柔軟に合わせていく姿勢にあります。
就職活動においては、こうした他者理解を基盤にした行動力こそが、チームでの協働や顧客対応の現場で発揮される重要なスキルとして評価されます。
この力を自己PRとして伝えるためには、「自分がどう思ったか」ではなく、「相手のためにどう行動したか」「その結果、何が変化したか」にフォーカスして伝えることが効果的です。
ここでは、「相手の立場に立って考える力」がどのような要素から成り立っているのかを、代表的な3つの視点から解説していきます。
聞き上手
「相手の立場に立って考える力」を持つ人には、自然と「聞き上手」という特徴が現れます。
相手の話を丁寧に聴き、その背後にある感情や真意にまで耳を傾けられる姿勢は、単なる会話のスキルを超えた大きな強みです。
表面的なやり取りでは見えてこない本音や悩みを引き出せるのは、相手の言葉に寄り添いながら話を聴こうとする誠実な姿勢があってこそです。
聞き上手な人は、相手の発言に対して即座に判断を下すのではなく、まずその背景や意図を理解しようとします。
相手の立場を尊重するその姿勢が、信頼関係の構築につながり、結果として円滑なコミュニケーションが生まれます。
特に職場では、報連相(報告・連絡・相談)の質を高めるうえでもこの力は重宝され、上司や同僚、顧客との関係づくりにも良い影響を与えます。
臨機応変な対応が出来る
「相手の立場に立って考えることができる人」は、自分の都合や考えに固執せず、周囲の状況や相手の気持ちに応じて柔軟に行動を変えることができます。
このような人には、その場の空気や相手の感情を察知する感受性が備わっており、あらかじめ用意された正解に頼るのではなく、目の前の状況に応じて最善の選択をする力を持っています。
こうした臨機応変さは、想定外の事態やコミュニケーションのすれ違いが起こりやすい現場において特に重要です。
相手の立場に立って状況を考えることができれば、問題の本質を見極めやすくなり、結果としてスムーズな対応が可能になります。
また、その柔軟性は周囲に安心感を与え、信頼される存在として組織の中での役割を広げていくことにもつながります。
意見の押し付けをしない
「相手の立場に立って考える力」がある人は、他者と自分の考え方や価値観の違いを自然に受け入れることができます。
こうした人は、議論や話し合いの中でも一方的に自分の意見を押し付けることなく、相手の視点に配慮しながら言葉を選ぶことができるため、対話を対立ではなく前進の場として活用することができます。
この姿勢は、チームでの協働や多様性を重んじる組織環境において、特に価値あるものです。
異なる意見が交錯する場面で、自分の立場を主張しながらも、相手の考えを否定せず受け止めることができる人は、信頼され、調整役としての力を発揮します。
自己PRの中では、こうした姿勢が実際の経験にどう結びつき、どのように周囲との関係性や成果に影響を与えたかを具体的に語ることで、大きな説得力を持つエピソードになります。
【相手の立場に立って考える力で自己PR】「相手の立場に立って考える力」を企業が評価する理由
就職活動においては、学歴や知識、資格などのスペックだけでなく、「どのように人と関わり、どう行動するか」といった人間力も重視されます。
その中でも、「相手の立場に立って考える力」は、多くの企業に共通して求められる要素であり、社会人としての基盤ともいえる資質です。
目の前の相手が何を求めているかを考え、それに応じて行動できる人は、顧客との信頼関係を築いたり、チームの調和を保ったりと、さまざまな場面で力を発揮します。
この力が自己PRとして評価されるためには、単なる「優しい人」で終わらせず、ビジネスにおける実用性と成果につながる行動として伝えることが大切です。
以下では、企業がこの力をどのように見ているのか、その背景や理由を3つの視点から解説していきます。
企業が重視する力とは
企業が求める人材像には、「自律性」や「成果を出す力」といった要素だけでなく、「他者と協力しながら物事を進められる力」も含まれています。
特に共感力や協調性、柔軟性といった対人スキルは、多くの職場で高く評価されています。
これらの力は、一人で仕事を完結するのではなく、他者と連携して業務を進める場面で非常に重要な役割を果たします。
「相手の立場に立って考える力」は、これらのスキルを土台から支える基礎的な力です。
他人の気持ちや視点を理解し、状況に応じた言動ができる人は、周囲との摩擦を避けながら的確な判断を下すことができるため、職場の安定や生産性向上にも貢献します。
また、職種を問わず発揮できる汎用性の高いスキルであることから、多くの企業で採用評価の指標とされています。
就活生には思考の柔らかさが求められている
変化のスピードが速く、正解がひとつではない現代のビジネス社会において、固定観念にとらわれない柔軟な思考が求められるようになっています。
特に就職活動を行う学生に対しては、「吸収力」や「変化への対応力」が備わっているかどうかが重視されており、それを見極める要素の一つとして「相手の立場に立って考える力」が注目されています。
この力は、ただ相手を思いやるという優しさにとどまらず、立場や状況の違いを理解したうえで、自分の行動を調整できるかどうかという、思考の柔らかさと応用力を内包しています。
例えば、自分と異なる意見に対しても否定せずに受け止める姿勢や、状況に応じて役割を変えられる柔軟性は、まさに「相手の視点で考えられる力」の証です。
「顧客視点」や「チームワーク」に直結する強み
「相手の立場に立って考える力」は、企業活動の根幹を支える「顧客視点」や「チームワーク」といった価値観とも密接に関わっています。
特に営業職やサービス業では、顧客が本当に必要としているものや、まだ言葉にしていない不安や要望をくみ取る力が、成果に直結します。
ただ商品を紹介するのではなく、相手の背景やニーズを的確に読み取り、それに合った提案をする力が求められます。
また、開発職や企画職のようなチームで進行する業務では、メンバー間の連携や進捗状況に対する配慮が欠かせません。
自分の作業だけでなく、他のメンバーの立場や負荷を理解したうえで動ける人は、全体の進行をスムーズにし、チームとしての成果を引き上げる存在となります。
こうした配慮や気づきは、まさに「相手の視点で物事を考える力」の賜物です。
【相手の立場に立って考える力で自己PR】「相手の立場に立って考える力」をアピールするべき人の特徴
「相手の立場に立って考える力」は、誰にとっても必要な資質のひとつですが、すべての人が同じように発揮できるわけではありません。
この力が自然と行動の中に表れている人には、共通する性質や思考の傾向があります。
就職活動においてこの力を自己PRとして伝えるべきか迷っている場合、自分の行動や人との関わり方を振り返ってみることが重要です。
特に、相手を理解しようとする姿勢が自然に身についていたり、周囲に配慮した行動が無意識にできていたりする人は、この力を持っていると自信を持ってアピールすることができます。
ここでは、そのような人に見られる代表的な特徴について解説していきます。
コミュニケーションがスムーズにできる
相手の立場に立って物事を考える力を持つ人は、他人の意図や感情を素早く読み取ることができるため、対話の中で相手が求めていることを適切に捉えながら返答をすることができます。
このような人は、必要以上に言葉を重ねなくても相手に安心感を与え、自然と会話の流れを作り出すことができます。
その結果、コミュニケーションの場面で摩擦が生じにくく、話し相手から「話しやすい」「理解してもらえている」という印象を持たれることが多くなります。
また、会話のキャッチボールにおいても、自分の言いたいことばかりを伝えるのではなく、相手の理解度や感情に配慮しながら言葉を選ぶことができるため、対話の質が高まり、職場やチームの中でも信頼を得やすい存在となります。
このような性質を持つ人は、自己PRの中で「対話において意識していること」や「周囲との関係性において心がけている行動」を具体的に伝えることで、「相手の立場を考えられる人物」として説得力のあるアピールが可能になります。
想像力がある
日頃から他者の視点に立って物事を考えている人は、自然と「この人は今、何を思っているのか」「どんな背景があるのか」と想像することに慣れています。
このような想像力のある人は、相手の立場や状況を推し量りながら行動するため、トラブルを未然に防いだり、適切なタイミングで支援の手を差し伸べたりすることができます。
さらに、想像力は共感や配慮だけでなく、創造性にもつながります。
さまざまな立場の視点を行き来しながら物事を考えられるため、固定観念に縛られない柔軟な発想ができ、新しい提案やアイデアを生み出すことが可能になります。
このような力を持つ人は、サービスや企画の場面でも「誰かの役に立つにはどうすればよいか」といった視点で物事を考えることができるため、自己PRにおいてもその想像力を「相手視点に立てる実践的な力」として表現することが効果的です。
観察力がある
他者の立場に立って行動するためには、まずその人がどのような状況にあるのかを正しく把握する必要があります。
そのためには、表情、言動、声のトーン、雰囲気といった非言語的な要素を細やかに読み取る観察力が求められます。
観察力に優れている人は、そうした些細な変化に気づくことができ、相手の本音や不安にいち早く気づき、タイミングよく行動することができます。
また、観察力がある人は人に対してだけでなく、物事や環境にも敏感で、チームや組織全体の動きや空気感を把握するのが得意です。
そのため、周囲が見落としがちな問題点に気づいたり、全体のバランスを見て行動を調整したりすることができ、リーダーや調整役としても活躍の場が広がります。
自己PRにおいては、「周囲の変化に気づき、どう対応したか」といった経験を語ることで、観察力を通じた「相手理解」の力を具体的に示すことができます。
【相手の立場に立って考える力で自己PR】評価されやすい業界・職種
「相手の立場に立って考える力」は、職場におけるコミュニケーションやチームワークだけでなく、顧客との関係構築やサービスの質にも大きく関わるため、多くの業界・職種で高く評価される傾向にあります。
特に、人と接する機会が多い職種では、相手の気持ちや背景を的確に捉えて行動することが、信頼や成果に直結する場面が数多く存在します。
この力を自然に発揮できる人は、相手の本音やニーズに寄り添った対応ができ、組織や顧客の満足度を高める存在として重宝されます。
以下では、特にこの力が評価されやすい代表的な職種について詳しく解説します。
営業職
営業職においては、商品やサービスをただ紹介するのではなく、クライアントが抱える課題や真のニーズをくみ取り、それに合った提案を行うことが成果に直結します。
そのためには、相手の立場に立って考え、置かれている状況や業界背景、担当者の感情まで含めて理解しようとする姿勢が不可欠です。
営業先では明確に要望が語られるとは限らず、表情や反応、発言の裏にある意図を読み取る力が試されます。
このような力を持つ人は、一方的な提案ではなく、相手にとって「ちょうどいい」解決策を提示することができるため、クライアントとの信頼関係を築きやすくなります。
その信頼が契約の継続や追加提案の機会につながり、結果的に長期的な成果として反映されていきます。
営業職では、売上だけでなく「人として信頼されるかどうか」も評価のポイントとなるため、相手視点を持てる人材は非常に重宝されます。
接客業
接客業では、日々多くの顧客と直接関わる中で、それぞれのニーズや感情に応じた柔軟な対応が求められます。
特に、クレーム対応や不安を抱えるお客様への接遇の場面では、マニュアル通りの対応ではなく、相手の立場に立った気配りが不可欠となります。
言葉の選び方ひとつ、表情や姿勢ひとつが、お客様に安心感や信頼感を与えるかどうかを左右するからです。
相手がどんな気持ちでその場にいるのか、何に困っているのかを想像しながら行動できる人は、自然と顧客満足度の高い対応ができるようになります。
また、そうした姿勢は一度限りの接客で終わらず、「またこの人に対応してほしい」と思わせる関係性を生み出します。
接客業では、このような小さな気配りの積み重ねが店舗全体の評価にもつながるため、「相手の立場に立って考える力」を持つ人は、サービス品質の根幹を支える存在として評価されます。
マーケティング職
マーケティング職では、商品やサービスの価値をどのように顧客に届けるかが重要であり、そのためには「使う人の視点」で物事を捉える力が求められます。
製品を作る側の論理や理想だけでは、顧客の心には響かず、真に求められるものを提供することはできません。
ユーザーが何を感じ、どんな場面で必要とし、どのような情報に反応するのかを想像しながら戦略を立てることができる人が、優れたマーケターとして成果を出すことができます。
この力を持つ人は、商品や企画を見たときに、常に「使う側の立場」から見直す視点を持っており、顧客との距離を感じさせない訴求が可能です。
たとえば、キャッチコピーひとつ、ビジュアルひとつをとっても、「相手にどう受け取られるか」を意識する姿勢があるかどうかで結果は大きく変わります。
そのため、「相手の立場に立って考える力」は、マーケティングにおける仮説力・分析力・発想力のすべてに通じる重要な能力として、高く評価されるのです。
コールセンター
コールセンターでは、電話越しに寄せられる顧客の不安や不満に対して、丁寧かつ的確に対応する力が求められます。
そのため、ただ言われたことに応じるのではなく、相手の感情に寄り添いながら話を受け止め、状況を理解しようとする姿勢が非常に重要です。
特にクレーム対応では、相手の言葉の背後にある不安や苛立ちをくみ取り、感情的な部分に共感を示した上で、冷静に問題解決へと導くスキルが必要とされます。
また、電話という対面ではないコミュニケーション手段であるからこそ、声のトーンや間の取り方など、相手の微妙な変化に気づく感受性と、誠実に対応し続ける粘り強さが求められます。
ときには、顧客の気持ちに寄り添い、話を「聞いてもらえた」と思ってもらえることが信頼につながるため、単なる情報のやりとりにとどまらず、メンタルケア的な要素も含まれるのがこの職種の特徴です。
「相手の立場に立って考える力」を備えた人は、このような場面で顧客からの信頼を得やすく、企業の印象を左右する重要な役割を担うことができます。
人事
人事の仕事は、単なる応募者のスキル確認にとどまらず、その人の価値観や可能性、将来的な成長のポテンシャルを見極める繊細な役割を担っています。
限られた時間の中で応募者の言葉の背景や表情、態度の変化に注意を向ける必要があるため、相手の立場や緊張感を理解したうえで接する力が求められます。
特に面接では、表面的な受け答えだけで判断するのではなく、その人がどのような経験をしてきたのか、何に価値を置いているのかを丁寧に引き出す姿勢が欠かせません。
また、採用活動は企業と応募者のマッチングを図るものであり、企業目線だけでなく、応募者の立場に立った視点も不可欠です。
その人がどんな環境で力を発揮できそうか、どのように育っていく可能性があるかを考えるには、高い共感力と観察力が求められます。
「相手の立場に立って考える力」を持つ人は、ただ評価する側としてではなく、一人の社会人として、応募者と誠実に向き合うことができ、信頼される人事担当者として活躍する素質を備えています。
教育業界
教育業界においては、相手の理解度や性格、置かれている環境に合わせてアプローチを変える柔軟な対応が強く求められます。
学生や社員、後輩といった対象は年齢や背景が異なり、一律の指導では効果が出ないことも少なくありません。
そのため、一人ひとりの個性や特性を見極め、どのような伝え方が響くのか、どのタイミングで手を差し伸べるべきかを判断する力が不可欠です。
また、相手がうまく言葉にできない不安や悩みをくみ取るには、常に相手の立場に立ち、心の動きを想像しながら接することが求められます。
叱るときも励ますときも、相手の成長を第一に考えた声かけや態度が求められ、「この人なら信頼できる」と思わせる存在であることが大切です。
「相手の立場に立って考える力」がある人は、単に知識を教えるのではなく、人の可能性を引き出し、長期的な視点で成長を支える役割を担うことができます。
医療業界
医療業界では、専門的な知識や技術に加え、患者や利用者の不安を和らげ、信頼関係を築くための対人スキルが重要視されます。
体調がすぐれない中で不安や孤独を感じている患者に対して、必要なのは医学的な説明だけでなく、「この人は自分のことを分かってくれている」という安心感です。
そのためには、言葉のやり取り以上に、相手の様子や感情の変化を注意深く観察し、心の動きに寄り添う姿勢が求められます。
「相手の立場に立って考える力」を持っている人は、患者の立場や生活背景、治療に対する不安を想像し、それに基づいた丁寧な対応ができます。
たとえば、声のトーンや話す速度、説明の順序といった細かな配慮も、患者にとっては大きな安心材料となります。
このような対応が積み重なることで、患者との信頼関係が強まり、より円滑な医療の提供が可能となります。
医療におけるケアとは、技術や知識だけでなく、心の部分にまで手を差し伸べることができる力を含んでおり、だからこそ「相手の立場を想像し、行動できる力」は不可欠な資質として評価されるのです。
【相手の立場に立って考える力で自己PR】「相手の立場に立って考える力」の言いかえ表現
「相手の立場に立って考える力」は、非常に汎用性の高い強みでありながら、そのままの表現では抽象的で、自己PRとしてのインパクトが弱くなってしまうことがあります。
そこで効果的なのが、この力をより具体的で伝わりやすい言葉に置き換えてアピールすることです。
言いかえ表現を活用することで、自分が持つ資質をよりはっきりと相手に印象づけることができ、また企業が求める人物像にピタリと合致させることも可能になります。
以下では、「相手の立場に立って考える力」を伝える際に使える代表的な言いかえ表現を紹介し、その背景や適性について解説します。
共感力
共感力は、相手の気持ちや状況を感情面から理解し、自分のことのように感じ取る力を指します。
この力を持つ人は、他者との会話や対話の中で、自然と相手の心情に寄り添うことができ、安心感や信頼感を与えることができます。
特に、相手が言葉にできない不安や迷いを抱えているときに、その感情を敏感に感じ取ることができるため、関係性を深める上で非常に効果的な資質です。
ビジネスの現場においても、共感力のある人は顧客や同僚、上司の思いや立場を理解しながら動くことができ、単なる論理的な対応を超えた「人として信頼できる」存在になります。
相手の気持ちに共鳴し、そこから行動につなげることができるこの力は、「相手の立場に立って考える力」の中核を担う要素の一つです。
傾聴力
傾聴力とは、相手の話を丁寧に聞き、話の内容だけでなく、その背景や意図までも受け止める姿勢を意味します。
話を途中で遮ったり、先入観で判断したりせず、相手の言葉に集中しながら耳を傾けることのできる人は、対話の中で多くの信頼を獲得することができます。
この力は、特に面談や会議、顧客対応などの場面で大きな価値を発揮します。
単に聞いているだけでなく、相手が本当に伝えたかったことに気づける人は、適切なタイミングで的確な返答ができるため、コミュニケーションの精度が高まります。
企業側も、相手の言葉を正確に理解しようとする姿勢を持つ人材を高く評価しており、傾聴力は職種を問わず重要な要素として注目されています。
気配り力
気配り力は、周囲の人や状況に対して敏感に反応し、相手から何かを求められる前に自ら動くことができる力です。
この力を持つ人は、常に周囲を観察しながら「今、誰が何を必要としているのか」「どんなサポートがあれば喜ばれるか」といった視点で考え、自然と先回りした行動を取ることができます。
このような振る舞いは、職場における信頼の蓄積に直結し、同僚や上司から「一緒に働きやすい人」として重宝される存在になります。
また、気配り力には「自分の立場だけで判断しない」という視点が根付いており、まさに「相手の立場に立って考える」行動の実践例とも言えます。
サービス業や事務職、チームで動く職種において特に重視されるこの力は、周囲への細やかな配慮を通じて組織全体の雰囲気や効率を高める存在となります。
柔軟性
柔軟性は、常に変化が伴うビジネスの現場において極めて重要な力です。
自分の考えに固執するのではなく、状況や他人の意見に耳を傾け、それに応じて行動や判断を調整できる人は、チームや組織において非常に信頼されやすい存在です。
特に、プロジェクトや業務が複数のメンバーと連携しながら進む現代の働き方では、ひとりの意見だけで物事が動くことはなく、他者の視点を取り入れながら最適解を見つけていく姿勢が求められます。
柔軟性を持つ人は、想定外の出来事や計画の変更にも前向きに対応できるため、結果的に組織全体の流れを止めることなく円滑に業務を進めることができます。
また、相手の考えを尊重したうえで自身の意見を調整できるため、調整力や協働性にも優れ、対人関係の中で衝突を避けながら前向きな関係構築ができる点も大きな特徴です。
「相手の立場に立って考える力」の実践として、柔軟性は単なる態度のやわらかさではなく、状況に応じてより良い結果を導くための行動力でもあり、企業が高く評価する資質のひとつです。
ホスピタリティ精神
ホスピタリティ精神とは、相手にとって心地よい環境や体験を提供するために、自分から進んで行動する姿勢を指します。
相手の気持ちやニーズを先回りして考え、その場にいる誰よりも早く気づき、必要なサポートや対応を行うことができる人は、接客やサービスの現場において非常に重宝されます。
この精神は、表面的なマナーや礼儀だけではなく、「相手にどう感じてもらいたいか」を常に意識しながら行動するという、深い配慮に基づいています。
ホスピタリティ精神を持つ人は、相手の立場や気持ちを丁寧に想像し、「言われたからやる」のではなく、「言われる前に動く」ことが自然とできるため、周囲からの信頼も厚くなります。
接客業だけでなく、チームでの仕事や社内外のやり取りにおいても、相手を気遣うその姿勢は、組織の雰囲気を和らげ、信頼関係の構築に大きく寄与します。
【相手の立場に立って考える力で自己PR】「相手の立場に立って考える力」をアピールする際のコツ
「相手の立場に立って考える力」は、多くの企業が高く評価する資質であり、自己PRとして非常に有効なテーマです。
しかし、その反面、抽象的になりやすく、伝え方次第では他の就活生と似たような印象になってしまうリスクもあります。
そのため、この力を効果的にアピールするには、伝え方に工夫が必要です。
エピソードの具体性、表現の選び方、成果の明示など、ちょっとした工夫を加えるだけで、自己PRの説得力は大きく向上します。
ここでは、「相手の立場に立って考える力」を自己PRに盛り込む際に意識すべき3つのコツを紹介します。
誰に対して何をしたのかを明確にする
自己PRで最も重要なのは、「自分がどんな行動を取り、誰にどんな影響を与えたか」を具体的に示すことです。
「相手の立場に立って考えた」という経験を伝える際も、漠然と「周囲に気を配った」「人にやさしくした」などと述べるだけでは、採用担当者には行動の背景や価値が伝わりません。
そのため、「誰に対して」「どんな状況で」「どのような配慮や工夫を行ったのか」を明確に語ることで、エピソードに具体性と説得力が生まれます。
対象が明確であればあるほど、相手を理解しようとした視点や、自分の判断に至った理由を伝えやすくなり、再現性の高い行動としてアピールできます。
たとえ小さな出来事であっても、丁寧に状況と行動を描写することで、印象に残る自己PRに仕上がります。
言い換え表現を用いる
「相手の立場に立って考える力」は非常に重要な力である一方で、そのまま伝えると抽象的でありふれた印象を与えることがあります。
そこで有効なのが、自分の経験や性格によりフィットする言い換え表現を活用することです。
共感力、傾聴力、柔軟性、気配り力、ホスピタリティ精神など、それぞれが異なる角度からこの力を表現しており、自分の強みをより立体的に伝える助けになります。
例えば、人の話をじっくり聞くことが得意であれば「傾聴力」、相手の状況に応じて行動を変えた経験があるなら「柔軟性」といった言葉に置き換えることで、より具体的で説得力のある表現になります。
企業が採用基準として重視する資質と、自分の行動がどのように合致しているかを示す上でも、適切な言い換えは効果的です。
自身の経験にもっともしっくりくる言葉を選び、その意味を深掘りすることで、個性あるアピールが可能になります。
行動と結果をセットで伝えるようにする
どれほど素晴らしい行動を取ったとしても、それが何につながったのかが伝わらなければ、自己PRとしてのインパクトは弱くなってしまいます。
そのため、「行動」と「結果」をセットで伝えることが重要です。
実際に行ったことに加えて、その結果として何が改善されたのか、相手や周囲にどのような変化が生まれたのかを明確に語ることで、行動の価値が具体的に伝わります。
また、結果を示すことで、自分の行動が単なる一時的な思いつきではなく、目的意識を持って行われたこと、そして同様の場面でも再現可能であることをアピールできます。
再現性のある行動は、採用後の活躍をイメージさせる材料にもなり、企業からの信頼を得る大きなポイントになります。
成果は数字でなくても構いません。
相手の反応や感謝の言葉、チームの雰囲気の変化などでも十分に評価される要素となります。
【相手の立場に立って考える力で自己PR】「相手の立場に立って考える力」をアピールする際の注意点
「相手の立場に立って考える力」は多くの企業で評価される重要な資質ですが、自己PRとして伝える際にはいくつか注意すべきポイントがあります。
よくあるのが、気配りや優しさといった表面的な印象だけにとどまり、実際の行動や成果が伝わらないというケースです。
どれだけ魅力的な強みであっても、それを裏づける具体的な情報がなければ、採用担当者には信ぴょう性のあるアピールとして受け取ってもらえません。
裏付けのエピソードを用いる
自己PRにおいてもっとも重要なのは、自分の強みをただ主張するだけでなく、それを証明する具体的なエピソードを示すことです。
いくら「私は相手の立場に立って考える力があります」と口にしても、それを裏付ける体験がなければ、相手にとっては信ぴょう性に欠ける印象となってしまいます。
エピソードは壮大なものや特別な成果である必要はなく、日常の中で発揮された小さな行動でも問題ありません。
ただし、その行動を通じてどんな配慮をし、相手にどのような変化をもたらしたかを具体的に語ることで、強みの「実在感」を持たせることができます。
事実に基づいたエピソードは、聞き手にとって印象にも残りやすく、「この人は本当にそういう力を持っている」と納得感を与える材料になります。
主体性を意識してアピールする
「相手の立場に立って行動した」ことを伝える際には、その行動に主体性があったかどうかが重要な評価ポイントとなります。
どれだけ素晴らしい行動であっても、それが誰かに言われて仕方なく行ったものであったり、周囲の流れに乗っただけの受動的なものであったりすると、強みとしての説得力が弱まってしまいます。
自己PRでは、自分の意思や判断によって動いたことを明確にする必要があります。
「自分がなぜそうしようと思ったのか」「その行動にどんな意味があると考えていたのか」といった内面的な動機を丁寧に言語化することで、主体性のある行動としてアピールすることができます。
企業が求めているのは、環境に流される人ではなく、自ら考え、行動を選び取ることができる人材です。
だからこそ、自発的に相手を思いやり、行動に移した経験を示すことが、より高い評価につながります。
成果を用いてアピールする
強みを語る上で見落とされがちなのが、その行動が結果としてどのような成果につながったかを伝えることです。
「相手の立場に立って考えられた」という事実だけでは、面接官にとってはただの行動で終わってしまいます。
そこに「その行動によってどんな良い変化があったのか」「誰がどう感じたのか」「周囲にどんな影響があったのか」といった成果を加えることで、自己PRはより力強いものになります。
成果は必ずしも数字や大きな表彰である必要はありません。
相手への感謝の言葉、雰囲気の変化、関係性の改善など、目に見えにくいものであっても十分に価値があります。
また、その成果から自分が何を学び、今後にどう活かそうと考えているのかまで言及できれば、採用後の成長可能性も感じさせることができます。
【相手の立場に立って考える力で自己PR】エピソード別例文集
「相手の立場に立って考える力」は、あらゆる職種や業界で求められる資質です。
しかし、この力を自己PRとして伝える際には、実際にどのような場面で発揮されたのかを具体的に示すことが不可欠です。
抽象的な表現だけではなく、「誰に対して」「どのような配慮をし」「どのような結果につながったのか」を明確にすることで、強みの信ぴょう性が増し、採用担当者に好印象を与えることができます。
ここでは、資格取得、部活動、アルバイト、ゼミ活動、留学経験という5つの場面を取り上げ、それぞれの経験をもとに「相手の立場に立って考える力」を効果的にアピールする自己PRの例文をご紹介します。
資格取得経験
この強みは、大学時代に簿記の資格取得を目指して学習グループを組んでいた経験で活かされました。
グループ内には、理解のペースが遅れて不安を抱えるメンバーがいて、学習の進行に差が出てしまうという課題がありました。
この課題を解決するために、相手の理解状況を丁寧に観察し、図解を用いた説明や具体的な身近な例えを使ってサポートしました。
また、全員が安心して質問できるように声かけや空気づくりにも意識を向けました。
結果、グループ全員が無事に資格試験に合格し、互いに学び合う文化が自然と根づきました。
貴社に入社した際も、周囲の理解度や立場に配慮しながら丁寧に仕事を進め、チームとしての成果に貢献していきたいと考えています。
部活動経験
この強みは、大学の運動部に所属していた際、メンバー全体のモチベーション維持に取り組んだ経験で発揮されました。
チーム内には、試合に出場できないメンバーが多く、練習への意欲が低下しつつあるという課題がありました。
この課題を解決するために、そうしたメンバーの立場に立ち、彼らが主力選手を支える「戦略班」「分析担当」としての役割を持てるよう再設計しました。
また、定期的に意見交換の機会を設け、存在意義を感じてもらえるよう努めました。
結果、チーム全体に一体感が生まれ、実際の試合においても全員が自分ごととして動く体制が整い、パフォーマンスの向上につながりました。
貴社に入社した際も、仲間の立場に寄り添い、組織全体の活性化に貢献できる存在を目指したいと考えています。
アルバイト経験
この強みは、飲食店でのホールスタッフとしてのアルバイト経験で活かされました。
勤務先では子連れのお客様が来店される機会が多かったのですが、ベビーカーの置き場や食事のタイミングなどに不便を感じている様子があり、満足度のバラつきが課題となっていました。
この課題を解決するために、お子様連れのお客様には広めの席を優先案内し、料理提供の順番も親子の食事タイミングに合わせて調整しました。
さらに、食器の配置や椅子の高さなどにも気を配り、居心地のよい環境づくりに努めました。
結果、対象のお客様の来店頻度が高まり、「また来たい」という声も増え、リピーターの獲得に貢献することができました。
貴社に入社した際も、相手のニーズを敏感に察知し、信頼と満足を生む行動ができる社会人として貢献したいと考えています。
ゼミ活動経験
この強みは、大学のゼミ活動で行ったグループ発表の準備の中で活かされました。
ディスカッション中に、班内で主張の異なるメンバー同士が激しく対立し、議論が前に進まなくなるという課題が発生しました。
この課題を解決するために、それぞれの意見の背景や意図を個別にヒアリングし、双方の主張の共通点を整理しました。
そのうえで、双方が納得できる中間案を提示し、議論の土台を整えることに注力しました。
結果、班全体が同じ方向を向いて準備に取り組むことができ、最終的には教授からも高い評価を得る質の高い発表に仕上がりました。
貴社に入社した際も、さまざまな意見や価値観を尊重しながら、前向きな協働を促す存在として組織に貢献していきたいと考えています。
留学経験
この強みは、大学3年時のカナダへの留学経験を通して発揮されました。
当初は現地の学生との間に価値観の違いによる距離を感じ、会話が弾まなかったり、疎外感を覚える場面も多いという課題がありました。
この課題を解決するために、自分の考え方を押し付けるのではなく、相手の興味関心に合わせて会話の内容を工夫したり、相手の文化に敬意を示す言動を意識的に取り入れるようにしました。
結果として、次第に信頼関係が築かれ、勉強以外の時間も共に過ごす友人が増え、学びの幅も広がりました。
貴社に入社した際も、異なる価値観や背景を持つ人々と柔軟に関係を築きながら、多様性を活かすチームの一員として貢献していきたいと考えています。
まとめ
「相手の立場に立って考える力」は、どの業界・職種においても求められる普遍的な強みです。
ただし、そのまま伝えるだけでは抽象的になりやすいため、具体的な行動やエピソードを通して説得力を持たせることが、自己PRとして評価されるポイントになります。
この力は、共感力や傾聴力、柔軟性やホスピタリティ精神など、さまざまな言い換え表現によって自分らしく表現することが可能です。
また、伝える際には、誰に対してどんな行動をとったのか、どのような成果が得られたのかを明確にし、主体性を持って行動したことを強調することが重要です。