
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
教員を目指す皆さんにとって、志望動機の作成は避けて通れないステップです。
本記事では、よくある例文とともに、説得力のある志望動機の書き方を徹底的に解説します。
【教員の志望動機】子供が好きだけじゃ弱い?
教員を目指す理由として「子どもが好き」はよく挙げられますが、それだけでは説得力に欠けてしまいます。
教員には、教育理念や指導方針、子どもたちにどう向き合い、どう成長を促していくのかといった具体的なビジョンが求められています。
そのため、志望動機には「なぜ教員なのか」「どのような教員になりたいのか」といった内容を盛り込むことが重要です。
以下では、評価されやすい志望動機の構成や具体例をご紹介していきます。
【教員の志望動機】教育実習の志望動機との違い
教員採用試験の志望動機を考える際に、過去に教育実習で志望動機を書いた経験がある方も多いでしょう。
しかしながら、教育実習と教員採用試験では求められる視点や立場が大きく異なります。
教育実習で作成した志望動機をそのまま使ってしまうと、採用担当者に熱意や適性が十分に伝わらず、場合によってはマイナス評価につながる恐れがあります。
そのため、両者の違いをしっかり理解したうえで、採用試験にふさわしい内容に練り直すことが重要です。
目的の違い
教員採用試験:教員として働く決意と資質
教育実習:現場で学ぶ意欲
教員採用試験における志望動機では、「教員として働く決意と資質」が伝わることが求められます。
現場での責任を引き受け、子どもと向き合いながら教育を通じて社会に貢献する意識が重要です。
一方、教育実習の志望動機は「現場で学ぶ意欲」を示すものであり、目的自体が異なります。
実習では「何を吸収したいか」「どう成長したいか」といった学びの姿勢が重視されるため、表現すべき内容にも大きな違いが生まれます。
伝えるべき内容の違い
教員採用試験:教育への情熱や教育観・ビジョン
教育実習:学びの意欲や柔軟性
教員採用試験では、将来的にどのような教育を実践したいか、子どもとどう関わっていきたいかといったビジョンを伝える必要があります。
教育への情熱や教育観・子ども観が問われ、社会人としての責任感も重要な評価ポイントです。
一方、教育実習では「実習で得たい経験」「成長したい姿」など、学びの意欲や柔軟性が問われます。
立場と期待される役割が異なる分、アピールすべき要素にも違いが出るのです。
【教員の志望動機】学校種別で向いてる特徴を紹介

単に教員といっても小学校・中学校・高校などで向いてる人の特徴や強みは変わります。
生徒の成長過程に合わせた教育を行っていくので必要な能力はそれぞれ異なるのです。
教員の志望動機を考えるうえで、自分自身の強みを理解してそれをアピールできる人はほかの学生との差別化につながります。
ここからは学校種別に分けて紹介するので、自分に当てはめて考えてみましょう。
小学校教員に向いてる人
- 子どもの成長を多角的に見守りたい人
- 根気強く、柔軟な対応ができる人
- コミュニケーション能力が高い人
小学校教員は、子どもたちの性格など人格形成を築く重要な期間をそばで見守る重要な役割です。
6年間という長い期間で社会性を身につけて友達との関わり方など、様々なことを学びます。
学習面だけでなく、生活習慣や社会性を身につけるサポートも行うため、幅広い知識と子供たちへの愛情が求められる職種ということです。
初めての勉強につまずく低学年や、高学年にかけて発達段階も異なる子供たち一人ひとりに合わせて一緒に歩んでいくことが必要不可欠です。
中学校教員に向いてる人
- 専門分野への探求心と指導力がある人
- 生徒の心に寄り添える人
- 生徒の自主性を育みたい人
中学校教員は、思春期という心身ともに大きく変化する時期の生徒たちと向き合います。
専門教科の指導に加え、進路選択の導入や部活動指導など、多岐にわたるサポートが求められます。
授業内容も、専門的になっていくので教員の知識も小学校より求められてくるでしょう。
義務教育の過程で必ず差し掛かる高校受験では、生徒の進路についての相談など人生設計を一緒に考える役目もあるので大人としての指導力も必要です。
しかし、小学校よりも生徒が主体的に動くことも多くなるので、どこまで教員が導くかなど線引きが難しい分野でもあります。
高等学校教員に向いてる人
- 高度な専門性と指導力を備えた人
- 生徒の主体性を尊重し、導ける人
- 社会とのつながりを意識できる人
高等学校教員は、生徒が社会へ羽ばたく準備をする大切な時期に関わります。
専門教科の高度な知識を伝えるだけでなく、生徒一人ひとりの進路実現に向けたサポートが重要な役割となります。
子供と大人の間に位置する高校生は、大人びている部分もあるもののまだまだ大人の手助けも必要です。
将来への考えや思考が自立してくる生徒たちの個性を尊重して、進路選択などにおいては適切なアドバイスができるような人間力が求められます。
また、中学校よりもより高度な知識も必要になるので、高等学校教員になりたいと思った場合は自身の得意教科もしっかり鍛えておくといいですね。
特別支援学校教員に向いてる人
- 一人ひとりの特性を深く理解しようと努める人
- 根気強く、小さな変化に喜びを見出せる人
- チームで連携する力がある人
特別支援学校教員は、障害のある子どもたち一人ひとりの個性とニーズに合わせた教育を推奨しています。
専門的な知識・技能に加え、深い愛情と忍耐強さが不可欠な仕事です。
子どものよって障害の種類やレベル、発達段階も異なります。
その子に合わせた指導計画を作成し、障害を理解したうえで接する必要があるのです。
また、発達はゆっくりなものの確実に成長しています。
日々の生活の中で小さな”できたこと”に気づき、ともに喜べるような人柄も重宝されます。
【教員の志望動機】採用担当者がみているポイント
教員の志望動機を作成する際には、単なる理想や感情だけでなく、具体的な根拠や将来的なビジョンが必要です。
採用側は、現場を理解し、継続的に努力できる人材かどうかを見極めています。
特に重視されるのは「教育への熱意」と「人柄」の2点です。
これらを伝えることで、より評価される志望動機につながります。
教育への思い
教員の志望動機では、「教育に対してどれほど真剣な気持ちを持っているか」が大きな評価ポイントとなります。
たとえば、学校生活での経験やそこから得た教育観を具体的に伝えると説得力が増します。
また、理想だけでなく現場の現実を理解している姿勢も好印象につながります。
自分なりの教育観や目指す教員像を明確に示すことで、面接官に強い印象を与えることができます。
志望者の人柄
教員には、知識や指導力だけでなく、信頼関係を築ける人柄も求められます。
そのため志望動機では、誠実さや責任感、協調性といった人間性が伝わる内容が重要です。
ボランティアやアルバイトなどの経験を通じて得た学びや、他者との関わりから意識してきた価値観を盛り込むと効果的です。
就活コンサルタント木下より

また、子どもや保護者、同僚との関係構築への意識を示すことで、現場での適応力も伝えることができます!
将来ビジョン
教員になって、どうなりたいのかや教育にどんな影響を与えたいと思っているのかを明確にする必要があります。
ただ教員の仕事をするだけでは、どうしても機械的になってしまいます。
学校には、教員としてただ教える以外に様々なやることがあります。
部活動の顧問をしたり、不登校生徒やいじめなど生徒間の課題も存在しています。
自分自身がどんな教育者になりたいのか、成し遂げたいことなどをしっかりともつことで応募先への志望度にもつながるでしょう。
ほかの教員志望の学生と差別化をするためにも、将来ビジョンはよく考え深堀しておくことをおすすめします。
目標達成力
教員の仕事は、児童生徒の学力向上や人間的成長といった目標を設定し、その達成に向けて計画的に取り組むことが求められます。
採用担当者は、あなたが困難な状況に直面しても、目標達成のために粘り強く努力し、具体的な成果を出すことができる人物かを見ています。
志望動機では、これまでの学業、部活動、アルバイト、ボランティア活動などにおいて、自ら目標を設定し、その達成のためにどのような工夫や努力をし、結果として何を成し遂げたのか、具体的なエピソードを交えて説明することが重要です。
目標達成の経験を通じて、あなたの計画性、実行力、課題解決能力、そして責任感をアピールしましょう。
【教員の志望動機】作成する前に必要なこと
納得のいく志望動機を書くには、事前準備が欠かせません。
教育業界や志望校について調べ、自分の価値観や目指す教員像を整理することで、具体的で一貫性のある内容に仕上がります。
以下で準備すべき3つのポイントを解説します。
業界研究
学校の理解
自己分析
業界研究
教員としての志望動機に説得力を持たせるには、教育業界への理解が不可欠です。
「子どもが好き」という気持ちだけでなく、社会が教育に求めている役割を知ることで、視野の広い志望動機が生まれます。
たとえば、ICTの活用や多様性への対応、最適な学びの実現など、現代の教育現場で重視されている課題に注目しましょう。
そうした背景を踏まえて、自分がどう関わりたいかを語ることで、現実的で信頼性のある内容になります。
教育ニュースや現職教員の声を参考にするのも効果的です。昨今、教育問題は多く取り上げられています。
教育問題は、今に始まった問題ではありませんが、志望動機の内容に関連づけることでそれらを解決できるスキルなどをアピールすることにつながります。
学校の理解
志望する学校の理解を深めることは、説得力のある志望動機を書くために欠かせません。
小学校と高校では教育の目的や指導方法が異なり、自治体や私立校ごとにも教育方針に特色があります。
学校のホームページや教育委員会の資料を確認し、自分の考えや経験がその学校にどう貢献できるかを考えましょう。
「この学校で何をしたいか」を具体的に示すことで、志望動機に現実味が生まれます。
教育方針は、市区町村ごとに決められています。
もとめる教員像はそれぞれ違いますので、応募先の地域によってしっかりと調べておく必要があります。
自己分析
説得力のある志望動機を作成するには、自己分析が不可欠です。
学校生活や教育実習、ボランティアなどの経験を振り返り、「なぜ教員を目指したのか」「どんな教員になりたいのか」を深く考えましょう。
さらに、自分の強みや価値観を整理し、それが教育現場でどう活かせるのかを明確にすることで、志望動機に一貫性と具体性が生まれます。
就活コンサルタント木下より

面接でも自信を持って伝えるための大切な準備になります!
【教員の志望動機】学校別!高評価ポイント
教員の志望動機は、学校種ごとに求められる役割や教育の目的が違い、それぞれに合った内容にすることが重要です。
小学校・中学校・高校・特別支援学校・大学では、生徒の年齢や発達段階、指導内容に応じて異なる能力や姿勢が求められます。
志望する学校に合わせて、自分の経験や考えを適切に結びつけた志望動機を作成しましょう。
小学校
小学校は、子どもたちが学びの基礎を身につけ、生活習慣や社会性を育んでいく大切な時期です。
教科の学習だけでなく、友達との関わり方や集団行動のルールを学ぶ場としても大きな役割を果たしています。
また、担任制が基本であるため、一人の教員が複数の教科を指導し、子どもの日常生活にも深く関わることになります。
そのため、児童一人ひとりの変化に気づき、長期的な視点で成長を支える力と、信頼関係を築く力が求められます。
志望動機では、「子どもの成長を幅広く支えたい」「学びの土台を築くことに魅力を感じた」といった、小学校教育の本質を理解した表現が高評価につながります。
また、教科の幅広さに対応する柔軟性や、一人ひとりの児童に細やかに寄り添える力を示すことも重要です。
教育実習やボランティア経験を交えて、子どもとの具体的な関わりを記すと説得力が高まります。
中学校
中学校は、生徒が思春期を迎え、心身ともに大きく成長しながら、自我を確立していく重要な時期です。
このため、教科学習の指導だけでなく、生活指導や人間関係の悩みにも丁寧に対応できる力が求められます。
また、中学校では教科担任制が採用されており、担当教科に対する専門的な知識とわかりやすく伝える指導力も欠かせません。
さらに、生徒一人ひとりの心の変化に寄り添い、信頼関係を築く柔軟性や共感力も重要な資質となります。
「生徒の成長に寄り添い、社会へ羽ばたく力を育てたい」など、思春期特有の課題に理解を示す志望動機が好印象です。
また、自分の専門教科に対する熱意をしっかり伝えることも大切です。
「その教科を通して、どのような力を育みたいか」といった具体的なビジョンを語ると、教育への真剣な思いが伝わります。
生徒に対してどのように関わり、信頼を築いていきたいかを明確にしましょう。
高校
高校は、生徒が進学や就職など将来の進路を具体的に選択していく、大きな転機を迎える時期です。
そのため、高校教員には専門的な知識に基づいた学力指導だけでなく、個々の生徒の希望に応じた進路指導やキャリア教育への関与も強く求められます。
また、生徒の自主性や自立を尊重し、社会に出る準備を支援する姿勢や、的確な助言力、信頼関係を築く力も重要な役割となります。
加えて、高校は全日制と通信制の高校に分類されます。
特に通信制高校では、多様な背景を持つ生徒が在籍しており、それぞれに合った柔軟な対応が求められます。
対面授業よりも、レポート指導やオンラインでのコミュニケーションが中心になるため、ICTを活用した指導力や、文章で丁寧に伝える力が重要です。
また、不登校経験のある生徒や、働きながら学ぶ生徒も多いため、生徒一人ひとりの状況に寄り添い、学びを支える姿勢が求められます。
「専門知識を生かして、生徒の進路選択を支えたい」「将来を見据えた学びを通じて、自立を促したい」といった、高校教育の目的に即した志望動機は高く評価されます。
生徒一人ひとりが自らの道を主体的に選べるよう支援する姿勢や、責任感を持って進路指導に取り組む意欲を具体的に伝えることが重要です。
進路相談やキャリア支援に携わった経験がある場合は、その際の具体的な行動や生徒との関わり方を盛り込むことで、実践的な力と教育への熱意が伝わります。
特別支援学校
特別支援学校では、障害のある子どもたち一人ひとりの特性や状況に応じた、きめ細やかな支援と指導が求められます。
学習支援はもちろんのこと、食事や着替え、移動などの生活支援、そして社会性や自立心を育てるための関わりも重要な役割です。
また、子どもたちの小さな変化に気づく観察力や、相手の気持ちを理解する共感力、継続的に支援し続けるための根気強さや温かさなど、さまざまな力が必要とされる現場です。
「子ども一人ひとりの可能性を信じ、最大限に引き出したい」という強い思いを持っていることは、特別支援学校を志望するうえで最も重要な要素です。
特別支援教育では、子どもの特性や状況に合わせた個別対応が必要となるため、その重要性を理解し、丁寧に向き合う覚悟があることを志望動機にしっかり盛り込みましょう。
また、支援経験がある場合には、そこで感じた気づきや成長、困難をどう乗り越えたかなどを具体的に記すことで、実践力や誠実さ、教育への熱意がより強く伝わります。
大学教員
大学は、学生が自身の関心や専門性を深めながら、社会に出る準備をする重要な時期です。
このため、専門分野における高度な知識と研究実績に加えて、学生の学びを支える教育力や指導力が求められます。
また、学生の自主性を尊重しながらも、進路や研究活動に対する的確な助言や学習支援ができる柔軟な姿勢も必要です。
さらに、ゼミ運営や卒業研究の指導、就職活動のサポートなど、学習以外の側面にも関わる場面が多いため、学生との信頼関係を築く人間的魅力も大切になります。
「自身の専門性を活かして、学生の学びを深めたい」「研究と教育を両立し、社会に貢献する人材を育てたい」といった教育・研究への意欲を示すと好印象です。
また、「学生が自ら考え、行動できるよう促す指導をしたい」など、大学教育ならではの自律支援型の教育観を盛り込むと志望動機に説得力が増します。
加えて、自身の研究テーマと教育の関連性や、「学生にどのような学びの場を提供したいか」といった具体的な教育ビジョンを語ることが効果的です。
【教員の志望動機】学校種別例文を確認しよう!
教員採用試験で評価されやすい志望動機の例文を、学校種や教科ごとに紹介します。
構成や表現の参考にしながら、自分らしい志望動機づくりに役立ててください。
小学校教員の例文4選
ここでは小学校教員の志望動機の例文を2つ紹介します。
それぞれ違う過去経験に基づいた志望動機になっているので確認しましょう。
小学校教員①
私は地域の子ども食堂でのボランティア活動を通じて、子どもたちの学びや生活に寄り添う重要性を実感しました。
学力だけでなく、自己肯定感を育てることの大切さを目の当たりにし、小学校教育に関心を持つようになりました。
担任として幅広い教科や日常の生活指導に携わることにやりがいを感じています。
一人ひとりの違いを尊重しながら、安心して学べる教室をつくる力を身につけたいと考えています。
また、教育実習では授業準備から児童との関係づくりまで一貫して関わり、教師の役割の重さとやりがいを学びました。
子どもたちと日々向き合いながら、個々の力を最大限に伸ばせる教員を目指しています。
小学校教員②
私は地域の放課後児童クラブでのアルバイトを通して、子どもの日常に継続的に関われる小学校教員という仕事に強く魅力を感じました。
学年や教科を問わず、生活や学びのさまざまな場面で子どもの成長を支える存在に惹かれたことがきっかけです。
特に、工作が苦手な子どもが諦めずに完成させた姿を見て、「そばで見守り、励まし続けたい」という思いが芽生えました。
また、教育実習では、授業の合間の会話やふとした関わりが信頼関係を築く上で非常に大切だと実感しました。
今後は、学力の向上だけでなく、子どもたちが安心して自分らしく過ごせる環境を整え、心の成長にも寄り添える教員を目指して努力してまいります。
小学校教員③
私が小学校教員を志望する理由は、子どもたちの知的好奇心を刺激し、学ぶことの楽しさを伝えたいからです。
大学での教育実習において、特に小学校低学年の児童が、目を輝かせながら新しいことを吸収していく姿に感動しました。
私が担当した算数の授業で、図形パズルに夢中になり、難しい問題にも諦めずに挑戦し続けた児童がいました。
その子が問題を解いた時の満面の笑みを見て、子どもの可能性を引き出す瞬間に立ち会えるこの仕事に強い魅力を感じました。
貴校の「体験を通して主体的に学ぶ」という教育方針に共感しており、児童一人ひとりの個性を尊重し、知的好奇心を育む教育実践に貢献したいと考えております。
持ち前の明るさと粘り強さを活かし、子供たちとともに成長できる教員を目指します。
小学校教員④
私が小学校教員を志望する理由は、様々な背景を持つ子どもたちが関わっていく中で、共に成長し社会性を育める学級を作りたいからです。
大学時代の教育ボランティアで、様々な個性を持つ子どもたちと関わる中で、一人ひとりの良さを引き出し、協調性を育むことの重要性を学びました。
特に、グループワークで意見がぶつかりながらも、互いの考えを尊重し、一つの目標に向かって協力する姿を見たとき、教育の力を実感しました。
貴校の、児童の主体性を重んじ、豊かな人間関係を育む教育に魅力を感じています。
児童との対話を大切にし、一人ひとりに寄り添いながら、安心して自己表現できる温かい学級づくりに貢献したいです。
子どもたちの未来を支える責任感を持って、情熱を注いでまいります。
小学校教員の志望動機では、子どもたちの知的好奇心を引き出し、学ぶことの楽しさを伝えたいという熱意を示すことが大切です。
また、低学年から高学年までの幅広い発達段階に対応できる柔軟性や、基礎学力だけでなく豊かな人間性や社会性を育むことへの意欲もアピールポイントになります。
なぜ小学校教育に魅力を感じ、どのような児童像を理想とし、そのために自身の経験や強みをどう活かせるのかを具体的に述べましょう。
保護者との連携の重要性への理解も示すと良いでしょう。
中学校教員の例文5選
中学校教員の志望動機の例文を3つ紹介します。
科目別に分けたので、自分の専攻にあったものを確認しましょう。
中学校教員(数学①)
私は、数学に苦手意識を持つ生徒を支えたいという思いから中学校教員を志望しました。
中学生の頃、わからない内容を丁寧に教えてくれた先生の姿勢が、学ぶことへの自信を取り戻すきっかけとなりました。
教育実習では、生徒のつまずきを見逃さず、対話を重ねることで理解を深められる授業の難しさと面白さを体験しました。
また、単に公式を教えるのではなく、日常生活や社会との関わりを意識した導入が、生徒の興味を引く手応えを感じました。
今後は、学習内容を通じて論理的な思考力を育てるとともに、成長段階に応じた支援ができる教員を目指して努力を続けます。
中学校教員(数学②)
私が中学校教員を志望する理由は、多感な時期にある生徒たちに寄り添い、学ぶことの面白さと将来への希望を与えたいからです。
私自身、中学校時代に数学の先生から丁寧な指導を受けたことで、苦手意識を克服し、論理的に考えることの楽しさを知りました。
この経験から、生徒一人ひとりの躓きに真摯に向き合い、成功体験を積み重ねる手助けをしたいと考えるようになりました。
教育実習では、生徒との対話を重視し、個々の理解度に応じた課題を提供するなど、主体的な学びを促す工夫をしました。
貴校の「生徒の個性を伸ばし、自立を支援する」という教育目標に共感し、数学の指導を通して、生徒たちの思考力や問題解決能力を育み、自信を持って未来へ進むためのサポートをしたいと考えております。
中学校教員(英語①)
私が中学校教員を志望する理由は、グローバル化が進む社会で活躍できる生徒を育成したいからです。
大学で異文化コミュニケーションを専攻し、多様な価値観に触れることの重要性を学びました。
中学校時代は、英語学習を通して世界への関心が広がり、将来の可能性を感じた経験があります。
この経験を活かし、生徒たちに英語を学ぶ楽しさだけでなく、その先にある世界への扉を開くきっかけを提供したいです。
教育実習では、アクティブラーニングを取り入れ、生徒が主体的に英語でコミュニケーションを図る授業を実践しました。
貴校の国際理解教育への積極的な取り組みに魅力を感じており、これまでの学びと経験を活かして、生徒の英語力向上はもちろん、異文化への理解と関心を深める教育に貢献したいと考えております。
中学校教員(英語②)
私は国際交流ボランティアとして外国人観光客の案内をする中で、多様な文化や価値観に触れる機会を得ました。
その経験から、多文化理解の重要性を強く実感し、英語教育を通して生徒の視野を広げる手助けがしたいと考えるようになりました。
中学校は語学の基礎を学ぶだけでなく、自分の考えを持ち、それを言葉で表現する力を育む大切な時期です。
教育実習では、暗記中心の学習だけでなく、会話やスピーチなどの活動を取り入れることで、生徒たちが英語を使う楽しさに気づいてくれたことが嬉しく印象に残っています。
今後は、英語の知識だけでなく、表現する力や異文化への興味を育てる授業を工夫し、生徒一人ひとりの可能性を引き出せる教員を目指します。
中学校教員(体育)
私は高校時代、部活動の副キャプテンとして後輩の指導やチーム運営に関わる中で、体育を通じて人との関わり方や責任感が養われることを実感しました。
その経験から、体育教育が人間関係や社会性を育む重要な場であることに魅力を感じ、中学校教員を志すようになりました。
中学生は身体の成長に加え、精神的にも不安定になりやすいため、運動を通して自己肯定感を高める環境づくりが必要だと考えています。
教育実習では、安全を最優先にしながらも、生徒が前向きに取り組める授業の工夫や、全員に目を配る難しさを学びました。
今後は運動の楽しさを伝えるだけでなく、仲間との関わりや挑戦の中で自信を育てる体育指導を目指していきます。
中学校教員の志望動機では、思春期という多感な時期の生徒たちに寄り添い、彼らの自己肯定感を育みながら、将来への道筋をサポートしたいという意欲を示すことが重要です。
専門教科への深い知識と情熱はもちろん、部活動指導や進路指導への関心もアピールしましょう。
生徒が抱える悩みや葛藤を理解し、精神的な支えとなりたいという姿勢を示すことも大切です。
自身の経験を踏まえ、中学校でどのような教育を実践したいのかを具体的に記述してください。
高校教員の例文5選
高校教員の志望動機の例文を3つ紹介します。
よく確認しましょう。
高校教員(国語①)
私は、言葉が人の心を動かし、考えを深める力を持っていることに魅力を感じ、国語教育を通じて生徒の思考力や感受性を育てたいと考えています。
読書指導のボランティア活動では、物語を読んだ生徒たちが自分の意見を積極的に語り合う姿に触れ、言葉が人と人とをつなぐ媒体であることを実感しました。
教育実習では、生徒同士の意見交換を取り入れた授業を行い、他者の考えに触れながら自らの思考が深まっていく様子に、大きなやりがいを感じました。
今後は、作品の理解だけにとどまらず、表現を通して自分や他者を理解する力を養えるような授業を工夫し、生徒にとって国語が「自分を知るきっかけ」となるよう努めてまいります。
高校教員(国語②)
私が高校教員を志望する理由は、生徒たちが自己と向き合い、多様な価値観の中で自らの進路を主体的に切り拓く力を育みたいからです。
私自身、高校時代に国語の授業を通して、文学作品に描かれる人間の葛藤や社会のあり方について深く考える機会を得ました。
この経験が、多角的な視点を持つことの重要性を教えてくれました。
大学では日本文学を専攻し、言葉の持つ力や表現の奥深さを探求してきました。
教育実習では、古典作品の読解を通して、生徒たちが現代社会と結びつけて考察を深める授業を心がけました。
貴校の「主体性と探求心を育む」という教育方針のもと、国語の指導を通して、生徒たちの思考力、表現力、共感力を養い、将来社会で活躍するための基盤づくりに貢献したいと考えております。
高校教員(物理)
私が高校教員を志望する理由は、科学的な探究心を持つ生徒を育成し、未来の科学技術を担う人材の育成に貢献したいからです。
大学で物理学を学び、自然界の法則を探求することの面白さと、それが社会に与えるインパクトの大きさを実感しました。
高校時代に物理の実験に夢中になった経験があり、生徒たちにも知的好奇心を満たす体験を提供したいと考えています。
教育実習では、演示実験やグループでの探究活動を取り入れ、生徒が主体的に課題を発見し、解決していくプロセスを重視した授業を展開しました。
貴校のSSH指定校としての先進的な理数教育の実践に強い関心を持っております。
専門知識を活かし、生徒の探究心を刺激する授業づくりに努め、科学的思考力と創造性を育む教育に情熱を注ぎたいです。
高校教員(数学)
私は、問題を解いて正解にたどり着く達成感だけでなく、解法に至るまでの思考の過程を他者と共有することに楽しさを感じ、数学教育に関わりたいと思うようになりました。
塾講師として働く中で、数学に苦手意識を持つ生徒が自力で答えを導き出し、自信を取り戻す姿に立ち会い、学びを支える責任の重さと喜びを強く実感しました。
教育実習では、図や具体例を使った説明に加えて、生徒の考えを引き出すような問いかけを意識したところ、理解の深まりが見られ、教える側の工夫次第で学習意欲に変化が生まれることを学びました。
今後は、数学を知識として教えるだけでなく、論理的思考や問題解決力を育む授業を通して、生徒の可能性を広げられる教員を目指してまいります。
高校教員(地歴)
私は、歴史の学びを通じて過去を深く理解し、その知識をもとに未来を主体的に考える力を育てたいという思いから、地歴科教員を志望しました。
高校時代に模擬授業の発表を任された際、自分の言葉で歴史を伝える面白さと、相手に伝えることの難しさの両方を経験し、教育への関心が高まりました。
教育実習では、「なぜその出来事が起きたのか」をテーマに、生徒と一緒に背景を掘り下げる対話的な授業を行いました。
生徒の意見を引き出す中で、こちらが気づかなかった視点に出会う場面が多くあり、共に学ぶ姿勢の大切さを改めて実感しました。
今後は、自らも歴史に対する探究心を持ち続けながら、生徒が主体的に学びを深められる授業づくりに努めてまいります。
高校教員の志望動機では、専門分野への深い探求心と、それを生徒に分かりやすく伝えるための熱意が求められます。
大学進学や就職など、生徒一人ひとりの多様な進路希望に対応し、主体的な進路選択を支援したいという姿勢を示すことが重要です。
生徒の知的な成長を促すだけでなく、社会で自立していくために必要な思考力や判断力を育成したいという教育観を具体的に述べましょう。
自身の専門性や経験を、高校教育の場でどのように活かせるかを明確にすることがポイントです。
特別支援学校教員の例文厳選
特別支援学校教員の例文を2つ紹介します。
それぞれ、訴求しているポイントが違うので、よく確認しておきましょう。
特別支援学校教員①
私は、発達障害のある児童と関わるボランティア活動を通じて、子ども一人ひとりに応じた支援の大切さを強く実感し、特別支援教育への関心を深めました。
子どもによって理解の仕方やコミュニケーションの取り方が異なり、その子に合った関わり方を見つけることの難しさと、信頼関係が築けたときの喜びを経験しました。
教育実習では、日々の小さな変化に気づくために表情や行動を丁寧に観察し、安心して話せる雰囲気をつくることが信頼の第一歩であると学びました。
今後は、学習面だけでなく、生活の中での成功体験や人とのつながりを大切にし、子どもたちが自分に自信を持てるような環境づくりを意識して取り組んでまいります。
特別支援学校教員②
私が特別支援学級の教員を志望する理由は、一人ひとりの児童生徒が持つ個性と可能性を最大限に引き出し、社会で自立して生きていくための力を育みたいからです。
大学での特別支援教育に関する講義や、地域の放課後等デイサービスでのボランティア活動を通して、様々な特性を持つ子どもたちと関わってきました。
その中で、個々の発達段階やニーズに応じた丁寧な支援がいかに大切かを痛感しました。
特に、粘り強く関わることで、できなかったことができるようになった時の子どもたちの喜びや自信に満ちた表情に、大きなやりがいを感じました。
貴校の「インクルーシブ教育を推進し、一人ひとりを大切にする」という理念に深く共感しております。
これまでの学びと経験を活かし、児童生徒、保護者、関係機関と連携しながら、個に応じた最適な支援計画を作成・実行し、子どもたちの成長を全力でサポートしたいと考えております。
特別支援学校教員の志望動機では、障がいのある子どもたち一人ひとりの個性と可能性を尊重し、その成長を全力でサポートしたいという強い意志を示すことが不可欠です。
多様なニーズに対応するための専門知識やスキルを学ぶ意欲、そして何よりも子どもたちへの深い愛情と共感力が求められます。
困難に直面しても粘り強く向き合い、保護者や関係機関と連携しながら、子どもたちの自立と社会参加を支援したいという熱意を、具体的なエピソードを交えて伝えましょう。
中高一貫校教員の例文厳選
中高一貫校教員
私は、中学から高校へと続く6年間を通して、生徒の学びだけでなく人間的な成長にも継続して関われる中高一貫教育に強く魅力を感じています。
一人の教員として長期的な関係を築けることで、学習指導にとどまらず、悩みや目標に寄り添いながら成長を支えることができると考えました。
インターンシップでは、生徒それぞれの個性を尊重した声かけや、進路に向けての段階的な支援が印象に残り、丁寧な関わりが信頼関係につながることを学びました。
今後は、日々の授業の中で学力を育成するだけでなく、進路選択や人間関係など、生徒の人生に関わる場面でも支えになれる教員を目指し、誠実に努力してまいります。
中高一貫校の教員の志望動機では、6年間という長いスパンで生徒の成長を見守り、一貫した教育方針のもとで指導にあたりたいという点を強調することがポイントです。
中学生から高校生への発達段階の変化を理解し、それぞれの時期に応じた適切な指導やサポートを提供できることをアピールしましょう。
継続性のある教育を通じて、生徒の学力だけでなく、人間性や社会性を長期的に育んでいきたいという熱意を示すことが重要です。
学校の教育理念への共感も具体的に述べると良いでしょう。
【教員の志望動機】NGポイント
教員の志望動機では、内容だけでなく避けるべき表現にも注意が必要です。
曖昧な動機や待遇面の強調はマイナス評価につながるため、具体性と誠意が求められます。
ここでは、教員の志望動機で避けたいNGポイントを具体的に紹介し、それぞれの改善策についても解説します。
「子どもが好き」のみの内容
「子どもが好きだから教員になりたい」という志望動機は非常に多く見られます。
子どもへの思いは大切ですが、それだけでは教育に対する理解や教員としての責任感、将来への展望が見えにくく、説得力に欠けてしまいます。
そのため、「子どもが好き」という気持ちに加え、どのような教育をしたいのか、自分が目指す教員像や取り組みたい教育活動についても具体的に伝えることが大切です。
たとえば、「子どもが学びを楽しめる環境をつくりたい」など、教育観や実践的な目標を交えることで、より魅力的な志望動機になります。
福利厚生に言及
志望動機で福利厚生や安定性、給与など待遇面を強調するのは避けましょう。
教員には子どもと真剣に向き合う姿勢や教育への使命感が求められるため、「公務員だから安心」「休みが多いから」などの理由はマイナス評価につながります。
安定を求める気持ち自体は問題ありませんが、それだけでは教員としての適性や意欲が伝わりません。
志望動機では、自分が教育現場で果たしたい役割や、どのように貢献したいかを明確に語ることが大切です。
他の教育機構で使えるもの
どの学校にも当てはまるような一般的な志望動機は、説得力に欠けるため避けましょう。
「教育を通して社会に貢献したい」「子どもの成長を支えたい」といった内容は一見前向きでも、「なぜこの学校なのか」が伝わらなければ評価は上がりません。
面接官は、その学校に対する理解や共感、そしてマッチ度を重視しています。
志望校の教育方針や特色をしっかり調べ、自分の考えや経験とどう結びつくのかを具体的に示すことが大切です。
就活コンサルタント木下より

リサーチの深さは志望動機に自然と表れます!
教育方針の丸写し
学校のホームページ・パンフレットに書かれている教育方針を、そのまま志望動機に使ってしまうのは避けるべきです。
たとえ共感していても、自分の言葉で語らなければ「考えが浅い」と受け取られる可能性があります。
もし教育方針に強く共感したのであれば、 「自分の経験の中で、その理念と重なる体験があった」「その方針に沿ってこういう教育をしたい」 といった、自分の言葉と体験を交えた表現にしましょう。
自分の教育観や価値観とリンクさせることで、独自性のある志望動機に仕上がります。
志望動機のNGワードについては以下の記事で詳しく紹介しています。
あわせてご覧ください。
先生に憧れている
「先生に憧れている」という理由だけでは、教員として働く具体的な動機や適性が伝わりにくくなります。
採用側は、教育に対する自分なりの考えや、生徒とどう関わりたいかといった実践的な視点を重視しています。
憧れを原点とすることは問題ありませんが、そこから一歩踏み込み、「なぜ自分が教員として貢献できるのか」を明確に伝えることが大切です。
【教員の志望動機】考え方を紹介
教員としての志望動機を考える際は、ただ「子どもが好き」や「教育に関わりたい」といった漠然とした理由だけではなく、自分自身の内面としっかり向き合うことが大切です。
一貫性があり、かつ自分らしさが伝わる志望動機を作成するには、いくつかのステップを踏みながら整理していく必要があります。
教師を志望するきっかけを考える
最初のステップは、「なぜ教員を目指そうと思ったのか」を振り返ることです。
この段階では、完成された文章にしようとせず、素直な気持ちを書き出すことが大切です。
たとえば「先生に励まされた」「子どもと接して喜びを感じた」など、心が動いた経験を思い出しましょう。
そのきっかけは、志望動機の土台になります。
自分が教職に惹かれた理由を明確にすることで、オリジナリティのある志望動機につながります。
なぜ教員でなくてはいけないのかを考える
教育に関わる仕事は塾講師や福祉、企業の研修担当などさまざまありますが、その中でなぜ学校教員を選ぶのかを明確にすることで、志望動機に深みが出ます。
たとえば、「長期的に子どもと関わり、成長を見守りたい」「生活面や人間関係も含めて支援できる環境がある」といった理由が挙げられます。
ここをしっかり整理することで、志望動機の軸が定まり、ぶれない一貫性のある文章が書けるようになります。
他の職業では代替できない、教員だからこそ実現できる想いを言語化することが重要です。
教員になって実現したいことを考える
志望動機には、「教員になったあとに何をしたいのか」という将来への展望も欠かせません。
たとえば、「子どもたちが安心して挑戦できる教室をつくりたい」「社会に出てからも通用する思考力を育てたい」など、教育に対するビジョンを持っていると、面接官にも意欲が伝わります。
具体的な取り組みや方法があれば、それを加えることでさらに説得力が増します。
就活コンサルタント木下より

単に教員になりたいだけでなく、教員になった後にどんな価値を提供したいのかを考えることが大切です。
なぜそれを実現したいのか
最後に重要なのが、「なぜ自分はそれを実現したいのか」という内面的な理由を掘り下げることです。
ただの理想論ではなく、自分の経験や価値観と結びついているかどうかが、志望動機に深みを持たせる鍵になります。
たとえば、「自分が学校で救われた経験があり、今度は自分が誰かの力になりたい」といった、自身の体験を通して得た思いを言葉にすることで、よりリアリティのある内容になります。
このプロセスを丁寧に行うことで、表面的な言葉ではない、自分自身の芯から出てきた説得力ある志望動機が完成します。
【教員の志望動機】効果的に伝えるには
教員採用試験では、文章や言葉で自分の考えを正確に、わかりやすく伝える力も評価されています。
そのため、志望動機は内容だけでなく、伝え方にも工夫が必要です。
ここでは、教員の志望動機を効果的に伝えるための具体的なコツを紹介します。
一文を短く
志望動機を作成する際は、一文をできるだけ短くすることを意識しましょう。
一つの文に複数の内容を詰め込みすぎると、読み手にとって意味がわかりにくくなり、印象も弱くなってしまいます。
「教育実習で児童と接する中で、子どもの成長に関わるやりがいを感じ、教員として責任ある立場で子どもに寄り添いたいと考えるようになりました」
というような文は、一見丁寧ですが長すぎて伝わりづらくなります。
文を区切り、1文1メッセージで書くことを意識することで、簡潔で伝わりやすい志望動機になります。
ありきたりな内容にしない
「子どもが好きだから」「教えることに興味があるから」といった内容だけでは、他の志望者と差別化ができません。
もちろんその気持ちが悪いわけではありませんが、それだけではあなた自身の魅力や本気度が伝わりにくくなってしまいます。
就活コンサルタント木下より

ありきたりな志望動機を避けるためには、自己分析をしっかり行い、自分だけの体験や考えを掘り下げることが大切です。
実際にどんな場面で「教えたい」と感じたのか、なぜその瞬間に気づきがあったのかなど、自分の言葉で語ることが志望動機にオリジナリティを与えます。
○○×○○で考えよう
志望動機をオリジナリティのあるものにするためには、「気持ち」×「具体的な経験」の組み合わせで考える方法が効果的です。
たとえば、「子どもが好き」という気持ちだけでは弱くなりがちですが、「子どもが好き×教育実習で支援した経験」と掛け合わせることで、よりリアルで説得力のある内容になります。
他にも、「教えることが好き×部活動の指導経験」「誰かの力になりたい×不登校の生徒との関わり」など、自分の体験と結びつけることで、深みのある志望動機が完成します。
具体的なエピソードを用いる
説得力のある志望動機にするためには、具体的なエピソードを盛り込むことが重要です。
抽象的な理想や理念だけを語ると、どこか現実味に欠けてしまい、本当に現場を理解しているのか疑問に思われる可能性があります。
たとえば、「子どもと信頼関係を築くことが大切だと考えています」と述べるだけではなく、「実習中に言葉にできない悩みを抱える児童と向き合い、毎日挨拶と声かけを続けたことで、少しずつ笑顔が増えた」という具体的な行動を添えることで、思いや姿勢が伝わりやすくなります。
教育実習・ボランティア経験を志望動機に活かす
教育実習やボランティア活動の経験は、教員を目指すうえで非常に強力なアピール材料となります。
実際の現場で子どもと関わった経験があるということは、教職への理解が深いことの証明にもなるからです。
ただし、単に「実習を経験しました」と伝えるだけでは不十分です。
その経験の中で何を感じ、どんな学びがあったのか、そしてその学びがどのように教員を志望する理由につながったのかまでを語ることが大切です。
自分の考えや行動がどう変わったのかを明確にし、成長や教育への思いを具体的に伝えましょう。
わかりやすい表現を使う
志望動機では、難しい言葉や抽象的な表現を避け、誰にでも伝わるわかりやすい言葉を使うことが大切です。
採用担当者は多くの書類を読むため、一読で内容が伝わる明快さが好印象につながります。
「教員として何をしたいのか」「なぜ教員を目指すのか」を具体的なエピソードや言葉で表現することで、伝わりやすく共感されやすい志望動機になります。
自己PRと一貫性をもたせる
志望動機と自己PRに一貫性があると、あなたの人物像や教育への思いがより明確に伝わります。
たとえば、「子どもに寄り添いたい」という志望動機に対し、「傾聴力が強み」という自己PRが一致していれば、説得力が増します。
バラバラな内容にならないよう、教員を目指す理由と、自分の強みがどう教育現場で活かせるかを結びつけて伝えることが重要です。
教員の自己PRについては以下の記事で詳しく説明しているので是非参考にしてみてください。
【教員の志望動機】基本的な志望動機の構成

教員の志望動機を書く際は、話の流れを意識した構成にすることで、伝わりやすくなります。
特に面接やエントリーシートでは、話の順序や論理の一貫性が非常に重要です。
基本となる構成は「結論 → 根拠 → 今後の展望」の3つ。
この順番を意識することで、簡潔で説得力のある志望動機が完成します。
また、履歴書の書き方・履歴書での志望動機の書き方については以下の記事で詳しく説明しています。
是非参考にしてください。
結論
まず最初に、「なぜ教員になりたいのか」という結論をはっきりと伝えましょう。
冒頭で志望理由を明確にすることで、読み手や聞き手にとって理解しやすく、内容に入りやすくなります。
たとえば、「子ども一人ひとりの可能性を引き出す教育をしたいと思い、教員を志望しました」といった一文を最初に置くと、その後の展開もわかりやすくなります。
最初から結論を伝えることを意識するだけで、全体の印象が大きく変わります。
根拠
次に、自分がなぜその結論に至ったのかを、具体的なエピソードを交えて説明します。
ここでは教育実習、ボランティア活動、学校生活などの経験を活かして、志望理由の裏付けを行いましょう。
「教育実習で学習に苦手意識を持つ児童と向き合い、小さな成功体験を重ねたことで自信をつけていった姿を見て、教えることの喜びとやりがいを感じた」といった具体的な場面を伝えると効果的です。
このように、実際に行動した経験をもとに語ることで、志望動機に説得力が加わります。
今後の展望
最後に、教員になったあとに「どのような教育をしたいのか」「どんな教員を目指したいのか」といった今後の展望を述べましょう。
未来への意欲が伝わる内容は、採用側にとって非常に好印象です。
たとえば、「生徒が自分に自信を持ち、前向きに学べる環境づくりに取り組みたい」といった目標や、「自身のコミュニケーション力を活かして保護者や同僚とも連携しながら指導したい」といった強みの活用も効果的です。
今後のビジョンを示すことで、単なる過去の経験談にとどまらない、前向きな志望動機として伝わります。
志望動機の書き方については以下の記事で詳しく解説しています。
【教員の志望動機】思いつかない場合はどうする?
教員の志望動機がどうしても思いつかないという場合は、無理に言葉をひねり出すのではなく、まずは自分の経験や考え方を丁寧に整理することから始めましょう。
焦らず、次のようなステップを踏むことで、自分らしい志望動機を見つけやすくなります。
過去経験を振り返る
最初に取り組みたいのは、自分の過去の経験を振り返ることです。
就活コンサルタント木下より

「教員を目指すきっかけとなった出来事は何か」「教育に興味を持った瞬間はいつだったか」など、素直な気持ちで思い返してみましょう。
たとえば、部活動で後輩を指導した経験や、教育実習での気づき、学校の先生との思い出などがきっかけになるかもしれません。
その経験から自分が何を感じたのかを言語化することで、自分だけのリアルな志望動機につながります。
理想の教員像を考える
「自分はどんな教員になりたいか」を考えることも、志望動機をつくるうえで有効です。
たとえば、「子どもに安心感を与えられる教員になりたい」「学ぶ楽しさを伝えられる教員になりたい」といった理想を思い描いてみましょう。
その理想像ができたら、なぜそうなりたいのか、どんな経験がそれに影響しているのかを考えていくことで、志望動機の核が固まります。
理想の姿を志望理由に結びつけることで、より一貫性と熱意のある動機になります。
それでも思いつかない場合は以下の記事も参考にしてみてください。
【教員の志望動機】作成した後は、、
志望動機を書き終えたあとは、必ず第三者による添削を受けることをおすすめします。
自分では気づかない言い回しの不自然さや論理の飛躍、伝わりにくい表現が見つかることがあります。
特に教員採用試験では、「教育に対する考え方」や「表現力」も見られているため、文章の構成や言葉の選び方一つで印象が大きく変わります。
教育関係の指導者や就職支援の担当者に見てもらうことで、実際の選考を意識した具体的なアドバイスが得られるでしょう。
【教員の志望動機】よく使われるフレーズ集
教員採用試験の志望動機では、伝わりやすさが非常に重要です。
とはいえ、「わかりやすい表現」と言われても、具体的にどのような言い回しが適しているのか、ピンとこない方も多いでしょう。
ここでは、教員志望動機によく使われる定番のフレーズを紹介します。
自分の考えを言葉にする際の参考として活用してください。
教育への情熱を伝えるフレーズ
「すべての子どもが安心して学べる環境をつくりたい」
「教育の力で地域社会に貢献したい」
「子どもの可能性を信じて、共に成長できる教員になりたい」
教員としての熱意や教育に対する価値観は、志望動機の中心となる要素です。
「すべての子どもが安心して学べる教室づくりを目指したい」や「子どもの可能性を最大限に引き出す教育を実践したい」などの表現は、教育への思いを端的に示す言い回しです。
また、「教育を通じて地域社会に貢献したい」というように、広い視点を取り入れた表現も高評価につながる傾向があります。
ただし、使い回されがちな表現にならないよう、自分の体験とつなげて具体化することが大切です。
子供との関わりを表すフレーズ
「子ども一人ひとりに寄り添い、その成長を支えたい」
「子どもの小さな変化に気づける教員でありたい」
「子どもと信頼関係を築き、共に歩む教育をしたい」
子どもとの関係性をどのように築いていきたいかを伝えることも、志望動機の中で重要な視点です。
「子どもと一緒に成長していける教員を目指している」「一人ひとりの気持ちや変化を丁寧に受け止めたい」といった表現は、寄り添う姿勢を示すうえで有効です。
さらに、「子どもの声を大切にした対話的な授業を行いたい」など、具体的な関わり方に踏み込むことで、現場をイメージした志望動機になります。
経験と結びつけて使えば、説得力が大きく増します。
志望理由を一文でまとめるフレーズ
「私は、教育を通じて子どもたちの未来を拓く教員を目指しています」
「子どもたちの可能性を信じ、共に成長できる教育を実践したいです」
「学ぶことの楽しさを伝えられる教員になりたいと考えています」
志望動機の冒頭や締めには、自分の考えを簡潔に表現する一文を入れると効果的です。
たとえば、「教育を通じて未来を担う子どもたちを支えたい」「子どもの学ぶ力を信じ、成長を後押しする存在になりたい」などのフレーズは、明確な意思表示になります。
こうした一文は、採用担当者の印象に残りやすく、文章全体の主張を強化する役割も果たします。
できるだけ自分の経験や想いから導き出した、オリジナルのフレーズにすることが望ましいです。
【教員の志望動機】面接で意識したほうがいいことは?
教員採用の面接では、熱意と教育への考えを明確に伝えることが重要です。
自信を持ってハキハキと話す姿勢はもちろん、質問の意図を正確に理解し、論理的かつ簡潔に回答するよう心がけましょう。
自身の強みや経験を具体的なエピソードを交えて話せると、説得力が増し、人柄も伝わりやすくなります。
1文は簡潔に話す
面接で話す際は、1文をできるだけ短く、簡潔にすることを意識しましょう。
長い文章は、話している途中で論点がずれたり、聞き手である面接官が内容を理解しづらくなったりする可能性があります。
主語と述語を明確にし、「~ですが、~なので、~」といった接続助詞で長くつなげるのではなく、適度に文を区切ることを心がけてください。
簡潔な話し方は、思考が整理されている印象を与え、自信があるように聞こえる効果もあります。
限られた時間の中で、自分の考えを的確に伝えるために、短く分かりやすい表現を練習しておきましょう。
難しい表現を使わない
面接では、意図的に難しい言葉や専門用語を多用する必要はありません。
もちろん、教育に関する基本的な用語を知っていることは大切ですが、それ以上に、自分の考えや経験を分かりやすく伝えることが重要です。
難しい表現は、かえって意味が伝わりにくくなったり、場合によっては知識をひけらかしているような印象を与えたりする可能性もあります。
面接官に確実に意図を伝えるためには、できるだけ平易な言葉を選び、誰が聞いても理解できるような説明を心がけましょう。
専門用語を使う場合は、相手に伝わっているか配慮することも大切です。
結論ファースト
面接での質問には、まず結論から答えることを強く意識しましょう。
最初に「はい/いいえ」や「〇〇だと考えます」といった結論を明確に述べることで、面接官はあなたが何を伝えたいのかをすぐに把握できます。
その後に、結論に至った理由や具体的なエピソード、補足説明などを続けることで、話の構成が分かりやすくなり、論理的な思考力もアピールできます。
話が冗長になったり、質問の意図からずれた回答をしてしまったりするのを防ぐ効果もあります。
限られた面接時間で最も伝えたいことを確実に伝えるためにも、常に結論から話すことを心がけましょう。
【教員の志望動機】よくある質問
文字数はどれくらいに調整したらいいですか?
指定されていることがほとんどです。
もし、文字数指定がなければ300~400字程度におさめるのがいいとされています。
長すぎず短すぎない文量で書くことを意識しましょう。
志望動機に自信がありません...。
第3者に確認してもらうことをおすすめします。
意外と自分では気づけなかった点をアドバイスしてもらえたり、新たに付け加えたほうがいいことを発見できるでしょう。
まとめ
教員の志望動機を考える際は、「きっかけ」「教員を選んだ理由」「将来の展望」という3つの要素を明確にすることが大切です。
さらに、志望する学校種や教科の特性に合わせて、具体的なエピソードや教育観を盛り込むことで、他の志望者との差別化に繋がります。
完成後は、必ず第三者に添削してもらい、内容の伝わりやすさや説得力を高めることも欠かせません。
丁寧な仕上げが、合格への第一歩になります。


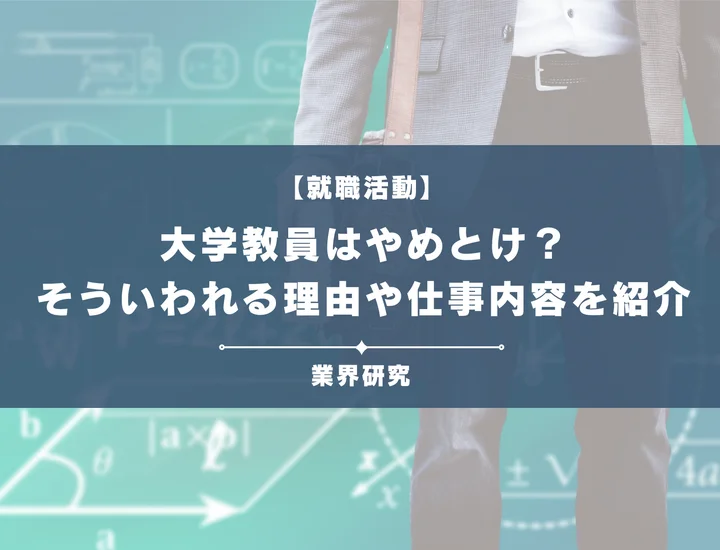

















伊東美奈
(Digmedia監修者/キャリアアドバイザー)
伊東美奈
(Digmedia監修者)
教育実習で得た経験は、教員採用試験の志望動機に説得力を持たせるうえで非常に有効です。
たとえば、生徒との関わりの中で教育の難しさや意義を実感したことや、授業づくりを通じて指導の工夫を学んだことなどは、自分の教育観を語る根拠になります。
ただし、「楽しかった」「やりがいがあった」だけでは説得力に欠けます。
どのような気づきがあり、それが自分の志望にどう影響を与えたのかまでをしっかりと言語化することが、印象に残る志望動機につながります。