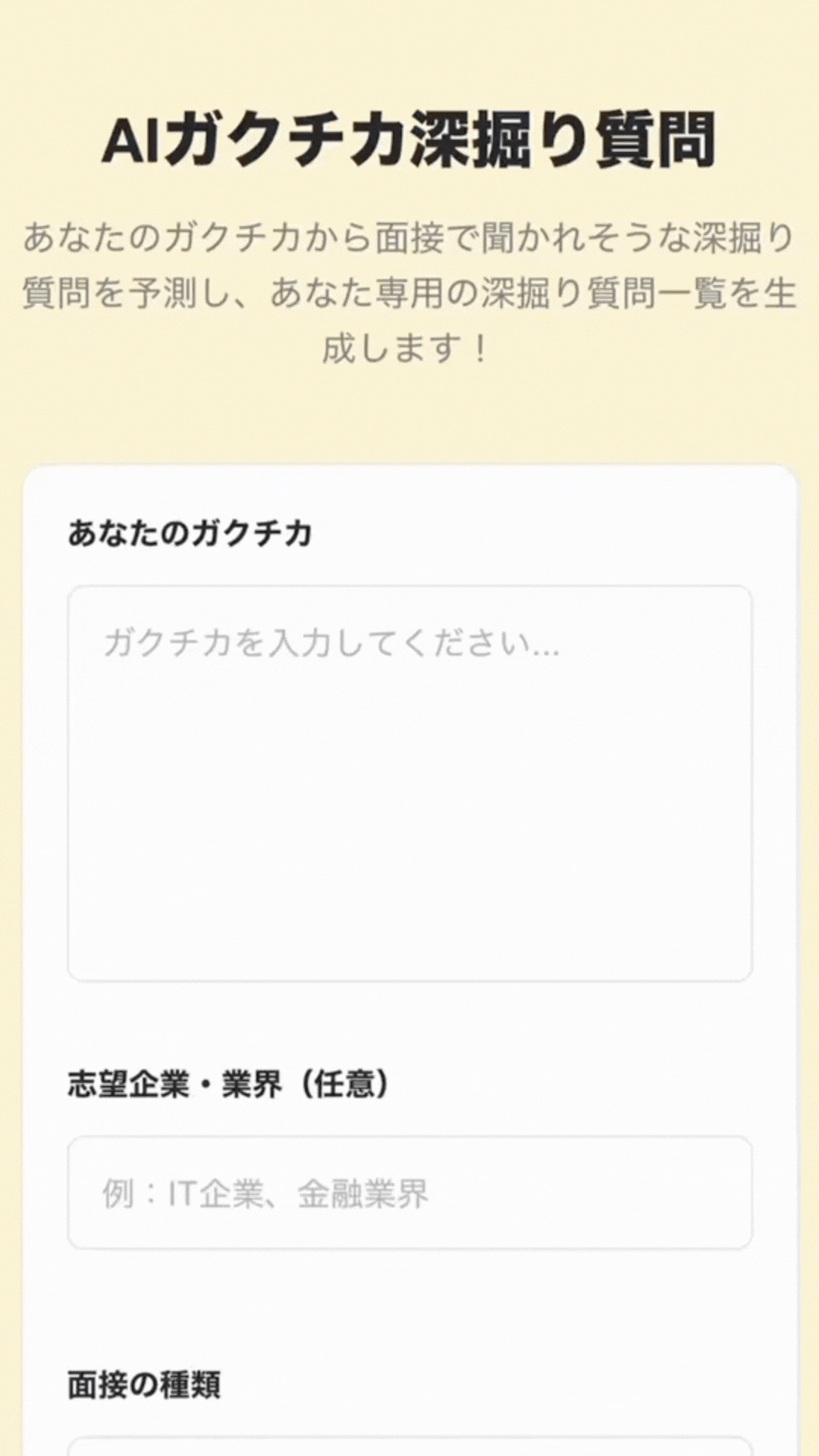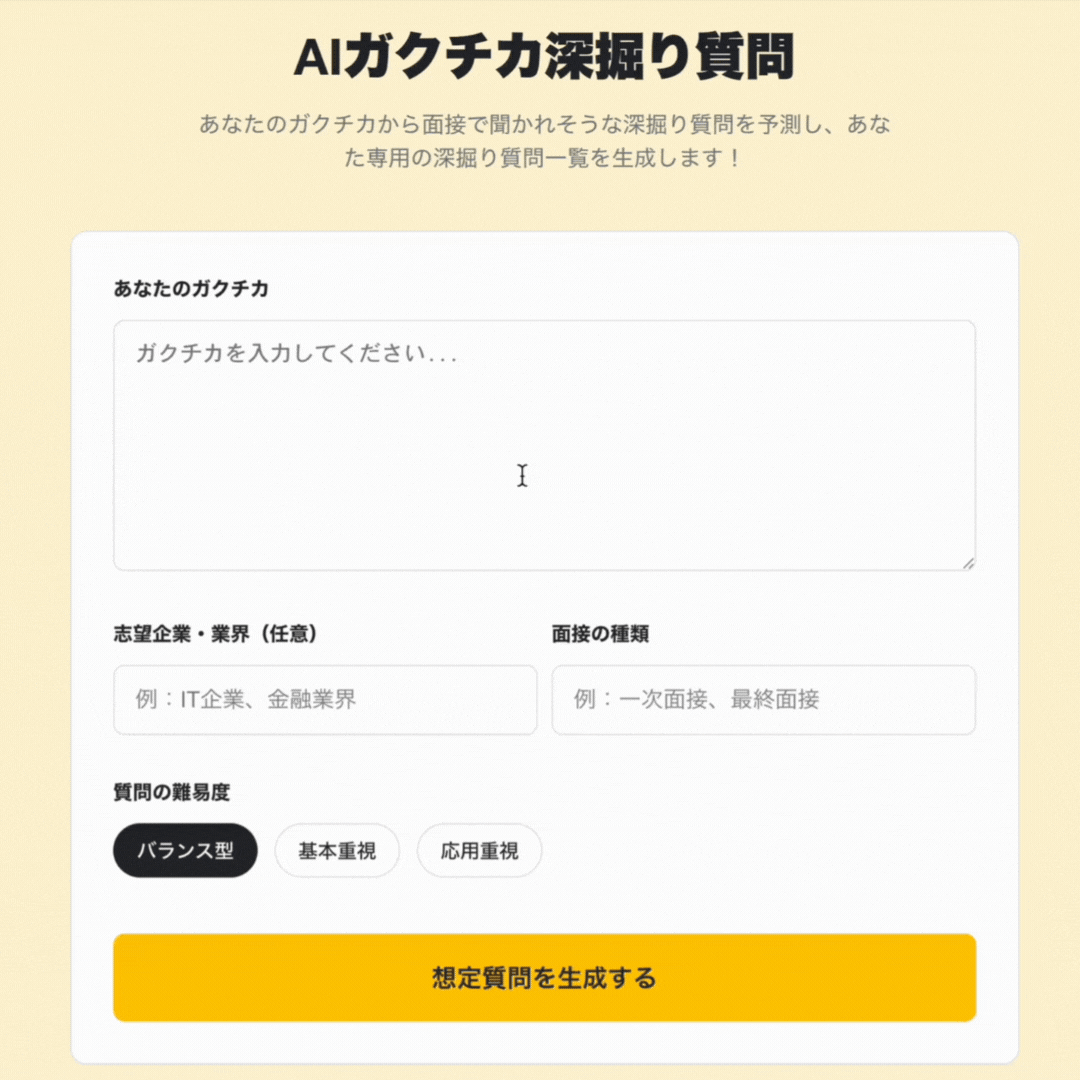HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
面接で「〇〇の経験について、もし当時に戻れるならどうしますか?」と問われ、回答に困ったことはありませんか?
多くの就活生が悩むこの深掘り質問は、あなたの評価を大きく左右する重要なポイントです。
しかし、その意図と正しい答え方さえ知れば、この深掘り質問は「後悔」ではなく「伸びしろ」をアピールする絶好のチャンスに変わります。
本記事では、面接官の心に響く回答の型と、すぐに使える具体的な回答例文を解説します。
NEW!!『あなたのガクチカ』に対する深掘り質問生成ツール【完全無料】
ガクチカの深掘り対策を徹底して行いたい就活生必見!
この度、DigmediaからAIの最新ツールとして、「AIガクチカ深掘り質問ツール」をリリースいたしました。
「あなたのガクチカ」に特化した面接での想定質問を最低でも15個以上生成できます。
完全無料で利用できるため、ぜひ、ガクチカの対策に活用してみてください!
ガクチカで「当時に戻れるなら?」|頻出の深掘り質問
ガクチカに関する一連の質疑応答の終盤、「もし当時に戻れるならどうしますか?」と問われるのは、面接における頻出パターンです。
「改善点はありますか」という形で聞かれることもありますが、本質は同じです。
これは、あなたの行動の粗探しをするための質問ではありません。
むしろ、この回答からあなたのポテンシャルを多角的に見極めようとしています。
したがって、準備の有無が評価に直結し、他の就活生と差がつく重要な質問であると認識しておく必要があります。
ガクチカで「当時に戻れるなら?」|面接官の意図3つ
この一見、過去を問うような質問には、就活生の未来のポテンシャルを測るための明確な意図があります。
面接官は、あなたの回答から単なる反省点を聞きたいのではありません。
その回答を通して、入社後に活躍できる人材かどうかを見極めようとしています。
具体的には、これから解説する「課題発見力」「客観性」「成長意欲」の3つの能力を評価しています。
これらの能力は、業種や職種を問わず、あらゆるビジネスシーンで求められる重要な素養です。
質問の裏にある意図を正しく理解し、的確なアピールにつなげましょう。
1. 課題発見力
企業は、与えられた業務をこなすだけでなく、現状をより良くするために自ら課題を見つけ、改善を提案できる人材を求めています。
面接官は、「もし戻れるなら」という問いに対し、あなたが過去の経験を具体的に分析し、「何が問題だったのか」「どうすればもっと良い結果を出せたのか」を論理的に説明できるかを見ています。
単に「もっと頑張ればよかった」という精神論ではなく、「〇〇という視点が欠けていたため、次は△△というアプローチを試みたい」のように、論理的な改善策を提示できる思考力が、入社後の業務における問題解決能力の証明となります。
2. 客観性
自身の経験、特に成功体験を語る際、人は主観的になりがちです。
面接官は、あなたが自身の行動や成果を過大評価することなく、冷静かつ客観的に振り返ることができるかを確認しています。
自分の行動の「限界」や「考慮できていなかった点」を素直に認められる謙虚さは、他者からのフィードバックを素直に受け入れられる素質の表れです。
また、物事がうまくいかなかった原因を環境や他人のせいにするのではなく、「自身の〇〇という点に改善の余地があった」と当事者意識を持って語れるかどうかも重要です。
この客観性は、チームで協働する上で不可欠な能力と判断されます。
3. 成長意欲
3つの意図の中で、面接官が最も重視しているのがこの「成長意欲」です。
企業は完成された人材ではなく、入社後に自ら学び、成長し続けてくれる「伸びしろ」のある人材を求めています。
この質問は、過去の経験から得た学びや反省を、未来にどう活かそうとしているか、その意志の強さを測るためのものです。
「この経験での反省を活かし、御社では〇〇という形で貢献したい」というように、未来志向の姿勢を示すことができれば、「失敗から学び、次へと繋げられる人材」として高く評価されます。
過去の反省が、未来への成長の糧になっていることを明確に伝えましょう。
ガクチカで「当時に戻れるなら?」|NG回答パターン3選
面接官の意図を理解していても、伝え方を誤ると評価を大きく下げてしまう可能性があります。
良かれと思って発した言葉が、意図せずネガティブな印象を与えてしまうことは少なくありません。
ここでは、就活生が陥りがちな代表的なNG回答パターンを3つ紹介します。
これらの失敗例を事前に把握し、自身の回答が該当しないか客観的に見直すことが、面接の選考通過率を上げるポイントになります。
1.「特にありません」
「やりきったので後悔は特にありません」という回答は、自信の表れのようで、実は最も避けるべき回答です。
これは、面接官に「自己分析ができていない」「成長意欲がない」と判断される典型的なパターンです。
面接官は、完璧な経験など存在しないという前提で質問しています。
そのためこの回答は、自身の行動を客観的に振り返ることを放棄した「思考停止」の状態と見なされてしまいます。
どんなに素晴らしい成果を上げた経験であっても、必ず改善点や別の選択肢は存在するはずです。
その探求する姿勢そのものが、あなたの伸びしろとして評価されます。
「特にない」と一言で思考を終えるのではなく、より良くするための視点を探し続ける謙虚な姿勢を示しましょう。
2.「もっと〇〇すればよかったです」
「もっとコミュニケーションを取ればよかったです」「もっと準備すればよかったです」といった、具体性のない反省で終わってしまうのも避けるべきです。
一見、反省しているように聞こえますが、これでは思考の浅さを露呈してしまいます。
面接官が知りたいのは、精神論や抽象的な後悔ではありません。
「なぜコミュニケーションが不足したのか」「具体的にどのように準備すればよかったのか」という、課題の構造を分析する力です。
この回答で止まってしまうと、次に同じ状況に陥っても改善できない、再現性のない人材だと判断されかねません。
「何を」すべきだったかに加え、「なぜ」「どのように」という具体的なアクションプランまで言及することが不可欠です。
3.「周囲の人が〇〇だったため〜」
「メンバーの意欲が低かったため、うまく進みませんでした」「〇〇という環境の制約があったため、あれが限界でした」など、うまくいかなかった原因を自分以外の他者や環境に求めるのは、避けてほしい回答パターンです。
この回答は、「他責思考」で「当事者意識が欠如している」という極めてネガティブな印象を与えます。
企業は、困難な状況に直面した際、それを乗り越えるために自らが主体的に動ける人材を求めています。
たとえ事実であったとしても、それを他者のせいにして語るべきではありません。
「その制約の中で、自分には何ができたか」という視点に切り替え、自身の行動に焦点を当てて語る姿勢が、社会人として必須の素養と評価されます。
ガクチカで「当時に戻れるなら?」|面接官が好む回答のフレームワーク
NG回答を避け、面接官の意図に的確に応えるためには、思考を整理するための型を知っておくといいでしょう。
これから紹介する4ステップのフレームワークは、誰でも論理的で説得力のある回答を作成できるように設計されています。
この流れに沿って自身の経験を当てはめることで、あなたのポテンシャルを最大限にアピールする回答を作成できます。
ぜひ、ご自身の回答作りの参考にしてください。
Step1. 経験の肯定
まず、いきなり反省点から話すことは避けるべきです。
ガクチカの経験全体がネガティブな印象になりかねません。
最初に、その経験自体が自身にとって価値あるものであり、成長の機会であったことを明確に伝えましょう。
「この〇〇という経験を通じて、△△という強みを身につけることができ、大変有意義な時間だったと考えております」といった形で、まず簡潔に成果や学びを述べます。
この肯定的な前置きがあることで、あなたに自己分析力と経験から学ぶ姿勢があることを示せます。
そして、この土台があるからこそ、次に続く課題の指摘が「後ろ向きな後悔」ではなく、「さらなる成長を目指す前向きな振り返り」として、面接官に好意的に受け止められるのです。
Step2. 課題の特定
経験を肯定した上で、「しかし、現在の視点から当経験を振り返ると、一点改善できたと感じる部分がございます」と、本題に繋げます。
ここで重要なのは、NG例のような抽象的な反省ではなく、課題を具体的に特定し、客観的に分析する姿勢です。
例えば「チームの連携不足」で終わらせず、「各担当者の進捗状況をリアルタイムで共有する仕組みがなかったため、作業の重複や手戻りが発生していた点です」のように、課題の構造を明確に言語化します。
なぜそれが課題だと考えたのか、その背景まで簡潔に説明できると、自身の行動を冷静に分析できる課題発見能力の高さをアピールできます。
Step3. 具体的な改善策
特定した課題に対し、「もし当時に戻れるのであれば、私は〇〇という行動を取ります」と、具体的な改善策を提示します。
ここでのポイントは、誰が聞いても行動をイメージできるレベルまで具体的に語ることです。
「もっとコミュニケーションを取る」ではなく、「週に一度15分の定例ミーティングを設定し、全員が発言する機会を設けることで、情報格差の解消を図ります」のように、具体的な施策を述べます。
なぜその改善策が有効だと考えるのか、その理由も添えることで、あなたの思考の深さを示すことができます。
この具体的な改善策は、課題解決能力の高さを証明し、面接官に「入社後も活躍してくれそうだ」という再現性を期待させる上で極めて重要です。
Step4. 入社後の応用
回答の締めくくりとして、過去の経験から得た「教訓」を、入社後における自身の「行動指針」として提示します。
「御社に入社後は、どのような業務においても目先の成果を過信することなく、常にもっと良くするためには何ができるか、という主体性と当事者意識を持って取り組んでいきたいと考えております。」
のように、過去の反省を未来の行動指針へと繋げることで、あなたの「謙虚に学び、成長し続ける力」を魅力的にアピールし、入社後に活躍する姿を面接官に具体的にイメージさせることができます。
ガクチカで「当時に戻れるなら?」|経験別回答例文5選
これまで解説してきたフレームワークを、実際の回答にどう落とし込むのかを、具体的な経験別の回答例文を5つ紹介します。
これらの例文は、上記で解説した「経験の肯定」から「入社後の応用」までの4ステップで構成されています。
ご自身の経験に最も近いものを参考にご活用ください。
回答例1. サークルでのイベント企画
イベント企画リーダーとしてチームをまとめ、目標を達成した経験は、主体性を学ぶ貴重な機会でした。
しかし、私がタスクを抱え込みすぎ、一部メンバーの当事者意識が薄れてしまった点が課題であったと分析しております。
もし戻れるなら、各メンバーに明確な役割と裁量権を与え、週次で進捗共有会を開き、チーム全体の力を最大化します。
この経験から、御社でも個の力だけでなく、チーム全体の成果を意識し、周囲を巻き込みながら業務を進めたいと考えております。
回答例2. 居酒屋でのアルバイト経験
居酒屋のアルバイトでお客様に合わせた接客を工夫し、店舗の売上向上に貢献できた経験は自信になっています。
しかし、自身のスキルに頼る部分が多く、店舗全体のサービス品質に波があった点が課題でした。
もし当時に戻れるのであれば、自身の成功事例をマニュアルとして言語化し、他のスタッフと共有する勉強会を自主的に開催します。
この経験から、御社でも属人的な成果に満足せず、組織全体の生産性向上に貢献できる視点を持ちたいです。
回答例3. ゼミの卒業論文
卒業論文の執筆を通じ、未知のテーマに対し粘り強く情報を収集し、論理的に構造化する力を養えました。
しかし、当初の計画に固執するあまり、研究途中で見つかった新たな論点を深掘りできなかった点が反省点です。
もし戻れるなら、定期的に教授や仲間と議論の場を設け、多角的な視点を取り入れながら計画を柔軟に見直します。
この反省から、御社でも計画遂行力だけでなく、状況変化に柔軟に対応する姿勢を持って業務に取り組みたいです。
回答例4. 塾講師のアルバイト経験
塾講師として生徒一人ひとりと向き合い、成績向上に貢献できたことで、目標達成を支援する喜びを学びました。
しかし、担当生徒の成績を上げることに集中するあまり、保護者の方への状況報告が不足し、ご心配をおかけした点が課題でした。
もし戻れるなら、月に一度は必ず保護者の方との三者面談の機会を設け、指導方針と進捗を密に共有します。
この経験から、御社でも顧客との関係構築において、こまめな報告・連絡・相談を徹底したいです。
回答例5. 留学のアルバイト経験
留学先でのカフェのアルバイトを通じ、多様な文化背景を持つ同僚と協働する中で、柔軟なコミュニケーション能力を培いました。
しかし、当初は文化の違いに戸惑い、自分の意見を主張するのを遠慮してしまった点が反省点です。
もし戻れるのであれば、不明点は即座に質問し、背景にある文化の違いを理解した上で、積極的に自分の考えを発信していきます。
この反省から、御社でも多様な価値観を尊重しつつ、臆することなく自分の意見を発信する主体性を持ちたいです。
まとめ
面接での「もしガクチカ当時に戻れるなら?」という質問は、過去の後悔を問うものではなく、あなたの未来への成長意欲を測るためのものです。
本記事で紹介したフレームワークを活用すれば、自身の経験から得た学びを「伸びしろ」として効果的にアピールできます。
反省点があるということは、あなたがそれだけ成長した証です。
この質問を自分を売り込む絶好の機会と捉え、自信を持って面接に臨んでください。
あなたの就職活動が実りあるものになることを、心より応援しております。