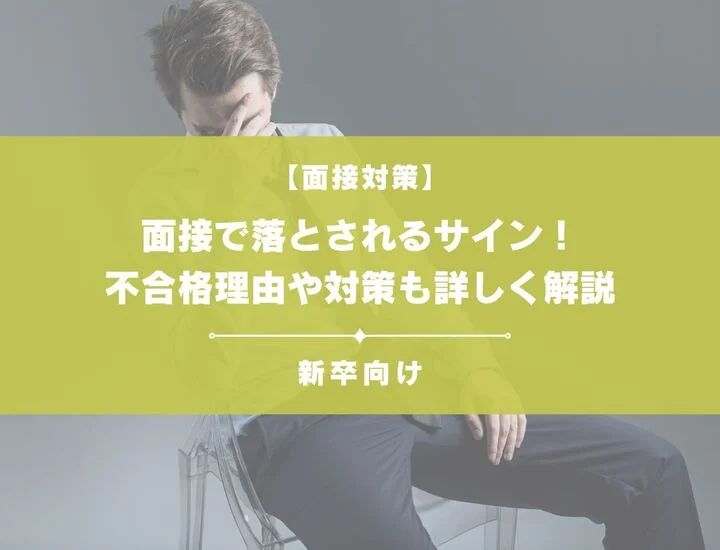HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
グループディスカッションとは
グループディスカッションは就職活動の選考プロセスの一環で、参加者が特定のテーマについて議論する方法です。
この方法で企業は、時間制限の中、与えられたお題に対して複数人で議論するプロセスと、そのお題の解という結果に対して評価をします。
グループディスカッションで用いられるテーマは具体的なビジネス課題から抽象的なシナリオまで様々です。
「デパートの売上向上策」のような実践的な問題や、「無人島に持っていく一つのものは?」といった思考力を問う問題が出されます。
また、グループディスカッションには複数の形式があり、どの形式でディスカッションをするかで進め方や意識すべきポイントが異なるので十分理解した上で選考に臨みましょう。
グループディスカッションとグループワークの違い
グループディスカッションと似た言葉でグループワークという選考方法があります。
それぞれの違いは、主に目的と成果物にあります。
グループディスカッションは主に議論や意見交換に焦点を当てており、与えられたテーマについての知識や意見を共有する場です。
これに対し、グループワークは具体的な成果物やプロジェクトの完成を目指す活動であり、実作業やタスクの遂行が含まれます。
グループワークでは、最終的なアウトプットの質が評価され、参加者の実行能力や創造性が重視されます。
グループワークとグループディスカッションで企業から評価されるポイントが違ってくるので注意しましょう。
グループディスカッションの種類
グループディスカッションには、フェルミ推定型、課題解決型、ディベート型、選択型、自由討論型の5種類の形式があります。
どの形式を用いるかによって、進め方や企業の評価ポイントが異なるので、十分に理解しておくとよいでしょう。
各形式の説明とテーマ例をご紹介していきます。
フェルミ推定型
フェルミ推定型のグループディスカッションでは、具体的なデータや情報がない状況下で論理的な推測と計算によって答えを導き出す形式です。
このタイプのディスカッションは、参加者の論理的思考能力、問題分解能力、および協働して推定を行う能力が試されます。
問題を分解して考え、既知の情報や一般的な知識から推測を立て、参加者と情報を共有し、協同して最終的な結論を導き出しましょう。
フェルミ推定型のテーマ例
・東京のコーヒーショップの数はいくつか
・1日に東京駅を通る人の数は
・大学のカフェテリアで1日に売られるサンドイッチの数は
・平日に空港を利用する乗客の数はどれくらいか
・ある都市の公共交通機関を1日に利用する人数は
課題解決型
課題解決型グループディスカッションは、参加者が与えられた課題に対して共同で解決策を導き出す形式です。
この形式のテーマは、実際にビジネスや日常生活で遭遇するような実用的な課題が提示されるため、改善策を考えるには少々難易度が高いことが特徴です。
しかし、問題をしっかりと理解すること、多くのアイデアを出し、その中から様々な視点を考慮することができれば、現実的で効果的な解決策を選び出すことができます。
課題解決型のテーマ例
・カフェのランチタイムの売上をあげるには
・社内イベントの参加率を高めるには
・学生向け割引プランの効果的な広告戦略
・市内の交通渋滞を減らすには
・若年層の政治参加を増やすには
ディベート型
ディベート型グループディスカッションは、あるテーマについて賛成と反対など、異なる意見をもった2つのチームに分かれて討論する形式です。
この形式では、主に論理的思考力、説得力、協調性が評価されます。
ディスカッションを成功させるには、明確な論点を用意すること、相手の意見を尊重しながら論理的に反論し、チーム内での意見の調和を図ることが重要です。
そして時間内にポイントを的確に伝える能力が求められます。
ディベート型のテーマ例
・在宅勤務とオフィス勤務はどちらが生産性が高いか
・AIの進化は人間の雇用にとって脅威か否か
・職場でのドレスコードは必要か否か
・対面での面接とリモートでの面接はどちらが有利か
・未成年の投票権を18歳から16歳に引き下げるべきか否か
選択型
選択型グループディスカッションは、参加者が複数の選択肢から最適な解決策を選択する形式です。
この形式では、情報を正確に把握し、それぞれの選択肢の利点と欠点を論理的に分析することが重要です。
また、グループ内で意見を共有し、他のメンバーの視点を尊重しながら、最も合理的な選択肢について討論を深めていきます。
最終的な決定を行う際には、グループとしての合意形成を目指し、全員が納得のいく結果を導き出すことがカギとなります。
選択型のテーマ例
・社員福利厚生プログラムに新たに導入すべきサービスとは
・会社全体の残業時間を低減するために推進すべきプロジェクトはどれか
・日本企業のデジタル化を推進するために優先すべき技術投資はどれか
・駅前のカフェの売上を伸ばすためのアプローチとして最適な戦略はどれか
自由討論型
自由討論型グループディスカッションは、特定の正解が存在しない開かれたテーマに基づき、参加者が自由に意見を交換する形式です。
この形式でディスカッションを行う目的は、創造的思考や多様な視点を刺激し、参加者の発想力と議論スキルをみるためです。
コツとしては、柔軟な思考を持ち、他の意見に対してもオープンであることが重要です。
また、自分の意見だけでなく他者のアイデアにも耳を傾け、それに基づいて新たな視点を提案することが評価の対象となります。
自由討論型のテーマ例
・学校制服の必要性について
・SNSが社会に与える影響について
・年間休日数を増やすことの利点と欠点について
・ゲームのプレイ時間に親が介入すべきか
・オンライン学習の長所と短所について
グループディスカッションで見られていること
グループディスカッションでは、意欲や協調性、コミュニケーション能力、状況に応じた適切な立ち回り、論理的な思考、そして創造的な発想力をもっているかが見られています。
これらはチームで協同してディスカッションする上で不可欠な要素であり、個々の対応能力も重要視されます。
各項目のポイントを押さえたうえで臨めるとより通過率があがるでしょう。
意欲
採用担当者は、応募者がディスカッションにどれだけ積極的に参加し、自発的に貢献しようとするかを注意深く観察します。
具体的には、課題に対する積極的なアプローチ、議論をリードしようとする姿勢、新しいアイデアや解決策を提案する頻度などが評価されます。
また、他の参加者の意見に興味を持ち、関連する質問をすることも、高い意欲の表れと見なされます。
このように、意欲を示すことは、応募者が仕事に対しても同様の熱意を持って取り組む可能性が高いと評価されるため、採用の重要な判断基準となります。
協調性
グループディスカッションでは、応募者が他のメンバーとどのように作業を進めるかが評価の対象になります。
採用担当者は、応募者が他の参加者の意見をどれだけ尊重し、建設的なフィードバックを提供できるか、また意見の相違がある場合にどのように妥協点を見つけるかを見ています。
さらに、グループ内での助け合いの態度も協調性の重要なポイントです。
効果的なコミュニケーションスキルと他者との関係構築能力は、職場でのチームワークを円滑にし、プロジェクトの成功に貢献するため、非常に価値のある特性です。
コミュニケーション能力
採用担当者は、応募者がいかに効果的に意見を表現し、他のメンバーと情報を交換できるかをみています。
評価ポイントには、明確かつ簡潔にアイデアを伝える能力、適切なリスニングスキル、そして議論を前進させるための質問や意見の提示が含まれます。
また、非言語的コミュニケーションも重視され、身振り手振り、目のコンタクト、表情がポジティブな対話を促進しているかどうかも重要視されます。
これらのスキルは、職場でのチームワーク、プロジェクト管理、顧客との対話など、多方面での成功に直結するため、採用プロセスにおいて高く評価されます。
立ち回り
採用担当者は、応募者が議論の流れの中でどのように自己を位置付け、チームにどのような影響を与えるかみています。
重要なのは、適切なタイミングで意見を述べ、他の意見に対して建設的なフィードバックを提供することです。
また、チーム内で意見の衝突が起こった時にどのように対処し、グループを一致団結させるかも重要な評価ポイントとなります。
立ち回りが上手い応募者は、状況を正確に読み取り、柔軟に対応することができ、これが組織内での協働や問題解決能力に直結します。
論理性
論理性とは、グループディスカッション中に応募者が示す思考の整合性と理由づけの能力を指します。
採用担当者は、応募者が問題を分析し、その情報を基にどのように論点を組み立て、合理的な結論に至るかを評価します。
具体的には、提案されたアイデアが事実やデータに基づいているか、また、その思考過程が一貫しているかが見られています。
また、応募者が議論の中で論理的に意見を展開し、反対意見に対しても理由をもって応じることができるかも評価のポイントになります。
発想力
発想力は、応募者が既存の枠組みを超えて新しいアイデアを提案する能力です。
採用担当者は、グループディスカッションで応募者がどれだけ創造的で独創的な解決策を思いつくかを注目します。
これには、一見関連のない概念を組み合わせてユニークな提案をする能力や、新しい視点から問題を見直す柔軟性が求められます。
また、応募者がどれだけ速やかに新しいアイデアを提案し、他のメンバーからのフィードバックを取り入れてアイデアを進化させるかも評価の対象です。
グループディスカッションの流れ
グループディスカッションは通常、テーマが発表されたあと、役割分担決め、テーマに関する議論、結論のまとめ、最終発表の順で進行します。
時間管理と効率的な議論が求められ、各段階で応募者がどのように貢献しているかが評価されます。
役割を決める
ディスカッションを効率的かつ効果的に進行させるためです。
役割を明確にすることで、各参加者が特定の責任を持ち、その役割に応じて特技やスキルを活かすことができます。
例えば、司会進行は議論を円滑に進める責任があり、書記は議論の内容を正確に記録し、タイムキーパーは時間管理を行います。
発表者はグループの結論を整理し、プレゼンテーションを担当します。
これにより、グループ全体の協調性と生産性が向上し、各参加者のコミュニケーション能力や協働能力を適切に評価することが可能になります。
司会進行
司会進行はグループディスカッションを円滑に進めるためのキーパーソンです。
議論の開始、進行、終了のタイミングを管理し、話題がテーマから逸れないように指導します。
また、全ての参加者が意見を言いやすい環境を作り、活発な議論を促進する役割も担います。
書記
書記はグループディスカッションでの議論内容を正確に記録する役割を持ちます。
議論の要点、合意点、異論など、ディスカッションの進行に関する全ての重要な情報を詳細にノートに取り、議論の内容を正確にまとめることが求められます。
タイムキーパー
タイムキーパーは、グループディスカッションの時間管理を担当します。
各セクションの時間を厳守し、時間内に討論が終了するように注意を促します。
この役割は、効率的な時間の使用を保証し、討論が定められた枠内で完結することを確認するためにとても重要な役割です。
発表者
発表者は、グループディスカッションの結果をまとめ、最終的に全体に向けてプレゼンテーションを行います。
この役割では、グループの意見を明確に伝え、効果的にプレゼンテーションする能力が求められます。
また、質問に対しても適切に回答することが期待されます。
役職なし
役職なしの参加者は、特定の役割に縛られず、議論に自由に参加します。
この立場から、様々な角度から意見を提供し、議論を豊かにすることができます。
また、状況に応じて積極的に発言し、グループ内の活動を支援することも重要な役割です。
時間を決める
役割決めが終わったら次は時間を決めます。
これは議論を効率的に進め、すべての参加者に公平な発言機会を与えるために必要不可欠です。
さらに、明確な時間枠があることで、参加者は議題の本質から逸脱することなく、焦点を維持しやすくなります。
限られた時間内で有効に議論を進めるには、最初に全体のタイムスケジュールと各セクションの目標を明確に定めるとよいでしょう。
議論する
役割と時間が決まったら、チーム内で議論を始めます。
ここで重要なのは、自身の意見を示すことと、他の参加者の意見に耳を傾け、尊重する態度を心がけることです。
参加者はそれぞれ異なるバックグラウンドや価値観を持っているはずです。
全員が発言することによって、新たな気づきやヒントが得られ、広い視野で物事を考えることができるので、積極的に意見を述べ、他の参加者の意見も取り入れていきましょう。
発表する
議論のあとは発表にうつります。
簡潔に要点をまとめて明確に伝えること、重要なポイントを強調し、時間内に発表を終えることを心がけましょう。
発表はグループ全体の成果として、チームの一体感を前面に出しながら、可能であれば、視覚敵にみせられる資料やスライドを活用することで聞いている人の理解も深まります。
また、発表後の質疑応答にも対応できるように、事前に質問を予測し、適切な回答を準備しておくと良いでしょう。
グループディスカッションのコツ
効果的なグループディスカッションを行うためには、明確な意見を持ちつつ、他者の意見に対してもオープンであることが重要です。
そして自分に与えられた役割に責任を持ち、また、自分だけ目立とうとせず、他者と協力して結論を導き出すことが成功の鍵です。
自分に合った役割を理解する
グループディスカッションでは、自分の強みを活かせる役割を選ぶことが重要です。
例えば、話すことが得意な人は発表者、細かいことに注意を払える人は議事録を書くのに向いています。
自分の性格やスキルセットを正しく理解し、チームのニーズに合わせて最適な役割を選択することで、自己効力感も高まり、ディスカッションの全体的な成果に寄与できます。
また、役割を理解し、それに応じて準備をしておくことで、自信を持ってディスカッションに臨むことができます。
相手の話をしっかり聞く
効果的なディスカッションを行うためには、相手の話を注意深く聞くことが大切です。
これにより、理解が深まり、より建設的なフィードバックや意見を提供することができます。
相手の言葉だけでなく、身振りや手ぶりにも注目し、相手が本当に伝えたいことを汲み取る努力をすることが大切です。
また、相手が話している間は、適切なうなずきや目のコンタクトで反応を示すことで、対話の質を高めることができます。
明るくふるまうこと
ポジティブな態度はグループディスカッションの雰囲気を大きく左右します。
明るく前向きな態度を持つことで、他の参加者も積極的に話しやすくなり、グループ全体の雰囲気もよくなります。
また、明るい表情や積極的な姿勢は、自分自身にもポジティブな影響を与え、自信を持って発言することができるようになります。
難しい議論や緊張が走る場面でも、冷静かつ楽観的に対処することで、効果的な解決策につながる場合があります。
まとめ
以上、今回は就活の選考においてよくあるグループディスカッションについて人事がどういった点をみているのかということや、書き方のコツを解説してきました。
ただ漫然とグループディスカッションに臨むのではなく、人事の視点や、そもそもどんな種類の議論形式があるのか事前に把握しておくだけでも、かなり違いが出てきます。
是非この記事を参考にしてしっかりと準備をし、本番で自信を持って振舞えるようにしましょう。