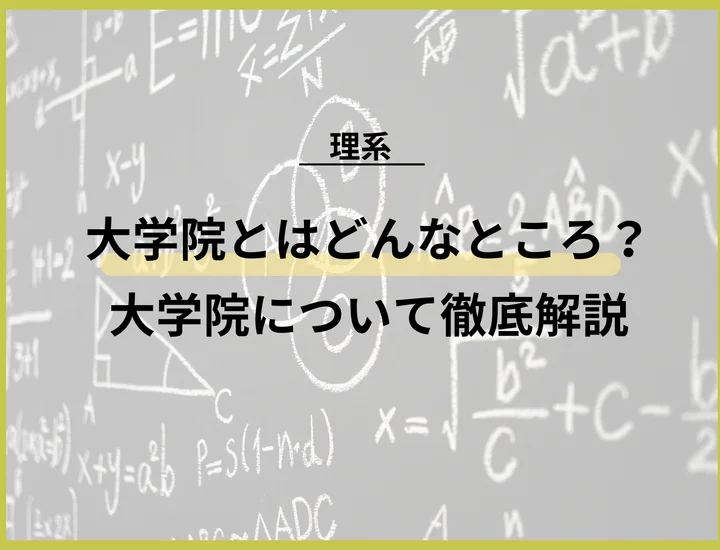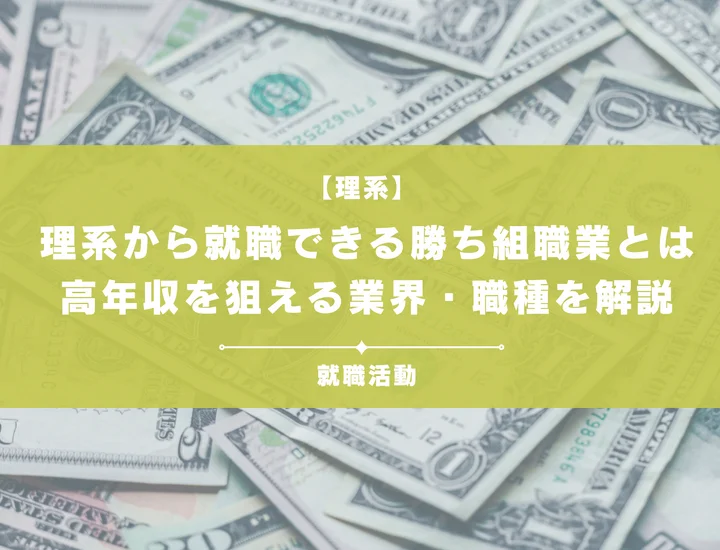HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
はじめに
大学は、高校卒業もしくはそれに準じる資格を持った人が受験をして合格すると入学できる最高学府です。
それでは、大学院とはどういうところでしょうか。
大学院は、大学を卒業またはその大学院が認めた人が入学できるので、大学を卒業しなくても入学することが可能です。
大学院は、大学で培った知識や理論をさらに深く研究するところなので、ずっと研究を続けたい人や教授を目指す人が行くところというイメージですが、理系に関しては、専門的な知識を身につけたほうが就職に有利という側面もあります。
大学院は、専門的な勉強をして「修士号」や「博士号」を取得する場所と思われていますが、本当は、どのような場所なのでしょうか。
【大学院に入るには】大学院への進学方法は?
 大学院への進学方法は、それぞれですが、主に3つの試験方法があります。
大学院への進学方法は、それぞれですが、主に3つの試験方法があります。
・一般入試 大学卒業見込みもしくは、大学を卒業した人が受けられる試験です。
一般的な試験は、外国語と専門科目の筆記、書類審査、面接となっています。
・社会人入試 名前の通り、一度社会人を経験した人が受けられる入試方法です。
大学院によって多少の試験内容は異なりますが、基本的に研究知識や研究に対する熱意などが判定基準となります。
・AO入試 書類審査と面接で合否が決まります。
・推薦入試 基本的に、通っている大学の大学院に進学するときの入試方法で、大学の成績によって合否が決まりますが、他大学からの推薦でも入試ができる場合もあります。
このように、指定されている入試方法に違いがあるので、気になる大学院がある場合は、ホームページなどで確認してみると良いでしょう。
【大学院に入るには】大学院進学率は?
1990年代は、「大学教員・研究者のみならず社会の多方面で活躍する人材育成のため、大学院を現在の2倍程度拡大する」という提言が出されたため、大学院を設置する大学が増え、大学院生数も2.1倍に増加しました。
この傾向は、2005年まで続きましたが、「各大学における大学院と学部の量的な構成は、各大学の責任において検討すべき」とし、量的な整備目標がなくなったため、2011年をピークに院生の数は減少しました。
2011年にピークを迎えた原因は、リーマンショックによる雇用情勢の悪化で、就職活動を先送りする学生が増えたためと考えられています。
その後の進学率は減っていますが、2019年の「学校基本調査」によると、同年3月の大学卒業者485,613名に対して大学院へ進学した人は、58,782名なので、全体の約12%が進学していることになるのです。
このことから、8人のうち1人が進学して、残りの7人は、ほかの進路を選択したことがわかります。
大学院進学率はおよそ4割
大学院への進学率は、全体で12%程度ですが、理系に限っていえば、約4割の人が進学しています。
理学・工学・農学の卒業生107,803人に対して大学院へ進んだ人は、42,841人ですが、この中の31,711人が工学系学部の卒業生となっているのです。
このことから、理系の大学院進学率が高いことがわかります。
特に、京都大学では87.2%、東京工業大学86.2%、東京大学85.1%など、上位大学に限っていえば、9割近い人が進学を決めています。
【大学院に入るには】どれくらいの費用がかかるの?
大学院進学を考える際、多くの人が最初に気になるのは費用面です。
学費だけでなく、生活費や研究活動にかかる費用まで含めると、全体の負担は想像以上に大きくなることがあります。
また、国立と私立では学費の差が大きく、専攻する分野によっても必要な金額は変わります。
進学前に全体像を把握しておくことが、安心して学びに専念するための第一歩です。
学費
大学院の学費は、国立か私立か、そして専攻分野によって大きく異なります。
国立大学大学院では入学金が約28万円、授業料は年間約54万円で、2年間の合計は130万円から140万円程度が目安です。
学部時代とほぼ同等か、やや安い場合もあります。
私立大学大学院では入学金が20万円から30万円、授業料は年間70万円から150万円ほどかかります。
理系分野では実験や設備にかかる費用が加わるため、文系よりも高額になりやすく、2年間で200万円を超えるケースもあります。
これらの金額はあくまで目安であり、大学や専攻によって差があります。
実際の費用は各大学の公式情報を確認して正確に把握しておくことが大切です。
生活費
学費に加えて、大学院生活には生活費が必要です。
一人暮らしをする場合、家賃、食費、交通費、光熱費などを合わせて月10万円から15万円程度が目安です。
地域や住環境によって差はありますが、都市部では特に家賃が高くなる傾向があります。
さらに、研究活動に必要な書籍や消耗品、学会発表や出張に伴う交通費や宿泊費も発生します。
これらは年間で数十万円単位になることもあります。
進学前に生活費と研究費の両方を見積もり、必要に応じて貯蓄や奨学金で補う計画を立てることが重要です。
奨学金や研究補助金
大学院進学にかかる経済的な負担を減らすために、奨学金や研究補助金の制度があります。
日本学生支援機構では、返還義務のある貸与型と、返還不要の給付型の両方があり、多くの大学院生が利用しています。
また、リサーチアシスタントやティーチングアシスタントとして大学の研究や授業を手伝い、給与を得る方法もあります。
これにより実務経験を積みながら収入を確保できます。
さらに、民間財団や自治体による奨学金では、特定分野や出身地など条件付きの支援もあります。
進学前に条件や募集時期を調べ、早めに準備を進めることが費用負担を軽減する鍵となります。
【大学院に入るには】大学院に行くメリットは?
では、大学院に行くと、どのようなメリットがあるのでしょうか。
ここでは、理系の人が進学する場合のメリットを紹介します。
高い専門性が身につく
大学院に進学する一番のメリットは、勉強したい学科に対して、より専門的な知識が身につくことです。
大学でも3、4年生になると、自分の選んだ専門授業を受けることになりますが、講義や演習、実験方法、レポートの書き方などの受け身的な授業を中心に勉強することになります。
しかし、大学院では、自分が学び研究したいことに注力することができます。
わかりやすくいうと、大学院にいるすべての時間を研究に費やすことが可能になるのです。
また、同じ分野を研究している人と知り合う機会が増え、さらに新しい知識を見つけることや掘り下げて研究することもできます。
大学よりも研究したいテーマをより自発的、専門的に勉強、研究できるだけでなく、学生一人ひとりが、専門性を持つ研究者として取り組むことができるのが最大のメリットでしょう。
また、研究職に就職したい場合も、大きなメリットになります。
多くの研究機関や企業では、「大学院卒」を必要条件の一つに挙げています。
専門分野を研究するような仕事に就きたい場合は、大学院を卒業したということが強みになるでしょう。
就職先の選択肢が増える
研究職に就職したい場合も、大学院卒というのは、大きなメリットです。
大手メーカーや研究機関の多くは、大学院卒が必要条件となっているので、その専門分野に就職したい場合は、強みになるでしょう。
これは、大学院を卒業していると、高い専門知識を持っているとみなされるからです。
特に、理系分野の専門職は、大学院での研究成果が注目されることもあります。
また、研究室から推薦を受けられることや研究で培った人脈を活かすこともできるので、就職先の選択肢が増えます。
初任給が学部卒より高い
企業によっては、初任給に差をつけているところもあります。
これは、入社時点での年齢が高いこともありますが、専門知識のレベルが高いと判断して、学部卒よりも基本給を高く設定している場合もあります。
就職した企業の規模にもよりますが、大学院卒業者の方が、30,000円ほど高くなるようです。
たとえば、トヨタ自動車の場合は、学部卒業者207,000円に対して大学院卒業者は、229,000円となっています。
研究者としてのキャリアパスが開ける
大学院は高度な専門知識や技術を習得する場であると同時に、研究者としてのキャリアを築くための重要な通過点です。
将来、大学や国立研究所など公的機関で研究職に就くことを目指す場合、多くのケースで大学院進学は必須とされています。
修士課程を修了した後、さらに博士課程へ進学することで、自身の専門分野における独自性と研究能力を確立できます。
博士号を取得すれば、大学教員や研究機関の研究員、企業の基礎研究部門など、専門性を最大限に活かせる職種への道が広がります。
また、学部卒では応募が難しい高度専門職の求人にも挑戦できるようになり、研究者以外のキャリア選択肢も増えます。
大学院で培った問題解決力や論理的思考、継続的な探究姿勢は、産業界でも高く評価される資質で、将来の職業選択の幅を大きく広げることができます。
【大学院に入るには】大学院に行くデメリットは?
では、大学院に進学するデメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
社会人になるのが遅れる
研究している分野への就職であれば、学部卒業よりも大きなメリットとなりますが、一般企業で普通に就職する場合は、学部卒業者に比べて2年以上社会に出るのが遅くなるので不利に働くことがあります。
企業側としては、若い人を採用する方が、社内教育に時間をかけることができます。
また、長く会社に貢献してくれる期待もあるでしょう。
さらに、初任給にも差があります。
どうせ雇用するのであれば、若くて初任給が安いほうが良いと考えるのも理解できます。
生涯年収が減る
社会人になるのが、学部卒よりも遅いため、生涯年収が減ってしまうこともあります。
確かに24歳時点では、学部卒業者の平均年収325万円に対して大学院卒業者は、309万円となっていますが、25歳以降は、学部卒業者のほうが低くなるのです。
しかし、学部卒業者と給料が変わらないところもあります。
そうなると、社会人になるのが遅いと生涯年収が減る可能性もあります。
生涯年収に関しては、就職する企業によって差があるので、事前に確認しておくと安心です。
研究室生活の厳しさ
大学院での研究室生活は、自由に研究に打ち込める魅力がある一方で、多くの厳しさも伴います。
指導教員や先輩、同期との人間関係は日々の研究環境に大きく影響し、場合によっては精神的な負担となります。
また、研究テーマに対するプレッシャーも避けられません。
研究は必ずしも順調に進むとは限らず、実験が失敗したり、データが思うように得られなかったりすることもあります。
そうした状況でも諦めず、試行錯誤を重ねながら前進する粘り強さが求められます。
さらに、学会発表や論文執筆といった成果発信も大学院生の重要な役割であり、準備や締め切りに追われることも少なくありません。
【大学院に入るには】大学院はどうやって選ぶの?
大学院を選ぶ基準は、いろいろありますが、ここでは、後悔しない大学院の選び方を解説します。
どこに行くかよりも何の研究をするか
大学院には、偏差値というものはありません。
そのため、「大学名で選ぶ」ではなく、「研究の内容」「有名な先生がいる研究室か」「知名度の高いジャーナルに論文が出ているか」「研究費は多いか」「先生は学生と真摯に向き合ってくれるか」などを判断基準にすると後悔することは少ないでしょう。
本当にその分野を学びたいと考えているのであれば、研究室の規模や成果を見ることが大切です。
研究よりも就職にスポットを当てて大学院進学を考えているのであれば、「有名な大学の大学院」「大学や研究室に就職のコネがあるか」「コアタイムが短いか」「インターンや就活が自由に行えるか」を判断基準にすると良いでしょう。
いずれにしても、大学の独自スタイルがあるので、よく調べてから受験することが大切です。
では、着目するポイントはどこにあるのでしょうか。
同大学受験
大学から推薦を得て、通っていた研究室に進学すれば、今までと同じように研究を続けていくことができるだけでなく、一から人間関係を構築していく必要もありません。
他大学受験
ほかの大学院に「どうしてもやりたい研究がある」「師事したい先生がいる」などの場合は、他大学を受験する選択肢もあります。
このように、大学院に進むと決めたら、推薦で大学からエスカレーター式で行くか他大学院を受験するかを決める必要があります。
研究分野から絞る
大学院を選ぶときは、大学名で決めるのではなく、研究内容を判断基準にすることが大切です。
特に、理系の場合は、NatureやScienceなど著名なジャーナルに論文が出ている研究室や賞などを受賞している大学院を選ぶと良いでしょう。
著名なジャーナルへの掲載や賞を受賞しているということは、その分野でしっかり研究を行い画期的な発見があったということです。
また、研究室に資金があるかどうかを判断する基準にもなります。
さらに、研究したい分野の論文が多く出ている研究室を選ぶことも大切です。
教授を考える
賞などを多く受賞し、テレビでも見るような有名な教授は、その分野を牽引していると言えます。
その教授のもとで、研究をしている学生は、最先端の恵まれた環境で勉強ができるということです。
また、有名な先生のもとで、最先端の研究をしていると、どのような研究をすれば良いのかわからないほど困難なテーマを与えられることもありますが、結果を出すために多くの論文を読むことや周囲の人とディスカッションを繰り返し、深く勉強をしていくことになります。
そのときは大変でも、得られるものも多く、自分の成長につながるでしょう。
また、研究室によっては、やる気のない教授によって放置されてしまうことがあります。
ほかにも、自分の意見ばかりを押し付けてくる教授もいます。
研究だけでなく学生に対しても、真摯な態度で接してくれる教授のいる研究室のある大学院を選ぶことも大切です。
研究室の雰囲気やOB・OGの進路を調べる
大学院を選ぶ際には、研究テーマや指導教員の専門性だけでなく、研究室の雰囲気も慎重に確認することが重要です。
どれほど興味深いテーマであっても、環境が自分に合わなければ満足度の高い大学院生活を送るのは難しくなります。
雰囲気を知る方法としては、研究室のホームページや業績を確認するだけでなく、実際に足を運んで在籍中の先輩や教員と話すことが効果的です。
オープンキャンパスや研究室訪問の機会を活用し、活気の有無やメンバー間の交流の様子、働きやすい環境かどうかを自分の目で確かめましょう。
さらに、OB・OGの進路を調べることも欠かせません。
過去の卒業生がどのような企業や職種に就いているかを知ることで、その研究室で身につくスキルや人脈が将来のキャリア形成にどのようにつながるのかを判断できます。
【大学院に入るには】大学院入試の対策方法
大学院入試は、学部入試とは異なり、専門性や将来の研究計画が重視されます。
多くの場合、筆記試験、面接、研究計画書の3つが選考の柱となります。
それぞれの対策を計画的に進めることで、自分の強みや研究意欲を効果的に伝えることが可能になります。
特に、過去問や面接練習、研究計画書の作成は時間をかけて取り組む必要があります。
ここでは、それぞれの対策方法を詳しく見ていきます。
筆記試験の対策
大学院入試の筆記試験では、専門科目と英語が課されることが多いです。
専門科目は学部時代に学んだ基礎知識から出題されることが多く、過去問を繰り返し解くことで出題傾向を把握できます。
問題形式や頻出分野を理解し、弱点分野を重点的に学習することが効果的です。
英語は、試験形式によっては長文読解や専門分野の文章が出題される場合があります。
さらに、TOEICやTOEFLのスコア提出が求められることも多く、早めの受験準備が重要です。
毎日少しずつ英語に触れ、語彙力や読解力を鍛える習慣をつけると安定した得点につながります。
面接対策
面接では、これまでの研究内容、大学院での研究計画、将来の展望などが問われます。
自分の研究テーマについて、背景や目的、取り組み内容を簡潔かつ論理的に説明できるように準備しておくことが大切です。
また、志望理由やその大学院を選んだ理由も明確にしておきましょう。
模擬面接を行い、質問への答え方や話すスピード、表情なども確認すると効果的です。
面接官は知識だけでなく、熱意や人柄、研究への適性も見ています。
落ち着いて受け答えができるよう、繰り返し練習して自信を持って臨むことが重要です。
研究計画書の作成
研究計画書は、大学院でどのような研究を行いたいのかを示す重要な書類です。
内容には研究の背景や目的、具体的な方法、期待される成果を盛り込み、構成を明確にすることが求められます。
指導を希望する教授の研究分野をよく理解し、自分の関心やアイデアをその枠組みに合わせて具体化することが重要です。
また、計画が現実的であることを示すために、必要なデータや参考文献を整理しておくと説得力が増します。
作成後は信頼できる教員や先輩に内容を見てもらい、改善点を反映させることで完成度を高められます。
【大学院に入るには】大学院進学以外の選択肢はあるの?
就職でもなく進学でもない選択肢はあるのでしょうか。
もちろん、将来的なことを考えなければ、「何もしない」という選択肢もありますが、「将来的に、自分にとってプラスになるような選択を考えたい」と思うのであれば、よく考える必要があります。
大学院留学
日本ではなく、海外の大学院を目指すという選択肢もあります。
たとえば、アメリカやドイツで進学をすると、大学によって違いはありますが、学費が免除される可能性が高くなるのです。
また、大学によっては、生活費として、給与や奨学金を貰える制度もあります。
このように、海外では、研究に専念できるシステムができているというメリットがあるのです。
また、研究設備や資金が豊富な点も挙げられます。
当然ではありますが、研究設備や資金が豊富であれば、それだけ研究成果が出るスピードが違います。
自分が研究したい分野について、どの国の大学に著名な教授がいるか、研究や技術のレベルなどを調べてみると良いでしょう。
さらに、卒業後は、海外で働くためのビザを取得しやすくなります。
グローバルな研究や将来的に事業を展開したいと考えているのであれば、大学院留学も選択の一つではないでしょうか。
事業を立ち上げる
「自分で事業を立ち上げる」という選択肢もあります。
よく、テレビで大学生起業家が出ていますが、彼らのように学生のうちに起業するのも方法です。
しかし、「この事業を行いたい」「時代のニーズに合っている」などしっかりとした信念やリサーチがないと失敗する可能性が高くなります。
「なんとなく事業を立ち上げてみよう」という程度の気持ちであれば、うまくいく可能性は低く厳しい世界です。
まとめ
文系と比べると大学院への進学率の高い理系は、修士課程を含めたカリキュラムになっている大学も多くあります。
しかし、大学院に進んだからといって、良い就職ができるとは限りません。
確かに、専門分野を深く勉強、研究するので、ニーズが合えば、望んでいるような企業に就職ができます。
しかし、学部卒よりも学費や時間がかかることや研究したことを活かせないこともあります。
また、研究分野によっては、海外の大学院留学を選択肢の一つに入れる必要があるかもしれません。
進学する場合は、自分の未来を見据えて、「どのような自分になりたいのか」をしっかり考えてみましょう。
それが、自分にとって最良な未来を手にする第一歩です。