
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
_800xAuto.webp)
就活の中で行われるESの提出や面接では、ガクチカを聞かれることが非常に多くなってきました。
ガクチカを作成した経験のない就活生はどのように作成したらいいかを悩むことでしょう。
このガクチカの作成では、書き出しの良し悪しでその後の文章が読まれるかが決まってしまいます。
そこで今回は、ガクチカの書き出しのポイントと書き方について解説します。
最後には書き出しの例文もいくつか紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次[目次を全て表示する]
【ガクチカの書き出し】ガクチカでは人柄や価値観を評価される
「ガクチカ」とは、「学生時代に力を入れたこと」の略称で、就職活動のESや面接で定番の質問です。
ほとんどの企業で尋ねられるため、学生の間でも広く浸透しています。
学生時代に頑張ったことや取り組み、その結果得られた成果や印象に残った出来事に焦点をあてて書くことが重要です。
ただし、題材は特に問われず、自分の経験を通じて人柄や価値観が伝わる内容にすることが求められます。
つまり、単なる経験の羅列ではなく、その経験から何を学び、どのように成長したかを示すことで、自己PRや志望動機に説得力を持たせることがポイントです。
しっかりと自己分析を行い、自分の強みや人間性を伝えるガクチカを作成しましょう。
ガクチカと自己PRの違い
ガクチカと同じくらいよく聞かれる質問で、自己PRがあります。
自分のことを話す内容としては、似ている部分もあるため、違いをわからずに混同している人も多く見受けられます。
ガクチカは学生時代に力を入れた経験をエピソードで伝えるのに対し、自己PRは性格や人柄が伝わるような自身の強みや能力を伝えるといった違いがあります。
この2つは一見すると似ているようにも感じられますが、しっかりと違いを理解して作成に臨む必要があります。
【ガクチカの書き出し】企業が見ているポイント
就活では、よく聞かれるガクチカですがそもそも企業は何のためにガクチカを聞くのでしょうか。
企業がガクチカを聞く目的をしっかりと理解していなければ、企業が望む答えを返すこともできません。
そのため、まずは企業がガクチカを聞く目的をきちんと理解する必要があります。
以下にその理由を3つに分けて紹介します。
モチベーションの源泉は何か
経験レベルと学びを活かせる人か
課題や困難な状況への向き合い方
それぞれを確認して、企業がガクチカを聞く理由を理解した上で、自身のガクチカを作成すると良いでしょう。
モチベーションの源泉は何か
企業は、なぜその活動に力を入れたのかという動機や背景に注目しています。
そこから応募者が大切にしている価値観や人柄を読み取り、自社の文化や風土にマッチするかを判断しています。
「なぜその活動に取り組んだのか」「どんな時にやりがいを感じたのか」といった動機の部分には、その人のモチベーションの源泉が表れます。
たとえば、人を支えることにやりがいを感じる人であれば、チームワークを重視する企業と相性が良い可能性があります。
面接官はその源泉を見つけることで、入社後にどう活躍しそうかを具体的にイメージしようとしているのです。
経験レベルと学びを活かせる人か
企業は、学生時代にどのような経験をしてきたかを通じて経験値や実践力を確認しています。
長期インターンやアルバイトなどで実務に近い活動をしてきた学生は、入社後の早期戦力として期待されやすくなります。
ただし、実務経験がなくても、ゼミ活動やサークル、教育実習などで役割や責任を持って行動した経験は十分に評価の対象です。
企業は、過去の経験から何を学び、それをどう活かせるかを重視しています。
つまり、単なる経験の列挙ではなく、「そこから得た学びを今後にどう活かすか」という再現性のある力があるかが評価されるポイントです。
課題や困難な状況への向き合い方
企業がガクチカを通じて確認したいもう一つの重要な視点が、困難への向き合い方です。
どのような課題に直面し、それにどう向き合って解決しようとしたか。
また、失敗を経験した際にどのように立て直したかという過程には、その人の努力の姿勢や責任感、行動力が表れます。
企業は、仕事においても困難や想定外のことが多くあるため、問題解決への姿勢や粘り強さ、計画性といった資質を見ようとしています。
そのため、ガクチカの冒頭で「〇〇に課題を感じた」「△△がうまくいかなかった」といった具体的な壁を提示し、そこにどう挑んだかを示す構成が効果的です。
【ガクチカの書き出し】まずは全体の構成を確認
ガクチカを作成する際には、構成は非常に重要です。
構成が整っていなければ、何を伝えたいのかが分かりにくくなるため、相手にも内容が伝わりにくくなってしまいます。
逆に構成をしっかりと整えた文章は、伝えたいことが明確になり、端的にアピールできる特徴があります。
このため、構成はしっかりと行い、相手に伝わりやすい文章の作成を作成しましょう。
結論:学生時代に力をいれたこと
構成で重要になるのは、まずは書き出しの部分の文章です。
ここでは、端的に結論を述べることが重要です。
最初の段階で長い説明を入れてしまうと、分かりにくくなってしまう上に、今後の文章を読み進める興味も薄くなってしまいます。
そのため、書き出しの文章では、できるだけ短い文章で端的に結論を述べることを意識して書きましょう。
背景と取り組み:目標設定や苦労したこと
ガクチカで経験を伝える際は、単に結論や成果だけを述べるのではなく、取り組んだ背景や課題解決の過程まで丁寧に説明することが重要です。
そのためには、「なぜその活動に取り組んだのか」という動機や当時の状況から説明し、読んだ人がその場面を具体的に想像できるように工夫することが求められます。
文章構成のポイントとしては、「取り組みの内容→動機→課題の発見や目標設定→直面した困難→試行錯誤→成果や学び」というストーリーの流れを意識することで、話の筋道が明確になります。
この順序で書くことにより、読んだ面接官に対して、どのように考え行動したのかが一貫して伝わり、納得感のあるアピールになります。
最終的に成果や学びをどのように今後に活かしていきたいかまで言及すると、より説得力のある内容に仕上がります。
①取り組みの環境や背景
「どんな場所や設備で行ったのか」「周りの人間関係はどうだったのか」「そのときの状況はどうだったのか」
②何を改善したいのか、その「問題点」を明確に
「何をどう良くしたいのか」「どんな課題や問題があったのか」
③問題を解決するために考えたアイデアや工夫
「どうやってその問題を解決しようと考えたのか」「どんな戦略や工夫をしたのか」
④問題に対してどんな行動をとったのか(対策)
「自分はどんなことをしたのか」「どんな工夫や努力をしたのか」
就活コンサルタント木下より

「努力の過程や苦労を伝える」
結果だけを見ると簡単に思えることでも、その裏にはたくさんの試行錯誤や苦労があったはずです。
どんな工夫をして、どんな失敗や壁にぶつかりながらも乗り越えたのかを話すと、あなたの努力や粘り強さが伝わります。
経験から学んだこと
具体的な内容や、それによる結果が書けたら、次は経験から何をどのように学んだのかを具体的に記載します。
自身が力を入れて行ってきたことから、何を学んだのかを述べることで最終的にどのように活かしたかまでをスムーズにつなげることができます。
ガクチカに取り組み、定めた目標を達成するために行動した中で、苦労した点や工夫した点などがあるはずです。
これらをよく思い出し、経験してきた内容から得られた強みを見つけ出すことでアピールにつなげることが出来ます。
どのような経験であっても、平坦ではなかったはずです。
途中にあった問題点をクリアするための創意工夫が学びであり、今後の仕事にも活きてくる強みです。
これらをうまくアピールすることで、企業の印象にも残りやすいガクチカを作成できます。
入社後どのように活かすのか
最後に、学んだことから入社後にどのように活かし、活躍や貢献をしていくのかを述べます。
ガクチカを通して経験してきたことから、たくさんの学びがあったはずです。
これらは、前述部分で説明をしていますので、その学んだ内容や強みを企業の中でどのように活かしていくのかを具体的に説明します。
志望する企業や職種によって、求められる人材や必要としているスキルは変わってくるはずです。
このため、その企業の研究をしっかりと行い、どのような人材やスキルを求めているかを掴んでおくことは非常に重要です。
ガクチカを通して、得られた強みがマッチするようなエピソードで締めくくることができれば、より印象を強く残すことができるでしょう。
【ガクチカの書き出し】書き出しが重要な理由
ガクチカを作成する上では、書き出しの部分は非常に大事です。
この最初の入口になる文章がしっかりと書けるかどうかで、ガクチカ全体の良し悪しが決まると思ってもいいほど重要な部分であり、良く考えて作成する必要があります。
具体的にどのような点が大切であり、気をつける必要があるかを、2点に絞り以下で紹介します。
しっかりと理解した上で作成し、書き出し部分で失敗することがないように注意をしてください。
読むかどうかに関わるから
書き出しがしっかりと書けているかどうかで、その先を読み進めるかどうかまでが決まってしまいます。
これは、自分自身が読み手と考えると分かりやすいです。
自身が読み手であった場合に、読みにくい書き出しの文章をその先まで読み進めていくかを考えてください。
きっと途中で止めてしまうか、最後まで読んでも頭に入っていないでしょう。
面接担当も全く同じであり、書き出しが読みにくい文章では、その先を読まれない可能性が高まりますし、読んでもらったとしても印象に残ることはありません。
このため、書き出しの文章は非常に大事であり、ガクチカ全体の評価に影響を及ぼす可能性があることを理解した上で書き出しを作成する必要があります。
書き出しで印象が左右するから
書き出しの文章でガクチカ全体の雰囲気を感じることができますし、応募者の印象まで決まってしまうことがあります。
読みやすくて分かりやすい内容で書けている場合や、しっかりと構成されている場合などには、丁寧な性格の応募者であるなとの印象を持つでしょう。
逆に構成が考えられていなかったり、乱雑な書き出しでは良い印象を持たれることはなく、評価も悪くなってしまう可能性があります。
人事担当は、毎年数多くのガクチカを読み込んできてる、面接のプロです。
書き出しの文章だけで、全体の雰囲気を把握したり、印象を判断することは問題なくできることでしょう。
細部にまでしっかりと気を配り、注意を払って作成することが必要です。
【ガクチカの書き出し】良い書き出しに必要な2つの要素
ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)の書き出しで、他の人と差をつけて目を惹く魅力的な文章を作るためには、どんなポイントに気をつければ良いのかを理解することが大切です。
そこでここでは、良いガクチカの書き出しに必要な2つの重要な要素について詳しく解説します。
これらの要素を押さえることで、印象に残る魅力的な書き出しを作ることができるので、ぜひ意識してみてください。
1.力を入れたポイントを具体的に「結論」から伝える
最初に、「何に力を入れたのか」を明確に伝えることが大切です。
経験の概要や背景を長々と説明するのではなく、「自分が注力した部分」や「最も伝えたいポイント」を、まずは結論として伝えましょう。
たとえば、「私はチームリーダーとして、メンバーの意見をまとめる役割を担い、プロジェクトを成功に導きました」といった具合です。
これにより、読む側はあなたの強みや取り組みの核をすぐに理解できます。
ポイント
経験の概要ではなく、「自分が注力した部分」から入る
就活コンサルタント木下より

このように、書き出しでは、自分の経験をただ羅列するのではなく、全体のストーリーの「入口」として、読者に印象づける導入文を意識して書くことがポイントです。
経験の背景や動機を簡潔に伝えつつ、「何に注力したのか」を明確に示すことで、あなたのガクチカの魅力がより伝わりやすくなります。
2.興味を引く具体性を加える
次に、読者の興味を引くために、具体的な情報を盛り込みましょう。
たとえば、チームの規模や役割、達成した成果、具体的な行動や数字を入れると、より伝わりやすくなります。
例として、「私は5人のチームを率いて、3ヶ月で売上を20%向上させることに成功しました」や、「毎週のミーティングを導入し、メンバーの意見を反映させることで、作業効率を30%改善しました」などです。
こうした具体的な例を挙げることで、あなたの取り組みの具体性や成果が伝わりやすくなります。
これにより、読む側はあなたの努力や工夫をイメージしやすくなり、印象に残る書き出しになります。
「販売促進のためにSNSを活用し、フォロワー数を2倍に増やしました」
ポイント
- チームの役割・規模・成果
- 具体的な行動を含める
就活コンサルタント木下より

具体的な役割や規模、成果を示すと、あなたの努力や実績が明確になります。
数字や具体的なエピソードを入れることで、取り組みがよりリアルに伝わるため説得力が増し、読む側にインパクトを与えることができます。
エントリーシートなどで文字数の制限がある場合、すべての要素を盛り込もうとすると、肝心な内容が薄くなる恐れがあります。
そのため、「私が学生時代に力を入れたことは、」などの定型的な表現は省略しても問題ありません。
たとえば、「ダンスサークルの教育係としてメンバー10人の指導と進行を担当し、地域イベント成功に尽力しました。」のように、役職・行動・目的を一文に集約することで、短い中でも情報量のある書き出しが可能です。
重要なのは、結論から始まる構成を意識しつつ、読み手がすぐに「何をした人なのか」がわかることです。
【ガクチカの書きだし】良い例と悪い例
書き出しを魅力的にするためのポイントを押さえたところで、実際にどんな書き出しが「魅力的」と感じられるのか、具体例を使って解説していきます。
特に、NG例と改善例を比較しながら、どこを工夫すればより印象に残る文章になるのかをわかりやすくお伝えします。
NG例とその問題点
NG例文
「私は大学時代、吹奏楽部でトランペットを担当し、毎日練習に励みました。」
「飲食店のアルバイトでリーダーとして売上向上に力を入れました。」
これらの書き出しはよくある書き出しの一般例ですが、具体性や個性が伝わりません。
読む側にとって印象に残りにくく、何に熱心だったのかが伝わりにくくなっています。
また、「大学時代、部活動に取り組んだ」「アルバイトリーダーをした」とだけ伝えており、具体的な活動内容やあなたの役割、努力のポイントが曖昧です。
「アルバイトリーダーとして売上向上に努めたこと」も内容としては伝わりますが、リーダーとして何をしたのか(役割)、どんな工夫や努力をしたのかが伝わりにくいです。
改善例と解説
OK例文(改善例)
「私が力を入れたことは、吹奏楽部でトランペットを担当し、技術向上のために毎日1時間以上の個人練習を欠かさず行ったことです。特に、音程や表現力を高めるために、毎週の個人レッスンを受けたり、録音して自分の演奏を客観的に振り返ったりすることに注力しました。」
「飲食店のアルバイトリーダーとして、売上向上のためにスタッフの接客スキル向上やメニュー提案の工夫に取り組みました。具体的には、スタッフ向けの接客研修を企画・実施し、顧客満足度を高めることに注力しました。」
このように、「毎日1時間以上の練習」「個人レッスン」「録音して振り返る」など、具体的な役割や努力のポイントを盛り込むことで、より印象的な書き出しになります。
この書き出しは、「何に取り組んだのか」「どのような役割を果たしたのか」といった「具体的に力を入れたポイント」(練習メニューの工夫や振り返りの時間の導入)が伝わります。
アルバイトの例でも、「具体的な取り組み内容(接客研修やメニュー提案)」「工夫したポイント」「成果(売上の増加)」が明示されています。
就活コンサルタント木下より

これにより、採用担当者もあなたのリーダーシップや努力の具体性、取り組みへの熱意をイメージしやすく工夫した点もよく伝わる内容になります。
【ガクチカの書き出し】高評価を得るために重要なこと
ガクチカの書き出しは、読み手に最初の印象を与える非常に重要な部分です。
しかし、どれほど工夫された文章でも、事前準備が不十分であれば内容の説得力が欠け、評価にはつながりません。
企業が求める人物像に合致したエピソードであるかどうか、話の軸がぶれていないかを確認するためにも、書き始める前の準備が成功の鍵となります。
事前準備を怠らない
成果のアピールよりも過程を重点的に
なるべく数値を入れて具体的に説明する
文章の一貫性や論理性を意識する
志望企業にマッチするエピソードを選ぶ
事前準備を怠らない
高評価を得るガクチカを書くためには、事前準備が不可欠です。
準備を怠ると、具体性に欠けた抽象的な内容になってしまい、応募企業の求める人物像とかけ離れた内容になってしまう恐れがあります。
その結果、「伝えたいことが伝わらない」「印象に残らない」といった理由で、書類選考の段階で不合格となるケースも少なくありません。
まずは、自分がアピールしたい経験や強みを明確にしたうえで、その経験を企業が評価する資質にどう結びつけられるかを考えることが重要です。
さらに、応募する企業の業界研究や企業理念、採用情報などを把握し、自分の価値観や経験とどこが重なるのかを洗い出しておくと良いでしょう。
業界分析は就職活動の出発点であり、これを怠るとガクチカ、志望動機、自己PRにも悪影響を及ぼします。
企業が何を求めているか、業界内での位置付けや競合との差別化ポイントを理解することは、自己PRを的確に構築し、志望動機を深く語るために不可欠です。
さらに、企業分析を徹底的に行い、その企業が直面している課題や業界のトレンドを把握することで、自分がどのように価値を提供できるかを明確に示すことが可能となります。
業界分析の次に行うべきは、志望企業を含む様々な企業の分析です。
企業ごとの社風、経営理念、事業内容、強みや競争環境などを深く理解することが、効果的な就職活動には不可欠です。
このプロセスを通じて、自分の価値観やキャリア目標と合致する企業を見極めることができます。
また、企業分析は、面接やエントリーシートでの志望動機の説明をより具体的かつ説得力あるものにするためにも重要です。
幅広い企業を分析することで、自分にとって最適な職場環境を見つけ出し、目指すべき企業の選定に役立てることができます。
企業だけではなく、自己分析をしっかりとすることが重要です。
自己分析とは、自分の過去を振り返り、長所や短所、習得したスキルや能力を深く理解する作業です。
この自己理解を深める作業を丁寧に行うことで、自分の強みや改善点を明確にし、それをガクチカや自己PRに活かすことができます。
自己分析を行うことで、自己の価値をより具体的に表現し、就職活動での差別化を図ることが可能になります。
自己分析の方法については、専門の記事やガイドを参考にすると、自己分析のプロセスを効率的かつ効果的に進めることができます。
成果のアピールよりも過程を重点的に
ガクチカでありがちな失敗は、経験や成果の羅列に終始してしまうことです。
もちろん優れた成果は目を引く要素ですが、新卒採用において企業が重視しているのは、その成果よりもそこに至るまでの過程や姿勢です。
たとえば、困難に直面したときにどう問題を捉え、どのように行動したのか、チームの中で自分の役割をどう理解し、どう貢献しようとしたのか。
こうした過程の中にこそ、応募者の人柄や価値観、思考力、コミュニケーション力といった人間性を表す情報が詰まっています。
成果よりも「どのように取り組んだか」を深掘りし、読んだ相手が応募者の価値観や行動スタイルを具体的にイメージできるようなガクチカを目指しましょう。
なるべく数値を入れて具体的に説明する
なるべく数字を盛り込むことを意識することが大切です。
頑張りましたや、努力しましたといった表現は、人によって受け取る程度が異なるため、表現が伝わりにくく、誤解を生む可能性もあります。
数字を使って表現することで、誰にでも同じ内容で程度を伝えることができます。
例えば「毎日頑張った」を「毎日2時間頑張った」と表現するだけで、その程度が伝わります。
このように、できるだけ数字を使った表現を意識することで、伝わりやすさが変わります。
文章の一貫性や論理性を意識する
ガクチカを含むエントリーシートでは、文章全体の一貫性と論理性が非常に重要な評価ポイントとなります。
たとえば、自己PRでは「とにかくまず行動する積極性」をアピールしているのに、ガクチカでは「コツコツと継続して取り組んだこと」を前面に出していると、一貫性がないように受け取られてしまいます。
結果として、応募者がどんな人物なのか、面接官に正しく伝わらなくなります。
自分が「どう評価されたいか」「どういう人物として見られたいか」を明確にし、エピソードや表現方法にブレがないように意識することが大切です。
志望企業にマッチするエピソードを選ぶ
ガクチカでどのエピソードを選ぶかは、志望企業との相性やマッチ度を意識して決めることが重要です。
企業が求める人材像や価値観に沿った経験を提示することで、より魅力的な自己アピールにつながります。
たとえば、チームで成果を上げる力が求められる企業では、協調性やリーダーシップを発揮したエピソードが適しています。
複数の経験がある場合は、自己分析によって内容を深掘りし、企業の求める方向性に合致するものを選びましょう。
一方で、経験が一つしかない場合でも、異なる視点から切り出した複数のエピソードを用意しておくことで対応が可能です。
【ガクチカの書き出し】経験別の書き出し例文
ここまで企業がガクチカを求める理由や、ガクチカの構成についてを解説してきました。
また、ガクチカでは書き出しが非常に重要であることを伝えてきました。
ガクチカは最初の書き出しに失敗すると、その先を読み進めてもらうことができなかったり、うまく内容が伝わらなかったりするため、書き出しに細心の注意を払う必要があります。
そのため、ここではいくつかの経験に合わせたガクチカの書き出し例を紹介します。
紹介する書き出し例を参考にして、自身のガクチカの書き出しを考えてください。
例文1.部活動
部活動での経験をガクチカにする際の書き出し例を紹介します。
全部で5つの書き出し例を紹介しますので、自身のガクチカを作成する際の参考にしてください。
部活動の書き出し例文
①陸上部
私は陸上部の活動で、400mと800mの県記録更新を目標に、スタミナ強化や筋力トレーニングの継続に力を入れました。
具体的には、走りの後半で失速しないよう朝練でインターバル走を取り入れ、放課後は体幹や下半身を中心とした筋トレを習慣化しました。
②バスケットボール部
私はバスケットボール部で、約100人の部員をまとめる部長として、組織の一体感を高める工夫に力を入れました。
具体的には、上下関係の壁をなくすミーティングの定期開催や、練習後の「振り返りノート」の共有を導入しました。
③ラグビー部
私はラグビー部のマネージャーとして、選手が練習や試合に集中できる環境づくりに力を入れました。
80名の部員を支える中で、効率的な練習運営のためのスケジュール表作成や、備品・水分補給管理の徹底を行いました。
④吹奏楽部
私は吹奏楽部で、10曲以上ある課題曲を完璧に演奏するための反復練習と客観的な振り返りに力を入れました。
具体的には、パート練習の主導だけでなく、自分の演奏を録音して聞き直すことを日課にし、音程や音色、リズムの細かいズレを修正しました。
⑤美術部
私は美術部で、地域アートイベントへの出展に向けた創作活動と、部全体の制作スケジュール管理に力を入れました。
出展作品のコンセプト作成から始まり、部員20名の制作進行を管理するためのチェックリストを作成しました。また、イベント広報のためにSNSでの告知や、地域施設との調整も行いました。
例文2.サークル活動
ここでは、サークル活動をベースにしたガクチカの書き出し例文を5つほど紹介していきます。
サークル活動の書き出し例文
①テニスサークル
私はテニスサークルの広報活動に力を入れ、効果的な宣伝戦略によってサークルの規模拡大に貢献しました。
新入生の目に留まるようSNSのデザインや投稿文の工夫、大学内でのチラシ配布場所の見直しなどを行い、魅力が伝わる広報を意識しました。
②国際交流サークル
私は国際交流サークルの代表として、異文化理解を深める多国籍イベントの企画・運営に力を入れました。
50人の部員をまとめ、月1回の交流会を軸に、日本文化体験イベントや多国籍料理パーティーなどを企画しました。
③フットボールサークル
私はフットボール未経験ながら、サークルに入り基礎練習の反復とチーム理解に力を入れて取り組みました。
初心者である自分にできることを徹底するため、基礎練習を動画で撮影して毎回見直し、課題を可視化しました。
④ダンスサークル
私はダンスサークルがなかった大学で、自ら代表となりゼロからサークルを立ち上げることに力を注ぎました。
まず、興味を持ってもらえるようSNSでの呼びかけや学内掲示を活用し、有志メンバーを集めました。発表の場を確保するため、学園祭や地域イベントとの交渉も行い、定期的な練習と振付制作も自ら主導しました。
⑤サークルでのイベント企画
私はサークルでのイベント企画において、多様な意見を取り入れた包括的なコミュニティづくりに力を入れました。
新歓イベントや季節ごとの企画では、性別・学年・専攻を問わず全員が楽しめる内容を重視し、事前にメンバーアンケートを実施して意見を収集。企画内容だけでなく、当日の役割分担にも配慮し、誰もが居場所を感じられる運営を意識しました。
例文3.アルバイト
次はアルバイト経験でのガクチカの書き出しを紹介します。
同じく5つ紹介しますので、参考にしてください。
アルバイトの書き出し例文
①売上目標について
居酒屋でのアルバイトでは、約100種類あるドリンクメニューの作り方を短期間で習得し、提供スピードと正確さの向上に注力しました。
お客様の注文傾向を観察し、おすすめドリンクの提案を積極的に行うことで、売上アップに貢献しました。
②居酒屋アルバイト
私が学生時代に力を入れたことは、居酒屋でのアルバイトです。
お店では100種類近くあるドリンクメニューの作り方を覚え、売上への貢献を目指しました。
③ケーキ店でのアルバイト
ケーキ店では、新商品の開発にも携わり、試作やお客様の反応を分析しました。
その結果、販売戦略を工夫し、担当月での販売数1位を2回達成。スタッフ間での情報共有も促進し、チームとしての売上向上に寄与しました。
④カフェのアルバイト
カフェでのアルバイトでは、回転率の向上を重視し、注文から提供までの時間短縮に取り組みました。
混雑時は効率的な動線や役割分担を提案・実践し、お客様の待ち時間を短縮することで、売上の増加と顧客満足度向上を実現しました。
⑤シフトリーダーの経験
アルバイトリーダーとして、シフト管理と日々の売上集計を担当しました。
スタッフのモチベーション維持のためにコミュニケーションを積極的に取り、接客研修を企画・実施。結果として、スタッフの接客スキルが向上し、売上増加に貢献しました。
ガクチカでアルバイトを書く場合には、こちらの記事も参考になります。
ぜひ、確認してみてください。
例文4.学業
ここでは、学業をベースにしたガクチカの書き出し例文を5つほど紹介していきます。
学業の書き出し例文
①資格取得
私は資格取得に力を入れ、毎日3時間の計画的な自己学習を継続しました。
特に効率的な学習法を模索し、優先順位をつけて勉強することで、10以上の資格を取得。これにより自己管理能力と専門知識を大幅に向上させることができました。
②TOEIC受験
TOEIC800点以上を目標に掲げ、日常的に英語のリスニングやリーディングを中心に勉強を進めました。
具体的には、模試の分析を行い弱点を把握した上で、毎日の学習計画を調整。結果、目標達成だけでなく、持続可能な学習習慣も確立できました。
③大学の成績
学業ではGPA3.5以上を維持するため、予習復習や過去問演習に加えて、グループワークや教授とのディスカッションにも積極的に取り組みました。
これにより、高い学習意欲と効果的な時間管理能力を培うことができました。
④独学での学習
大学時代は心理学の分野を独学で深め、講義内容を超える専門書や論文を読み込みました。
理解度を高めるためにノートにまとめ、定期的に自分で振り返る習慣を続け、知識の定着と応用力向上に努めました。
⑤大学の講義
高校時代から日本経済に貢献したいという目標を持ち、大学では経済学に加えて政治学や国際関係学も幅広く学びました。
複数分野の知識を融合し、多角的な視点でビジネス課題を考察できる力を身につけました。
例文5.ゼミ
ここでは、ゼミをベースにしたガクチカの書き出し例文を5つほど紹介していきます。
ゼミの書き出し例文
①ゼミ長
ゼミ長として、50名のメンバーのスケジュール調整や議題設定、進行管理を担当しました。
メンバー間の意見調整やモチベーション維持に注力し、チーム全体の活動を円滑に進めることができました。この経験でリーダーシップとチームワークの重要性を深く学びました。
②プロジェクトの推進
遺伝子工学に特化したゼミで、複数の実験プロジェクトの計画立案から進捗管理までを推進しました。
問題発見時には原因分析を行い、対策をメンバーと共有。科学的探求心と問題解決能力を養う貴重な経験となりました。
③専門知識の理解
ゼミ活動を通じて専門知識の習得に努め、論文や文献を積極的に読み込みました。
また、定期的な発表を重ねることで、学術的な理解を深めると同時に、分かりやすく伝えるコミュニケーション能力も向上させました。
④特定のスキルを磨いた
ゼミ活動ではスケジュール管理を重視し、メンバーの予定調整やタスク分担を効率的に行うための計画立案を担当しました。
結果、全員が時間内に課題を完了できる体制を構築し、時間配分能力と調整力を身につけました。
⑤研究発表
ゼミでの研究発表に力を入れ、自身の研究成果をスライドや資料で効果的にまとめました。
質疑応答にも積極的に対応し、内容の理解を深めるとともに、プレゼンテーションスキルの向上に繋げました。
例文6.長期インターン
ここでは、長期インターンをベースにしたガクチカの書き出し例文を4つほど紹介していきます。
長期インターンの書き出し例文
①営業インターン
ITベンチャー企業で1年間営業インターンとして勤務し、当初の目標売上100万円を大幅に超える200万円を達成しました。
顧客ニーズのヒアリングや提案方法を工夫し、効率的な営業戦略を策定したことで成果を上げることができました。
②マーケティングのインターン
大学1年生からマーケティングインターンを始め、SNS運用を担当しました。
投稿内容の分析とターゲット層の設定に注力し、フォロワー数を0から2000人に増やすことに成功しました。この経験でデジタルマーケティングの実践力を身につけました。
③メディア記事作成のインターン
大学2年生から1年間、メディア記事作成のインターンに従事しました。
SEOの基本を学びつつ、読者に伝わる文章構成を意識してコンテンツ制作に取り組みました。この経験は効果的な情報発信力の基盤となりました。
④商品開発のインターン
インターンシップで商品企画に携わり、市場調査から企画立案、プレゼンまでの一連の流れを経験しました。
チーム内で意見をまとめ、顧客視点を意識した提案を行い、実践的なビジネススキルを磨きました。
例文7.ボランティア活動
ここでは、ボランティアをベースにしたガクチカの書き出し例文を5つほど紹介していきます。
ボランティア活動の書き出し例文
①地域清掃ボランティア
学生時代、地域の環境美化を目的に毎月2回の清掃ボランティアに積極的に参加しました。
自治会の方々と協力してゴミの分別や回収を行い、地域の安全・快適な環境維持に貢献。この活動を通じて、コミュニティの一員としての自覚と責任感を深めました。
②災害復興ボランティア
大学在学中、2024年の能登半島地震被災者支援として6ヶ月間ボランティア活動を行いました。
物資配布や仮設住宅での生活支援に加え、被災者の声を聞くことにも注力。困難な状況下でも前向きに取り組む力と人への思いやりを養いました。
③学童ボランティア
地元の学童保育で週3回、子供たち向けのレクリエーション企画・運営を担当し、約2年間で100以上のイベントを成功させました。
子供たちの興味を引く内容を考え、チームメンバーと連携して円滑に進行。企画力とチームワークの重要性を学びました。
④国際交流ボランティア
大学3年生の時、国際文化交流イベントで通訳ボランティアとして活動し、10ヶ国以上の参加者とコミュニケーションを取りながら、円滑な進行をサポートしました。
異文化理解とコミュニケーション能力を高める貴重な経験となりました。
例文8.留学
ここでは、留学をベースにしたガクチカの書き出し例文を5つほど紹介していきます。
留学経験の書き出し例文
①異文化コミュニケーション
イギリス留学中、グループプロジェクトのリーダーを務め、異なる文化背景を持つメンバー間の意見調整や役割分担を行いました。
多様な価値観を尊重しながらチームをまとめることで、異文化間コミュニケーション能力とチームワークの重要性を実感しました。
②積極性と行動力
大学2年生で積極性と行動力を身につけるため、3ヶ月間の海外留学プログラムに参加し10カ国以上の学生と交流して、言語だけでなく異文化理解に積極的に取り組みました。
この経験を通じ、自ら挑戦する姿勢が大きく成長しました。
③世界中の人との関係性構築
留学生活を始めてから、30カ国以上の友人を作り、多様な文化や価値観に触れました。
世界中に100人の友達を作る目標に向けて、積極的にコミュニケーションを図り、異文化理解と人間関係構築力を高めました。
④海外での多様な活動への挑戦
アメリカの1ヶ月間の短期留学では、20以上の異なる活動に挑戦し、未知の環境での行動力と適応力を養いました。
新しい経験に臆せず飛び込むことで、自身の可能性を広げることができました。
⑤環境適応スキルの向上
留学中に6カ国を訪問し、各地の文化や言語、慣習の違いに柔軟に対応しました。
現地の人々との交流を通じて環境適応力を大幅に向上させ、多様な状況でのコミュニケーション力を身につけました。
例文9.実習
実習経験の書き出し例文
①看護実習
私は看護実習で、患者さんの体調変化の早期発見と報告・連携に具体的に力を入れました。
毎日の観察を丁寧に行い、小さな変化も見逃さないよう努めました。
②サロン実習
私はサロン実習で、お客様のニーズを正確に把握するヒアリング力と、施術技術の向上に具体的に力を入れました。
お客様がリラックスできる接客にも注力しました。
③介護実習
私は介護実習で、利用者の尊厳を守るケアと安心して過ごせる環境づくりに具体的に力を入れました。
スタッフとの連携も積極的に図りました。
④教育実習
私は教育実習で、生徒一人ひとりの理解度に応じた指導方法の工夫と、質問しやすい雰囲気づくりに具体的に力を入れました。
生徒が主体的に学べる環境を意識しました。
⑤特別支援実習
私は特別支援実習で、児童・生徒の個別ニーズに応じた支援計画の立案と、環境調整やコミュニケーション方法の工夫に具体的に力を入れました。
【ガクチカの書き出し】注意点と困った時の対処法
ガクチカを書く際の注意点についても解説します。
注意点を怠ると、内容がわかりにくいガクチカになってしまい、伝わりにくくなるため、面接官からの評価も低いものになる可能性があります。
構成を考え、読みやすさを意識して作成する必要がありますが、いくつかの注意点にも気を付けながら作成を進める必要があります。
以下でガクチカ作成におけるNGポイントを詳しく解説しているので自分のガクチカに当てはまる部分が無いかチェックしておきましょう。
難しくはないのでしっかりと注意を払い、作成を進めてください。
専門用語は使わない
一番注意を払うべき重要な点は、専門用語を使いすぎないことです。
ガクチカでは自分の興味があって取り組んだことや、趣味の部分を説明する機会が多いため、意識しなければ、専門用語を多く使ってしまいがちです。
また、自分の中では普通に使う言葉であっても、関心のない人にとっては専門的と感じる言葉も多くあるため、注意が必要です。
専門用語は、その分野での経験や知識がない人にとっては全くわからない言葉になってしまうため、頑張ってガクチカを作成しても伝わらないものになってしまいます。
これらを避けるためにも、単語を意識して専門用語を使いすぎないように注意する必要があります。
話しを誇張しすぎない
就活では、自分を少しでも良く見せようと話を盛ってしまいたくなる気持ちもありますが、誇張しすぎた内容は逆効果になる可能性があります。
面接官は多くの就活生を見てきた経験豊富なプロであり、話に一貫性がなかったり、深掘りの質問に答えられなかったりすると、すぐに違和感に気づかれます。
企業が重視しているのは、表面的な成果よりも人柄や価値観、仕事への向き合い方です。
等身大の経験を丁寧に振り返り、そこから得た学びや行動の過程を真摯に伝えることで、信頼感のあるガクチカになります。
無理に話を作るのではなく、自分らしさを活かせるエピソードでアピールしましょう。
何年も前のエピソードは避ける
ガクチカにおいて、高校時代など何年も前のエピソードを使うのは避けたほうが無難です。
人は環境の変化によって価値観や行動スタイルが大きく変わるため、昔の経験が今の自分と結びつかないことが多く、説得力に欠けます。
また、大学時代の経験がないと思われたり、成長の過程が見えにくくなったりすることで、面接官に不安を抱かせる可能性もあります。
企業は「今のあなた」を知りたいと考えているため、大学生活の中で取り組んだ活動を振り返り、どんなに小さなことでも主体的に動いた経験からガクチカを構成するようにしましょう。
ガクチカがなかなか書けなかったり、選考に通過できずに不安を感じている場合は、一人で悩まず周囲に頼ることが大切です。
大学のキャリアセンターではES添削や模擬面接、業界研究など幅広い支援が受けられます。
また、就活エージェントを活用することで、自分に合った企業紹介や書類・面接対策のアドバイスを個別に受けることも可能です。
たとえば「ジョブコミット」などのサービスでは、就活全体をサポートしてくれるため、方向性に悩んだ際にも力になります。 悩みは早めに相談して、効率よく就活を進めていきましょう。
まとめ
ここまでガクチカの書き出しについてを解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
就活の中でガクチカは、応募者の人となりを知るための重要なツールになっています。
丁寧に作成する必要があるのは当然ですが、やはり入口となる書き出しは非常に重要であり、注意を払って作成する必要があります。
ここまでの解説を参考にしながら、自分なりの書き出しの作成を目指してください。
ガクチカの書き出しがうまくいけば、全体の成功も近いです。
就活が思い通り進むように頑張りましょう。






_720x550.webp)










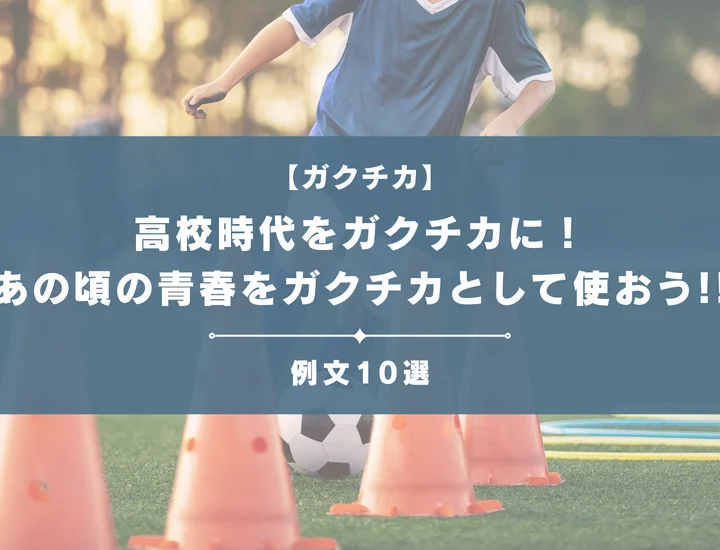





伊東美奈
(Digmedia監修者/キャリアアドバイザー)
伊東美奈
(Digmedia監修者)
【結論】学生が自社に合う人材かどうか知りたい
結論、面接官がガクチカを聞く理由は自社の社風や理念とマッチした人材どうかを判断するためです。
ガクチカを聞くことで、学生時代に何に没頭してきて、どのような問題解決を行ったのかや、目標達成に向けた努力などを確認することで、応募者の人間性が見えてきます。
これらを確認することで、企業は自社にとって必要な能力を持った人材であるかや、求める業務にマッチできる人材であるかを判断しています。
このため、志望する企業への企業研究は事前に行い、どのような社風かなどは確認しておくべきでしょう。