
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
周囲を巻き込んだ経験について就活の場で企業から質問されることがありますが、これは仕事の場においても非常に重要視する内容だからです。
基本的に仕事というものは1人で完結せず、周囲の人の力があって初めて成果が出るものなので、学生時代にこの経験があるかどうかを見ているのです。
この記事ではそんな企業の意図や、どのように回答すると効果的かというポイントを徹底解説します。
目次[目次を全て表示する]
【他者を巻き込んだ経験 es】企業が聞く理由
企業がこの質問をするのは、仕事が一人で完結せず、周囲との協力が不可欠だからです。
この経験を通して、企業は学生が持つ潜在能力を多角的に見ています。
具体的には、①自ら課題を見つけ、周りを動かす「主体性」、②多様な人と対話し、協力関係を築く「コミュニケーション能力」、③困難な状況で、周囲の力を借りて乗り越える「課題解決力」です。
これらの能力から、入社後に組織の一員として成果を出せる人材かを見極めています。
リーダーシップや主体性を評価するため
企業が「周囲を巻き込んだ経験」を質問する背景には、リーダーシップや主体性の有無を見極める意図があります。
社会に出ると、自ら課題を見つけて行動し、周囲を巻き込みながら解決へ導くことが求められます。
そのため、学生時代に自ら行動を起こし、メンバーを引っ張る姿勢があったかどうかを確認したいのです。
リーダーシップは役職があるかに限らず、状況を把握し、自発的に役割を果たそうとする姿勢にも表れます。
たとえば、サークルでイベントを主導した経験や、アルバイト先で業務改善を提案したエピソードなどが該当します。
こうした経験がある学生は、入社後も主体的にプロジェクトを牽引し、チームを成長させられると期待されます。
自ら動き、周囲を動かす力があるかを見せることが重要です。
コミュニケーション能力を確認するため
周囲を巻き込む経験には、メンバーとの連携が不可欠です。
そのため、企業はこの質問を通してコミュニケーション能力を見極めようとしています。
職場では、部署間の調整や取引先との折衝など、多様な人々との関係構築が求められます。
自分の意見を一方的に伝えるのではなく、相手の話を聞き、共通の目標に向かって協力できるかが重要です。
例えば、ゼミで意見が対立した際に、双方の意見を調整し、全員が納得できる解決策を導いた経験は強力なアピールポイントになります。
こうした経験を持つ学生は、入社後も円滑なコミュニケーションを通じてチームをまとめ、プロジェクトを成功へと導ける可能性が高いと判断されます。
課題解決力や巻き込むための戦略性を知るため
企業は、問題が発生した際に自ら課題を見つけ、解決に向けて周囲を巻き込める人材を求めています。
そのため、「周囲を巻き込んだ経験」は、課題解決力や戦略性の指標となります。
ただ目の前の問題を解決するのではなく、どのようにメンバーを動かし、プロジェクトを前進させたかが問われます。
たとえば、文化祭で予算不足が発覚した際に、スポンサーを募るための企画を立案し、メンバーを巻き込んでプレゼンを行い資金を確保したといった経験が該当します。
限られたリソースを最大限に活かし、周囲を巻き込む戦略的な行動が評価されるのです。
企業はこうした学生に対し、困難に直面しても柔軟に対応し、チームを導く力があると期待します。
【他者を巻き込んだ経験 es】そもそもどんな経験のこと?
就活において「他者を巻き込んだ経験」は、単なるチーム参加ではなく、自らの働きかけによって周囲の人の行動や意欲を変え、チームや組織として成果に導いた経験を指します。
このような経験からは、リーダーシップやコミュニケーション力、課題解決力など、社会人に求められる複合的な力を読み取ることができます。
ここでは、他者を巻き込む力の中でも特に重視される5つの視点から、どのように評価されるかを解説していきます。
リーダーシップを発揮した経験
リーダーシップとは、単に命令を出すことではありません。
自ら課題を見つけ、目標を明確にし、周囲の意欲を引き出しながら行動を促す力が求められます。
就活においては、立場に関係なくチームを前進させた行動があれば、それは十分に評価されるリーダーシップとなります。
たとえば、サークルやアルバイトでのプロジェクトを主体的に立ち上げ、周囲に働きかけて協力を得ながら目標を達成した経験などが該当します。
重要なのは、何を目指して、どのようにメンバーの行動を変えたのかというプロセスを明確に語ることです。
コミュニケーション能力を発揮した経験
他者を巻き込むうえで最も基本となるのが、的確なコミュニケーションです。
自分の意見を押し通すのではなく、相手の考えを尊重しつつ、共通の目的に向かって理解と合意を形成する力が問われます。
ESで効果的に伝えるには、対話を通じて相手の納得を得たプロセスや、誤解を解消して関係を築いたエピソードを具体的に示すことが重要です。
たとえば、ゼミやグループ活動で意見が対立した際に、丁寧な説明や質問を重ねて調整に成功した経験は、信頼される話し手としての力を示します。
チームワーク力を発揮した経験
チームの一員として貢献する力も、「他者を巻き込む力」の重要な一面です。
ここで評価されるのは、自分の役割を理解し、チーム全体の目標達成に向けてどう動いたかという行動力です。
リーダーではない立場でも、メンバー間の橋渡しをしたり、モチベーションを支える存在になった経験などは高く評価されます。
たとえば、メンバー間のギャップを埋める調整役を担った、または率先してフォローに回ることでチームの安定に貢献したような行動が挙げられます。
自分の役割を客観的に理解し、周囲と連携して行動した具体例を示しましょう。
課題解決力を発揮した経験
トラブルや困難な状況に直面したときに、自分ひとりで抱え込まず、周囲と連携して解決に導いた経験も強いアピールになります。
問題を見過ごさず、関係者と協力しながら工夫を重ねて打開した行動は、柔軟性や冷静な判断力を印象づけることができます。
ESでは、「何が問題だったのか」「なぜ周囲を巻き込む必要があったのか」「巻き込みによってどんな変化があったのか」の3点を明確にしましょう。
たとえば、イベントでのトラブルに際して、複数部署を調整して解決した経験などは、実行力や周囲との連携力の証明になります。
信頼関係力を発揮した経験
「この人のためなら協力したい」と思わせる関係性を築ける人は、自然と周囲を巻き込む力を持っています。
信頼は一朝一夕で得られるものではなく、普段の行動や姿勢の積み重ねで築かれるものです。
ESでは、地道な行動や継続的な関わりによって周囲の信頼を得た過程を伝えることが効果的です。
たとえば、常に他人をサポートし続けたことで、プロジェクトの中心メンバーとして任されるようになったなどの経験が該当します。
結果として協力を得られたことに加え、「なぜ信頼されたか」「その信頼をどう活かしたか」に言及すると説得力が増します。
【他者を巻き込んだ経験 es】構成
「他者を巻き込んだ経験」をESで伝えるには、出来事のプロセスを丁寧に描くことが不可欠です。
企業は「何をしたか」だけでなく、「なぜそう行動したか」「どう周囲が動いたか」を重視します。
そのため、エピソードの流れをわかりやすく整理できるSTAR法(状況→課題→行動→結果)を用いるのが効果的です。
次の見出しでは、なぜPREP法よりSTAR法が適しているのかについても詳しく解説します。
PREP法ではなくてSTAR法を用いるべき
PREP法は「結論→理由→具体例→再主張」という構成のため、説得的な意見や主張を述べる際には非常に有効です。
しかし、「他者を巻き込んだ経験」を伝える際には、行動のプロセスと変化をしっかり描くことが重要です。
PREP法で書くと、どうしても最初に「結論」や「主張」が来るため、エピソードの背景や他者との関わりの深さが浅くなりがちです。
一方で、STAR法は「何が起きたか(状況)」「何が課題だったか(課題)」「自分はどう動いたか(行動)」「その結果どうなったか(結果)」という構成なので、自然な流れで読み手に伝わりやすく、説得力が高まります。
とくに「行動」を細かく描くことで、主体性・巻き込み力・思考力がリアルに伝わります。
①状況
まずは、エピソードの背景となる「状況」を簡潔かつ明確に伝えましょう。
どのような組織やチームで、どのような目的や課題があったのかを示すことで、読者がその場面を具体的にイメージできるようになります。
たとえば、「大学の文化祭実行委員会で、広報チームの一員として活動していた」「アルバイト先の飲食店で、新人教育の担当になった」など、いつ・どこで・どのような立場だったのかを述べることが重要です。
状況をしっかりと描くことで、これから語る経験の前提が明確になり、その後の展開にも説得力が増します。
②課題や目標
状況を説明したら、次に「どんな課題があったのか」「どんな目標を掲げたのか」を示します。
このパートは、読者にあなたの挑戦の方向性や意図を理解させるための重要な部分です。
たとえば、「チーム内で意見の対立が起こっていた」「新人が職場に馴染めずに早期退職が続いていた」など、あなたが向き合った問題や改善すべき状態を明示してください。
また、どのような結果を目指して取り組んだのか、その目標を設定した理由も併せて伝えると、あなたの視点や考え方がより伝わります。
③行動
このセクションが、STAR法において最も重視されるパートです。
あなたが周囲を巻き込むために、どんな行動をとったのかを具体的に描写しましょう。
重要なのは、ただ結果的にうまくいったという話ではなく、「なぜその行動を選んだのか」「どうやって周囲を動かしたのか」という思考とプロセスを明確にすることです。
たとえば、「定期的なミーティングを設けて意見を吸い上げた」「相手の得意分野を見極めて役割を割り振った」など、具体的な工夫や工夫の背景を丁寧に書いてください。
あなたの主体性・柔軟性・リーダーシップが伝わるように意識しましょう。
④結果
行動の結果、どのような成果や変化が生まれたのかを述べましょう。
ここでは「定量的(数字)」または「定性的(評価や反応)」な結果を明示すると、読み手にインパクトを与えることができます。
さらに、その経験を通して何を学び、どう成長したのか、そしてその学びを今後どのように活かしていきたいかまで言及することで、文章の完成度が高まります。
たとえば、「参加者数が前年比120%に増加し、アンケートでも高評価を得た」「この経験から、人の力を信じて任せることの大切さを学び、今後はチームの強みを活かすマネジメントを目指したい」といったように、ビジョンまで示すと効果的です。
【他者を巻き込んだ経験 es】高評価を得るためのポイント
高評価を得るには、経験の「具体性」と「再現性」を示すことが鍵です。
①どのような課題に対し、あなたが「どう考え、どう行動し」他者を巻き込んだのか、そのプロセスを具体的に記述します。
②あなたの働きかけで、周囲の人の行動やチームの状況が「どう変化したか」まで描写することで、巻き込み力を証明できます。
③最後に、その経験から得た学びを入社後どう活かすかという展望に繋げ、活躍イメージを持たせることが重要です。
エピソードは具体的に
エピソードを具体的に述べることで、信憑性が高まり、選考担当者の興味を引くことができます。
曖昧な表現や広範囲にわたる説明ではなく、自分が最も力を入れた部分や深掘りされても自信を持って答えられる部分に焦点を当てましょう。
一つの経験から多くの学びがあったとしても、全てを詰め込むと内容が薄く見えてしまうため、ポイントを絞って伝えることが大切です。
具体性があれば、そのエピソードがリアルに伝わり、他の就活生との差別化にも繋がります。
周囲の変化を含める
「周囲を巻き込み取り組んだ経験」を述べる際には、自分の行動がチームや周囲にどのような影響を与えたかを具体的に説明しましょう。
たとえば、自分の働きかけでメンバーの士気が向上したり、コミュニケーションが円滑になったり、チーム全体のパフォーマンスが向上したエピソードを含めることで、「巻き込み力」を強くアピールすることができます。
自分だけでなく、周囲の変化を語ることで、リーダーシップや協調性の具体的な成果を示すことができます。
展望を明らかにする
経験から学んだことや、その学びを今後どのように活かしたいかを述べることで、面接官に「この人はどのように貢献してくれるのか」というビジョンを明確に伝えることができます。
たとえば、「この経験を通じて学んだリーダーシップを活かし、貴社のチームをまとめ、組織の利益を最大化させるために貢献したい」といった具体的な展望を示すことで、企業にとってのメリットをアピールできます。
学びを今後どう活かすかを明らかにすることで、自身の成長意欲と企業への貢献意識を強調することが重要です。
企業で生かせることを述べる
冒頭でも触れたように、仕事は多くの人と関わりながら進めていくものです。
そのため、周囲を巻き込んで取り組んだ経験を語る際には、単なる過去のエピソードの紹介で終わらせないことが重要です。
「この経験から何を学び、それを企業でどう生かしていくのか」を明確に伝えることで、企業側に入社後の活躍をイメージしてもらいやすくなります。
たとえば、チームの士気を高めた経験がある場合は、職場でも積極的に声をかけて周囲の意欲を引き出したいというように、行動の展望まで言及しましょう。
さらに、自分の役割や責任をどのように認識していたのかを示すことで、協働に対する姿勢や仕事への向き合い方も伝えることができます。
経験と企業での貢献をつなげることで、より説得力のあるアピールが実現できます。
【他者を巻き込んだ経験 es】注意点
せっかくの「周囲を巻き込んだ経験」も、伝え方を誤ると評価を大きく下げる原因になります。
良かれと思って書いた内容が、実は「独りよがり」「主体性がない」と見なされる危険も。
ここでは、アピールが逆効果になりかねない4つのNGポイントを解説します。
あなたのエントリーシートが当てはまっていないか、提出前に必ず確認しましょう。
要点がまとまっていない
エピソードを盛り込みすぎると、話が冗長になり結論が曖昧になることがあります。
これでは企業の採用担当者にも伝わりにくく、アピールが弱くなってしまうので意識しましょう。
したがって、最もアピールしたい部分にフォーカスし、重要なポイントを明確かつ簡潔に伝えることが大切です。
要点を明確にすることで、企業が理解しやすく、印象に残る自己PRが可能になります。
文字数超過
エントリーシート(ES)には「〇〇文字以内」という文字数指定があり、面接でも「1分で話してください」といった指示が出ることがあります。
この制限を超えると、最低限のルールを守れないと判断される恐れがあります。
指定された文字数や時間内で内容を的確に伝えるスキルは、選考担当者が意外と重視するポイントです。
時間や文字数に収めることで、適切なコミュニケーション能力を示しましょう。
自分勝手なエピソード
自分中心の話や、他人の意見や協力を無視して進めたエピソードは、リーダーシップやチームワークの欠如を示してしまうリスクがあります。
「周囲を巻き込み取り組んだ経験」では、周囲との協力やコミュニケーションが重要視されます。
周囲を巻き込むとは、他人に指示を出すだけでなく、協力し合って目標を達成することを意味します。
チーム全体の成果を重視したエピソードを選び、独りよがりにならないように注意が必要です。
周囲に流されて行動したもの
自分の意思やリーダーシップを発揮せず、ただ周囲に従っただけのエピソードは、主体性やリーダーシップのアピールには不向きです。
主体的に取り組み、周囲を巻き込んで目標達成に導いた経験を伝えることが求められます。
自分がリーダーシップを発揮し、周囲に影響を与えた具体的な行動を盛り込むことで、効果的なアピールができるようになり、企業からの評価も高まります。
【他者を巻き込んだ経験 es】見つからない時の対処法
就職活動において、「周囲を巻き込んだ経験」は企業が重視するポイントの一つです。
しかし、自分がリーダーとして大きな成果を上げた経験がないと感じ、適切なエピソードが見つからないと悩む人も少なくありません。
実際のところ、企業が重視するのは「影響の規模」よりも、「どのように周囲を動かし、物事を進めたのか」という過程です。
ここでは、「周囲を巻き込んだ経験」が見つからないときに試すべき対処法を紹介します。
「小さな影響」を意識する
「周囲を巻き込んだ経験」と聞くと、大勢を動かしたり、組織全体に影響を与えたエピソードを思い浮かべるかもしれません。
しかし、企業が見ているのは「影響の大きさ」ではなく、「どのように周囲に働きかけたのか」という点です。
例えば、アルバイト先で新人スタッフに仕事を教えた経験や、サークルで意見をまとめた場面も立派なエピソードになります。
重要なのは、自分の働きかけによって相手の行動や考え方に変化が生まれた経験を探すことです。
些細な場面でも、自分の行動が周囲にどのような影響を与えたかを振り返ることで、エピソードを見つけやすくなります。
他者と協力した経験を振り返る
「周囲を巻き込む経験」というと、リーダーとして指示を出す場面を思い浮かべがちですが、それだけが該当するわけではありません。
チームで協力しながら目標を達成した経験や、誰かと共に課題を乗り越えた場面も、十分にアピールできる要素になります。
例えば、ゼミのグループ研究で役割分担を調整したり、バイト先でスタッフ同士の連携を強化するための工夫をしたりした経験も有効です。
チームの中で自分がどのような役割を果たし、どのように周囲を動かしていったのかを振り返ることで、適切なエピソードを見つけることができます。
自己分析で過去経験を深ぼる
「周囲を巻き込んだ経験がない」と感じる場合、実は自己分析が十分にできていない可能性があります。
過去の経験を時系列で振り返りながら、どのような場面で自分が周囲に働きかけたのかを整理することが重要です。
例えば、「学業」「アルバイト」「サークル」「ボランティア」など、異なる活動ごとに自分の行動を振り返り、影響を与えた経験を見つけてみましょう。
また、友人や家族に「自分が周囲にどのような影響を与えたことがあるか」を聞いてみるのも効果的です。
自分では気づいていなかった行動が、他人から見ると「周囲を巻き込んだ経験」として評価されることもあります。
【他者を巻き込んだ経験 es】言い換え表現
「周囲を巻き込んだ経験」という表現は、就職活動で頻出する言い回しのひとつです。
しかし、この言葉をそのまま使うだけでなく、自分の経験に合った別の表現に言い換えることで、より具体的で伝わりやすいアピールが可能になります。
企業が求める人物像に応じて適切な表現を選ぶことで、自身の強みを多角的に伝えることができるようになります。
表現を工夫することで、より自分らしい魅力が伝わる文章に仕上げることができるでしょう。
協力して成果を上げた経験
「協力して成果を上げた経験」という言い換えは、チームで目標を達成するために互いに連携し、役割を果たした姿勢を強調できる表現です。
単なる個人の努力ではなく、他者との協力によって生まれた成果を強調することで、協調性や柔軟な対応力をアピールできます。
この言い回しは、協調性を求める職場環境に適しています。
また、周囲との連携を求められる職場に向けた自己PRとして効果的です。
たとえば、学園祭の運営やグループでのプレゼンテーションなどで、それぞれの意見を尊重し合いながら成果を出した経験を述べると説得力が増します。
そのうえで、自分が果たした役割や周囲にどのようにアプローチしたのかを明示することが大切です。
他者をサポートして目標を達成した経験
「他者をサポートして目標を達成した経験」という表現は、チームの中心で引っ張る立場ではなく、支える立場で貢献した経験をアピールする際に有効です。
リーダーでなくとも、サポート役としての行動が成果に大きく寄与したことを示すことで、協調性や気配り、信頼性を伝えることができます。
たとえば、苦手なメンバーに声をかけてフォローしたり、周囲が気づかない課題を先回りして解決するような行動は、チームにとって欠かせない力です。
このような姿勢は、企業内での潤滑油としての役割を担える人材として評価されやすくなります。
具体的なサポートの内容や、それによってどんな結果が得られたのかを丁寧に伝えることで、あなたの価値がより明確に伝わるでしょう。
【他者を巻き込んだ経験 es】巻き込む行動一覧
「周囲を巻き込み取り組んだ経験」を効果的に伝えるためには、単に役割を割り当てるだけではなく、相手が主体的に動きたくなるような環境や意義を提供することが重要です。
以下に、巻き込み力を高めるための具体的なポイントを紹介しますので参考にしてみてください。
相手が動きたくなる意義を提示
人が動くためには、明確な理由や目標が必要です。
「何を目標にするのか」「どんな意味があるのか」といった具体的で明確な目標や目的をチーム全体に伝えることが不可欠です。
これが不明瞭だと、チームの一体感や方向性が曖昧になり、メンバーが主体的に行動することが難しくなります。
したがって、チーム全体が同じ目標に向かって進むためには、具体的なビジョンを示すことが巻き込み力のアピールの鍵となります。
相手を深く理解する
「周囲を巻き込み取り組んだ経験」を語る際には、巻き込みたい相手を深く理解することが重要です。
目標達成に必要なスキルや役割を理解し、それに適した人材を選ぶことが巻き込みの第一歩です。
また、巻き込みたい相手にその取り組みがもたらすメリットや必要性を伝えることで、主体的に参加してもらうことが可能になります。
相手のタスク量やモチベーション、興味関心を理解し、それに対応する行動を取ることも、効果的な巻き込みの一環です。
周囲からの信頼度を高める
周囲を巻き込むためには、日頃から「この人なら大丈夫」と思ってもらえる信頼関係を築くことが大切です。
また、信頼はスキルだけでなく、人間性に基づいても築かれます。
「言ったことは必ず守る」「相手を尊重する」といった行動を心がけることで、周囲からの信頼を得ることができ、結果的に巻き込み力が向上します。
信頼を得ることで、自然と周囲を巻き込むことができるリーダーシップを発揮できます。
行動で示す
周囲を巻き込むためには、リーダー自身が率先して行動することが不可欠です。
情熱を持って取り組み、懸命に努力する姿を示すことで、周囲の人々は自然とその熱意に引き込まれ、「いつの間にか巻き込まれていた」と感じることがよくあります。
自分自身が模範となる行動を見せることで、周囲を巻き込む力を高め、チーム全体の成果を向上させることができます。
【他者を巻き込んだ経験 es】失敗経験を好印象に変える方法
就職活動では、成功体験だけでなく失敗経験も大切なアピール材料となります。
特に「周囲を巻き込んだ経験」において失敗した場合でも、その経験を通して何を学び、どのように成長したかを伝えられれば、好印象を与えることが可能です。
企業は完璧な成功を求めているのではなく、困難に直面したときにどう考え、どう行動を変えていけるかを見ています。
そのため、失敗をきっかけに「巻き込む力」の必要性に気づき、改善のために努力したエピソードを語ることで、成長意欲や行動力を効果的にアピールできます。
結論として失敗した具体的エピソードを述べる
失敗から学んだことを話すうえでは、失敗がどんな背景で発生したのかを最初に具体的に説明することが大切です。
単に「上手くいかなかった」と述べるだけでは伝わりにくく、評価にもつながりません。
プロジェクトの概要や自分の役割、何が原因で失敗したのかを明確にし、その時自分がどのような思考で行動していたのかまで示すことで、説得力が生まれます。
また、自分一人の失敗ではなく、周囲との連携不足や巻き込み方の甘さなど、チームとの関係性にも言及できると、より深みのあるエピソードになります。
失敗を隠さず、事実として冷静に説明する姿勢は、誠実さと自己分析力の高さを伝えることにもつながります。
失敗から学んだ「巻き込む力」の重要性を述べる
失敗経験を語るうえで大切なのは、単なる反省にとどまらず、その経験から何を学び、何に気づいたのかを明確にすることです。
特に「巻き込む力」の重要性に気づいたことを中心に据えると、周囲と連携して成果を上げる力を持っていることを印象づけることができます。
たとえば、計画を独断で進めた結果、周囲の協力を得られなかったことが原因でうまくいかなかった体験から、情報共有や意見の吸い上げが重要であると学んだことを伝えると良いでしょう。
さらに、気づきだけで終わらせず、「自分がどう変わる必要があるのか」といった改善への意欲を述べることが大切です。
学びを次に活かす意識があることを伝えることで、成長できる人材としての魅力が伝わります。
その具体的改善のアクションと結果を述べる
気づきを行動に移せているかどうかは、企業が特に注目するポイントです。
そのため、失敗を経てどのように自分の行動を変えたのか、実際にどんな改善策を実行したのかを具体的に示しましょう。
たとえば、「メンバーの意見を事前にヒアリングする機会を設けた」「こまめに進捗を共有する体制を作った」など、実践的なアクションを挙げることが効果的です。
その取り組みによって、メンバー間の関係性がより円滑になった、協力体制が強化された、プロジェクトが成功に至ったといった成果まで明確に示すことが求められます。
改善に向けた努力と成果が明確であればあるほど、あなたの成長力や主体性が伝わりやすくなり、面接官からの評価にもつながります。
【他者を巻き込んだ経験 es】参考例文集
ここからは周囲を巻き込んだ経験やエピソードの例文をいくつか紹介します。
サークルやアルバイトなど学生時代で一般的な事例別に分けて紹介しているので、是非参考にしてみてください。
アルバイト経験
居酒屋のアルバイトで新人を巻き込み、チームとしての一体感を高めながら、全員が卒業まで一緒に働き続けることができました。
私が目標としたのは、新人が早く職場に馴染み、仕事に自信を持って取り組めるようにすることです。
特にアルバイトの離職率が高い職場だったため、早期退職を防ぎ、チームの安定性を保つことが重要でした。
初めは簡単な業務から始め、少しずつ仕事の幅を広げていくよう指導し、各々が達成感を感じられるように配慮しました。
結果として、新人たちは仕事に自信を持ち、居心地の良い環境で働けるようになりました。
今後も、どのような環境でも他者を巻き込み、チームとしての力を引き出すリーダーシップを発揮し、組織に貢献したいと考えています。
以下の記事ではアルバイト経験を有効に伝えるためのポイントをたくさん紹介してますので是非参考にしてみてください。
体育会
吹奏楽部のパートリーダーとして、同じ楽器のメンバーを巻き込み、コンクールで金賞を受賞することができました。
私の目標は、コンクールで金賞を受賞することで、特に、パート全体の技術力を底上げし、チームとして一つの音楽を作り上げることに重点を置きました。
まず、各メンバーの技術的な課題を共有し、個々の改善点を明確にしました。
その後、全体練習だけでなく、個別指導や小グループでの練習時間を設け、メンバー全員が自分の役割を理解し、自信を持って演奏できるようにサポートしました。
その結果、メンバー全員の技術力が向上し、演奏全体にまとまりが生まれ、金賞を受賞することができました。
今後もこの経験を活かし、どのようなチームでもパフォーマンスを最大化させ、目標達成に貢献したいと考えています。
以下の記事では体育会での経験を有効に伝えるためのポイントをたくさん紹介してますので是非参考にしてみてください。
サークル活動
ボランティアサークルの活動で、学年や国籍を超えた交流イベントを企画・運営し、多くの参加者を巻き込んで成功させました。
このイベントの目標は、インターナショナルスクールの子どもたちと日本国籍の子どもたちが互いの文化を理解し合い、異文化交流を深めることでした。
まず、イベントの内容を子どもたちが楽しみながら異文化に触れられるよう工夫しました。
次に、集客のためにSNSやポスターを活用し、サークルメンバー全員に情報拡散を依頼しました。
イベントは成功し、多くの子どもたちが参加し、互いの文化に触れる貴重な機会となり、参加者からは非常に高い評価を受け、サークルメンバー間の絆も深まりました。
入社後も、様々なチームでリーダーシップを発揮し、組織や事業に貢献できる人材になりたいです。
以下の記事ではサークル活動での経験を有効に伝えるためのポイントをたくさん紹介してますので是非参考にしてみてください。
長期インターンシップ
私はIT企業の長期インターンに参加し、プロジェクトの進行管理を担当しました。
最初はタスクの進捗がばらついており、納期に間に合わない状況が続いていました。
そこで、メンバーごとの負担を可視化し、作業の優先度を整理することで進捗を均等にしました。
また、週次のミーティングを設け、各自の進捗や課題を共有しやすい環境を整えました。
その結果、タスクの遅延が減り、納期通りにプロジェクトを進めることができました。
さらに、チーム内の意見交換が活発になり、各メンバーが自主的に課題解決に取り組む姿勢が生まれました。
プロジェクト終盤では、新たな機能の提案も行い、最終的に顧客満足度の向上にも貢献できました。
この経験を通じ、周囲を巻き込みながらチーム全体の生産性を向上させる力を養いました。
今後もこの経験を活かし、組織全体を動かす視点を持ちながら仕事に取り組んでいきたいです。
さらに、個々のメンバーの強みを活かすマネジメント力も磨きながら、より良い成果を生み出せるよう努めたいです。
以下の記事では長期インターンでの経験を有効に伝えるためのポイントをたくさん紹介してますので是非参考にしてみてください。
ゼミ活動
大学のゼミでは、企業との共同研究に取り組み、私はデータ分析を担当していました。
しかし、最初はメンバーの専門分野が異なり、情報共有が不十分で研究の進行が滞る場面があり、各メンバーの得意分野を活かし、分担を明確にすることで、スムーズな作業フローを確立しました。
また、定期的にミーティングを開き、進捗確認と方向性のすり合わせを行い、結果、企業側から高い評価をいただき、成果報告会でも好評を得ることができました。
研究の過程では、データ分析手法を改良し、より精度の高い結果を得るための工夫も行いました。
この経験から、異なる専門性を持つメンバーをまとめ、チームとして成果を上げる力を身につけました。
社会人になっても、周囲と連携しながら成果を出す姿勢を大切にしたいと考えています。
また、新しい知識や技術を積極的に学び、より高いレベルで研究や業務に貢献できるよう努力していきます。
以下の記事ではゼミ活動での経験を有効に伝えるためのポイントをたくさん紹介してますので是非参考にしてみてください。
ボランティア活動
私は地域の子ども向け学習支援のボランティアに参加し、小学生の学習サポートを行いました。
当初は児童ごとの理解度の差が大きく、一律の指導では効果が薄いと感じました。
そこで、個々の進度に合わせた指導方法を考え、学習レベルごとにグループを編成し、他のボランティアメンバーとも協力し、児童が楽しみながら学べるよう、ゲーム形式の問題を取り入れました。
その結果、子どもたちの学習意欲が向上し、継続的に参加する児童が増えました。
加えて、保護者や地域住民との関係も深まり、より多くの支援を受けることができるようになりました。
さらに、児童の成長を見守る中で、一人ひとりに寄り添う重要性を学び、相手の立場に立って考え、最適なアプローチを模索する力を身につけました。
今後も相手の状況を把握しながら、柔軟に対応できる人材を目指していきたいです。
教育の現場に限らず、相手に寄り添いながら信頼関係を築く力を活かし、幅広い分野で貢献したいです。
以下の記事ではボランティア活動での経験を有効に伝えるためのポイントをたくさん紹介してますので是非参考にしてみてください。
学園祭・イベント運営
大学の学園祭で、実行委員としてステージ企画を担当しました。
当初は出演者との調整や機材の手配がスムーズに進まず、スケジュールが遅れていました。
そこで、各チームの作業状況を一覧化し、担当者ごとに役割を明確にしました。
また、出演者と直接コミュニケーションを取り、希望する条件を整理することで、効率的に調整を進めました。
加えて、学園祭終了後も他のイベント運営で得たノウハウを活用し、後輩たちへ引き継ぐことができました。
さらに、学園祭当日だけでなく、事前の準備段階でもチーム内の連携を強化する取り組みを行い、定例ミーティングでは進捗状況を共有し、タスクの遅れが出た場合は早めにフォローを行う体制を整えました。
その結果、当日は予定よりもスムーズに進行し、イベント終了後も多くの参加者から感謝の声をいただきました。
この経験を通じ、関係者との連携を強化し、全体をまとめる重要性を学びました。
今後もチームを統率し、円滑な運営を実現できる力を活かしていきたいです。
留学
私は半年間、アメリカへ留学し、現地の学生と共同でプレゼンテーションプロジェクトを行いました。
最初は文化や価値観の違いから、意見のすれ違いが多く、議論が進みにくい状況でしたが、互いの考え方を理解するため、積極的にディスカッションの場を設けました。
また、英語が得意ではないメンバーが発言しやすい環境を整えることで、チーム内の連携が深まりました。
さらに、この経験を通じて異文化の中でリーダーシップを発揮し、意見を調整する力を養いました。
プロジェクト終了後も現地の学生と交流を続け、異文化理解をさらに深めることができました。
異なるバックグラウンドを持つメンバーと協力し、共通の目標に向かって努力する経験は、今後のキャリアにも活かせると考えています。
今後も多様な価値観を尊重しながら、協力して成果を出せる人材を目指したいです。
また、グローバルな環境でも適応し、自分の意見をしっかりと発信できる力をさらに伸ばしていきたいです。
以下の記事では留学での経験を有効に伝えるためのポイントをたくさん紹介してますので是非参考にしてみてください。
研究室
私は大学の研究室で、新しい分析手法の導入に取り組みました。
しかし、最初は既存の研究手法にこだわるメンバーが多く、新しいアプローチに対する理解が得られませんでした。
そこで、具体的なメリットや効果をデータを用いて説明し、納得してもらうためのプレゼンを行いました。
また、実験結果を共有しながら、徐々に新しい手法を取り入れることで、研究の精度を向上させました。
研究室全体の意識改革にもつながり、より積極的に新しい手法を取り入れる環境が整いました。
この過程で、単に知識を押し付けるのではなく、相手の意見を尊重しながら納得してもらう重要性を学び、新しい技術や手法を導入する際には、まず周囲の理解を得ることが大切であることを実感しました。
業務においても、論理的に伝える力を活かし、チームの発展に貢献していきたいです。
また、積極的に新しいアイデアを提案し、より良い成果を生み出せる環境づくりに貢献したいと考えています。
学内プロジェクト
私は大学の地域活性化プロジェクトに参加し、地域企業と協力してイベント企画を担当しました。
当初は学生と企業の間に認識のズレがあり、思うように進行しない場面が多くあり、双方の意見を整理し、企業の要望を反映しつつ、学生のアイデアを活かせる企画を提案しました。
さらに、定期的なミーティングを実施し、進捗状況を共有することでスムーズな運営を実現しました。
プロジェクト終了後も地域企業とのつながりが続き、新たなイベントへと発展しました。
また、関係者間のコミュニケーションを円滑にするために、SNSやオンラインツールを活用し、リアルタイムでの情報共有を推進しました。
その結果、会議の効率が向上し、計画の修正や対応が迅速に行えるようになりました。
今後も柔軟な調整力を活かしながら、円滑なコミュニケーションを大切にしていきたいです。
そして、多様な関係者と協力しながら、プロジェクトを成功に導くマネジメント能力をさらに向上させたいと考えています。
趣味
オンラインゲームのチーム運営を通じ、多様な価値観を持つ仲間を巻き込んで目標を達成しました。
私が所属していた約30名のチームは、高難易度コンテンツの攻略を目標としていましたが、メンバー間の実力やモチベーションに差があり、活動が停滞していました。
そこで私は、まず活動に参加できていないメンバー数名に個別に連絡を取り、参加しづらい理由をヒアリングしました。
その結果、スキルへの不安や多忙といった多様な事情があることを把握しました。
この状況をリーダーに共有し、実力や目的に応じて参加できる「攻略組」と「交流組」の2グループ制を提案。
他のメンバーにも協力を仰ぎ、攻略組の練習会や交流組のイベントをそれぞれ企画・運営しました。
結果、各々が自分のペースで楽しめるようになりチームの一体感が復活。
最終的に目標だったコンテンツの攻略も達成できました。
この経験から、相手の立場を深く理解し、誰もが参加しやすい仕組みを考えて働きかけることの重要性を学びました。
以下の記事では趣味での経験を有効に伝えるためのポイントをたくさん紹介してますので是非参考にしてみてください。
高校時代の経験
高校3年生の文化祭で、クラスメイトを巻き込み、全員参加の企画を実現しました。
受験を控え、クラスの多くが文化祭の準備に消極的で、企画(お化け屋敷)の準備が全く進まない状況でした。
クラスの雰囲気も悪化していたため、私は「最後くらい皆で笑って終わりたい」と考え、まず中心メンバー数名に相談し、問題意識を共有しました。
その上で、準備作業を「内装」「音響」「広報」など細かく役割分担し、各係の作業内容と必要時間をリスト化。
「1日30分だけの参加」や「得意なことだけの参加」を可能にする仕組みをクラスに提案しました。
私自身は率先して、皆が敬遠しがちな買い出しや連絡調整役を引き受けました。
すると、参加へのハードルが下がったことで、これまで非協力的だった生徒も少しずつ準備に参加してくれるようになりました。
最終的にクラスが一体となり、企画は大成功。
この経験から、役職がなくても当事者意識を持って働きかけることで、周囲の心を動かし、大きな力を生み出せることを学びました。
【他者を巻き込んだ経験 es】面接対策もしよう!
ESで「他者を巻き込んだ経験」をうまく書けても、面接ではさらに深く掘り下げられるため、事前の対策が欠かせません。
特に、どのように巻き込みを行ったのか、その背景や工夫、周囲の変化を自分の言葉で具体的に説明できるかが重要です。
また、エピソードの一貫性や、入社後にどのように活かせるかを問われるケースも多く、答えに詰まると説得力が下がってしまいます。
面接では「なぜその行動をとったのか」「どのように信頼を得たのか」など細かい視点が見られるため、事前に想定質問を用意し、回答の練習を重ねておくことが成功のカギとなります。
【他者を巻き込んだ経験 es】よくある質問
「他者を巻き込んだ経験」は就活で頻出の質問ですが、リーダー経験がない、ありきたりな話しか思いつかない、オンラインの話でも良いかなど、多くの就活生が疑問や不安を抱えています。
ここでは、ES・面接でつまずきやすいポイントに答える形で、よくある質問とその対策を丁寧に解説します。
リーダーの経験がありません。それでも大丈夫ですか?
リーダーの肩書きがなくても、他者を巻き込んだ経験は十分にアピール可能です。
企業が重視しているのは、立場よりも「周囲にどんな影響を与えたか」「自分から働きかけたか」という行動の中身です。
たとえば、グループワークで意見の対立を調整したり、アルバイトで新メンバーをサポートしてチームの雰囲気を良くした経験も評価されます。
リーダーでなくても、貢献意識や巻き込み力を示せるエピソードを掘り下げて伝えることが大切です。
文字数(200字/400字/600字)ごとの書き方のコツを教えてください。
文字数に応じて、伝える内容の「深さ」と「幅」のバランスを調整することが大切です。
200字なら「状況→課題→行動→結果」の骨組みを端的にまとめ、印象的な行動に絞って伝えましょう。
400字では、背景や具体的な工夫を少し詳しく入れると説得力が増します。
600字では、巻き込んだ相手の反応やチーム全体への影響、そこから得た学びや今後の活かし方まで展開できると、完成度の高いアピールになります。
200字例文
ゼミのグループ研究で、意見の対立による議論の停滞を解消しました。
私はこの状況を改善するため、通常の研究とは別に、全員が自由に意見を交わせる時間を設けることを提案。
議論中は自ら進行役となり、発言が少ないメンバーに話を振るなど、全員が安心して話せる環境を整えました。
結果、相互理解が深まり議論が活性化。
多様な視点を盛り込んだ、全員が納得できる結論を導き出すことができました。
この経験から、環境を整え対話を促すことの重要性を学びました。
400字例文
ゼミのグループ研究において、多様な意見を調整しチームの成果を最大化することに貢献しました。
当初、研究のアプローチを巡ってメンバー間で意見が鋭く対立し、議論が停滞していました。
私は、この状況を乗り越えることで研究の質が高まると考え、改善に乗り出しました。
まず、感情的な対立を避けるため、各自の意見と根拠をホワイトボードに書き出して可視化する場を提案。
全員の意見を客観的に整理し、共通の目標や論点の優先順位を明確にしました。
並行して、発言が少なかったメンバーには個別に声をかけて意見の背景にある考えを丁寧にヒアリングし、全員が安心して議論に参加できる空気を作りました。
その結果、チームの一体感が高まり、最終的に全員が深く納得できる結論を導き出すことができました。
発表では教授から「多角的な視点からの深い考察だ」とA評価を頂けました。
この経験で培った、多様な意見を尊重し建設的な議論へと導く調整力を、貴社でも活かしたいです。
600字例文
ゼミのグループ研究において、チームが抱える課題の根本原因を特定し、周囲を巻き込むことで状況を好転させました。
私が所属するグループでは「地域商店街の活性化策」を研究する中で、議論が停滞していました。
一部のメンバーの発言に終始し、他のメンバーは沈黙。
私はこの原因が単なる意見の対立ではなく、研究の最終ゴールに対する「認識のズレ」と、それを率直に話せない「コミュニケーション不足」にあると分析しました。
このままでは表面的な結論しか出せないという強い危機感から、全員が主体的に関わり、相乗効果を生むチームを目指して自ら議論の潤滑油となることを決意しました。
まず、感情的な衝突を避けるため、議論の前にGoogleフォームを用いて各自が考える研究ゴールとアプローチ案を事前に回収し、客観的なデータとして整理。
話し合いの場では、私が進行役となり、そのデータをもとに全員が合意できる「共通の目標」を最初に確認しました。
その上で、アプローチ方法の「相違点」について、なぜそう考えるのかという背景を一人ひとり丁寧に深掘りしました。
特に、これまで発言しにくそうにしていたメンバーには「〇〇さんの得意なフィールドワークの視点からどう思う?」と、専門性に敬意を払って意見を求め、心理的な安全性を確保することに努めました。
この働きかけにより、メンバー間の心理的な壁がなくなり、各自が持つ知識やアイデアが活発に交換されるようになりました。
議論の質は飛躍的に高まり、最終的にはデータ分析と現地調査を組み合わせた説得力のある活性化策を提案。
教授からは「アウトプットの質だけでなく、チームとして成熟していくプロセスが見事だった」と高く評価されました。
この経験から、課題の根本原因を見極め、適切な仕組みと働きかけで他者を巻き込むことの重要性を学びました。
貴社においても、常に状況を俯瞰し、円滑なチームワークを構築することで組織全体の成果に貢献したいと考えています。
ありきたりな経験でも大丈夫ですか?
「特別な経験がない」と不安に思う就活生は多いですが、日常的な経験でも他者を巻き込む行動が明確であれば、十分に評価されます。
たとえば、アルバイトで新人をフォローしたり、サークルでイベントの準備を助けたなど、誰もが経験する場面であっても、その中でどのような工夫をし、周囲にどんな変化をもたらしたのかを丁寧に語ることが大切です。
他人と違う内容よりも、あなたらしい行動や視点が伝わることの方が、企業にとっては魅力的に映ります。
オンラインでの経験(リモートインターンやゼミ)でもアピールできますか?
オンラインの経験でも「他者を巻き込んだ経験」として十分にアピール可能です。
むしろ対面よりもコミュニケーションのハードルが高い分、課題の特定や連携の工夫が伝われば、評価されやすい傾向にあります。
たとえば、リモート会議で意見が出にくい雰囲気だった場合に、チャットや匿名アンケートなどを活用して意見収集を試みたなど、環境に応じた工夫が重要です。
オンラインだからこそ求められる配慮や行動を、具体的に伝えるようにしましょう。
話を少し盛って話す場合、どこまでが許容範囲ですか?
ESや面接で話を多少「印象的に見せる」工夫は許容されますが、事実を大きくねじ曲げることは絶対に避けるべきです。
許容される範囲としては、「順序を入れ替える」「表現をわかりやすくする」程度にとどめましょう。
たとえば、チーム全体で達成した成果を自分中心に語るのはOKですが、自分が行っていない行動を加えたり、成果を実際以上に誇張するのはNGです。
面接では深掘りされるため、盛りすぎると矛盾が生じ、信頼を失うリスクがあります。
「伝わりやすさ」と「事実の正確さ」のバランスを意識しましょう。
まとめ
「周囲を巻き込んだ経験」は、仕事における協働力や主体性を伝えるうえで非常に有効なアピール材料です。
単なる成功体験だけでなく、失敗からの学びや改善のプロセスまで丁寧に語ることで、成長意欲や実行力を印象づけることができます。
また、表現を工夫して言い換えることで、自分の強みをより具体的に伝えることも可能になります。
自ら行動を起こし、他者を動かした経験は、どの業界においても求められる資質です。
さらに、入社後にその経験をどのように生かせるのかまで伝えることで、企業にとって魅力的な人材として印象づけることができます。
本記事を参考に、自分らしいエピソードを整理し、伝わる自己PRにつなげていきましょう。

_720x550.webp)
でアピールする際の注意点_720x550.webp)



_720x550.webp)


_720x550.webp)

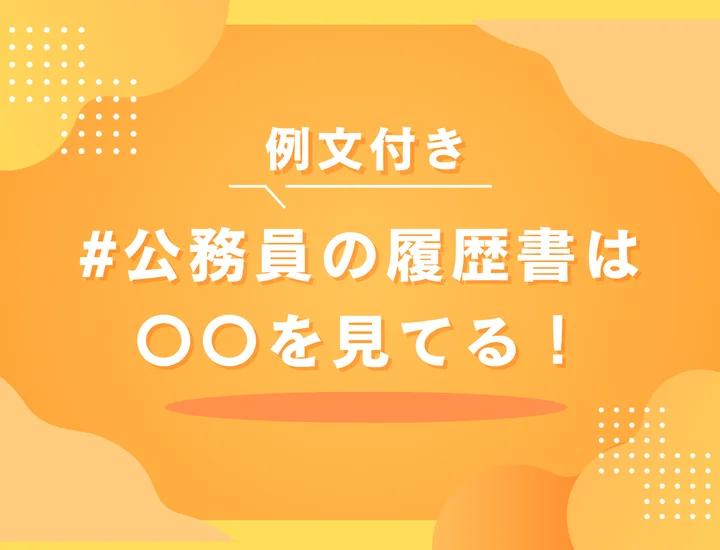

_720x550.webp)




