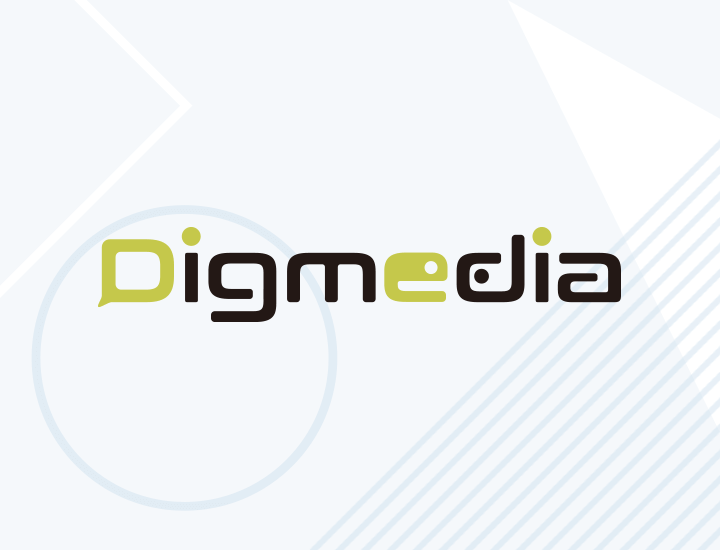就活にあたって就活の軸をあらかじめ定めることで、より自分に合った企業を選び出すことができるようになります。
就活の軸をもつことで、企業を選ぶ基準として入社後のミスマッチを避け、早期離職などのリスクを避けることができます。
気になる企業の共通点を探ってみるなど、就活の軸がはっきりしないときは、自分が企業や仕事に対して何を求めているのかを理解し、それをもとに改めて企業選びをしていきましょう。
はじめに
就活をスタートさせるにあたり、ノウハウ本やサイトには就活の軸をまず決めようと紹介されています。
当たり前のように用いられる言葉ですが、就活の軸と言われても、ピンとこない方も多いのではないでしょうか。
就活の軸は企業の面接において質問されることがあるのです。
一体どんなもので、どんなふうに決めればいいものなのか詳しく理解していきましょう。
就活の軸って何?
まず就活の軸を定める必要が、就活をスタートするときにはあると言われることがあります。
何も知らずに就活をスタートさせるなら、多くの人がやってみたい仕事や職種、気になる企業から探し始めるのではないでしょうか。
ですが、就活を成功させるためには企業を選ぶよりも先に、就活の軸をしっかり持っておくことを言われています。
内定を得た先輩たちのインタビューでも、就活の軸というワードがよく登場します。
一体、どんなものなのでしょうか。
①何に興味があるか
就職活動において「自分が何に興味があるか」を軸にすることは、自己のキャリアパスを決定する上で非常に重要です。
自分の興味や情熱を理解することで、仕事におけるモチベーションを高め、長期的なキャリアの満足度を向上させることが可能になります。
このアプローチは、就職後の職場での適応や、仕事を通じての成長にも大きく影響します。自己分析を深め、本当に情熱を感じる分野を見つけ出すことで、就職活動はより具体的で目的意識のあるものになります。
②スキルや強みが発揮できる環境
就職活動において「自分のスキルや強みが発揮できる環境」を重視することも大切です。
能力や資質を活かせる職場を選ぶことで、仕事への適応力が高まり、長期的にキャリアを築く上での基盤となります。
また自分の得意分野を生かせる仕事を見つけることは、モチベーション維持にも繋がり、プロフェッショナルとしての成長を促してくれます。
また、自己のスキルセットと職場の要求がマッチすることは、仕事の成果を最大化し、キャリアアップの機会を広げることにも役立ちます。
③モチベーションになるものか
就職活動において「自分のモチベーションにつながるかどうか」を軸にすることは、長期的な職業生活での充実感と仕事での成功に繋がるという意味で大切です。
仕事に対する情熱や内発的な動機付けは、日々の業務への取り組み方やキャリアの進展に大きく影響します。
自分が本当に興味を持ち、熱意を感じる仕事を見つけることができれば、困難な課題に直面しても乗り越える力となり、持続可能なキャリアを築くための土台となります。
【就活の軸の決め方】企業選びの軸との違い
企業選びの軸と就活の軸の違いは、前者が「どの企業で働くか」に焦点を当てるのに対し、後者は「どの業界や職種で働きたいか」を中心に考える点にあります。
企業選びでは、企業の文化、価値観、成長性など具体的な企業特性を基準に決めることが多いでしょう。
一方で、就活の軸では、広い視点から自分が情熱を持てる業界や、自分のスキルや興味を生かせる仕事を探します。
この違いを理解し、両方の視点から自己のキャリアを考えることが、充実した職業生活への第一歩となります。
【就活の軸の決め方】就活の軸を企業が聞く理由
ここからはそもそも企業が就活の軸を聞いてくる理由について詳しく解説していきます。
漠然と就活の軸を決めて面接などに臨む人も多いのですが、相手側の意図や質問背景を知っておくだけでも他の候補者と比較しても有利に就活を進められます。
以下で紹介する項目を全て把握した上で効果的な就活の軸を定めることで、内定への道も開けてくる可能性が高まりますので是非参考にしてみてくださいね。
キャリアビジョンを知りたい
企業が就活生の軸を聞くのは、応募者が持つキャリアビジョンを理解し、その人が自社で長期的に活躍し得るかを見極めるためです。
採用はその瞬間だけでなく、採用後の社員としての成長や貢献も視野に入れています。
応募者が自社のビジョンや価値観に共感し、将来のキャリアを自社で実現しようとする意欲があるかどうかを確認することで、入社後早期に離職するリスクを減らしているのです。
これは双方にとって最適なマッチングを見つけ出すために重要なことです。
価値観を知りたい
企業が就活生の価値観を重視するのは、採用後の社内での適応やトラブルを避け、長期的な関係を築くためです。
就活生の価値観が企業の事業理念や経営理念と合致するかを確認することで、採用後も安定して働き続けられるかを見極めようとしています。
また、就活生の性格が既存のチームメンバーや企業文化にフィットするかも重要視されます。
この過程を通じて、企業は自社にとって最適な人材を見つけ出そうとしているというわけです。
志望度を測るため
企業が就活生の軸を確認する主な目的の一つは、応募者の志望度を測るためです。
就活生が企業選びにおいて重視している点が、他社でも当てはまる一般的なものであれば、その応募者の企業に対する熱意や志望度が低いと判断される可能性があります。
逆に、応募者の軸がその企業の特色や強みと密接に結びついている場合、高い志望度を示していると評価されます。
このように、企業は応募者の就活の軸を通じて、自社への興味の深さやマッチング度を見極めようとしています。
【就活の軸の決め方】軸が決まる3STEP
では、どのようにして就活の軸を決めればいいのでしょうか。
「自分はこういうことがしたい」、「こんな自由な人生を送りたい」といった具体的な目標や目的があればいいのです。
入りたい企業ありきの企業バイアスもかからないので、より自分の理想を実現できる企業選びが可能となります。
さらにも、学生さんの多くは憧れている企業や入りたい企業はあっても、明確な軸を決められない方が少なくありません。
軸の決め方で悩んだ場合に、どうすれば決められるのか見ていきましょう。
STEP1:過去経験を振り返る
就活の軸を決める最初のステップとして、「過去経験の振り返り」は極めて重要です。
幼少期から現在に至るまで、自分が経験してきた出来事やその際に抱いた感情を振り返ることで、自己の好みや興味が何に向いているのかを深く理解することが可能になります。
この過程では、喜びや悲しみなど、幅広い感情を伴う出来事を思い出し、それらを通じて自分自身が何を価値あると感じ、どのような活動に情熱を感じるのかを探求します。
またこのようにすることで、将来何をしたいのか、どのようなキャリアを築きたいのかのヒントを見つけ出すことができます。
自分自身を深く理解することは、自分に合ったキャリアパスを選択する上で不可欠であり、自己実現に向けた第一歩となります。
STEP2:どう働きたいかを考える
就活の軸を決める次の段階は、「どう働きたいかを考える」ことです。
自己分析を深めつつ、希望する働き方についても具体的に検討します。
これには、給与水準、業務の内容、勤務形態、企業の規模や文化、ワークライフバランス、転勤の有無など、様々な就労条件を考慮する必要があります。
個人の価値観や生活スタイル、キャリアに対する期待を踏まえ、何を最も重視するかで優先順位を設定すると良いでしょう。
例えば、給料よりも休日の多さや柔軟な働き方を優先する人もいれば、キャリアアップの機会を最優先に考える人もいます。
自分にとって最適な働き方を明確にすることで、求める企業像がより鮮明になり、目指すべき企業選びに役立ちます。
自分の望む働き方を優先順位に応じて整理し、それに合致する企業を探すことが、満足のいく就職活動の鍵となります。
STEP3:合体させる
就活の軸を決める過程の最終段階では、「自分の過去を振り返る」ことと「どう働きたいかを考える」ことの二つの視点を統合します。
この二つを融合させることで、「自分が実現したいこと」と「理想の働き方」を兼ね備えた企業を見つけ出すことが可能になります。
自分の情熱を追求でき、かつ望む働き方ができる企業は、必ずしも容易には見つからないかもしれません。
ただ、この二つの要素から優先順位を設けることで、目指すべき方向性がより明確になります。
全ての条件を完全に満たす企業を見つけることは難しいかもしれませんが、自分の価値観やキャリアビジョンに最も合致する選択肢を見つけようとすることが大切です。
軸をもっているといいこと
就活の軸を考えるまでもなく、本命企業も第二志望や第三志望まで決まっているから、あえて考える必要はないと思う方もいるかもしれません。
こんな仕事がしたい、こんな働き方がしたいから、この企業しかないと決められるなら就活の軸をわざわざもたなくても就活はできます。
就活の軸をもっておくと、いくつかメリットが生まれます。
どのようなメリットが生まれるのか確認しておきましょう。
面接で深堀りされた時に一貫性がもる
好きな企業、憧れの企業、有名な企業だけの基準で選んでしまうと、企業リサーチも十分に行われていないため、面接で深堀りされた時に答えに窮したり、曖昧で抽象的な返答に終始しがちです。
あらかじめ就活の軸を定めてから、それに合う企業を探す場合には企業研究を行い、企業に関する理解を深めることができます。
また、気になる企業の共通点から就活の軸を設定するにあたっても、企業研究をしっかり行うことになるため、ただ漠然と有名な企業に就職したいだけの基準で選ぶより、企業のことをよく知ることが可能です。
これにより、面接で深堀りされても、言葉に窮することなく一貫した回答が可能となります。
入社後の後悔が少なくなる
こんな仕事がしたい、こんな働き方がしたい、こんな活躍をしたいと就活の軸を定めておけば、それを実現できる企業を探し出すことが可能です。
企業研究を十分に重ねた上で選ぶには、就活の軸に合う企業かどうか見定めなければならないため、入社後のミスマッチを抑えることができます。
仕事が合わない、仕事のやり方が合わない、職場の雰囲気が合わないなどのミスマッチのリスクを避け、早期離職をしたり、我慢しながらくすぶり続けるなど不満を抱えながら働き続けずにすみます。
就活の軸をもたずに、企業について十分に理解せず、表面的なイメージだけで入社してしまうと、こんなはずじゃなかったとなりやすく、せっかく就職したのにすぐに辞めてしまうこともあるため注意しましょう。
まとめ
就活にあたって就活の軸をあらかじめ定めることで、たくさんの企業の中から、より自分に合った企業を選び出すことができるようになります。
入社後のミスマッチを避け、早期離職などのリスクを避けるためにも、企業を選ぶ基準として就活の軸をもつことが大切です。
就活の軸が思い浮かばない場合には、気になる企業の共通点を探ってみるなど、自分が企業や仕事に対して、どのようなことを求めているのか、よく検討しましょう。