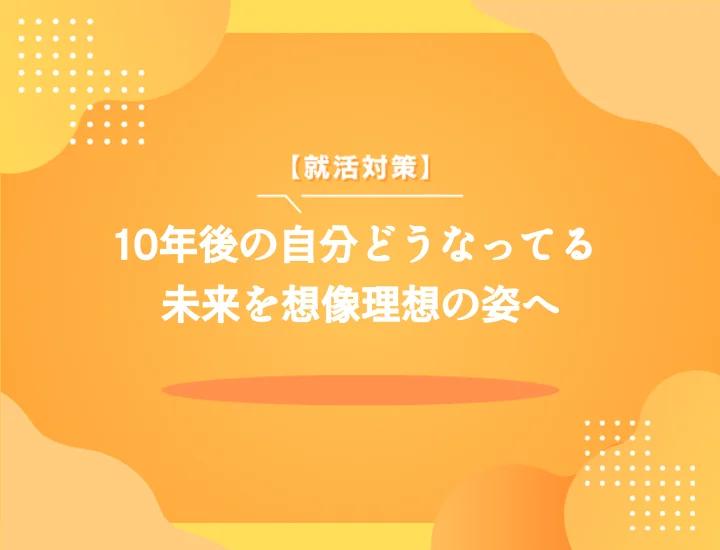HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
エントリーシートの得意科目欄「何を書こうかなぁ…」なんて悩んでいませんか。
中には「重要でもないだろうし、適当に英語とか書いとくか…」なんて事を考えている人もいるかもしれませんね。
けれどちょっと待った!得意科目欄は適当に書いてはいけません。
下手をすると得意科目欄のせいで不採用なんて事もあり得るからです。
得意科目のせいで不採用…なんて事にならないよう、得意科目の選び方について徹底解説しています。
さらには面接で得意科目について聞かれたときの受け答えについてもご紹介。
得意科目に何を書くか決めていないのならば、ぜひ本記事をチェックしてみてください。
役立ち情報がきっと見つかるはずです。
目次[目次を全て表示する]
【エントリーシート得意科目】そもそもなぜエントリーシートで得意科目を聞かれるの?
そもそもなんでエントリーシートで得意科目を聞かれるのでしょう?そこには大きく分けて2つの意味があります。
それぞれのポイントをチェックしてみたいと思います。
就活生の人柄を見るため
企業が得意科目を尋ねる理由の一つは、学生の人柄や価値観を知るためです。
成績の良し悪しではなく、「なぜその科目が得意なのか」「どんな学び方をしていたのか」といった背景に、個性や考え方が表れるからです。
たとえば、歴史が得意であれば物事を時系列で捉える力、数学なら論理的思考が強みとして見られる場合もあります。
学業の中でどのように自分らしさを発揮してきたかを、自然に伝えられるチャンスとも言えます。
職業適性を確認するため
得意科目を通じて、志望する職種や業務内容とのマッチ度を判断することも目的の一つです。
たとえば理系の職種を希望する場合に、物理や化学が得意であれば、実務との親和性が高いと評価されることがあります。
また、科目に対する興味の持ち方や勉強の仕方から、その人がどんな働き方を好むのかも読み取れる可能性があります。
実際の仕事に役立つ知識やスキルがあれば、即戦力として期待されることもあります。
就活生を評価するため
得意科目の設問は、学生を多角的に評価するための一環でもあります。
面接だけでは測りきれないポテンシャルや特性を、科目選びやその説明を通して探ろうとしているのです。
たとえば、得意科目の理由に「興味があって自主的に深く学んだ」といった姿勢が見られれば、自走力や学習意欲の高さとして評価されます。
一つの項目から、学生の成長性や取り組み方の特徴を読み取る材料とされるのがこの質問です。
コミュニケーション能力をチェックするため
ESに書いた「得意科目」は、面接で話題にされることが少なくありません。
そのため、単に好きな理由を述べるだけでなく、聞き手に伝わりやすい構成や表現ができているかを見られる可能性があります。
面接ではアイスブレイクとして使われることもあり、そこから自然な会話の展開が生まれるケースもあります。
内容を相手目線で整理し、話しやすいテーマとして活用することで、印象アップにつながるでしょう。
【エントリーシート得意科目】考えるポイントとは?
ではエントリーシートの得意科目選びは何を基準に考えればよいのでしょう?そのポイントについて解説していきたいと思います。
根拠があるか
まずは、得意といえる根拠が示せるような科目を基準として選びましょう。
単に「成績が良かった」「好きだから」と述べるだけでは説得力に欠け、他の応募者との差別化も難しくなります。
例えば、学業成績だけでなく、レポートや研究活動、資格取得、ゼミでの発表経験など具体的なエピソードを示すことで、その科目に対する理解の深さや主体的な取り組み姿勢を伝えられます。
また、得意科目と志望する業界・職種との関連性を明確にすれば、一層効果的になります。
希望職種とつながっているか
採用担当者はあなたの得意科目が「自社でどのように活かすことができるか」を見ています。
そのため自分が目指している業界と自分の得意科目の関連性を見つけてアピールすることが大切であるといえます。
希望する職種の業務内容と、得意科目を通じて得た学びやスキルを戦略的につなげることが不可欠です。
学んだことが仕事内容に直接活かせる場合、アピールとして効果的に相手に伝えることができます。
科目に対して深い知識があるか
ESに書いた内容は面接で深掘りされる可能性があります。
そのため、大学での専攻や取得資格など、自分が深い知識を持つ科目を選ぶことが重要です。
表面的な内容や理解の浅い科目を書くと、面接で答えに詰まってしまう恐れがあります。
また、成績や評価といった「他人からの評価軸」だけでなく、「自分がどのように感じ、どのように取り組んだか」という「自分軸」を意識することで、面接時に話を広げやすくなります。
自分らしさが表しやすい科目を選ぶ
得意科目を選ぶ際には、単に点数が高いかどうかではなく「自分らしさが表れるか」を意識することが大切です。
たとえば国語が得意なら「文章を整理して分かりやすく伝える力」、物理なら「仮説を立てて検証する姿勢」、体育なら「協調性やリーダーシップ」といった形で、その人の特性や考え方が伝わります。
重要なのは知識や成績のアピールではなく、「その科目を通して何を学び、どのように成長したか」を具体的に語れることです。
エピソードを交えて説明できれば、面接官に人柄や強みが伝わりやすく、他の応募者との差別化にもつながります。
【エントリーシートの得意科目】得意科目がない人はどうするの?
エントリーシートで「得意科目」を尋ねられても、「特別得意なものがない」と悩む人は少なくありません。
しかし、得意科目は単に成績が良かった科目を意味するだけではなく、興味や努力があったことを伝えるチャンスでもあります。
ここでは、得意科目が思い浮かばない人がどう選べばよいかを、2つの視点から解説します。
自分の興味、関心があるもの
得意科目が思い浮かばない場合は、まず過去の授業や学びの中で「興味を持てた内容」がなかったかを振り返ってみましょう。
たとえ成績が平均的であっても、授業に対して積極的に参加していた、講義の内容に強く関心を抱いたという経験があるなら、それは立派な得意科目と言えます。
「なぜその科目に惹かれたのか」「どんな視点で学んでいたか」といった関心の深さを説明すれば、十分に魅力ある自己PRになります。
得意科目=成績上位とは限らないため、自分の学びの姿勢や好奇心をもとに選ぶのがポイントです。
エピソードが伝えやすいもの
もう一つの選び方は、「努力の過程が語れる科目」を得意科目として選ぶ方法です。
たとえば、苦手だったけれど克服するために工夫した経験がある、課題提出に向けて継続的に勉強を続けた、といったエピソードは面接での話題として非常に有効です。
このように、自分の頑張りや成長を具体的に伝えられる科目であれば、それが得意科目として十分に通用します。
重要なのは「その科目にどう向き合ったか」を自分の言葉で表現することであり、成績だけで判断する必要はありません。
伝えやすく、かつ自分らしさが伝わる科目を選ぶと良いでしょう。
【エントリーシートの得意科目】思いつかないときの対処法
就活で得意科目を聞かれても「特に思い浮かばない…」と悩む人は多いです。
しかし、必ずしも突出した成績や専門性が必要なわけではありません。
少し視点を変えれば、自分の強みにつながる科目は見つかります。
ここでは得意科目が思いつかないときの考え方を3つ紹介します。
成績が良かった科目を振り返る
得意科目がすぐに思い浮かばない場合、まずは学生生活を通じて成績が良かった科目を振り返ってみましょう。
必ずしも学年トップの成績である必要はなく、テストで安定して高得点を取れていたなども立派な「得意」の基準になります。
また、成績が良いという事実は数字や評価として裏付けがあり、客観的にアピールしやすいのも強みです。
面接官から「なぜ得意なのか」と聞かれても「授業内容を理解するのが早く、クラスメイトから質問を受けることも多かった」といった具体的なエピソードにつなげやすくなります。
まずは過去の成績表や提出課題を振り返り、自分の強みを掘り起こしてみましょう。
自分のアピールポイントから逆算して考える
得意科目は単に「勉強ができた」という結果だけでなく、自分のアピールポイントと関連づけて選ぶのが効果的です。
「論理的思考力」をアピールしたいなら数学や理科、「発想力」を強調したいなら美術や国語といった具合に、自分が面接で伝えたい長所から逆算して科目を選ぶのです。
こうすることで、単なる得意科目の紹介にとどまらず、自己PRと一貫性を持たせることができます。
面接官にとっても理解しやすく、「この人は自分を客観的に分析できている」と好印象につながります。
【エントリーシートの得意科目】ESの構成のコツ
エントリーシートで得意科目を聞かれたとき、ただ好きな科目名を挙げるだけでは効果的なアピールにはなりません。
企業が知りたいのは、その科目から何を学び、どう活かしていけるのかという点です。
ここでは、得意科目を効果的に伝えるために押さえておきたい4つの構成を紹介します。
書き方①結論から書く
エントリーシートにおいては、文章の最初に結論を述べることで、採用担当者にとって理解しやすい内容になります。
冒頭で「私の得意科目は〇〇です」と明言することで、その後に続く理由やエピソードが読み手にとって明確な文脈になります。
就活では多くの書類が短時間で読まれるため、要点を先に示すことで、印象に残る内容にすることができます。
書き方②理由を書く
得意科目を挙げたあとは、なぜそれが得意になったのかという理由を述べることが重要です。
単に「得意です」と伝えるだけでは説得力に欠けるため、興味を持ったきっかけや学び始めた経緯、または工夫して努力した点などを盛り込みましょう。
こうした背景を語ることで、物事への取り組み方や姿勢が伝わり、企業はその人の人柄や成長力を読み取ることができます。
また、自分自身の興味や価値観が浮かび上がる内容にすることで、職種や企業との相性を伝える要素にもなります。
書き方③具体的なエピソードを書く
得意科目を裏づけるためには、できるだけ具体的な話をすることが不可欠です。
たとえば、その科目で高成績を修めたこと、難しい課題に挑戦した経験、他人と協力して成果を上げた実例など、具体的な行動を示しましょう。
このような経験を通じて、どのような力を養ったのか、どのような工夫をしたのかを丁寧に描写することで、説得力と信頼性が高まります。
また、過程を重視することで、自分自身がどう成長したのかも伝えられます。
単に「得意だから」という主張ではなく、根拠となるエピソードを提示することで、企業にとって魅力的な人物像を描きやすくなります。
書き方④将来の仕事にどう活かすかを書く
得意科目を述べた後は、その学びやスキルを将来の仕事にどう活かせるのかを説明することが求められます。
これは企業が「この学生が入社後にどのように貢献できるのか」をイメージする手がかりになる部分です。
たとえば、英語が得意なら「海外の取引先とのやり取りに強みを活かせる」、数学なら「数値分析やロジカルな提案に役立つ」といった形です。
具体的に職務内容や企業の事業と関連づけて説明することで、実務への適性や意欲が伝わりやすくなります。
【エントリーシート得意科目】例文をチェック|得意科目のエピソードについて話してみる
得意科目について面接で質問された場合、どんな受け答えが良いのでしょうか?文系・理系それぞれについて、その受け答えをチェックしていきたいと思います。
例文1.英語
私の得意科目は英語です。 中学生の頃から英語の音に魅了され、自然と語彙や表現に関心を持つようになりました。 大学ではTOEICの学習に力を入れ、スコアは835点を取得しました。 また、英語のプレゼンテーションを行う授業では、自分の考えを明確に伝える力を磨きました。 英語が得意であることを活かして、ゼミでは海外論文の翻訳や発表を担当し、クラス内でも情報共有の役割を担ってきました。 単に読み書きができるだけでなく、実際に使う中での応用力を意識し続けてきました。 今後は、英語を用いたコミュニケーションを通じて、グローバルな環境でも信頼される人材を目指していきたいと考えています。
例文2.数学
私が得意としているのは数学です。 高校時代から数理問題に取り組むことに楽しさを感じ、解き終えた時の達成感に魅了されました。 大学の経済学部に進学してからも統計学や計量経済学など、数式を扱う授業には特に力を入れてきました。 中でも、実データをもとに回帰分析を行ったゼミの課題では、仮説検証の大切さを実感しながら論理的に物事を組み立てる力を養いました。 数字を用いて事実を読み解き、それを根拠として相手に伝える姿勢は、将来どのような職種においても不可欠だと考えています。 複雑な課題に対して冷静に考え、着実に進めていく力を持っていることが、私の強みのひとつです。
例文3.国語
私は国語を得意科目として挙げています。文章を読むことが日常の一部となっており、内容を読み取るだけでなく筆者の意図や文脈の流れを深く考察する癖が身についています。大学では文学だけでなく、評論文や新聞記事を読み解く演習も積極的に取り入れてきました。授業の中でディスカッションを行う機会が多く、そこでの意見交換を通じて表現力や説得力のある話し方も磨くことができました。また、学外でもブログ形式で書評を発信しており、文章で思考を整理する習慣があります。情報の本質を捉え、相手に伝わる言葉で伝えることができる点は、ビジネスにおいても役立つ力だと実感しています。
例文4.心理学
私が最も関心を持ち、成績も優れていたのが心理学です。 高校時代に人間関係について悩んだ経験があり、そこから人の心の動きに興味を持ったことが学びの出発点でした。 大学では認知心理学や行動経済学を中心に履修し、特に「思考のバイアス」に関する研究では、グループワークで調査分析も行いました。 ゼミでは毎週研究論文を読んで発表を行っており、理解力と発信力の両方を鍛えることができました。 また、心理的要素を考慮しながらチームの関係性を構築する方法を学んだことは、組織内での円滑なコミュニケーションにもつながると考えています。 心理学を通して得た洞察力は、対人関係の構築や顧客対応にも活かせると確信しています。
例文5.プログラミング
私の得意科目はプログラミングです。 大学入学後に初めて触れた言語がPythonで、はじめは難しさを感じたものの、試行錯誤を繰り返すうちに問題解決のプロセスに魅了されました。 講義や課題に加えて、独学でWebアプリケーションの開発にも取り組み、簡単なToDoリストの作成やAPIの実装まで経験しています。 また、ハッカソンにも参加し、チームで一つのプロジェクトを完成させる達成感を味わいました。 個人で完結するだけでなく、協働の中で役割を果たす力が問われる点に、今後の仕事との共通性を感じています。 将来は、ユーザー視点で価値あるプロダクトを作れる技術者を目指して努力を続けていきたいと考えています。
例文6.流体力学
私は流体力学を最も得意としており、大学での専門科目の中でも特に力を入れて学んできました。 高校時代に水の動きに関するドキュメンタリーを見たことをきっかけに、自然現象を数式で表現する物理分野に強く惹かれるようになりました。 大学では数値シミュレーションの演習に取り組み、流速分布や圧力変化を予測するモデルを構築する課題で高評価を得ました。 演習レポートでは、精密さと再現性の高さが評価され、指導教員からも発表を推薦された経験があります。 複雑な現象を理論的に解析する過程は、自分の思考を体系化する力や根拠を持って判断する力を育ててくれました。 研究を通して養った視点を、今後の実務でも応用していきたいと考えています。
【エントリーシート得意科目】これはNGな得意科目の選び方
続いてはこれはNGな得意科目の選び方について解説していきたいと思います。
得意科目を選んだ際、以下に当てはまっていないか、しっかりとチェックしておきましょう。
当てはまる…という場合、違う科目を選んだ方が無難です。
特にエピソードが無い科目
ここまで見てきた通り、得意科目は面接で質問される可能性があります。
その時に「ただ得意なんです。理由は特にありません」では会話が全く盛り上がらないですよね。
これでは「コミュニケーション能力が低い」と判断されてしまいます。
面接は言葉のキャッチボールを繰り返す事で成り立ちます。
受けたボールは相手が受け取りやすいように投げ返さなくてはなりません。
特にエピソードが無い科目は避けるようにしておきましょう。
エピソードの種類としては「得意になったきっかけ」や「実際の研究でどう使っているのか」などです。
さらにそこから「この部分が仕事で活かせる」という事まで話せますとなお良しです。
実際には得意でない科目
得意科目ですから、得意でない科目を書いてはいけません。
「英語が得意だと何かと良いかな…」なんて事を思って、得意でもないのに「英語」と書いたらどうなるでしょう?面接で「TOEICは何点ですか?」なんて質問をされるかもしれません。
もっと最悪なのが「英語が得意な人」という理由で雇ったのに、英語が全然できないパターンです。
「この文面を英語に訳してこの人にメールで送っといて」なんて言われたときに「すいません…英語はちょっと苦手でして…」なんて言い出せないですよね。
下手をすると試用期間中に解雇されてしまうかもしれません。
この場合、エントリーシートに書いた嘘が原因ですから、不当解雇として訴える事もできません。
エントリーシートには絶対にウソを書いてはいけません。
業種に関係がない科目
就職活動で得意科目を伝える際、その内容が志望する業種と直接関係がない場合でも、工夫次第で十分にアピール材料になります。
重要なのは、その科目から何を学び、どのような姿勢やスキルを身につけたのかを明確にすることです。
たとえば、音楽が得意な人なら「継続的な練習で集中力や努力を培った」といった形で、仕事に通じる要素に落とし込む必要があります。
「なし」と書くのは避けよう
就活で「得意科目」の欄に「なし」と記入するのは絶対に避けたい行為です。
なぜなら、採用担当者に「自分にはアピールできる強みがない」「努力や工夫をしてこなかった」と受け取られやすく、評価を大きく下げてしまうからです。
実際には突出した成績でなくても構いません。
授業を通じて工夫した経験や、勉強する中で得られた気づきなども立派なアピール材料になります。
例えば「数学が得意ではないが、苦手を克服するために毎日30分復習を続け、結果的に成績が大幅に伸びた」などのエピソードは、粘り強さや継続力の証明になります。
面接では得意科目が会話のきっかけとなるため、「なし」とせず、必ず具体的な科目を選び、自分らしいエピソードに結び付けて伝えることが重要です。
企業の職種との乖離を避けよう
得意科目を記入する際は、志望する企業や職種とのつながりを意識することが欠かせません。
もし全く関連性のない科目を挙げてしまうと、「この人は仕事との接点を意識できていない」と思われ、採用担当者の評価が下がる可能性があります。
ただし、直接関係が薄い科目でも工夫の余地は十分にあります。
例えば、音楽が得意なら「継続的な練習で集中力と努力を培った」、歴史が得意なら「資料を読み解く力や論理的に説明する力を養った」といった形で、ビジネスに応用できるスキルへと落とし込むことが可能です。
大切なのは、科目そのものの知識を誇示することではなく、そこから得た学びや姿勢を仕事にどう活かせるかを伝えることです。
この工夫ができれば、面接官に強い印象を残すことができます。
まとめ
エントリーシートの得意科目について、なぜ問われるのかという理由から、得意科目の選び方、面接での受け答え例、そしておすすめできない得意科目について見てきましたが、気になる情報は見つかりましたか?
得意科目は志望理由や自己PRと比較しますと、記入欄も小さく、それほど重要ではなさそうに見えるものです。
けれど、エントリーシートに書く以上は何かしらの判断基準となり得ます。
得意科目に書いたちょっとした事がきっかけで内定をつかむ事もありますし、得意科目をきっかけとして不採用になるなんて事もありえます。
本記事でご紹介してきたポイントをしっかりと押さえて、自分なりの得意科目を見つけ出してください。
そのひと手間が素敵な未来へと繋がっています。

_720x550.webp)