
HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
「理系大学生は文系大学生より就職に有利?」
「理系大学生の就活はいつから始めればいい?」
就活する際にさまざまな疑問を持つ理系大学生もいるでしょう。
いつからどんな準備を始めればいいか、大学院に進学するか否か、悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
本記事では、大学卒業後もしくは大学院卒業後に就職をするメリット、それぞれいつから就活準備や本格的な就活を始めればいいか、就活準備の時期にしておくこと、などを解説します。
目次[目次を全て表示する]
【理系就活】就活はいつから始めるべき?
理系就活は早めの着手が有利です。
学部生は大学3年の夏から業界研究やインターン応募、ESのたたき台作成を始めましょう。
大学院生は期間が短めのため、修士1年の夏から研究概要の言語化と企業研究を進めるのが安心です。
スケジュール管理を徹底し、SPI対策や模擬面接にも早期に着手しましょう。
【理系就活】学部生の就活スケジュール
理系学部生の就職活動は、研究や卒業論文との両立が求められるため、計画的に進めることが重要です。
文系学生に比べると採用のスケジュール感や評価されるポイントが異なる場合が多く、自分の強みをどのように整理して伝えるかが鍵となります。
ここでは大学3年の夏から4年春までの流れを時期ごとに整理し、理系学部生が押さえるべき行動や考え方を解説します。
大学3年夏:サマーインターンシップ
大学3年の夏は、就活のスタートラインといえる大切な時期です。
このタイミングで多くの企業がサマーインターンシップを開催しており、積極的に参加することで業界や会社の雰囲気を実際に感じ取ることができます。
特に理系学生の場合、研究に専念していると外部の社会との接点が限られるため、インターンに参加することは視野を広げる大きなきっかけとなります。
また、インターンを通じて社会人と交流することで、自分の強みや不足している部分が明確になり、以降の自己分析にも役立ちます。
さらに、一部の企業ではサマーインターンを早期選考へとつなげるケースもあるため、志望度が高い企業には早めに挑戦することが望ましいです。
この時期はまだ就活への意識が高くない学生も多いですが、早めに動き出すことで余裕を持って次のステップへ進める点が大きな利点となります。
大学3年秋~冬:自己分析・企業研究の本格化
夏のインターンシップを経験した後、大学3年の秋から冬にかけては自己分析と企業研究を本格的に進める時期となります。
理系学生は、自分の研究テーマや得意な実験技術、扱えるプログラミング言語などを整理し、それが企業でどのように活かせるかを考えることが重要です。
また、企業によっては研究内容そのものよりも、課題をどう解決したか、どのような姿勢で取り組んだかといったプロセスを重視する場合があります。
そのため、研究を通じて身につけた分析力や粘り強さを自分の強みとして表現できるように準備しておきましょう。
加えて、この時期は業界研究も欠かせません。
自分の専攻を活かせる分野だけでなく、幅広い業界を調べることで選択肢を広げることができます。
OB・OG訪問やオンラインセミナーを活用すれば、現場の声を知ることができ、企業理解を深める大きな助けとなります。
大学3年冬~4年春:本選考のエントリー
大学3年の冬から4年春にかけては、いよいよ本格的な選考が始まります。
年明け以降は多くの企業がエントリー受付を開始し、エントリーシートの提出やWebテスト、面接といった実際の選考に挑むことになります。
これまでに準備してきた自己分析や企業研究を活かし、自分の強みを分かりやすく伝えることが求められます。
ただし、理系学生は研究や卒業論文の進行と並行して就活を進めなければならないため、計画的にスケジュールを管理することが欠かせません。
特に面接や説明会の日程が研究活動と重なることもあるため、指導教員や研究室の仲間と相談しながら調整する柔軟さも必要になります。
この時期は焦りを感じる学生も多いですが、準備の積み重ねが自信につながります。
また、複数の企業にエントリーすることで、自分に合う会社の見極めも進みます。
【理系就活】大学院生の就活スケジュール
大学院に進学した理系学生の就職活動は、学部生とは少し違う特徴があります。
専門性の高い研究を進める中で、その成果をどのように社会や企業で役立てられるかを明確にすることが大切です。
ここでは修士1年の夏から修士2年春までの流れを時期ごとに整理し、効果的な準備の方法を解説します。
修士1年夏:サマーインターンシップ
修士1年の夏は就職活動において重要な最初のステップです。
学部生と同じく多くの企業がサマーインターンシップを実施していますが、大学院生の場合はさらに専門性が評価されやすいため、研究内容と関連性の高い企業を中心に選ぶことが効果的です。
インターンに参加することで、これまで積み上げてきた研究スキルや知識が実際の現場でどのように役立つのかを体験できます。
また、大学院生向けのインターンは企業側も即戦力候補としての視点を持っているため、参加がそのまま内定や早期選考につながるケースもあります。
この段階で積極的に挑戦することで、将来のキャリアを具体的に描きやすくなります。
さらに、社会人や他大学の学生と交流できる貴重な場でもあり、自分の立ち位置を客観的に知るきっかけにもなります。
修士1年秋~冬:専門性を活かした企業研究
サマーインターンを経験した後、修士1年の秋から冬にかけては企業研究に重点を置く時期となります。
大学院生の場合、研究テーマや専門分野がキャリア選択に直結することが多いため、自分の知識や技術を活かせる企業を集中的に調べることが重要です。
また、企業研究を進めると同時に、自分の研究内容を専門外の人にも分かりやすく説明できるよう練習しておくことが求められます。
面接やエントリーシートでは、研究の専門性だけでなく、それを社会にどう応用できるかを伝える力が評価されます。
さらに、この時期は教授や先輩、OB・OGなどに相談することで、研究を活かしたキャリアパスを知ることができます。
研究に没頭するあまり視野が狭くなることもあるため、積極的に外部からの情報を取り入れることが大切です。
修士1年冬~修士2年春:本選考のエントリー
修士1年の冬から修士2年の春にかけて、いよいよ本格的な就職活動が始まります。
多くの企業がエントリーを受け付け、エントリーシートやWebテスト、面接などの選考が本格化する時期です。
大学院生にとっては、推薦応募と自由応募のどちらを選ぶかが大きなポイントとなります。
推薦応募を希望する場合は、研究室の教授や指導教員と早めに相談し、研究との兼ね合いを考えながら進めることが重要です。
一方で自由応募を利用する場合は、複数の企業に挑戦できる自由度がありますが、スケジュール管理が一層求められます。
また、研究や修士論文の準備と同時進行になるため、効率よく計画を立てることが欠かせません。
特に面接では、自分の研究を分かりやすく説明しながら企業での活用方法を示すことが大きな評価ポイントとなります。
【理系就活】文系就活との違いを理解しよう
理系の就職活動は、文系の就活と比べて独自の特徴があります。
推薦制度の存在や専門職採用の多さなど、採用の仕組みそのものに違いがあり、就活の進め方や準備内容も大きく変わってきます。
また、インターンや推薦を通じて早期に内定が決まるケースも少なくなく、結果的に活動期間が短くなる傾向があります。
ここでは文系との主な違いを整理し、理系就活の特徴を理解していきましょう。
文系就活との主な違い
理系の就職活動には、文系にはない独自の特徴があります。
推薦制度の活用や専門職採用の多さなど、採用の仕組みそのものに違いがあり、準備の進め方や就活のスピード感にも差が生まれます。
また、研究や論文と並行して進める必要があるため、短期間で効率的に行動することが求められる点も特徴的です。
推薦応募がある
理系就活で特徴的なのが推薦応募です。
大学や研究室の教授を通じて企業に推薦してもらい、選考に進む方法を指します。
自由応募と比べて内定率が高いとされ、安定した就職活動ができる点が大きな魅力です。
ただし、推薦を利用する場合は原則として他社との併願が制限されるため、志望企業を早い段階で決める必要があります。
また、推薦枠は研究室ごとに人数制限がある場合もあり、教授や同級生との調整が必要になることもあります。
推薦応募を利用することで選考フローが短縮されることも多く、研究と両立しやすいという利点もあります。
専門職採用がある
理系の就活では、研究開発職や技術職などの専門職採用が一般的です。
学生時代に学んだ研究テーマや技術が直接評価され、入社後すぐに専門性を発揮できることが期待されます。
一方、文系では総合職採用が中心であり、入社後に幅広い部署を経験するスタイルが多く見られます。
そのため、理系の学生は自分の研究を社会や企業でどう活かせるかを具体的に説明できるように準備しておく必要があります。
また、知識や技術だけでなく、研究活動で培った課題解決力や協調性も評価の対象となります。
就活期間が短い傾向にある
理系の就活は、文系に比べて活動期間が短くなる傾向があります。
その大きな理由は、インターンを通じた早期選考や推薦応募の存在です。
インターンで評価を得た学生が早期に内定をもらうケースや、推薦応募で短いフローを経て内定が決まるケースも珍しくありません。
このため、学部3年や修士1年の秋の段階で就活を終える学生もいます。
一方、文系は長期間にわたり多くの企業を受け続けることが一般的であり、その点で理系とは大きな違いがあります。
研究や論文と並行して活動する必要がある理系学生にとっては、この短期間で効率的に成果を出すことが重要です。
理系就活のメリット・デメリット
理系の就職活動には、文系にはない強みと課題が存在します。
まず大きなメリットとして、大学や大学院で学んだ専門知識をそのまま活かせる点が挙げられます。
研究開発職や技術職といった専門職採用では、これまで培ってきた知識やスキルが即戦力として評価されやすく、入社後のミスマッチが少なくなる傾向があります。
研究テーマや実験で身につけた分析力や課題解決力を直接仕事に結びつけられるため、やりがいを感じやすい点も魅力です。
一方で、デメリットもあります。
特に大学院生の場合、就職活動の時期と研究の佳境が重なることが多く、研究活動と就活を両立させる難しさがあります。
研究室の進行状況や教授との調整も必要になり、効率的に時間を管理しなければ両方が中途半端になる恐れもあります。
研究と就活を両立させる工夫を意識することが成功の鍵となります。
【理系就活】文系より就活に有利なの?
大学生の就活において、理系の方が文系よりも有利だと言われることがあります。
厚生労働省が実施した「大学等卒業者の就職状況調査」によると、令和3年3月の大学等卒業者の就職率は、文系出身者が96.0%、理系出身者が95.9%であり、< span class="yellow">就職率を見ると両者の差はほとんどありません。
一方、研究開発など一部の職種では、理系学部出身であることが必須条件になる場合があります。
また、推薦応募などで一般応募より就職が早く決まる学生がいることも、理系大学生が有利と言われる理由と考えられるでしょう。
出典:大学、短期大学及び高等専門学校卒業者の4月1日現在の就職状況調査の推移|厚生労働省
【理系就活】就活に強い理系学部とは
大学で学んだ内容が仕事につながる学部は、就活に強いと言えるでしょう。
その傾向が強い理系学部としては、医学部や歯学部、薬学部などが代表的です。
医師や歯科医、薬剤師などは資格の取得が必須であるため、国家試験に合格することが前提ではあるものの、比較的職場を見つけやすいと言えます。
続いて、理学部や工学部についても、自分が学んできた専門性や知識を活かせる企業は豊富に存在します。
優秀な理工系の学生を求めているメーカーなどでは、製品開発などに携わることも多いでしょう。
【理系就活】進路に悩む人が多い理由
理系大学生が進路について悩む大きな理由の一つに、卒業して就職するか、大学院へ進学するかという選択の問題があります。
大学卒業後の明確なビジョンを持っている場合は迷うことなく進路を選べますが、漠然としている場合はすぐに決めることは難しいでしょう。
その場合は、まず就活に取り組んでみることをおすすめします。
条件が良く自分の希望に合う企業から内定を得られればその企業に進むことができ、自分の希望の基準に満たない企業であれば内定を断ることもできます。
内定を辞退した場合でも、大学院に進学後、再び就活する際の参考になるでしょう。
大学卒業後に就職をするメリット
大学卒業後、修士課程に進まず就職するメリットの一つは、社会人としてのキャリアを早くスタートできることでしょう。
少しでも若いうちに社会人としての知識やスキル、実績を身につけることで、二年後に入社してきた同年のメンバーに差をつけることができます。
また、大学院での専門的な知識よりも、自社の業種や職種に合った専門性を磨き、自社の風土に即した人材を育てたいと考える企業にとっては、理系大学生の新卒者は貴重な存在です。
さらに、経済的な面で言えば、大学院に進むための学費は不要となり、毎月の給与や賞与などの定期的な収入が見込めるというメリットもあります。
大学院卒業後に就職をするメリット
大学院卒業後に就職する大きなメリットは、自分の学んでいる分野の専門性や研究者としてのスキルが磨かれるということです。
修士課程の間に、仮説から実験、検証という思考プロセス、プレゼン能力、他の研究者との人脈なども培えるでしょう。
また、そのようなスキルが備わっていると企業側にも評価されやすいため、就活の際に自分の研究分野に関する推薦応募を利用しやすくなります。
就活コンサルタント木下より

さらに、修士卒は学士卒よりも給与が高い傾向にあります!
【理系就活】理系学部が就活する際の応募方法
理系学生の就活においては、推薦応募と自由応募という二つの応募方法があります。
両者を併願できることも多いですが、大学に確認が必要です。
また、併願する場合はどちらかに注力するのではなく、バランスを図りながら進めていく必要があるでしょう。
推薦応募と自由応募、それぞれのメリットとデメリットを見ていきましょう。
推薦応募を利用する
自分が所属する大学や学科、専攻、研究科に対して、企業から寄せられる学校推薦枠の求人に応募すること。
推薦応募のメリットは、エントリーシート審査や一次選考の筆記試験を行うことなく、優先的に面接や二次選考に進める場合が多いことです。
これにより、内定までの時間や労力を省くことができます。
ただし、推薦応募は内定が保証されているわけではないことは、頭にいれておきましょう。
推薦応募のデメリットは、内定をもらったら容易に辞退できないことです。
大学や学科、専攻との信頼関係の下で推薦枠を設けているため、辞退すれば翌年以降の選考に悪影響を及ぼす可能性があります。
そのため、2社以上の学校推薦を同時にもらうことはできないと言われています。
学校推薦については、こちらの記事でご紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
自由応募を利用する
自由応募は、学生自身で応募したい企業を選び、エントリーする応募手法
いわゆる「就職活動」というと、自由応募を指すことが多いでしょう。
企業の採用サイトや求人情報で企業を探し、会社説明会やインターンシップへの参加、選考試験や面接などを経て、採用を目指します。
自由応募のメリットは、推薦応募に比べて幅広い選択肢があることです。
推薦応募とは異なり、複数の企業にエントリーすることもできます。
一方で、推薦応募に比べて競争率が高く、厳しい就活になることもあり、選考にかける時間と労力が大きくなるでしょう。
【理系就活】いつから就活の準備を始めればいいか
いつから就活を始めればいいかという疑問は、多くの学生が抱くのではないでしょうか。
就活スケジュールは、「準備期間」と「本格的な就活期間」の2つに大別できます。
就活生の一般的な就活準備は、大学3年生及び大学院生1年生共通で、5・6月から開始するとよいでしょう。
また、早期選考を実施している業界(外資コンサル、外資メーカー、外資金融、総合商社、広告代理店、大手メガベンチャーなど)は4・5月から本格的な就活期間になります。
早期選考に乗りたい場合は、学士卒なら大学2年生年内まで、修士卒なら大学4年生年内までに準備期間を開始する必要があるでしょう。
この時期までに就活のことを全く考えていないと、他の就活生に大きな差をつけられ焦ってしまうことになりかねません。
理系大学生は時間に追割れる生活になりがちな場合がありますが、意識的に自分の将来や進路を考える時間を設けましょう。
【理系就活】就活準備の時期にしておくこと
就活コンサルタント木下より

理系大学生については3年生の5月頃から翌年の2月頃までに、理系大学院生については1年生の5月頃から翌年の2月頃までに、就活の準備を行ないます!
大学院生の場合は、進学する前から就活に関する意識を高めておくと良いでしょう。
ここからは理系大学生や理系大学院生が、就活準備の時期にしておくことを解説します。
企業や業界について調べる
就活生にとって、自分が目指す業界や企業について調べることは就活準備期間で最も重要なことです。
企業への理解を深め、自分の志向と目指す企業がマッチするかどうかを見極めるために、企業研究を行いましょう。
また、早期選考が実施される企業の場合は、就活準備期間が早まるため、自分が目指す業界や企業がいつから選考が始まるのかを調べておくことも重要です。
自己分析をする
企業研究と同様に大切なことが、自己分析です。
これまでの人生の中で、自分が選択してきたこと、大切にしていた価値観や考え方を振り返ってみましょう。
これまでの自分と現在の自分、そしてその企業で働いている未来、加えて人生全体で成し遂げたい大義が一直線上になるような軸を設定しましょう。
これを職種や業界、企業選びの軸とします。
この軸は面接でも問われる内容であるため、ブレないように強固な軸を設定する必要があります。
インターンに参加する
企業は志望している学生を対象に、その企業で学生が実際に働くインターンシップを実施することがあります。
サマーインターンは主に6月頃に募集があり、7~8月頃に開催するとされています。
また、9月以降であれば秋冬のインターンに参加することができるでしょう。
インターンに参加すると、企業の雰囲気や業務内容を体感でき、その職場に加わった自分を明確にイメージできるメリットがあるため、積極的に参加しましょう。
インターンに参加する前に、自分の気になる企業の就職偏差値を調べておくのも手です。
研究室について考える
研究室選びは、その後の就職活動に大きな影響を与える重要なポイントです。
まず挙げられるのは、教授や研究室の持つ企業との繋がりです。
所属する研究室の教授が特定の企業と深い関係を築いている場合、その企業に推薦枠が設けられていることも少なくありません。
こうした推薦枠は、就職活動を有利に進められる大きな要素となるため、研究室を決める際には教授の人脈や過去の進路実績を確認しておくことが大切です。
さらに、自分の研究テーマと企業の事業内容との関連性も重要です。
志望する業界や企業がどのような研究分野を重視しているのかを調べ、自分の研究がそれに近いテーマであれば面接や選考の場で高く評価される可能性があります。
研究内容が企業のニーズと結びついていると、即戦力としての期待を持たれやすく、内定に直結することもあります。
【理系就活】理系大学生の企業選びのポイント
理系大学生および大学院生の主な就職先は、メーカーや製造業、IT系企業、医療系企業、建築・建設系企業などです。
大学や大学院で研究してきた専門的な知識やスキルを活かせる企業を選ぶ方が多いでしょう。
理系大学生が企業を選ぶ際のポイントを見ていきましょう。
- エントリー数を絞り過ぎない
- 文系職種も視野にいれてみる
- 自分のスキルを必要としている企業を探してみる
- インターンに参加しておく
エントリー数を絞り過ぎない
就活をする際に大切なことはエントリー数を絞り過ぎないことです。
理系大学生は、研究や講義に忙しく、就活に割ける時間が少ないことや、研究分野を意識しすぎるなどの理由で、応募数が少ない傾向にあります。
応募数が少なすぎると、就活が順調に進まなかったときに取り返すことができなくなります。
初めからエントリー数を絞り過ぎることなく、少しでも興味がある企業や業種、職種には積極的にエントリーしましょう。
文系職種も視野にいれてみる
広い視野を持つことも就活の大事なポイントの一つです。
前述したとおり、理系学生の中には自分の研究分野を意識しすぎるあまり、自分の研究分野に携わる企業の選考ばかりに目がいってしまう人もいます。
しかし、専門外の業種・職種に視野を広げるだけでなく、文系の職種も対象に加えてみるのも大切です。
文系の職種も多種多様で、統計や確率などの数学的要素が必要な職種もあるなど、自分の研究が活かせることもあるでしょう。
自分のスキルを必要としている企業を探してみる
自己分析によって出てきた自分のスキルや強みから企業選びをすると、ミスマッチが起きにくくなります。
「自分が持っている強みは何か」「その企業が自分を採用するメリットは何か」を考えながら、企業探しや履歴書の作成、面接対策に取り組むと、就活の成功につながる可能性が高くなるでしょう。
インターンに参加しておく
インターンに参加すると、その企業に就職した自分のイメージがより明確になります。
特に、理系学生の場合は、研究体験や工場見学といったより実務に近い体験ができる傾向があるため、有意義な経験になります。
また、その企業の実態が垣間見え、ネット情報や企業説明会だけでは得られないリアルな情報を得ることができるでしょう。
また、インターンの参加は、面接のアピール材料になったり採用に直結したりするなど、就活に有利に働く場合もあります。
興味のある企業のインターンは積極的に参加しましょう。
【理系就活】研究と就活の両立方法
理系学生の就職活動では、研究との両立が避けられない課題となります。
研究室での活動は日々忙しく、就職活動の準備に割ける時間は限られています。
そのため、研究室選びの段階から就活を意識し、時間の使い方を工夫することが成功の鍵になります。
研究と就活をバランスよく進めるためには、環境の選び方と効率的な時間管理の両面から取り組むことが求められます。
研究室選びが就活に与える影響
理系学生にとって研究室選びは、就職活動のスタート地点ともいえる重要な決断です。
研究内容と志望する企業や業界との親和性は、選考において大きなアピールポイントになります。
自分の研究テーマが企業の事業内容や求める人材像と近ければ、研究経験そのものが強みとなり、面接で説得力のある自己PRにつながります。
そのため、研究室を選ぶ段階で将来のキャリアを意識し、業界の動向や企業が求める分野を調べておくことが有効です。
また、研究室に企業から推薦枠があるかどうかも見逃せません。
推薦応募は理系学生にとって大きな利点であり、内定獲得の可能性を高める手段のひとつです。
しかし、この推薦枠は研究室ごとに与えられることが多いため、教授や先輩の進路実績を確認しておく必要があります。
就活を効率的に進めるための時間管理術
研究と就活を両立させるためには、計画的な時間管理が欠かせません。
まずは年間スケジュールを作成し、研究の進捗と就活のピーク時期を重ねて把握することが大切です。
どの時期に説明会や面接が集中するのかを見極めることで、研究の進め方を調整しやすくなります。
次に、大きなタスクを細分化する工夫が必要です。
自己分析や企業研究といった漠然とした作業を、「自己PRを1つ書き出す」「企業の事業内容を3つ調べる」といった小さな単位に分ければ、短時間でも着実に進められます。
さらに、通学時間や休憩時間といった隙間時間を活用することも効果的です。
スマートフォンやノートを使って企業情報を確認したり、Webテストの練習をしたりするだけでも積み重ねが大きな成果につながります。
【理系就活】いつから始めればいいか知り対策をしよう
文系・理系に関わらず、就活の準備をいつから始めるか考え、早めに情報収集をするなどの対策は必要になるでしょう。
その中でも、理系学生は学業が忙しいことや学校推薦枠がある場合も多いことから、なるべく早く就活について考える時間をとることが重要です。
理系大学生の就活をいつから始めればいいかを知り、しっかりと対策をしましょう。
理系就活の全体像を把握したい方は、こちらの記事もぜひチェックしてみてください。









のあるある16選を紹介!男女別に詳しく解説_720x550.webp)
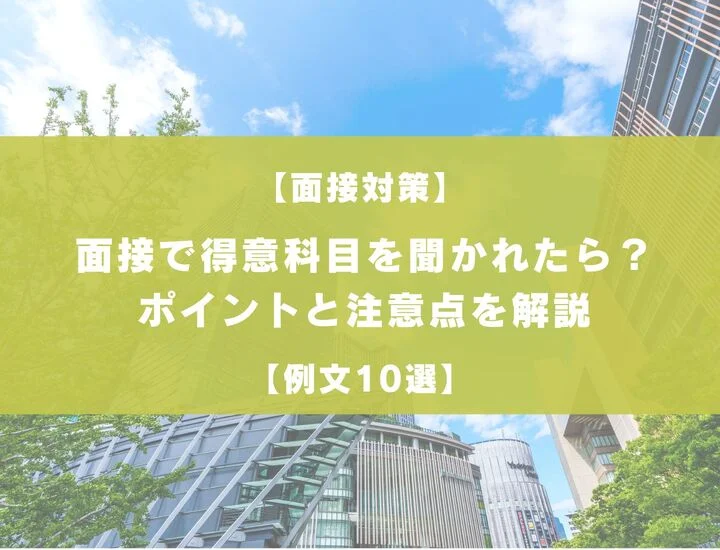






就活コンサルタント木下より
併せて、理系大学生の企業選びのポイントなども紹介するため、就活の際にやるべきことや注意すべきポイントなどもわかるでしょう。
本記事を参考にして、理系大学生の就活に関する悩みを解決し、後悔のない就活を進めましょう!