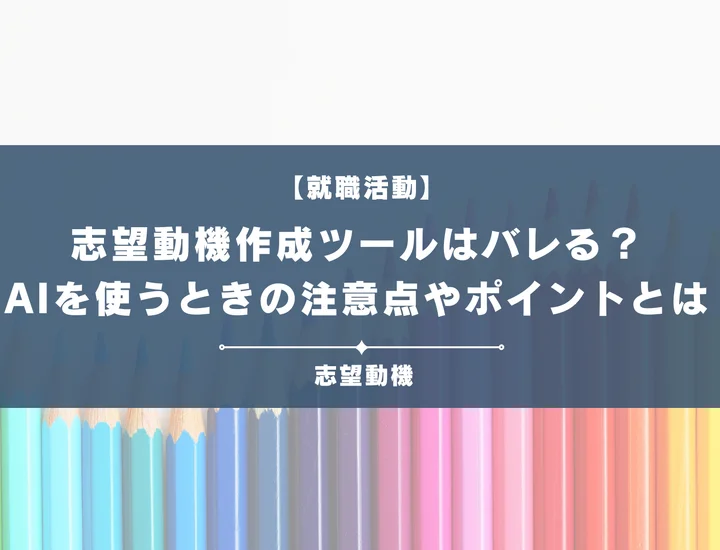HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。
国家公務員の志望動機は、制度理解や自己分析の深さが評価される重要な選考要素です。
本記事では、説得力ある志望動機を作成するための構成ポイントやNG例、実践的な例文まで詳しく解説します。
【国家公務員の志望動機】そもそも国家公務員とは
国家公務員は、国の政策を企画・立案・執行する中枢的な役割を担う職業です。
一言に「国家公務員」といっても、勤務する省庁や職種によって業務内容や求められる資質は異なります。
志望動機を考える際には、それぞれの違いを理解した上で、自分の関心や能力との一致点を見極めることが重要です。
国家総合職
国家総合職は、国の根幹となる政策の企画・立案を担うエリート職種です。
行政官としての将来を見据え、省庁の幹部候補としてキャリアを積んでいく点が最大の特徴です。
職務の内容は高度かつ複雑で、国全体に影響を与える制度や法律の設計に深く関わることが求められます。
そのため、論理的思考力や政策全体を俯瞰する力はもちろん、各省庁・地方自治体・国際機関と連携する機会も多いため、調整力や語学力、さらには国際的な視野が必要です。
国家一般職
国家一般職は、主に政策の執行や制度の運用を通じて、現場に近い立場で国民生活を支える職種です。
総合職と比べて地域ごとの採用が基本となり、採用された地域や機関に根付いて働き続けることが多いのが特徴です。
例えば、年金や雇用保険の申請手続き、各種補助金の受付業務、住民対応など、国の制度を実際に国民に届ける最前線で活躍します。
現場の声を制度に反映させる「ボトムアップ型」の仕事であることから、丁寧な対応力や責任感、安定して長く働ける人物かどうかが重視されます。
【国家公務員の志望動機】国家公務員試験では志望動機が重要!そのワケとは
国家公務員は、国民全体の利益に奉仕するという使命を持ち、国の制度や仕組みを支える中核的な存在です。
一人ひとりの国民と直接関わる機会は少ないものの、背後にいる多くの人々の暮らしや社会の安定に大きな影響を与える仕事です。
そのため、前例のない困難な課題に直面しても責任を持って粘り強く取り組み、最後までやり遂げる覚悟と強い使命感が不可欠です。
志望動機では、こうした姿勢があるかどうかを見極めるため、内容の深さや納得感が重視されます。
また、公務員として長期的に貢献する意思や、組織で協働しながら働く資質が備わっているかも評価の対象となるため、真摯かつ具体的に表現することが大切です。
【国家公務員の志望動機】採用担当者がみているポイント
国家公務員の採用において、志望動機は形式的なものではなく、その人物の本気度や適性を判断する重要な判断基準となります。
では、採用担当者はどのような視点で志望動機を評価しているのでしょうか。
ここでは、特に重視される2つのポイントについて詳しく解説します。
志望度の高さ
採用担当者は、国家公務員を「本気で目指しているかどうか」を非常に重視しています。
特に総合職では、政策の中枢を担う役割ゆえに、長期的なキャリア形成や、国家全体への貢献意識が求められます。
「他の選択肢と迷っている」「民間企業とも並行して受けている」という印象を与えてしまうと、志望度が低いと判断される可能性があります。
したがって、志望動機では「なぜ民間ではなく国家公務員なのか」「なぜこの省庁で働きたいのか」といった視点から、志望の強さや継続的な貢献意欲を、具体的な背景とともに伝えることが大切です。
仕事理解ができているかどうか
どれだけ熱意を伝えても、実際の業務内容や組織の役割を理解していなければ、現実味のある志望動機とは言えません。
採用担当者は、志望者が国家総合職としての具体的な業務をどの程度理解しているかを慎重に見ています。
「人の役に立ちたい」「国の役に立ちたい」といった抽象的な表現にとどまらず、どのような課題に取り組み、どういう手段で社会に貢献するのかという視点が重要です。
そのためには、政策文書や業務説明会、省庁インターンなどを通じて、現実の仕事の厳しさや地道さも含めたリアルな理解を深めることが不可欠です。
【国家公務員の志望動機】作成するときの3ステップ
志望動機を書く際には、いきなり文章を書き始めるのではなく、事前の準備が成功の鍵を握ります。
ここでは、効果的な志望動機を作成するための3つのステップをご紹介します。
自分の思いを明確に整理し、採用担当者に伝わる形に仕上げていきましょう。
Step 1: 徹底的な自己分析
まずは、自分自身の理解から始めることが重要です。
これまでの経験を振り返り、自分がどんなときにやりがいや達成感を感じてきたのか、どんな価値観を持っているのかを言語化してみましょう。
また、アルバイトやゼミ、部活動などを通して培ったスキルや強みを棚卸しし、どのような場面で活かされてきたかを整理することも有効です。
この段階で得られた情報は、後のステップで「なぜ国家公務員なのか」「どう活躍したいのか」を考える土台となります。
自己分析を丁寧に行うことで、自分ならではの説得力ある志望動機につながっていきます。
Step 2: 職務・省庁理解
自己分析の次は、国家公務員という仕事、さらには志望する省庁の役割や課題について理解を深めることが必要です。
たとえば、総務省は地方自治制度やICT政策、財務省は国家財政や税制改革、外務省は外交・国際協力を担っています。
それぞれの省庁で求められる視点やミッションは異なります。
志望動機を作るうえでは、その省庁のビジョンや最近の政策課題を調べ、自分の関心との接点を見出すことが効果的です。
実際に働いている職員の話を聞く機会があれば、リアルな情報を得て、自分の理解をより確かなものにしましょう。
Step 3: 自分と仕事内容を結びつける
最後に行うべきは、自己分析で得た自分の強みや価値観と、省庁や職務の理解を結びつける作業です。
ここで重要なのは、「自分がなぜ国家公務員になりたいのか」「どのように貢献したいのか」を、自分の言葉で具体的に語ることです。
たとえば、「地域の活性化に関心があり、大学で地域振興について学んだ経験から、地方創生政策に関わりたい」など、背景と志望先との関係を明確に伝えることで説得力が増します。
単なる理想論ではなく、自分の実体験を通じて生まれた動機であることが伝われば、採用担当者の心に響く志望動機となるでしょう。
【国家公務員の志望動機】必ず盛り込みたい内容と構成
国家公務員の志望動機は、単なる憧れや表面的な理由だけでは通用しません。
志望の背景や動機に一貫性を持たせ、説得力のある構成で伝えることが重要です。
以下に紹介する4つの要素は、志望動機を作成する際に必ず盛り込みたいポイントです。
それぞれの項目をバランスよく取り入れ、自分自身の考えを表現していきましょう。
きっかけや原体験
志望動機には、国家公務員を目指すようになったきっかけや、自身の経験と結びついた原体験を盛り込むことが大切です。
たとえば、災害時に行政の対応に感動した経験や、留学中に日本の制度の良さ・課題を実感した出来事などがあれば、それを明確に伝えましょう。
抽象的な「国のために働きたい」ではなく、「なぜそう思ったのか」「その意識がどう形成されたのか」という背景があることで、動機に厚みが生まれます。
原体験が具体的であればあるほど、採用担当者に「この人は本気で国家公務員を目指している」と伝わりやすくなります。
経験の中で得た学びと、国家公務員の業務との接点を見出すことが、説得力のある志望動機につながります。
政策分野・課題
志望動機では、「自分がどのような政策分野に関心を持っているか」「どのような社会課題に取り組みたいのか」を具体的に示すことも重要です。
たとえば、人口減少、地方創生、デジタル化、財政再建、環境問題など、関心を持っているテーマを一つに絞り、その分野に対してどのように貢献したいかを明確にしましょう。
実際にその政策分野について学んだことや、調べた内容を交えると、理解度の高さが伝わります。
志望省庁の近年の取り組みや課題とも照らし合わせながら、自分の考えを展開していくと、より具体的で現実味のある内容になります。
分野の選定には、自分の経験や価値観と重なる部分があるとより自然で納得感のある志望動機となります。
自分の強みがどう活かせるか
志望動機の中では、自分の強みやスキルがどのように国家公務員の仕事に活かせるかを説明することも欠かせません。
たとえば、論理的思考力、コミュニケーション能力、情報収集力、語学力など、大学生活やインターン、課外活動を通じて培ってきた力を挙げましょう。
その際に、「強みをこう活かしたい」という表面的なアピールに終始するのではなく、「自分の強みがどのように社会課題の解決に役立つか」をセットで述べることが大切です。
たとえば、「多様な価値観を受け入れる姿勢を活かして、移民政策や国際協力の分野で柔軟な制度設計に貢献したい」など、業務との接点を具体的に描きましょう。
将来ビジョン
国家公務員としてどのようなキャリアを築いていきたいのか、また、将来的にどのような社会を実現したいのかというビジョンを明示することで、志望動機はより完成度の高いものになります。
ただ「長く働きたい」という意志を伝えるだけでなく、「どんなポジションで、どのような役割を果たしていたいか」「何を成し遂げたいか」を具体的に描くことが大切です。
たとえば、「将来的には地方と都市をつなぐ政策立案に携わり、持続可能な地域社会の実現に貢献したい」といった表現は、目指す方向性が明確で好印象です。
将来ビジョンを語る際は、自分の経験や関心の延長線上にある目標として語ると自然で一貫性が出ます。
【国家公務員の志望動機】例文を5つ紹介
国家公務員の志望動機は、自分の経験や関心をもとに具体的に伝えることが重要です。
ここでは総合職・一般職別に、個性の異なる例文を5つ紹介します。
国家総合職①
例文
高校時代に復興支援の講演を受け、防災政策の重要性に強く関心を持ちました。
大学では災害対策の制度について学び、実務と理論の両方から国の対応に触れてきました。
その過程で、現場に即した制度設計の必要性を感じ、自らの知見を国の仕組みに活かしたいと考えるようになりました。
国家総合職を志望する理由は、制度の根本から改善できる立場で、より多くの人々の安全と安心を支える政策に関わりたいからです。
法制度と実情の間にあるギャップを埋め、現実に即した運用がなされる仕組みづくりに貢献したいと考えています。
理論だけでなく、実践的な視点も持ちながら幅広く政策に携わる姿勢を大切にしていきたいです。
国家総合職②
例文
私は、国際的な環境問題に対する日本の取り組みに関心を持ち、大学では気候政策に関する研究を続けてきました。
講義だけでなく、他国の制度や国内の動向を比較する中で、日本の制度設計のあり方に課題を感じる場面も多くありました。
総合職では、各国との調整や政策立案において中心的な役割が求められます。
私は、その中で持続可能な社会構築に向けた制度づくりを進めることに魅力を感じています。
環境政策の改善には、複雑な利害関係の中でバランスを取る視点が不可欠です。
そうした状況で多角的に物事を捉える力を活かし、国の施策をより実効性ある形で推進していきたいと考えています。
国家一般職
例文
私は、地域の教育格差を目の当たりにした経験から、行政を通じた支援の重要性を実感しました。
大学では教育政策をテーマにしたゼミに所属し、地域差のある学習環境や支援制度について調査を進めました。
その中で、現場に寄り添いながら制度を運用する立場に強い意義を感じ、国家一般職を志望しました。
全国一律ではなく、地域ごとの実態を踏まえた柔軟な支援を行うには、運用現場での工夫や対応力が欠かせません。
私は、人と対話を重ねる中で状況を理解し、丁寧に対応する力に自信があります。
その力を活かし、住民にとって本当に必要な制度運用を行う存在として、長く貢献していきたいと考えています。
ゼミの経験を活かす例文
例文
大学では都市政策を研究するゼミに所属し、まちづくりに関する多様なアプローチを学びました。
特に、行政・企業・住民が連携して課題解決を行う事例に触れ、公共の役割の大きさを実感しました。
こうした経験を通じて、単なる政策提案だけでなく、現場との接点を持ちながら合意形成を図る力の必要性を感じました。
国家公務員として、関係者の意見を丁寧にくみ取りながら、多様な利害の中でも実現可能な政策を形にしたいと考えています。
ゼミ活動で培った分析力と課題設定力を活かし、複雑化する都市の課題に対して、実効性のある政策立案に挑戦したいです。
机上の理論に留まらない現実的な施策を通して、持続可能な社会の形成に貢献していきたいと考えています。
ボランティア経験を活かす例文
例文
大学1年の頃から、福祉施設での学習支援ボランティアに継続的に参加してきました。
そこで出会った子どもたちの中には、家庭や経済状況によって進学の選択肢が限られている現実がありました。
一人ひとりが可能性を広げられる社会にするには、制度面からの支援が不可欠だと強く感じました。
私はその課題を根本から変えていく力を持つ国家公務員の仕事に魅力を感じ、志望するようになりました。
現場で感じた違和感や課題意識を原点とし、誰もが支援を受けられる制度づくりに関わりたいと考えています。
ボランティアを通して得た共感力と現場感覚を活かし、福祉や教育の分野で国民に寄り添う制度運用を目指していきます。
【国家公務員の志望動機】これだけは避けたいNGポイント
国家公務員の志望動機は、熱意があるだけでは不十分で、内容に具体性と説得力が求められます。
ここでは、採用担当者がマイナス評価を下す可能性のある代表的なNG例を紹介し、それぞれの理由と改善のヒントを解説します。
抽象的で具体性に欠ける
「人の役に立ちたい」「社会に貢献したい」といった志望理由は、一見前向きに聞こえますが、国家公務員を目指す理由としては抽象的すぎます。
このような表現だけでは、民間企業や他の公務員職種にも当てはまり、国家総合職でなければならない理由が伝わりません。
具体的な課題への関心や、それに対する自分なりの視点を盛り込むことで、志望動機に独自性と説得力が生まれます。
たとえば「どの分野に関心があるのか」「なぜその政策に携わりたいのか」など、自身の経験と結びつけて語ることが有効です。
内容に具体性がないと、本気度や理解度を疑われてしまうため注意が必要です。
受け身な姿勢、待遇面への過度な言及
国家公務員は安定した職業であり、成長機会や福利厚生が整っているというイメージを持つ人も多いでしょう。
しかし、志望動機に「安定して働きたい」「成長できそうだから」といった受け身な表現ばかりが並ぶと、主体性や貢献意識が伝わりません。
また、待遇や休暇制度などへの言及が目立つと、「自分の利益が最優先」と見られてしまうリスクがあります。
国家公務員には、困難な業務にも前向きに取り組む姿勢や、公共の利益を第一に考えるマインドが求められます。
そのため、志望理由はあくまで「どのように貢献したいか」「どんな課題に挑戦したいか」といった能動的な視点から構成しましょう。
どの省庁・職種でも当てはまるような内容
「人の役に立ちたい」「社会に必要とされる仕事がしたい」といった表現は、どの省庁や職種でも使える内容であり、国家公務員を特別に選んだ理由としては弱く映ります。
こうした汎用的な表現ばかりでは、「なぜ国家総合職なのか」「なぜこの省庁を選んだのか」といった重要な問いに答えていないと判断されてしまいます。
志望動機を作成する際には、自分の関心を持つ政策分野や志望する省庁の役割としっかり結びつけることが大切です。
たとえば、「◯◯省が取り組んでいる△△政策に共感し、□□の経験を活かして携わりたい」といった具体的な構成にすることで、志望度の高さと理解の深さが伝わります。
省庁研究不足が露呈する内容
志望先の省庁に関する理解が浅いと、見当違いなことを書いてしまったり、誤った表現をしてしまう可能性があります。
たとえば、「外務省で国内の地方創生に関わりたい」など、業務の管轄とずれた内容を記載してしまうと、即座に知識不足と判断されることがあります。
省庁ごとに扱う政策テーマや業務範囲は大きく異なるため、事前に必ず公式情報やパンフレット、説明会などで正確な情報を得る必要があります。
志望動機の中に誤った情報があると、熱意や準備不足が疑われ、選考通過が難しくなります。
本気でその省庁を目指しているのであれば、丁寧な情報収集を怠らず、内容にも反映させるように心がけましょう。
【国家公務員の志望動機】よりよくするためにするべきこと
国家公務員の志望動機は、どれだけ自分の想いを言葉にできるかだけでなく、どれだけ相手の求める視点を理解しているかも問われます。
ここでは、志望動機の完成度を高めるために取り組んでおきたい4つのポイントを紹介します。
各省庁のウェブサイト、パンフレット、白書等の読み込み方
志望する省庁についての理解を深めるには、まず公式サイトやパンフレット、各種白書などを活用して、情報を体系的に把握することが第一歩です。
特に、省庁の「ミッション(使命)」や「政策の方向性」、近年の「重点施策」「取り組み中の課題」などを丁寧に確認しておくことが重要です。
表面的なスローガンや数字だけに注目するのではなく、それらが示す背景や社会的意義まで読み取ることが求められます。
たとえば、白書には中長期的な課題や省庁のスタンスが詳しく書かれているため、志望動機に説得力を持たせる材料として非常に有用です。
「なぜこの省庁か」を答えるためには、根拠ある理解が欠かせません。
官庁訪問や説明会、OB/OG訪問で得るべき情報
ウェブサイトなどの公式情報に加えて、現場の声を直接聞ける機会も積極的に活用しましょう。
オンライン説明会やインターン、さらにはOB・OG訪問を通じて、実際に働いている職員の姿勢や業務内容を知ることができます。
とくに、仕事のやりがいや、やりとりの中で感じた価値観の一致は、志望動機に個性を加えるうえで有効なヒントになります。
訪問時には、表面的な質問ではなく「どのような課題に向き合っているか」「入省前後でのギャップはあったか」など、より深い視点から話を聞くことを意識しましょう。
こうした生の情報は志望動機に厚みを与え、書類や面接でも他の受験者と差をつける要素となります。
自身の関心と各省庁のミッション・政策との接続
効果的な志望動機を作成するには、自分の関心や価値観、強みを、省庁の具体的な政策やミッションと結びつけて語ることが大切です。
たとえば、「高齢化社会に関心がある」だけでは弱く、「介護現場での経験から、厚生労働省の地域包括ケアシステムに共感した」といったように、接続点を明確にすることが必要です。
このように、自分の過去の体験や研究テーマと、政策への貢献意欲を結びつけることで、一貫性と説得力が生まれます。
さらに、接続の仕方が具体的であるほど、採用側に「この人はうちの業務に関心を持っている」と強く印象づけることができます。
なぜ民間企業ではないのかを深堀り
国家公務員を志望するうえで、民間企業ではなく「なぜ公務なのか」を明確に説明できることが重要です。
たとえば、「一人ひとりの顧客ではなく、社会全体に広く影響する制度設計に関わりたい」「利益ではなく長期的な視点で政策を考えたい」といった、自身の価値観と公務の特性が一致している点を説明しましょう。
さらに、民間企業の経験やインターンを通じて「自分には公務の方が向いている」と感じた具体的な気づきがある場合には、それを補足することでより自然な説得力が生まれます。
この問いに丁寧に向き合うことで、志望動機に一層の深みを加えることができます。
まとめ
国家公務員の志望動機を作成するには、自分の経験と省庁の政策やミッションをつなぐ具体性と深さが求められます。
そのためには、資料の読み込みや現場の声の収集、自己分析を丁寧に行い、納得感のある構成で言語化することが不可欠です。
本記事を参考に、自分自身の志をしっかりと伝えられる志望動機を目指しましょう。